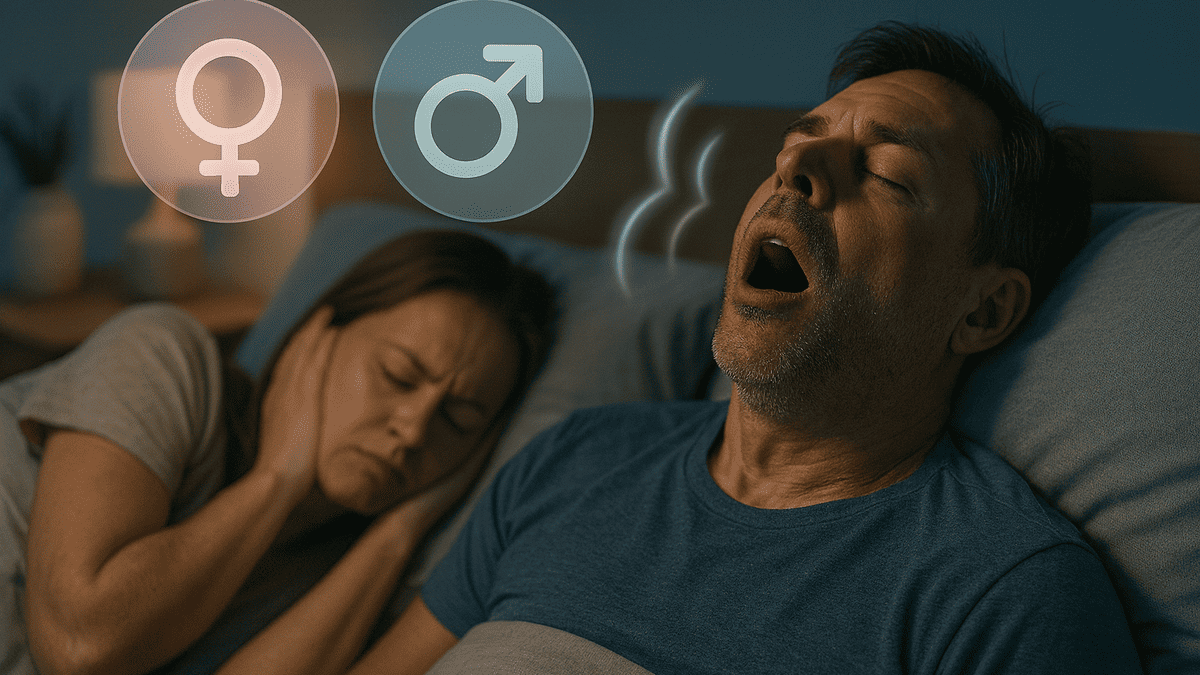パートナーのいびきがうるさくて眠れない、あるいは自分のいびきを家族から指摘されて悩んでいませんか。
単なるうるさい音と軽視されがちないびきですが、実は体が発している健康状態のサインかもしれません。特に「ひどいいびき」は睡眠の質を低下させるだけでなく、重大な病気が隠れている可能性もあります。
この記事では、いびきがひどい人によく見られる身体的・生活習慣的な特徴から男女別の原因の違い、そして今日から始められる改善方法まで、専門的な観点から分かりやすく解説します。
いびきがひどい人に見られる共通の特徴
大きないびきをかく人には、いくつかの共通した特徴が見られます。これらはいびきの原因である「気道の狭窄」に直接的、あるいは間接的に関わっています。
肥満体型と首周りの脂肪
体重が増加すると首周りにも脂肪がつきます。この脂肪が内側から気道を圧迫し、空気の通り道を狭めてしまうため、いびきをかきやすくなります。
特にBMIが25以上の肥満の方は、いびきのリスクが高いと言えます。
鼻づまりやアレルギー性鼻炎
アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、鼻中隔彎曲症などで鼻の通りが悪いと、口呼吸になりやすくなります。
口呼吸になると舌が喉の奥に落ち込み(舌根沈下)、気道を塞ぎやすくなるため、いびきの原因となります。
いびきの原因となる鼻の疾患
| 疾患名 | 主な症状 |
|---|---|
| アレルギー性鼻炎 | くしゃみ、鼻水、鼻づまり |
| 副鼻腔炎(蓄膿症) | 色のついた鼻水、鼻づまり、頭痛 |
| 鼻中隔彎曲症 | 慢性的な鼻づまり、口呼吸 |
顎が小さいまたは後退している骨格
生まれつき下顎が小さい、または後退している方は、もともと気道が狭い傾向があります。このような骨格的な特徴を持つ方は痩せていてもいびきをかきやすいです。
飲酒や喫煙の習慣
アルコールは喉の筋肉を弛緩させる作用があります。これにより気道が狭くなり、いびきが発生しやすくなります。
また、喫煙は喉や気道の粘膜に炎症を引き起こし、腫れさせるため、空気の通りを悪くしてしまいます。
なぜいびきをかくのか?音が発生する体の仕組み
いびきの音は、決して口や鼻から直接出ているわけではありません。その音の正体は狭くなった気道を空気が通る際に発生する振動音です。
上気道が狭くなるのが原因
いびきの根本的な原因は、鼻から喉の奥にかけての空気の通り道である「上気道」が何らかの理由で狭くなることです。
起きている時は筋肉の働きで気道が開いていますが、睡眠中はその働きが弱まります。
睡眠中に筋肉が緩む影響
眠りに入ると全身の筋肉がリラックスします。これには喉や舌を支える筋肉も含まれます。
これらの筋肉が緩むと舌が喉の奥に落ち込んだり、喉の壁(軟口蓋や口蓋垂)がたるんだりして、気道を狭めてしまいます。
狭い気道を空気が通る時の振動音
狭くなった気道を呼吸によって空気が無理やり通過しようとすると、周辺の粘膜や組織が振動します。この時に発生する「ブーブー」「ガーガー」という音が、いびきの正体です。
ホースの先を指でつぶすと水の勢いが強くなるのと同じ原理です。
男性に多いいびきの原因と特徴
一般的に、いびきは男性に多いとされています。これには男性特有の体のつくりや生活習慣が関係しています。
内臓脂肪による気道の圧迫
男性は女性に比べて、お腹周りに脂肪がつく「内臓脂肪型肥満」になりやすい傾向があります。
内臓脂肪が増えると首周りの脂肪も増えやすく、物理的に気道を圧迫しやすくなるため、いびきの大きな原因となります。
肥満タイプの違いといびき
| 肥満タイプ | 特徴 | いびきへの影響 |
|---|---|---|
| 内臓脂肪型(リンゴ型) | 腹部に脂肪がつく。男性に多い。 | 首周りにも脂肪がつきやすく、気道を圧迫しやすい。 |
| 皮下脂肪型(洋ナシ型) | 下半身に脂肪がつく。女性に多い。 | 内臓脂肪型に比べると、影響は少ない傾向。 |
上気道の構造的な違い
男性は女性よりも喉頭(のどぼとけ)の位置が低く、喉の空間が前後に長いという骨格的な特徴があります。
この構造は睡眠中に舌が落ち込みやすく、気道を塞ぎやすい要因の一つと考えられています。
アルコール摂取と筋肉の弛緩
社会的にお酒を飲む機会が多いことも、男性のいびきが多い一因です。
アルコールは筋肉を弛緩させる作用が強いため、普段いびきをかかない人でも飲酒後には大きないびきをかくことがあります。
女性のいびきが増える原因と特有の背景
いびきは男性の問題と思われがちですが、女性も決して無関係ではありません。特に年齢とともに、いびきに悩む女性は増加します。
女性ホルモンの減少と気道の筋力低下
女性ホルモンの一つであるプロゲステロンには上気道を開いた状態に保つ筋肉(開大筋)の活動を活発にする働きがあります。
更年期を迎え、この女性ホルモンが減少すると気道の筋力が低下し、いびきをかきやすくなります。
妊娠中の体重増加とホルモン変化
妊娠中は体重が増加し、体に水分を溜め込みやすくなるため、喉の粘膜がむくんで気道が狭くなることがあります。
また、ホルモンバランスの変化も影響し、一時的にいびきが悪化することがあります。多くは出産後に改善します。
顎の小ささと骨格的な要因
女性は男性に比べて顎が小さい傾向があります。
もともと気道が狭いところに加齢による筋力低下や体重増加が加わることで、いびきが顕著になるケースが少なくありません。
女性のいびきに関連する要因
| ライフステージ | 主な要因 |
|---|---|
| 若年層 | 扁桃腺の肥大、顎の小ささ |
| 妊娠中 | 体重増加、ホルモン変化、むくみ |
| 更年期以降 | 女性ホルモンの減少、筋力低下、体重増加 |
注意が必要な「危険ないびき」の見分け方
すべてのいびきが問題なわけではありませんが、中には「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」という病気のサインである「危険ないびき」も存在します。
放置すると、深刻な健康問題につながる可能性があります。
呼吸が止まる・途切れる
いびきの最も危険なサインは睡眠中に呼吸が止まることです。
大きないびきが突然止まり、しばらく静かになった後、あえぐように呼吸を再開する場合は、睡眠時無呼吸症候群の典型的な症状です。
いびきの音の変化
単調ないびきではなく、音が途切れたり、静かな状態から突然爆音のような大きないびきが始まったりするなど、リズムや音量が不規則な場合も注意が必要です。
危険ないびきのチェックリスト
- いびきの途中で呼吸が10秒以上止まる
- 大きないびきの後に、静かになる時間がある
- 息苦しそうに、あえぐように呼吸を再開する
- 寝汗をひどくかく
日中の強い眠気や倦怠感
睡眠中に無呼吸を繰り返していると脳や体が十分に休まらず、深刻な睡眠不足に陥ります。
その結果、日中に耐えがたいほどの強い眠気を感じたり、常に疲労感が抜けなかったりします。これは、仕事中のミスや居眠り運転の原因となり、大変危険です。
今日からできるいびきを改善するためのセルフケア
病的なものでない軽度のいびきは生活習慣を見直すことで改善が期待できます。専門医に相談する前に、まずはご自身でできる対策を試してみましょう。
横向き寝を試す
仰向けで寝ると、重力で舌が喉の奥に落ち込みやすくなります。横向きで寝ることで舌の落ち込みを防ぎ、気道の確保につながります。
抱き枕などを利用すると、自然な横向きの姿勢を保ちやすくなります。
枕の高さや寝具を見直す
枕が高すぎると顎が引けて気道が圧迫されます。逆に低すぎても口が開きやすくなり舌が落ち込む原因になります。自分に合った高さの枕を選ぶことが重要です。
一般的には、横になった時に首の骨が背骨とまっすぐになる高さが良いとされています。
枕選びのポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 高さ | 首の角度が自然で気道が圧迫されない高さ |
| 硬さ | 頭が沈み込みすぎず、しっかり支えてくれる硬さ |
| 素材 | 通気性が良く、寝返りが打ちやすい素材 |
市販のいびき対策グッズの活用
ドラッグストアなどでは鼻腔を広げるテープや、口を閉じるテープ、顎を固定するサポーターなど、様々な対策グッズが販売されています。
鼻づまりが原因の場合は鼻腔拡張テープ、口呼吸が原因の場合は口閉じテープなど、ご自身の原因に合わせて試してみるのも一つの方法です。
専門医に相談する根本的な治療法
セルフケアを試しても改善しない場合や、呼吸の停止など危険ないびきのサインがある場合は、専門の医療機関を受診することが重要です。
睡眠時無呼吸症候群の検査
まずは、いびきの原因が睡眠時無呼吸症候群(SAS)でないかを調べる検査を行います。
自宅でできる簡易検査や、医療機関に一泊して行う精密検査(PSG検査)で、睡眠中の呼吸の状態を詳しく評価します。
CPAP(シーパップ)療法
中等症から重症のSASと診断された場合に最も標準的な治療法です。鼻に装着したマスクから寝ている間に圧力をかけた空気を送り込み、気道が塞がるのを防ぎます。
多くの患者様で、いびきの消失や日中の眠気の改善といった高い効果が期待できます。
マウスピース(口腔内装置)による治療
軽症から中等症のSASの患者様や、CPAP療法が合わない場合に用いられる治療法です。
睡眠中に専用のマウスピースを装着し、下顎を前方に少し突き出させることで気道を広げます。歯科で作成します。
主な治療法の比較
| 治療法 | 対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| CPAP療法 | 中等症〜重症SAS | 治療効果が高い。毎晩の装着が必要。 |
| マウスピース | 軽症〜中等症SAS | 持ち運びが便利。効果に個人差がある。 |
| 外科手術 | 扁桃肥大などが原因の場合 | 原因が明らかな場合に根本治療となる。 |
いびきに関するよくある質問
最後に、いびきに関して患者様からよく寄せられる質問にお答えします。
- Q子供のいびきは問題ありませんか?
- A
子供のいびきの多くは、アデノイドや扁桃腺の肥大が原因です。
大きないびきをかいている、呼吸が苦しそうといった場合は成長や発達に影響を及ぼす可能性もあるため、小児科や耳鼻咽喉科に相談することをお勧めします。
- Qいびきは遺伝しますか?
- A
いびきそのものが遺伝するわけではありません。しかし、いびきの原因となる「顎が小さい」「鼻が曲がっている」といった骨格的な特徴や、「太りやすい」といった体質は遺伝する可能性があります。このことにより、親子でいびきをかきやすい傾向が見られることがあります。
- Q急にいびきをかくようになった原因は何ですか?
- A
急にいびきが始まった場合、いくつかの原因が考えられます。
- 急激な体重増加
- 過労やストレスによる筋肉の弛緩
- 飲酒量の増加
- 加齢による筋力の低下
主に生活習慣の変化がきっかけとなることが多いです。
また、アレルギー性鼻炎の発症なども考えられますので、症状が続く場合は一度医療機関に相談してください。
以上
参考にした論文
NAGAYOSHI, Mako, et al. Risk factors for snoring among Japanese men and women: a community-based cross-sectional study. Sleep and breathing, 2011, 15.1: 63-69.
YAEGASHI, Toru, et al. Association between Asthma and Sleep-Disordered Breathing in Elementary School Children in Japan. Sleep Medicine, 2025, 106749.
PEPPARD, Paul E.; AUSTIN, Diane; BROWN, Richard L. Association of alcohol consumption and sleep disordered breathing in men and women. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2007, 3.3: 265-270.
YOUNG, Terry; PEPPARD, Paul E.; GOTTLIEB, Daniel J. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. American journal of respiratory and critical care medicine, 2002, 165.9: 1217-1239.
NAGAYOSHI, Mako, et al. Self-reported snoring frequency and incidence of cardiovascular disease: the Circulatory Risk in Communities Study (CIRCS). Journal of epidemiology, 2012, 22.4: 295-301.
WANG, Junwen, et al. Sex Differences in the Relationship Between Self-Reporting of Snoring and Cardiovascular Risk: An Analysis of NHANES. Nature and Science of Sleep, 2024, 965-977.
COLLOP, Nancy A.; ADKINS, David; PHILLIPS, Barbara A. Gender differences in sleep and sleep-disordered breathing. Clinics in chest medicine, 2004, 25.2: 257-268.
RYU, Soomin, et al. The cross-sectional association of sleep disturbance and sleep apnea with complex multimorbidity among Chinese and Korean Americans. American Journal of Epidemiology, 2023, 192.3: 420-429.
STRAND, Linn B., et al. Insomnia and endothelial function–the HUNT 3 fitness study. PloS one, 2012, 7.12: e50933.
BUXBAUM, Sarah Gail. Genetics of sleep apnea. Case Western Reserve University (Health Sciences), 2002.