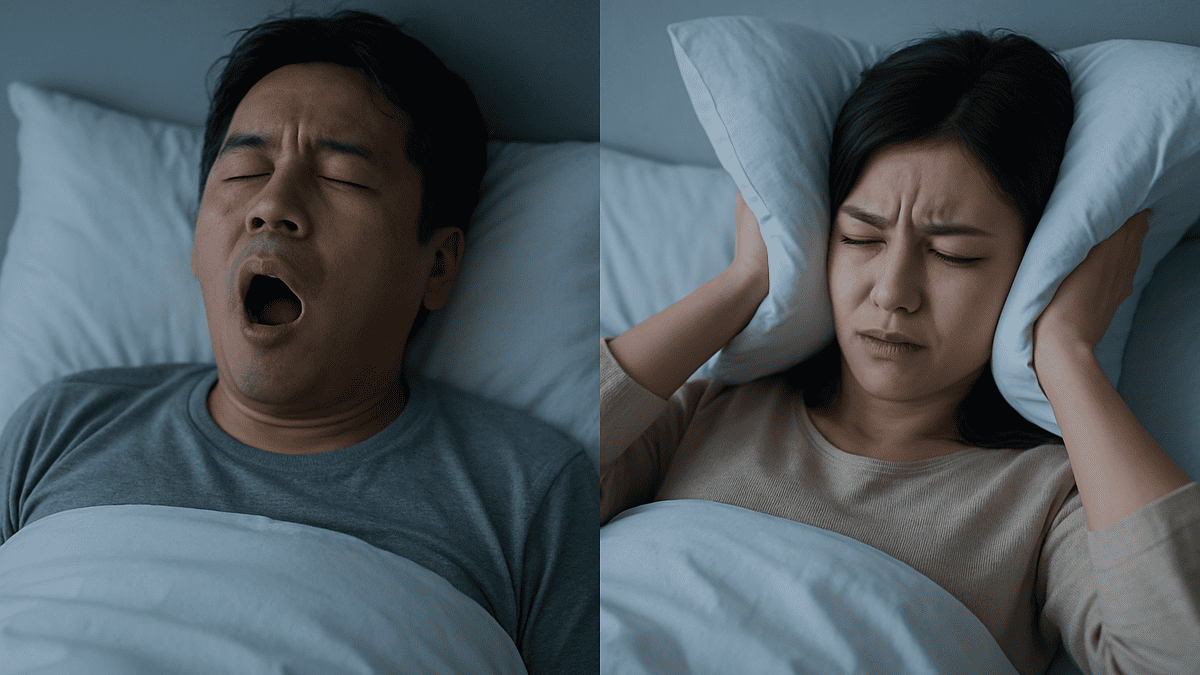睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診断では、「無呼吸」と「低呼吸」という二つの言葉が出てきます。どちらも睡眠中の異常な呼吸状態を指しますが、その意味には明確な違いがあります。
呼吸が完全に止まるのが無呼吸、浅くなるのが低呼吸です。
この記事ではこの二つの違いと、それぞれが体にどのような影響を与えるのか、そして診断や治療にどう関わってくるのかを基本から分かりやすく解説します。
ご自身の状態を正しく知ることは健康への第一歩です。
「無呼吸」と「低呼吸」の基本的な定義
睡眠時無呼吸症候群の診断は睡眠中に「無呼吸」と「低呼吸」がどのくらい発生しているかに基づいて行われます。
どちらも体に負担をかける危険な状態ですが、その定義は異なります。
呼吸が完全に止まる「無呼吸」
「無呼吸」とはその名の通り、呼吸が完全に停止してしまう状態を指します。医学的には口や鼻からの空気の流れ(気流)が10秒以上停止した場合に「無呼吸」と定義します。
この状態では肺に全く空気が送り込まれないため、体内の酸素濃度が急激に低下します。
呼吸が著しく浅くなる「低呼吸」
一方、「低呼吸」は呼吸が完全には止まらないものの、著しく浅く弱々しくなった状態です。
定義としては換気量が普段の50%以下に低下し、その結果として血液中の酸素濃度が3〜4%以上低下する状態が10秒以上続いた場合を指します。
完全に止まっていなくても体に必要な酸素を取り込めていないため、無呼吸と同様に危険な状態です。
無呼吸と低呼吸の定義比較
| 項目 | 無呼吸(Apnea) | 低呼吸(Hypopnea) |
|---|---|---|
| 気流の状態 | 10秒以上、完全に停止 | 10秒以上、著しく低下 |
| 体への影響 | 急激な酸素不足 | 持続的な酸素不足 |
どちらも危険な「酸欠状態」
無呼吸と低呼吸は程度の差こそあれ、どちらも体が酸素不足に陥るという点では共通しています。
睡眠中にこのような状態が何度も繰り返されると心臓や脳、血管に大きな負担がかかり、さまざまな生活習慣病を引き起こす原因となります。
そのため、診断においては両者を合わせて評価します。
なぜ無呼吸や低呼吸が起こるのか
睡眠中に呼吸が止まったり浅くなったりする主な原因は空気の通り道である「上気道」が狭くなることにあります。その背景にはさまざまな要因が関わっています。
上気道の物理的な閉塞
睡眠中は全身の筋肉が弛緩します。これには喉の周りの筋肉も含まれます。
この弛緩によって舌の付け根(舌根)や喉の奥の軟口蓋が下がり、気道を狭めたり、完全に塞いでしまったりすることがあります。
これが閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)と呼ばれる最も一般的なタイプのSASです。
気道を狭める主な要因
| 分類 | 具体的な要因 | 内容 |
|---|---|---|
| 体型 | 肥満(特に首周りの脂肪) | 脂肪が気道を外側から圧迫する |
| 骨格 | 顎が小さい、下顎が後退している | 舌が収まるスペースが狭い |
| 組織 | 扁桃腺やアデノイドの肥大 | 物理的に気道を塞ぐ |
脳の呼吸指令に問題がある場合
非常にまれですが、気道は開いているにもかかわらず、脳からの呼吸指令そのものが一時的に停止してしまうタイプもあります。これを中枢性睡眠時無呼吸(CSA)と呼びます。
心臓の機能が低下している方などに見られることがあります。
生活習慣との関連
就寝前のアルコール摂取は喉の筋肉の弛緩を増強させるため、無呼吸や低呼吸を悪化させます。また、喫煙は喉の粘膜に炎症を引き起こし、気道を狭める原因となります。
これらの生活習慣はSASのリスクを著しく高めるため注意が必要です。
無呼吸と低呼吸が体に及ぼす影響
無呼吸と低呼吸はどちらも体にダメージを与えますが、その影響の現れ方には若干の違いがあります。
しかし、最終的に引き起こされる結果は同じく深刻です。
血中酸素飽和度の低下
呼吸が止まる無呼吸では血中の酸素飽和度(SpO2)は急激に低下します。一方、低呼吸では比較的緩やかに低下します。
しかし、低呼吸が長く続けば結果的に無呼吸と同じくらい酸素濃度が低下することもあり、どちらも危険であることに変わりはありません。
脳の覚醒反応
体が酸素不足を感知すると脳は危険を察知して体を覚醒させ、呼吸を再開させようとします。この覚醒反応は無呼吸のように急激な酸素低下が起こる方が強く現れる傾向があります。
この反応が頻繁に起こることで、睡眠が分断され、熟睡感が得られなくなります。
呼吸イベントと身体反応
| 呼吸イベント | 酸素低下 | 覚醒反応 |
|---|---|---|
| 無呼吸 | 急激 | 強い |
| 低呼吸 | 比較的緩やか | 比較的弱い |
心臓・血管への累積ダメージ
一回ごとのダメージは無呼吸の方が大きいかもしれませんが、低呼吸も頻繁に繰り返されれば心臓や血管への負担は着実に蓄積されます。
どちらの状態も高血圧、心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる病気のリスクを高めるという点では同じです。
検査でどのように評価するのか
ご自身の睡眠中に無呼吸や低呼吸がどれくらい起きているかは専門的な検査によって初めて正確に知ることができます。
AHI(無呼吸低呼吸指数)という指標
SASの重症度を判断するために用いるのが、AHI(Apnea Hypopnea Index)です。これは睡眠1時間あたりの「無呼吸」と「低呼吸」の合計回数を示します。
例えばAHIが20回であれば1時間あたり平均20回、呼吸が止まったり浅くなったりしていることを意味します。
簡易検査と精密検査(PSG)
最初の段階では自宅で行える簡易検査でAHIのおおよその数値を調べます。
この検査で異常が疑われた場合、次に入院して行う精密検査(PSG)で脳波なども含めて詳細に評価し、確定診断を行います。
検査方法の比較
| 検査 | 場所 | 測定項目 |
|---|---|---|
| 簡易検査 | 自宅 | 呼吸、酸素飽和度など |
| 精密検査(PSG) | 医療機関(入院) | 脳波、心電図、呼吸など多数 |
AHIにおける無呼吸と低呼吸の扱い
AHIを計算する上では無呼吸も低呼吸も区別なく、同じ「1回」のイベントとしてカウントします。
これは、どちらも等しく睡眠の質を低下させ、体に負担をかける危険な状態であるという考え方に基づいています。
この合計回数によって重症度が判定されます。
AHI(無呼吸低呼吸指数)と重症度
AHIの数値は、SASの重症度を知り、適切な治療法を選択するための最も重要な手がかりです。
AHIによる重症度分類
AHIの数値に基づいて、SASの重症度は「軽症」「中等症」「重症」に分類されます。この分類は治療方針や保険適用の判断基準となります。
AHI数値と重症度
| 重症度 | AHI(1時間あたりの回数) |
|---|---|
| 正常 | 5回未満 |
| 軽症 | 5回以上15回未満 |
| 中等症 | 15回以上30回未満 |
| 重症 | 30回以上 |
重症度と治療法の選択
一般的にAHIが20以上の中等症から重症の場合、CPAP(シーパップ)療法という治療法の良い適応となります。
軽症の場合はマウスピース治療や生活習慣の改善が中心となりますが、症状によってはCPAP療法を検討することもあります。
自覚症状とAHIが一致しないことも
日中の眠気などの自覚症状が強いのにAHIの数値はそれほど高くないというケースもあります。逆にAHIが高い重症であるにもかかわらず、自覚症状がほとんどない方もいます。
そのため症状だけで重症度を判断するのは危険であり、客観的な検査データが重要です。
日常生活で注意すべきサイン
無呼吸や低呼吸は睡眠中に起こるため自覚しにくいですが、日常生活の中にそのサインが隠されています。
いびきは危険のサイン
いびきは気道が狭くなっている証拠です。
特に大きないびきが途中で止まり、しばらく静かになった後、あえぐような大きな呼吸とともに再びいびきが始まる場合は無呼吸が起きている典型的なパターンです。
- 毎晩大きないびきをかく
- いびきが途中で止まる
- 息苦しそうに呼吸を再開する
日中の強い眠気や倦怠感
夜間に無呼吸や低呼吸を繰り返していると脳や体が十分に休息できず、日中に強い眠気や倦怠感、集中力の低下といった症状が現れます。
これらの症状は睡眠の質が著しく低下していることを示しています。
家族からの指摘は重要な情報源
「呼吸が止まっていたよ」という家族からの指摘はSASを発見するための最も重要な手がかりです。
本人には自覚がないため、指摘されたら真摯に受け止めて専門の医療機関を受診することを強くお勧めします。
よくある質問
最後に、無呼吸と低呼吸に関して患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。
- Q低呼吸だけなら治療は不要ですか?
- A
いいえ、そんなことはありません。
AHIの数値が基準を超えていれば、それが低呼吸だけであっても治療の対象となります。
低呼吸も繰り返されれば無呼吸と同様に体に深刻なダメージを与え、合併症のリスクを高めます。
- Q無呼吸と低呼吸で治療法は変わりますか?
- A
治療法は無呼吸か低呼吸かという違いではなく、AHIの数値(重症度)や患者さん個々の症状、合併症の有無などによって総合的に決定します。
例えばCPAP療法は無呼吸も低呼吸も同様に防ぐことができます。
- Qいびきをかかなければ無呼吸ではありませんか?
- A
いびきを伴わない無呼吸(特に中枢性)も存在しますが、非常にまれです。ほとんどの閉塞性睡眠時無呼吸では、いびきが先行して現れます。
ただし、いびきの大きさや有無だけでSASを否定することはできません。気になる症状があれば検査を受けることが大切です。
以上
参考にした論文
HIROTSU, Camila, et al. Effect of three hypopnea scoring criteria on OSA prevalence and associated comorbidities in the general population. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2019, 15.2: 183-194.
AKASHIBA, Tsuneto, et al. Sleep apnea syndrome (SAS) clinical practice guidelines 2020. Respiratory Investigation, 2022, 60.1: 3-32.
NOZAWA, Shuhei, et al. The positional characteristics of patients with obstructive sleep apnea: a single institute retrospective study in Japan. Sleep and Biological Rhythms, 2022, 20.1: 115-121.
NAITO, Ryo, et al. Association between frequency of central respiratory events and clinical outcomes in heart failure patients with sleep apnea. Journal of clinical medicine, 2022, 11.9: 2403.
OHDAIRA, Fumi, et al. Demographic characteristics of 3,659 Japanese patients with obstructive sleep apnea–hypopnea syndrome diagnosed by full polysomnography: associations with apnea–hypopnea index. Sleep and Breathing, 2007, 11: 93-101.
NISHIBAYASHI, Momoka, et al. Correlation between severity of obstructive sleep apnea and prevalence of silent cerebrovascular lesions. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2008, 4.3: 242-247.
NAKANO, Hiroshi, et al. Validation of a new system of tracheal sound analysis for the diagnosis of sleep apnea-hypopnea syndrome. Sleep, 2004, 27.5: 951-957.
UENO, Kanako, et al. Evaluation of the apnea-hypopnea index determined by the S8 auto-CPAP, a continuous positive airway pressure device, in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2010, 6.2: 146-151.
TAKEDA, Takayuki, et al. Usefulness of the oximetry test for the diagnosis of sleep apnea syndrome in Japan. The American journal of the medical sciences, 2006, 331.6: 304-308.
KUWABARA, Mitsuo, et al. Novel triggered nocturnal blood pressure monitoring for sleep apnea syndrome: distribution and reproducibility of hypoxia‐triggered nocturnal blood pressure measurements. The Journal of Clinical Hypertension, 2017, 19.1: 30-37.