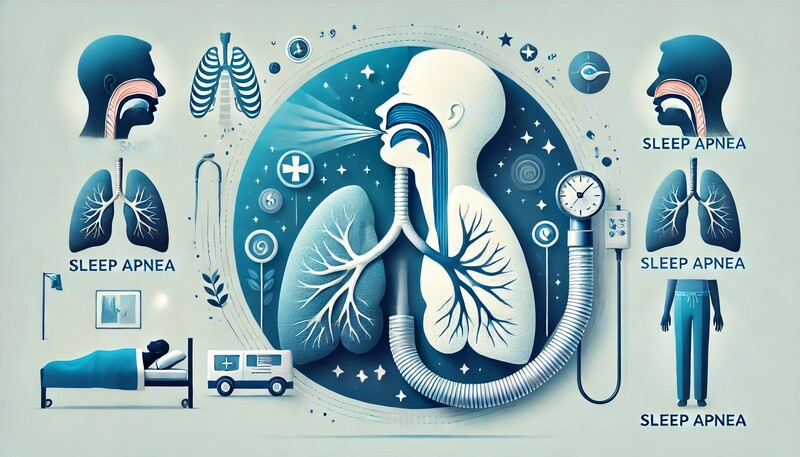夜間に響くいびきは単なる睡眠時の音だと思われがちですが、実は健康状態の変化を示すサインでもあります。
特にいびきをかく人の中には呼吸が何度も止まる「睡眠時無呼吸症候群」へ進行する可能性を抱えている場合もあります。
いびきを放置すると日中の眠気や集中力の低下、生活習慣病のリスク増大など、さまざまな問題につながります。
ここではいびきと睡眠時無呼吸症候群の関係やその危険性、そして適切な対策方法を詳しくお伝えいたします。
いびきと睡眠時無呼吸症候群の基礎知識
いびきを軽く考えてしまうと、気づかないうちに睡眠時無呼吸症候群へ移行し、健康面で大きな影響を受けるかもしれません。
まずはいびきや睡眠時無呼吸症候群の概要を理解し、早期発見や予防につなげることが大切です。
いびきの仕組み
いびきは睡眠中に気道が狭くなり、空気が通りにくくなることで発生します。
仰向けに寝たときや筋肉が緩んでいるときに起こりやすく、舌や軟口蓋が喉の奥へ落ち込みやすくなることで気道が狭まり、音が生じます。
いびきの主な要因と関連性
| 要因 | 内容 |
|---|---|
| 筋肉の緩み | 加齢や疲労、アルコールの影響で舌やのどの筋肉が緩む |
| 肥満 | 首回りの脂肪が気道を圧迫しやすくなる |
| 鼻づまり | アレルギー性鼻炎などで口呼吸になりやすくなる |
| 顎の構造 | 下顎が小さい場合や後退している場合、気道が狭くなる |
睡眠時無呼吸症候群とは
いびきがある人の中には無呼吸の状態が頻繁に起こる「いびきがある睡眠時無呼吸症候群」を抱えているケースがあります。
睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に呼吸が10秒以上停止する状態が1時間に5回以上見られる状態を指します。
このような状態になると深い眠りを得にくく、起床時の疲労感や日中の眠気、集中力の低下などにつながります。
いびきと無呼吸の関係
無呼吸といびきは非常に密接です。無呼吸の直前・直後には気道が狭くなっていることが多く、そこで喉や鼻の奥が振動していびきをかくパターンが見られます。
いびきが断続的に止まり、しばらくして大きな音とともに再開する場合は、いびきがある無呼吸症候群を疑う材料となります。
いびきがある無呼吸症候群が及ぼすリスク要素
| リスク | 具体的な影響 |
|---|---|
| 起床時の頭痛 | 酸素不足や寝不足による頭痛 |
| 日中の眠気 | 集中力の低下や事故のリスク増加 |
| 心臓への負担 | 血圧上昇や心拍数増加につながりやすい |
| 睡眠の質低下 | 成長ホルモン分泌の乱れ生活習慣病のリスク増大 |
睡眠時無呼吸症候群を疑うサイン
- 夜間に激しいいびきをかく
- いびきがとぎれとぎれで、その後大きく息を吸うような呼吸をする
- 日中に強い眠気やだるさを感じる
- 目覚めが悪く頭痛が起こりやすい
上記のような症状が続く場合は単に「疲れているから」と見過ごすのではなく、一度医療機関へ相談すると早期対策につながります。
なぜいびきを放置してはいけないのか
いびきは身近な存在と思われがちですが、放置すると睡眠の質の低下だけではなく多岐にわたるトラブルを引き起こす要因になります。
自分自身はもちろん、周りの人々にも悪影響を及ぼすことがあるので注意が必要です。
いびきがもたらす健康への影響
いびきをかく人は呼吸が一定のリズムを保ちにくい傾向があります。
結果として睡眠の質が悪くなり、深い眠り(ノンレム睡眠)が妨げられやすくなります。
睡眠の質が下がる主な影響
- 成長ホルモンの分泌低下
- 免疫力の低下
- 感情の不安定化
- 体の疲労回復の遅れ
眠りが浅くなると翌日の体力や集中力が落ちるだけでなく、体内のホルモンバランスが乱れ、食欲のコントロールが難しくなることも報告されています。
睡眠不足が体にもたらす弊害
いびきの影響で睡眠不足になると日中のパフォーマンス低下だけでなく、高血圧や糖代謝異常など生活習慣病のリスクも上がります。
長期間の睡眠不足が続くと、うつ症状をはじめとする精神面への悪影響も大きくなります。
生活習慣病リスクとの関連性
| 生活習慣病 | いびき・睡眠不足との関係 |
|---|---|
| 高血圧 | 睡眠不足による交感神経亢進が血圧を上昇させる |
| 糖尿病 | ホルモンバランスの乱れが血糖コントロールを悪化させる |
| 心疾患 | 循環器系への負担増大で心臓に負荷がかかる |
| 肥満 | 睡眠不足による食欲増進と基礎代謝の低下 |
生活習慣病とのつながり
無呼吸といびきが長引くと代謝系や循環器系に負担がかかります。
肥満が原因の人はさらに体重が増えやすくなり、生活習慣病のリスクを高める悪循環に陥りがちです。
こうした連鎖を断ち切るためにも、いびきを単なる症状として終わらせず、早めに根本的な対策を検討することが重要です。
周囲の家族やパートナーへの影響
- 同室の人の睡眠を妨げる
- いびきを心配し、夜中に起こしてしまう
- 家族が睡眠不足になる
家族やパートナーが不安やストレスを抱えるケースもあるため、いびきの治療は本人だけでなく周囲の生活の質も改善するメリットが期待できます。
睡眠時無呼吸症候群が原因となる合併症
いびきがある無呼吸症候群を放置すると、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。
日常生活の不調にとどまらず、心血管系や脳血管系などに重大なリスクを及ぼすため、早期発見と治療が望まれます。
高血圧や心疾患との関係
無呼吸といびきを繰り返す睡眠時無呼吸症候群では夜間の酸素不足が交感神経を刺激します。
結果として血圧が上がりやすくなり、心臓に負担をかけて心不全や狭心症のリスクを高めることがあります。
心疾患に関する警戒ポイント
- 夜間や早朝の胸の違和感
- 朝起きたときの強い動悸
- 運動時の息切れ・胸部圧迫感
- 不整脈の頻度が増える
脳血管疾患のリスク
無呼吸による慢性的な酸素不足や血圧上昇が続くと脳の血管にも負担をかける可能性があります。
脳卒中や一過性脳虚血発作を起こすリスクが高まるという報告もあり、いびきがある睡眠時無呼吸症候群を軽視できません。
糖尿病との関連
睡眠の質が悪化し、ホルモンバランスが乱れると血糖値のコントロールが難しくなります。
もともと糖尿病予備群だった人は、いびきや無呼吸が症状を悪化させる一因になる可能性があります。
糖尿病患者の睡眠時無呼吸症候群における特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| インスリン抵抗性の上昇 | 睡眠不足でホルモン分泌が乱れやすい |
| 血糖値のコントロール低下 | 寝不足により食事の摂取量やタイミングが乱れる |
| 体重増加傾向 | 倦怠感や運動不足が拍車をかける |
交通事故や労働災害のリスク
日中の眠気や集中力の低下は車の運転や高所作業などで重大な事故につながります。
いびきがある無呼吸症候群を抱えている場合、居眠りや注意力散漫が深刻化しやすく、自分や周囲の安全を脅かすことにもなりかねません。
- 長距離運転時に強い眠気を感じる
- 信号待ちなどでうとうとしてしまう
- 作業中に集中力が途切れる
上記の症状がある場合、早めの医療相談が大切です。
自分でできるチェックポイント
いびきがある無呼吸症候群は本人が気づきにくい部分もありますが、まずは自分の生活習慣や体調を見直すことで症状の有無やリスクをある程度把握できます。
簡単に実践できるチェックを活用し、早めの予防や対応につなげてください。
日常生活での観察項目
- 夜間のいびきの大きさや途切れ方
- 朝起きたときののどの渇きや痛み
- 深夜に何度も目が覚める頻度
- 日中の強い眠気や疲労感
自宅で一人暮らしの場合は自分のいびきを直接観察できませんが、スマートフォンの録音機能などを活用する方法があります。
パートナーや家族がいる場合は、いびきが無呼吸を伴うかどうかを聞いてみると判断材料になります。
自己チェックに便利なポイント
| 項目 | 確認方法 |
|---|---|
| いびきの音量 | アプリの録音機能を使う |
| 無呼吸の有無 | 同居人に聞いてもらう、録音で音の途切れを確認 |
| 起床時の状態 | のどの乾燥や頭痛の有無 |
| 日中の眠気 | 昼間の集中力の度合い |
眠気の度合いや集中力の低下
日中の眠気や集中力低下は睡眠時無呼吸症候群のサインかもしれません。
仕事中や運転中に突然の眠気が襲う、テレビを見ているときにうとうとしてしまうなどの頻度が増えているなら要注意です。
首回りの太さと体格
首回りが太い人や肥満傾向がある人はいびきをかきやすく、睡眠時無呼吸症候群になるリスクも高いとされています。
体格指数(BMI)や腹囲を測る習慣をつけることも自分のリスクを把握するうえで有用です。
- BMI(体格指数): 体重(kg) ÷ [身長(m)]²
- 首回りの計測: 首の付け根部分の周囲を測る
アプリやデバイスによる睡眠管理
最近は睡眠トラッキング機能を搭載したアプリやスマートウォッチ、バンド型のデバイスなどが普及しています。
これらを活用して夜間の活動量やいびきの有無を記録しておくと医師に相談するときの情報としても役立ちます。
クリニックで行う診断方法
いびきと睡眠時無呼吸症候群の疑いが強い場合は医療機関での診断が正確な判断につながります。
専門の検査を受けることで、より適切な治療方法を選択しやすくなります。
問診や身体診察
医師はまず、患者さんから生活習慣や症状について詳しく聞き取りを行います。
そのうえで首の太さや口腔内の構造をチェックし、いびきがある無呼吸症候群のリスクを判断します。既往症や服用中の薬の種類なども確認対象となります。
問診時に聞かれる主なポイント
- いびきの有無とその頻度
- 睡眠時間、睡眠の深さ
- 起床時の頭痛やのどの違和感
- 日中の眠気や居眠りの状況
- 喫煙や飲酒の習慣
簡易検査(スクリーニング)
自宅で装着可能な携帯型の機器を使い、夜間の呼吸状態や血中酸素飽和度を記録する方法があります。
この簡易検査で無呼吸や低呼吸の頻度が高いと判定された場合、詳細な検査を行うことが推奨されます。
本格的な睡眠検査(ポリソムノグラフィ)
睡眠外来などで実施するポリソムノグラフィは脳波、心電図、呼吸の動き、いびきの音量など多岐にわたるデータを同時に測定します。
この検査によって、いびきや呼吸停止がどの程度深刻か、何が原因となっているかを詳細に把握できます。
ポリソムノグラフィで記録する主な項目
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| 脳波 | 睡眠の深さや眠りの周期を知る |
| 酸素飽和度 | 血中の酸素レベルを測定 |
| 心電図 | 心拍数や不整脈の有無を確認 |
| 気流センサー | 鼻・口の呼吸流量を測定 |
| いびきマイク | いびきの音量やタイミングを把握 |
結果の評価と治療方針
検査結果をもとに、いびきがある無呼吸症候群の重症度や合併症のリスクを評価します。医師はこれらの情報を総合的に判断して治療方針を決定します。
軽症であれば生活習慣改善を中心に、中等症以上であればマウスピースやCPAP(シーパップ)の検討などが行われます。
治療の選択肢とその効果
いびきがある睡眠時無呼吸症候群の治療には生活習慣の改善から医療機器の使用、外科的治療など多彩な方法があります。
それぞれの方法にメリットとデメリットがありますので、自分の症状やライフスタイルに合った治療を選ぶことが重要です。
生活習慣の改善
- 減量:肥満傾向がある場合、体重を落とすことで気道周囲の脂肪を減らし、いびきを緩和しやすくなる
- 禁酒・節酒:アルコールは咽頭周囲の筋肉を緩ませ、いびきや無呼吸を悪化させる要因
- 禁煙:喉や鼻粘膜への刺激を減らし、気道の炎症を抑える
- 睡眠姿勢の工夫:横向き寝など気道を確保しやすい姿勢を意識する
生活習慣改善によるメリット比較
| 項目 | 効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 減量 | 気道の圧迫軽減 | 急激なダイエットは避け、継続を目指す |
| 禁酒 | 筋肉の弛緩を抑える | 完全に断つのが難しい場合は量を減らす |
| 禁煙 | 炎症を減らし呼吸通路を保護 | 長期間継続が必要 |
| 横向き寝 | 気道閉塞を防ぎやすい | 枕やクッション選びがポイント |
マウスピース治療
歯科で作成するマウスピース(口腔内装置)は就寝時に下顎を前方に固定することで喉の奥の気道を広げ、いびきと無呼吸を軽減する方法です。
中等症までの睡眠時無呼吸症候群には有効とされ、手軽に開始しやすいのが特徴です。
CPAP(シーパップ)療法
中等症から重症のいびきがある無呼吸症候群に対してはCPAP装置を用いる方法があります。
鼻や口にマスクを装着し、一定の陽圧をかけることで気道の閉塞を防ぎます。
無呼吸や低呼吸を即時に抑制する効果が高い一方で、機器の装着に慣れる必要があります。
CPAP利用者が感じやすいメリットと課題
| メリット | 課題 |
|---|---|
| 無呼吸がほぼゼロに近づき、日中の眠気が改善しやすい | 機器の装着感に慣れる期間が必要 |
| 血圧や心血管リスクの低減が期待できる | マスクや機器の定期的なメンテナンスが必要 |
| 高い治療継続率で効果を実感しやすい | 装置の動作音やエア漏れに気をつける必要がある |
外科的治療
口蓋や鼻中隔など構造的な問題によって気道が狭い場合、手術で余分な組織を切除・修正していびきや無呼吸を改善する手段も存在します。
ただし体への負担やダウンタイムを考慮したうえで、医師とじっくり相談することが大切です。
睡眠時無呼吸症候群を予防するポイント
いびきがある無呼吸症候群を未然に防ぐには早期の注意と予防策の実践が大切です。
症状が深刻化してから治療を始めるより、普段から対策を心がけることで身体的・経済的な負担を減らすことができます。
日常生活の工夫
- 食事内容の見直し:高カロリー・高脂質の摂取を控える
- ストレッチや適度な運動:首や肩回りのコリを解消し、睡眠を深める
- 規則正しい生活リズム:就寝・起床時間を一定にする
- 部屋の環境整備:適度な室温や湿度、照明で眠りを誘いやすくする
運動習慣と睡眠の相関
| 運動時間 | 睡眠の質の変化 | おすすめ度 |
|---|---|---|
| 朝の軽い体操 | 体温を上げて1日を活発に過ごしやすい | ★★★ |
| 昼の散歩 | ストレス緩和や血行促進に役立つ | ★★ |
| 夜の激しい運動 | 交感神経が高ぶり、寝付きが悪くなる場合がある | ★ |
睡眠の質を高める習慣
寝る前のスマートフォン利用や、カフェインの過剰摂取は睡眠の質を下げる要因になります。
青白い光や興奮作用を含む飲食物を就寝前に控えることはいびきの発生を減らすだけでなく、全般的な睡眠の質を向上させる可能性があります。
アルコールや喫煙の影響
アルコールは喉の筋肉を弛緩させ、いびきが発生しやすくなります。また、喫煙によって鼻や喉の粘膜が炎症を起こし、気道が狭くなることも指摘されています。
いびきや無呼吸を軽減するためにはアルコール摂取量の管理や禁煙が大きな意味を持ちます。
継続的な経過観察の大切さ
いびきがある無呼吸症候群は一時的に改善したように見えても、生活習慣が変わらなければ再発リスクが高いです。
症状の変化をこまめに記録し、定期的に検査を受けることで健康な睡眠を維持しやすくなります。
当院でのサポート体制
いびきがある無呼吸症候群は医療機関での専門的なサポートによって適切な治療と生活指導を受けられます。
当院では患者さんが安心して治療を継続できるよう、多方面からのサポートを行っています。
カウンセリングの流れ
問診から始まり、必要に応じて検査や生活習慣へのアドバイスを行います。診断結果によっては治療方法を提案し、定期的にフォローアップを実施します。
患者さんの状態や希望に合わせて個別のプランを立てるため、治療を始めやすい環境を提供しています。
当院の初診時に行う主な内容
| 内容 | 目的 |
|---|---|
| 問診 | 症状・生活習慣の把握 |
| 身体測定 | BMIや首回りの測定 |
| スクリーニング検査 | 睡眠時の呼吸状態を簡易的に把握 |
| カウンセリング | 今後の治療方針や疑問点の解消 |
検査や治療の受け方
当院では簡易検査から本格的なポリソムノグラフィまで対応し、患者さまの症状に応じた診断を行います。
結果に基づき、マウスピースやCPAPの使用、または生活習慣の指導など複数の治療選択肢を提示します。
継続的にサポートし、効果や副作用を確認しながら治療を進める方針です。
多職種との連携によるケア
睡眠外来の医師や歯科医師、管理栄養士など、必要に応じて連携を図ることで包括的に患者さまの健康を支える体制を整えています。
例えば肥満が強く関係している場合は食事指導を、顎の形状や歯並びが影響している場合は歯科領域の検討をすすめるといった形です。
受診を検討している方へ
- いびきの大きさや日中の眠気など気になる症状があれば早めにご相談ください
- 自己判断で「まだ大丈夫」と思う段階でも検査で確かめることが安心につながります
- 一度診断を受けると適切な治療と生活指導が受けられます
以上
睡眠時無呼吸症候群を知ろう
参考にした論文
NAGAYOSHI, Mako, et al. Risk factors for snoring among Japanese men and women: a community-based cross-sectional study. Sleep and breathing, 2011, 15: 63-69.
YANAGI, Hiromasa, et al. Acute aortic dissection associated with sleep apnea syndrome. Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2013, 19.6: 456-460.
KASHINE, Susumu, et al. Characteristics of sleep-disordered breathing in Japanese patients with acromegaly. Endocrine journal, 2012, 59.1: 31-38.
SEKIZUKA, Hiromitsu; MIYAKE, Hitoshi. Relationship between snoring and lifestyle-related diseases among a Japanese occupational population. Internal Medicine, 2020, 59.18: 2221-2228.
MUTOH, Tomoyuki, et al. Study on the frequency and risk factors of moderate-to-severe sleep apnea syndrome in rheumatoid arthritis. Modern Rheumatology, 2016, 26.5: 681-684.
TADA, Takeshi, et al. The predictors of central and obstructive sleep apnoea in haemodialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantation, 2007, 22.4: 1190-1197.
TANAKA, Nobuaki, et al. Sleep apnea severity in patients undergoing atrial fibrillation ablation: home sleep apnea‐test and polysomnography comparison. Journal of Arrhythmia, 2023, 39.4: 523-530.
WADA, Hiroo, et al. Prevalence and clinical impact of snoring in older community‐dwelling adults. Geriatrics & Gerontology International, 2019, 19.11: 1165-1171.
NAGAYOSHI, Mako, et al. Self-reported snoring frequency and incidence of cardiovascular disease: the Circulatory Risk in Communities Study (CIRCS). Journal of epidemiology, 2012, 22.4: 295-301.
KATSUMATA, Kazuo, et al. High incidence of sleep apnea syndrome in a male diabetic population. Diabetes research and clinical practice, 1991, 13.1-2: 45-51.
TAKAMA, Noriaki; KURABAYASHI, Masahiko. Possibility of close relationship between sleep disorder breathing and acute coronary syndrome. Journal of cardiology, 2007, 49.4: 171.