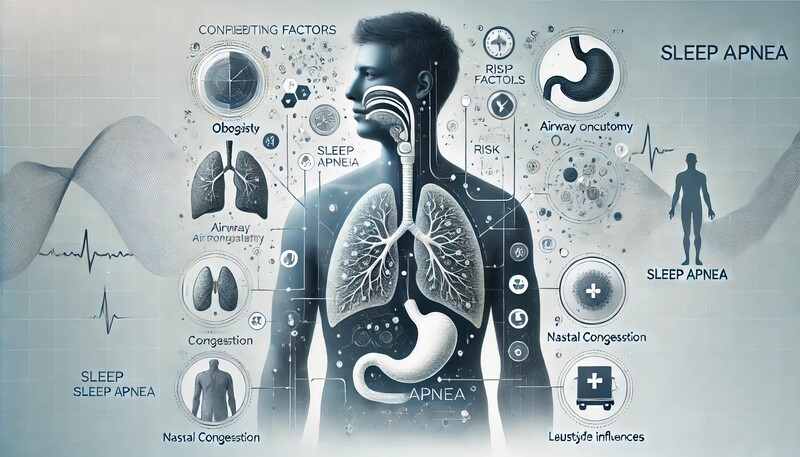眠中に断続的に呼吸が止まる状態が繰り返される睡眠時無呼吸症候群は、ただ寝ている間に息が止まるだけと思われがちですが、体全体に大きな負担を与えます。
自覚症状が乏しい方も多く、気付かないうちに生活の質を落としている場合もあります。
この記事では睡眠時無呼吸症候群の原因や発症リスクを高める要因について、できるだけ詳しく解説します。
今後の予防や早期治療を考える上での参考にしていただければ幸いです。
睡眠時無呼吸症候群とは何か
睡眠時無呼吸症候群は夜間の睡眠中に呼吸が何度も止まる状態を指し、血中の酸素濃度が低下しやすくなるのが特徴です。
この状態が長期間続くと、さまざまな健康上の問題に結びつく可能性があります。
日常的な疲労感だけでなく、心血管系のトラブルとも関連があると考えられています。
ここでは、まず睡眠時無呼吸症候群という病気について基本的な部分を整理します。
睡眠時無呼吸症候群の定義
睡眠時無呼吸症候群では10秒以上の呼吸停止が1時間あたり5回以上起こります。
特に長時間にわたる無呼吸によって酸素不足が深刻化すると睡眠の質が著しく低下し、昼間の眠気が強まったり集中力が落ちたりする原因になりやすいです。
また、高血圧や心不全などの循環器系疾患を合併しやすい傾向があります。
主な特徴
- 夜間のいびきが大きい
- 呼吸停止後に突然息を吹き返すようないびきがある
- 朝起きたときの口の乾き
- 日中の強い眠気や集中力の低下
- 起床時の頭痛や熟睡感の欠如
閉塞性と中枢性の2つのタイプ
睡眠時無呼吸症候群は大きく分けて気道がふさがることによって生じる閉塞性と、脳の呼吸中枢から呼吸指令が十分に出せないために生じる中枢性の2つのタイプがあります。
一般的には閉塞性が多く、肥満や顎の骨格などの構造上の特徴が関与する場合が多いです。
一方、中枢性では脳が呼吸指令を出す働きが低下することが原因となり、高齢者や心疾患を持つ方にみられることがあります。
睡眠時無呼吸症候群が引き起こす問題
睡眠時無呼吸症候群が長期化すると心血管系のリスクが上昇し、高血圧・心筋梗塞・脳卒中といった疾患の発症につながる恐れがあります。
さらに日中の眠気が強くなるため、業務に支障が出たり、交通事故のリスクが高まったりする懸念もあります。
生活全体のパフォーマンスを落とすだけでなく、家族や職場など周囲との関係にも影響を与えます。
睡眠障害により起こりやすい生活への影響
- 昼間の眠気と仕事や家事の能率低下
- 心理的ストレスの増大
- 夜間頻尿による睡眠断片化
- 肥満傾向の強化(悪循環)
- 不整脈など循環器合併症
睡眠時無呼吸症候群の主な原因
睡眠時無呼吸症候群の原因としては物理的に上気道が狭くなることによって無呼吸が生じるケースが代表的です。
しかし、それ以外にも解剖学的や遺伝的、生活習慣にまつわる要因などが複雑に絡み合うことが多いです。
ここでは無呼吸症候群の原因となる代表的な要素を挙げて解説します。
上気道が狭くなる要因
睡眠時無呼吸症候群の原因の大部分は睡眠中に上気道が物理的に狭くなることと関連します。
軟口蓋、舌、咽頭まわりの筋肉が弛緩し、空気の通り道が閉塞しやすくなるため、息がうまく通らず無呼吸が起こります。
特に肥満があると喉周囲の脂肪が増えて気道が狭くなりやすくなります。
上気道を狭めるリスクに関連する因子一覧
| 因子 | 具体例 | なぜ気道が狭くなるか |
|---|---|---|
| 肥満 | 首まわりの脂肪増加 | 喉周辺の軟部組織が肥大し空気の通り道が狭まる |
| 顎の骨格 | 下顎が小さい、後退している | 舌や軟口蓋が気道方向に押し出されやすい |
| 上気道粘膜のむくみ | アレルギー性鼻炎、慢性鼻炎など | 喉や鼻腔周辺の粘膜が肥厚し空気抵抗が上がる |
| 筋力の低下 | 加齢、筋肉量の減少 | 喉周辺の筋肉がたるんで気道が閉塞しやすい |
肥満と体型の影響
肥満と睡眠時無呼吸症候群の原因は密接な関係があります。
特に首周りに脂肪がつきやすい「りんご型肥満」の方は首や顎の周囲の組織が厚くなることで無呼吸につながりやすくなります。
肥満だけが直接の要因ではありませんが、睡眠中に気道がふさがるリスクを飛躍的に高める大きな要因の1つと考えられています。
肥満が無呼吸に及ぼす主な影響
- 首まわりの脂肪組織が増えることで気道が圧迫される
- 内臓脂肪の増加が呼吸筋の動きを制限して呼吸が浅くなる
- 体重が増えると呼吸のためのエネルギー消費が大きくなり疲労感が増す
- 血中酸素濃度の低下が代謝を悪化させ体重増加を助長する場合もある
解剖学的・遺伝的要素
遺伝要素や生まれつきの顎の形、鼻や喉の解剖学的構造なども無呼吸の原因となります。
例として、小顎症や扁桃肥大、鼻中隔湾曲などの問題が挙げられます。これらは体質による部分が大きく、生活習慣を見直すだけでは改善しにくい場合もあります。
解剖学的な問題が疑われる場合のチェックリスト
- 子供のころから大きないびきをかいていた
- 扁桃腺がもともと大きかった
- 慢性的な鼻詰まりがある
- 近親者に睡眠時無呼吸症候群が多い
発症リスクを高める要因
睡眠時無呼吸症候群が起こりやすいかどうかには肥満や構造的な特徴だけでなく、年齢や性別、生活習慣などさまざまな要因が絡み合います。
ここでは主な発症リスクを高める要因を具体的に見ていきます。
年齢と性別の影響
一般的に40代以降の男性に多いイメージがありますが、更年期を迎えた女性にも起こります。
女性の場合はホルモンバランスの変化によって筋肉の緊張度や体脂肪率の変化が出やすく、閉経後に急激にリスクが増すケースがあります。
年齢や性別による発症率の違い
| 年齢層 | 男性の発症率傾向 | 女性の発症率傾向 |
|---|---|---|
| ~30歳 | 低め | 低め |
| 30~40代 | 徐々に上昇(特に肥満傾向) | 比較的低めだが肥満や遺伝要素で増える |
| 40~50代 | 高め(ホルモン分泌の変化も影響) | 更年期に近づくと増加傾向 |
| 60歳~ | 加齢による気道筋肉の弛緩 | 閉経後はリスクが高まる |
生活習慣がもたらすリスク
食生活の乱れや運動不足、偏った食事などは体重増加につながりやすく、上気道閉塞のリスクを高める要因になります。
また、夜間の飲酒や寝る直前の大量食事は呼吸中枢だけでなく気道の筋肉を弛緩させ、無呼吸の原因になることがあります。
生活習慣における気を付けたいポイント
- 高カロリー・高脂質の食事が中心になっている
- 運動習慣が少なく体重管理ができていない
- 睡眠前のアルコールや喫煙習慣がある
- 夜更かしや不規則な生活リズム
喫煙や飲酒との関係
喫煙は喉や鼻粘膜の炎症を助長して気道を狭める原因になります。
さらに飲酒は咽頭周辺の筋肉を弛緩させやすく、特に就寝前の飲酒は無呼吸発作を助長します。
深酒をすると呼吸が乱れやすくなるだけでなく、いびきや覚醒反応が強くなることもあるので注意が必要です。
飲酒と喫煙が無呼吸発作に与える影響
| 習慣 | 具体的影響 | リスク度合い |
|---|---|---|
| 喫煙 | 気道粘膜の炎症、分泌物の増加 | 中程度~高い |
| 飲酒 | 咽頭筋肉の弛緩、呼吸中枢の感度低下 | 高い(就寝前はさらに注意) |
睡眠時無呼吸症候群の症状と日常生活への影響
睡眠時無呼吸症候群は夜間のいびきや無呼吸だけではなく、日中の眠気や倦怠感など生活のあらゆる面に影響を及ぼします。
ここでは代表的な症状と日常生活で起こり得る影響を見ていきます。
代表的な自覚症状
自分自身で気付きやすい症状としては大きないびきや夜間の息苦しさ、朝起きたときの口渇感などが挙げられます。
夜間頻尿や汗をかきやすいこともあり、寝付きが悪くなったり夜間にしばしば目が覚めたりするケースもあります。
ただし、これらが必ずしも睡眠時無呼吸症候群に直結するわけではないため、気になる場合には早めに受診して検査を受けることが大切です。
他覚的な徴候と周囲の気付き
本人は深く眠っているつもりでも大音量のいびきや息が止まる状態は家族やパートナーが先に気付く場合が多いです。
一方で1人暮らしの方は指摘が受けられず、自分でまったく気付かないまま無呼吸症候群が進行するケースも珍しくありません。
周囲が気付きやすいポイント
- 寝ている間に10秒以上息が止まっている
- いびきが止んだあと一気に呼吸を始める
- 寝姿勢が異常に悪い、あるいは体を頻繁に動かす
- 夜間にむせるような咳き込みが度々起こる
日常生活への負荷
無呼吸の原因が解消されない状態が続くと眠りが浅くなり日中の眠気や疲労感が強まります。その結果、仕事のミスが増えたり集中力が続かなくなったりする可能性があります。
また、慢性的な睡眠不足がストレスを増大させ、精神面にも悪影響を及ぼす懸念があります。
睡眠時無呼吸症候群が引き起こす日中の疲労感
| 症状 | 日中の影響 | 二次的な問題 |
|---|---|---|
| 慢性的な眠気 | 業務効率の低下、注意力散漫 | 交通事故リスクの上昇 |
| 集中力・判断力の低下 | ミスの増加、学習・仕事能力の低下 | 焦燥感・イライラの増大 |
| 睡眠の質の低下による疲労 | 活動量の低下、体力の消耗が早まる | 運動不足による肥満リスク増加 |
睡眠時無呼吸症候群の検査方法
睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、まずは専門の検査を受けて状態を正確に把握することが大切です。
ここでは主な検査の手法とそれぞれの特徴を解説します。
ポリソムノグラフィー(PSG)
最も詳しく状態を調べる方法として睡眠医療の現場でよく用いられるものがポリソムノグラフィーです。
脳波や心電図、筋電図、気流、胸腹部の動きなどを同時に測定し、睡眠時に起こる身体の変化を詳細に調べます。
検査結果から無呼吸の程度だけでなく脳の活動状態や心拍の変動も分かるため、総合的な診断に役立ちます。
ポリソムノグラフィーで測定できる主な項目
- 脳波(睡眠ステージの把握)
- 眼球運動(REM睡眠の測定)
- 心電図(不整脈や心拍数の変動)
- 呼吸気流と胸腹部の動き
- 酸素飽和度と二酸化炭素濃度
簡易検査
医療機関で行う簡易検査では酸素飽和度や気流、いびきの有無など限られた項目だけを測定します。
ポリソムノグラフィーほど詳細ではありませんが、自宅で装着して行うことも可能で、初期スクリーニングとして有効です。
無呼吸症候群の原因を幅広く探るには物足りない場合もありますが、簡易検査で一定の数値が確認された場合には、さらに精密検査を検討します。
簡易検査のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 自宅で検査が可能 | 睡眠環境が普段と変わらないため自然に近い |
| 費用と時間の負担が少ない | 医療機関に泊まるよりも手軽 |
| スクリーニングとして有用 | 重症度の大まかな判定が容易 |
自宅での検査の注意点
自宅で行う簡易検査は気軽に受けやすい反面、センサーの装着状態や測定環境によっては誤差が生じる可能性があります。
また、データの質が病院での精密検査ほど高くないため最終的な診断には医師の判断が不可欠です。
自己判断で安心せず、医療機関でのフォローアップも視野に入れてください。
早期治療の重要性
睡眠時無呼吸症候群は放置すると心臓や血管、脳に対して悪影響を及ぼすリスクが高くなります。
軽度と思われていた症状が実際には深刻な合併症の温床となっているケースもあるため早期発見と早期治療が大切です。
ここでは睡眠時無呼吸症候群が長引くことで生じるリスクと治療開始のタイミングについて解説します。
心血管リスクの増大
無呼吸の原因を放置すると血中酸素濃度が断続的に低下し、交感神経が過剰に刺激されます。
その結果、血圧が上がりやすくなり、高血圧や不整脈、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まります。
夜間に十分な休息がとれず心臓に負担がかかると循環器系トラブルのリスクがさらに上乗せされます。
心血管リスクに関連するデータ
| リスク因子 | 睡眠時無呼吸症候群の影響 | 将来的に考えられる疾患 |
|---|---|---|
| 高血圧 | 夜間の酸素低下と交感神経刺激 | 慢性的な血圧上昇 |
| 不整脈 | 酸素不足による心筋への影響 | 心房細動、期外収縮など |
| 動脈硬化 | 交感神経の亢進と血管内皮障害 | 心筋梗塞、脳梗塞 |
生活の質を維持するための治療
日中の眠気が続くと仕事や家事に支障が出たり、学習意欲や集中力の低下により、人生全般のクオリティを下げてしまう恐れがあります。
睡眠の質を改善することで意欲や思考力が回復し、生活そのものが大幅に楽になります。
十分な睡眠は体だけでなく心の安定にもつながり、社会生活を円滑に営む上でも重要です。
睡眠の質を維持するメリットのリスト
- 朝の目覚めがすっきりしやすくなる
- 日中の作業効率が高まる
- ストレス耐性が向上する
- 家庭や職場での活力が増す
治療を検討するタイミング
いびきや日中の眠気が続くだけでなく、高血圧やメタボリックシンドロームを抱えている方は早めに検査を受けたほうが望ましいです。
症状が軽度でも予備軍として早めに対処しておくことで将来的なリスクを下げられる可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群の治療と対策
無呼吸症候群の原因に応じて、さまざまな治療法や対策が考えられます。
代表的なアプローチとしてはCPAP療法やマウスピース、ライフスタイルの改善などがあります。
ここではそれぞれの特徴とメリット・デメリットを詳しく見ていきます。
CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)
CPAPは就寝時にマスクを装着して気道に持続的に空気を送り込むことで上気道の閉塞を防ぐ治療法です。
効果が高い一方で毎晩機器を使用しなければならないことや、マスクの装着感に慣れる必要があることなどがデメリットとして挙げられます。
CPAP使用のメリット
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 高い治療効果 | 無呼吸発作のほとんどを抑制できる |
| 合併症予防 | 血圧・心拍への負担を軽減する |
| 即効性 | 装着したその日から効果を感じやすい |
| 検査データの管理 | CPAP機器の使用データで治療効果を把握しやすい |
マウスピース(口腔内装置)
マウスピースは歯科医が作成する装置で下顎を前方に保持して気道を広げる仕組みを利用します。
軽度から中等度の睡眠時無呼吸症候群に対して有効で、装着が比較的簡便なため、CPAPが苦手な方や旅行の際に使用したい方にも向いています。
ただし、顎関節症などを抱えている場合には装着が難しいケースもあります。
マウスピースの適応になりやすいケース
- 軽度~中等度の睡眠時無呼吸症候群
- 肥満度が比較的低い
- CPAPに抵抗感がある
- 持ち運びや管理のしやすさを重視
手術やライフスタイルの改善
鼻中隔湾曲や扁桃肥大など構造的な異常が明らかな場合には手術によって気道を広げる方法も検討されます。
また、肥満が原因として大きい場合には減量に向けた食生活の改善や運動療法も積極的に行う必要があります。
いずれの場合も一時的な対策だけでなく、生活習慣を継続的に見直すことが大切です。
生活習慣改善で意識したいリスト
- 高カロリー食品を控えてバランスの良い食事を心がける
- ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動を週に数回取り入れる
- 就寝前の飲酒量を減らす、喫煙をやめる
- 規則正しい睡眠時間を確保し、起床時間を一定に保つ
予防や日常生活で気を付けるポイント
睡眠時無呼吸症候群を予防するためには原因となる上気道の閉塞や肥満などをコントロールすることが重要です。
ここでは具体的に日常生活で実践できる予防策を紹介します。
体重管理の重要性
体重が増加すると首まわりの脂肪が増え、気道が狭くなる可能性が高まります。
BMIが高い方やウエスト周りが増えてきたと感じる方は、睡眠の質を高めるためにも体重管理に注意してください。
適正体重をキープするだけで無呼吸発作が軽減するケースも多々あります。
体重管理で意識すべきポイント
| 項目 | 具体的な目標・方法 |
|---|---|
| 目標体重設定 | BMI25以下を目指す |
| 食事コントロール | 野菜・たんぱく質を中心に炭水化物や脂質を適量 |
| 運動習慣 | 1日30分程度の有酸素運動を週3回以上 |
| 睡眠との連動 | 食事や運動時間を調整して睡眠の質を下げない |
睡眠姿勢や睡眠環境の工夫
仰向けに寝ると舌や軟口蓋が気道を塞ぎやすいため横向きで寝る姿勢を意識することも無呼吸対策の1つです。
また、枕の高さや寝具の硬さも重要で、首を適度にサポートして呼吸がしやすい環境を作ることが大切です。
寝室の温度や湿度にも注意して鼻や喉が乾燥しないように心がけると、いびきの軽減にもつながります。
寝具の選び方や睡眠環境を見直す際のリスト
- 横向き寝をサポートする抱き枕を活用する
- 首のカーブに合う枕を選ぶ
- 部屋を適温(約20度前後)に保つ
- 加湿器で適度な湿度を保ち、鼻・喉の乾燥を防ぐ
口腔ケアと定期的な検診
口腔ケアや歯科検診は虫歯や歯周病を防ぐだけでなく、マウスピースを検討する際の基盤にもなります。
口の中を清潔に保つことで口呼吸が減り、無呼吸の原因となる喉の乾燥や炎症を防ぎやすくなります。
歯科での定期的な検診やクリーニングも睡眠時無呼吸症候群の早期発見につながる可能性があります。
口腔ケアで気を付けたいポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 歯磨き | 食後に正しいブラッシングを行う |
| フロス・歯間ブラシ | 歯垢をしっかり除去して歯周病予防に努める |
| 舌苔のケア | 舌ブラシなどで舌苔を取り除き口臭を予防する |
| 定期検診 | 半年に1回程度の歯科健診で口腔内を確認する |
以上
睡眠時無呼吸症候群を知ろう
参考にした論文
AKASHIBA, Tsuneto, et al. Sleep apnea syndrome (SAS) clinical practice guidelines 2020. Respiratory Investigation, 2022, 60.1: 3-32.
TEODORESCU, Mihaela, et al. Predictors of habitual snoring and obstructive sleep apnea risk in patients with asthma. Chest, 2009, 135.5: 1125-1132.
MOJON, Daniel S., et al. Association between sleep apnea syndrome and nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy. Archives of ophthalmology, 2002, 120.5: 601-605.
YEBOAH, Joseph, et al. Association between sleep apnea, snoring, incident cardiovascular events and all-cause mortality in an adult population: MESA. Atherosclerosis, 2011, 219.2: 963-968.
LAVIE, Peretz, et al. Mortality in sleep apnea patients: a multivariate analysis of risk factors. Sleep, 1995, 18.3: 149-157.
SANDERS, A. E., et al. Sleep apnea symptoms and risk of temporomandibular disorder: OPPERA cohort. Journal of dental research, 2013, 92.7_suppl: S70-S77.
NETZER, Nikolaus C., et al. Prevalence of symptoms and risk of sleep apnea in primary care. Chest, 2003, 124.4: 1406-1414.
TEODORESCU, Mihaela, et al. Association between asthma and risk of developing obstructive sleep apnea. Jama, 2015, 313.2: 156-164.
JURKOVICOVA, Ingrid; CELEC, Peter. Sleep apnea syndrome and its complications. Acta Medica Austriaca, 2004, 31.2: 45-50.
TAJ, Fawad, et al. Identifying people at high risk for developing sleep apnea syndrome (SAS): a cross-sectional study in a Pakistani population. BMC neurology, 2008, 8: 1-9.