日常生活の中で長引く咳や息苦しさを感じたとき、気管支炎を疑う方が多いようです。
気管支炎には急性と慢性があり、一度発症するとすぐに治る場合もあれば、長引いて何度もくり返す場合もあります。
適切な治療を行い生活習慣を整えると回復をめざせますが、症状を放置すると重症化する可能性があります。
この記事では気管支炎の基本的な理解や治療方法、どのような生活面に気をつけるとよいかについて幅広く解説します。
気管支炎が治るまでや気管支炎が完治するまでの期間の目安も取り上げるため、ご自身や家族の不安を解消する参考にしてください。
気管支炎とは何か?
ここでは気管支炎の概要について説明します。気管支炎という言葉は耳にするものの、どのような状態を指すのかを正確に把握していない方も多いです。
まずは気管支炎の概念を理解し、症状や種類を把握すると治療へスムーズに取り組みやすくなります。
気管支炎の定義と特徴
気管支炎は肺へ空気を運ぶ気管支に炎症が起こった状態です。
ウイルスや細菌などの感染が主な原因ですが、喫煙や大気汚染などの刺激によっても炎症が起こる場合があります。
気管支炎を発症すると、以下のような症状がみられます。
- 咳(痰を伴うことが多い)
- 息苦しさ
- 胸部の違和感
- 発熱や倦怠感
気管支が炎症を起こすと気道が狭くなって痰がたまりやすくなり、呼吸がしづらくなることがあります。
急性の場合は数週間程度で治まることが多いですが、慢性の場合は数か月以上続いて呼吸機能が低下することもあるため注意が必要です。
気管支炎が疑われる主な症状と特徴
| 症状 | 主な特徴 |
|---|---|
| 咳 | 短期的に激しく続く場合や、乾いた咳から湿った咳に変わる場合が多い |
| 痰 | 粘度が高く、白色や黄緑色などの色を帯びることがある |
| 息苦しさ | 呼吸回数が増えたり、階段昇降や軽い運動で息が上がったりしやすくなる |
| 胸部の痛み | 咳や深呼吸をした際に胸や背中が痛むことがある |
| 発熱 | 軽度から中等度の発熱が起こることがある |
| 全身倦怠感 | 食欲不振やだるさ、集中力の低下を感じることがある |
急性と慢性の違い
気管支炎には大きく分けて急性気管支炎と慢性気管支炎の2種類があります。
急性の場合は呼吸器系のウイルスや細菌感染によって発症し、数日から数週間で回復することが多いです。
慢性の場合は喫煙や大気汚染、職場環境などの刺激が長期的に気管支に影響を与え、慢性的な炎症が続きます。慢性気管支炎では長期間にわたる咳や痰、息切れに悩まされやすく、生活の質が下がる恐れがあります。
気管支炎が広がる仕組み
主な原因であるウイルスや細菌は飛沫感染や接触感染を通じて体内に侵入します。風邪のように上気道から気管支へと拡大し、粘膜を刺激して炎症を引き起こします。
一方、喫煙や有害物質は気管支の粘膜を直接刺激し、炎症のきっかけになることがあります。
こうした刺激を継続的に受けると急性気管支炎をくり返したり、慢性化に移行したりするリスクが高まります。

気管支炎の主な原因
気管支炎を発症する引き金は1つではありません。ウイルスや細菌などの感染経路だけでなく、日常生活の習慣や環境要因が影響を与える場合があります。
ここでは主な原因を深掘りし、感染経路やリスク因子を詳しく見ていきます。
ウイルス感染による発症
急性気管支炎の原因で最も多いのはウイルス感染です。風邪のウイルスと同じように、インフルエンザウイルスやRSウイルスなどが気管支に入り込み、炎症を起こします。
特に冬場から春先にかけて流行しやすく、人混みや密閉空間で長時間過ごすと感染リスクが高まります。
ウイルス感染のリスクを下げると考えられる行動
- 手洗いを徹底して行う
- 体調管理に注意を払う
- 外出時にマスクを活用する
- 公共交通機関やイベント会場など混雑する場所での滞在時間を短くする
ウイルス感染による気管支炎は急激に症状が出現して数日から数週間で回復するパターンが多いです。
発熱や強い咳がみられるため、早期に医療機関で診察を受けたほうがよいでしょう。
細菌感染と合併症
気管支炎の一部は細菌感染も関係します。元々はウイルス感染による急性気管支炎であっても二次感染として細菌が気管支に入り、症状が悪化することがあります。
抗生物質が必要になる場合があるため、医師の判断のもとで適切に治療を進めると回復をめざしやすくなります。
細菌感染が疑われる主なサインと目安
| サイン | 判断の目安 |
|---|---|
| 痰の色が黄緑色や茶色に近い | ウイルス感染よりも強い炎症が起こり、細菌増殖が進行している可能性がある |
| 発熱が長引く | 1週間程度経過しても熱が下がらない場合は細菌感染の恐れがある |
| 呼吸が苦しくなる | 抗生物質の投与を検討する場面が多く、肺炎への進行を防ぐために医療機関へ行くことが望ましい |
| 全身の倦怠感が増す | 二次感染による炎症拡大の恐れがあるため、安静と医師の診断が重要となる |
喫煙や環境因子
喫煙は気管支炎の発症リスクを高める代表的な要因です。たばこの煙には多数の有害物質が含まれており、気管支の粘膜を傷つけます。
同居者が喫煙している場合の受動喫煙や、大気汚染の激しい地域、塵や化学物質を扱う工場などでの就業もリスクを押し上げます。
慢性気管支炎になる要因として喫煙や職業性粉塵の吸入が大きく作用します。
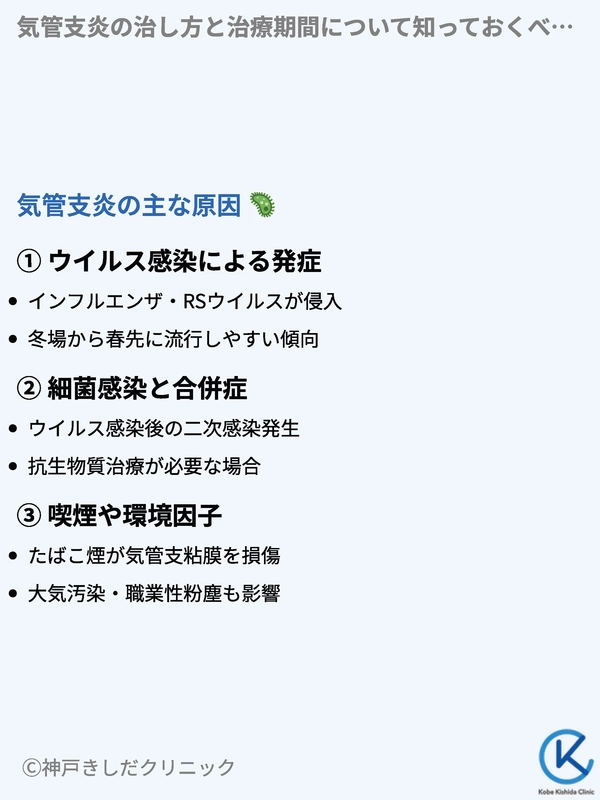
気管支炎の治し方の基本
気管支炎の症状を軽減し、できるだけ早く治すためには、いくつかの重要な取り組みがあります。
ここでは気管支炎の治し方の基本として、休養や水分補給、医薬品の役割などをまとめます。生活習慣を見直しながら医療の力を上手に利用すると、気管支炎が治るまでの期間を短縮できる可能性があります。
適切な休養と睡眠
身体がウイルスや細菌と闘うためには十分な休養と睡眠が役立ちます。
高熱がある場合や咳が続く場合は体力を消耗しやすいため、できるだけ安静に過ごし、睡眠時間を長めに確保すると回復をめざしやすくなります。
無理をして外出や仕事を続けると、免疫力が低下して気管支炎が長引く恐れがあるので注意が必要です。
疲労を軽減して回復を促す工夫
- 背中や胸に余計な負担をかけない姿勢で横になる
- 部屋の湿度を50~60%程度に保つ
- 咳が強いときは上半身を少し高くして寝る
- 就寝前のスマートフォン使用を控える
水分補給と食事管理
気管支炎になると咳や鼻水、発熱などで体内の水分が失われやすくなるため、こまめな水分補給が大切です。
特に発熱がある場合には発汗量が増えるので水分や電解質を補充するように心がけるとよいでしょう。
食事はたんぱく質やビタミン類を含んだバランスのとれた内容が望ましく、消化器系に負担をかけすぎないように調理方法や量を工夫すると回復をサポートできます。
気管支炎の回復を支える主な栄養素と推奨食材
| 栄養素 | 推奨食材 | 注意点 |
|---|---|---|
| たんぱく質 | 鶏肉、魚、豆類、卵 | 過度な油の使用を避け、消化にやさしい調理方法を選ぶ |
| ビタミンA | にんじん、かぼちゃ、ほうれん草 | βカロテンが多く含まれ、粘膜の保護に役立つ |
| ビタミンC | 柑橘類、キウイフルーツ、ブロッコリー | 加熱に弱いため、生か軽い加熱で摂取すると吸収効率が向上 |
| ミネラル | 海藻類、ナッツ類、乳製品 | カルシウムや亜鉛など多様なミネラルを適度に取り入れ、免疫機能を支える |
| 電解質 | スポーツドリンク、味噌汁、経口補水液 | 塩分や糖分の取りすぎに注意しながら、適度に摂取する |
医薬品の役割
気管支炎の症状を早めに改善したい場合は医療機関で処方される薬や市販薬の活用が大切です。
急性気管支炎の場合は咳止め薬や去痰薬、解熱鎮痛剤などを組み合わせて症状を和らげる方法がよく取られます。
細菌感染が疑われる場合は抗生物質を投与する場合がありますが、医師が必要と判断した場合に限定して使用するほうが安心です。
自己判断で薬を増減すると症状をこじらせるリスクがあるため、必ず医師や薬剤師の指示に従いましょう。

気管支炎が治るまでの期間の目安
気管支炎が治るまでの期間は個人の体調や原因などにより差があります。一般的な傾向として、急性か慢性かで大きく異なるので、目安を理解すると日常生活や仕事の調整がしやすくなります。
ここでは急性と慢性それぞれの治療期間や、なかなか回復しないケースについて確認します。
急性気管支炎の治療期間
急性気管支炎の場合、原因の多くがウイルス感染です。適切な休養や薬物療法を行うと、約1~3週間程度で症状が軽くなることが多いです。
咳は炎症が収まっても残る場合があり、完治まで2~4週間かかることがあります。
ただし、高熱が数日続く場合や痰の色が濃い場合には細菌感染が併発している可能性があるため、医療機関への受診が必要です。
回復への流れで意識しておきたい点
- 早めに医師の診断を受けて、適切な薬を用いる
- 熱が下がるまでは無理をせず安静を保つ
- 咳が落ち着いても急に動きすぎないようにする
- 十分な水分と栄養を確保する
慢性気管支炎の治療期間
慢性気管支炎は数か月以上にわたって咳や痰などの症状が続く状態を指します。
原因として喫煙や大気汚染などの継続的な刺激が関係し、元の生活習慣や環境を変えない限り症状が長引く傾向があります。
禁煙や作業環境の改善、適度な運動、薬物療法などの総合的な対策を行っても、数か月から半年以上かかることがあります。
慢性気管支炎の長期治療で意識したい要素
| 要素 | 具体策 | コメント |
|---|---|---|
| 禁煙・喫煙環境 | 完全にたばこを断つ 受動喫煙の機会を極力なくす | 喫煙習慣を断ち切らなければ、慢性的な炎症が抑えにくい |
| 作業環境の改善 | 粉塵や化学物質が多い現場の場合、対策用品を使用 換気を徹底 | 発症リスクを下げるため、周囲の環境づくりが大切 |
| 運動と呼吸法 | ウォーキングや軽いジョギング 腹式呼吸などの呼吸トレーニング | 過度な運動は控え、無理のない範囲で継続して呼吸機能を保つ |
| 薬物療法 | 気管支拡張薬・去痰薬など 適時医師と相談しながら投薬内容を調整 | 症状に合わせて薬を正しく利用し、悪化を防ぐ |
| 定期検診・通院 | 定期的に肺機能検査やレントゲン検査を受ける 医師からのアドバイスをこまめに確認 | 症状変化に早く気付き、治療方針を柔軟に変更できる |
治療期間が長引く場合
気管支炎が長引く場合には下記のような要因が考えられます。
- 原因が複数重なっている(ウイルス+細菌など)
- 生活習慣や環境が改善されていない(喫煙、粉塵、高ストレスなど)
- 免疫力が低下している(栄養不足、疲労など)
- 別の疾患が隠れている(気管支喘息やCOPDなど)
こうした要因を特定して対応しないと治療期間がさらに延びる恐れがあります。
早めに受診して検査やカウンセリングを受けると、症状の原因を明確にしやすくなります。
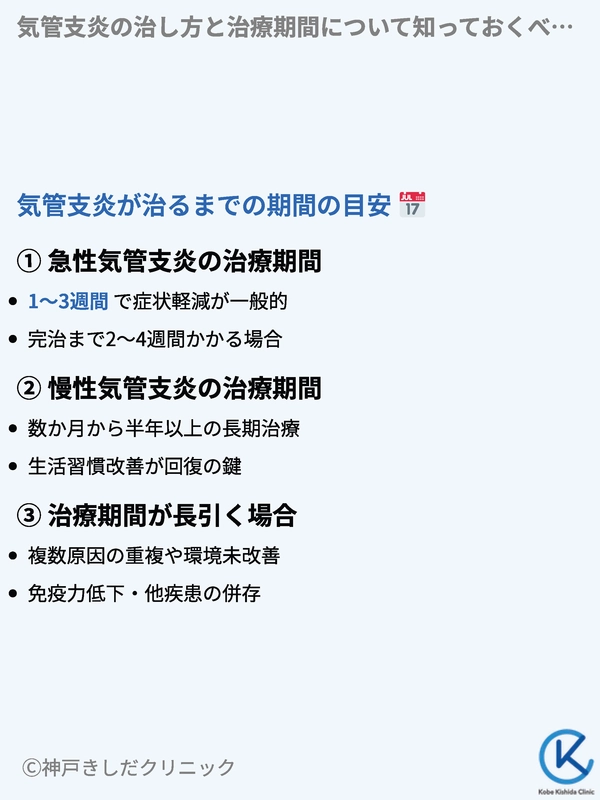
気管支炎が完治するまでに意識したい生活習慣
気管支炎をしっかり完治させるためには医療機関での治療だけではなく生活習慣の見直しが重要です。
ここでは禁煙や適度な運動、定期的な通院について詳しく解説します。気管支炎が完治するまでの間に心がける習慣を取り入れると、予後が良好になる可能性が高まります。
禁煙・受動喫煙を避ける
喫煙は気管支へ強い負担をかけて慢性気管支炎や肺疾患のリスクを高めます。たばこの煙が気道を直接刺激して炎症を深刻化させるからです。
また、家族や周囲の人が吸うたばこによる受動喫煙も大きな影響を及ぼします。
気管支炎が治るまでという限定ではなく、長期的にみても禁煙は重要な取り組みです。
禁煙が身体にもたらすポジティブな変化
- 咳や痰の軽減
- 呼吸機能の向上
- 味覚や嗅覚の改善
- 肺がんやCOPDなどのリスク低下
適度な運動と呼吸法
気管支炎を経験した後でも適度な運動は身体機能を維持し、回復を助ける上で大切です。ウォーキングや軽いストレッチなどは呼吸筋の強化にもつながる可能性があります。
また、腹式呼吸や口すぼめ呼吸などの呼吸法を取り入れると痰を排出しやすくし、息苦しさを軽減できる場合があります。
ただし、急性の症状が強い間は無理せず、医師と相談しながら段階的に運動を始めると安全です。
適度な運動習慣を継続するためのコツ
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 腹式呼吸 | 息を吸うときは腹部をふくらませ、吐くときはへこませる | いきなり強く吸い込むと咳き込みやすい |
| 口すぼめ呼吸 | 息を吐くときに口をすぼめる | 呼気時間を少し長めにすることで肺の換気を促す |
| ウォーキング | 会話ができる程度の負荷で行い、無理にペースを上げない | 急激に速度を上げない、天候や気温に注意 |
| ストレッチ | 肩や背中周りの筋肉をやわらかくする | 痛みや息苦しさがあるときは休憩をこまめに取り入れる |
定期的な通院と検査
気管支炎が慢性化したり再発をくり返したりする場合には定期的に医師の診察を受けて肺機能検査や画像検査を行うことが大切です。
定期的な受診を行うと炎症の進行具合を把握し、必要に応じた治療やアドバイスを得やすくなります。
症状が軽くなったからといって自己判断で通院をやめると再発のリスクが高まります。

病院で行う診断と治療方法
気管支炎が疑われる場合、医師の診察や検査を受けると正確な診断がつきやすくなります。自己判断で対処しようとしても、実は別の病気が隠れているケースもあり得ます。
ここでは病院で行う代表的な診断と治療方法を紹介します。
診察や検査内容
医療機関ではまず問診と聴診を行い、咳の音や呼吸の状態を確認します。
必要に応じてレントゲン検査や血液検査、痰の検査などを実施して肺炎や他の呼吸器疾患との鑑別を行います。
慢性気管支炎が疑われる場合には肺機能検査で呼吸機能を評価することもあります。
診断のためによく使う検査と特徴
| 検査名 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| レントゲン | 胸部のX線撮影を行い、肺や気管支の状態を画像で確認 | 肺炎や肺腫瘍など、他の疾患の有無をチェック |
| 血液検査 | 炎症反応(CRP)や白血球数などを測定 | 細菌感染や全身状態の確認 |
| 痰の検査 | 痰を採取し、細菌やウイルスの種類を調べる | 抗生物質の種類を選ぶ際の参考にする |
| 肺機能検査 | 呼吸の量やスピードを測定する | 慢性気管支炎やCOPDなどの機能低下を評価 |
薬物療法
急性気管支炎の場合は咳止め薬や去痰薬、必要に応じて解熱鎮痛薬を用いて症状をコントロールします。
細菌感染が疑われる場合は抗生物質を処方することで症状の進行を抑えることが可能です。
慢性気管支炎の場合は気管支拡張薬や長期間作用型の吸入ステロイド、去痰薬などを組み合わせて炎症を抑え、呼吸を楽にする方法をとることが多いです。
薬の使い方で押さえておきたい事柄
- 処方された薬を指示通りに飲む(自分で増減しない)
- 症状が改善しても、医師の指示なしに中断しない
- 副作用が疑われる場合は、すぐに医療機関へ相談する
- 吸入薬は使い方の指導を受け、正確な手順で使用する
吸入療法や呼吸リハビリ
慢性気管支炎やCOPDなどの併存症がある場合、吸入療法や呼吸リハビリテーションが有効です。
吸入療法では気管支を拡げる薬剤やステロイドを直接気道に届け、炎症や気道の狭窄を和らげます。
呼吸リハビリでは専門の指導のもと、腹式呼吸や運動療法を組み合わせて呼吸機能を高めるためのプログラムを行います。
吸入療法と呼吸リハビリを行うメリット
| 方法 | 目的 | メリット |
|---|---|---|
| 吸入療法 | 気管支拡張薬や吸入ステロイドをダイレクトに気道へ届ける | 薬剤の効果が局所に集中し、全身副作用のリスクを下げやすい |
| 呼吸リハビリ | 呼吸筋を強化し、肺活量を保ち、痰の排出を促進する | 日常生活での息切れを軽減し、運動能力の向上を期待できる |
| 吸入器の使用指導 | 機器の使い方を正しく学び、吸入効果を最大限に引き出す | 適切な吸入方法で薬剤の効果が増し、治療効率が上がる |
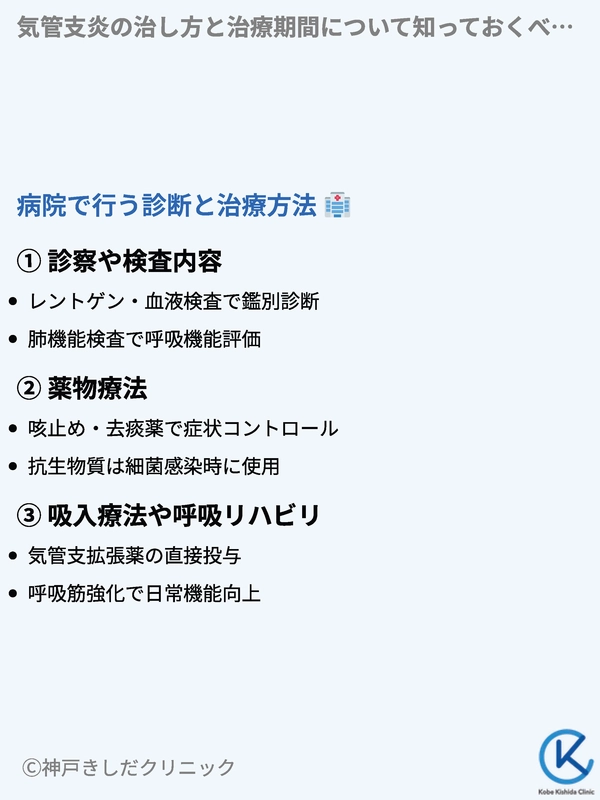
気管支炎と併発する恐れがある症状
気管支炎が長引くと、ほかの呼吸器疾患を併発する可能性があります。
早めに対策しないと重症化し、呼吸機能の低下や長期的な体力消耗を招く恐れがあるため、併発リスクを理解することが大切です。
肺炎
気管支炎が進行して肺実質まで炎症が及ぶと肺炎へ移行する場合があります。肺炎になると高熱や強い倦怠感、呼吸困難を起こしやすく、入院が必要になるケースも少なくありません。
特に高齢者や基礎疾患を抱えている人は肺炎のリスクが上がるため、気管支炎の段階でしっかり治療を行うことが望ましいです。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
長期喫煙などで気管支や肺がダメージを受け続けると、慢性閉塞性肺疾患(COPD)に移行するリスクがあります。COPDは息苦しさや慢性の咳と痰が特徴で、特に朝方に強い咳や大量の痰が出るケースが多いです。
一度COPDを発症すると完全に元に戻すことは難しく、適切な管理を続けながら症状の進行を抑えていく必要があります。
COPDを疑うポイント
- 朝起きたときの咳と痰が長期的に続く
- 階段や坂道で極端に息切れが起こる
- たばこを10年以上吸っていた、または受動喫煙の環境が長かった
- 胸部の圧迫感や呼吸苦を感じることが増えた
気管支喘息
気管支炎と気管支喘息が合併すると、咳や呼吸困難がさらに強くなる場合があります。
気管支喘息は気道の過敏性が高まり、アレルゲンなどの刺激で発作的な咳や呼吸苦が出現する状態です。
アレルギー要因の除去や吸入ステロイドの使用など喘息の管理を同時に行わないと症状が安定しにくくなります。

呼吸器内科の受診を検討したい人の特徴と来院の目安
気管支炎を疑った場合や症状が治まりにくい場合には早めに呼吸器内科の受診を検討するのが望ましいです。
呼吸器内科では気管支炎だけでなく肺炎やCOPD、気管支喘息など呼吸器にまつわるさまざまな疾患を総合的に診察してもらえます。
ここでは受診を検討すべき特徴や症状の具体例を示します。
長引く咳
咳が2~3週間以上続く場合は通常の風邪ではなく、気管支炎や他の呼吸器疾患を疑ったほうがよいです。
気管支炎が治るまでにはある程度の期間がかかることが多いですが、あまりにも長引く場合は慢性化や別の病気を併発している可能性があります。
長引く咳に痰や発熱、全身倦怠感などが加わるようであれば早めに呼吸器内科を受診して原因を特定し、適切な治療を行うことが大切です。
咳が続いているときにチェックしたい内容
| チェック項目 | 具体的な確認 |
|---|---|
| 発熱の有無 | 数日以上熱が続いていないか、最高体温がどのくらいか |
| 痰の色や量 | 痰が黄緑色や濃い茶色に変化していないか、量は増えていないか |
| 息苦しさの程度 | 日常生活に支障をきたすほど呼吸がつらいか、運動時に苦しさが増していないか |
| 体のだるさや疲労感 | 睡眠や休息をとっても改善しない慢性的な疲労があるか |
息苦しさと呼吸苦
階段を上がるとすぐに息切れしてしまったり、少し歩いただけで呼吸が苦しくなったりする場合は、気管支や肺に何らかの問題が潜んでいるかもしれません。
運動不足や加齢だけの問題と考えず、呼吸器内科で検査することで病気の早期発見につながる可能性があります。
慢性的な息苦しさがある場合は酸素飽和度などを測定し、肺機能検査を受けると正確な状態を把握できます。
血痰や高熱
咳に血が混じる血痰や38℃以上の高熱が続く場合は、気管支炎から肺炎へ移行したり他の重篤な疾患が隠れている可能性があります。
血痰は気管支や肺に損傷があることを示すことが多く、一度きりでも確認したら早めの受診が望ましいです。
受診を急いだほうがよいと考えられる症状
- 38℃以上の高熱が2日以上継続する
- 痰に血液が混じっている
- 呼吸苦で夜間に眠れない
- 胸の痛みが激しく、安静にしても改善しにくい
このような症状を訴える場合は気管支炎以外の病気の可能性を念頭に置いて医師が診察し、必要に応じて専門的な検査や治療を提案します。
以上

参考にした論文
KOBE, Hiroshi, et al. Short-acting β2 Agonist Inhalation Therapy for Asthma or Chronic Obstructive Pulmonary Disease with a High-flow Nasal Cannula in Japan-An Online Questionnaire Survey by the Japanese Respiratory Society, Japanese Society of Intensive Care Medicine, and Japanese Society of Respiratory Care Medicine. Internal Medicine, 2025, 4863-24.
MINAGAWA, Shunsuke, et al. Real-life effectiveness of dupilumab in patients with mild to moderate bronchial asthma comorbid with CRSwNP. BMC pulmonary medicine, 2022, 22.1: 258.
TOYOSAKI, Masako, et al. Temporal changes in corticosteroid dose during ibrutinib treatment in patients with cGVHD and pulmonary involvement. International Journal of Hematology, 2025, 121.3: 388-396.
HOSHINO, et al. Inhaled corticosteroid reduced lamina reticularis of the basement membrane by modulation of insulin‐like growth factor (IGF)‐I expression in bronchial asthma. Clinical & Experimental Allergy, 1998, 28.5: 568-577.
MINESHITA, Masamichi, et al. Bronchoscopic Lung Volume Reduction with One-way Valves: A Review of Clinical Outcomes and Future Directions. Respiratory Endoscopy, 2025, 3.1: 1-11.
KADOWAKI, Toru, et al. An analysis of etiology, causal pathogens, imaging patterns, and treatment of Japanese patients with bronchiectasis. Respiratory investigation, 2015, 53.1: 37-44.
AGARWAL, Ritesh, et al. Revised ISHAM-ABPA working group clinical practice guidelines for diagnosing, classifying and treating allergic bronchopulmonary aspergillosis/mycoses. European Respiratory Journal, 2024, 63.4.
RUBIN, Bruce K.; HENKE, Markus O. Immunomodulatory activity and effectiveness of macrolides in chronic airway disease. Chest, 2004, 125.2: 70S-78S.
TANIGUCHI, Chizu, et al. Pharmacological effects of urinary products obtained after treatment with saiboku-to, a herbal medicine for bronchial asthma, on type IV allergic reaction. Planta medica, 2000, 66.07: 607-611.
KODAMA, Yuzo, et al. Antioxidant nutrients in plasma of Japanese patients with chronic obstructive pulmonary disease, asthma‐COPD overlap syndrome and bronchial asthma. The Clinical Respiratory Journal, 2017, 11.6: 915-924.
VAN SCHAYCK, Constant P., et al. Bronchodilator treatment in moderate asthma or chronic bronchitis: continuous or on demand? A randomised controlled study. British Medical Journal, 1991, 303.6815: 1426-1431.



