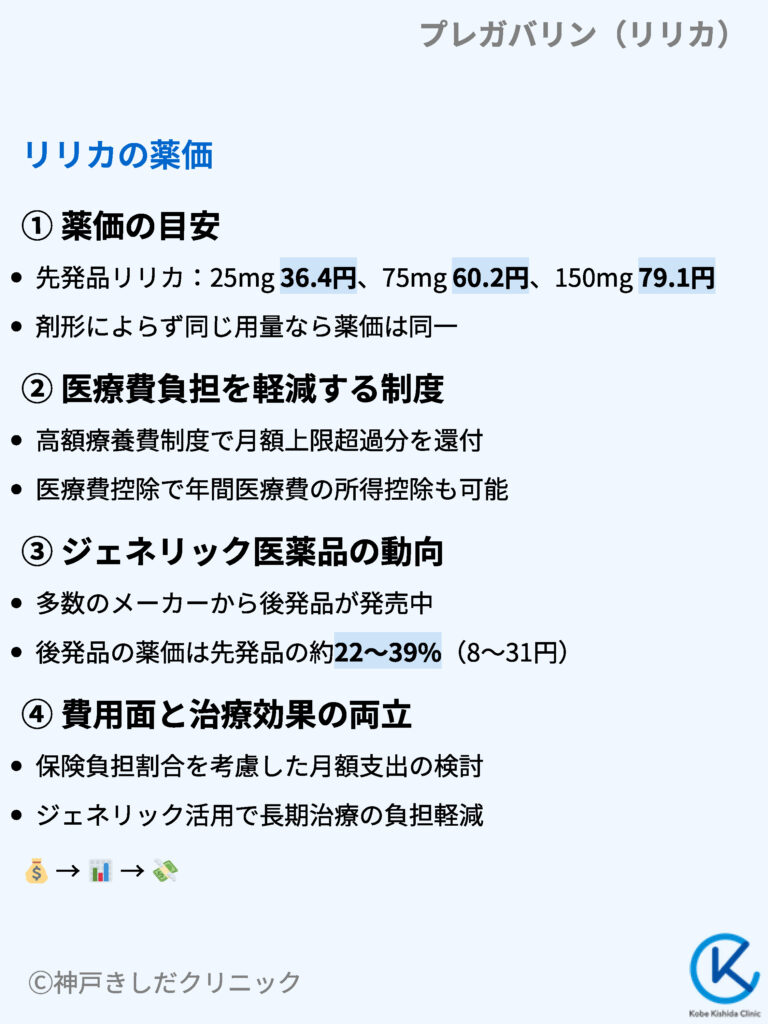プレガバリン(リリカ)は、神経からくる痛みへの治療薬として知られていますが、糖尿病性神経障害や帯状疱疹後神経痛などの痛みの緩和にも幅広く使われます。
神経痛に対する治療に加えて、線維筋痛症にみられる全身の痛みに対しても処方されることが多いです。
実際に服用を検討する段階でどういった作用があるのか、使用方法や注意点は何か、副作用にはどんなものがあるのかなど疑問を抱える方は少なくありません。
ここではプレガバリン(リリカ)の特徴や治療の流れを詳しく紹介していきます。
服用を迷っている方が判断しやすくなる情報提供を心がけています。

プレガバリンの有効成分と効果、作用機序
プレガバリンは一般的に神経由来の痛みに対して大きな効果をもたらす薬として知られています。
痛みの原因となる神経の興奮を抑える機能があり、糖尿病性神経障害や帯状疱疹後神経痛などで生じるしびれや痛みに使われます。
さらに線維筋痛症による慢性痛にも効果を期待できます。
ここでは有効成分であるプレガバリンの特徴とその薬理作用を詳しく見ていきます。
プレガバリンの成分特性
プレガバリンはガバペンチン系に分類される薬です。
元々はてんかんの部分発作治療薬として開発が進められ、現在は神経障害性の痛みにも応用されるようになりました。
神経の過剰興奮を抑えたい場合に処方されることが多いです。
服用すると血中濃度が安定しやすく、比較的早い段階から鎮痛効果を得やすい特徴があります。
主な特徴を簡単にまとめると次のようになります。
- 神経の興奮を抑える作用をもつ
- 神経由来の痛みの抑制に有用
- 筋肉痛やしびれを伴う線維筋痛症にも対応できる
服用を開始してから効果を感じるまでにはある程度の時間が必要です。
ただし、継続的な内服により血中濃度が安定すると痛みの軽減を実感しやすいです。
効果のメカニズム
プレガバリンはカルシウムチャネルのα2δサブユニットと結合します。
神経末端でのカルシウムイオンの流入が減ることで神経伝達物質の放出量が抑えられ、痛みやしびれを感じにくくなります。
特に糖尿病性神経障害、帯状疱疹後神経痛など末梢神経がダメージを受けているケースでの神経性の痛みを和らげるのに向いています。
プレガバリンの主な作用ポイントと作用部位は以下の通りです。
| 作用ポイント | 具体的な作用の流れ |
|---|---|
| カルシウムチャネルとの結合 | 過剰に興奮した神経細胞内へのカルシウムイオン流入を抑制 |
| 神経伝達物質の放出抑制 | グルタミン酸やサブスタンスPなどの放出量を減らし、痛みを制御 |
| 神経興奮の抑制 | 結果として痛みのシグナル伝達を鎮静化 |
効果が期待できる症状
プレガバリンは下記のような症状に対して使用されることが多いです。
- 糖尿病性神経障害
- 帯状疱疹後神経痛
- 線維筋痛症
- 神経由来の慢性痛(坐骨神経痛、腰痛など)
血糖値や体調の管理と合わせてプレガバリンを使うことで痛みと上手につきあう一助となります。
主な利点と特性
プレガバリンは従来の非ステロイド性抗炎症薬やオピオイド鎮痛薬とは機序が異なり、神経自体に働きかけます。
炎症を抑える薬ではなく、過度に活性化された神経活動を調整する役割を果たすため慢性的な神経痛で悩む方には有益です。
なお、すべての神経痛がこの薬だけで十分に管理できるわけではありません。
薬剤変更や併用療法が必要になるケースもあるため、専門医に相談しながら服用することが大切です。
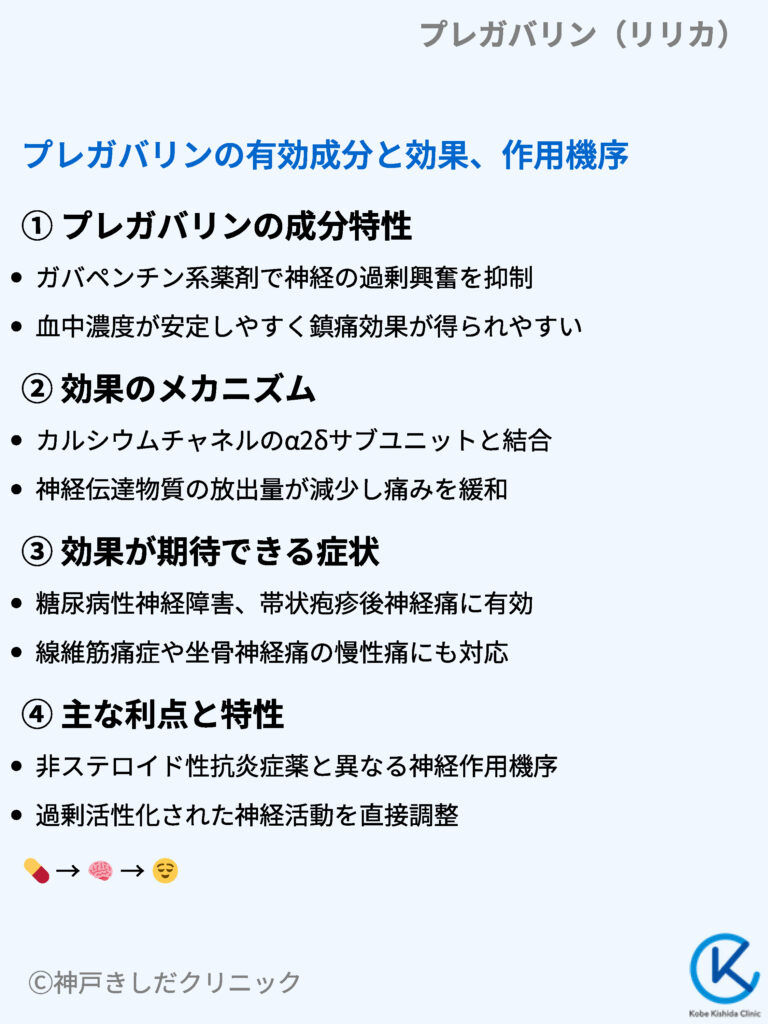
リリカの使用方法と注意点
プレガバリン(リリカ)の効果を十分に得るためには正しい服用方法と注意すべきポイントを理解することが重要です。
用量やタイミングを守らないと効果を適切に得られなかったり、予期せぬ副作用が生じるリスクもあります。
ここでは安全かつ効果的に服用するための情報を示します。
服用の基本的な流れ
医師の指示に従って決められた用量を飲むことが基本で、一般的には食後の服用が推奨されることが多いです。
ただし各患者の状態や治療方針によっては就寝前に飲むなどの指示がある場合もあります。
手元にある薬のラベルや説明書をよく読んで指示通りに飲むようにしてください。
以下は1日2回服用の場合での服用スケジュール例です。
| 服用タイミング | 朝(もしくは昼) | 夜(就寝前) |
|---|---|---|
| 食事との関係 | 食後もしくは医師の指示に従う | 食後または寝る直前 |
| 1回あたりの用量 | 医師の処方量 | 医師の処方量 |
| 水分の摂取 | コップ1杯程度の水 | 同上 |
医師の指示以外で自己判断による減量や増量は控えてください。
効果がすぐに感じられなくても数日から数週間飲み続けることで血中濃度が安定し、症状改善を期待できることがあります。
用量調整時の注意
服用開始時や症状の変化に応じて用量調整を行う場合があります。
特に高齢者や腎機能低下が見られる場合は初期用量を少なめに設定することが多いですが、医師の監督下で調整することが大切です。
- 腎機能検査の結果に応じて用量変更が必要なことがある
- 症状が著明に改善した場合でも自己判断での中断は推奨されない
- 不安な点があれば医療機関に相談する
飲み忘れ時の対処
飲み忘れに気づいたときは、時間が経ちすぎていない限りできるだけ早く服用したほうがよい場合があります。
ただし次の服用タイミングが迫っているときに2回分をまとめて飲むことは危険です。
自己判断ではなく、医師や薬剤師に相談してから対応するほうが安全です。
飲み忘れを防ぐ方法には次のようなことも効果的でしょう。
- スマートフォンのアラームを活用する
- 1週間分を分包された状態にしておく
- 毎日同じタイミングで飲む習慣をつける
アルコールや他薬剤との併用
プレガバリンは中枢神経に作用する薬です。
アルコールを同時に摂取すると、めまいや眠気が強く出る可能性があります。
また、ほかの鎮痛薬や抗不安薬など中枢神経に作用する薬剤との併用には注意が必要です。
主治医に服用中の薬をすべて伝えることで相互作用のリスクを下げられます。
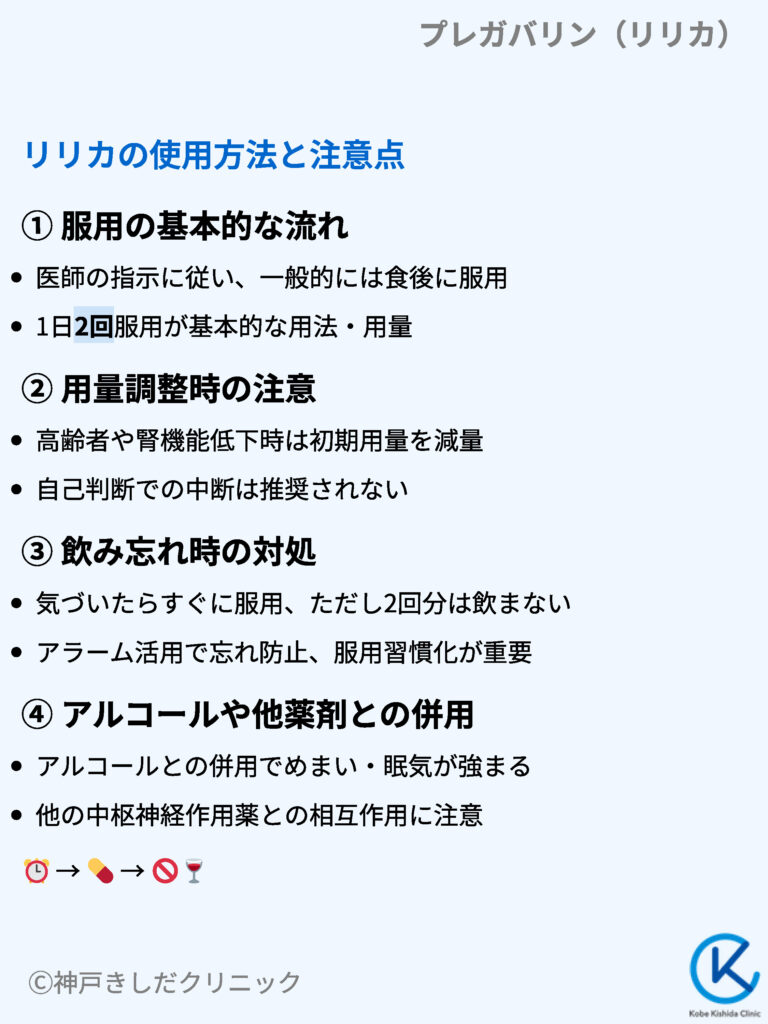
適応対象患者
プレガバリンは神経障害性の痛みを中心に幅広い症状に対して処方されます。
特に糖尿病性神経障害や帯状疱疹後神経痛などの慢性痛で困っている方や線維筋痛症での全身性の痛みに悩む方にとっては有効な選択肢となることが多いです。
ここではどんな患者がプレガバリンの処方対象になりやすいかを解説します。
糖尿病性神経障害をもつ方
糖尿病の合併症として神経障害が起こると手足のしびれや焼けるような痛みが慢性的に続きます。
血糖コントロールに加えて神経痛を抑える薬であるプレガバリンを使用することで日常生活の苦痛を和らげるケースが多いです。
神経性の痛みは生活の質に大きく影響するため状態に応じた早期の治療が大切です。
糖尿病性神経障害の主な症状とプレガバリンの役割は次のようになります。
| 主な症状 | プレガバリンの効果 |
|---|---|
| 四肢のしびれ | 神経伝達の過剰を抑え、しびれ感やピリピリ感を緩和 |
| チクチクする痛み | 神経からの痛み信号を抑制し、疼痛をコントロール |
| 夜間の不快感 | 特に就寝前に服用すると、睡眠の質向上に寄与 |
帯状疱疹後神経痛がある方
帯状疱疹を発症した後に神経痛が残る場合は皮膚症状が治まっていても強い痛みが続きます。
従来の鎮痛薬だけでは十分に改善しにくく、プレガバリンのような神経障害性疼痛に対応した薬が重宝されます。
部位によっては日常動作が困難になるほどの痛みになることもあり、早めの対策が求められます。
線維筋痛症による慢性痛を訴える方
全身に及ぶ持続的な痛みや日々の疲労感、こわばりなどで日常生活に支障をきたすことが多い線維筋痛症にもプレガバリンが使われます。
痛みに対する感受性が高く、通常の鎮痛薬では十分に緩和しないケースが少なくありません。
プレガバリンの投与で痛みをコントロールすることで生活の質を向上させる可能性があります。
その他の神経性疼痛をもつ方
坐骨神経痛や頸椎症性神経根症など慢性的な神経痛全般に対してプレガバリンの処方を検討する場面があります。
骨格や関節が原因の疼痛に対して炎症を抑える薬では十分に改善できない場合に選択されることがあります。
症状の原因が神経に関連している場合には薬理学的にプレガバリンの作用が期待できます。
箇条書きで適応対象患者が多い理由をまとめると次のようになります。
- 神経性疼痛の抑制に特化した作用がある
- 血中濃度の安定後に鎮痛効果を期待しやすい
- 他の鎮痛薬で改善しにくい痛みにアプローチできる
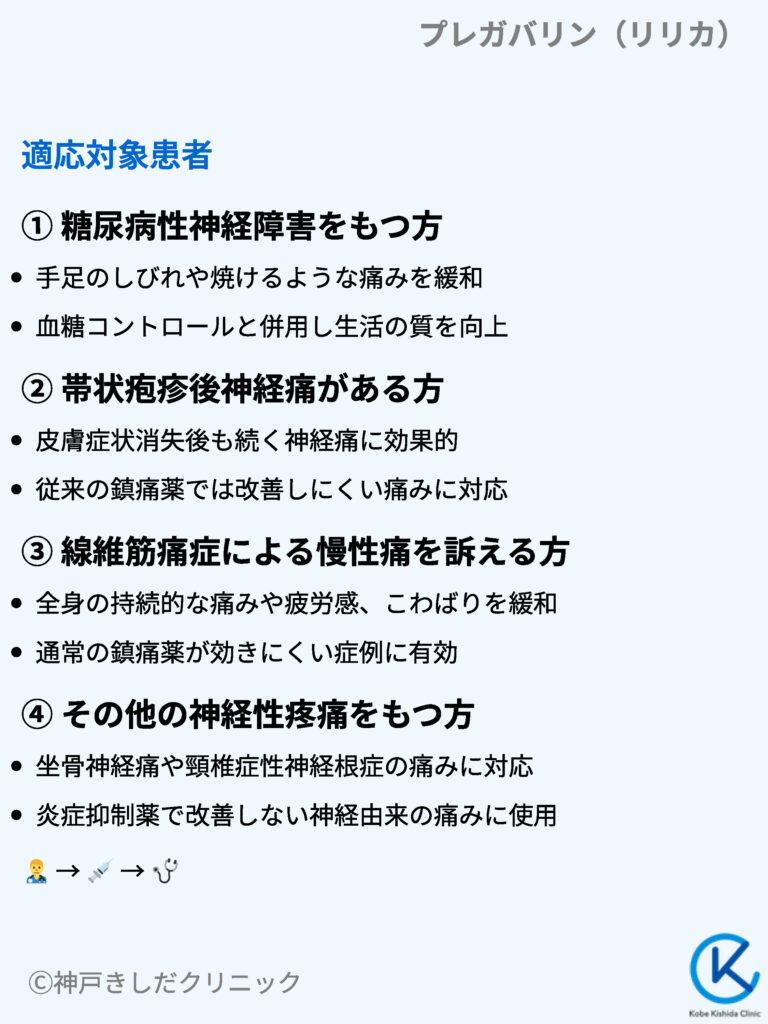
リリカの治療期間
プレガバリンによる治療期間は一律で決まっているわけではありません。痛みの原因や程度、患者個々の状況によって期間が左右されます。
しびれや痛みが治まっても再発予防や症状のぶり返しを防ぐために、ある程度の期間継続することを提案される場合があります。
ここではどのような目安で治療期間を考えるのかを解説します。
治療期間の目安
糖尿病性神経障害の場合、血糖コントロールが大幅に改善しても神経痛が長引くことがあります。
帯状疱疹後神経痛については痛みの感覚が安定するまでに数カ月から半年以上の期間が必要となることが少なくありません。
線維筋痛症の場合は症状が波状的に悪化・寛解を繰り返すケースがあるため、さらに長期的な視点で治療を継続することがあります。
主な神経障害の治療期間の目安は次の通りです。
| 神経障害の種類 | 治療期間の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 糖尿病性神経障害 | 数カ月〜1年程度 | 血糖コントロールを合わせて行う |
| 帯状疱疹後神経痛 | 半年〜1年程度 | 早期治療が重要 |
| 線維筋痛症 | 半年〜数年にわたる場合もある | 痛みの波があるため状況に合わせて調整 |
痛みの評価と調整
医師は治療の過程で痛みの評価を行い適宜用量や服用回数を調整します。
痛みの評価には痛みの強さを0〜10の数字で表すスケールを用いることが多いです。
症状が改善して数値が低下しても急に薬を中止すると痛みが再び強くなるリスクがあるため、医師の判断のもと徐々に減量を行うことが望ましいです。
継続治療のメリット
プレガバリンを適切な期間継続すると、神経痛による睡眠障害や日常活動への支障が減る可能性があります。特に慢性痛は心身のストレスを増やす要因でもあり、うつ状態や意欲低下につながることもあります。痛みをコントロールできるようになることで、生活の質が高まりやすくなります。
治療終了のタイミング
治療の終了に際しては再発リスクの有無や痛みの残存状況を総合的に判断します。
症状が安定していることを確認しながら医師と相談して減量→休薬へ移行します。
痛みが完璧に消失するケースもあれば、ある程度の軽減状態で日常生活に支障が少ないレベルまでコントロールすることを目指す場合もあります。
いずれの場合も計画的な観察が必要です。
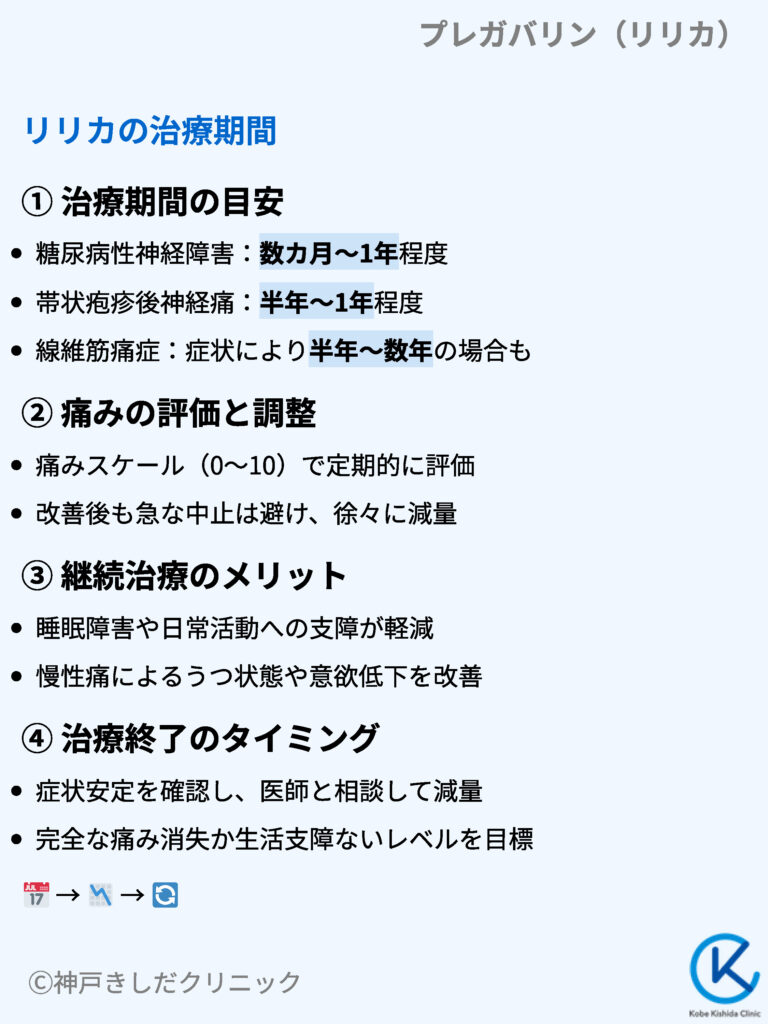
プレガバリンの副作用・デメリット
プレガバリンは神経障害性疼痛に有用な一方で副作用がまったくないわけではありません。
症状の程度や表れ方は個人差が大きいですが、めまいや眠気、体重増加などの症状が報告されています。
副作用の特徴を理解して注意しながら使用することでリスクを軽減できる可能性があります。
よく見られる副作用
プレガバリンで比較的よく見られる副作用としては次のようなものがあります。
- めまい
- 眠気
- 体重増加
- 口渇
これらは中枢神経に作用する性質からくるもので、初期のうちは程度が強く出る場合があります。
ただし血中濃度が安定してくると徐々に軽減することもあるため、医師と相談しながら観察することが大切です。
副作用を感じた時の対処法の例を挙げます。
- 眠気やめまいが強い場合は車の運転を控える
- 水分補給をこまめに行い口の渇きを防ぐ
- 体重が増加したと感じたら食事や運動を見直す
- 気になる症状が続けば医師に相談する
めまい・眠気の対策
プレガバリンは脳や脊髄など中枢神経に作用するため、めまいや眠気を起こしやすい特徴があります。運転や高所作業などに従事する方は、特に注意が必要です。服用開始後しばらくは症状が出やすいので、日常生活の中で安全に配慮してください。例えば、通勤を公共交通機関に切り替えたり、家族に送迎を頼んだりする工夫が考えられます。
体重増加と生活習慣の見直し
プレガバリンを服用すると食欲が増す傾向があり、結果として体重増加を感じる方も一定数います。
過剰なカロリー摂取を控えてバランスの良い食事を心がけるとともに、適度な運動を取り入れることが望ましいです。
ただし痛みが強い段階で無理に運動するのは逆効果になることもあるため、医師や理学療法士などと相談して無理のない範囲で取り組むことが大切です。
以下は体重増加を防ぐためのポイントになります。
| 生活習慣 | 具体策 |
|---|---|
| 食事 | 野菜中心の献立、過剰な甘味料や脂質を控える |
| 運動 | 痛みが強くない日は軽いウォーキングから始める |
| ストレス対処 | 睡眠を確保し、気分転換の時間をつくる |
長期使用によるリスク
プレガバリンは依存性が極めて高いわけではありませんが、中枢神経に働きかける薬である以上は一定の注意が必要です。
長期使用で用量が増えていくと休薬時にしびれや不安感が出ると報告されることがあります。
医師と相談しながら適正量を守って徐々に用量を調整しながら使用すればリスクを抑えることができます。
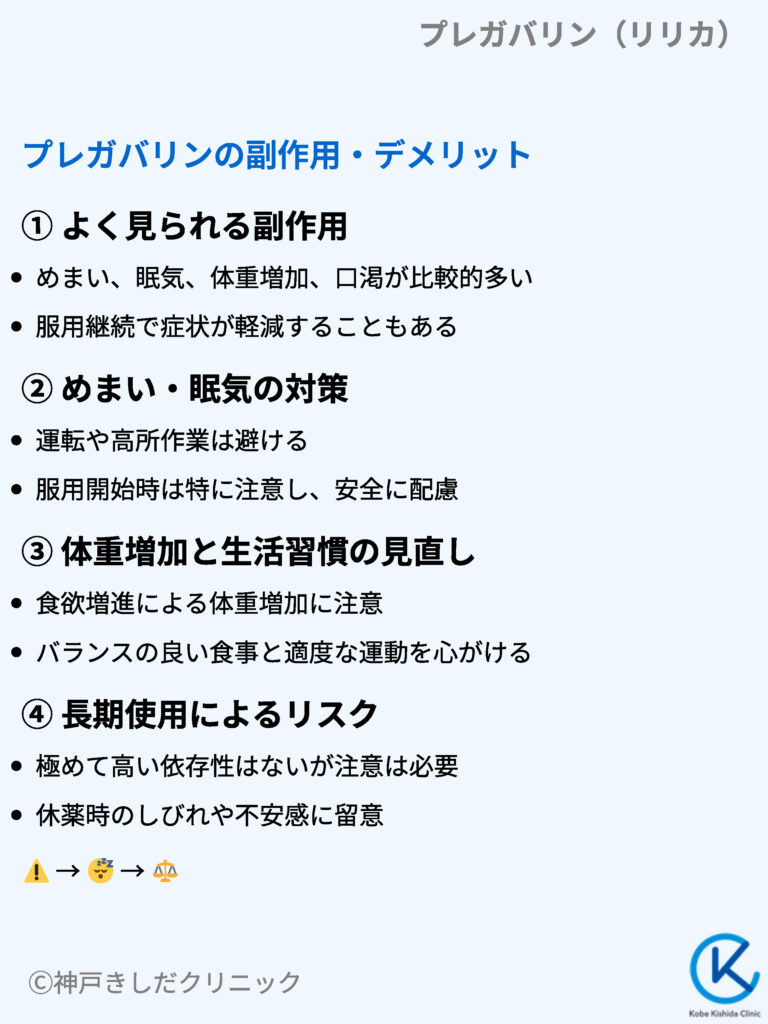
プレガバリンの代替治療薬
プレガバリンと同じように神経痛を抑える効果がある薬は他にも存在します。
慢性痛の原因や患者の症状に合わせて複数の薬や治療法から選択することが一般的です。
ここではプレガバリンの代替となる主な薬剤や合わせて検討される治療法について説明します。
他のガバペンチン系薬剤
プレガバリンと同じガバペンチン系に分類される薬としてガバペンチンがあります。
こちらも神経障害性疼痛に用いられ、効果や副作用の特徴が類似しています。
用量の範囲や服用回数などに若干の違いがあるため、患者さんの状態によって医師が使い分ける場合があります。
プレガバリンとガバペンチンを比較すると次の通りです。
| 項目 | プレガバリン | ガバペンチン |
|---|---|---|
| 服用回数 | 1日2回 | 1日3回 |
| 吸収速度 | 比較的速い | やや緩やか |
| 主な適応 | 神経障害性疼痛全般 | てんかん、神経痛など |
三環系抗うつ薬
アミトリプチリンなどの三環系抗うつ薬は慢性痛に対する効果が認められています。
痛みの伝達にかかわる神経伝達物質の調整を行うことで神経痛を緩和する可能性があります。
ただし口渇や便秘、眠気などの副作用が出る場合があり、プレガバリンと比較して使い勝手が異なる点に留意が必要です。
他の鎮痛薬との併用
中等度以上の痛みを抱えている方はプレガバリンだけでなく他の鎮痛薬を併用することもあります。
非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やオピオイド系の薬を組み合わせることで痛みの強さや発生メカニズムに多面的に対処できます。
ただし薬の相互作用や副作用リスクも高まる可能性があるため、医師の管理下で行う必要があります。
補助的な治療法
薬物療法以外にも理学療法や神経ブロック注射、認知行動療法などの取り組みを検討できます。
神経ブロック注射は痛みの原因となる神経に局所麻酔薬を注入し、一時的に痛みを遮断します。
認知行動療法は痛みに対する思考や行動の歪みを修正し、痛みとの上手なつきあい方を学ぶ方法です。
これらを組み合わせることで薬の依存度を下げながら痛みのコントロールを目指すことが考えられます。
代替治療薬や併用療法のポイントをまとめます。
- ガバペンチンなど類似薬との比較検討
- 三環系抗うつ薬による神経伝達調整
- NSAIDsやオピオイド鎮痛薬との併用
- 理学療法、ブロック注射、認知行動療法など薬以外の方法も考慮
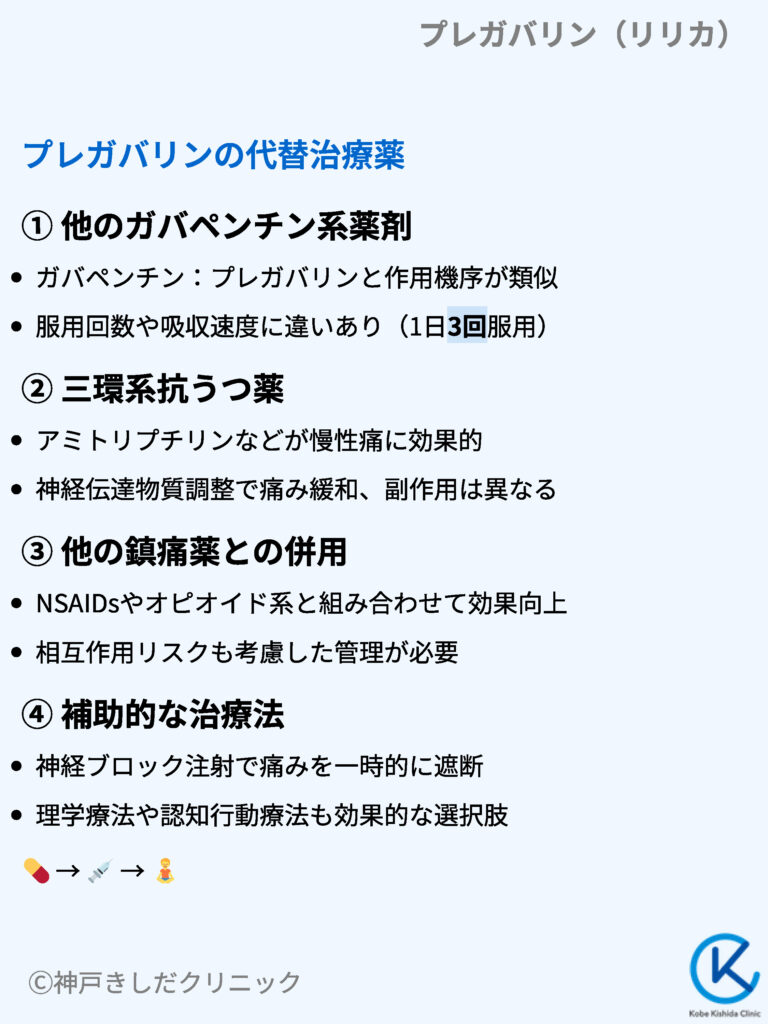
併用禁忌
プレガバリンは比較的安全性が高い薬ですが、併用を避けたほうがよい薬も存在します。
特に中枢神経に作用する薬との組み合わせでは眠気やめまいが増強される可能性があります。
ここでは併用に注意が必要な薬剤や避けたほうがよいケースについて解説します。
他の中枢神経抑制薬との併用
抗不安薬や睡眠薬、オピオイド系鎮痛薬など中枢神経に強く作用する薬と同時に服用すると、呼吸抑制や過度の眠気が生じるリスクが高くなります。
特にオピオイド鎮痛薬と併用する場合は医師が慎重に用量を調整することが必要です。
中枢神経抑制薬との併用リスクには次のようなものがあります。
| 中枢神経抑制薬の種類 | 具体例 | 併用時のリスク |
|---|---|---|
| 抗不安薬・睡眠薬 | ベンゾジアゼピン系など | 極度の眠気、注意力散漫、転倒リスク増など |
| オピオイド系鎮痛薬 | モルヒネ、フェンタニルなど | 呼吸抑制、意識障害のリスク |
アルコールとの組み合わせ
アルコールは中枢神経抑制作用があり、プレガバリンの眠気やめまいのリスクを増幅させます。
日常的に飲酒する方は服用とアルコール摂取のタイミングに注意してください。
夕食時に飲酒する習慣がある場合は服用時間をずらすなどして症状の悪化を避ける工夫が必要です。
妊娠中・授乳中の服用
妊娠中や授乳中のプレガバリンの安全性は十分に確立していない部分があります。
動物実験では胎児への影響が示唆される報告もあります。
医師は利益とリスクを比較したうえで、プレガバリンの投与を行うかどうかを検討します。
自己判断での服用や中断は推奨されないので、妊娠の可能性がある方は必ず医師に相談してください。
重篤な腎障害を抱える方
プレガバリンは腎臓から排泄されるため、重い腎障害がある方は血中濃度が上昇しやすくなります。
極端に腎機能が低下している場合は投与を避けるか、用量を大きく調整する必要があります。
定期的な血液検査で腎機能を確認して異常があれば医師と再度治療方針を話し合うことが重要です。
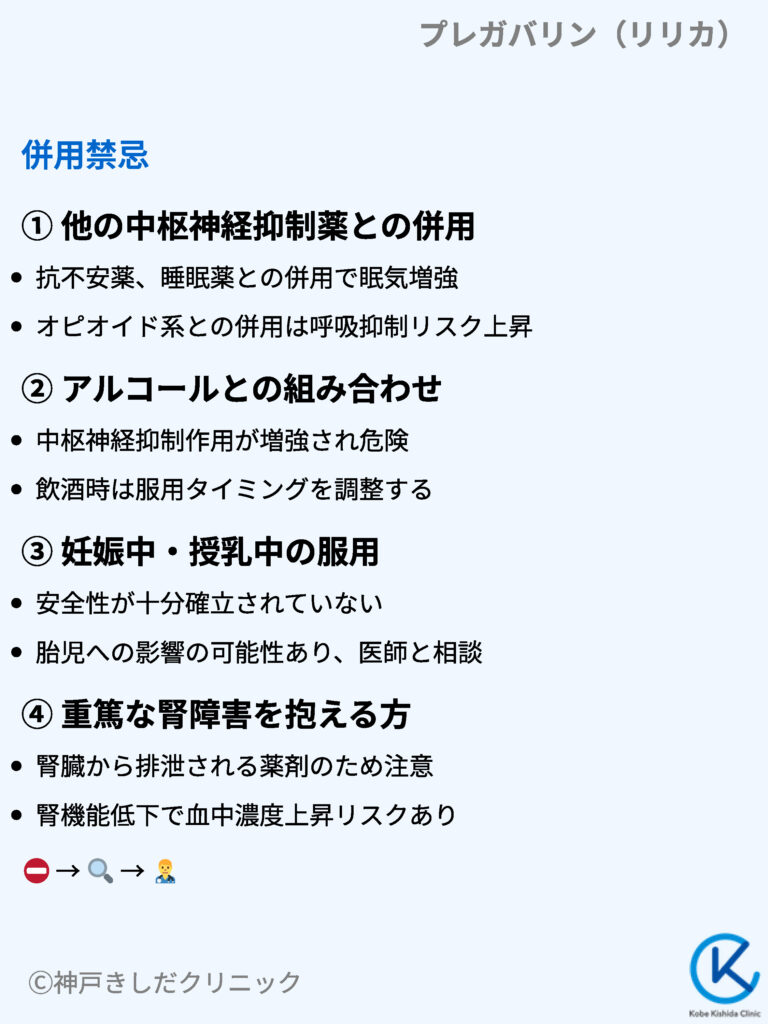
リリカの薬価
プレガバリン(リリカ)の費用は健康保険の適用を受けるか否か処方される用量や日数によって異なります。投与量が増えればそれだけ費用も上昇します。
慢性的な痛みで長期間服用するケースが多いため、コスト面も考慮して治療計画を立てることが大切です。
ここではおおまかな薬価の目安や費用負担の考え方について整理します。
薬価の目安
プレガバリンにはカプセルやOD錠(口腔内崩壊錠)など複数の剤形があり、それぞれに含まれる有効成分量により薬価が異なります。
プレガバリンの先発医薬品である「リリカ」(ヴィアトリス製薬)の薬価は、2025年3月時点で以下の通りです。
カプセル剤と口腔内崩壊錠(OD錠)のそれぞれで25mg、75mg、150mgの規格があり、同じ用量であれば剤型にかかわらず薬価は同一です。
| 規格 | 先発品(リリカ)の薬価 |
|---|---|
| 25mg | 36.4円(1 OD錠・1カプセルともに) |
| 75mg | 60.2円(1 OD錠・1カプセルともに) |
| 150mg | 79.1円(1 OD錠・1カプセルともに) |
中間規格(50mgや100mg)は日本では承認されていません。
医療保険が適用される場合では自己負担割合によって実際の支払額は変わります。
箇条書きで薬価に関するポイントをまとめます。
- 含有量によって単価が異なる
- カプセル・OD錠など剤形でも薬価は異なる
- 1回あたりの処方日数で月々の費用負担が変動する
医療費負担を軽減する制度
高額療養費制度や医療費控除を活用することで自己負担額を抑えられる可能性があります。
長期にわたってプレガバリンを服用する場合は医療保険制度の仕組みを活用することが大切です。
特に高齢者は後期高齢者医療制度による自己負担割合の減免が適用される場合もあります。
以下は医療費負担軽減制度の一例です。
| 制度名 | 概要 |
|---|---|
| 高額療養費制度 | 月の医療費が一定額を超えた場合に超過分を還付 |
| 医療費控除 | 1年間の医療費が一定額を超えた場合に所得控除を受ける |
ジェネリック医薬品の動向
プレガバリンのジェネリック医薬品は非常に多数のメーカーから発売されています。
ジェネリック医薬品でも有効成分が同じであれば基本的な効果は同様です。
ただ、剤形や添加物などが異なる場合もあるため、切り替えを検討する際は医師・薬剤師としっかり相談したほうがよいです。
2020年12月の初回収載時には22社から80品目もの後発品が承認され、75mg錠の薬価は先発品の約33%にあたる36.30円に設定されています。
その後薬価改定等を経て、2025年現在、ジェネリックの薬価はさらに低下しています。
代表的な例として、沢井製薬のプレガバリンカプセル「サワイ」では25mgが12.9円、75mgが20.9円、150mgが28.8円と、先発品に比べて大幅に安価です。
他社のジェネリックも概ね同水準で、25mg剤が8~13円程度、75mg剤が13~23円程度、150mg剤が18~31円程度の範囲に収まっています。
| 規格 | 先発品(リリカ)の薬価 (円/カプセル) | 代表的な後発品の薬価 (円/カプセル) | 後発品の価格レンジ (円/カプセル) | 後発品薬価/先発品薬価 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 25mg | 36.4 | 12.9 | 8 ~ 13 | 約22%~36% |
| 75mg | 60.2 | 20.9 | 13 ~ 23 | 約22%~38% |
| 150mg | 79.1 | 28.8 | 18 ~ 31 | 約23%~39% |
費用面と治療効果の両立
痛みに悩む方にとって治療効果の高さだけでなく費用面も重要な要素です。
プレガバリンの処方を受ける際には保険負担割合や月々の支出額を見据えて他の治療法やジェネリック医薬品との比較検討を行うとよいでしょう。
以上