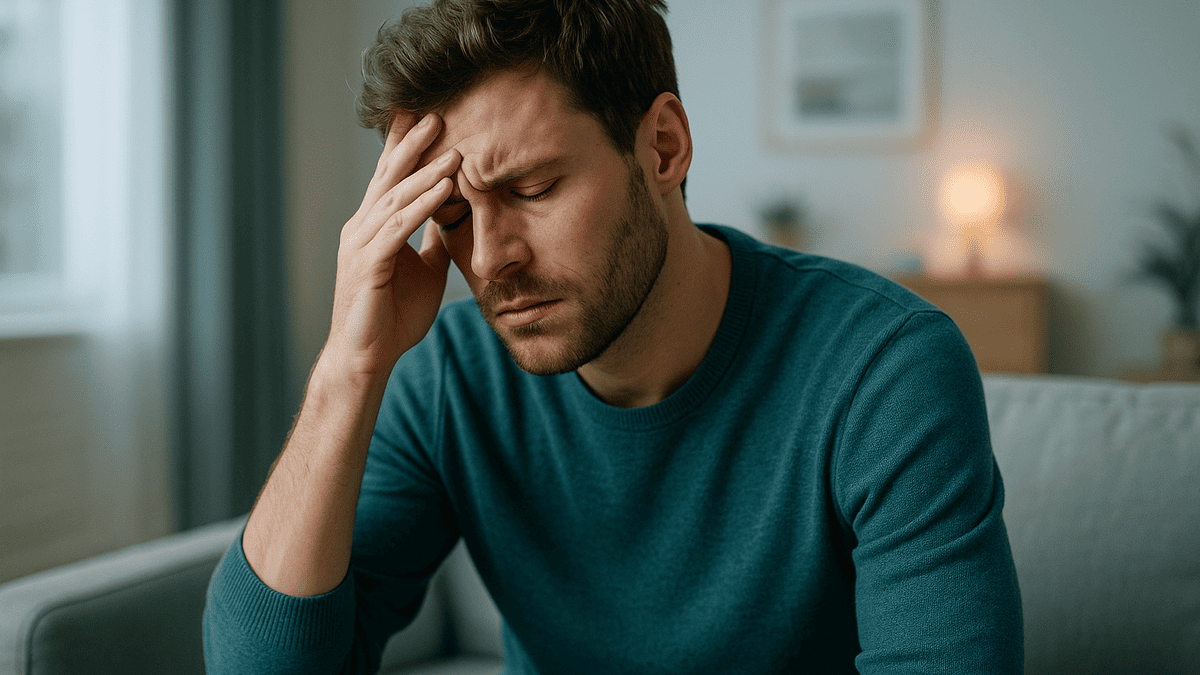「なんだか体がだるい」「すっきりしない不快感が続く」。こうした経験は誰にでもあるかもしれません。診察の際に、医師から「マレーズがありますね」と言われたことはないでしょうか。
マレーズ(malaise)とは医療現場で使われる言葉で、単なる疲れやだるさとは少し異なる体全体の不調や不快感を示す状態を指します。この症状は様々な病気の初期サインである可能性も考えられます。
この記事ではマレーズの正確な意味、倦怠感との違い、そしてマレーズを引き起こす可能性のある病気について、特に糖尿病との関連にも触れながら詳しく解説します。
医療用語「マレーズ」とは?倦怠感との違い
マレーズは多くの人が日常的に使う「だるさ」や「倦怠感」と似ていますが、医療の現場では区別して用いることがあります。
その背景にあるニュアンスを理解することは、ご自身の体調を正確に医師へ伝える上で助けになります。
全身の不調を示す漠然とした不快感
マレーズは特定の部位の痛みや症状ではなく、「なんとなく体全体がすぐれない」「気分が晴れない」といった、漠然とした全身の不快感や不調を表現する言葉です。
はっきりとした原因が思い当たらないにもかかわらず、気力や活力が湧かない状態を指します。
病気の始まりや、体が何らかの異常を抱えているサインとして現れることが多い症状です。
疲労感や倦怠感とのニュアンスの差
疲労感は主に身体的または精神的な活動の後に生じる「エネルギーを消耗した状態」を指し、休息によって回復することが期待できます。
一方、マレーズは休息を取ってもなかなか改善しない、病的なだるさや不快感を伴う点で異なります。
マレーズと類似する症状の比較
| 症状 | 主な特徴 | 回復の目安 |
|---|---|---|
| マレーズ | 原因の特定が難しい全身の不快感・不調 | 休息だけでは改善しにくい |
| 疲労感 | 活動後のエネルギー切れの状態 | 十分な休息で回復する |
| 倦怠感 | マレーズとほぼ同義で使われるが、より「だるさ」が強い状態 | 原因による |
医師がマレーズという言葉から探るもの
患者さんが「だるい」と訴えたとき、医師はその背景にあるものを探ります。
それが活動の結果なのか、それとも病的なものなのかを見極めるために「マレーズ」という言葉を使い、全身に影響を及ぼす病気の可能性を念頭に置いて診察を進めます。
この言葉は、より詳細な検査や問診への入り口となる重要な情報です。
マレーズが起こる身体のサインと背景
マレーズは単なる気分の問題ではなく、体内で何らかの変化が起きていることを示す重要なサインです。その背景には体を守るための正常な反応や、心身のバランスの乱れが関係しています。
身体の異常を知らせる警告信号
私たちの体は異常が生じるとさまざまな方法で警告を発します。マレーズもその一つで、「これ以上無理をしないでほしい」「体内で問題が起きている」という体からのメッセージと捉えることができます。
このサインを無視せず、自身の生活習慣や体調を振り返るきっかけにすることが重要です。
免疫システムが働いている証拠
風邪をひいたときなどに感じるだるさは、ウイルスや細菌と戦うために免疫システムが活発に働いている証拠です。
免疫細胞がサイトカインという物質を放出することで炎症反応が起こり、その副作用として発熱やマレーズが生じます。
この場合のマレーズは、体が正常に防衛反応を示している証拠とも言えます。
マレーズが起こる主な背景
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 身体的要因 | 感染症、内分泌疾患、悪性腫瘍、栄養不良 |
| 精神的要因 | ストレス、うつ病、不安障害 |
| 生活習慣要因 | 睡眠不足、過労、不規則な生活 |
精神的なストレスが引き金になることも
過度な精神的ストレスは自律神経やホルモンバランスの乱れを引き起こし、マレーズの原因となります。
体には明らかな異常が見つからないにもかかわらず強い不調が続く場合は、心の問題が体に影響を及ぼしている可能性も考えなくてはなりません。
マレーズの原因となる主な病気① 感染症と内分泌疾患
マレーズは非常に多くの病気でみられる症状ですが、ここでは特に頻度が高い感染症と、糖尿病を含む内分泌・代謝疾患について解説します。
風邪やインフルエンザなどの急性感染症
ウイルスや細菌が体内に侵入すると免疫システムが活動を開始し、その反応としてマレーズが現れます。
発熱や喉の痛み、咳といった他の症状と共に現れることが多く、原因となる感染症が治癒すればマレーズも改善します。
糖尿病とマレーズの深い関係
糖尿病は血糖値を下げるインスリンというホルモンの働きが悪くなる病気です。
血糖値のコントロールが悪い状態が続くと細胞がエネルギー源であるブドウ糖をうまく利用できなくなり、エネルギー不足に陥ります。
このことが、糖尿病患者様特有のマレーズや倦怠感の大きな原因となります。
糖尿病で見られる主な症状
| 症状 | 原因 |
|---|---|
| マレーズ・倦怠感 | エネルギー不足、高血糖による脱水 |
| 喉の渇き・多飲・多尿 | 高血糖により尿量が増え、脱水状態になるため |
| 体重減少 | ブドウ糖をエネルギーとして利用できないため |
甲状腺機能の異常(低下症・亢進症)
甲状腺は体の新陳代謝を活発にするホルモンを分泌する臓器です。
このホルモンの分泌が過剰になる「甲状腺機能亢進症」では、常に体が走り続けているような状態になり疲弊してマレーズを感じます。
逆にホルモンが不足する「甲状腺機能低下症」では体の活動が鈍くなり、無気力や強いマレーズが現れます。
マレーズの原因となる主な病気② 慢性疾患とその他の病気
マレーズはゆっくりと進行する慢性的な病気や、精神的な不調によっても引き起こされます。長引く場合は、これらの病気の可能性も考える必要があります。
悪性腫瘍(がん)が潜んでいる可能性
がん細胞が体内で増殖する過程で、体は多くのエネルギーを消費します。また、がん細胞が放出する物質が正常な細胞の働きを妨げることもあります。
これらの要因が組み合わさり、原因不明のマレーズや体重減少が、がんの初期症状として現れることがあります。
関節リウマチなどの自己免疫疾患
自己免疫疾患は、本来体を守るはずの免疫システムが自分自身の体を攻撃してしまう病気です。
関節リウマチなどが代表的で慢性的な炎症が続くため、痛みや腫れだけでなく強いマレーズや微熱を伴うことがよくあります。
注意すべきマレーズ以外の症状
| 疑われる病気 | 伴いやすい症状の例 |
|---|---|
| 悪性腫瘍 | 急な体重減少、食欲不振、しこり |
| 自己免疫疾患 | 関節の痛みや腫れ、皮疹、微熱 |
| 心臓・腎臓の病気 | むくみ、息切れ、動悸 |
心臓・腎臓・肝臓の病気
心臓の機能が低下すると全身に十分な血液を送れなくなり、腎臓や肝臓の機能が低下すると体内に老廃物が溜まります。
これらの状態はいずれも全身の細胞の働きを悪くし、持続的なマレーズの原因となります。
うつ病など精神的な不調
うつ病では脳内の神経伝達物質のバランスが崩れ、精神的なエネルギーが低下します。
このことが「何をしても楽しくない」「何もする気が起きない」といった精神症状だけでなく、「体が重い」「起き上がれない」といった身体的なマレーズとして強く現れることがあります。
医療機関を受診する目安と診療の流れ
「このだるさは病院に行くべきか」と迷うこともあるでしょう。ここでは受診を判断するための目安と、医療機関での一般的な診察の流れを紹介します。
こんな症状があれば早めに相談を
単なる疲れとは違う以下のようなサインが見られたら、医療機関の受診を検討してください。
- 2週間以上、原因不明のだるさが続いている
- 休息をとっても全く改善しない
- 発熱、体重減少、リンパ節の腫れなど他の症状がある
- 日常生活や仕事に支障が出ている
丁寧な問診から始まる診断
診察では、まず医師が症状について詳しく話を聞きます。
いつから、どのようなだるさがあるのか、他に気になる症状はないか、生活習慣やストレスの状況など、できるだけ具体的に伝えることが正確な診断につながります。
血液検査や画像検査で原因を探る
問診や身体診察の結果から医師は病気の可能性を考え、必要な検査を計画します。
血液検査は貧血や炎症の有無、肝臓や腎臓、甲状腺の機能、血糖値などを調べ、マレーズの原因を探るための重要な情報を与えてくれます。
必要に応じて、レントゲンや超音波(エコー)などの画像検査を行うこともあります。
血液検査で主に確認する項目
| 検査項目 | 分かること |
|---|---|
| 血球計算 | 貧血や感染症の有無 |
| 生化学検査 | 肝臓・腎臓の機能、血糖値、電解質バランス |
| 甲状腺ホルモン | 甲状腺機能の異常 |
日常生活でマレーズを感じたときの対処法
病気が原因ではないマレーズの場合、生活習慣を見直すことで改善が期待できます。ただし、症状が長引く場合は自己判断せず、必ず医療機関に相談してください。
十分な休息と栄養バランスの取れた食事
心と体のエネルギーを回復させるためには、質の良い睡眠を十分にとることが基本です。
また、特定の食品に偏らず、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどをバランス良く摂取する食生活を心がけましょう。特にエネルギー代謝に必要なビタミンB群は重要です。
ストレスとの上手な付き合い方
ストレスを完全になくすことは難しいですが、自分なりの解消法を見つけることが大切です。
軽い運動をする、趣味に没頭する時間を作る、信頼できる人に話を聞いてもらうなど心身をリラックスさせる習慣を取り入れましょう。
セルフケアのポイント
| 項目 | 具体的な行動例 |
|---|---|
| 休息 | 7時間以上の睡眠、昼寝(15分程度) |
| 食事 | 1日3食、主食・主菜・副菜を揃える |
| 運動・気分転換 | ウォーキング、ストレッチ、趣味の時間 |
自己判断での市販薬の使用には注意
栄養ドリンクやサプリメントは一時的な気休めにはなるかもしれませんが、根本的な解決にはなりません。
また、安易に市販の痛み止めや風邪薬を使い続けると、原因となっている病気の発見が遅れる可能性もあります。
不調が続く場合は、専門家である医師に相談することが最善の策です。
マレーズに関するよくある質問
最後に、マレーズに関して患者様からよく寄せられる質問にお答えします。
- Qただの疲れと病的なマレーズの見分け方は?
- A
最も大きな違いは「休息で回復するかどうか」です。
一晩ぐっすり眠ったり、週末にゆっくり休んだりして改善するものは、生理的な疲労の可能性が高いです。
一方で十分休んでも改善しない、むしろ悪化する、他の症状(発熱、体重減少など)を伴う場合は病的なマレーズを疑い、受診を検討すべきです。
- Q糖尿病でマレーズが起こるのはなぜですか?
- A
主な理由はエネルギー不足です。
糖尿病では食べ物から摂取したブドウ糖を細胞がうまくエネルギーとして使えなくなります。このため体中の細胞がガス欠のような状態になり、マレーズや強い倦怠感を感じます。
また、高血糖の状態が続くと脱水傾向になり、それもだるさの一因となります。適切な治療で血糖値を良好にコントロールすることが症状の改善につながります。
- Q何科を受診すればよいでしょうか?
- A
まずは、かかりつけの内科や総合診療科を受診するのが良いでしょう。丁寧な問診と基本的な検査を通じて、原因を幅広く探ってくれます。
その上で、糖尿病や甲状腺疾患が疑われれば内分泌内科へ、関節の痛みが強ければ膠原病科へ、といったように専門の診療科を紹介してくれます。
何が原因か分からないからこそ、まずは総合的に診てくれる医師に相談することが大切です。
以上
参考にした論文
TANAKA, Yoshiya, et al. Why does malaise/fatigue occur? Underlying mechanisms and potential relevance to treatments in rheumatoid arthritis. Expert Review of Clinical Immunology, 2024, 20.5: 485-499.
ARAKAKI, Minoru, et al. Personalized nutritional therapy based on blood data analysis for Malaise patients. Nutrients, 2021, 13.10: 3641.
GLOECKL, Rainer, et al. Practical recommendations for exercise training in patients with long COVID with or without post-exertional malaise: a best practice proposal. Sports Medicine-Open, 2024, 10.1: 47.
HUNTER, James Davison. The modern malaise. In: Making Sense of Modern Times. Routledge, 2024. p. 76-100.
BORNER, Tito; DE JONGHE, Bart C.; HAYES, Matthew R. The antiemetic actions of GIP receptor agonism. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 2024, 326.4: E528-E536.
GHALI, Alaa, et al. Warning signals of post-exertional malaise in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome: a retrospective analysis of 197 patients. Journal of Clinical Medicine, 2021, 10.11: 2517.
PAGEN, Demi ME, et al. High proportions of post-exertional malaise and orthostatic intolerance in people living with post-COVID-19 condition: the PRIME post-COVID study. Frontiers in medicine, 2023, 10: 1292446.
PAGEN, Demi ME, et al. High proportions of post-exertional malaise and orthostatic intolerance in people living with post-COVID-19 condition: the PRIME post-COVID study. Frontiers in medicine, 2023, 10: 1292446.
MOTOO, Yoshiharu. Role of Kampo medicine in modern cancer therapy: towards completion of standard treatment. Journal of Nippon Medical School, 2022, 89.2: 139-144.
BURNUM, John F. The malaise in internal medicine. Archives of Internal Medicine, 1977, 137.2: 226-229.