最近「急に体重が減った」「思い当たる原因もなく痩せてしまった」という方で、特に健康診断で血糖値などの異常を指摘された経験のある方は、糖尿病ではないかとご心配があるのではないでしょうか。
とくに糖尿病の初期段階では、何らかのきっかけで急激に痩せるケースが見られます。ここでは、急激な体重減少に着目して、糖尿病内科の視点から考えられるリスクや対処のヒントをまとめています。
長引く体重減少が気になるときのチェックポイントや、健康診断との向き合い方などを順を追ってご紹介します。
最近急に痩せた、急な体重減少が気になるなど、糖尿病ではないかとご心配な方は神戸きしだクリニックの糖尿病内科で専門的な診察を承ります。詳しくはこちら
この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長
医学博士
日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医
日本核医学会認定 核医学専門医
【略歴】
神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)
急な体重減少は要注意 – 早期発見で防ぐ重大疾患
急に体重が減ると、多くの人は「何か病気ではないか」と不安になってしまうことと思います。
たしかに、体重が短期間で大きく変わる場合は、身体の中で何らかの異常が進んでいる可能性があります。ここでは、急な体重減少を見過ごさないために押さえたい基本的な視点をお伝えします。
「急に痩せた」と感じる状態とは
短期間で2~3kg以上の減少があると、多くの人が「急に痩せた」と感じます。
食欲不振や運動量の変化など、生活習慣が大きく変わったわけでないのに痩せた場合は、内臓機能や代謝に異常があるかもしれません。
人によっては、日常の忙しさやストレスによって食事量が減っていたり、不眠などが続いていても体重が落ちることがあります。
しかし、原因がはっきりしないときは、何らかの病気が隠れているリスクを考える必要があります。
健康診断で異常を指摘されたときの心構え
健康診断の結果で血糖値や中性脂肪、肝機能などの項目に異常が示された場合は、原因を放置しない姿勢が重要です。
体重減少が続いているとき、たとえば血糖値の数値が高い・HbA1cが基準値を超えているなどの異常が同時に見られるなら、糖尿病に限らず甲状腺機能亢進症や悪性腫瘍など、複数の可能性を視野に入れたチェックが必要です。
迷ったときは、早めに医師に相談することが推奨されます。
体重変動の見逃せないサイン
体重変動は体調不良のサインであるだけでなく、生活習慣が偏っている兆候でもあります。食事と運動のバランスが極端であったり、精神的ストレスが大きいと、体重の増減が激しくなります。
実際に、知らないうちに暴食と絶食を繰り返している場合や、過度にカフェイン飲料を摂取している場合もあるため、日々の生活を見直して原因を探る必要があります。
特に連日の体重変化が大きい方は、生活習慣だけでなく病気のリスクを考慮してください。
体重が急に減少したときにチェックするポイント一覧
| チェック項目 | 具体例 | 備考 |
|---|---|---|
| 食事量・食欲 | 食事回数の減少、食欲不振 | 無意識の間食減少や偏食の可能性 |
| 運動量・活動量 | 過度な運動、仕事量増加で体力消耗が続く | エネルギー不足による減量に注意 |
| 睡眠状態 | 不眠、睡眠時間の極端な減少 | ホルモンバランスの乱れを招くリスク |
| ストレスの有無 | 精神的負担、環境変化 | 自律神経の乱れによる食欲変動 |
| 健康診断の数値 | 血糖値・HbA1c・甲状腺ホルモンなどの異常 | 病気の初期兆候を把握する重要な手がかり |
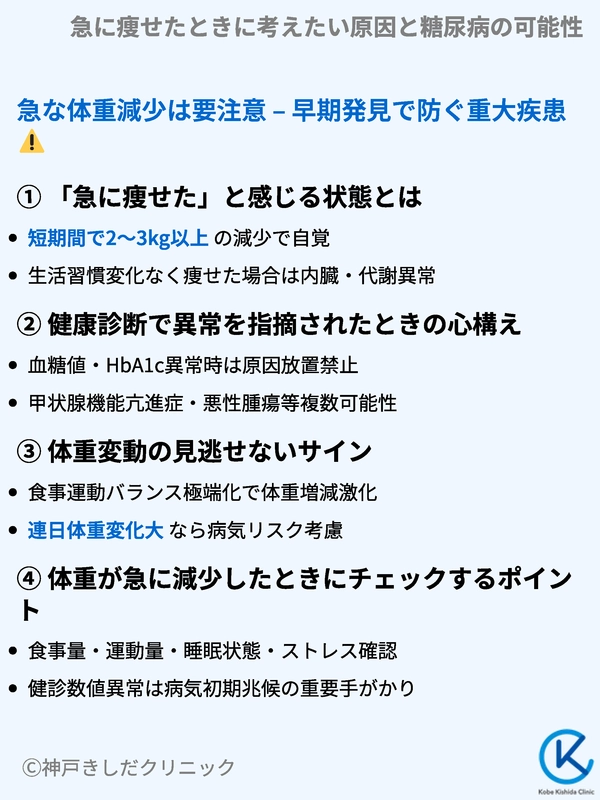
糖尿病と体重減少の関係
急な痩せや体重減少は、糖尿病と密接に関係するケースがあります。とくにインスリンの分泌や作用に問題があると、身体がエネルギーを十分に利用できず、結果的に体重が減りやすくなります。
ここでは、糖尿病のメカニズムと体重変化の関連を見ていきましょう。
血糖値が高まる仕組み
糖尿病では、血液中にブドウ糖が過剰に存在します。一般的に血糖値が高いと肥満というイメージを抱きがちですが、インスリンの働きが低下すると細胞が糖を取り込めなくなり、エネルギー不足になります。
そのため、体は脂肪だけでなく筋肉のタンパク質なども分解してエネルギーを作ろうとするため、急な体重減少が起こります。
インスリンとエネルギー利用の関係
インスリンは、血液中のブドウ糖を細胞に取り込む指示を出すホルモンです。
必要量のインスリンが分泌されない、またはインスリン抵抗性によって効果が発揮できない状態になると、身体は十分なエネルギーを得られません。結果的に「痩せの症状」を呈する人もいます。
肥満型の糖尿病だけでなく、やせ型の糖尿病もあるため、急に痩せたという状態は糖尿病を疑う一因になります。
糖尿病におけるやせ型・肥満型の特徴
糖尿病といっても全員が太っているわけではありません。やせ型でもインスリン分泌量が低い状態になると、身体が糖を利用しにくくなって高血糖と体重減少が同時に生じます。
肥満型であっても、急に血糖コントロールが悪化し、インスリン分泌が間に合わない状況になると、同様に体重が落ちてしまうケースがあります。
糖尿病のタイプ別特徴
| タイプ | やせ型の場合 | 肥満型の場合 |
|---|---|---|
| 1型糖尿病 | インスリンの分泌量が著しく少ない | まれ |
| 2型糖尿病 | 分泌量もしくは作用が不十分でやせの症状あり | インスリン抵抗性が強く肥満を伴うこと多い |
| 重症化した場合 | エネルギー不足により体重減少 | 急激に血糖値が悪化すると痩せることも |
放置すると起こり得る合併症
急激な体重減少と高血糖の状態を放置すると、腎機能障害や神経障害、網膜症などの合併症に進行しやすくなります。
糖尿病は血管にも負担をかけるため、心筋梗塞や脳梗塞などの大きなリスクにつながる可能性があります。急に痩せた状態が続くと体力が低下して免疫力も落ち、感染症にかかりやすくなる点にも注意が必要です。
- 血管障害(細小血管・大血管)
- 神経障害(手足のしびれ、感覚異常)
- 腎機能障害(むくみや尿たんぱくの増加)
- 網膜症(視力低下や視野欠損)
このように、体重減少と糖尿病が結びつく場合は、一刻も早く対策を取ることが大切です。
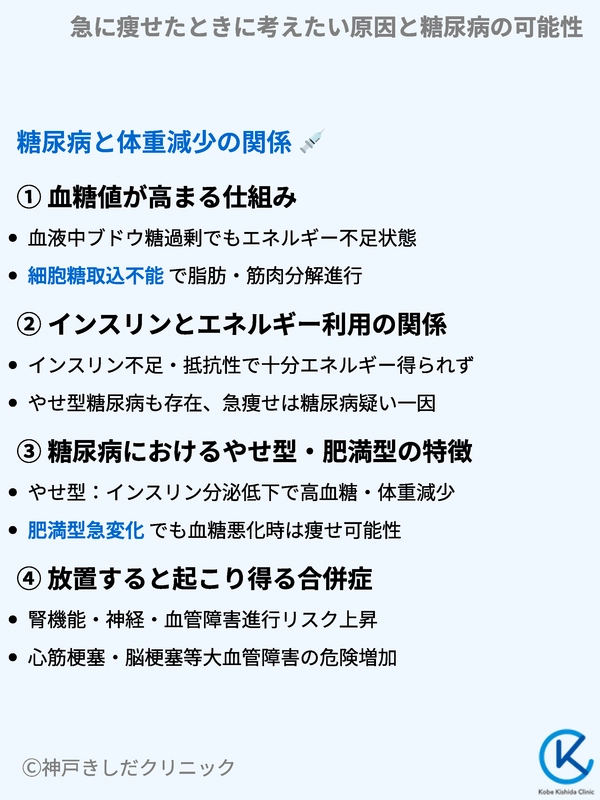
急な体重減少を引き起こすその他の疾患
急に体重が落ちる症状は、糖尿病以外にもさまざまな病気の可能性があります。とくに甲状腺の異常や悪性疾患、心理的要因は見逃せません。
痩せたからといって必ずしも糖尿病とは限りませんが、複数の疾患を鑑別するために正しい情報を把握しておくと役立ちます。
甲状腺機能亢進症
甲状腺ホルモンの分泌過多になると、基礎代謝が高まり、エネルギー消費が増えます。食べても食べても体重が減るという人は、甲状腺機能亢進症の可能性があります。
動悸や手の震え、多汗などの症状を伴う場合は特に要注意です。健康診断や血液検査で甲状腺ホルモンの値を調べることで判断できる場合があります。
悪性疾患を疑う必要性
がんを含む悪性疾患では、知らないうちに体重が落ちることがあります。
食欲があるのに痩せる、あるいは慢性的に体調がすぐれない状態が続くなら、悪性腫瘍を含む可能性を視野に入れる必要があります。
喫煙習慣や家族歴など、リスクファクターをお持ちの方は一度検査を受けると安心です。
ストレスや心身の負担
強いストレスを受けていると、自律神経やホルモンのバランスが乱れて食欲不振を起こすことが多く、結果的に体重が減ることがあります。
過度のストレスがうつ症状を引き起こして食事が摂れなくなる事例もあり、心理的要因による体重減少は軽視できません。
- 仕事や家庭での強いプレッシャー
- 睡眠不足や慢性的な疲労
- 対人関係の問題
- 不安障害や気分障害などの精神的な負担
上記のような事情があるなら、精神科や心療内科などで相談すると同時に、栄養補給方法を工夫する必要があります。
体重減少を伴う主な疾患・要因
| 疾患・要因 | 主な症状と特徴 |
|---|---|
| 糖尿病 | 高血糖、口渇、多尿、疲れやすい、体重減少 |
| 甲状腺機能亢進症 | 動悸、発汗過多、手指の震え、食欲増でも体重減少 |
| 悪性疾患(がんなど) | 食欲低下または食欲があるのに痩せる、慢性的な疲労感や痛み |
| ストレス関連 | 食欲不振、胃腸障害、睡眠障害、うつ症状による意欲の低下 |
| 心不全・腎不全など | むくみや呼吸困難など別の症状を伴いつつ、進行すると体重減少が起こる |
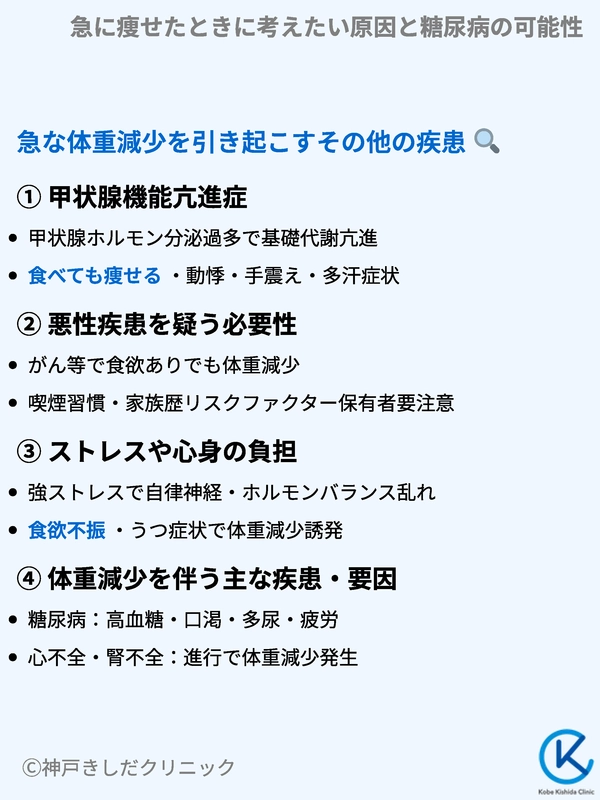
糖尿病の可能性を見分けるためのセルフチェック
「急に痩せた」「健康診断で血糖値が高めと言われた」という段階で糖尿病を疑うことは大切です。ただし、実際には糖尿病以外の原因も多々あります。
ここでは、初期症状や生活の中でのサインを簡単に確認する方法をまとめます。
初期症状の把握方法
糖尿病の初期段階では、自覚症状が乏しいケースも少なくありません。典型的には、次のような症状があれば一度受診を検討するきっかけになります。
- のどの渇きが続き、水分をよく欲する
- トイレの回数が増え、尿が多くなる
- だるさや疲労感が抜けにくい
- 視界がぼやける、目の疲れを感じる
- 傷が治りにくい
特に体重減少を伴う場合は、血糖コントロールが大きく乱れている可能性が高いです。
日常生活の観察ポイント
日々の暮らしのなかで糖尿病を疑うサインを見落とさないようにする工夫があります。朝起きたときの口渇の具合や、手足の冷え、しびれなどにも気を配ると健康管理に役立ちます。
また、少し歩いただけで疲れを感じるようになったなど、体力の衰えを実感した場合は、早めに血糖値や体組成を確認すると安心です。
糖尿病予備軍が感じやすい変化
| 気づきやすい変化 | 具体例 | 疑うべきポイント |
|---|---|---|
| のどの渇き | 夜間に何度も水分をとりたくなる | 高血糖で体内の水分が不足している |
| 尿の回数・量の増加 | 1日に何度もトイレに行く必要が出る | 糖が尿に混ざる影響で排尿回数・量が増える |
| だるさや疲れやすさ | 仕事や家事が長続きせず、休憩しても疲労感が抜けにくい | 細胞がエネルギーを取り込みにくい状態 |
| 目のかすみ | 文字が読みづらくなる、視力の低下を感じる | 血管障害が進行すると網膜にダメージを負いやすい |
| 手足のしびれ | とくに夜間や朝方に手足の先端がチクチクする | 神経障害がすでに始まっている可能性 |
簡易的な血糖値チェックの意義
近年、薬局やドラッグストアで血糖値測定器を取り扱うケースがあります。自己測定で正確に診断できるわけではありませんが、定期的に測って大きな変化に気づく手がかりになります。
健康診断とあわせて自己測定の結果をメモしておけば、医師との情報共有が円滑に進みます。
受診のタイミング
「急に痩せた」「水分を大量にとる」「トイレが近い」といった症状を同時に感じるなら、早期受診が重要です。
特に健康診断で血糖値やHbA1cの異常を指摘された場合、放置すると合併症のリスクが高まる可能性があります。
受診の段階で症状が進行していると、治療方法も限られてくるため、できるだけ早く行動に移すことをおすすめします。
- 体重が1カ月で2kg以上落ち続けている
- 尿が泡立ちやすい、色の変化が気になる
- 手足にしびれや痛みを感じる
- 微熱や倦怠感が慢性的に続く
これらに当てはまる方は、糖尿病内科などの専門医に相談するとよいでしょう。
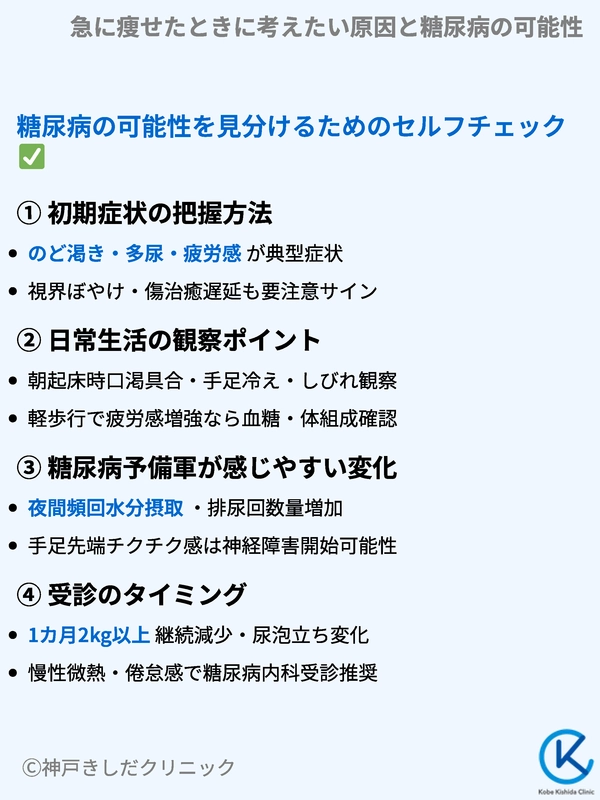
健康診断で指摘された血糖値の異常があるとき
健康診断の結果で空腹時血糖値やHbA1cに異常があると言われた場合、生活習慣を見直すだけでなく、医療機関で詳細な検査を受けることが大切です。
ここでは、指摘後の基本的な流れや、受診前に押さえておきたいポイントを説明します。
空腹時血糖値とHbA1c
空腹時血糖値は食事をとっていない状態の血糖値で、HbA1cは過去1~2カ月の血糖値の平均的な状態を示します。
空腹時血糖値が正常でも、HbA1cが高いと糖尿病のリスクが高いこともあります。
逆に、健康診断の日だけ特別な状況(極度の緊張や過度な食事制限)が重なって血糖値が変動していることもあるため、確定診断には追加の検査が必要です。
- 空腹時血糖値:基準値はおおよそ100mg/dL未満
- HbA1c:6.0%台後半を超えると糖尿病予備軍や糖尿病の可能性
予備軍の段階で気をつけたい生活習慣
糖尿病予備軍と診断された場合でも、生活習慣の改善によって症状が進行するのを防げる場合があります。
日常的にエネルギー過多にならないよう食事量や栄養バランスを調整し、適度な運動を取り入れることがポイントです。
また、ストレスのコントロールや十分な睡眠も血糖コントロールに大きく影響します。
生活習慣を見直すポイント
- 糖質の摂り過ぎを防ぎ、全体のカロリーを抑える
- 脂質や塩分も適度に制限し、動脈硬化のリスクを減らす
- 毎日30分程度のウォーキングなど、有酸素運動を続ける
- 睡眠時間を6~7時間ほど確保し、ストレスをため込みすぎない
- 定期的に血糖値を測定し、自分の状態を把握する
クリニックでの精密検査と治療方針
健康診断で引っかかった数値を精査するために、経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)などの詳しい検査を行う場合があります。
検査結果次第では、内服薬やインスリン注射などの治療が提案されることもあります。糖尿病内科では患者一人ひとりの状態に応じて、栄養指導や運動指導を組み合わせた治療方針を立てます。
糖尿病の主な検査方法と目的
| 検査名 | 目的・特徴 |
|---|---|
| 空腹時血糖値 | 8時間以上絶食後の血糖値を測定 |
| HbA1c | 過去1~2カ月間の平均的な血糖コントロール状況 |
| 経口ブドウ糖負荷試験(OGTT) | ブドウ糖溶液を飲み、時間ごとに血糖値の推移を確認 |
| 尿検査 | 糖やケトン体、蛋白などの有無を確認 |
| 血中インスリン濃度 | インスリン分泌量とインスリン抵抗性を推測 |
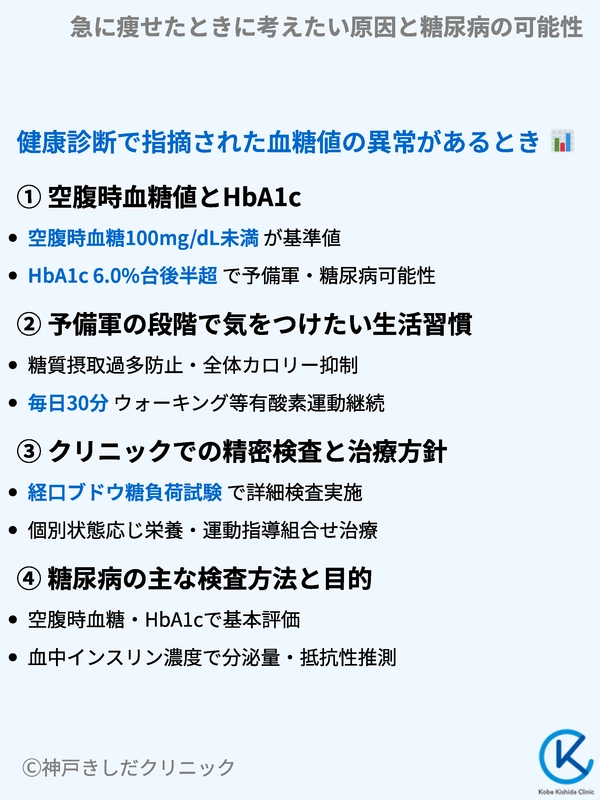
体重減少と食事管理のポイント
急な体重減少があり、糖尿病や予備軍の可能性がある場合、食事内容を適切に見直すことが大事です。
食欲不振や胃腸の不調などがないかをチェックしながら、身体に必要な栄養を十分に摂れるメニューを考える必要があります。
栄養バランスを考慮する意義
体重が減るということは、摂取カロリーが消費カロリーを下回っている可能性が高いです。とくにタンパク質やビタミン、ミネラルが不足すると、筋肉量の減少や免疫力の低下につながります。
糖尿病の場合、血糖値を上げやすい糖質だけに目を向けるのではなく、全体的なバランスを重視すると病状の進行を抑えやすくなります。
タンパク質とエネルギー補給
急に痩せた方は、筋力低下や疲労感を訴えるケースが多いです。肉、魚、卵、大豆製品といったタンパク質源を適度に摂るだけでなく、主食からのエネルギー補給も欠かせません。
ただし、白米やパンなど血糖値を上げやすい炭水化物の摂取量には注意し、野菜や海藻類と一緒に食べると血糖値の急上昇を抑えやすくなります。
食材とエネルギー源の目安
| 食材カテゴリ | 例 | 摂取時のポイント |
|---|---|---|
| タンパク質源 | 鶏肉、魚、豆腐、納豆など | ビタミンやミネラル豊富な食材と組み合わせる |
| 炭水化物 | 玄米、全粒粉パン、蕎麦など | 食物繊維が多く血糖値の急上昇を緩和しやすい |
| 野菜 | ほうれん草、ブロッコリーなど | 食物繊維やビタミン、ミネラルの補給 |
| 果物 | りんご、柑橘類 | 摂り過ぎは糖質過多になるため1日1~2個程度に留める |
| 乳製品 | 牛乳、ヨーグルト、チーズ | カルシウム補給に役立つが、脂質量に注意 |
食事内容の見直し
急激に痩せる状態を放置するとエネルギー不足に陥り、低血糖を起こしやすくなったり、筋力が落ちたりします。
特に糖尿病の疑いがある方は、医師や管理栄養士に相談しながら1日の摂取カロリーと栄養素のバランスを調整すると安心です。
外食が多い方は、揚げ物や甘いドリンクを控え、野菜やタンパク質を多く含むメニューを選ぶことを意識しましょう。
食欲不振への対処法
短期間で体重が落ち続けると、「食べたい」という気持ちが出にくくなることもあります。
胃が疲れているときは1回の食事量を少なめにして回数を分ける方法や、消化の良いスープやおかゆなどを活用するとよいでしょう。
また、香味野菜や柑橘系の酸味を加えると食欲が増す場合があります。無理に大量に食べるより、少量でも高カロリー・高タンパクの食品を取り入れる工夫が求められます。
- 食事回数を1日3回から4~5回に小分けにする
- 香辛料や柑橘類で味に変化をつける
- 高カロリーの油や乳製品を過剰に使わないように注意
- 栄養補助食品やサプリメントを上手に利用する
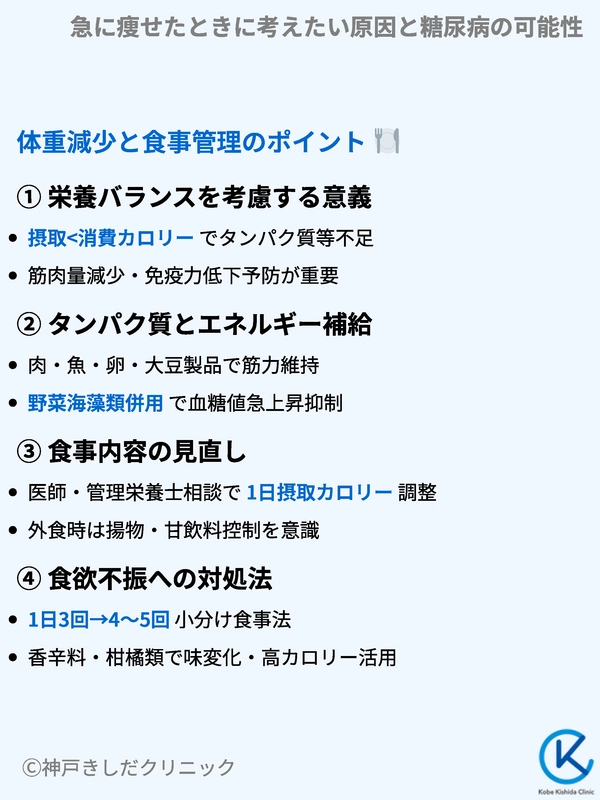
体重減少が続くときの運動と生活習慣
体重減少が続く方は、運動を取り入れるか迷うことが多いです。極端な運動不足や過度な負荷をかけると、かえって健康を損なう可能性があります。
適切な運動や生活習慣の見直しによって、身体のエネルギー代謝を安定させ、健康的な体重維持を目指すことが大切です。
適度な運動量とカロリー消費
体重が減りやすい人ほど、激しい運動でさらにカロリーを消費しすぎると、かえって体調を崩すリスクがあります。
ウォーキングや軽めのヨガ、ストレッチなど、身体に負担の少ない運動を日常に組み込むと、血流を高めて食欲や消化機能を促進しやすくなります。
特に筋力が落ちていると感じる方は、筋トレも無理のない範囲で取り入れると基礎代謝の維持に役立ちます。
取り入れやすい運動の種類
- ウォーキングや軽いジョギング
- ストレッチやヨガ
- スクワットやプランクなどの自重トレーニング
- 水中ウォーキングや軽めの水泳
睡眠とホルモンバランス
睡眠時間が短いまたは不規則だと、ホルモンバランスが乱れて食欲が減退したり、逆に深夜に空腹を感じて偏った食事をしがちになります。
とくに成長ホルモンやインスリン、コルチゾールなどのホルモンは睡眠中の身体の状態と密接に関係しているため、体重管理に影響を与える要因として見逃せません。
就寝前のスマホやパソコン利用を控え、できるだけリラックスした状態で布団に入ることが理想です。
ストレスコントロール
ストレスは食欲と体重変化に直結します。ストレスが蓄積すると、ホルモン分泌や自律神経の働きに乱れが生じ、食事量の変化や消化不良につながります。
適度な運動や趣味の時間を確保したり、カウンセリングやセルフケアを行うなど、ストレス緩和を図る方法を習慣化すると健康維持に貢献します。
ストレス軽減のための工夫
| 方法 | 具体的な実践例 |
|---|---|
| 適度な運動 | 軽い有酸素運動やストレッチ |
| リラックスできる趣味 | 音楽鑑賞、読書、アロマテラピーなど |
| 人とのコミュニケーション | 友人や家族、専門家との相談や雑談 |
| 呼吸法やマインドフルネス | 深呼吸、瞑想で自律神経を整える |
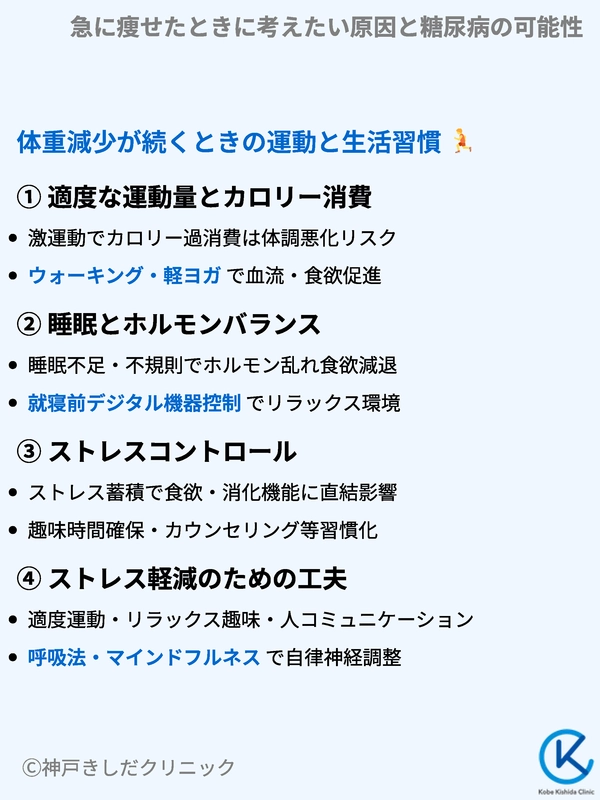
受診を検討すべき症状と糖尿病内科の役割
急な体重減少があり、なおかつ血糖値の異常を指摘された場合は、早めに専門的な検査を受けることがリスク回避につながります。
糖尿病内科は、糖尿病の疑いだけでなく、生活習慣病や代謝に関する総合的な検査とサポートを行う診療科です。自覚症状が乏しくても、合併症予防の観点から受診を検討する価値があります。
自覚症状がないときの危険性
糖尿病の初期は明確な症状がないことが多く、体重減少などで異変を感じたときにはすでに進行している可能性があります。
自覚症状がないからといって安心するのではなく、血液検査や尿検査を定期的に受けることが予防と早期発見につながります。
急激な体重減少と血糖異常が重なるケースは、治療が必要な段階に差しかかっているかもしれません。
かかりつけ医との連携
健康診断の結果をかかりつけ医と相談し、その医師の判断で糖尿病内科へ紹介状を書いてもらう流れもあります。
糖尿病が否定された場合も、甲状腺や他の内分泌疾患の検査を受けられる医療機関を紹介してもらえる場合もあるので、遠慮なく相談すると安心です。
定期検診の重要性
糖尿病は慢性疾患であり、血糖値のコントロールと合併症の予防が長期的な課題です。定期的に通院している方ほど、血糖コントロールが安定しやすい傾向があります。
逆に自己判断で受診をやめてしまうと、合併症のリスクが高まるだけでなく、急激な体重変化にも気づきにくくなります。
治療と日常生活の両立
糖尿病内科では薬物療法だけでなく、栄養や運動、ストレスマネジメントなど、総合的なアドバイスを行います。
患者の生活リズムや仕事の都合に合わせた治療計画を作り、定期的なフォローを行うので、上手に活用すると日常生活を維持しながら病気の管理がしやすくなります。
急に痩せる症状が続いているときは、食事や運動のバランスを慎重に調整しながら治療を進める必要があります。
糖尿病内科の主な役割と支援の内容
| 主な役割 | サポート例 |
|---|---|
| 診断と治療方針の確立 | 検査結果に応じた薬物療法やインスリン治療の開始 |
| 生活指導 | 食事療法、運動療法、ストレス管理などのアドバイス |
| 合併症の早期発見と予防 | 定期検診や精密検査によるリスク評価 |
| チーム医療の提供 | 医師・看護師・管理栄養士・薬剤師の連携 |
| 患者指導 | 個別相談や情報提供により自己管理能力を高める |
急に体重が減ったときは、糖尿病や甲状腺機能亢進症、悪性疾患など、さまざまな原因を疑う必要があります。
血糖値の異常が見られる場合は特に、糖尿病内科で検査を受けると早期対応につながります。生活習慣や食事のバランスを整えて体重の安定を図り、必要に応じて医師に相談することが大切です。
糖尿病を知ろう
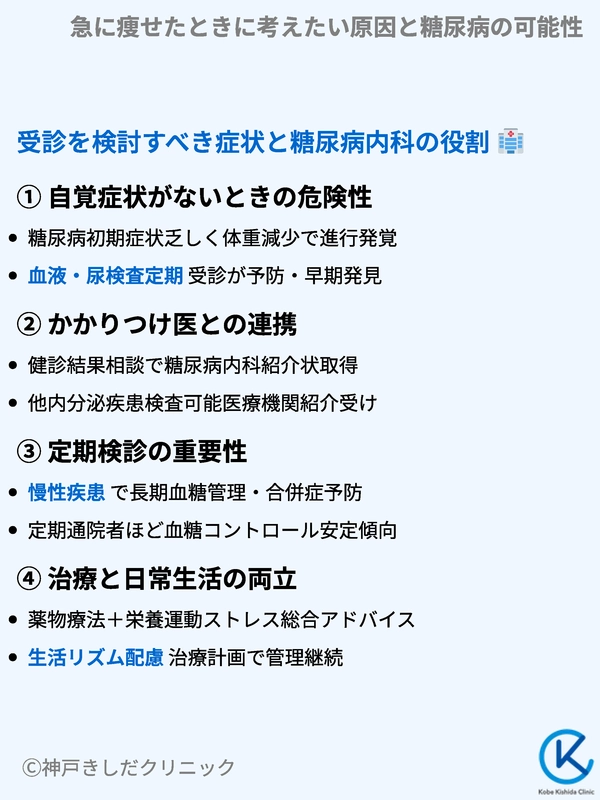
当院(神戸きしだクリニック)への受診について
気になる症状があり糖尿病検査をご希望の方は、当院の糖尿病内科で対応させていただきます。経験豊富な専門医による丁寧な診察と、充実した検査機器による精密検査を提供しています。
糖尿病内科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |
| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |
| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |
| 月 | – | 〇 |
| 火 | 〇 | 〇 |
| 水 | – | 〇 |
| 木 | 〇 | – |
| 金 | – | 〇 |
| 土 | 〇 隔週 | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |
検査体制
- 血糖値検査(随時血糖・空腹時血糖)
- HbA1c検査
- 経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)
- 尿検査(尿糖・尿蛋白)
- 血液検査(脂質・肝機能・腎機能など)
など、必要に応じた検査を実施いたします。網膜症の精査や詳細な合併症検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など専門医療機関と連携して対応いたします。
予約・受診方法
当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約
お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。
▽ クリック ▽



