血圧が高い状態が続くと動脈硬化などが進みやすくなり、血糖値のコントロールが乱れたまま放置すると糖尿病へ近づく可能性が高まります。
実は高血圧と糖尿病は密接に関連していて、片方を改善しないともう片方も悪化しやすいという特徴があります。
本記事では、高血圧の基礎知識から糖尿病との関連性、合併症のリスク、さらに生活習慣の見直し方まで詳しく紹介します。血圧管理と血糖管理の両立は、今後の健康を左右する重要なポイントです。
高血圧など気になる症状があり、糖尿病との関係についてご心配な方は神戸きしだクリニックの糖尿病内科で専門的な診察を承ります。詳しくはこちら
この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長
医学博士
日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医
日本核医学会認定 核医学専門医
【略歴】
神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)
高血圧とは何か
血圧が高い状態が続くと、全身の血管や臓器へ大きな負担をかけます。まずは高血圧の定義や分類、どのようにして血圧が上がるのかといった基礎的な部分について解説します。
血圧が上昇するメカニズムを理解すると、その後の予防や対策が取りやすくなります。
高血圧の定義と分類
一般的に高血圧とは、収縮期血圧(いわゆる上の血圧)が140mmHg以上、または拡張期血圧(下の血圧)が90mmHg以上の状態を指します。
血圧値によるおおまかな分類は次のようになります。
血圧分類の目安
- 正常血圧:収縮期血圧120mmHg未満 かつ 拡張期血圧80mmHg未満
- 正常高値血圧:収縮期血圧120~129mmHg かつ 拡張期血圧80mmHg未満
- 高値血圧:収縮期血圧130~139mmHg または 拡張期血圧80~89mmHg
- 高血圧:収縮期血圧140mmHg以上 または 拡張期血圧90mmHg以上
高血圧の見過ごされやすさ
高血圧は自覚症状がほとんどありません。頭痛や肩こり、めまいなどがあっても「疲れや年齢のせい」と思って放置しがちです。
そのため、気づかないうちに病状が進行していることが珍しくありません。
血圧が高くなるメカニズム
血圧は、心臓が血液を送り出すポンプ機能と血管の抵抗によって決まります。以下のような状態や要因で血圧が高くなるケースがあります。
- 塩分の過剰摂取
- 自律神経の乱れ
- ストレスの蓄積
- 血管の柔軟性低下
- 腎臓の機能低下
血圧に影響を与える要素
心拍出量(心臓が送り出す血液量)と末梢血管抵抗が大きくなると、血圧は上がりやすくなります。血管が硬くなると、血液の流れにくさが増し、結果として血圧が高くなります。
血圧計の正しい測り方
血圧を自宅で測定する習慣をつけると、日常の変化に気づきやすくなります。正しい測定方法が大切です。
- 毎日同じ時間帯(朝起きて排尿後、または就寝前など)に測る
- 腕に合ったサイズのカフを使う
- 腕を心臓の高さに保つ
- 座った状態で1~2分安静にしてから測定する
家庭血圧の意義
診察室で測定する血圧より、家庭で測定する血圧の方が実生活に近い値を得られやすいです。家庭血圧は、一日のうちの変動や環境変化を把握するうえでも役立ちます。
血圧に関わる主な数値と意味
| 項目 | 意味 |
|---|---|
| 収縮期血圧 | 心臓が収縮し血液を送り出すときの血圧 |
| 拡張期血圧 | 心臓が拡張し血液を受け入れるときの血圧 |
| 脈拍数 | 1分間に心臓が拍動する回数 |
| 家庭血圧 | 自宅で毎日決まったタイミングで測定する血圧 |
| 診察室血圧 | 病院の診察室などで測定する血圧 |
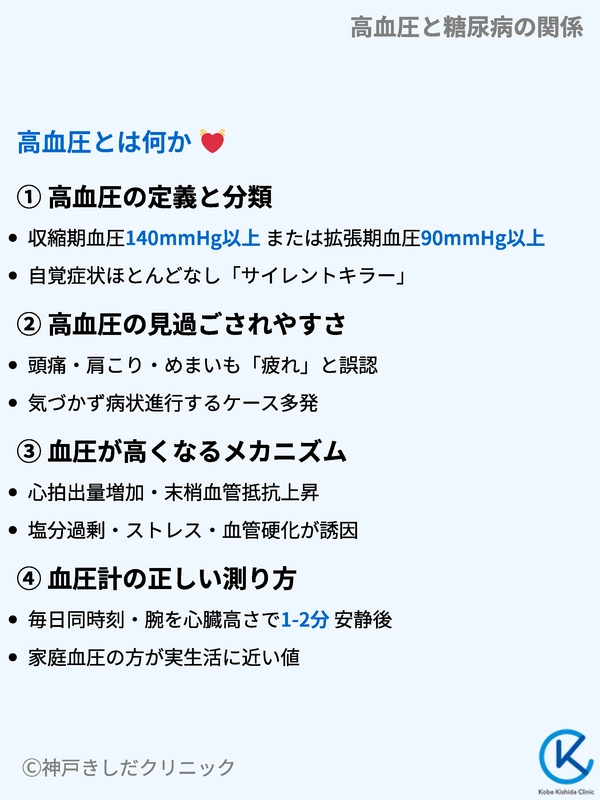
高血圧と糖尿病の関係
高血圧と糖尿病は、生活習慣や体質によって互いを悪化させる可能性があります。両者がなぜ関係しやすいのか、またどのように影響し合うのかを紹介します。
血圧と血糖値は異なる指標ですが、全身の代謝や血管の状態に深くかかわっています。
血圧と血糖値の共通要因
高血圧と糖尿病には以下のような共通した要因があります。
- 肥満や過体重
- 食塩や糖質の過剰摂取
- 運動不足
- 遺伝的な傾向(家族に高血圧や糖尿病がある)
- ストレスの多い生活環境
生活習慣病としての共通点
- 食事バランスの乱れ
- 睡眠不足や不規則な生活
- アルコールの多量摂取
- 喫煙
「血管への負担が大きい」「インスリン抵抗性が高まる」などの共通の問題点があるため、高血圧と糖尿病は同時に発症しやすい状況へ陥ることが多いです。
インスリン抵抗性と高血圧
糖尿病の発症にはインスリン抵抗性の高さが関係します。インスリンが体内できちんと働きにくくなると、血糖値が下がりにくくなります。
同時に、インスリン抵抗性が高まると体内の血管壁にも影響を与え、血圧上昇に関与する物質が増えやすくなるケースがあります。
高血圧が糖尿病を引き起こす可能性
必ずしも高血圧が糖尿病を直接引き起こすわけではありませんが、高血圧の背景にある生活習慣が糖尿病を誘発しやすい傾向は確かに存在します。
塩分過多や肥満、運動不足などが重なると、血管や糖代謝に悪影響が及びやすくなり、結果として糖尿病のリスクが高まります。
高血圧から糖尿病へ発展しやすい人の特徴
- 体重が増えやすく、ウエスト周りの脂肪が多い
- スナック菓子や甘い飲み物などを日常的にとる
- 野菜やタンパク質が不足している
- 定期的な運動をする習慣がない
- 親族に糖尿病患者がいる
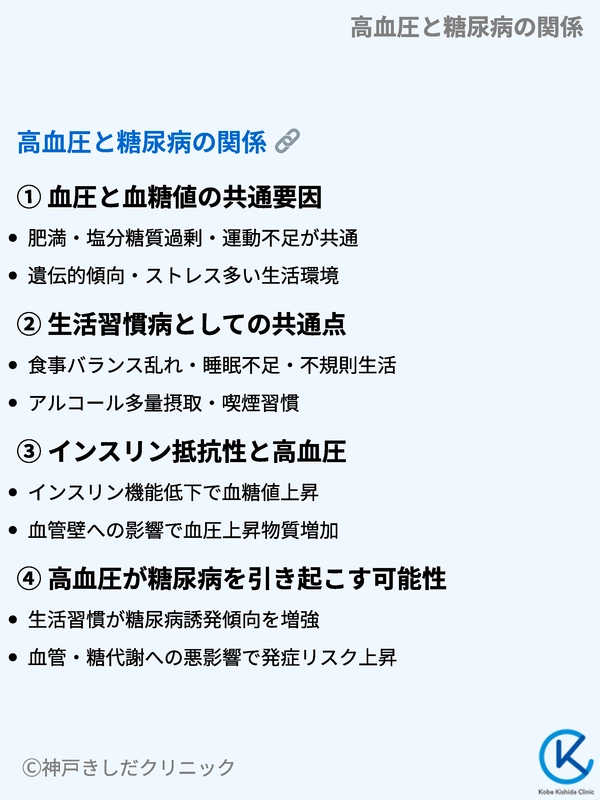
高血圧と糖尿病が重なると起こりやすい合併症
高血圧と糖尿病は、単独でも動脈硬化や血管障害のリスクを高めますが、両方が重なるとリスクはさらに高まります。
どのような合併症が起こりやすいのかを確認していきましょう。早い段階でリスクを把握することが、心身の健康を守るために大切です。
動脈硬化の進行
高血圧は血管にかかる圧力を大きくし、糖尿病は血管の内皮細胞にダメージを与えます。両方の影響が重なると、動脈硬化はさらに進行しやすくなります。
動脈硬化が進むと脳や心臓、腎臓などへの血流が悪くなり、以下の合併症を招きやすくなります。
動脈硬化による主な合併症
| 合併症名 | 特徴 |
|---|---|
| 脳梗塞 | 脳の血管が詰まり、言語障害・運動障害などを起こす |
| 心筋梗塞 | 心臓の血管が詰まり、胸痛や呼吸困難を起こす |
| 狭心症 | 心臓の血管が狭くなり、運動時やストレス時に胸痛が起こる |
| 腎硬化症 | 腎臓の血管が硬くなり、腎機能が低下する |
腎機能への影響
腎臓は血液をろ過して老廃物を排出する重要な臓器です。高血圧による血流量の変化や、糖尿病による血糖値の上昇は、腎臓に大きな負担をかけます。
慢性的に腎臓がダメージを受けると、タンパク尿やむくみが出るなどの症状が表れ、やがて慢性腎不全につながる危険があります。
腎機能低下が起こる仕組み
- 血圧上昇で腎臓の血管が傷つきやすくなる
- 糖尿病で血管の内皮細胞が障害を受けやすい
- ろ過機能が低下し、タンパク質などが漏れ出す
眼疾患(糖尿病網膜症・高血圧性網膜症)
糖尿病網膜症は血糖値が高い状態が長く続くことで、網膜の細い血管がダメージを受ける病気です。
一方、高血圧性網膜症は血管にかかる圧力が大きいことで血管が破れたり、厚くなったりする状態です。
両方が重なると網膜の血流障害は深刻化しやすく、最悪の場合は失明につながるリスクがあります。
目のトラブルに気づくサイン
- 視野の一部がかすむ
- 光がまぶしく感じられる
- 飛蚊症が増えたように感じる
- 視界に黒い点や線がちらつく
血管合併症リスクを把握するために
血管合併症は徐々に進むため、早期発見・早期対策が重要です。
定期的な健康診断や専門医の受診によって、血液検査や尿検査、眼底検査などを行い、自分の血管年齢や臓器状態をチェックする必要があります。
- 健康診断の受診回数:年1~2回
- 病院での定期検査(糖尿病・高血圧連携外来など):3か月~6か月ごと
- 目の検査(眼底検査など):定期的に
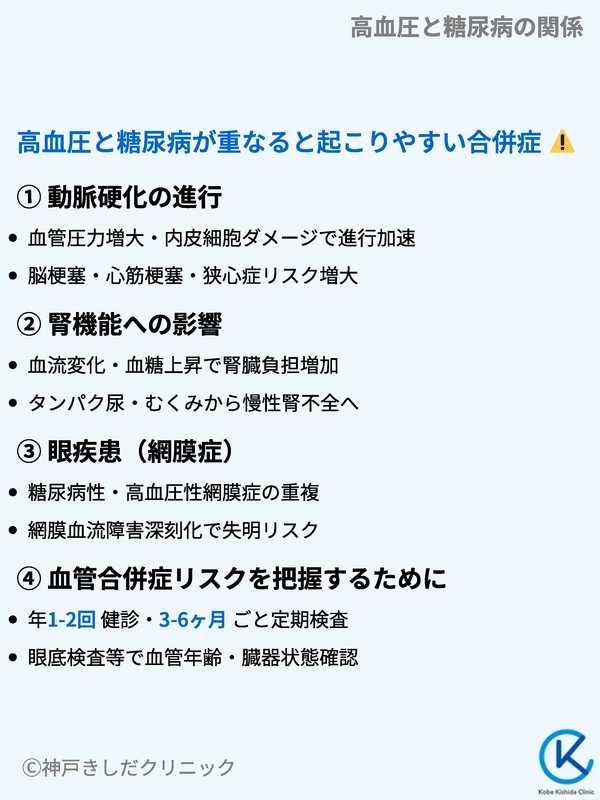
高血圧と糖尿病を予防・管理する生活習慣
高血圧と糖尿病を同時に予防・管理するうえでは、食生活や運動などの日々の習慣が大きく関わります。
ここでは、具体的にどのようなポイントに気をつければいいのかを見ていきましょう。早めに取り組むことで、将来的なリスク低減につながります。
食生活の見直し
食塩と糖質の過剰摂取は血圧や血糖値を上昇させます。外食やインスタント食品、清涼飲料水を多用する人は、以下の点を意識することが大切です。
- 塩分摂取を1日6g未満に抑える
- 野菜や果物でビタミン、ミネラル、食物繊維をしっかり補給する
- 動物性脂肪は控えめにし、魚や大豆製品を活用する
- 甘い飲み物やスナック菓子はなるべく避ける
1日の食事例
| 食事時間 | メニュー例 |
|---|---|
| 朝食 | 玄米のおにぎり、みそ汁、青菜のお浸し、ゆで卵 |
| 昼食 | 雑穀米、鮭の塩焼き(塩分控えめ)、野菜サラダ(ノンオイルドレッシング)、豆腐の味噌汁 |
| 夕食 | 胚芽米、鶏胸肉の蒸し料理、ほうれん草の胡麻和え、具だくさんのけんちん汁 |
| 間食 | 無糖ヨーグルト、ナッツ類 |
適度な運動の習慣
運動不足は肥満やインスリン抵抗性の悪化につながるため、血圧と血糖値の両面から悪影響を及ぼします。ウォーキングや筋力トレーニングなどを生活に取り入れることで、血管や筋肉に良い刺激を与えられます。
効果的な運動習慣のポイント
- 有酸素運動(ウォーキングやジョギング)を週3~5回、1回30分程度
- 筋力トレーニング(スクワットや軽いダンベル運動)を週2~3回
- 通勤時の階段利用や、こまめなストレッチを心がける
- 無理のない範囲から始め、少しずつ運動強度を上げる
体重とウエスト周囲径の管理
体脂肪が過剰になると、高血圧と糖尿病の両方のリスクが上昇します。特に内臓脂肪の蓄積が大きいとインスリン抵抗性が高まりやすいです。
体重管理の目安
- BMI(Body Mass Index)で25未満を目指す
- ウエスト周囲径が男性85cm以上、女性90cm以上の場合は注意が必要
- 体重を急激に落とすのではなく、ゆるやかに減らすことが望ましい
BMIと肥満度の関係
| BMI値 | 判定 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重 |
| 18.5~25未満 | 普通体重 |
| 25~30未満 | 肥満(1度) |
| 30~35未満 | 肥満(2度) |
| 35~40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
ストレス管理と睡眠
ストレスが増えると交感神経が優位になり、血圧は上昇傾向になります。また、睡眠不足が重なるとホルモンバランスが崩れて食欲が増進し、肥満リスクが高まります。
- 毎日7時間前後の質の良い睡眠を確保する
- 自分に合ったストレス解消法(趣味、軽い運動、呼吸法など)を見つける
- スマホやPCなどの電子機器を就寝前に長時間見続けない
- 定期的に気分転換の機会を持つ
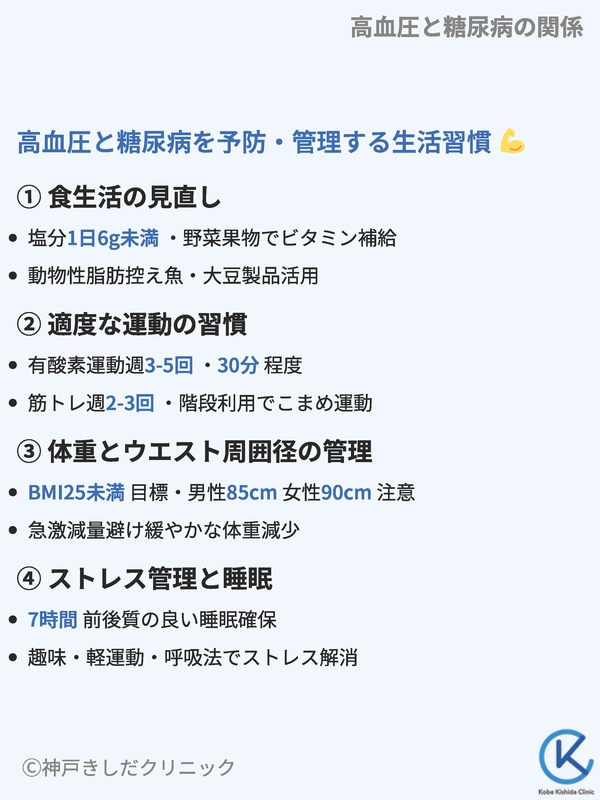
血圧と血糖値を意識した測定・コントロール方法
血圧と血糖値の管理は、健康診断だけでなく自宅でも積極的に行うことが望ましいです。
次に、どのように測定とコントロールを進めるかを紹介します。自分の数値を意識することで、異変に早く気づけます。
血圧測定の活用
前章でも触れましたが、血圧はできる限り毎日同じ条件で測定すると変化を捉えやすくなります。朝と夜の2回測定して、平均値を把握するのも有効です。
血圧測定のメリット
- 自宅血圧の推移がわかる
- 体調の変化(ストレスや睡眠不足など)を数値で確認しやすい
- 測定データを医療機関に提供すれば、治療計画が立てやすい
血糖値測定のポイント
糖尿病の疑いがある人、または血糖値がやや高めと言われたことがある人は、自己血糖測定(SMBG: Self-Monitoring of Blood Glucose)を行うとより正確に状況を把握できます。
糖尿病診断を受けていない人でも、医師や専門家に相談のうえで適宜測定を検討すると良いです。
血糖値を測定するタイミング
- 空腹時(起床後すぐなど)
- 食後2時間後
- 就寝前
血糖値とその目安
| 状態 | 目安値(mg/dL) |
|---|---|
| 空腹時血糖値 | 100未満が望ましい |
| 食後2時間後血糖値 | 140未満が望ましい |
| HbA1c(過去1~2か月の平均血糖) | 5.8%未満が望ましい(医療機関によって基準が異なる場合あり) |
血圧と血糖を同時に記録するメリット
血圧と血糖値を同時に管理することで、自分の生活習慣と数値変動との関連が見えやすくなります。以下のような観点で振り返りができます。
- 運動量が多かった日は、血圧と血糖値の両方が良好だった
- 飲み会の翌日は血圧と血糖値が上がりやすい
- 睡眠時間が短かった翌日は数値が悪化しやすい
記録のポイント
- 日付と時刻を明記
- 食事内容や運動量を簡潔に書く
- 毎週・毎月など一定周期で見返す
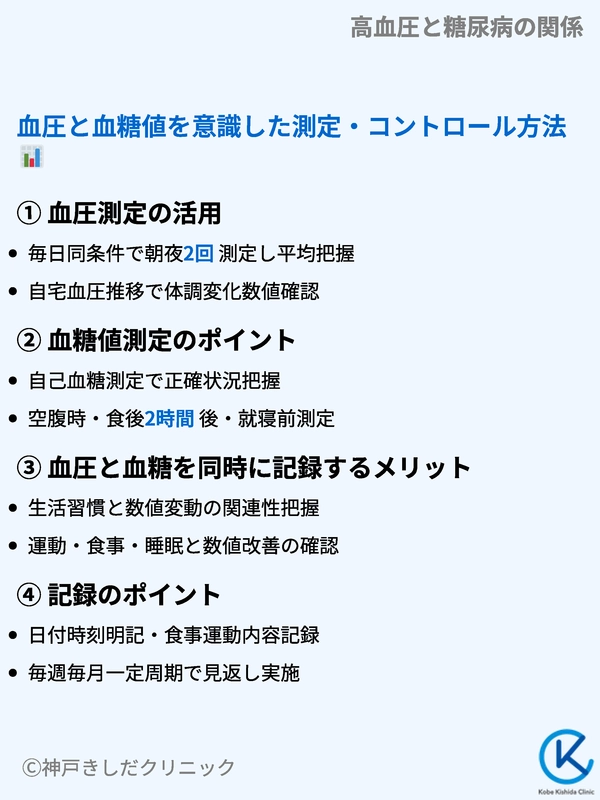
高血圧と糖尿病の薬物治療
生活習慣の改善だけで血圧や血糖値が思うように下がらない場合、医師の判断で薬物治療を始めることがあります。
ここでは、高血圧と糖尿病それぞれの治療薬の概要と、同時に服用する場合の注意点を挙げていきます。
高血圧治療薬の種類
高血圧に対する薬には、血管を拡張するものや利尿作用のあるものなど多様なタイプがあります。
主な高血圧治療薬
| 薬の種類 | 作用の特徴 |
|---|---|
| ACE阻害薬 | アンジオテンシン変換酵素を阻害し、血管を拡張する |
| ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬) | 血管を収縮させる物質の作用を抑制 |
| β遮断薬 | 心拍数や心収縮力を抑え、血圧を下げる |
| Ca拮抗薬 | 血管平滑筋へのカルシウム流入を抑え、血管を拡張する |
| 利尿薬 | 余分な水分を体外に排出し、血液量を減らす |
糖尿病治療薬の種類
糖尿病の場合も、血糖値の下げ方や作用機序によってさまざまな薬があります。インスリン注射を含め、患者さんの状態に合わせて処方が選ばれます。
主な糖尿病治療薬
| 薬の種類 | 作用の特徴 |
|---|---|
| ビグアナイド薬 | 肝臓での糖新生を抑え、筋肉での糖利用を促す |
| スルホニル尿素薬(SU薬) | 膵臓のβ細胞を刺激してインスリン分泌を促進する |
| DPP-4阻害薬 | インクレチンの分解を抑え、インスリン分泌やグルカゴン抑制を高める |
| GLP-1受容体作動薬 | インクレチンを模倣し、インスリン分泌を促進し食欲を抑える |
| SGLT2阻害薬 | 腎臓での糖の再吸収を抑えて尿中に糖を排泄させる |
| インスリン製剤 | 直接インスリンを補う |
高血圧と糖尿病薬の飲み合わせの注意
複数の薬を服用する場合は、相互作用によって思わぬ副作用が出ることがあります。医師や薬剤師に以下の情報を正確に伝えることが大切です。
- 現在服用している薬の種類と用量
- サプリメントや漢方薬など、他に摂取しているもの
- アレルギーや副作用の既往歴
治療薬と生活習慣の両立
薬は血圧や血糖値をコントロールする強力な手段ですが、生活習慣をなおざりにすると、薬の効果を十分に引き出せません。
薬物治療を補う形で、食事や運動、睡眠、ストレスケアを継続的に行うことが必要です。
- 飲み忘れを防ぐため、服用スケジュールを可視化
- 自己判断で薬をやめず、医師に相談
- 処方通りの時間やタイミングを守る
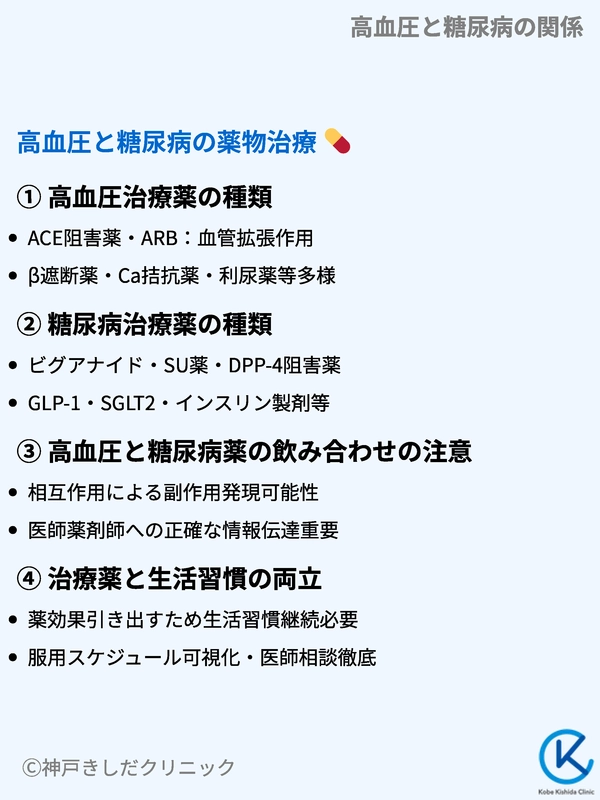
医療機関の受診タイミングと専門医の役割
高血圧と糖尿病のリスクが高い場合、早めの段階で医療機関を受診して対策をとることが望ましいです。どんなタイミングで受診すべきか、どの専門医が適切かを紹介します。
受診の目安と症状
高血圧も糖尿病も症状がわかりにくいため、定期的な健診結果や以下のような体調変化を指標にして受診を考えてください。
- 血圧が連日140/90mmHgを上回っている
- 空腹時血糖値が100mg/dLを超えている日が続く
- 口渇や多尿、体重減少などの糖尿病疑いの症状がある
- 動悸や息切れ、微熱のような体調不良が続く
気になる症状と考えられる原因
| 症状 | 考えられる原因や病気 |
|---|---|
| 起床時の激しい頭痛 | 高血圧による脳圧変化 |
| トイレが近い、喉が渇きやすい | 血糖値上昇による多尿や脱水 |
| むくみ、タンパク尿の増加 | 腎臓への負担(高血圧・糖尿病の進行) |
| 目のかすみ | 網膜症の進行 |
糖尿病内科や循環器内科などの専門
高血圧は主に循環器内科、糖尿病は内分泌代謝内科や糖尿病内科などが専門分野です。
最近では生活習慣病を総合的に診るクリニックが増えているため、一か所で高血圧と糖尿病の両方を管理できる体制も整いつつあります。
- 糖尿病内科:血糖値管理、合併症予防、インスリン治療など
- 循環器内科:血圧管理、動脈硬化の検査や治療など
受診時に準備しておくと便利な情報
事前準備として以下の情報を整理しておきましょう。
- 家庭血圧と血糖値の記録
- 食事や運動の記録・生活パターン
- 服用中の薬やサプリメントの一覧
- 健診結果、健康診断の履歴
早期受診によるメリット
早期に受診することで、病状を進行させずに適切な治療計画を立てやすくなります。
特に糖尿病では、血糖管理を厳密に行うほど合併症の進行を遅らせられる可能性が高まります。高血圧と糖尿病を抱える方は、一度専門医やクリニックで総合的なチェックを受けるのがおすすめです。
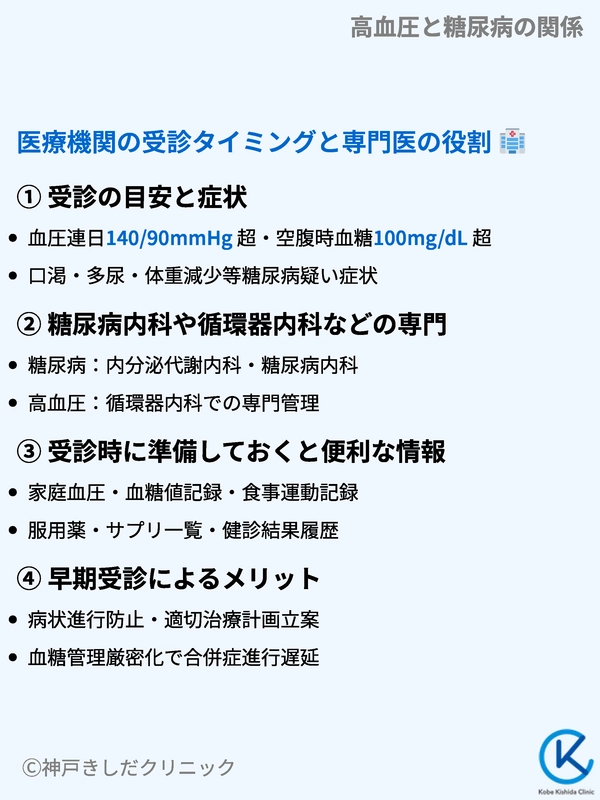
糖尿病内科クリニックを上手に活用する
高血圧と糖尿病について不安や疑問を持つ人は多く、専門の医療機関を活用することで的確なアドバイスや治療を受けられます。
糖尿病内科クリニックで受けられる主なサポートや受診のメリットについてまとめました。
糖尿病内科クリニックの特徴
糖尿病内科では、血糖値管理はもちろん、合併症の検査や生活指導を一貫して行うところが多いです。
- 血糖管理の専門知識と検査設備が整っている
- 管理栄養士が個別の食事指導を行う
- 運動療法やフットケアなど、多方面からサポートできる
糖尿病内科で期待できるサポート
| 支援の種類 | 内容 |
|---|---|
| 栄養指導 | 食事バランスやカロリー計算、塩分・糖質制限の仕方などを丁寧に指導 |
| 運動指導 | 体力や目標に合わせた運動メニューの提案 |
| 服薬管理 | 血圧・血糖の状態に合わせた処方と副作用の確認 |
| フットケア | 糖尿病に多い足トラブルを防ぐための点検や指導 |
高血圧へのアプローチも同時に可能
糖尿病内科の多くは、血圧を含む循環器系のチェックも重視しています。
血糖値だけでなく、血圧やコレステロール値、腎機能検査などを定期的に行い、合併症を早期発見しやすくなります。さらに、糖尿病内科から循環器専門の医療機関への紹介もスムーズです。
疑問や不安を相談しやすい環境
専門医やスタッフが常駐しているため、患者さんの不安や質問に対して、医学的知識に基づくアドバイスを受けやすいです。
特に糖尿病と高血圧は日常生活との結びつきが強いので、細かな相談ができる環境は大きなメリットです。
- 「食事制限を続ける自信がない」などのメンタル面
- 「運動をする時間を確保しにくい」などの生活リズム面
- 「仕事の都合で薬を飲み忘れやすい」などの実務面
定期受診で合併症リスクをチェック
糖尿病内科クリニックでは、一定の間隔で血液検査・尿検査・眼底検査などを実施し、合併症の兆候について早期発見に努めています。
高血圧についても、家庭血圧との比較や24時間血圧計測(ホルター血圧計)など、より詳細な検査を行うケースもあります。
- 定期的な検査を受けることで、日々の生活習慣が数値に反映されるのが分かる
- 異常が見つかれば早期に対処し、重症化を防ぐ
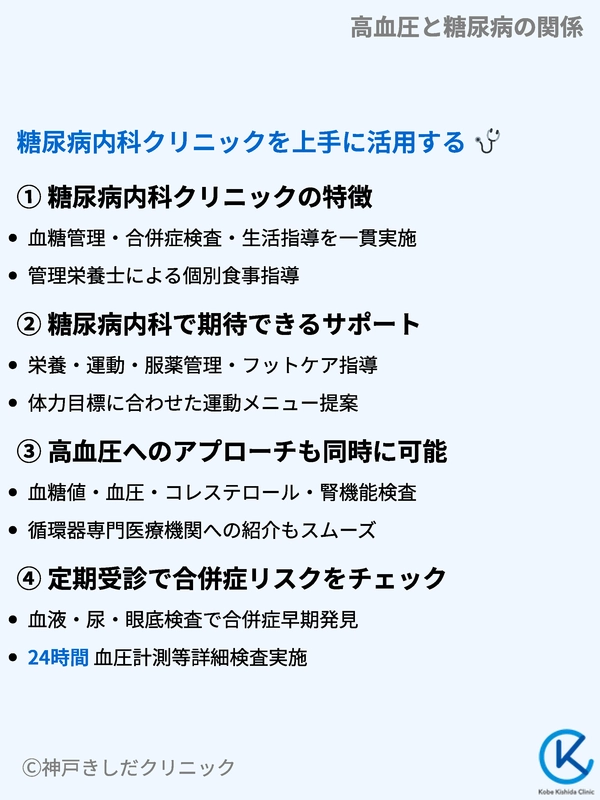
まとめ~高血圧と糖尿病を理解し、早めの対策を
高血圧と糖尿病は、単独でも健康リスクが高い病気ですが、同時に抱えると合併症を含めて多くの問題が生じやすくなります。
生活習慣の改善は血圧と血糖値の両方に良い影響を与え、さらに定期的な受診や検査によって進行を防ぎやすくなります。
少しでも気になる症状や数値があるなら、早めに専門医へ相談し、自分に合った対策を取ることが重要です。
日常生活で意識したいポイント
- 塩分や糖質を控え、バランスのよい食事をとる
- 適度な有酸素運動や筋力トレーニングを続ける
- 血圧や血糖値を定期的に記録し、変化を把握する
- ストレスや睡眠不足を避け、体を休ませる時間を確保する
- 気になる数値や症状がある場合は、早めに糖尿病内科や循環器内科などを受診する
上記の取り組みを習慣化することで、高血圧と糖尿病の進行予防だけでなく、健康的な体づくりにもつながります。自分や家族の健康管理のために、まずはできることから始めてみてください。
糖尿病を知ろう
当院(神戸きしだクリニック)への受診について
気になる症状があり糖尿病検査をご希望の方は、当院の糖尿病内科で対応させていただきます。経験豊富な専門医による丁寧な診察と、充実した検査機器による精密検査を提供しています。
糖尿病内科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |
| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |
| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |
| 月 | – | 〇 |
| 火 | 〇 | 〇 |
| 水 | – | 〇 |
| 木 | 〇 | – |
| 金 | – | 〇 |
| 土 | 〇 隔週 | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |
検査体制
- 血糖値検査(随時血糖・空腹時血糖)
- HbA1c検査
- 経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)
- 尿検査(尿糖・尿蛋白)
- 血液検査(脂質・肝機能・腎機能など)
など、必要に応じた検査を実施いたします。網膜症の精査や詳細な合併症検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など専門医療機関と連携して対応いたします。
予約・受診方法
当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約
お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。
▽ クリック ▽



