糖尿病と深い関係があるといわれる脂質異常症は、コレステロールや中性脂肪などの脂質バランスが乱れる状態です。
健康診断や血液検査で「コレステロールが高い」と指摘されたものの、自覚症状が乏しく受診のきっかけをつかめない方も多いです。
実は、脂質異常症のコントロールが不十分だと、糖尿病のリスクが高まる可能性があります。ここでは脂質異常症と糖尿病の関連性を踏まえ、症状や診察のポイントをわかりやすくお伝えします。
脂質異常症の症状がある方、コレステロール値が気になる方へ。脂質異常症と糖尿病は密接に関連しており、一方の病気があると他方のリスクも高まるため早期発見と予防が重要です。
神戸きしだクリニックの糖尿病内科では、両疾患の関連性を踏まえた専門的な診察と個別のアドバイスを提供しています。将来の合併症リスクを減らすため、お気軽にご相談ください。詳しくはこちら
この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長
医学博士
日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医
日本核医学会認定 核医学専門医
【略歴】
神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)
脂質異常症とは
脂質異常症は、血液中のコレステロールや中性脂肪の値が基準から外れた状態です。
以前は「高脂血症」と呼ばれていましたが、必ずしも数値が高いだけではなく、低すぎる場合も含めて脂質のバランスが乱れた状態を指すため、現在では脂質異常症という呼び名が使われています。
気づかないうちに動脈硬化が進み、脳や心臓のトラブルを招くリスクが高まることもあり、生活習慣の見直しや早めの受診が重要です。
脂質異常症の定義と背景
血液検査で測定するLDL(悪玉)コレステロール、HDL(善玉)コレステロール、中性脂肪(トリグリセリド)などの値が基準から外れている状態を脂質異常症と呼びます。
以前は「高脂血症」という名称が使われましたが、脂質の構成要素全体の乱れを考慮する意味で呼称が変わりました。
現代では食事の欧米化や運動不足などによって、多くの人がリスクを抱えています。
日本人に多い理由
日本人には体質的に糖分や脂質を代謝する力が弱い人が多いといわれます。
加えて、食事内容が近年大きく変化し、外食やインスタント食品などを選ぶ機会が増えました。主菜や副菜のバランスが崩れやすく、脂質の摂取が過多になる傾向があります。
また、デスクワークなど活動量の少ない生活を送る人が増えたことも、脂質異常症になりやすい一因と考えられます。
自覚症状の少なさ
脂質異常症は早期にはほとんど症状がなく、検診などでたまたま指摘されるケースが多いです。
血液検査の結果に不安を持っていても、はっきりした体調不良を感じないために、受診を先延ばしにする方が多いと考えられます。
しかし、症状が目立たなくても血管の内側では動脈硬化が進行しやすく、将来的に脳卒中や心筋梗塞などの合併症が起こる可能性があります。
生活習慣病との共通点
脂質異常症と高血圧、糖尿病などは「生活習慣病」と総称され、同時に合併するケースが少なくありません。いずれも過度のカロリー摂取と運動不足、ストレスなどが関係するといわれます。
複数のリスクを抱えている場合、動脈硬化がさらに加速する可能性があり、重大な合併症への経過をたどる恐れもあるため、生活習慣全体の改善が求められます。
脂質異常症に関連する主な検査項目と基準値のめやす
| 項目 | 基準値のめやす | 主な役割 |
|---|---|---|
| LDLコレステロール | 60〜119 mg/dL | 動脈硬化を進行させやすい悪玉 |
| HDLコレステロール | 40 mg/dL以上 | 血管内の余分なコレステロール回収 |
| 中性脂肪 | 30〜149 mg/dL | エネルギー源として重要だが過剰は危険 |
| 総コレステロール | 140〜199 mg/dL | LDL・HDLを合わせた大まかな指標 |
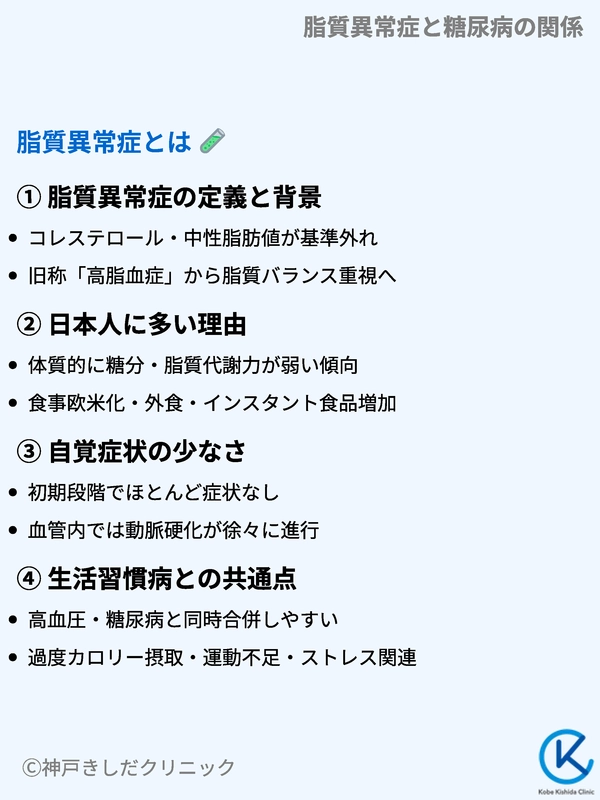
脂質異常症の原因と種類
脂質異常症を起こす原因は生活習慣や遺伝など、複数の要因が複雑に絡み合っています。特に食生活や運動不足、喫煙、過度の飲酒などは脂質バランスを乱す大きな要因になります。
遺伝的な要素で脂質の代謝がうまくいかないケースもあるため、一概に生活習慣だけが原因とは限りません。
原因の分類
脂質異常症を大きく分けると、原発性と続発性の2つがあります。
原発性は主に遺伝的素因に基づくもので、親から子へ受け継がれる体質的な要素が大きいです。続発性は肥満や糖尿病など他の疾患、あるいは薬剤の影響などで脂質異常を起こす場合を指します。
原発性脂質異常症の特徴
原発性の場合、若いころからLDLコレステロールが高めに出るなど、特徴的なパターンがあります。
遺伝性の脂質異常症は症状が顕著なケースもあり、早い段階で受診すると治療の選択肢を検討しやすくなります。
家族や近親者で心筋梗塞や脳卒中の既往が多い方は要注意です。
続発性脂質異常症の背景
続発性の場合、糖尿病や甲状腺機能低下症、ネフローゼ症候群などの基礎疾患が原因になります。
また、一部の降圧薬や経口避妊薬、利尿薬などによって一時的に脂質代謝が乱れるケースもあります。
基礎疾患や服薬の状況を確認しつつ、医師が総合的に判断します。
食習慣との関連
高カロリー食や不規則な食生活、外食の頻度が多いと脂質異常症のリスクは高まります。
甘いお菓子や清涼飲料水など、糖質が過剰な飲食も中性脂肪を増やす一因となります。
さらに満腹になるほど摂取してしまう大盛り料理や深夜の間食など、摂取カロリーが消費カロリーを大幅に上回る状態が続くと、やがて脂質異常症に陥る可能性が高まります。
脂質異常症の主な原因と背景
| 因子 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 遺伝 | 家族性高コレステロール血症など | 若年期から値が高めになることが多い |
| 生活習慣 | 不規則な食事、飲酒、喫煙、運動不足 | 動脈硬化リスクがまとめて高まりやすい |
| 基礎疾患 | 糖尿病、甲状腺機能低下症など | 疾患の管理が不足していると脂質も乱れやすい |
| 薬剤の影響 | 降圧薬、経口避妊薬、利尿薬など | 別の目的で使う薬でも脂質に影響を与える場合がある |
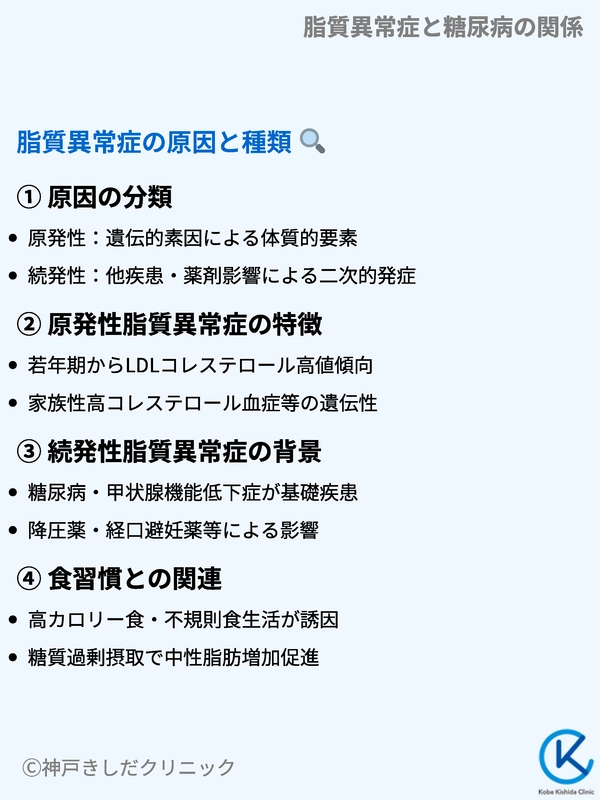
脂質異常症と糖尿病の関連
脂質異常症を放置すると糖尿病になるわけではありませんが、両者が同時に存在すると動脈硬化が進展しやすいなど、相乗的なリスクを生じる場合があります。
実際に、糖尿病患者の多くが脂質異常症を合併しているといわれ、糖尿病に発展する前段階で脂質代謝に異常がみられるケースも少なくありません。
インスリン抵抗性と脂質異常症
糖尿病の発症にはインスリン抵抗性が深く関わります。インスリン抵抗性が高い状態では血糖値を下げる力が弱まるだけでなく、脂質代謝にも悪影響を及ぼします。
具体的には中性脂肪が増え、HDLコレステロール(善玉)が低下する傾向があります。脂質異常症が糖尿病のリスクと重なり合って、血管障害が促進される恐れがあります。
代謝シンドロームとの関係
肥満、高血圧、脂質異常症、糖尿病などが重複した状態を「代謝シンドローム」と呼ぶことがあります。
腹部肥満があり、血圧や血糖、脂質のいずれか複数が基準を超える場合には、動脈硬化性疾患へのリスクがより大きくなります。
代謝シンドロームは生活習慣の影響が大きいとされ、いかに早期から食事や運動の見直しを始めるかが要点になります。
代謝シンドロームに該当しやすい目安
| 項目 | 男性の基準 | 女性の基準 |
|---|---|---|
| 腹囲 | 85cm以上 | 90cm以上 |
| 血圧 | 130/85mmHg以上 | 130/85mmHg以上 |
| 空腹時血糖 | 100mg/dL以上 | 100mg/dL以上 |
| 中性脂肪またはHDL-C | TG 150mg/dL以上 または HDL-C 40mg/dL未満 | TG 150mg/dL以上 または HDL-C 50mg/dL未満 |
血管合併症のリスク
脂質異常症と糖尿病が合併すると、血管障害のリスクがさらに高まります。
糖尿病では高血糖状態によって血管の内皮機能が損なわれるうえ、脂質異常症によってLDLコレステロールや中性脂肪が増えると動脈硬化が早期に進行する可能性があります。
血管合併症が心臓や脳に及ぶと狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などの重大な疾患につながる恐れがあります。
糖尿病の初期段階と脂質異常症
血糖値がやや高めの段階(境界型糖尿病)でも、脂質が乱れている例は珍しくありません。
インスリン分泌量が増えることで血糖値はある程度抑えられていても、中性脂肪やLDLコレステロールが増加している場合、すでに代謝負担が増大していると考えられます。
この状態を放置すると、将来的に本格的な糖尿病へ進む可能性が上昇します。
境界型の段階から注意すべきポイント
- 普段から空腹時血糖値が100~125mg/dL前後で推移
- LDLコレステロールや中性脂肪がわずかに上昇している
- BMIの増加や血圧の上昇がみられる
- 偏った食習慣や運動不足の自覚がある
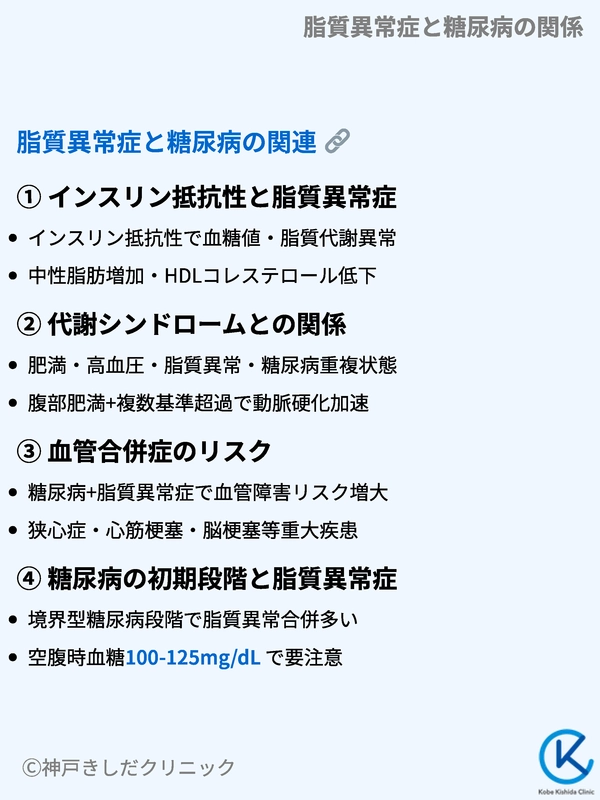
脂質異常症の症状と合併症のリスク
脂質異常症は初期段階では目立った症状があまりなく、症状に気づいたときには動脈硬化がだいぶ進んでいる可能性があります。
症状が軽微なまま進行し、やがて重大な合併症を引き起こす恐れがあるため、定期的な健診や血液検査の活用が大切です。
症状が乏しい理由
脂質異常症は血液中の脂質バランスが崩れている状態ですが、痛みや発熱、倦怠感などの症状を引き起こすわけではありません。
動脈硬化が進行してから初めて、胸の痛みや息切れ、手足の冷えなどに気づくケースもあります。
逆にいうと、こうした症状が出た段階では既に血管に負担がかかり、治療に時間がかかる恐れがあるのが現実です。
動脈硬化による合併症
動脈硬化が進むと、脳や心臓、腎臓などの重要な臓器に血流障害が起こります。特に脳血管が詰まって脳梗塞が発症すると、片麻痺や言語障害など後遺症が残ることがあります。
心臓の血管が狭くなると狭心症や心筋梗塞が生じ、命にかかわる事態に至る場合があります。腎臓に影響が及ぶと慢性腎不全を生じ、血液透析などの大きな負担が加わります。
皮膚症状の例
まれにコレステロールの値が非常に高い場合、アキレス腱や肘、膝の周囲に黄色腫と呼ばれる隆起ができることがあります。
これは脂質が皮下組織に沈着して起こるもので、周囲が黄色っぽく見えるのが特徴です。
また、まぶたの周辺にキサンテラズマと呼ばれる黄色味を帯びた隆起が生じることもあり、見た目の違和感で受診を検討する人もいます。
脂質異常症にともなう合併症
| 合併症 | 関連する主な病変 | 発症時の症状や問題 |
|---|---|---|
| 脳血管障害 | 脳梗塞、脳出血など | 半身麻痺、言語障害、意識障害など |
| 冠動脈疾患 | 狭心症、心筋梗塞 | 胸痛、動悸、冷や汗、ショック状態 |
| 末梢動脈疾患 | 下肢虚血など | 足のしびれ、歩行困難、潰瘍など |
| 慢性腎臓病 | 糸球体の障害 | むくみ、倦怠感、腎不全の進行など |
病気の進行を防ぐポイント
脂質異常症や糖尿病が原因で発症する合併症の多くは、食事や運動を中心とした生活習慣の改善によってリスクを軽減できます。
検査結果で危険因子が確認された段階で、なるべく早く生活面の対策をスタートしたいところです。医療機関で定期的に受診し、経過観察を続けていくことも欠かせません。
合併症リスクを抑えるために
- 血液検査の結果を把握し、値の変動を定期的に確認
- 適度な有酸素運動(ウォーキングや軽いジョギングなど)を継続
- アルコールや喫煙を控え、ビタミンや食物繊維を多く含む食事を意識
- ストレスケアや十分な睡眠をとり、ホルモンバランスを整える
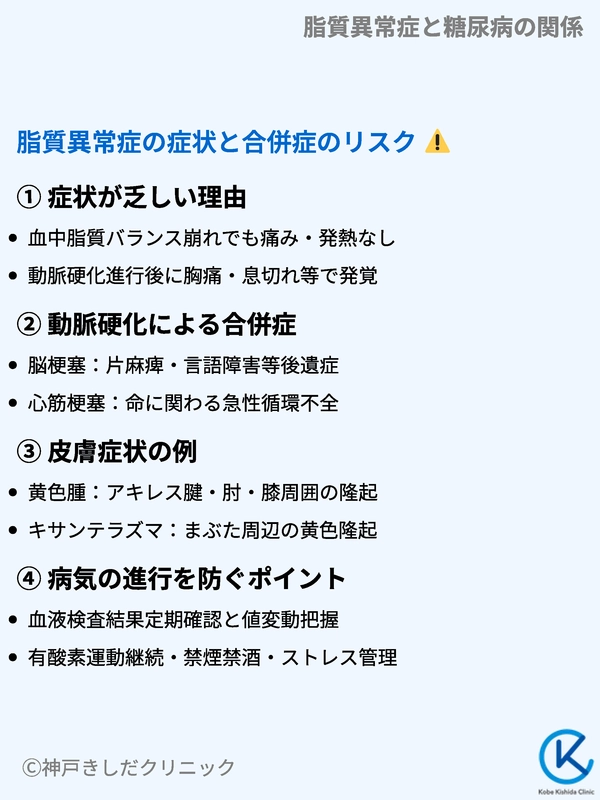
脂質異常症の検査と診断
脂質異常症の診断には血液検査が欠かせません。
主にLDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、総コレステロールなどを測定し、それぞれの値が基準範囲からどの程度外れているかを確認します。
必要に応じて二次的な原因(他の疾患や薬剤)を探るための追加検査を行う場合もあります。
血液検査のポイント
健診などで脂質の値が基準範囲から外れていた場合、医師は生活習慣や家族歴、基礎疾患の有無を確認しながら診断を進めます。
空腹時と食後では血液中の脂質濃度が変化するため、空腹時採血の条件で測定した値がより正確といわれます。
中性脂肪は特に食事の影響を受けやすいため、採血前の食事時間を確認することが大切です。
生活習慣や服薬状況の問診
診断時には食事内容や運動習慣、飲酒や喫煙の有無などをお聞きします。基礎疾患の有無や服薬状況も重要です。
例えば、糖尿病の治療薬や利尿薬などを服用している場合、脂質のバランスに影響が及ぶケースもあるので、正確に申告すると診断がスムーズに進みます。
脂質異常症の診断を考えるうえで確認したい項目
| チェック項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 食習慣 | 高脂質・高糖質の摂取量、外食・夜食の頻度 |
| 運動習慣 | 運動の種類や頻度、日常的な活動量 |
| 飲酒・喫煙 | 飲酒量・頻度、喫煙本数 |
| 既往歴・家族歴 | 糖尿病、高血圧、動脈硬化性疾患の有無など |
| 服薬状況 | 降圧薬、経口避妊薬、糖尿病薬など |
追加検査の例
血液検査だけでなく、エコー検査やCT、MRI、心電図、血管年齢測定など、動脈硬化の進行度合いを確かめる検査を行う場合があります。
必要に応じて負荷心電図やホルモン検査などを追加して、他の疾患の有無を判定することも選択肢に含まれます。
早期発見のメリット
脂質異常症を早期発見すれば、食事や運動などの習慣を整えやすくなります。
薬物治療が必要となるケースでも、値が軽度のうちに改善を図ることで、合併症リスクを最小限に抑えられる可能性があります。
定期健診をしばらく受けていない方や、数値が高いと指摘されたものの放置している方は、早めに医療機関を受診することが望ましいです。
早期検査のメリット
- 自覚症状のない段階でリスクを把握できる
- 生活習慣の改善によって薬の使用を抑えやすい
- 他の隠れた疾患を同時に見つけられる可能性
- 将来的な動脈硬化の進行を遅らせるチャンスが広がる
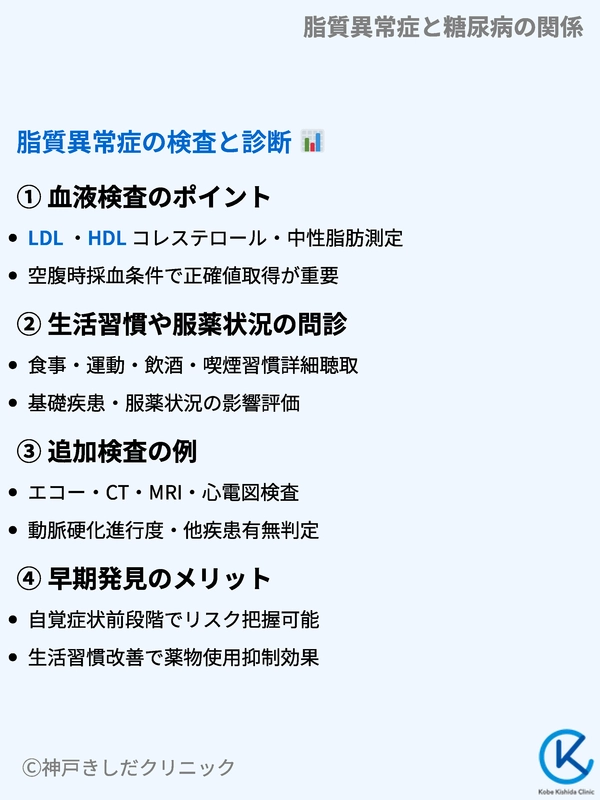
脂質異常症の治療法
脂質異常症の治療は、主に生活習慣の改善と薬物治療の2本柱で進めます。
生活習慣を見直すだけでも大幅に数値が改善するケースは多く、必要に応じてスタチンなどの脂質低下薬を使うことがあります。
合併症の予防やリスク管理の観点から、定期的なチェックが重要です。
食事療法と栄養バランス
脂質異常症の治療で最も大切とされるのが食事療法です。
過度な食事制限ではなく、バランスのよい栄養摂取を意識して、摂取カロリーと消費カロリーのバランスを保ちます。
揚げ物や脂っこい肉よりは、魚や野菜を中心にしたメニューを増やすことが基本です。糖質の過剰摂取も中性脂肪増加につながるため、甘い飲料や菓子類を控えめにします。
食事療法のポイント
| 食材のグループ | 具体的な例 | おすすめの摂り方 |
|---|---|---|
| 野菜・海藻類 | ブロッコリー、ほうれん草、わかめ | 温野菜や和え物で大量に摂取しやすい |
| 魚介類 | サバ、サンマ、イワシ、サケ | 青魚のEPAやDHAはコレステロール低下に寄与 |
| 大豆製品 | 豆腐、納豆、豆乳 | タンパク質源として活用しやすい |
| 良質な油 | オリーブオイル、なたね油 | 揚げ物よりも炒め物や煮物に利用 |
| 果物 | みかん、りんご、ベリー系 | 食物繊維とビタミンを効率的に補給 |
運動療法
軽いウォーキングやジョギング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動を継続すると、中性脂肪の減少やHDLコレステロールの増加が期待できます。
筋トレも効果的で、筋肉量を増やすことで基礎代謝が高まり、エネルギー消費量のアップにつながります。日々の生活に取り入れやすい運動を選んで続けるのが良い方法です。
運動習慣の導入例
- 通勤の一部区間を徒歩や自転車に切り替える
- エレベーターやエスカレーターの使用を減らす
- テレビ視聴中に軽い筋トレやストレッチを取り入れる
- 休日に散歩やジョギングを楽しむ
薬物治療
スタチン製剤(HMG-CoA還元酵素阻害薬)は、LDLコレステロールを下げる代表的な薬です。
そのほかにもフィブラート系薬剤やエゼチミブなど、患者の脂質パターンや合併症の有無に応じて処方が変わります。
薬物治療を開始した場合でも、生活習慣の改善との併用が欠かせません。薬だけに頼るのではなく、日常習慣全体を整えることが肝心です。
主な脂質低下薬の種類と特徴
| 薬の種類 | 代表例 | 主な作用 |
|---|---|---|
| スタチン製剤 | ロスバスタチンなど | LDLコレステロールの合成を抑制し低下を促す |
| フィブラート系 | フェノフィブラートなど | 中性脂肪を主に低下させ、HDLを増やす |
| エゼチミブ | エゼチミブ | 腸管でのコレステロール吸収をブロック |
| PCSK9阻害薬 | エボロクマブなど | LDL受容体を増やしてLDLを効率的に除去する |
継続的なフォローアップ
治療を開始したあとも、定期的に血液検査を行い経過を見守ります。脂質の値だけでなく、血圧や血糖値、体重の推移を含めて総合的に判断することが大切です。
医師や栄養士との相談を重ねながら、無理なく続けられる治療と生活習慣の管理を行うと、長期的に良好な状態を維持しやすくなります。
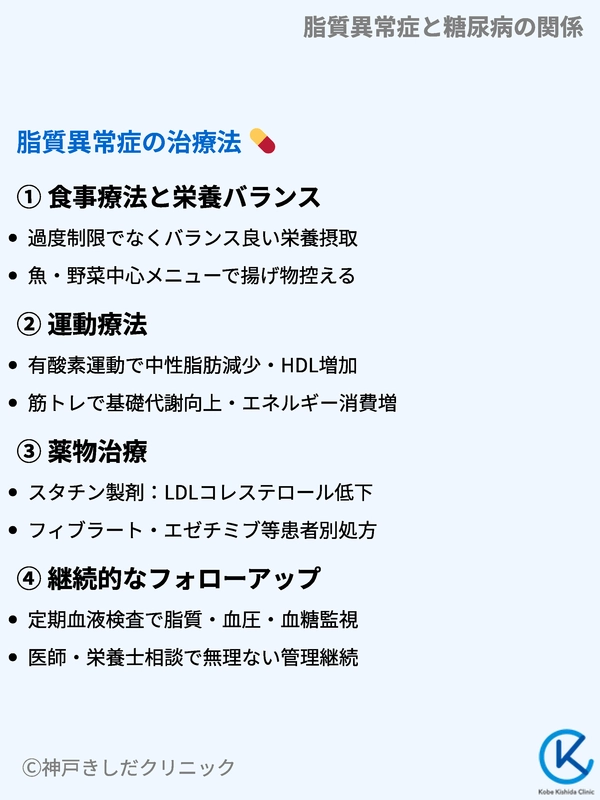
予防と生活習慣の見直し
脂質異常症を予防するには、バランスのとれた食事と適度な運動が基本です。日常のちょっとした工夫が、長期的には動脈硬化のリスクを抑える重要な手立てになります。
また、仕事や家事で忙しい方でも取り入れやすい方法を見つけ、習慣化することが鍵となります。
食生活の工夫
野菜を先に食べて血糖値や中性脂肪の急上昇を抑える「ベジファースト」や、穀物のなかでも玄米や全粒粉など食物繊維が豊富なものを選ぶ工夫などが効果的です。
甘い物が好きな方は、果物など自然由来の甘味を上手に使い、お菓子や清涼飲料水を減らすことが賢明といえます。
日常で摂取しやすい食物繊維が多い食材
| 食材 | 可食部あたりの食物繊維量の目安 | 一緒に摂りたい栄養素 |
|---|---|---|
| ごぼう | 約5.7g/100g | カリウム、マグネシウム |
| きのこ類 | 約2.7g/100g | ビタミンB群、ミネラル |
| 玄米 | 約3.0g/100g | ビタミンB1、鉄分、亜鉛 |
| アーモンド | 約10.9g/100g | 良質な脂質、ビタミンE |
運動不足解消のヒント
激しい運動をいきなり始めるのではなく、まずは歩数を増やすなど身近な取り組みから始める方法が現実的です。
心拍数が少し上がる程度の運動を週に150分ほど行うと、脂質代謝の改善が期待できます。筋力維持のためにスクワットや腕立て伏せなどの筋トレを追加しても良いでしょう。
日常活動を増やすコツ
- エスカレーターより階段を優先する
- バスや電車をひと駅早く降りて歩く
- こまめに姿勢を正し、腹筋を意識する
- テレビコマーシャルの間に軽いストレッチ
ストレスケアと睡眠
精神的なストレスや睡眠不足はホルモンバランスを乱し、食欲を抑えにくくしたり、インスリンの働きを低下させたりする恐れがあります。
忙しい中でもリラックスできる時間をつくったり、寝る前のスマホ使用を控えるなど、睡眠の質を向上させる工夫が望ましいです。
定期健診の活用
自覚症状がなくても、年に1回程度は健診を受け、血液検査の結果を確認することが大切です。基準値を少し超えている段階で行動を起こせば、大きな病気を回避できる可能性が上がります。
忙しくて病院に行く余裕がない方でも、自治体が行う健康診断や企業健診などを活用して、数値をチェックすることをおすすめします。
健診項目とチェックすべきポイント
| 検査項目 | 確認すべき値や範囲 | 意識する生活習慣 |
|---|---|---|
| 血圧 | 130/85mmHg未満が望ましい | 塩分制限、適度な運動 |
| 空腹時血糖 | 99mg/dL以下が望ましい | 糖質の摂り過ぎに注意 |
| HbA1c | 5.6%以下が望ましい | 食後の血糖管理、継続的な血糖測定 |
| LDLコレステロール | 60~119mg/dLが望ましい | 揚げ物、脂質の多い食材の摂取頻度の調整 |
| 中性脂肪 | 30~149mg/dLが望ましい | 甘味料やアルコールを控えめに |
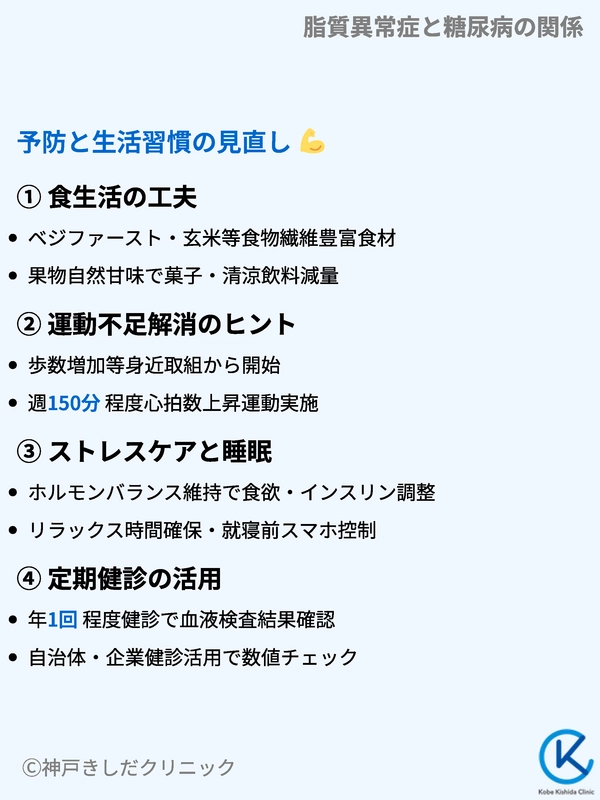
受診のタイミングと糖尿病内科の役割
脂質異常症が気になる方や、糖尿病の疑いがある方は、まず医療機関を受診して血液検査を受けると安心です。
糖尿病内科では血糖管理だけでなく、生活習慣病全般の相談も可能です。日常生活でのアドバイスや、他科との連携による合併症の早期発見が期待できます。
こんな場合は受診を検討
- 健診でLDLコレステロールや中性脂肪が基準値を超えている
- 血圧や空腹時血糖値も同時に高めである
- 家族に心臓病や脳卒中の既往が多く、遺伝的リスクを疑う
- 肥満がなかなか改善せず、食事制限や運動だけでは管理が難しい
- すでに糖尿病で治療中だが、脂質の値も高くなってきている
クリニックでできること
糖尿病内科では、血糖値やHbA1cだけでなく、脂質や肝機能、腎機能など多角的な検査を実施します。
結果に基づき、生活習慣の指導や薬物治療を行い、動脈硬化や合併症のリスクを抑えるためのアドバイスを受けられます。
管理栄養士との連携を行うクリニックであれば、食事療法を具体的にサポートできるメリットもあります。
糖尿病内科のサポート
| サポート内容 | 具体的な取り組み |
|---|---|
| 血糖管理 | 血糖値やHbA1cの測定、インスリン分泌能の評価 |
| 脂質管理 | LDLコレステロールや中性脂肪の定期測定 |
| 生活習慣アドバイス | 管理栄養士や看護師による食事・運動指導 |
| 他科連携 | 循環器科や腎臓内科、眼科など必要に応じた紹介 |
かかりつけ医との連携
糖尿病内科に限らず、かかりつけ医に定期的に通院している方は、脂質異常症も合わせて相談してみるのが良い手段です。
大病院より気軽に通いやすく、血液検査や継続的なフォローを一括して行える利点があります。必要に応じて専門医を紹介してもらうこともでき、長期的な健康管理に役立ちます。
受診前の心構え
受診前には、過去の健診結果や食事・運動の状況、服薬中の薬をメモしておくと、診療がスムーズに進みます。
また、受診の理由(脂質異常症を心配している、糖尿病にならないか不安、など)を明確にしておくと、具体的なアドバイスを得やすいです。
受診をスムーズにするための準備
- 健診結果や検査データを持参する
- 普段の食事や運動内容をざっくりとメモしておく
- 気になる症状や疑問をリストアップしておく
- 服用中の薬やサプリメントを正確に伝える
以上、脂質異常症と糖尿病の関係について、症状や合併症、予防策を中心に解説しました。
自分の血液検査の数値が気になる方や、家族歴がある方は、早めの受診によって長期的なリスクを軽減できる可能性があります。
健康診断の結果に「高コレステロール」や「中性脂肪が高い」と書かれていた場合には、一度糖尿病内科やかかりつけ医を相談先として検討してみてください。
糖尿病を知ろう
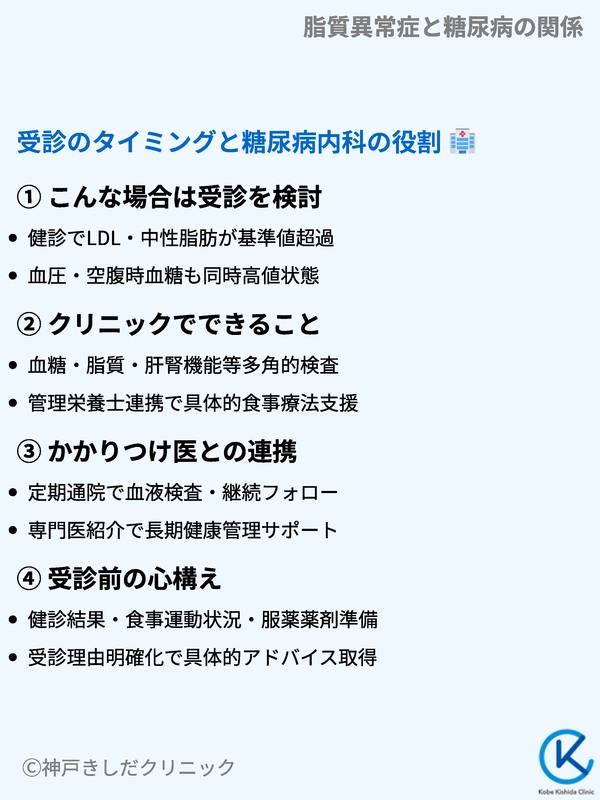
当院(神戸きしだクリニック)への受診について
神戸きしだクリニックの糖尿病内科では、脂質異常症・糖尿病の両疾患の関連性を踏まえた専門的な診察を行っております。将来の合併症リスクを減らすため、気になる症状がある方はお気軽にご相談ください。
糖尿病内科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |
| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |
| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |
| 月 | – | 〇 |
| 火 | 〇 | 〇 |
| 水 | – | 〇 |
| 木 | 〇 | – |
| 金 | – | 〇 |
| 土 | 〇 隔週 | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |
検査体制
- 血糖値検査(随時血糖・空腹時血糖)
- HbA1c検査
- 経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)
- 尿検査(尿糖・尿蛋白)
- 血液検査(脂質・肝機能・腎機能など)
など、必要に応じた検査を実施いたします。網膜症の精査や詳細な合併症検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など専門医療機関と連携して対応いたします。
予約・受診方法
当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約
お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。
▽ クリック ▽



