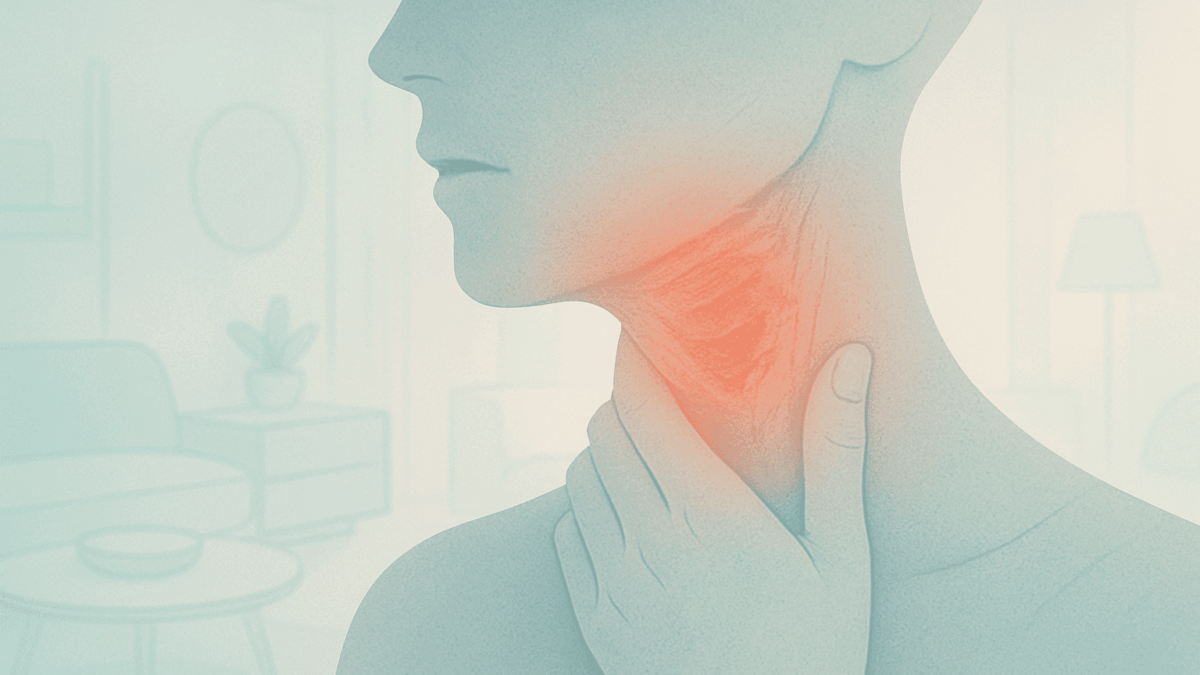「最近、声がかすれる」「長時間話すと声が出にくくなる」「風邪をひいた後から声の調子が悪い」など、のどのかすれ(嗄声:させい)に関するお悩みはありませんか。
声は、私たちのコミュニケーションにおいて重要な役割を担っています。声のかすれが続くと、日常生活や仕事に支障をきたすこともあります。
この記事では、のどのかすれがなぜ起こるのか、その原因や考えられる病気、ご自身でできる対処法、そして医療機関ではどのような対応が行われるのかについて、詳しく解説します。
のどのかすれ(嗄声)とは
のどのかすれは、声が普段と異なり、がらがらしたり、かれたり、弱々しくなったりする状態を指します。医学的には嗄声(させい)と呼びます。
声は、肺から送られた空気が喉頭(こうとう)にある声帯(せいたい)を振動させることで作られます。この声帯の振動が何らかの原因でうまくいかなくなると、声がかすれてしまうのです。
のどのかすれが起こる仕組み
声帯は、左右一対のひだ状の組織で、喉頭の中央に位置しています。発声時には左右の声帯が閉じて、肺からの呼気流でリズミカルに振動します。この振動によって原音が生み出され、それが咽頭、口腔、鼻腔などで共鳴し、言葉としての声になります。
声帯に炎症が起きたり、ポリープや結節ができたり、声帯を動かす神経に問題が生じたりすると、声帯の正常な振動が妨げられ、声がかすれる原因となります。
また、声帯そのものに異常がなくても、加齢によって声帯の筋肉が痩せたり、声帯の潤いが不足したりすることでも、声のかすれは起こり得ます。
声がかすれる主な症状の現れ方
声のかすれといっても、その現れ方はさまざまです。以下のような症状が代表的です。
- がらがら声(雑音の混じった濁った声)
- 力のない弱々しい声(息が漏れるような声)
- 声が出しにくい、声が途切れる
- 高い声が出ない、または声域が狭くなる
- 長時間話すと声が疲れる
これらの症状は、単独で現れることもあれば、複数組み合わさって現れることもあります。症状の程度や持続期間も、原因によって異なります。
日常生活への影響
声のかすれは、単に声が出にくいというだけでなく、日常生活のさまざまな場面で影響を及ぼすことがあります。例えば、仕事で人と話す機会が多い方にとっては、業務に支障が出ることがあります。
また、友人や家族との会話が楽しめなくなったり、電話でのコミュニケーションが困難になったりすることもあります。趣味の歌や読み聞かせなどが思うようにできなくなるなど、QOL(生活の質)の低下につながることも少なくありません。
声のかすれが長引く場合は、その原因を特定し、適切な対応をすることが大切です。
のどのかすれを引き起こす主な原因
のどのかすれは、さまざまな原因によって引き起こされます。ここでは、代表的な原因について解説します。
声の使いすぎ(音声酷使)
教師、歌手、保育士、コールセンターのオペレーターなど、日常的に大きな声を出したり、長時間話し続けたりする職業の人は、声帯に負担がかかりやすく、声がかすれることがあります。
また、カラオケでの歌いすぎや、スポーツ観戦での応援なども、一時的に声帯に炎症を引き起こし、声のかすれの原因となることがあります。これを音声酷使と呼びます。声帯が過度に振動することで、粘膜が傷ついたり、炎症を起こしたりします。
音声酷使による声帯への影響
音声酷使が続くと、声帯粘膜が充血したり、腫れたりします。初期には一時的な声のかすれで済みますが、慢性的に声帯に負担がかかり続けると、声帯ポリープや声帯結節といった器質的な変化(形が変わってしまうこと)が生じることもあります。
適切な声の出し方を意識したり、こまめに声の休息を取ったりすることが重要です。
炎症によるもの(風邪・咽頭炎・喉頭炎)
風邪やインフルエンザなどのウイルス感染、あるいは細菌感染によって、のどに炎症が起こると、声帯も炎症を起こし(急性声帯炎)、声がかすれることがあります。
特に、喉頭(声帯のある場所)に炎症が及ぶ喉頭炎では、声のかすれが主な症状として現れます。咽頭炎(のどの奥の炎症)でも、炎症が喉頭に波及すれば声がかすれます。
これらの場合、のどの痛みや発熱、咳などの他の症状を伴うことが一般的です。
炎症時の声帯の状態
炎症が起こると、声帯の粘膜が赤く腫れ上がり、正常な振動ができなくなります。また、痰がからみやすくなり、それも声のかすれの原因となります。
通常、原因となる感染症が治癒すれば、声のかすれも改善しますが、炎症が長引いたり、不適切な声の出し方を続けたりすると、声のかすれが慢性化することもあります。
加齢による変化
年齢を重ねるとともに、身体のさまざまな部分に変化が現れるように、声帯にも変化が生じます。
声帯の筋肉(声帯筋)が萎縮したり、声帯粘膜の潤いが失われたり、声帯の弾力性が低下したりすることで、声がかすれたり、弱々しくなったりすることがあります。
これは「加齢性嗄声」や「音声老化」などと呼ばれます。特に70歳代以降で顕著になることが多いですが、個人差があります。
加齢に伴う声帯の変化の具体例
| 変化する部分 | 具体的な変化 | 声への影響 |
|---|---|---|
| 声帯筋 | 萎縮し、細くなる | 声が細くなる、力のない声になる |
| 声帯粘膜 | 乾燥しやすくなる、硬くなる | 声がかすれる、声の潤いがなくなる |
| 声帯の弾力性 | 低下する | 声域が狭くなる、声が震えることがある |
喫煙や飲酒の影響
喫煙は、声帯にとって非常に有害です。タバコの煙に含まれる有害物質が、声帯の粘膜を慢性的に刺激し、炎症や浮腫(むくみ)を引き起こします。
これにより、声が低くなったり、がらがら声になったりします(喫煙者特有の「ヤニ声」)。また、喉頭がんのリスクも高めます。
飲酒も、適量を超えると声帯の粘膜を脱水させたり、炎症を助長したりする可能性があります。特に、飲酒しながら大声を出すような行為は、声帯への負担が大きくなります。
のどのかすれから考えられる病気
のどのかすれが続く場合や、他の症状を伴う場合には、何らかの病気が隠れている可能性もあります。ここでは、声のかすれを症状とする代表的な病気について解説します。
急性声帯炎・慢性声帯炎
急性声帯炎は、主に風邪などのウイルス感染や声の使いすぎによって声帯に急性の炎症が起きた状態です。声のかすれやのどの痛み、咳などの症状が現れます。
通常は数日から2週間程度で改善しますが、炎症が長引いたり、繰り返したりすると慢性声帯炎に移行することがあります。慢性声帯炎では、声のかすれが持続し、声が低くなったり、がらがら声になったりします。
喫煙や大気汚染、アレルギーなども慢性声帯炎の原因となることがあります。
声帯ポリープ・声帯結節
声帯ポリープは、声帯の片側にできる、きのこ状や水ぶくれのような柔らかい隆起です。
主に声の使いすぎや、咳払いなどで声帯に強い衝撃が加わることが原因で、声帯粘膜の血管が破れて内出血し、それが吸収されずにポリープになると考えられています。
声帯結節は、声帯の両側にできる、ペンのタコのような硬い隆起です。慢性的な声の使いすぎが原因で、声帯の同じ場所がこすれ合うことで生じます。
教師や歌手など、声を酷使する職業の人に多く見られます。どちらも、声のかすれ(特に息が漏れるような声)が主な症状です。
声帯ポリープと声帯結節の違い
| 項目 | 声帯ポリープ | 声帯結節 |
|---|---|---|
| できやすい場所 | 声帯の片側 | 声帯の両側(対称的) |
| 主な原因 | 急激な音声酷使、咳 | 慢性的な音声酷使 |
| 形状 | 柔らかい隆起、水ぶくれ様 | 硬い隆起、ペンだこ様 |
喉頭がん・下咽頭がん
喉頭がんや下咽頭がんは、声のかすれを引き起こす可能性のある悪性腫瘍です。喉頭がんは声帯そのものやその周辺にできるがんで、初期症状として声のかすれが現れることが多いのが特徴です。
特に喫煙者や多量飲酒者に多く見られます。下咽頭がんは、喉頭のさらに奥にある下咽頭にできるがんで、初期には症状が出にくく、進行すると声のかすれやのどの違和感、飲み込みにくさなどが出現します。
これらのがんは、早期発見・早期治療が非常に重要です。
喉頭がんの警戒すべきサイン
- 2週間以上続く原因不明の声のかすれ
- 血痰(痰に血が混じる)
- のどの痛みや異物感
- 呼吸困難感
- 首のしこり
反回神経麻痺
反回神経は、声帯を動かす役割を担っている神経です。この神経が何らかの原因で麻痺すると、声帯の動きが悪くなり、声がかすれたり、息が漏れるような声になったりします(嗄声)。
また、食べ物や飲み物が気管に入りやすくなる誤嚥(ごえん)を起こすこともあります。
反回神経麻痺の原因は多岐にわたり、甲状腺がん、食道がん、肺がんなどの頸部や胸部の腫瘍、大動脈瘤、手術(甲状腺手術、食道手術、肺手術など)の合併症、ウイルス感染などが考えられます。
原因が特定できない特発性のものもあります。
逆流性食道炎(胃食道逆流症)
逆流性食道炎(胃食道逆流症:GERD)は、胃酸や胃の内容物が食道に逆流することで、食道の粘膜に炎症を起こす病気です。
胸やけや呑酸(酸っぱいものが上がってくる感じ)が主な症状ですが、逆流した胃酸が喉頭まで達すると、声帯に炎症を引き起こし、声のかすれや咳、のどの違和感(咽喉頭酸逆流症:LPRD)の原因となることがあります。
特に、朝起きた時に声がかすれている、食事の後や横になると症状が悪化するなどの特徴が見られることがあります。
こんな症状は要注意 医療機関受診の目安
のどのかすれは、多くの場合、一時的なもので自然に治まりますが、中には注意が必要なケースもあります。
以下のような症状が見られる場合は、早めに耳鼻咽喉科などの医療機関を受診することを推奨します。
かすれが2週間以上続く場合
風邪などが治った後も声のかすれが2週間以上続く場合や、明らかな原因がないのに声のかすれが続く場合は、単なる炎症ではない可能性があります。
声帯ポリープや声帯結節、あるいは悪性腫瘍などが隠れていることも考えられるため、専門医による診察が必要です。
呼吸困難や嚥下困難を伴う場合
声のかすれに加えて、息苦しさ(呼吸困難)や、食べ物や飲み物が飲み込みにくい(嚥下困難)、むせやすいといった症状がある場合は、注意が必要です。
喉頭やその周辺に大きな病変があったり、神経の麻痺が広範囲に及んでいたりする可能性があります。これらの症状は、生命に関わることもあるため、速やかな受診が求められます。
受診を検討すべき症状の組み合わせ
| 主症状 | 伴う症状 | 考えられる状態の例 |
|---|---|---|
| 声のかすれ | 呼吸困難 | 喉頭の腫瘍、両側反回神経麻痺、喉頭浮腫など |
| 声のかすれ | 嚥下困難、むせる | 反回神経麻痺、下咽頭がん、脳血管障害など |
| 声のかすれ | 首のしこり | 喉頭がん・下咽頭がんの転移、甲状腺腫瘍など |
声以外の症状がある場合(血痰、首のしこりなど)
痰に血が混じる(血痰)、首にしこりが触れる、原因不明の体重減少、持続するのどの痛みや異物感など、声のかすれ以外の症状がある場合も、悪性腫瘍などの重大な病気のサインである可能性があります。
これらの症状に気づいたら、放置せずに医療機関を受診しましょう。
急に声が出なくなった場合
突然、全く声が出なくなる「失声」という状態になることがあります。強い精神的ストレスが原因で起こる心因性失声症のほか、声帯に急激な変化(出血など)が起きた可能性も考えられます。
原因を特定するためにも、一度専門医に相談することをお勧めします。
自分でのどのかすれを和らげるためのセルフケア
医療機関を受診するほどではない軽度のかすれや、声の使いすぎによる一時的なかすれの場合、ご自身でできるセルフケアで症状が和らぐことがあります。
ただし、症状が長引く場合や悪化する場合は、自己判断せずに医療機関を受診してください。
声の安静を保つ
声のかすれがあるときは、声帯を休ませることが最も重要です。できるだけ声を出さないように心がけましょう。
仕事などでどうしても話さなければならない場合は、小さな声でゆっくりと話すようにし、長時間の会話は避けてください。筆談やジェスチャーなどを活用するのも良い方法です。
また、咳払いは声帯に負担をかけるため、できるだけ控えるようにしましょう。のどがイガイガして咳払いをしたくなる場合は、少量の水を飲むなどして対処します。
のどの保湿と加湿
のどが乾燥すると、声帯の粘膜も乾燥し、声のかすれが悪化しやすくなります。
こまめに水分を摂取し、のどを潤すことが大切です。カフェインやアルコールは利尿作用があり、かえって脱水を招くことがあるため、水や白湯、ノンカフェインの温かい飲み物などが適しています。
また、部屋の湿度を適切に保つことも重要です。特に乾燥しやすい冬場やエアコンを使用する環境では、加湿器を使用したり、濡れタオルを干したりして、湿度を50~60%程度に保つように心がけましょう。
のどの保湿に役立つ飲み物の例
| 飲み物の種類 | 期待できること | 注意点 |
|---|---|---|
| 水、白湯 | 直接的な水分補給 | 特になし |
| ハーブティー(カモミールなど) | リラックス、保湿 | アレルギーに注意 |
| はちみつ入り温かい飲み物 | 保湿、のどの保護 | 1歳未満の乳児には与えない |
加湿器を選ぶ際のポイント
- 部屋の広さに合った加湿能力
- 手入れのしやすさ(清潔を保つため)
- 静音性
生活習慣の見直し(禁煙・節酒など)
喫煙は声帯にとって百害あって一利なしです。声のかすれを改善したいのであれば、禁煙することが強く推奨されます。禁煙することで、声帯の炎症が軽減され、声質の改善が期待できます。
また、喉頭がんのリスクも低減できます。アルコールの摂取も控えめにしましょう。特に、飲酒しながら大声を出すことは声帯に大きな負担をかけます。
バランスの取れた食事や十分な睡眠も、体の免疫力を高め、のどの健康を保つ上で重要です。刺激の強い香辛料や熱すぎる食べ物、冷たすぎる飲み物なども、のどへの刺激となることがあるため、控えるようにしましょう。
バランスの取れた食事と十分な睡眠
体の健康は、のどの健康にもつながります。栄養バランスの取れた食事を心がけ、ビタミンCやビタミンAなど、粘膜の健康維持に役立つ栄養素を積極的に摂取しましょう。
十分な睡眠時間を確保することも、体の抵抗力を高め、炎症の回復を助けます。ストレスを溜めないように、適度な休息やリフレッシュも大切です。
医療機関で行われる検査と一般的な対応
のどのかすれで医療機関(主に耳鼻咽喉科)を受診すると、まず問診で症状の詳しい状況や生活習慣などについて確認し、その後、のどの状態を観察するための検査が行われます。
原因に応じて適切な対応がなされます。
問診と視診
医師はまず、いつから声がかすれているのか、どのような声のかすれ方か、他に症状はないか、声を使う職業か、喫煙歴や飲酒歴はあるか、既往歴や服用中の薬はあるかなどを詳しく尋ねます(問診)。
その後、口を開けてもらい、舌圧子(ぜつあつし)という器具で舌を押さえながら、のどの奥(咽頭)の状態を目で見て確認します(視診)。
喉頭ファイバースコープ検査
声帯の状態を直接観察するために、喉頭ファイバースコープ検査(喉頭内視鏡検査)が行われることが一般的です。
これは、細い管状のカメラ(ファイバースコープ)を鼻または口から挿入し、喉頭や声帯をモニターに映し出して詳しく観察する検査です。
声帯の形、色、動き、振動の様子、ポリープや結節、腫瘍の有無などを確認できます。検査中の不快感を和らげるために、鼻の中に局所麻酔のスプレーをすることがあります。検査時間は数分程度です。
喉頭ファイバースコープ検査でわかること
| 観察項目 | 確認できることの例 |
|---|---|
| 声帯の色・形状 | 炎症の有無、ポリープ・結節・腫瘍の有無 |
| 声帯の動き | 麻痺の有無、左右対称性 |
| 声帯の振動 | (ストロボスコピー併用時)振動の規則性、振幅 |
画像検査(CT、MRIなど)
喉頭ファイバースコープ検査で異常が見つかった場合や、さらに詳しい情報が必要な場合には、CT(コンピュータ断層撮影)検査やMRI(磁気共鳴画像)検査などの画像検査が行われることがあります。
これらの検査は、喉頭やその周辺の組織の断層画像を撮影し、病変の広がりや深さ、リンパ節への転移の有無などを評価するのに役立ちます。
特に、がんが疑われる場合や、反回神経麻痺の原因を調べる際などに有用です。
原因に応じた対応(薬物療法、音声治療、手術など)
検査の結果、診断がついたら、その原因に応じた対応が行われます。
- 炎症(急性声帯炎など) 消炎鎮痛薬、去痰薬、場合によっては抗菌薬などが処方されます。声の安静も重要です。
- 声帯ポリープ・声帯結節 保存的治療(声の安静、ステロイド吸入、音声治療)で改善しない場合や、ポリープが大きい場合には、手術(喉頭微細手術)が検討されます。
- 喉頭がん・下咽頭がん がんの進行度や患者さんの状態に応じて、放射線治療、化学療法、手術(喉頭摘出術など)を単独または組み合わせて行います。
- 反回神経麻痺 原因疾患の治療が優先されます。麻痺が回復しない場合は、声帯内注入術(声帯にコラーゲンなどを注入して隙間を埋める)や甲状軟骨形成術(声帯の位置を調整する手術)、音声治療などが行われます。
- 逆流性食道炎 胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬など)や、消化管運動機能改善薬などが用いられます。生活習慣の改善も重要です。
これらの対応はあくまで一般的なものであり、個々の患者さんの状態によって異なります。医師とよく相談し、納得のいく対応を受けることが大切です。
原因別の大まかな対応方針
| 原因 | 主な対応法 | 補足 |
|---|---|---|
| 音声酷使 | 声の安静、音声衛生指導 | 発声方法の改善が有効なことも |
| 感染による炎症 | 薬物療法(消炎剤、抗菌薬など)、安静 | 原因菌・ウイルスに応じた対応 |
| 声帯ポリープ | 保存的治療、改善なければ手術 | 術後も音声リハビリが重要 |
のどのかすれに関するよくある質問
- Qのど飴は効果がありますか?
- A
のど飴には、のどの乾燥を防ぎ、一時的に炎症を和らげる成分が含まれているものがあります。そのため、軽いのどのかすれや不快感に対しては、ある程度の効果が期待できる場合があります。
しかし、のど飴はあくまで対症療法であり、声のかすれの原因そのものを治すものではありません。
メントールなどの刺激が強いものは、かえってのどを乾燥させたり、咳を誘発したりすることもあるため、注意が必要です。症状が続く場合は、医療機関を受診しましょう。
- Q声変わりとの違いは何ですか?
- A
声変わりは、主に思春期の男性に起こる生理的な変化です。第二次性徴に伴い、男性ホルモンの影響で喉頭が急速に成長し、声帯が長く太くなることで声が低くなります。
この過程で一時的に声が不安定になったり、かすれたりすることがありますが、通常は自然に落ち着きます。
一方、大人の声のかすれは、何らかの病気や声帯への負担が原因で起こることが多く、原因に応じた対応が必要です。声変わりの時期を過ぎた大人の声のかすれは、単なる声変わりとは異なります。
- Q子供でものどがかすれることはありますか?
- A
はい、子供でものどがかすれることはあります。大きな声で叫んだり、泣き続けたりすることで声帯に負担がかかり、一時的に声がかすれることがあります(音声酷使)。
また、風邪やクループ症候群(急性喉頭気管気管支炎)などの感染症でも声がかすれます。まれに、先天的な声帯の異常や、若年性再発性呼吸器乳頭腫症(喉頭に良性の腫瘍ができる病気)などが原因となることもあります。
子供の声のかすれが長引く場合や、呼吸が苦しそうな場合は、小児科や耳鼻咽喉科を受診してください。
- Q予防法はありますか?
- A
のどのかすれを完全に予防することは難しいですが、リスクを減らすためにできることはあります。
声のかすれの予防策
- 声の使いすぎに注意し、適度に声帯を休ませる。
- 正しい発声方法を意識する(特に声をよく使う人)。
- こまめに水分補給をし、のどの乾燥を防ぐ。
- 室内の加湿を心がける。
- 禁煙する。
- 飲酒は控えめにする。
- 風邪やインフルエンザの予防(手洗い、うがい、マスク着用など)。
- バランスの取れた食事と十分な睡眠で免疫力を保つ。
これらの点に気をつけることで、のどへの負担を軽減し、声のかすれが起こりにくくなることが期待できます。
以上