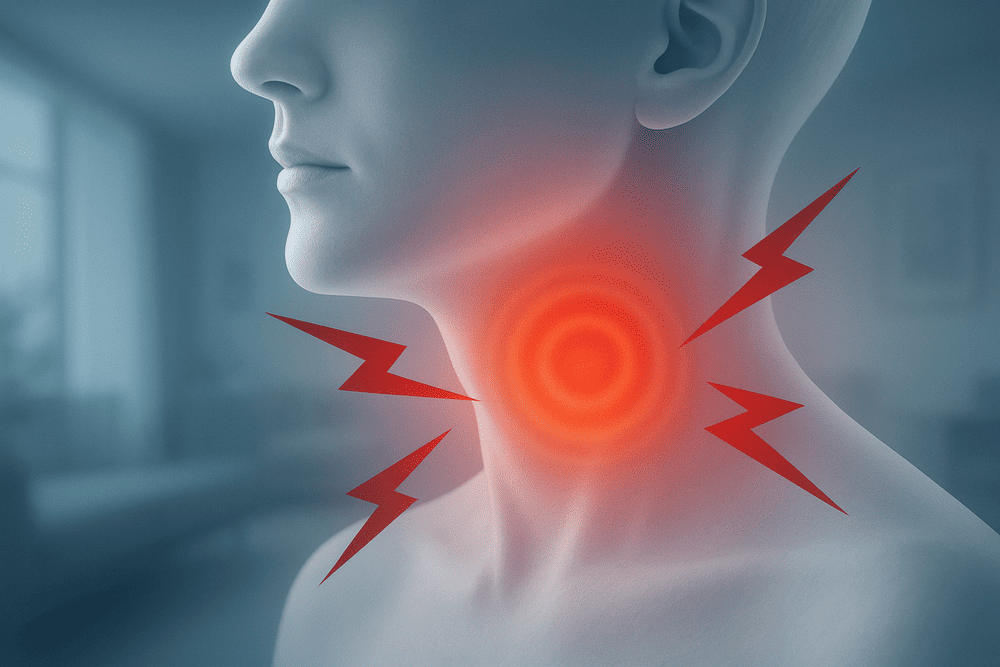「喉がズキズキと脈打つように痛い…」そんな経験はありませんか?いつもの風邪とは違う強い痛みに、不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、ズキズキする喉の痛みがなぜ起こるのか、考えられる原因やご自身でできる対処法、医療機関を受診する目安について、詳しく解説します。
つらい症状の緩和と適切な対応のためにお役立てください。
ズキズキする喉の痛みとは?特徴と主な症状
ズキズキする喉の痛みは、医学的には「拍動性の咽頭痛(はくどうせいのいんとうつう)」と表現されることがあります。この痛みは、心臓の鼓動に合わせて痛みが強弱する感覚を伴うのが特徴です。
単なるイガイガ感や乾燥感とは異なり、炎症が比較的強く起きているサインと考えられます。日常生活にも支障をきたすほどの強い痛みとして感じることが少なくありません。
痛みの性質と現れ方
ズキズキする痛みは、喉の奥や扁桃腺(へんとうせん)周辺に炎症が起きている場合に感じやすいです。炎症が強くなると、神経が刺激されて拍動に合わせた痛みとして認識されます。
飲み込む動作(嚥下:えんげ)の際に特に痛みが強くなる「嚥下痛(えんげつう)」を伴うことが多く、食事や水分摂取が困難になることもあります。
また、安静にしていてもズキズキとした痛みが持続することもあります。
一般的な喉の痛みとの違い
風邪の初期症状などで感じる喉の痛みは、ヒリヒリ、イガイガといった軽い刺激感や、乾燥感が主であることが多いです。これに対し、ズキズキする痛みは、より深部での強い炎症を示唆します。
痛みの強さも格段に強く、何もしなくても痛む、唾を飲み込むのもつらい、といった状態になりやすいのが特徴です。原因によっては、発熱や倦怠感など全身症状を伴うこともあります。
喉の痛みの種類の比較
| 痛みの種類 | 主な感覚 | 特徴的な状況 |
|---|---|---|
| ズキズキする痛み | 拍動性、鋭い痛み | 嚥下時痛が強い、安静時にも痛むことがある |
| イガイガ・ヒリヒリする痛み | 表面的な刺激感、乾燥感 | 風邪の初期、軽度の炎症 |
| 圧迫されるような痛み | 喉が締め付けられる感じ | 異物感、腫れが強い場合 |
痛みに伴うことのあるその他の症状
ズキズキする喉の痛みに加えて、以下のような症状が現れることがあります。これらの症状の有無や程度は、原因によって異なります。
- 発熱(高熱になることも)
- 全身の倦怠感、筋肉痛、関節痛
- 頭痛
- 首のリンパ節の腫れや圧痛
- 声のかすれ(嗄声:させい)
これらの症状が複数見られる場合は、単なる喉の不調ではなく、何らかの疾患が背景にある可能性を考え、注意深く経過を観察することが大切です。
特に高熱を伴う場合や、呼吸が苦しいといった症状がある場合は、速やかに医療機関を受診することを検討してください。
喉がズキズキ痛む場合に考えられる主な原因
ズキズキとした強い喉の痛みを引き起こす原因は多岐にわたります。大きく分けて、細菌やウイルスなどの微生物による「感染性の原因」と、それ以外の「非感染性の原因」があります。
適切な対処のためには、原因を見極めることが重要です。
感染性の原因
喉の痛みの多くは、ウイルスや細菌の感染によって引き起こされます。特にズキズキとした強い痛みを伴う場合は、炎症が強く起きていることを示唆します。
急性扁桃炎(きゅうせいへんとうえん)
急性扁桃炎は、口蓋垂(こうがいすい、のどちんこ)の両側にある扁桃に細菌やウイルスが感染し、急性の炎症が起こる病気です。代表的な症状は、高熱、強い喉の痛み(特に嚥下痛)、全身倦怠感です。
扁桃が赤く腫れ上がり、白い膿(うみ)が付着することもあります。ズキズキとした拍動性の痛みを訴える方が多い疾患の一つです。
扁桃周囲膿瘍(へんとうしゅういのうよう)
急性扁桃炎の炎症が扁桃の周囲にまで波及し、膿がたまってしまう状態を扁桃周囲膿瘍といいます。非常に強い喉の痛み、嚥下困難、開口障害(口が開きにくい)、発熱などが特徴です。
片側の喉だけが異常に痛むこともあります。進行すると気道を圧迫する可能性もあるため、緊急の対応が必要となることがあります。
急性咽頭炎・喉頭炎(きゅうせいいんとうえん・こうとうえん)
咽頭(いんとう:鼻の奥から食道に至るまでの部分)や喉頭(こうとう:気管の入り口で発声に関わる部分)に急性の炎症が起こる病気です。ウイルス感染が主な原因ですが、細菌感染によるものもあります。
喉の痛み、発熱、咳、声のかすれなどの症状が現れます。炎症が強いと、ズキズキとした痛みを感じることがあります。
その他の感染症
インフルエンザウイルスやアデノウイルス、EBウイルス(伝染性単核球症の原因)など、特定のウイルス感染症でも強い喉の痛みが現れることがあります。
また、頻度は低いですが、ジフテリアなどの特殊な細菌感染も考慮に入れる必要があります。
主な感染性の原因と特徴
| 原因疾患 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 急性扁桃炎 | 高熱、強い嚥下痛、倦怠感 | 扁桃の腫れ、膿の付着 |
| 扁桃周囲膿瘍 | 激しい喉の痛み、開口障害、嚥下困難 | 片側性の腫脹、緊急対応が必要な場合も |
| 急性咽頭炎・喉頭炎 | 喉の痛み、咳、声のかすれ、発熱 | ウイルス性が多く、炎症の程度により痛みが変動 |
非感染性の原因
感染以外にも、喉にズキズキとした痛みを引き起こす原因があります。
口腔内や歯周組織の炎症の波及
重度の虫歯(う蝕)や歯周病、智歯周囲炎(親知らずの炎症)などが進行し、その炎症が喉の奥にまで広がると、喉の痛みとして感じることがあります。
特に顎の近くに炎症が及ぶと、ズキズキとした拍動性の痛みを伴うことがあります。この場合、歯科や口腔外科での治療が主体となります。
アレルギー反応
特定の食物や薬剤、吸入物などに対するアレルギー反応の一部として、喉に強い炎症や腫れが生じ、痛みを引き起こすことがあります。
アナフィラキシーと呼ばれる重篤なアレルギー反応では、喉の閉塞感や呼吸困難を伴うこともあり、迅速な対応が必要です。
逆流性食道炎
胃酸が食道へ逆流することで、食道だけでなく喉(咽喉頭)にも炎症を引き起こすことがあります。これを咽喉頭酸逆流症(いんこうとうさんぎゃくりゅうしょう)と呼びます。
胸やけや呑酸(どんさん:酸っぱいものが上がってくる感じ)といった典型的な症状だけでなく、喉の痛み、咳、声のかすれ、喉の違和感などが現れることがあります。
痛みがズキズキと感じられることもあります。
その他の稀な原因
非常に稀ですが、喉頭蓋炎(こうとうがいえん:喉頭の蓋の部分に起こる急性の炎症で、窒息の危険がある)、悪性腫瘍(がん)、神経痛(舌咽神経痛など)なども、ズキズキとした喉の痛みの原因となることがあります。
これらの疾患は専門的な診断と治療を必要とします。
主な非感染性の原因と特徴
| 原因 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 口腔・歯周組織の炎症 | 歯痛、歯肉の腫れ、開口障害、喉の痛み | 歯科的問題が先行することが多い |
| アレルギー反応 | 喉の痛み、腫れ、痒み、呼吸困難(重症時) | 特定物質への曝露後に発症 |
| 逆流性食道炎(咽喉頭酸逆流症) | 胸やけ、喉の痛み、咳、声のかすれ | 食後や臥位で症状が悪化しやすい |
ズキズキする喉の痛みに伴いやすい症状
ズキズキする喉の痛みは、単独で現れることもありますが、多くの場合、他の症状を伴います。これらの随伴症状は、原因疾患を特定する上で重要な手がかりとなります。
どのような症状に注意すべきかを知っておきましょう。
発熱と悪寒
細菌やウイルス感染が原因である場合、体の防御反応として発熱が見られることが一般的です。特に急性扁桃炎などでは38℃以上の高熱が出ることも珍しくありません。
発熱に伴い、悪寒(おかん:寒気)や体の節々の痛み(関節痛、筋肉痛)を感じることもあります。体温の変化や、熱の上がり方(急激か、徐々にかなど)も診断の参考になります。
嚥下痛と食事摂取困難
嚥下痛、つまり物を飲み込むときの痛みは、ズキズキする喉の痛みを伴う疾患で非常によく見られる症状です。炎症が強いほど嚥下痛も強くなり、唾液を飲み込むことさえつらく感じることがあります。
これにより、食事や水分摂取が困難になると、脱水症状や栄養不足に陥る危険性もあるため注意が必要です。
声の変化や咳
炎症が声帯やその周辺(喉頭)に及ぶと、声がかすれたり、出しにくくなったりする嗄声(させい)という症状が現れます。また、喉の刺激によって咳が出やすくなることもあります。
咳は乾いた咳(乾性咳嗽:かんせいがいそう)であることもあれば、痰(たん)を伴う湿った咳(湿性咳嗽:しっせいがいそう)であることもあります。痰の色や性状も診断の手がかりの一つです。
首のリンパ節の腫れ
喉の周辺で炎症が起きると、近くにある頸部(けいぶ)リンパ節が反応して腫れることがあります。顎の下や耳の後ろ、首の側面などにしこりのようなものを触れることがあります。
腫れたリンパ節は、押すと痛みを感じる(圧痛)ことが多いです。リンパ節の腫れの範囲や硬さなども、医師が診察する際の重要な情報となります。
注意すべき随伴症状
| 症状 | 観察ポイント | 考えられる背景 |
|---|---|---|
| 呼吸困難・息苦しさ | 安静時の呼吸状態、ゼーゼー音の有無 | 気道狭窄(扁桃周囲膿瘍、喉頭蓋炎など) |
| 開口障害(口が開きにくい) | 指が何本分入るか | 扁桃周囲膿瘍、顎関節の炎症 |
| 強い頭痛、意識の変化 | 嘔吐の有無、会話の明瞭さ | 髄膜炎など重篤な感染症の可能性 |
上記の表に挙げたような症状は、緊急性が高い状態を示唆している可能性があります。これらの症状が一つでも見られる場合は、自己判断せずに速やかに医療機関を受診してください。
自宅でできる喉の痛みの対処法とセルフケア
ズキズキする喉の痛みがある場合、医療機関の受診が基本ですが、症状が比較的軽い場合や、受診までの間に少しでも楽に過ごすために、ご自身でできる対処法もあります。
ただし、これらはあくまで対症療法であり、原因を取り除くものではないことを理解しておきましょう。
安静と十分な睡眠
体調が悪いときは、何よりもまず体を休めることが大切です。十分な睡眠時間を確保し、体力の消耗を避けましょう。免疫力を高め、体が病気と戦う力をサポートします。
仕事や学校なども無理せず、可能な範囲で休息を取るように心がけてください。
喉の加湿と保温
喉の乾燥は痛みを悪化させる原因の一つです。室内の湿度を適切に保つことが重要です。加湿器を使用したり、濡れタオルを部屋に干したりするのも効果的です。
また、マスクの着用は、自分の呼気で喉を潤す効果に加え、他人への感染拡大を防ぐ意味でも有効です。首元を温めることも、血行を促進し、痛みの緩和につながることがあります。
室内の適切な湿度管理
| 対策 | 方法 | ポイント |
|---|---|---|
| 加湿器の使用 | 適切な湿度(50-60%目安)に設定 | 清潔に保ち、カビの発生に注意 |
| 濡れタオルの利用 | 室内に干す | 手軽にできるが、加湿力は限定的 |
| 洗濯物の室内干し | 清潔な洗濯物を干す | 生活空間の湿度上昇に役立つ |
水分補給と栄養摂取
発熱や嚥下痛があると、脱水状態になりやすいです。こまめに水分を補給しましょう。経口補水液やスポーツドリンク、白湯、麦茶などが適しています。
食事は、喉への刺激が少なく、消化の良いものを選びましょう。おかゆ、うどん、ゼリー、プリン、スープなどがおすすめです。香辛料の強いもの、熱すぎるもの、硬いものは避けるようにしてください。
喉に優しい飲食物の例
- 常温またはぬるま湯
- 薄味のスープ(野菜スープ、鶏がらスープなど)
- ゼリー飲料、ヨーグルト
- すりおろしたリンゴ、バナナ
うがい
うがいは、喉の粘膜を潤し、付着した細菌やウイルス、ほこりなどを洗い流す効果が期待できます。
ただし、痛みが強いときに過度に行うと、かえって粘膜を傷つけてしまう可能性もあるため、優しく行うことが大切です。うがい薬を使用する場合は、刺激の少ないものを選びましょう。
緑茶や塩水でのうがいも一定の効果があると言われています。
市販薬の利用について
喉の痛みを和らげる目的で、市販の鎮痛薬(アセトアミノフェンやイブプロフェンなど)や、喉の炎症を抑える成分が含まれたトローチ、スプレー剤などを使用することも一つの方法です。
ただし、これらは症状を一時的に緩和するものであり、原因を治療するものではありません。使用する際は、薬剤師に相談し、用法・用量を守って正しく使用してください。
数日使用しても症状が改善しない、あるいは悪化する場合は、医療機関を受診しましょう。
医療機関を受診する目安となる症状
ズキズキする喉の痛みは、時に重篤な疾患のサインであることもあります。自己判断で様子を見ているうちに症状が悪化してしまうケースも少なくありません。
どのような場合に医療機関を受診すべきか、具体的な目安を知っておくことが重要です。
痛みが非常に強い、または悪化している場合
我慢できないほどの強い痛みがある場合や、数日間痛みが続く、あるいは徐々に悪化している場合は、医療機関を受診しましょう。
特に、唾液を飲み込むのもつらい、夜も眠れないほどの痛みは、扁桃周囲膿瘍など、より専門的な治療が必要な状態を示唆している可能性があります。
高熱が続く場合
38℃以上の高熱が2日以上続く場合、または一度下がった熱が再び上昇してくるような場合は、細菌感染が強く疑われます。
適切な抗菌薬による治療が必要となることがあるため、医師の診察を受けることを推奨します。
呼吸が苦しい、息がしにくい場合
喉の腫れが気道を圧迫し、呼吸困難を引き起こすことがあります。ゼーゼーという呼吸音がする(喘鳴:ぜんめい)、安静にしていても息苦しい、横になると苦しさが増すといった症状は危険なサインです。
このような場合は、夜間や休日であっても、救急外来を受診するなど、直ちに医療機関に連絡してください。
食事がとれない、水分がとれない場合
喉の痛みが強すぎて、食事や水分を十分に摂取できない状態が続くと、脱水症状や栄養失調に陥る危険性があります。特に高齢者や小さなお子さんの場合は、脱水が進みやすいため注意が必要です。
口の中が乾燥している、尿の量が減った、ぐったりしているなどの兆候が見られたら、早めに受診しましょう。点滴による水分・栄養補給が必要となることもあります。
その他の注意すべき症状
以下の症状が見られる場合も、医療機関の受診を検討してください。
- 口が開きにくい(開口障害)
- 声がこもる、ろれつが回りにくい
- 首のリンパ節が著しく腫れている、または片側だけが特に腫れている
- 皮膚に発疹が出ている
- 強い頭痛や嘔吐を伴う
受診を検討すべき症状のまとめ
| 症状 | 緊急度 | 対応 |
|---|---|---|
| 呼吸困難、息苦しさ | 非常に高い | 直ちに救急受診 |
| 強い痛み、嚥下不能 | 高い | 早めに医療機関を受診 |
| 高熱が持続(2日以上) | 中程度~高い | 医療機関を受診 |
| 水分摂取困難、脱水症状 | 中程度~高い | 医療機関を受診(特に小児・高齢者) |
| 開口障害、声のこもり | 中程度 | 医療機関を受診 |
これらの目安は一般的なものであり、ご自身の体調や不安に応じて、早めに医師に相談することが大切です。
医療機関で行われる検査と治療法
ズキズキする喉の痛みで医療機関を受診した場合、医師はまず問診と視診を行い、症状や喉の状態を詳しく確認します。
その上で、原因を特定し、適切な治療法を決定するために、必要に応じていくつかの検査を行います。
問診と視診
問診では、いつからどのような痛みがあるのか、他にどのような症状があるか、既往歴やアレルギーの有無、喫煙歴、普段の生活習慣などについて詳しく聞かれます。
視診では、ペンライトや舌圧子(ぜつあつし:舌を押さえる器具)を使って、喉の奥の扁桃や咽頭の状態(発赤、腫脹、膿の付着など)を直接観察します。頸部リンパ節の腫れなども触診で確認します。
迅速検査
特定の感染症が疑われる場合、迅速検査が行われることがあります。綿棒で喉の奥をこすって検体を採取し、短時間(5~15分程度)で結果が判明します。
代表的な迅速検査
- A群β溶血性連鎖球菌(溶連菌)迅速検査
- インフルエンザウイルス迅速検査
- アデノウイルス迅速検査
- RSウイルス迅速検査(主に乳幼児)
これらの検査結果は、抗菌薬の必要性を判断したり、適切な治療方針を立てたりする上で重要です。ただし、全てのウイルスや細菌を検出できるわけではありません。
血液検査
炎症の程度(白血球数やCRP値など)や、特定のウイルス感染(EBウイルスなど)が疑われる場合に血液検査を行うことがあります。全身状態の把握や、他の疾患との鑑別にも役立ちます。
画像検査
扁桃周囲膿瘍や喉頭蓋炎など、喉の深部の状態を詳しく調べる必要がある場合には、頸部CT検査や頸部超音波(エコー)検査などの画像検査が行われることがあります。
これにより、膿瘍の正確な位置や大きさ、気道の状態などを評価することができます。
主な検査とその目的
| 検査名 | 目的 | 所要時間(目安) |
|---|---|---|
| 視診・触診 | 喉の状態、リンパ節の腫れの確認 | 数分 |
| 迅速検査 | 特定の細菌・ウイルスの検出 | 5~15分 |
| 血液検査 | 炎症の程度、全身状態の評価 | 結果判明まで数時間~1日 |
| 画像検査(CT、エコー) | 深部の炎症、膿瘍の確認 | 15~30分(検査自体) |
治療法
治療法は、原因疾患や症状の重症度によって異なります。
薬物療法
細菌感染が原因であると判断された場合は、抗菌薬(抗生物質)が処方されます。
ウイルス感染の場合は、抗菌薬は効果がないため、基本的には症状を和らげる対症療法が中心となります(インフルエンザなど一部のウイルスには抗ウイルス薬があります)。
痛みが強い場合には鎮痛薬(解熱鎮痛薬)、炎症を抑える薬、痰を出しやすくする薬、咳止めなどが症状に応じて処方されます。
局所療法
喉の炎症を抑えるために、吸入療法(ネブライザー)や、炎症を抑える薬液を直接喉に塗布する処置が行われることもあります。
外科的治療(必要な場合)
扁桃周囲膿瘍の場合は、膿を排出するために穿刺(せんし:針を刺して膿を吸い出す)や切開排膿(せっかいはいのう:切開して膿を出す)といった外科的な処置が必要になることがあります。
また、頻繁に扁桃炎を繰り返す場合や、扁桃肥大が著しい場合には、扁桃摘出術が検討されることもあります。
喉の痛みを予防するために心がけたいこと
ズキズキするような強い喉の痛みを経験すると、二度とあのような思いはしたくないと感じる方も多いでしょう。
完全に予防することは難しいかもしれませんが、日頃からいくつかの点に気をつけることで、喉のトラブルのリスクを減らすことが期待できます。
基本的な感染対策の徹底
多くの喉の痛みは感染症が原因です。手洗いやうがいを習慣にし、ウイルスや細菌が体内に入るのを防ぎましょう。特に外出後や食事前、トイレの後などは念入りに行うことが大切です。
咳エチケットとして、咳やくしゃみをする際はマスクを着用したり、ティッシュや袖で口鼻を覆ったりすることも、自分だけでなく周囲への感染拡大を防ぐために重要です。
生活習慣の見直し
免疫力を高く保つためには、バランスの取れた食事、質の高い睡眠、適度な運動が基本です。特定の栄養素に偏ることなく、主食・主菜・副菜をそろえ、ビタミンやミネラルも十分に摂取しましょう。
睡眠不足や過労は免疫力を低下させる大きな要因です。規則正しい生活を送り、心身のストレスを溜め込まないようにすることも大切です。
免疫力維持に役立つ栄養素の例
| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |
|---|---|---|
| ビタミンC | 抗酸化作用、免疫細胞の活性化 | 柑橘類、イチゴ、キウイ、パプリカ |
| ビタミンA | 粘膜の保護・強化 | レバー、うなぎ、緑黄色野菜(人参、ほうれん草) |
| 亜鉛 | 免疫細胞の機能維持 | 牡蠣、牛肉、豚レバー、卵 |
喉の乾燥を防ぐ
喉の粘膜が乾燥すると、バリア機能が低下し、ウイルスや細菌に感染しやすくなります。空気が乾燥しやすい季節(特に冬場)は、加湿器を利用するなどして室内の湿度を適切(50~60%程度)に保ちましょう。
こまめに水分を補給することも、喉を潤す上で効果的です。マスクの着用も、自分の呼気で喉の湿度を保つのに役立ちます。
刺激物を避ける
喫煙は喉の粘膜に慢性的な炎症を引き起こし、免疫力を低下させます。禁煙することが最も望ましいですが、難しい場合でも本数を減らす努力をしましょう。
また、アルコールの過度な摂取や、香辛料の強い刺激的な食べ物も、喉にとっては負担となることがあります。これらを日常的に多く摂取する習慣がある方は、頻度や量を見直すことを検討してみてください。
ズキズキする喉の痛みに関するよくある質問
ここでは、ズキズキする喉の痛みに関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてください。
- Q喉の痛みに効く食べ物や飲み物はありますか?
- A
喉の痛みを直接治す特定の食べ物や飲み物はありませんが、症状を和らげたり、回復を助けたりするものはあります。喉への刺激が少なく、栄養価の高いものが基本です。
例えば、はちみつ(1歳未満の乳児には与えないでください)には抗菌作用や保湿作用があると言われ、お湯に溶かして飲むと喉が楽になることがあります。また、大根や生姜も炎症を抑える効果が期待できるとされています。
飲み物は、常温かぬるま湯、経口補水液、薄いお茶などが良いでしょう。熱すぎるもの、冷たすぎるもの、炭酸飲料、アルコール、カフェインの多いものは刺激になることがあるため避けた方が無難です。
- Q喉の痛みが片側だけズキズキします。なぜですか?
- A
A2 片側だけの強い喉の痛みは、いくつかの原因が考えられます。代表的なものとしては、扁桃周囲膿瘍があります。これは、片側の扁桃の炎症が周囲に広がり、膿がたまる状態です。
その他、智歯周囲炎(親知らずの炎症)が喉の方へ影響している場合や、稀ですが舌咽神経痛などの神経性の痛み、片側の声帯炎なども考えられます。
いずれにしても、片側だけの強い痛みは詳しい診察が必要なサインですので、医療機関を受診することをお勧めします。
- Qズキズキする喉の痛みはどれくらいで治りますか?
- A
治るまでの期間は、原因や重症度、治療内容によって大きく異なります。
一般的なウイルス性の咽頭炎や軽度の扁桃炎であれば、適切な対処をすれば数日から1週間程度で改善することが多いです。
細菌性の扁桃炎で抗菌薬が処方された場合は、通常、服用開始から2~3日で症状の改善が見られ始めますが、処方された期間は最後まで飲み切ることが重要です。
扁桃周囲膿瘍などで切開排膿が必要な場合は、完全に治癒するまでにもう少し時間がかかることがあります。
症状が長引く場合や、一度改善した後に再び悪化する場合は、再度医療機関を受診してください。
- Q喉の痛みに市販の風邪薬は効きますか?
- A
市販の総合感冒薬(風邪薬)には、解熱鎮痛成分や抗炎症成分が含まれているものが多く、喉の痛みを一時的に和らげる効果は期待できます。
しかし、これらはあくまで症状を抑える対症療法であり、原因そのものを治すものではありません。特に、細菌感染が原因の場合、抗菌薬が必要になることがありますが、市販薬には抗菌薬は含まれていません。
痛みが強い場合や、高熱が続く場合、数日服用しても改善しない場合は、自己判断を続けずに医療機関を受診することが大切です。
- Q喉が痛いとき、お風呂に入っても大丈夫ですか?
- A
高熱がなく、体力が著しく消耗していなければ、入浴自体は問題ありません。むしろ、湯気で喉が加湿されたり、体が温まることで血行が良くなり、リラックス効果も期待できます。
ただし、長湯や熱すぎるお湯は体力を消耗させるため避けましょう。入浴後は湯冷めしないようにすぐに体を拭き、温かくして休むことが大切です。
高熱がある場合や、倦怠感が強い場合は、無理せずシャワー程度にするか、体を拭くだけにとどめておきましょう。
以上