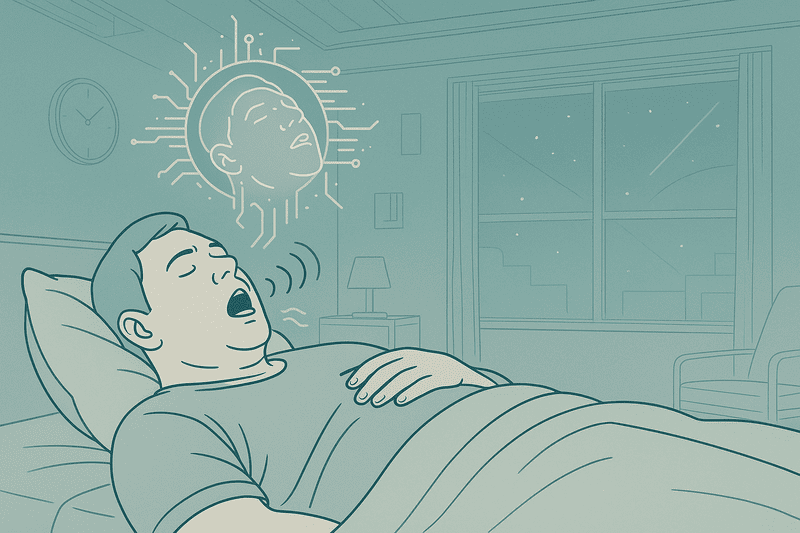毎晩の大きないびき、ご家族に指摘されていませんか?もしかすると、ご自身では「よく眠っている」と思っていても、日中に強い眠気を感じることがあるかもしれません。
そのいびき、単なる音の問題ではなく、実は深刻な病気のサインかもしれません。
この記事では、いびきがなぜ危険なのか、特に「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」との関係、その見分け方や放置するリスクについて詳しく解説します。
ご自身のいびきやご家族のいびきが「病気のサイン」なのかどうかを判断するヒントが得られます。早期発見と対策が、将来の健康を守る鍵となります。
いびきが「病気のサイン」と言われる理由
いびきは、睡眠中に空気の通り道(上気道)が狭くなり、そこを空気が通る際に粘膜が振動して鳴る音です。この「気道が狭くなる」状態こそが、多くの健康問題の入り口となります。
いびきをかくこと自体が、気道が完全に塞がる一歩手前の危険な状態を示している場合があります。
ただの「うるさい音」ではないいびきの正体
いびきは、睡眠中に喉の筋肉が緩み、舌や軟口蓋(口の奥の柔らかい部分)が気道に落ち込むことで発生します。特に仰向けで寝ていると、重力の影響で舌根が沈下しやすくなり、気道はさらに狭くなります。
この狭い隙間を空気が無理に通り抜けようとするとき、周囲の組織が振動し、いびきの音となります。これは、体が「空気が足りない」と訴えているサインでもあります。
危険ないびきと心配ないいびき
いびきには、一時的なものと慢性的なものがあります。
疲労が溜まっている時やお酒を飲んだ後、風邪で鼻が詰まっている時などに一時的にかくびきは、原因が解消されれば治まることが多く、過度に心配する必要はありません。
しかし、毎晩のように大きないびきをかいている場合や、いびきが途中で止まり、大きな呼吸と共に再開するような場合は、注意が必要です。
それは「危険ないびき」、すなわち病気のサインである可能性が高いです。
危険ないびきと心配ないびきの特徴
| 特徴 | 危険ないびき(要注意) | 心配ないびき(一時的) |
|---|---|---|
| 頻度 | ほぼ毎晩、慢性的 | 疲労時、飲酒後、鼻詰まり時など |
| 音 | 非常に大きい、不規則 | 小さい、規則的 |
| 呼吸 | 途中で止まる、むせる、あえぐ | 呼吸は止まらない |
なぜいびきが病気のサインになるのか
慢性的な大きないびきは、気道が常に狭くなっている証拠です。気道が狭いと、睡眠中に十分な酸素を体に取り込むことが難しくなります。特に、気道が完全に塞がってしまうと「無呼吸」状態に陥ります。
この状態が頻繁に起こるのが「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」という病気です。つまり、いびきはSASの最もわかりやすい症状の一つであり、放置してはいけない病気のサインなのです。
いびきと睡眠の質の深い関係
いびきをかいている時、体は酸素不足を補うために、無意識のうちに覚醒(脳が起きる)を繰り返しています。本人はぐっすり眠っているつもりでも、脳や体は十分に休まっていません。
その結果、睡眠の質は著しく低下します。朝起きた時に疲れが取れていない、日中に耐え難い眠気があるといった症状は、この睡眠の質の低下が原因です。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは何か
睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、睡眠中に呼吸が止まったり(無呼吸)、浅くなったり(低呼吸)する状態を繰り返す病気です。
いびきをかく人の多くに、この病気が隠れている可能性があります。この病気の本質は、睡眠中の断続的な酸素不足と、それを補うための覚醒反応による身体への負担です。
睡眠中に呼吸が止まる「無呼吸」の定義
医学的には、気道の空気の流れが10秒以上止まる状態を「無呼吸」と定義します。
また、呼吸が浅くなり、体内の酸素レベルが低下する状態を「低呼吸」と呼びます。睡眠時無呼吸症候群の診断では、この無呼吸と低呼吸が1時間に何回起こるか(AHI:無呼吸低呼吸指数)を指標とします。
SASの主な2つのタイプ
SASは、その原因によって主に2つのタイプに分類されます。最も多いのが「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」で、物理的に上気道が塞がることが原因です。
もう一つは「中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)」で、脳からの呼吸の指令が出なくなることが原因です。
SASの2つのタイプ
| タイプ | 原因 | 特徴 |
|---|---|---|
| 閉塞性(OSAS) | 喉の閉塞(肥満、扁桃肥大、骨格など) | SAS患者の約90%を占める。大きないびきを伴う。 |
| 中枢性(CSAS) | 脳の呼吸中枢の問題(心不全、脳卒中など) | いびきを伴わないこともある。呼吸努力自体が停止する。 |
日本におけるSASの患者数
日本において、睡眠時無呼吸症候群の潜在的な患者数は非常に多いと推定されています。いびきをかく人を含めると、その数は数百万人に上るとも言われています。
しかし、多くの人が「いびきは体質」と思い込み、検査や治療を受けていないのが現状です。日中の眠気や倦怠感を「疲れのせい」と片付けず、病気の可能性を疑うことが重要です。
SASはどのようにして起こるのか
閉塞性SASの主な原因は、睡眠中の筋肉の弛緩です。
起きている時は筋肉が気道を支えていますが、眠ると筋肉が緩み、特に肥満で首周りに脂肪が多い人や、顎が小さい人、扁桃腺が大きい人は、気道が塞がりやすくなります。
アルコールの摂取も筋肉を弛緩させるため、SASを悪化させる大きな要因となります。
危険な症状セルフチェック「病気のサイン」を見逃さない
睡眠時無呼吸症候群の症状は、睡眠中だけでなく日中の活動にも現れます。ご自身やご家族に当てはまるものがないか、確認してみましょう。
これらのサインに早期に気づくことが、重大な合併症を防ぐために必要です。
ご家族が気づく睡眠中のサイン
睡眠中の症状は、ご自身では気づきにくいものがほとんどです。ベッドパートナーやご家族からの指摘が、病気を発見する最も重要な手がかりとなります。
睡眠中のチェックポイント
- 非常に大きないびきをかく
- いびきが突然止まり、しばらくして「ガッ」と大きな呼吸と共に再開する
- 睡眠中に呼吸が苦しそう、あえいでいる
- 寝汗をひどくかく
ご自身で感じる日中の眠気やだるさ
SASの患者様が最も多く訴える症状の一つが、日中の強い眠気です。睡眠の質が悪いため、どれだけ長く寝ても脳と体が休まっていません。
会議中や運転中など、本来起きていなければならない場面で、耐え難い眠気に襲われることがあります。
起床時の頭痛や口の渇き
朝起きた時に、頭が重い、あるいはズキズキと痛む場合、睡眠中の酸素不足が原因かもしれません。体内の酸素が不足すると、脳の血管が拡張して頭痛を引き起こすことがあります。
また、SASの方は口呼吸になっていることが多く、朝起きた時に喉がカラカラに乾いている、口の中がネバネバするといった症状もよく見られます。
集中力の低下や気分の落ち込み
慢性的な睡眠不足と酸素不足は、脳の機能にも影響を与えます。日中の集中力や記憶力が低下し、仕事や家事の効率が落ちることがあります。
また、十分な睡眠が取れない状態が続くと、精神的にも不安定になりやすく、イライラしたり、気分の落ち込みを感じたりすることもあります。
SASセルフチェックリスト
| 分類 | 症状 | チェック |
|---|---|---|
| 睡眠中 | 大きないびきを指摘される | |
| 睡眠中 | 呼吸が止まっていると指摘される | |
| 起床時 | 起きた時にスッキリしない、疲れが取れていない | |
| 起床時 | 口が渇いている、喉が痛い | |
| 起床時 | 頭痛がする | |
| 日中 | 日中に強い眠気がある(会議中、運転中など) | |
| 日中 | 集中力が続かない、物忘れが多い | |
| 日中 | 体がだるい、倦怠感が続く |
いびきやSASを放置する危険な未来
いびきや睡眠時無呼吸症候群を「たかがいびき」「寝不足なだけ」と軽視して放置すると、体に大きな負担がかかり続け、重大な生活習慣病を引き起こす原因となります。
無呼吸による低酸素状態は、じわじわと全身の血管や臓器をむしばんでいきます。
身体が「酸欠状態」になる影響
睡眠中に無呼吸を繰り返すと、血液中の酸素濃度が低下します。体はこれを緊急事態と捉え、酸素を全身に届けようと心臓や血管に大きな負担をかけます。
交感神経が活発になり、血圧や心拍数が上昇します。この状態が毎晩何時間も続くことが、様々な健康問題の引き金となります。
高血圧や心疾患のリスク
SAS患者の約半数は高血圧を合併していると言われています。睡眠中の低酸素状態と交感神経の興奮が、血圧を上昇させます。
通常の高血圧は朝方よりも日中に高くなる傾向がありますが、SASが原因の高血圧は、早朝高血圧や夜間高血圧を引き起こしやすい特徴があります。
薬を飲んでも血圧が下がりにくい「治療抵抗性高血圧」の原因が、実はSASだったというケースも少なくありません。
脳卒中(脳梗塞・脳出血)の危険性
SASによる血圧の上昇や低酸素状態は、脳の血管にも深刻なダメージを与えます。
血管が硬くなる動脈硬化を促進し、脳梗塞や脳出血といった脳卒中を発症するリスクを健常者の数倍に高めると報告されています。
特に夜間や早朝に発症する脳卒中は、SASとの関連が強く疑われます。
糖尿病や脂質異常症との関連
SASによる低酸素状態は、血糖値をコントロールするインスリンの働きを悪くし(インスリン抵抗性)、糖尿病の発症や悪化につながります。
また、脂質の代謝にも異常をきたし、悪玉コレステロール(LDL)や中性脂肪が増加する脂質異常症を引き起こすことも知られています。
SASが引き起こす可能性のある主な合併症
| 分類 | 具体的な病名 |
|---|---|
| 循環器系 | 高血圧、不整脈、心筋梗塞、狭心症、心不全 |
| 脳血管系 | 脳梗塞、脳出血(脳卒中) |
| 代謝系 | 糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症(痛風) |
いびきやSASの原因となる生活習慣
睡眠時無呼吸症候群、特に閉塞性タイプは、日々の生活習慣や体型が大きく関わっています。原因を知ることが、予防と対策の第一歩です。
ご自身の生活を見直すことで、症状の改善が期待できる場合もあります。
肥満と気道の関係
SASの最大の原因の一つが肥満です。特に、首周りや喉、舌に脂肪がつくと、上気道が内側から圧迫されて狭くなります。仰向けに寝ると、脂肪の重みで気道はさらに塞がりやすくなります。
肥満の方が減量するだけで、いびきや無呼吸の症状が劇的に改善することは珍しくありません。
アルコール(飲酒)の影響
アルコールは、喉の筋肉(上気道を開いておく筋肉)を弛緩させる作用があります。普段はいびきをかかない人でも、寝る前にお酒を飲むといびきをかきやすくなるのはこのためです。
SASの患者様が飲酒すると、無呼吸の回数が増え、時間も長くなるため、非常に危険です。
喫煙が気道に与えるダメージ
喫煙は、タバコの煙に含まれる有害物質が喉や鼻の粘膜に慢性的な炎症を引き起こします。炎症によって粘膜が腫れると、気道が狭くなり、いびきや無呼吸が悪化します。
また、喫煙は睡眠中の覚醒を引き起こしやすく、睡眠の質自体を低下させる要因にもなります。
仰向け寝のリスク
仰向けで寝ると、重力の影響で舌の付け根(舌根)や軟口蓋が喉の奥に落ち込みやすくなります。その結果、気道が物理的に狭くなり、いびきや無呼吸が発生しやすくなります。
特にアジア人は欧米人に比べて顎が小さい骨格の人が多く、肥満でなくても仰向け寝で気道が塞がりやすい傾向があります。
SASのリスクを高める要因
| 要因 | 気道への影響 |
|---|---|
| 肥満(特に首周り) | 脂肪によって気道が内側から圧迫される |
| アルコール | 喉の筋肉が弛緩し、舌根が落ち込みやすくなる |
| 喫煙 | 気道粘膜の炎症と腫れを引き起こす |
| 仰向け寝 | 重力で舌根が喉の奥に落ち込む |
| 骨格(顎が小さい等) | もともと気道のスペースが狭い |
クリニックで行う検査と診断
「もしかしてSASかも?」と不安に感じたら、専門のクリニックで検査を受けることが重要です。いびきや無呼吸の状態を客観的に評価し、適切な治療方針を決めるために検査は欠かせません。
まずは簡易検査でご自身の睡眠状態を知ることができます。
まずは自宅でできる「簡易検査」
クリニックを受診すると、まずはご自宅でできる「簡易検査(簡易ポリソムノグラフィー)」を行うことが一般的です。
これは、手のひらサイズの小さな検査機器をご自身で装着して、一晩寝ていただく検査です。指先に酸素濃度を測るセンサー、鼻に呼吸の状態をみるチューブなどを取り付けるだけで、痛みはありません。
簡易検査で何がわかるのか
簡易検査では、睡眠中の呼吸の状態、血液中の酸素濃度、いびきの音、脈拍などを記録します。
この結果から、1時間あたりに無呼吸や低呼吸が何回あったか(AHI)を算出します。このAHIの数値によって、SASの重症度を大まかに把握することができます。
さらに詳しい「精密検査(PSG検査)」
簡易検査でSASの疑いが強いと判断された場合や、他の睡眠障害が疑われる場合には、さらに詳しい「精密検査(終夜ポリソムノグラフィー:PSG検査)」を行います。
これは通常、病院やクリニックに一泊入院して行う検査です。脳波、眼球運動、筋電図、呼吸、酸素濃度など、より多くのセンサーを体に取り付け、睡眠の質と呼吸状態を詳細に調べます。
簡易検査と精密検査の比較
| 項目 | 簡易検査 | 精密検査(PSG検査) |
|---|---|---|
| 場所 | 自宅 | 病院・クリニック(1泊) |
| 検査項目 | 呼吸、酸素濃度、脈拍、いびき音など | 上記に加え、脳波、眼球運動、筋電図など |
| わかること | 無呼吸・低呼吸の回数(AHI) | AHIに加え、睡眠の深さ、覚醒回数など |
診断の基準となるAHI(無呼吸低呼吸指数)
AHI(Apnea Hypopnea Index)は、睡眠1時間あたりの「無呼吸」と「低呼吸」の合計回数を示す数値です。このAHIがSASの診断と重症度の判定基準となります。
AHIによる重症度分類
| AHI(1時間あたりの回数) | 重症度 |
|---|---|
| 5回未満 | 正常 |
| 5回以上 15回未満 | 軽症 |
| 15回以上 30回未満 | 中等症 |
| 30回以上 | 重症 |
例えば、AHIが30回の場合、1時間に30回、つまり平均して2分に1回のペースで呼吸が止まっているか浅くなっていることを意味し、体への負担が非常に大きいことがわかります。
主な治療法とセルフケア
睡眠時無呼吸症候群の治療は、重症度や原因、患者様のライフスタイルに応じて様々な方法があります。代表的な治療法と並行し、ご自身での生活改善も大切です。
治療の目的は、睡眠中の無呼吸や低呼吸をなくし、睡眠の質を改善することで、日中の症状を解消し、将来の合併症を予防することです。
CPAP(シーパップ)療法とは
CPAP(Continuous Positive Airway Pressure:持続陽圧呼吸療法)は、中等症から重症のSASに対する最も標準的で効果の高い治療法です。
これは、寝ている間に鼻に装着したマスクから、機械で空気を送り込み、気道が塞がらないように内側から圧力をかける治療法です。
空気を送り込むことで、喉の奥のスペースを物理的に広げ、呼吸の通り道を確保します。
CPAP療法を始めると、その日の夜からいびきや無呼吸がなくなり、ぐっすり眠れるようになります。多くの方が、翌朝の目覚めのスッキリ感や日中の眠気の劇的な改善を実感されます。
マウスピース(口腔内装置)による治療
軽症から中等症の患者様や、CPAP療法の使用が難しい方には、マウスピース(口腔内装置)による治療が選択されることがあります。
これは、寝ている間に特殊なマウスピースを装着し、下の顎を上の顎よりも少し前に突き出させた状態で固定するものです。
下の顎を前に出すことで、舌根が喉の奥に落ち込むのを防ぎ、気道を広げる効果があります。
生活習慣の改善(減量・禁酒禁煙)
SASの治療において、原因となっている生活習慣の改善は非常に重要です。特に肥満が原因の場合、減量が最も根本的な治療となることがあります。
体重を5%から10%減らすだけでも、AHIが大幅に改善することが報告されています。また、前述の通り、寝る前のアルコール摂取を控えること、禁煙することも、症状の悪化を防ぐために大切です。
横向き寝の推奨
仰向けで寝ると無呼吸が悪化し、横向きで寝ると症状が改善する(体位依存性)患者様も多くいます。そのような方には、横向きで寝る習慣をつけることが有効な場合があります。
抱き枕を利用したり、背中にクッションを当てたりするなど、自然と横向きを維持できる工夫を試してみるのも良いでしょう。
よくある質問
睡眠時無呼吸症候群に関して、患者様から多く寄せられるご質問にお答えします。
- Qいびきをかいていなければ大丈夫ですか?
- A
いびきはSASの大きなサインの一つですが、まれにいびきをかかなくても呼吸が浅くなる「低呼吸」を主体とするSASの方もいます。
また、中枢性(CSAS)の場合もいびきを伴わないことがあります。
日中に強い眠気や倦怠感、起床時の頭痛など、他の症状がある場合は、いびきがなくても一度検査を検討することをお勧めします。
- Q子どもでも睡眠時無呼吸症候群になりますか?
- A
はい、お子様でもSASになることがあります。小児のSASの主な原因は、大人の肥満とは異なり、アデノイド(鼻の奥にあるリンパ組織)や扁桃腺の肥大がほとんどです。
いびきや無呼吸のほか、お口ポカン、寝相の悪さ、夜尿(おねしょ)、日中の落ち着きのなさ、学業不振、成長の遅れなどが見られる場合は、小児科や耳鼻咽喉科にご相談ください。
- Q治療はどのくらいの期間続けますか?
- A
治療期間は、SASの原因や重症度によって異なります。CPAP療法やマウスピース治療は、気道が塞がるのを防ぐ対症療法であり、使用している間だけ効果があります。
肥満が原因の方が減量に成功するなど、根本的な原因が解消されれば、治療が不要になることもあります。
しかし、骨格的な問題が原因の場合は、継続的な治療が必要となることが多いです。
- Q検査や治療は痛いですか?
- A
簡易検査も精密検査も、体にセンサーを取り付けるだけで、針を刺したりするものではないため、痛みは全くありません。
CPAP療法も空気を送り込むだけなので痛みはありませんが、使い始めはマスクの装着感や空気の圧に違和感を覚える方もいます。しかし、ほとんどの方は数日から数週間で慣れていきます。
- Q痩せている人でもSASになりますか?
- A
はい、なります。肥満はSASの大きな原因ですが、痩せている方でもSASになることはあります。
これは、顎が小さい、首が短い、下顎が後退している、扁桃腺が大きいなど、もともとの骨格や気道の構造的な問題で、気道が狭くなっているためです。
特に日本人を含むアジア人は、欧米人に比べて骨格的にSASになりやすいと言われています。