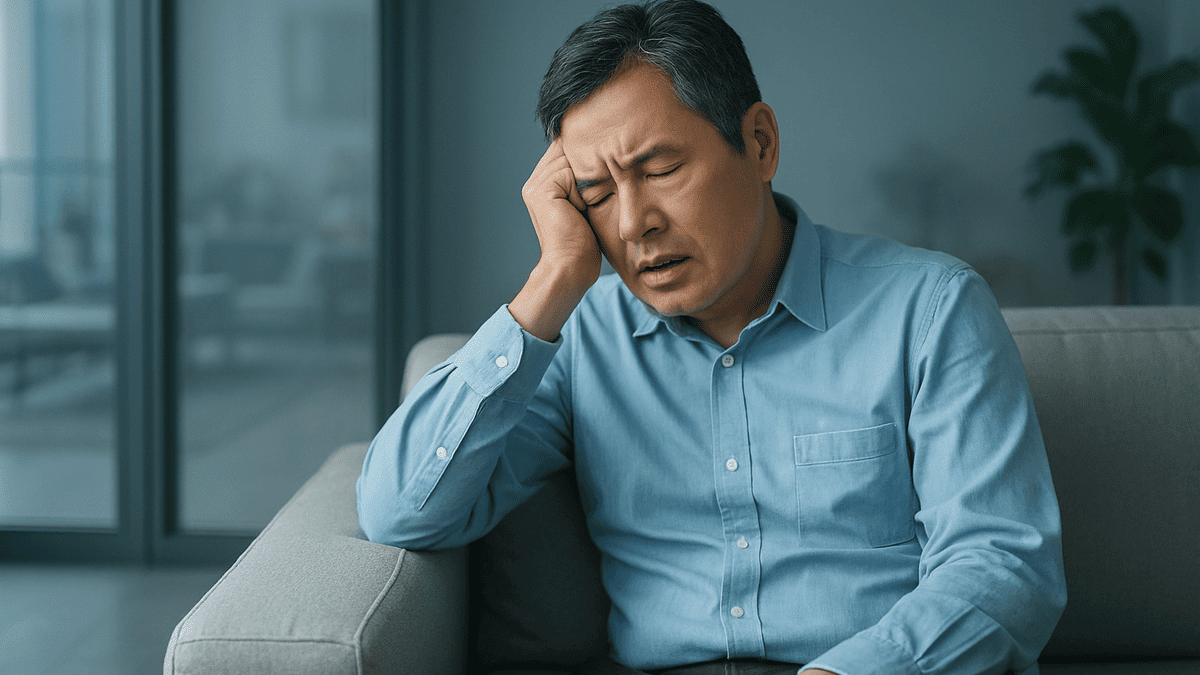会議中や運転中、耐えがたいほどの眠気に襲われることはありませんか。
夜に十分寝ているつもりでも日中眠いなら、それは単なる寝不足ではなく「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」のサインかもしれません。
この記事では、なぜこの病気で異常な眠気が生じるのか、その原因と放置する危険性、自分でできる眠気のチェック方法まで詳しく解説します。
隠れた病気を見逃さず、健やかな毎日を取り戻しましょう。
なぜ睡眠時無呼吸症候群で日中眠くなるのか
日中の強い眠気は、睡眠時無呼吸症候群の最も代表的な症状です。その背景には、睡眠中に繰り返される「無呼吸」が引き起こす、深刻な睡眠の質の低下があります。
睡眠の質を低下させる「無呼吸」と「低呼吸」
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に空気の通り道である上気道が狭くなることで、10秒以上の呼吸停止(無呼吸)や、呼吸が浅くなる状態(低呼吸)を繰り返す病気です。
この状態が一晩に何十回、何百回と起こることで、体は深い睡眠に入れなくなります。
脳が覚醒を繰り返す「睡眠の分断」
呼吸が止まると体は酸素不足を補おうとして、脳に「起きろ」という指令を出します。このため、本人は気づかないうちに、一晩中ごく短い覚醒(マイクロアローザル)を繰り返すことになります。
この「睡眠の分断」が熟睡感を奪い、睡眠時間を長く取っても疲れがとれない状態を作り出します。
健常な睡眠とSAS患者の睡眠の違い
| 項目 | 健常な睡眠 | SAS患者の睡眠 |
|---|---|---|
| 睡眠構造 | 深い睡眠が十分とれる | 覚醒反応が頻発し、浅い睡眠ばかりになる |
| 呼吸 | 安定している | 無呼吸・低呼吸を繰り返す |
| 起床時 | すっきりしている | 頭痛、倦怠感がある |
体内が酸欠状態になる影響
無呼吸が続くと、血液中の酸素濃度が低下します。この低酸素状態は脳や心臓をはじめとする全身の臓器に大きな負担をかけます。
日中の眠気だけでなく、長期的には様々な生活習慣病を引き起こす原因ともなります。
ただの眠気ではない!SAS特有の眠気の特徴
睡眠時無呼吸症候群による眠気は、一般的な寝不足とは少し性質が異なります。特徴的なサインに気づくことが早期発見の鍵です。
状況を選ばない強い眠気
最も特徴的なのは、本来眠ってはいけない状況、例えば大切な会議中、車の運転中、人と話している最中などに、自分ではコントロールできないほどの強い眠気に襲われることです。
これは「過眠」と呼ばれ、単なる眠気とは区別します。
集中力や記憶力の低下
質の悪い睡眠が続くと脳が十分に休息できず、日中のパフォーマンスが著しく低下します。
仕事での単純なミスが増えたり、新しいことを覚えられなくなったり、物事への意欲が低下したりするのも重要なサインの一つです。
SASが引き起こす日中の症状
| 症状の種類 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 精神・認知機能 | 集中力低下、記憶障害、意欲減退 |
| 身体的症状 | 起床時の頭痛、倦怠感、夜間頻尿 |
| 睡眠中の症状 | 大きないびき、呼吸が止まる、寝汗 |
起床時の頭痛やだるさ
朝起きた時に頭が重い、すっきりしない、熟睡感がない、といった症状もよく見られます。
これは睡眠中の低酸素状態によって脳の血管が拡張することや、睡眠が分断されて疲れが取れていないことが原因と考えられています。
日中の眠気が引き起こす危険なサイン
「眠いだけ」と軽視していると、取り返しのつかない事態を招くことがあります。睡眠時無呼吸症候群の眠気がもたらす具体的なリスクについて解説します。
居眠り運転による交通事故のリスク
睡眠時無呼吸症候群の患者さんは、健康な人と比べて交通事故を起こすリスクが数倍高いという報告があります。
特に高速道路や信号の少ない道など、単調な状況で突然眠りに落ちてしまうことがあり、非常に危険です。
眠気が引き起こす運転中の危険
- 居眠り運転
- 注意散漫による判断ミス
- 反応時間の遅れ
労働災害や仕事の能率低下
集中力の低下は仕事のパフォーマンスを落とすだけでなく、機械の操作ミスなどによる労働災害の原因にもなります。
社会生活全体に大きな影響を及ぼす問題です。
生活習慣病との深い関係
睡眠中の無呼吸と低酸素は体に強いストレスを与え、交感神経を過剰に刺激します。
これらの影響により、高血圧、心臓病、脳卒中、糖尿病といった命に関わる生活習慣病を発症・悪化させるリスクが著しく高まることが分かっています。
SASと関連の深い生活習慣病
| 疾患名 | SAS患者における発症リスク |
|---|---|
| 高血圧 | 約1.4~2.9倍 |
| 心不全・不整脈 | 約2~4倍 |
| 糖尿病 | 約1.5倍 |
眠気のセルフチェックと評価方法
ご自身の日中の眠気がどの程度のものなのか、客観的に評価する方法があります。医療機関でも用いられる簡単な質問票を紹介します。
エプワース眠気尺度(ESS)とは
エプワース眠気尺度(Epworth Sleepiness Scale、略してESS)は、日中の眠気の程度を評価するために世界中で広く使われている質問票です。
8つの具体的な状況下で、どのくらいうとうとする(眠ってしまう)かを点数で回答します。
ESSを使った自己評価の方法
以下の状況で、過去1ヶ月の間にどのくらいうとうとしたかを0~3点の4段階で評価し、合計点を出します。
合計点が11点以上の場合になると病的な眠気の可能性があり、専門医への相談が推奨されます。
エプワース眠気尺度(ESS)の質問
| 状況 | 点数 (0-3) |
|---|---|
| 座って読書をしている時 | 0: 全くない 1: ときどきある 2: よくある 3: いつもある |
| テレビを見ている時 | |
| 会議や劇場などで座っている時 | |
| 車に乗せてもらって1時間休まずにいる時 | |
| 午後に横になって休んでいる時 | |
| 座って誰かと話している時 | |
| 昼食後(飲酒なし)に静かに座っている時 | |
| 車を運転中、信号などで数分止まっている時 |
セルフチェックで注意すべき点
このチェックはあくまで簡易的な目安です。
点数が低くても、いびきや呼吸の停止を家族から指摘されている場合や、日中のだるさが続く場合は睡眠時無呼吸症候群が隠れている可能性があります。
気になる症状があれば、点数にかかわらず専門医に相談しましょう。
眠気の原因はSASだけではない?他の病気の可能性
日中の強い眠気を引き起こす病気は睡眠時無呼吸症候群だけではありません。正しい診断を受けるためにも、他の病気の可能性を知っておくことは大切です。
ナルコレプシーとの違い
ナルコレプシーも日中に耐えがたい眠気が突然現れる病気です。
しかし、笑ったり驚いたりした時に体の力が抜ける「情動脱力発作」を伴うことが多いなど、睡眠時無呼吸症候群とは異なる特徴があります。
SASとナルコレプシーの主な違い
| 特徴 | 睡眠時無呼吸症候群(SAS) | ナルコレプシー |
|---|---|---|
| 主な原因 | 上気道の閉塞 | 脳内の覚醒維持物質の異常 |
| 夜間の睡眠 | いびき、無呼吸、中途覚醒 | 金縛り、鮮明な夢 |
| 特有の症状 | 起床時の頭痛 | 情動脱力発作 |
うつ病など精神的な不調
うつ病などの精神的な不調でも、過眠や倦怠感が症状として現れることがあります。
睡眠時無呼吸症候群とうつ病は合併することも少なくなく、両面からのアプローチが必要な場合もあります。
甲状腺機能低下症などの内科的疾患
体の新陳代謝をコントロールする甲状腺ホルモンの分泌が低下する「甲状腺機能低下症」や、腎臓の機能が低下する「腎不全」など、内科的な病気が原因で強い倦怠感や眠気が生じることもあります。
眠気の原因を調べる検査と治療
「眠い」という症状の裏に何が隠れているのかを突き止め、適切な治療につなげるための流れを解説します。
問診と診察で原因を探る
まずは専門の医療機関を受診し、医師に詳しい症状を伝えることが第一歩です。
眠気の程度や頻度、いびきの有無、生活習慣、既往歴などを詳しく問診し、原因を探ります。
睡眠の状態を調べる検査
睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、まずは自宅でできる簡易検査や、入院して行う精密検査(PSG)で睡眠中の呼吸状態を評価します。
これらの検査で無呼吸の重症度を客観的に診断します。
診断までの流れ
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1. 受診・問診 | 症状や生活習慣の聞き取り |
| 2. 検査 | 簡易検査または精密検査(PSG) |
| 3. 診断・治療方針決定 | 検査結果に基づき重症度を判定 |
眠気を改善する治療法
診断が確定すれば、治療を開始します。最も標準的な治療は睡眠中に鼻に装着したマスクから空気を送り、気道の閉塞を防ぐ「CPAP(シーパップ)療法」です。
この治療によって睡眠の質が劇的に改善し、日中の眠気も解消されることが期待できます。
主な治療法
- CPAP療法
- マウスピース(口腔内装置)
- 生活習慣の改善(減量など)
よくある質問
最後に、睡眠時無呼吸症候群と眠気に関してよくある質問にお答えします。
- Q治療を始めたら眠気はすぐになくなりますか?
- A
CPAP療法を開始した多くの方は、治療を始めた初日や数日後から「朝の目覚めが違う」「日中眠くならなくなった」と効果を実感します。
ただし、効果の現れ方には個人差があり、数週間から数ヶ月かけて徐々に改善していく場合もあります。
- Q眠気覚ましのコーヒーは効果がありますか?
- A
カフェインには一時的な覚醒作用がありますが、睡眠時無呼吸症候群による根本的な睡眠不足を解決するものではありません。
特に運転前などに頼るのは危険です。眠気の原因を突き止め、適切な治療を受けることが重要です。
- Q家族にいびきを指摘されたら、眠気がなくても受診すべきですか?
- A
はい、受診を強くお勧めします。
日中の眠気は代表的な症状ですが、自覚症状がなくても、体は無呼吸によるダメージを受けている可能性があります。
大きないびきや呼吸の停止は、それ自体が受診を考えるべき重要なサインです。
- Q痩せ型でも睡眠時無呼吸症候群になりますか?
- A
はい、なります。
肥満は大きなリスク因子ですが、あごが小さい、首が短い、扁桃腺が大きいといった骨格や気道の構造的な特徴によって、痩せている方でも発症します。
体型に関わらず、気になる症状があれば専門医に相談してください。
以上
参考にした論文
KANEITA, Yoshitaka, et al. Excessive daytime sleepiness among the Japanese general population. Journal of epidemiology, 2005, 15.1: 1-8.
OGAKI, Keitaro, et al. Factors contributing to sleep disturbances and excessive daytime sleepiness in patients with Parkinson’s disease. Frontiers in neurology, 2023, 14: 1097251.
TSUKADA, Eriko, et al. Prevalence of childhood obstructive sleep apnea syndrome and its role in daytime sleepiness. PloS one, 2018, 13.10: e0204409.
MATSUI, Kentaro, et al. Insufficient sleep rather than the apnea–hypopnea index can be associated with sleepiness-related driving problems of Japanese obstructive sleep apnea syndrome patients residing in metropolitan areas. Sleep medicine, 2017, 33: 19-22.
SUZUKI, Keisuke, et al. Excessive daytime sleepiness and sleep episodes in Japanese patients with Parkinson’s disease. Journal of the neurological sciences, 2008, 271.1-2: 47-52.]
OHTA, Y., et al. Prevalence of risk factors for sleep apnea in Japan: a preliminary report. Sleep, 1993, 16.suppl_8: S6-S7.
DOI, Yuriko; MINOWA, Masumi. Gender differences in excessive daytime sleepiness among Japanese workers. Social Science & Medicine, 2003, 56.4: 883-894.
GAINA, Alexandru, et al. Daytime sleepiness and associated factors in Japanese school children. The Journal of pediatrics, 2007, 151.5: 518-522. e4.
UDAKA, Tsuyoshi, et al. Relationships between nasal obstruction, observed apnea, and daytime sleepiness. Otolaryngology—Head and Neck Surgery, 2007, 137.4: 669-673.
INOUE, Yuichi; TAKASAKI, Yuji; YAMASHIRO, Yoshihiro. Efficacy and safety of adjunctive modafinil treatment on residual excessive daytime sleepiness among nasal continuous positive airway pressure-treated Japanese patients with obstructive sleep apnea syndrome: a double-blind placebo-controlled study. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2013, 9.8: 751-757.