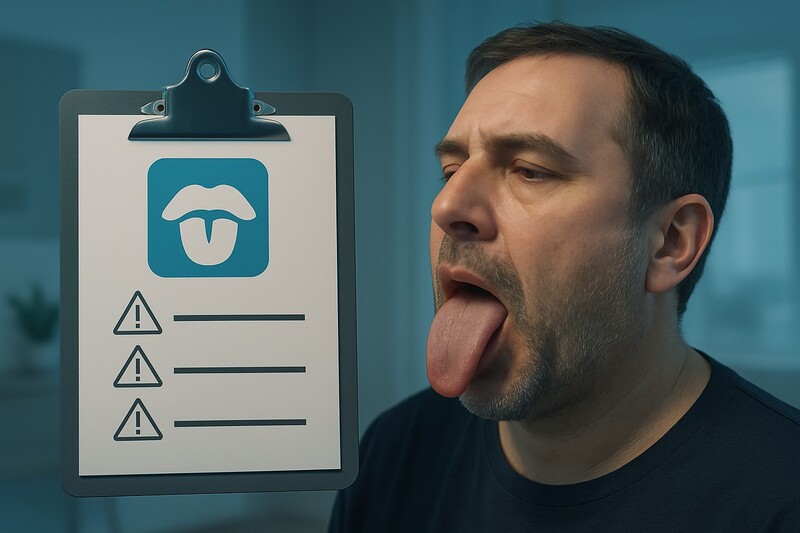いびきや日中の眠気でお悩みの方の中には「自分の舌が大きいからでは?」と感じている方もいるかもしれません。
実は舌の大きさや形状は睡眠時無呼吸症候群(SAS)のリスクと深く関わっています。
この記事ではSASの危険度を考える上で重要な「舌」の特徴に注目し、どのような舌がSASと関連しやすいのか、自分でできる簡単なチェック方法、そして注意点について解説します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)と気道の関係
睡眠時無呼吸症候群(SAS)、特に最も多い閉塞性SASは、睡眠中に空気の通り道である「上気道」が狭くなったり、完全に塞がったりすることで発生します。
上気道は鼻からのど(咽頭)までの部分を指し、舌はこの上気道の空間に大きく影響を与える重要な要素です。
上気道の構造
上気道は鼻腔、咽頭(鼻咽頭、中咽頭、下咽頭)、喉頭から構成されます。
このうち特に咽頭部分は周囲に骨のような硬い支えがなく筋肉や軟部組織でできているため、睡眠中に筋肉が弛緩すると狭くなりやすい特徴があります。
睡眠中の気道の変化
起きている間は筋肉の働きによって気道の広さが保たれています。しかし睡眠中、特に深い睡眠(ノンレム睡眠)やレム睡眠中は全身の筋肉が弛緩します。
この筋肉が弛緩により上気道の周りの筋肉も緩み、気道が狭くなりやすくなります。
睡眠段階と筋弛緩
| 睡眠段階 | 筋肉の緊張度 | 気道の状態 |
|---|---|---|
| 覚醒時 | 高い | 広く保たれる |
| ノンレム睡眠 | 低下 | やや狭くなる傾向 |
| レム睡眠 | 著しく低下(弛緩) | 最も狭くなりやすい |
舌が気道に与える影響
舌は筋肉の塊であり、その付け根(舌根)は中咽頭の後壁に接しています。
睡眠中に舌を支える筋肉が弛緩すると重力によって舌根がのどの奥(後方)に落ち込みやすくなります。これを舌根沈下と呼びます。
舌が大きい場合や舌を収めるスペースである下顎が小さい場合、この舌根沈下が起こりやすく、気道を狭窄・閉塞させる大きな原因となります。
SASリスクを高める舌の特徴
すべての人の舌が同じ形状や大きさではありません。
特定の舌の特徴は睡眠中の気道閉塞のリスクを高めることが知られています。鏡の前でご自身の舌を観察してみましょう。
舌の大きさ(巨大舌)
口の中のスペースに対して相対的に舌が大きい場合、舌根沈下が起こりやすくなります。
舌が大きいかどうかは口を開けたときの舌の見える範囲や、後述する歯の圧痕(歯痕)の有無などで推測できます。
舌の厚み・脂肪沈着
舌の体積が大きいだけでなく、舌内部への脂肪沈着が多いこともSASのリスクを高める要因として注目されています。
肥満の方は全身だけでなく舌にも脂肪がつきやすく、舌の体積が増加して気道を圧迫しやすくなります。これは「舌脂肪」とも呼ばれます。
肥満と舌脂肪の関係
| 指標 | SASとの関連 | 舌への影響 |
|---|---|---|
| BMI (体格指数) | 高いほどリスク増 | 全身の肥満と相関 |
| 首周りの太さ | 太いほどリスク増 | 気道周囲の脂肪と関連 |
| 舌脂肪量 | 多いほどリスク増 | 舌の体積増加、可動性低下 |
舌の側面の圧痕(歯痕舌)
舌の縁に波状の歯の跡がついている状態を「歯痕舌(しこんぜつ)」と呼びます。
これは舌が口の中で歯列に押し付けられていることを示唆し、相対的に舌が大きい、あるいは口の中のスペースが狭い(下顎が小さいなど)ことを反映している可能性があります。
歯痕が明瞭な場合はSASのリスクが高い可能性があります。
舌の位置(低位舌)
安静時に舌の先端が下の前歯の裏側についていたり、舌全体がだらんと下がっていたりする状態を「低位舌(ていいぜつ)」と呼びます。
通常、舌は上顎の口蓋部分に軽く接触しています。低位舌の場合、舌を支える筋力が低下している可能性があり、睡眠中に舌根が沈下しやすくなります。
SASリスクに関連する舌の特徴まとめ
- 舌が大きい(口の中を占める割合が大きい)
- 舌に厚みがある、脂肪が多いと感じる
- 舌の側面に歯の跡(歯痕)がついている
- 安静時に舌が下の歯についている、または下がっている(低位舌)
自分でできる舌の危険度チェック方法
専門的な診断ではありませんが、ご自身の舌の状態を観察することでSASのリスクをある程度推測することができます。
鏡を用意して以下の点をチェックしてみましょう。
鏡を使った観察
明るい場所で鏡の前に立ち、リラックスして口を開けて舌を自然な位置で観察します。舌を無理に前に出したり力を入れたりしないでください。
チェックポイント
- 舌の大きさ: 口を開けたとき舌が口の中のスペースに対してどのくらいの割合を占めているか確認します。舌が大きく盛り上がって見えるか、口の中がいっぱいに見えるかなどを観察します。
- 歯痕の有無: 舌の左右の縁に波のようなギザギザした歯の跡がついていないか確認します。
- 舌の色・状態: 舌の色が白っぽかったり、むくんでいるように見えたりする場合も舌の機能低下や体調不良のサインである可能性があります(SASとの直接的な関連は限定的ですが、参考情報となります)。
- 舌の安静時の位置: 意識せずに口を閉じているとき、舌の先端や全体がどこに触れているか感じてみます。上顎についているか、下の歯の裏についているか、あるいはどこにも触れずに下がっているか確認します(低位舌のチェック)。
Mallampati(マランパチ)分類の応用
Mallampati分類はもともと麻酔科医が気管挿管の難易度を評価するために使う指標ですが、SASのリスク評価にも応用されます。
口を大きく開けて舌をできるだけ前に出した状態で、のどの奥(口蓋垂や軟口蓋)がどの程度見えるかを評価します。
簡易Mallampati分類によるチェック
| クラス | 見える範囲 | SASリスクの目安 |
|---|---|---|
| クラスI | 口蓋垂、口蓋弓、軟口蓋が完全に見える | 低い |
| クラスII | 口蓋垂の上部が舌で隠れる | やや低い |
| クラスIII | 軟口蓋と口蓋垂の付け根のみ見える | 高い |
| クラスIV | 軟口蓋が完全に見えない | 非常に高い |
クラスIIIやクラスIVに該当する場合、舌が大きい、あるいは上気道が狭い可能性があり、SASのリスクが高いと考えられます。
チェック時の注意点
これらのチェックはあくまで簡易的な目安です。舌の特徴だけでSASの有無や重症度を確定することはできません。
また、観察時の口の開け方や舌の出し方によって見え方が変わることもあります。
舌の形状以外に考慮すべきSASのリスク因子
SASのリスクは舌の形状だけで決まるわけではありません。他の様々な要因も複合的に関与します。
舌のチェックと合わせて以下のリスク因子についても考慮することが重要です。
肥満(BMI・首周り)
体重増加、特に首周りの脂肪増加は、気道を直接圧迫し、SASの最も大きなリスク因子の一つです。
BMIが25以上、または首周りが太い(男性43cm以上、女性38cm以上が目安)場合は注意が必要です。
顎の骨格
下顎が小さい、後退している、あるいは上顎が狭いなどの骨格的な特徴は舌が収まるスペースを狭め、気道閉塞のリスクを高めます。
これは痩せている人でもSASになる原因となります。
骨格的なリスク因子
| 部位 | 特徴 | 気道への影響 |
|---|---|---|
| 下顎 | 小さい、後退している | 舌が後方に落ち込みやすい |
| 上顎 | 狭い、歯並びが悪い | 鼻腔や咽頭腔が狭い可能性 |
| 顔貌 | 面長、首が短い・太い | 気道構造に影響 |
年齢・性別
加齢とともに筋力が低下し、気道が弛緩しやすくなるため、SASのリスクは高まります。
また、一般的に男性の方が女性よりもSASになりやすい傾向があります。ただし、女性も閉経後にはリスクが上昇します。
生活習慣
寝る前の飲酒、喫煙、特定の薬剤(睡眠薬、筋弛緩薬など)の使用は気道の筋肉を弛緩させたり、炎症を起こしたりしてSASのリスクを高める可能性があります。
リスクを高める生活習慣
- 習慣的な飲酒(特に就寝前)
- 喫煙
- 仰向け寝(舌根沈下を助長しやすい)
舌のチェックとSAS診断の限界
舌の形状やMallampati分類によるチェックはSASのリスクを推測する上で有用な情報を提供しますが、それだけで確定診断はできません。
自己判断には限界があることを理解しておく必要があります。
確定診断には睡眠検査が必要
SASの確定診断と重症度の評価には睡眠中の呼吸状態を客観的に記録する睡眠検査(簡易検査または精密検査)が不可欠です。
これらの検査によって実際に無呼吸や低呼吸がどのくらいの頻度(AHI)で発生しているか、血中酸素飽和度がどの程度低下しているかなどを評価します。
舌の特徴と重症度は必ずしも一致しない
舌が大きい、歯痕がある、Mallampati分類でクラスIII/IVであるといった特徴があっても、必ずしも重症のSASであるとは限りません。
逆に、舌の特徴があまり目立たなくても重症のSASである場合もあります。症状の感じ方にも個人差があります。
自己チェックと専門診断の比較
| 評価項目 | 舌の自己チェック | 専門医による診断 |
|---|---|---|
| 評価内容 | 形態的なリスクの推測 | 形態評価+睡眠検査による機能評価 |
| 客観性 | 主観的、限定的 | 客観的データに基づく |
| 診断精度 | 低い(あくまで目安) | 高い(確定診断) |
他の要因の重要性
前述の通り、SASのリスクは舌の形状だけでなく、肥満、骨格、年齢、生活習慣など多くの要因が複合的に関わっています。
舌のチェックだけで安心したり、過度に心配したりせず、総合的に判断することが大切です。
舌の特徴が気になったら:専門医への相談
舌のチェックでSASのリスクが高い可能性を感じた場合や、いびき、日中の眠気などの自覚症状がある場合は、自己判断せずに専門医に相談しましょう。
受診の目安
以下のいずれかに当てはまる場合は、医療機関の受診を検討してください。
受診を推奨するケース
- 舌が大きい、歯痕が明瞭、Mallampati分類III/IVなどに該当する
- 大きないびきや睡眠中の呼吸停止を指摘される
- 日中に強い眠気や倦怠感がある
- 起床時に頭痛や口の渇きがある
- 肥満、高血圧、糖尿病などの生活習慣病がある
どの診療科を受診すべきか
睡眠時無呼吸症候群の診断・治療は、主に以下の診療科で行っています。
- 呼吸器内科
- 睡眠専門クリニック
- 耳鼻咽喉科
- 一部の内科、循環器内科など
どの科を受診すればよいか分からない場合は、まずはかかりつけ医に相談するか、お近くの睡眠医療に対応しているクリニックを探してみましょう。
診察時に伝えること
診察時には、ご自身でチェックした舌の特徴(大きさ、歯痕など)に加えて、いびきや眠気などの具体的な症状、生活習慣、既往歴などをできるだけ詳しく医師に伝えてください。
ご家族から見た睡眠中の様子なども重要な情報です。
診断と治療へ
医師は問診や診察、必要に応じて睡眠検査を行い、SASの診断と重症度を評価します。診断結果に基づき、CPAP療法、マウスピース治療、生活習慣の改善など個々の患者さんに合った治療方針を提案します。
舌の特徴がSASのリスクを高めている場合でも適切な治療を行えば症状の改善が期待できます。
よくある質問
Q1. 舌のトレーニング(あいうべ体操など)はSASに効果がありますか?
A1. 舌や口周りの筋肉を鍛えるトレーニング(口腔筋機能療法)は舌の位置を改善したり、気道の筋力を高めたりする効果が期待され、軽症のSASやいびきの改善に役立つ可能性があります。
代表的なものに「あいうべ体操」などがあります。
ただし効果には個人差があり、中等症以上のSASに対する効果は限定的と考えられています。CPAP療法などの標準治療と併用する、あるいは軽症例で試みるなどの位置づけになります。
実施する場合は自己流ではなく、医師や歯科医師の指導のもとで行うことが望ましいです。
Q2. 舌が大きいのですが、手術で小さくすることはできますか?
A2. 舌の一部を切除して小さくする手術(舌縮小術)も存在しますが、侵襲が大きく、出血や味覚障害、構音障害などのリスクも伴うため一般的にはあまり行われていません。
SASの外科治療としては口蓋垂や扁桃を切除する手術(UPPP)や、顎の骨を切って移動させる手術などが選択される場合がありますが、これらの手術も適応は限られます。
まずはCPAP療法やマウスピース治療などの保存的治療が優先されます。
Q3. 子供の舌にも歯痕がありますが、SASの可能性がありますか?
A3. 子供の舌に歯痕が見られる場合も大人と同様に舌が大きい、あるいは顎が小さいなどの可能性を示唆します。
子供のSASはアデノイド・扁桃肥大が主な原因であることが多いですが、舌や顎の問題が関与していることもあります。
いびき、口呼吸、落ち着きのなさ、おねしょなどの症状が見られる場合は小児科や耳鼻咽喉科に相談してください。
Q4. 舌のチェックだけでSASかどうか分かりますか?
A4. いいえ、舌のチェックだけでSASの確定診断はできません。舌の大きさや形状、歯痕の有無、Mallampati分類などは、あくまでSASのリスクを推測するための参考情報です。
確定診断には睡眠中の呼吸状態を客観的に評価する睡眠検査(簡易検査または精密検査)が必要です。
舌の特徴が気になる場合やSASが疑われる症状がある場合は必ず専門医の診察を受けてください。
以上
参考にした論文
TAKAI, Yujiro, et al. Cephalometric assessment of craniofacial morphology in Japanese male patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. Sleep and biological rhythms, 2012, 10: 162-168.
ISHIGURO, Keishi, et al. Relationship between severity of sleep-disordered breathing and craniofacial morphology in Japanese male patients. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 2009, 107.3: 343-349.
SATA, Naoko, et al. Clinical, polysomnographic, and cephalometric features of obstructive sleep apnea with AHI over 100. Sleep and Breathing, 2021, 25: 1379-1387.
OHMURA, Kazuyuki, et al. Predicting the presence and severity of obstructive sleep apnea based on mandibular measurements using quantitative analysis of facial profiles via three-dimensional photogrammetry. Respiratory Investigation, 2022, 60.2: 300-308.
ITO, Eiki, et al. Upper airway anatomical balance contributes to optimal continuous positive airway pressure for Japanese patients with obstructive sleep apnea syndrome. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2014, 10.2: 137-142.
SHIGETA, Yuko, et al. Influence of tongue/mandible volume ratio on oropharyngeal airway in Japanese male patients with obstructive sleep apnea. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 2011, 111.2: 239-243.
TANABE, Atsuro, et al. Upper Airway Simulation of Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Advanced Biomedical Engineering, 2023, 12: 74-80.
OKUBO, Mau, et al. Morphologic analyses of mandible and upper airway soft tissue by MRI of patients with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. Sleep, 2006, 29.7: 909-915.
ZHANG, Li, et al. Association of craniofacial and upper airway morphology with cardiovascular risk in adults with OSA. Nature and Science of Sleep, 2021, 1689-1700.
TAKEUCHI, Akiko, et al. Evaluation of oral air space volume in obstructive sleep apnea syndrome using clinical and postmortem CT imaging. Oral Radiology, 2022, 1-8.