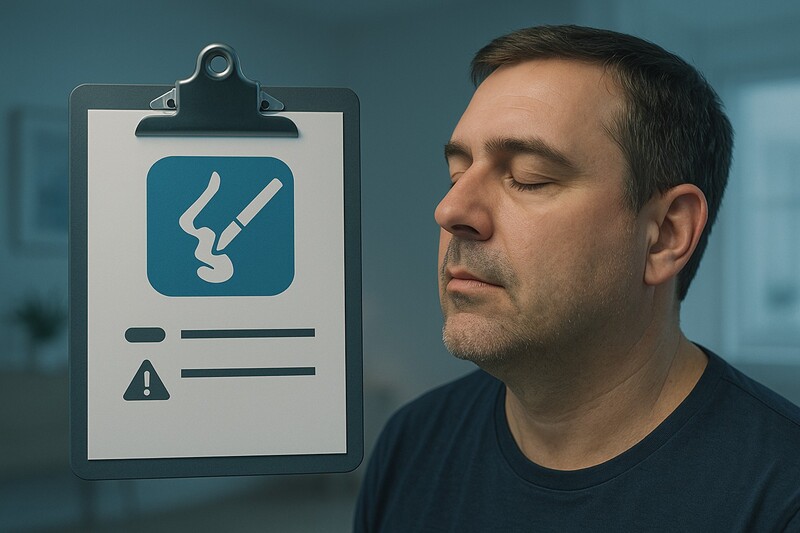睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療といえば、CPAP(シーパップ)療法やマウスピースが一般的ですが、「手術で根本的に治せないのか?」と考える方もいらっしゃるでしょう。
実際にSASに対しては様々な手術療法が存在します。しかし、手術がすべての人に適しているわけではなく、その効果やリスクも十分に理解する必要があります。
この記事では、睡眠時無呼吸症候群はどのような場合に手術が適応となるのか、そして手術は本当に根本的な解決法となり得るのかについて解説します。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)における手術の位置づけ
睡眠時無呼吸症候群、特に閉塞性SASは睡眠中に上気道(空気の通り道)が狭くなるか塞がることで起こります。
手術療法はこの狭窄や閉塞の原因となっている部位を物理的に広げることを目的とします。しかし、成人のSAS治療において、手術は第一選択ではありません。
第一選択はCPAP療法や口腔内装置
中等症以上のSASに対してはCPAP療法が最も標準的で効果的な治療法とされています。軽症や一部の中等症に対しては口腔内装置(マウスピース)も有効な選択肢です。
これらの保存的治療は効果が高く、比較的安全に行えるため、まず試みることが推奨されます。
主なSAS治療法の比較
| 治療法 | 主な対象 | 特徴 |
|---|---|---|
| CPAP療法 | 中等症~重症 | 効果が高い、継続が必要、装置装着 |
| 口腔内装置 | 軽症~中等症の一部 | 比較的簡便、適応に限界あり、歯科連携 |
| 手術療法 | 特定の原因がある場合、保存的治療が困難な場合 | 根本的改善の可能性、侵襲性あり、効果に個人差 |
手術が検討されるケース
手術療法は以下のような場合に検討されることがあります。
- 気道の狭窄・閉塞の原因が解剖学的に明らかで、手術によって改善が見込める場合(例:大きな扁桃腺、アデノイド、鼻中隔弯曲症など)
- CPAP療法や口腔内装置などの保存的治療が何らかの理由で継続困難、または効果が不十分な場合
- 小児のSASで、アデノイド・扁桃肥大が主な原因である場合(小児では手術が第一選択となることが多い)
根本治療への期待と限界
手術によって気道の構造的な問題が解消されれば、SASが根本的に改善する可能性があります。しかし、気道の閉塞部位は一人ひとり異なり、複数の部位が関与していることも少なくありません。そのため、特定の手術がすべての人に有効とは限らず、効果が限定的であったり、再発したりする可能性もあります。
主な睡眠時無呼吸症候群の手術の種類
SASに対する手術は閉塞の原因となっている部位に応じて様々な種類があります。主に鼻、のど(咽頭)、顎の骨に対する手術に分けられます。
鼻に対する手術
鼻詰まりは口呼吸を誘発し、いびきやSASを悪化させる要因となります。
鼻の通りを改善する手術はSASそのものを治すというより、他の治療(CPAPなど)の効果を高めたり、鼻呼吸を楽にしたりする目的で行われることが多いです。
代表的な鼻の手術
| 手術名 | 目的 | 対象 |
|---|---|---|
| 鼻中隔矯正術 | 曲がった鼻中隔を矯正し、鼻腔を広げる | 鼻中隔弯曲症 |
| 下鼻甲介手術 | 肥厚した下鼻甲介を切除・縮小し、鼻腔を広げる | アレルギー性鼻炎、肥厚性鼻炎 |
| 鼻茸切除術(内視鏡下副鼻腔手術) | 鼻ポリープ(鼻茸)を切除し、鼻腔・副鼻腔の通りを改善 | 慢性副鼻腔炎(蓄膿症)、鼻茸 |
のど(咽頭)に対する手術
のどの奥(中咽頭・下咽頭)はSASで最も閉塞しやすい部位であり、この部分を広げるための手術がいくつかあります。
口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)
口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)は最も代表的なSAS手術の一つです。
口蓋垂(のどちんこ)やその周りの軟口蓋、および肥大した口蓋扁桃(扁桃腺)を切除して、のどの奥のスペースを広げます。全身麻酔下で行い、入院が必要です。
術後の痛みが比較的強く、効果にも個人差があります。
レーザー口蓋垂軟口蓋形成術(LAUP)
レーザー口蓋垂軟口蓋形成術(LAUP)はレーザーを用いて口蓋垂や軟口蓋の一部を切除・蒸散させる方法です。
局所麻酔で日帰りまたは短期入院で行えることが多いですが、効果はUPPPに比べて限定的であり、複数回の手術が必要になることもあります。
近年では実施されることが少なくなっています。
扁桃摘出術・アデノイド切除術
口蓋扁桃やアデノイド(咽頭扁桃)が著しく大きい場合、これらを切除する手術が有効です。特に小児のSASではこれが主な原因であることが多く、手術によって劇的に改善することが期待できます。
成人でも扁桃肥大が明らかな場合は扁桃摘出術・アデノイド切除術適応となります。
舌や顎に対する手術
舌根(舌の付け根)の沈下や下顎が小さいことが原因の場合、これらを改善する手術も行われます。
舌根縮小術・舌骨吊り上げ術
舌根部の体積を減らしたり(高周波凝固など)、舌の付け根が付着する舌骨を前上方に移動させて固定したりすることで舌根沈下を防ぎ、気道を広げる手術です。
単独で行われることは少なく、他の手術と組み合わせて行われることがあります。
顎顔面骨格の手術(上下顎前方移動術:MMAなど)
上顎と下顎の骨を切り、前方へ移動させて固定する手術です。これにより舌が付着する下顎骨が前方に移動し、舌根部の後ろの気道が大幅に広がります。
効果は高いとされていますが、顔貌の変化を伴い、身体への負担も大きい手術です。重症例や他の治療法が無効な場合に検討されます。
主な手術の対象部位と目的
| 手術の種類 | 主な対象部位 | 目的 |
|---|---|---|
| 鼻の手術 | 鼻中隔、下鼻甲介、副鼻腔 | 鼻腔通気の改善 |
| UPPP, LAUP | 軟口蓋、口蓋垂、扁桃 | 中咽頭の拡大 |
| 扁桃・アデノイド切除 | 口蓋扁桃、咽頭扁桃 | 肥大組織の除去による気道拡大 |
| 舌根・舌骨手術 | 舌根、舌骨 | 舌根沈下の防止、下咽頭の拡大 |
| 顎顔面骨格手術 (MMA) | 上顎骨、下顎骨 | 気道全体の大幅な拡大 |
手術療法の適応となる条件
どのような場合に手術が適応となるのでしょうか。単にSASであるというだけでは手術の適応にはならず、いくつかの条件を満たす必要があります。
閉塞部位の特定
まず、睡眠中の気道閉塞がどの部位で起こっているかを正確に特定することが重要です。
これには内視鏡検査(覚醒時および睡眠導入下)、画像検査(CT、MRI)、薬物誘導下睡眠時内視鏡検査(DISE)などが行われます。
閉塞部位と手術で改善できる部位が一致していることが手術適応の前提となります。
解剖学的な異常の存在
扁桃腺やアデノイドの著しい肥大、重度の鼻中隔弯曲症、明らかな顎の骨格異常など手術によって改善可能な解剖学的な異常が存在することが条件となります。
肥満が主たる原因である場合はまず減量が優先されます。
保存的治療の評価
成人の場合、原則としてCPAP療法や口腔内装置などの保存的治療を試み、その効果や継続の可否を評価します。
これらの治療が効果不十分であったり、副作用や装着困難などの理由で継続できなかったりする場合に手術が選択肢として考慮されます。
手術適応の判断基準(成人例)
| 基準項目 | 評価内容 | 手術を考慮する条件 |
|---|---|---|
| 閉塞部位 | 睡眠検査、内視鏡、画像検査等 | 手術で改善可能な部位の特定 |
| 解剖学的異常 | 診察、画像検査等 | 扁桃肥大、顎骨異常等の存在 |
| 保存的治療 | CPAP・マウスピースの効果・継続性 | 効果不十分 または 継続困難 |
| 患者の希望・全身状態 | 手術への理解度、合併症リスク | 十分な理解と同意、手術に耐えうる状態 |
患者さんの希望と理解
手術には必ずリスクが伴い、期待通りの効果が得られない可能性もあります。
手術の目的、方法、期待される効果、合併症のリスクなどについて患者さん自身が十分に理解し、納得した上で手術を受ける意思があることが大切です。
手術のメリットとデメリット(リスク)
手術療法を検討する際には、そのメリットとデメリット(リスク)を十分に理解しておくことが重要です。
手術のメリット
最大のメリットは成功した場合にSASが根本的に改善し、CPAP療法やマウスピースなどの装置から解放される可能性があることです。
これにより、睡眠の質の向上はもちろん、日中の眠気改善、合併症リスクの低減、そして煩わしい装置の装着やメンテナンスからの解放が期待できます。
手術のデメリット・リスク
一方、手術には以下のようなデメリットやリスクも伴います。
- 侵襲性・痛み: 手術は身体への負担(侵襲)を伴い、術後の痛みも避けられません。特にUPPPなどは術後の痛みが強い傾向があります。
- 合併症: 出血、感染、麻酔に伴うリスク、術後の嚥下困難(飲み込みにくさ)、声の変化、味覚の変化などが起こる可能性があります。
- 効果の不確実性・再発: 手術をしてもSASが十分に改善しない、あるいは一度改善しても再発する可能性があります。特に肥満が解消されない場合や、加齢による変化などで再発することがあります。
- 入院・費用: 手術の種類によっては入院が必要となり、それに伴う時間的・経済的な負担も考慮する必要があります。
手術の種類別 主なリスク例
| 手術の種類 | 考えられる主なリスク |
|---|---|
| 鼻の手術 | 出血、感染、鼻の乾燥感、嗅覚の変化 |
| UPPP | 術後疼痛、出血、感染、嚥下困難、鼻咽腔閉鎖不全(鼻声) |
| 扁桃・アデノイド切除 | 術後疼痛、出血、感染、味覚変化 |
| 顎顔面骨格手術 (MMA) | 顔面腫脹、疼痛、神経麻痺(唇の痺れ等)、咬合変化、感染 |
成功率について
手術の成功率は、手術の種類、患者さんの状態(重症度、肥満度、閉塞部位など)、そして「成功」の定義(AHIの改善度など)によって大きく異なります。
一般的にUPPP単独での成功率は50%前後とも言われ、必ずしも高いとは言えません。
複数の手術を組み合わせることで成功率が上がる場合もありますが、侵襲も大きくなります。
手術以外の治療法との比較
手術を考える際にはCPAP療法や口腔内装置といった他の治療法の特徴と比較検討することが大切です。
CPAP療法との比較
CPAP療法は適切に使用すればほぼ確実に無呼吸・低呼吸を抑制できる非常に効果の高い治療法です。
しかし毎晩装置を装着する必要があり、マスクの不快感、管理の手間、旅行時の携帯などのデメリットがあります。
手術は成功すればこれらの煩わしさから解放される可能性がありますが、効果が不確実でリスクも伴います。
口腔内装置(マウスピース)との比較
マウスピースはCPAPより簡便ですが、効果は軽症~中等症に限られることが多く、顎関節への負担や歯への影響が出る可能性もあります。
手術はより根本的な改善を目指しますが、侵襲性やリスクはマウスピースより高くなります。
治療法の特徴比較
| 特徴 | CPAP療法 | 口腔内装置 | 手術療法 |
|---|---|---|---|
| 効果の確実性 | 高い | 中程度(適応による) | 不確実(個人差大) |
| 侵襲性 | 低い(装置装着) | 低い(装置装着) | 高い(身体への負担) |
| 継続の必要性 | 必要(毎晩) | 必要(毎晩) | 不要(成功すれば) |
| 根本改善の可能性 | 低い(対症療法) | 低い(対症療法) | あり(成功すれば) |
治療法の選択
どの治療法が最も適しているかはSASの重症度、原因、患者さんのライフスタイルや希望、そして各治療法のメリット・デメリットを総合的に考慮して、医師と十分に相談した上で決定することが重要です。
手術後の経過と注意点
手術を受けた後の経過や注意点について理解しておくことも大切です。
術後の痛みと回復期間
手術の種類によって異なりますが、術後数日から数週間は痛みや腫れ、飲み込みにくさなどが続くことがあります。特にUPPPなどは痛みが強い傾向があります。
回復期間中は食事内容の制限(柔らかいもの中心など)や、安静が必要となる場合があります。
回復期間は手術内容により様々ですが、完全に元の生活に戻るまでには数週間から数ヶ月かかることもあります。
定期的な経過観察
手術の効果を確認し、合併症の有無をチェックするために術後も定期的な診察が必要です。
手術の効果判定には通常、術後数ヶ月経ってから再度睡眠検査を行います。
生活習慣の維持
手術によってSASが改善した場合でも体重管理や禁煙、節酒などの健康的な生活習慣を維持することは効果を持続させ、再発を防ぐために重要です。
特に術後に体重が増加すると再び気道が狭くなり、SASが再発するリスクが高まります。
術後の一般的な注意点
| 注意点 | 内容 | 期間(目安) |
|---|---|---|
| 痛み・腫れ管理 | 鎮痛剤の使用、冷却など | 数日~数週間 |
| 食事制限 | 柔らかい食事、刺激物の回避 | 数日~数週間(手術による) |
| 活動制限 | 激しい運動や力仕事の回避 | 数週間~(手術による) |
| 定期検診 | 創部の確認、効果判定 | 術後継続的に |
よくある質問
Q1. 手術を受ければ、CPAPやマウスピースは完全に不要になりますか?
A1. 手術が成功してSASが十分に改善すれば、CPAPやマウスピースが不要になる可能性はあります。しかし手術の効果は個人差が大きく、完全に治癒するとは限りません。
手術後も軽度から中等度のSASが残存し、引き続きCPAPやマウスピースが必要となる場合や、効果が不十分で他の治療法を再検討する必要がある場合もあります。
手術前に期待される効果について、医師とよく相談することが大切です。
Q2. 手術の費用はどのくらいかかりますか?保険は適用されますか?
A2. SASに対する手術の多くは診断基準を満たせば健康保険が適用されます。ただし、手術の種類や入院期間、施設によって費用は大きく異なります。
例えば扁桃摘出術や鼻中隔矯正術などは比較的一般的な手術ですが、顎顔面骨格の手術(MMA)などは高度な技術を要し、高額になる傾向があります。
自己負担額(3割負担の場合)は数万円から数十万円、あるいはそれ以上になることも考えられます。具体的な費用については手術を検討する医療機関に直接確認してください。
Q3. 手術後の痛みはどのくらい続きますか?
A3. 術後の痛みは手術の種類や範囲、個人の感じ方によって大きく異なります。
鼻の手術は比較的痛みが軽いことが多いですが、UPPPや扁桃摘出術はのどの痛みが強く、食事や会話が辛い時期が1~2週間程度続くことが一般的です。
顎顔面骨格の手術では腫れや痺れが数ヶ月続くこともあります。
通常痛み止めが処方されますので、痛みをコントロールしながら回復を待ちます。
Q4. 手術を受けるかどうか迷っています。どう判断すればよいですか?
A4. 手術はSAS治療の一つの選択肢ですが、安易に決断すべきではありません。
まずはCPAP療法や口腔内装置などの保存的治療を試み、その効果やご自身に合っているかどうかを確認することが基本です。
その上で保存的治療が困難な場合や解剖学的な問題が明確で手術による改善が強く期待できる場合に、手術のリスクとベネフィットを十分に理解した上で検討します。
セカンドオピニオンを聞くことも有効です。主治医と納得いくまで話し合い、ご自身の状況や価値観に合った選択をすることが重要です。
以上
参考にした論文
AKASHIBA, Tsuneto, et al. Sleep apnea syndrome (SAS) clinical practice guidelines 2020. Respiratory Investigation, 2022, 60.1: 3-32.
IWATA, Noboru, et al. Clinical indication of nasal surgery for the CPAP intolerance in obstructive sleep apnea with nasal obstruction. Auris Nasus Larynx, 2020, 47.6: 1018-1022.
FUKUDA, Tatsuya, et al. Selection of response criteria affects the success rate of oral appliance treatment for obstructive sleep apnea. Sleep Medicine, 2014, 15.3: 367-370.
PARK, Do-Yang, et al. Clinical practice guideline: clinical efficacy of nasal surgery in the treatment of obstructive sleep apnea. Clinical and experimental otorhinolaryngology, 2023, 16.3: 201-216.
NAKAMURA, Kei, et al. Survival benefit of continuous positive airway pressure in Japanese patients with obstructive sleep apnea: a propensity-score matching analysis. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2021, 17.2: 211-218.
OKUNO, Kentaro, et al. The success rate of oral appliances based on multiple criteria according to obstructive sleep apnoea severity, BMI and age: A large multicentre study. Journal of Oral Rehabilitation, 2020, 47.9: 1178-1183.
NAKATA, Seiichi, et al. Effects of nasal surgery on sleep quality in obstructive sleep apnea syndrome with nasal obstruction. American journal of rhinology, 2008, 22.1: 59-63.
YAMAUCHI, Motoo, et al. Nerve stimulation for the treatment of obstructive sleep apnea. Sleep and biological rhythms, 2020, 18.2: 77-87.
NISHIO, Yoshitomo, et al. Treatment outcome of oral appliance in patients with REM-related obstructive sleep apnea. Sleep and Breathing, 2020, 24: 1339-1347.
TSUDA, Hiroko; WADA, Naohisa; ANDO, Shin-ichi. Practical considerations for effective oral appliance use in the treatment of obstructive sleep apnea: a clinical review. Sleep Science and Practice, 2017, 1: 1-11.