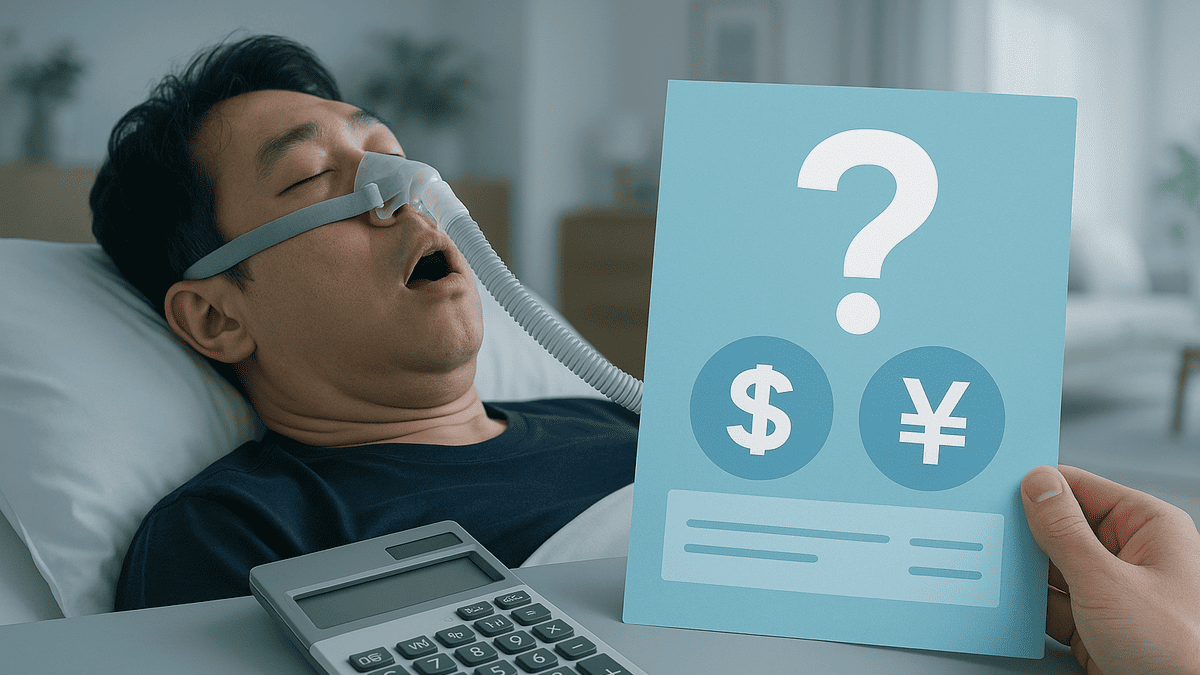「いびきの治療に興味はあるけれど、費用がどれくらいかかるか分からなくて不安」と感じていませんか。
いびきは、ときに睡眠時無呼吸症候群という病気のサインである可能性があり、適切な治療が必要です。治療法によって費用は大きく異なり、保険が適用されるかどうかで自己負担額も変わります。
この記事では、いびき治療を検討している方のために、初診から検査、CPAP療法やマウスピース治療など、それぞれの段階でかかる費用の目安を分かりやすく解説します。
ご自身の症状と予算に合った治療法を見つけるための参考にしてください。
いびきを放置する危険性と治療の必要性
単なる「うるさい音」として軽視されがちないびきですが、実は体からの危険信号である場合があります。
なぜいびきが起こるのか、そしてどのような場合に専門的な治療を検討すべきなのか、基本的な知識から解説します。
空気の通り道が狭くなることが主な原因
いびきは睡眠中に鼻や喉(のど)などの空気の通り道(上気道)が狭くなり、そこを空気が通過する際に粘膜が振動して発生する音です。
目が覚めている時は筋肉の働きで気道が十分に開いています。しかし、睡眠中は全身の筋肉が緩むため、元々気道が狭い方はさらに狭くなり、いびきをかきやすくなります。
気道が狭くなる要因
- 肥満による首周りの脂肪沈着
- 扁桃腺やアデノイドの肥大
- 舌の付け根(舌根)の落ち込み
- 顎が小さいなどの骨格的な特徴
- 加齢による筋力の低下
危険ないびきとそうでないいびきの違い
疲れている時やお酒を飲んだ後にたまにかく程度であれば、過度に心配する必要はないかもしれません。
しかし、毎晩のように大きないびきをかいていたり、次のような特徴が見られたりする場合は注意が必要です。これらは睡眠の質が著しく低下している、あるいは体に負担がかかっているサインと考えられます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)との深い関係
いびきをかく人のなかには睡眠中に呼吸が何度も止まったり、浅くなったりする「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」が隠れていることがあります。
この病気は大きないびきの後に呼吸が止まり、しばらくして「ガッ」という大きないびきとともに呼吸が再開するのが特徴です。
この状態を放置すると、体にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
睡眠時無呼吸症候群が引き起こす可能性のある健康問題
睡眠中に呼吸が止まると体内の酸素濃度が低下し、心臓や血管に大きな負担がかかります。このことにより、高血圧や糖尿病、心筋梗塞、脳卒中といった生活習慣病のリスクを高めることが知られています。
また、深刻な寝不足から日中に強い眠気に襲われ、重大な事故を引き起こす原因にもなり得ます。
いびき治療の保険適用と自由診療の違い
いびき治療の費用を考える上で最も重要なのが、保険が適用されるかどうかです。
どのような場合に保険診療となり、どのような場合に自由診療となるのか、その基準とそれぞれの特徴について解説します。
保険適用は「睡眠時無呼吸症候群」の診断が基準
いびき治療で健康保険が適用されるのは、原則として「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」と診断された場合です。単に「いびきの音が気になる」という美容的な理由だけでは保険適用にはなりません。
医師が診察や検査を通じて、いびきの背景に治療が必要な病気が隠れていると判断した場合に、その病気の治療として保険診療が認められます。
保険診療のメリットと範囲
保険診療の最大のメリットは治療にかかる費用の一部を健康保険が負担してくれるため、自己負担額を抑えられる点です。通常、医療費の1割から3割の負担で治療を受けられます。
保険が適用される治療法には、CPAP(シーパップ)療法やマウスピース(スリープスプリント)治療、一部の外科手術などがあります。
保険診療と自由診療の比較
| 項目 | 保険診療 | 自由診療 |
|---|---|---|
| 対象 | 睡眠時無呼吸症候群など病気の治療 | 美容目的や保険適用外の治療 |
| 費用負担 | 1割~3割負担 | 全額自己負担 |
| 主な治療法 | CPAP、マウスピース、一部手術 | レーザー治療など |
自由診療になるケースとその特徴
睡眠時無呼吸症候群の基準を満たさない軽症のいびきや、美容的な改善を目的とする場合は自由診療(自費診療)となります。自由診療では公的な医療保険が使えないため、費用は全額自己負担です。
費用は高額になる傾向がありますが、保険診療の枠にとらわれない多様な治療法を選択できるという側面もあります。
代表的なものに、レーザーで喉の粘膜を処置する治療法などがあります。
【ステップ1】初診から検査までの費用
いびき治療は、まず専門の医療機関を受診し、原因を特定するための検査を受けることから始まります。
ここでは、初診から診断が確定するまでにかかる費用の目安を解説します。
初診料・再診料の目安
初めてクリニックを受診する際には初診料がかかります。保険適用(3割負担)の場合、初診料は1,000円前後です。
2回目以降の受診では再診料がかかり、こちらは数百円程度が目安となります。これらは診察や相談に対する基本的な費用です。
自宅でできる簡易アプノモニター検査の費用
睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合、まずは自宅で手軽に行える簡易検査(簡易アプノモニター)を実施することが一般的です。
手の指や鼻にセンサーを取り付け、睡眠中の呼吸の状態や血液中の酸素濃度を記録します。この検査費用は保険適用(3割負担)で3,000円程度です。
初診から簡易検査までの費用目安(3割負担)
| 項目 | 費用の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 初診料 | 約1,000円 | 問診、診察 |
| 簡易検査 | 約3,000円 | 検査機器のレンタル、データ解析 |
| 合計 | 約4,000円 | – |
より詳細な精密検査(PSG検査)の費用
簡易検査の結果、中等症以上の睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合や、より詳しい状態を調べる必要がある場合には精密検査(ポリソムノグラフィー検査、PSG検査)を行います。
この検査は医療機関に一泊入院して脳波や心電図、筋電図など、より多くのセンサーを体に取り付けて睡眠の状態を総合的に調べるものです。
費用は保険適用(3割負担)で、入院費を含めて20,000円から50,000円程度が目安です。
【ステップ2】CPAP療法にかかる費用
検査の結果、中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群と診断された場合に、標準的な治療法として選択されるのがCPAP(持続陽圧呼吸療法)です。
CPAP療法にかかる月々の費用について解説します。
CPAP療法とは
CPAP療法は鼻に装着したマスクから一定の圧力をかけた空気を送り込み、睡眠中に気道が塞がるのを防ぐ治療法です。睡眠中の無呼吸やいびきを効果的に減らし、睡眠の質を改善します。
治療は専用の装置を医療機関からレンタルし、毎晩使用することで行います。
毎月の診察と装置レンタル料
CPAP療法は毎月1回の定期的な受診が必要です。この診察で治療の効果や体調の変化を確認し、装置の使用状況などを報告します。
この月々の費用には診察料と装置のレンタル料が含まれており、保険適用(3割負担)の場合、合計で5,000円前後となります。
CPAP療法の月額費用(3割負担の場合)
| 項目 | 費用の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 診察料 | 約1,500円 | 月1回の対面またはオンライン診察 |
| 装置レンタル・管理料 | 約3,500円 | CPAP本体、マスク、チューブ等の費用 |
| 合計 | 約5,000円 | – |
CPAP療法を継続する重要性
CPAP療法は、あくまで対症療法であり、使用を中止すると元の無呼吸やいびきの状態に戻ってしまいます。そのため根本的な原因(肥満など)が改善されない限り、長期的に治療を継続することが重要です。
毎月の費用はかかりますが、合併症のリスクを軽減して日中の眠気を改善するなど、生活の質を大きく向上させる効果が期待できます。
【ステップ2】マウスピース治療にかかる費用
軽症から中等症の睡眠時無呼吸症候群や、いびき症の方にはマウスピース(スリープスプリント)を用いた治療も選択肢となります。
歯科医院などで作成するこの装置の費用について解説します。
マウスピース(スリープスプリント)治療とは
この治療法は睡眠中に専用のマウスピースを装着することで下顎を少し前に突き出させた状態に固定し、気道を広げるものです。
CPAP装置のような大掛かりな機器が不要で手軽に始められるのが特徴です。持ち運びも簡単なため、旅行や出張が多い方にも向いています。
保険適用で作成する場合の費用
いびき治療を専門とする医科からの紹介状(診療情報提供書)があれば、歯科医院で保険適用のマウスピースを作成できます。
この場合、検査料や製作費などを含めて自己負担額(3割負担)は15,000円から20,000円程度が目安です。ただし、すべての歯科医院で対応しているわけではないため、事前に確認が必要です。
自由診療で作成する場合の費用
保険適用の基準を満たさない場合や、より高機能な素材、精密な調整を希望する場合は自由診療でマウスピースを作成することもできます。
費用は全額自己負担となり、50,000円から200,000円程度と医療機関によって幅があります。
マウスピース治療の費用比較
| 種類 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 保険診療 | 15,000円~20,000円 | 費用を抑えられる。医科からの紹介状が必要。 |
| 自由診療 | 50,000円~200,000円 | 素材や設計の自由度が高い。全額自己負担。 |
【ステップ2】外科手術による治療と費用
CPAP療法やマウスピース治療で効果が得られない場合や、扁桃腺が大きいなど解剖学的な原因が明らかな場合には外科手術が検討されることもあります。
手術の種類と費用の目安を見ていきましょう。
手術が選択肢となるケース
手術は、いびきの原因となっている物理的な問題を直接取り除くことを目的とします。
例えば子供のいびきの主な原因であるアデノイドや扁桃腺の肥大、鼻の通りを悪くしている鼻中隔弯曲症などが手術の対象となります。
成人の場合は口蓋垂(のどちんこ)やその周辺の軟口蓋が気道を狭くしている場合に手術を検討します。
代表的な手術方法と費用の目安
いびき治療で行われる代表的な手術に口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)があります。これは、のどちんこやその周りの緩んだ粘膜を切除して気道を広げる手術です。
この手術は保険が適用され、費用(3割負担)は高額療養費制度の対象にもなりますが、一般的には100,000円から200,000円程度の自己負担が必要です。
入院期間は1週間から10日ほどが目安です。
主な外科手術の費用目安(3割負担)
| 手術名 | 費用の目安 | 主な対象 |
|---|---|---|
| 口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP) | 100,000円~200,000円 | 軟口蓋や口蓋垂の肥大 |
| アデノイド・扁桃腺切除術 | 80,000円~150,000円 | アデノイド・扁桃腺の肥大(主に小児) |
| 鼻中隔矯正術 | 80,000円~120,000円 | 鼻中隔弯曲症による鼻づまり |
手術のリスクと注意点
手術には痛みを伴うことや、術後に出血などの合併症が起こるリスクがあります。また、手術をしてもいびきが完全に解消されない場合や、時間が経つと再発する可能性もゼロではありません。
手術を受けるかどうかはその効果とリスクを医師と十分に相談し、慎重に判断することが大切です。
自由診療のレーザー治療とその費用
近年、手軽ないびき治療として注目されているのがレーザー治療です。これは基本的に自由診療となり、保険は適用されません。
その内容と費用について解説します。
レーザー治療の概要
レーザー治療は、いびきの原因となりやすい口蓋垂や軟口蓋にレーザーを照射し、粘膜組織を引き締めることで気道を広げる治療法です。
施術時間が短く、日帰りで受けられることが多いため、「切らないいびき治療」とも呼ばれます。
ただし効果には個人差があり、持続期間も限定的で、複数回の施術が必要になる場合があります。
レーザー治療の費用相場
自由診療のため、費用はクリニックによって大きく異なります。1回の照射で数万円から、複数回の施術がセットになったプランで100,000円から300,000円程度が相場です。
治療を検討する際は複数のクリニックでカウンセリングを受け、費用や治療内容を比較検討することをおすすめします。
レーザー治療の費用目安(自由診療)
| 施術内容 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 初回カウンセリング・診察 | 無料~10,000円 | クリニックにより異なる |
| レーザー照射(1回) | 30,000円~100,000円 | 照射範囲や機種により変動 |
| 複数回コース | 100,000円~300,000円 | 3回~5回程度のセットプラン |
自由診療のメリットとデメリット
自由診療であるレーザー治療は入院の必要がなく、短時間で終わる手軽さがメリットです。
一方で費用が全額自己負担で高額になること、効果が永続的ではない可能性があること、そして保険適用の治療法で効果が見込める人にとっては必ずしも第一選択とはならない点がデメリットとして挙げられます。
いびき治療の費用に特化したよくある質問
最後に、いびき治療の費用に関して患者様からよくいただく質問とその回答をまとめました。
- Qいびき治療の費用は医療費控除の対象になりますか?
- A
はい、医師による診断の結果、睡眠時無呼吸症候群などの「病気の治療」と判断された場合の費用は医療費控除の対象となります。
これには診察料、検査費用、CPAP療法の自己負担額、保険で作成したマウスピースの費用、治療目的の外科手術費用などが含まれます。
確定申告の際に必要となるため、領収書は必ず保管しておきましょう。
医療費控除の対象となる費用
通院にかかった交通費(公共交通機関)
医師の診察料、検査費用
CPAP療法の月額自己負担額
保険適用のマウスピース作成費用
治療目的の外科手術費用
- Q支払いにクレジットカードは使えますか?
- A
多くの医療機関でクレジットカードや電子マネーでの支払いが可能になっています。特に自由診療では高額になることもあるため、対応している場合がほとんどです。
ただし、クリニックによって対応状況は異なりますので、受診前にホームページで確認するか、直接問い合わせておくと安心です。
- Q子供のいびき治療にも保険は適用されますか?
- A
はい、お子様のいびき治療も、原因がアデノイド肥大や扁桃肥大など治療が必要な病気と診断されれば保険が適用されます。
また、多くの自治体では子ども医療費助成制度があり、保険診療の自己負担額が助成されるため、窓口での負担がほとんどない、あるいは非常に少額で済む場合が多いです。
お住まいの自治体の制度を確認してください。
以上
参考にした論文
OKUBO, Reiko, et al. Cost-effectiveness of obstructive sleep apnea screening for patients with diabetes or chronic kidney disease. Sleep and Breathing, 2015, 19.3: 1081-1092.
MCDAID, C., et al. Continuous positive airway pressure devices for the treatment of obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: a systematic review and economic analysis. Health Technology Assessment, 2009, 13.4: 1-146.
KAMEDA, Yoshihito, et al. Epidemiology of Sleep Apnea Syndrome. The Current State of Sleep Disordered Breathing in Japan and Around the World, 2025, 1.
SEINO, Yoshihiko, et al. Clinical efficacy and cost-benefit analysis of nocturnal home oxygen therapy in patients with central sleep apnea caused by chronic heart failure. Circulation Journal, 2007, 71.11: 1738-1743.
KAWAKAMI, Hiroshi, et al. Cost-effectiveness of obstructive sleep apnea screening and treatment before catheter ablation for symptomatic atrial fibrillation. Circulation reports, 2020, 2.9: 507-516.
KAMEDA, Yoshihito, et al. Epidemiology of Sleep Apnea Syndrome in Adult: What is the Current Prevalence of Obstructive Sleep Apnea in Adults?. In: The Current State of Sleep Disordered Breathing in Japan and Around the World. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025. p. 3-16.
TANAHASHI, Tokusei, et al. Factors that predict adherence to continuous positive airway pressure treatment in obstructive sleep apnea patients: A prospective study in Japan. Sleep and Biological Rhythms, 2012, 10.2: 126-135.
KITAZAWA, Takayuki, et al. Snoring, obstructive sleep apnea, and upper respiratory tract infection in elementary school children in Japan. Sleep and Breathing, 2024, 28.2: 629-637.
NELOGI, Santosh, et al. Modified mandibular advancement appliance for an edentulous obstructive sleep apnea patient: a clinical report. Journal of Prosthodontic Research, 2011, 55.3: 179-183.
IDA, Hitomi, et al. Unique clinical phenotypes of patients with obstructive sleep apnea in a Japanese population: a cluster analysis. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2022, 18.3: 895-902.