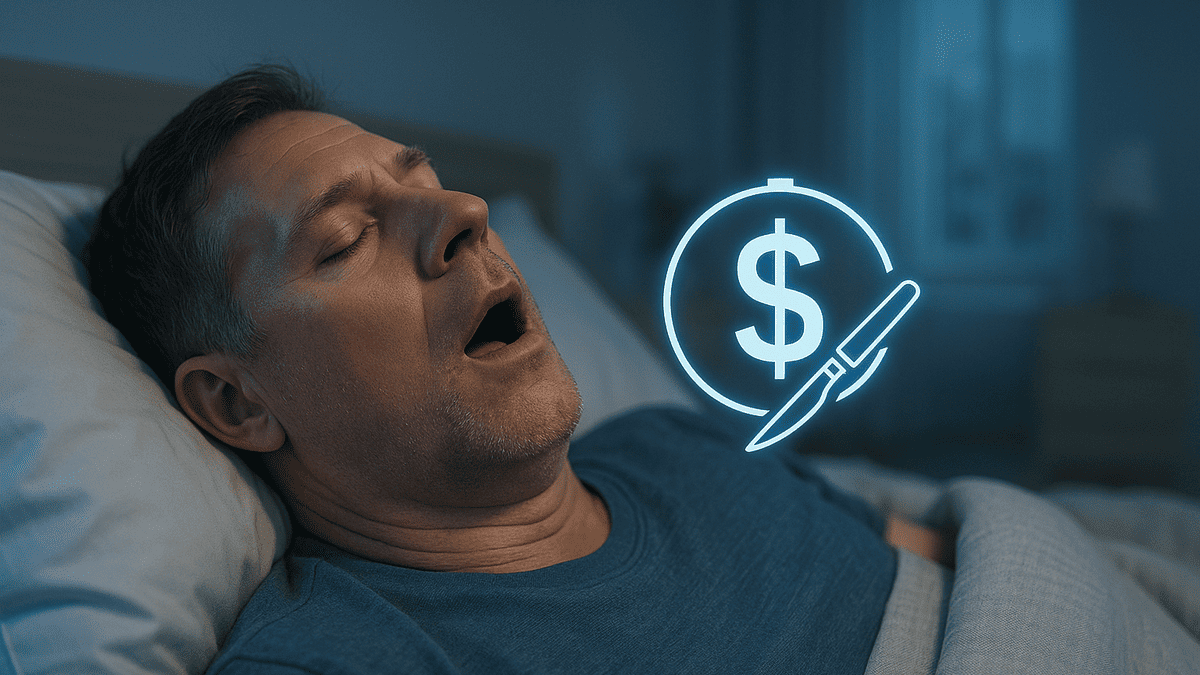CPAPやマウスピース治療でもいびきが改善しない場合、「手術」という選択肢が頭をよぎるかもしれません。
しかし、「費用はいくらかかるのか」「本当に保険は使えるのか」「どんな手術があるのか」など、多くの疑問が浮かぶことでしょう。
この記事では、いびきの外科治療を検討している方のために保険が適用される代表的な手術の種類から、それぞれの費用の目安、入院期間、そして信頼できる医師の探し方までを詳しく解説します。
手術という大きな決断をする前に正しい知識を身につけましょう。
いびき治療で手術が選択肢となるケース
いびき治療において、手術は誰もが対象となるわけではありません。
CPAP療法やマウスピース治療といった保存的治療が第一選択となることが多く、手術は特定の条件を満たす場合に検討されます。
保存的治療で効果が見られない場合
CPAP療法を試したものの装置が合わずに継続が難しい方や、マウスピース治療を行ってもいびきや無呼吸が十分に改善しない場合に、次の選択肢として手術が考えられます。
物理的な原因が明確な場合
いびきの原因が扁桃腺の肥大や鼻中隔弯曲症など気道を狭くしている物理的・解剖学的な問題であることが明らかな場合、手術によって根本的な解決が期待できます。
特にお子様のいびきの多くはアデノイドや扁桃腺の肥大が原因であり、手術が良い適応となります。
手術を検討する主な理由
| 理由 | 具体的な状況 |
|---|---|
| 保存的治療の限界 | CPAPの不耐、マウスピースの効果不足 |
| 解剖学的な問題 | 扁桃腺肥大、アデノイド、鼻中隔弯曲症 |
| 根治を目指したい | 毎日の装置使用から解放されたいという希望 |
手術の前に必要な検査
手術を検討する際は、まず睡眠時無呼吸症候群(SAS)の精密検査(PSG検査)を行い、重症度を正確に評価します。
さらに、CT検査や内視鏡検査で気道のどこがどの程度狭くなっているのかを詳細に調べ、最適な術式を判断します。
【喉の手術】口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)
喉の奥のスペースが狭いことが原因のいびきに対して行われる最も代表的な手術の一つがUPPPです。その内容と費用について詳しく見ていきましょう。
UPPPとはどのような手術か
口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)は睡眠中に気道を塞ぐ原因となりやすい口蓋垂(のどちんこ)や、その周辺の軟口蓋、扁桃腺を部分的に切除して縫い合わせることで、喉の奥の空間を物理的に広げる手術です。
UPPPの費用と保険適用
睡眠時無呼吸症候群の治療として行われるUPPPは健康保険の適用対象です。
3割負担の場合の自己負担額は、入院費などを含めて100,000円から200,000円程度が目安となります。この費用は高額療養費制度の対象にもなります。
UPPPの費用内訳(目安)
| 項目 | 費用(3割負担) | 備考 |
|---|---|---|
| 手術料 | 約80,000円~ | 術式により変動 |
| 入院費・その他 | 約50,000円~ | 入院日数や部屋代による |
| 合計 | 100,000円~200,000円 | 高額療養費制度の利用が可能 |
入院期間と術後の経過
UPPPは全身麻酔で行われ、通常7日から10日間程度の入院が必要です。術後は喉に強い痛みがあり、食事は流動食から徐々に固形物へと慣らしていきます。
痛みが完全に引くまでには2週間から1ヶ月程度かかることが一般的です。
【鼻の手術】鼻中隔矯正術・粘膜下下鼻甲介骨切除術
鼻づまりが原因で口呼吸となり、いびきを引き起こしている場合に有効なのが鼻の手術です。代表的な二つの術式について解説します。
鼻中隔矯正術
左右の鼻の穴を隔てている壁である「鼻中隔」が曲がっている状態(鼻中隔弯曲症)を矯正する手術です。
曲がっている鼻中隔の軟骨や骨の一部を切除し、まっすぐに整えることで鼻の通りを改善します。
粘膜下下鼻甲介骨切除術
アレルギー性鼻炎などで鼻の内部にある下鼻甲介という粘膜のヒダが慢性的に腫れている場合に行います。
腫れている粘膜の内部にある骨を取り除くことで下鼻甲介のボリュームを減らし、鼻腔を広げます。
鼻の手術の費用と入院期間
| 術式 | 費用目安(3割負担) | 入院期間の目安 |
|---|---|---|
| 鼻中隔矯正術 | 80,000円~120,000円 | 4~7日 |
| 粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 40,000円~60,000円 | 日帰り~3日 |
| 両方の同時手術 | 100,000円~150,000円 | 4~7日 |
鼻の手術の効果と注意点
これらの手術により鼻呼吸が楽になり、鼻いびきは大きく改善します。ただし喉にもいびきの原因がある場合は鼻の手術だけではいびきが完全には無くならないこともあります。
術後は鼻の中に詰め物をするため、一時的に鼻呼吸ができなくなります。
その他の手術と自由診療の選択肢
UPPPや鼻の手術以外にも、いびきの原因に合わせて様々な術式があります。また、保険適用外の治療法も存在します。
アデノイド・扁桃腺切除術
特にお子様のいびきや無呼吸の原因として多いアデノイドや扁桃腺の肥大に対して行われる手術です。
原因となっている組織を摘出することで気道が劇的に広がり、高い効果が期待できます。もちろん保険適用です。
レーザー手術(LAUP)
レーザーを用いて口蓋垂や軟口蓋の一部を切除・蒸散させる治療法で、口蓋垂レーザー形成術(LAUP)と呼ばれます。
UPPPに比べて出血が少なく、日帰りでできることが多いのが特徴です。ただし、この治療法は保険適用外の自由診療となります。
保険適用手術と自由診療(レーザー)の比較
| 項目 | 保険適用手術(UPPPなど) | 自由診療(LAUP) |
|---|---|---|
| 費用 | 3割負担(高額療養費適用あり) | 全額自己負担(15~30万円程度) |
| 入院 | 必要(約1週間) | 不要(日帰り) |
| 効果 | 効果の持続性が高い傾向 | 後戻り(再発)の可能性も |
手術のメリット・デメリットとリスク
手術はいびきの根本原因を取り除ける可能性がある一方で、体への負担やリスクも伴います。メリットとデメリットを十分に理解した上で慎重に判断することが重要です。
手術の主なメリット
最大のメリットは成功すればいびきや無呼吸が根本的に改善し、CPAPやマウスピースといった毎日の装置装着から解放される可能性がある点です。
生活の質(QOL)の向上が期待できます。
手術のデメリットと合併症のリスク
デメリットとしては術後の痛みが挙げられます。特にUPPPは強い痛みが2週間以上続くこともあります。
また、手術である以上、出血や感染症などのリスクはゼロではありません。
- 術後の痛み
- 出血、感染症
- 声の変化、飲み込みにくさ
- 効果が不十分、または再発の可能性
手術を受ける前の確認事項
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 期待できる効果 | 自分の症状がどの程度改善する見込みか |
| リスクと合併症 | どのような危険性があるのか |
| 術後の生活 | 回復までの期間や注意点 |
いびき手術の「名医」の探し方
手術の成否は執刀する医師の技術や経験に大きく左右されます。安心して治療を任せられる医師や医療機関はどのように探せばよいのでしょうか。
日本睡眠学会の専門医
一つの目安となるのが、「日本睡眠学会専門医」の資格です。睡眠医療全般に関する深い知識と経験を持つ医師の証であり、学会のウェブサイトで認定医のリストを確認できます。
これらの医師が在籍する施設では、適切な診断と治療方針の提案が期待できます。
耳鼻咽喉科の専門医と手術実績
いびきの手術は主に耳鼻咽喉科で行われます。日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が認定する「専門医」であることは基本条件です。
さらに、その中でも睡眠外科を専門とし、いびき手術の経験が豊富な医師を選ぶことが重要です。
病院のホームページなどで年間の手術件数などを確認するのも良いでしょう。
カウンセリングでの相性
最終的には実際に医師の診察を受け、説明の丁寧さや人柄など自分との相性を確認することが大切です。
自分の疑問や不安に真摯に耳を傾け、メリットだけでなくデメリットやリスクについても十分に説明してくれる医師を選びましょう。
いびきの手術に特化したよくある質問
いびきの手術を検討している方からよく寄せられる質問と、その回答をまとめました。
- Q手術費用は医療費控除の対象になりますか?
- A
はい、医師が治療のために必要と判断した手術であれば保険適用の手術はもちろん、自由診療の手術費用も医療費控除の対象となります。
確定申告の際に必要ですので、病院から発行された領収書は必ず保管しておきましょう。
- Q手術をすれば、いびきは100%治りますか?
- A
残念ながら100%とは断言できません。
手術によって気道は広がりますが、術後の体重増加や加齢による筋力の低下など新たな要因でいびきが再発する可能性はあります。
手術はあくまで一つの手段であり、術後も健康的な生活習慣を維持することが重要です。
- Q高額療養費制度について教えてください。
- A
高額療養費制度は医療機関の窓口で支払う医療費が1ヶ月で上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。上限額は年齢や所得によって異なります。
事前に入院することが分かっていれば「限度額適用認定証」を申請しておくことで、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。
以上
参考にした論文
OKUBO, Reiko, et al. Cost-effectiveness of obstructive sleep apnea screening for patients with diabetes or chronic kidney disease. Sleep and Breathing, 2015, 19.3: 1081-1092.
KAWAKAMI, Hiroshi, et al. Cost-effectiveness of obstructive sleep apnea screening and treatment before catheter ablation for symptomatic atrial fibrillation. Circulation reports, 2020, 2.9: 507-516.
KUNISAKI, Ken M., et al. The Comparative Effectiveness, Harms, and Cost of Care Models for the Evaluation and Treatment of Obstructive Sleep Apnea (OSA): A Systematic Review. 2016.
MCDAID, C., et al. Continuous positive airway pressure devices for the treatment of obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: a systematic review and economic analysis. Health Technology Assessment, 2009, 13.4: 1-146.
LEGER, Damien, et al. Impact of sleep apnea on economics. Sleep medicine reviews, 2012, 16.5: 455-462.
NAKAMURA, Kei, et al. Survival benefit of continuous positive airway pressure in Japanese patients with obstructive sleep apnea: a propensity-score matching analysis. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2021, 17.2: 211-218.
NAKATA, Seiichi, et al. Effects of nasal surgery on sleep quality in obstructive sleep apnea syndrome with nasal obstruction. American journal of rhinology, 2008, 22.1: 59-63.
HSU, Yu-Ching, et al. Effectiveness of treating Obstructive Sleep Apnea by surgeries and continuous positive airway pressure: evaluation using objective sleep parameters and patient-reported outcomes. Journal of Clinical Medicine, 2024, 13.19: 5748.
IWATA, Noboru, et al. Clinical indication of nasal surgery for the CPAP intolerance in obstructive sleep apnea with nasal obstruction. Auris Nasus Larynx, 2020, 47.6: 1018-1022.
KITAZAWA, Takayuki, et al. Snoring, obstructive sleep apnea, and upper respiratory tract infection in elementary school children in Japan. Sleep and Breathing, 2024, 28.2: 629-637.