冬の寒い屋外から暖かい室内に入った時や、朝方に冷たい空気を吸い込んだ時、急に咳き込んでしまうことはありませんか。
「寒い時期はいつも咳が出やすい」「風邪は治ったはずなのに咳だけが残っている」と感じる方は少なくないでしょう。その咳単なる風邪や体質の問題だと諦めていませんか。
実は、寒さや寒暖差が引き金となって起こる咳には、はっきりとした原因があります。放置すると「咳喘息」などの病気に繋がる可能性も考えられます。
この記事では、なぜ寒いと咳が出やすくなるのかその原因を詳しく解説し、今日からすぐに実践できる具体的な対策から病院を受診する目安までを分かりやすく紹介します。
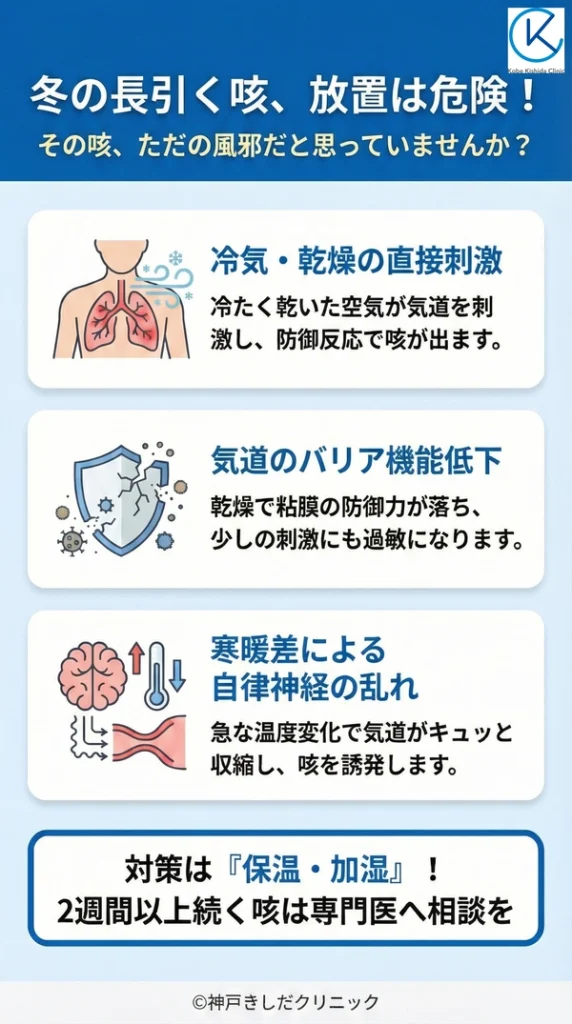
神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。
なぜ寒いと咳が出やすくなるのか
寒い季節になると咳が出やすくなるのには、私たちの体の防御反応や自律神経の働きが深く関わっています。
冷たい空気が体に与える影響を知ることが、咳対策の第一歩です。
冷たく乾燥した空気の刺激
冬の空気は冷たいだけでなく、非常に乾燥しています。この冷たく乾いた空気を吸い込むと、鼻やのど、気管といった空気の通り道である「気道」が直接刺激を受けます。
気道の粘膜は、この刺激を異物とみなし、体外に排出しようとする防御反応として咳を引き起こします。
気道の粘膜の働きと乾燥
気道の表面は粘膜で覆われており、線毛という細かい毛が絶えず動くことでウイルスや細菌、ホコリなどを痰として体外に排出する機能を持っています。
しかし、気道が乾燥するとこの線毛の動きが鈍くなり、異物を排出しにくくなります。その結果、少しの刺激にも過敏に反応して咳が出やすくなるのです。
寒暖差による自律神経の乱れ
暖かい場所から寒い場所へ移動するなど、急激な温度変化に体がさらされると、体温を一定に保とうとする自律神経のバランスが乱れやすくなります。
この自律神経の乱れは気道をコントロールしている神経にも影響を与え、気道を収縮させて咳を誘発することがあります。
自律神経の乱れが気道に与える影響
| 要因 | 体への影響 | 結果 |
|---|---|---|
| 急激な温度変化 | 交感神経と副交感神経のバランスが崩れる | 気道が過敏になり収縮しやすくなる |
| 冷たい空気 | 気道の血管が収縮し、粘膜が刺激される | 咳反射が起こりやすくなる |
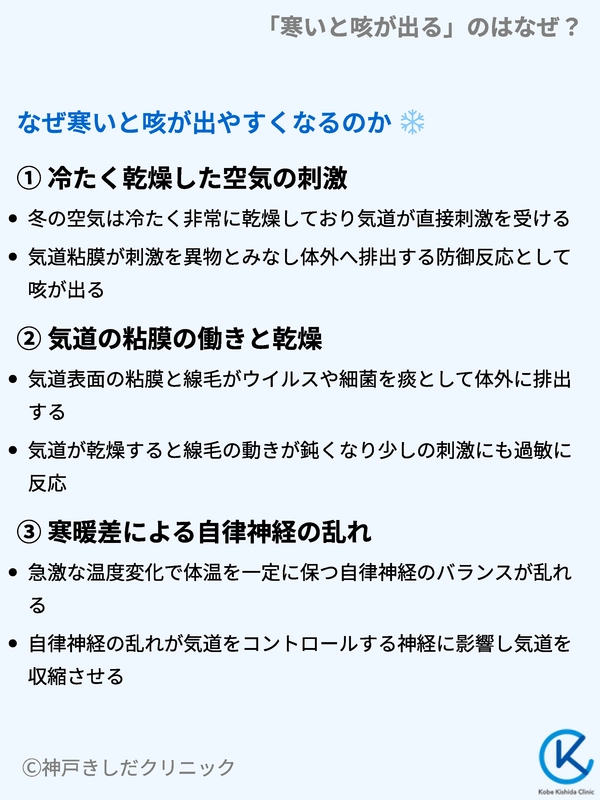
寒い時期の咳 考えられる原因と病気
「寒い時期の咳」と一括りにしても、その背景には様々な原因が考えられます。一般的な風邪から特定の病気のサインである可能性まで、正しく見分けることが大切です。
風邪やインフルエンザとの違い
風邪やインフルエンザでも咳は出ますが、これらの感染症の場合、発熱や鼻水、のどの痛み、全身の倦怠感といった他の症状を伴うことがほとんどです。
一方、寒さが引き金となる咳は熱などの他の症状がほとんどなく、咳だけが長引くという特徴があります。
症状による原因の見分け方
| 症状 | 風邪・インフルエンザ | 寒さが引き金となる咳 |
|---|---|---|
| 咳 | 他の症状と共に出現 | 咳が中心で、他の症状は少ない |
| 発熱 | よくみられる | ほとんどみられない |
| 特定の状況 | 特になし | 寒い場所や寒暖差で悪化しやすい |
寒暖差アレルギー(血管運動性鼻炎)
寒暖差アレルギーは、アレルギーの原因物質(アレルゲン)がないにもかかわらず、急激な温度差によってアレルギーのような症状が出る状態です。
鼻水やくしゃみが主な症状ですが、鼻からのどへの刺激が咳を引き起こすこともあります。医学的には血管運動性鼻炎と呼ばれます。
咳喘息(せきぜんそく)の可能性
咳喘息は喘息の一種で、喘鳴や呼吸困難を伴わない“咳のみの喘息”とされています。
適切な治療をせず放置すると、約30~40%が典型的な気管支喘息に移行する可能性があるため注意が必要です
喘息特有の「ゼーゼー」「ヒューヒュー」といった喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難はなく、乾いた咳だけが長期間(一般的に8週間以上)続くのが特徴です。
特に夜間から早朝にかけて、また寒暖差や会話、運動などをきっかけに咳が悪化しやすい傾向があります。
その他の呼吸器疾患
長引く咳の原因として、他にも気管支炎やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)、アトピー咳嗽(がいそう)など様々な呼吸器の病気が隠れている可能性も考えられます。
自己判断はせず、咳が続く場合は専門医に相談することが重要です。
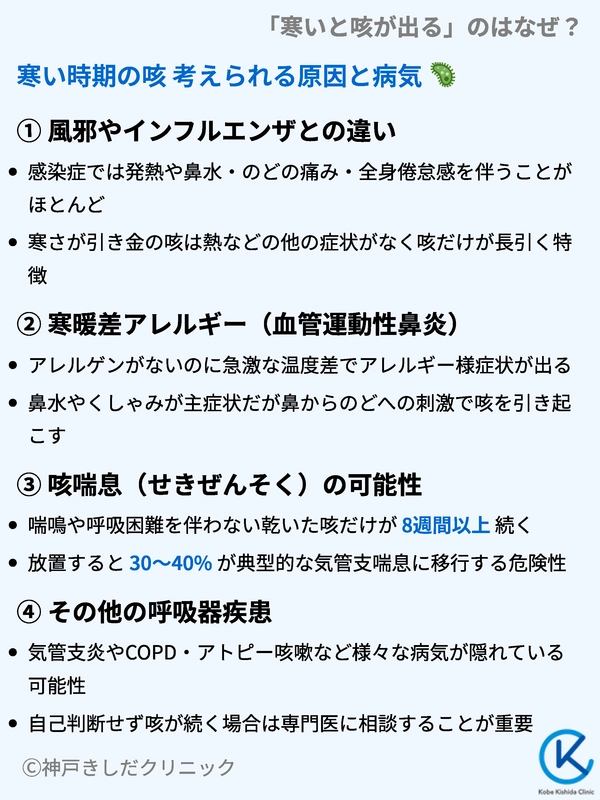
今すぐできる!日常的な咳対策
寒い季節の咳を和らげるためには、日常生活の中での少しの工夫が効果的です。体を冷やさず、気道への刺激を減らすための基本的な対策を紹介します。
外出時の服装と防寒対策
外出時は冷たい空気が直接体に触れないように、マフラーやネックウォーマー、タートルネックのセーターなどで首元をしっかりと温めましょう。
首元を温めることで、体全体の保温効果が高まります。
マスク着用による加温・加湿効果
マスクを着用すると、自分の呼気に含まれる水分と熱がマスク内に留まります。
このことにより、冷たく乾燥した外気を直接吸い込むのを防ぎ、適度に温かく湿った空気を吸うことができるため、気道への刺激を大幅に軽減できます。
防寒対策のポイント
| 対策 | 具体的な方法 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 首元の保温 | マフラー、ネックウォーマーの着用 | 体全体の冷えを防ぎ、気道への刺激を緩和 |
| マスクの着用 | 自分の呼気で加温・加湿する | 冷たく乾燥した空気の吸い込みを防ぐ |
体を内側から温める食生活
体を温める効果のある食材を食事に取り入れることも、咳対策に繋がります。
血行を促進し、体温を上げることで免疫機能の維持を助けます。
体を温める食材の例
- ショウガ
- ネギ
- ニンニク
- 根菜類(大根、ごぼう、人参など)
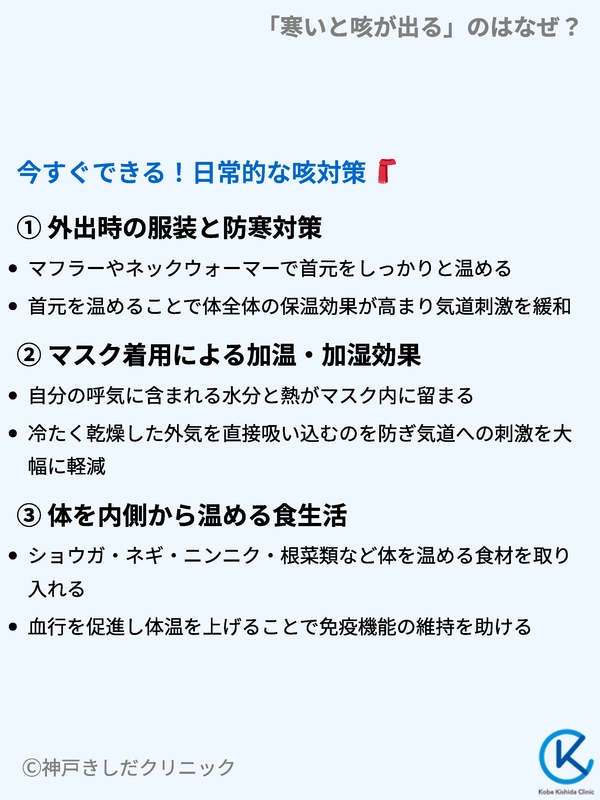
室内の環境を整えて咳を予防する
一日の多くを過ごす室内の環境は咳の予防において非常に重要です。特に冬場は暖房器具の使用で空気が乾燥しやすいため、適切な温度と湿度の管理が大切になります。
加湿器の正しい使い方と選び方
加湿器は乾燥対策に非常に有効なアイテムです。部屋の広さに合った能力のものを選び、清潔に保つことが大切です。
不衛生な加湿器はカビや雑菌を室内にまき散らす原因となり、かえって咳を悪化させることもあるため注意が必要です。
加湿器の種類と特徴
| 種類 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| スチーム式 | 水を沸騰させるため衛生的。加湿力が高い。 | 消費電力が大きい。吹き出し口が熱くなる。 |
| 気化式 | 熱を使わず安全。消費電力が少ない。 | フィルターの定期的な清掃が必要。 |
| 超音波式 | 静音性が高い。デザインが豊富。 | こまめな清掃をしないと雑菌が繁殖しやすい。 |
こまめな換気と空気清浄機の活用
冬場は窓を閉め切りがちですが、汚れた空気が室内にこもると咳の原因となるハウスダストやアレルゲンが増加します。
1日に数回、短時間でも窓を開けて空気を入れ替えましょう。空気清浄機を併用するのも効果的です。
睡眠環境の重要性
寝室の環境は夜間の咳に大きく影響します。特に就寝中は体温が下がり、乾燥した空気を長時間吸い続けることになるため、加湿が重要です。
枕元に濡れタオルを干すだけでも簡易的な加湿効果が期待できます。
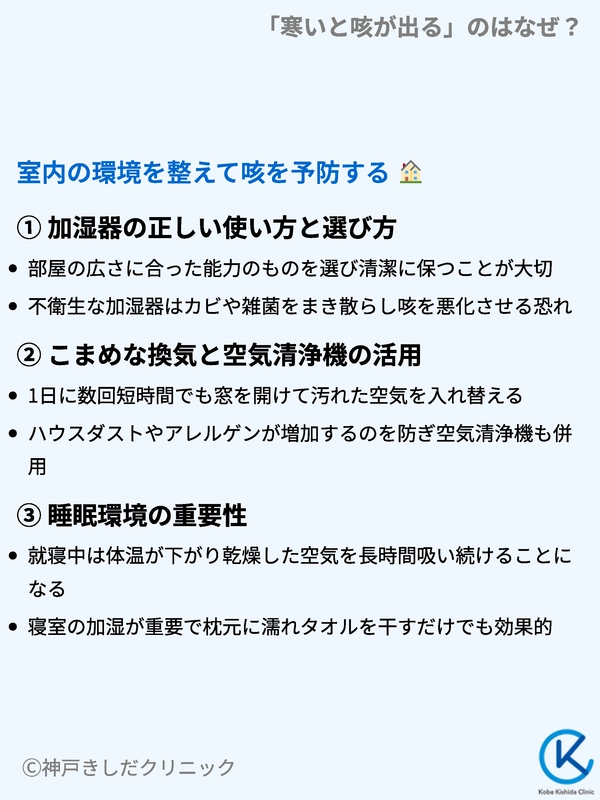
咳を悪化させないための生活習慣
日々の生活習慣を見直すことも咳の予防・改善には大切です。体の抵抗力を高め、気道を健康に保つためのポイントを意識しましょう。
十分な水分補給の重要性
水分をこまめに摂ることで、のどや気道の粘膜を潤し、線毛の働きを助けることができます。また、痰の粘り気を和らげ、排出しやすくする効果も期待できます。
白湯や常温の水、ハーブティーなどがおすすめです。
バランスの取れた食事と免疫力
体の免疫力を正常に保つためには、栄養バランスの取れた食事が基本です。
特に粘膜を健康に保つビタミンAや、免疫機能をサポートするビタミンCなどを意識して摂取しましょう。
粘膜の健康を助ける栄養素
| 栄養素 | 多く含まれる食品 |
|---|---|
| ビタミンA | 緑黄色野菜(人参、かぼちゃ)、レバー、うなぎ |
| ビタミンC | 果物(柑橘類、キウイ)、野菜(ピーマン、ブロッコリー) |
ストレス管理とリラックス法
過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、免疫力を低下させる原因となります。
自分に合ったリラックス法を見つけ、心身ともに休養を取る時間を確保することが、咳の悪化を防ぐ上で重要です。
喫煙や受動喫煙の影響
タバコの煙は気道の粘膜を直接傷つけ、咳を悪化させる最大の要因の一つです。
ご自身が喫煙している場合は禁煙を、周囲に喫煙者がいる場合は受動喫煙を避けるための対策が必要です。
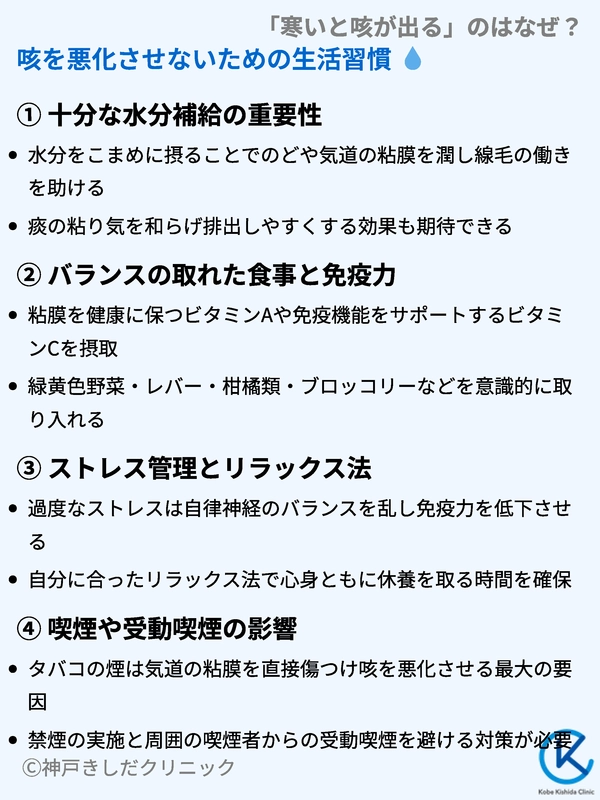
咳が続く場合に医療機関を受診する目安
セルフケアを続けても咳が改善しない場合や、特定の症状が見られる場合は、病気が隠れている可能性があります。
適切なタイミングで専門医の診察を受けましょう。
こんな症状があれば早めに受診を
ただの咳と自己判断せず、以下のような症状が見られる場合は呼吸器内科など専門の医療機関を受診してください。
- 2~3週間以上咳が続いている
- 咳で夜眠れない、目が覚める
- 息苦しさや胸の痛みを感じる
- 痰に色がついている(黄色、緑色など)
- ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音がする
呼吸器内科ではどんな検査をするのか
呼吸器内科では、問診で症状を詳しく聞いた上で必要に応じて以下のような検査を行い、咳の原因を正確に診断します。
呼吸器内科の主な検査
| 検査名 | どのような検査か |
|---|---|
| 胸部X線(レントゲン) | 肺や気管支に異常がないかを確認する |
| 呼吸機能検査 | 肺活量や息を吐く勢いを測定し、気道の狭さなどを調べる |
| 呼気NO(一酸化窒素)検査 | 吐く息に含まれるNO濃度を測定し、気道のアレルギー性炎症の程度を調べる |
医師に伝えるべき症状のポイント
診察を受ける際は、ご自身の症状を正確に伝えることが正しい診断への近道です。
以下の点を整理しておくとスムーズです。
- いつから咳が出始めたか
- どんな時に咳が出やすいか(時間帯、場所、状況など)
- 咳以外の症状はあるか
- 痰は出るか(色や量)
- これまでにかかった病気やアレルギーの有無
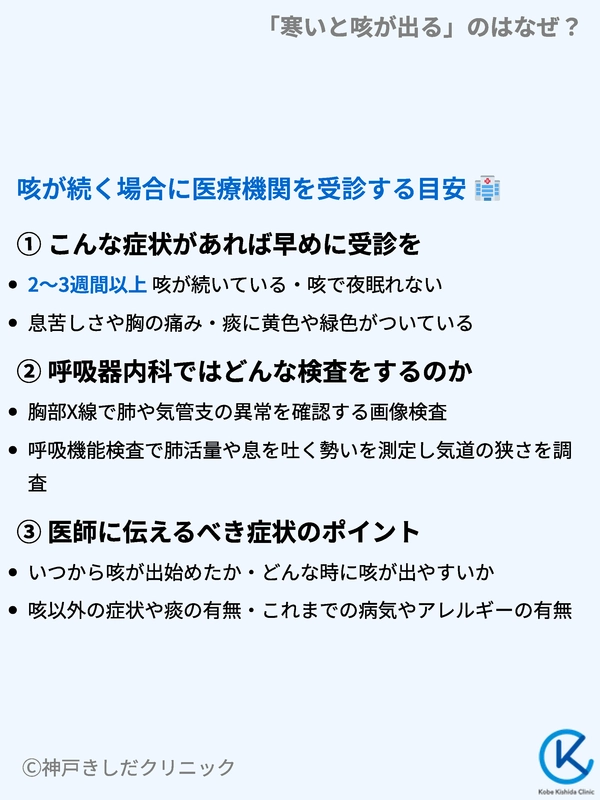
寒い時期の咳に関するよくある質問
最後に、寒い時期の咳に関して患者様からよくいただく質問にお答えします。
- Q咳止め薬を市販薬で済ませても良いですか?
- A
一時的な咳であれば市販薬で様子を見ることも可能ですが、2週間以上続く場合は原因を特定することが重要です。
特に咳喘息の場合では市販の咳止め薬は効果が薄いことが多く、適切な治療が遅れる原因にもなります。
長引く場合は、まず医療機関を受診してください。
- Q子供の咳で特に注意すべき点は何ですか?
- A
お子さんは大人に比べて気道が狭く、少しの炎症でも咳がひどくなりやすい傾向があります。
咳き込んで眠れない、呼吸が苦しそう、顔色が悪いといった様子が見られる場合は、夜間や休日でもためらわずに医療機関を受診することが大切です。
- Q運動すると咳が出やすくなるのはなぜですか?
- A
運動時には呼吸が速く深くなり、一度に多くの冷たい空気を吸い込むため、気道への刺激が強くなります。このことが、運動誘発性の咳の原因となります。
特に咳喘息の人は、運動によって咳が悪化しやすい傾向があります。
- Q加湿器がない場合の簡単な加湿方法はありますか?
- A
加湿器がない場合でも、いくつかの方法で室内の湿度を上げることができます。
手軽な加湿方法
方法 ポイント 洗濯物の部屋干し 最も手軽で効果的な方法の一つ 濡れタオルを干す 特に寝室など、狭い空間の加湿に有効 お湯を沸かす やかんや鍋でお湯を沸かすと、蒸気で湿度が上がる
以上
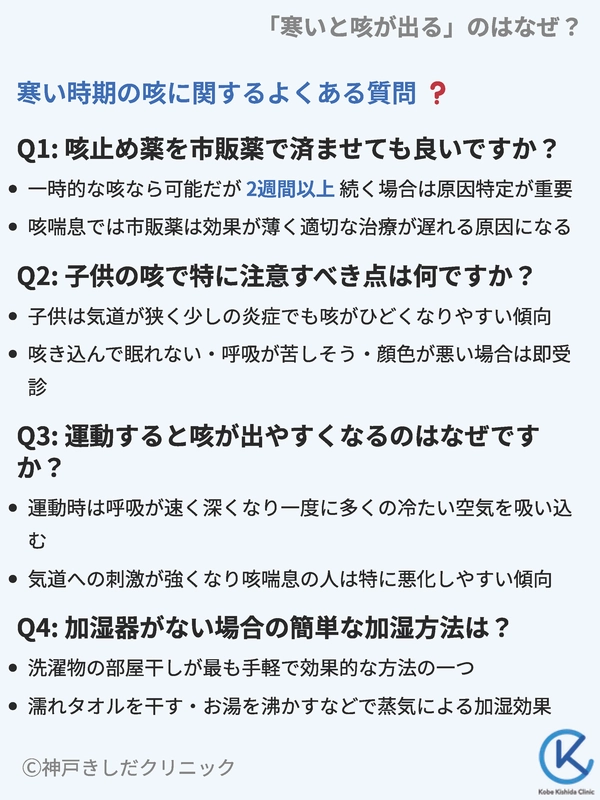
参考にした論文
KOSKELA, Heikki Olavi. Cold air-provoked respiratory symptoms: the mechanisms and management. International journal of circumpolar health, 2007, 66.2: 91-100.
MATSUMOTO, Hisako, et al. Cough triggers and their pathophysiology in patients with prolonged or chronic cough. Allergology International, 2012, 61.1: 123-132.
D’AMATO, Maria, et al. The impact of cold on the respiratory tract and its consequences to respiratory health. Clinical and translational allergy, 2018, 8.1: 20.
KANEMITSU, Yoshihiro, et al. “Cold air” and/or “talking” as cough triggers, a sign for the diagnosis of cough variant asthma. Respiratory investigation, 2016, 54.6: 413-418.
DONG, Ran, et al. A cold environment aggravates cough hyperreactivity in guinea pigs with cough by activating the TRPA1 signaling pathway in skin. Frontiers in Physiology, 2020, 11: 833.
XING, Hong, et al. TRPM8 mechanism of autonomic nerve response to cold in respiratory airway. Molecular Pain, 2008, 4: 1744-8069-4-22.
KANG, Sung-Yoon, et al. Cough persistence in adults with chronic cough: a 4-year retrospective cohort study. Allergology International, 2020, 69.4: 588-593.
PLEVKOVA, Jana, et al. The role of trigeminal nasal TRPM8-expressing afferent neurons in the antitussive effects of menthol. Journal of applied physiology, 2013, 115.2: 268-274.
CHUNG, K. F. Chronic ‘cough hypersensitivity syndrome’: a more precise label for chronic cough. Pulmonary pharmacology & therapeutics, 2011, 24.3: 267-271.



