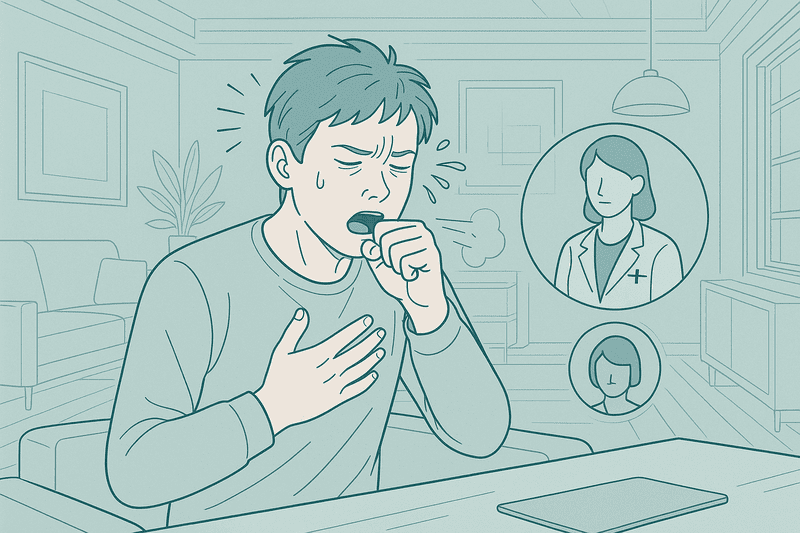食事中や飲み物を飲んだ時、あるいは何でもない時に突然むせて、激しい咳が止まらなくなると不安になるものです。
「むせる 咳が止まらない」状態が続く場合、単なる「むせ」ではなく、背景に何らかの病気が隠れている可能性があります。
この記事では、むせて咳が止まらなくなる原因、考えられる病気、そして何科を受診すべきかについて、呼吸器内科の観点から詳しく解説します。
そもそも「むせる」とはどういう状態か
食べ物や飲み物が気管に入る「誤嚥(ごえん)」
私たちは通常、口から入った食べ物や飲み物を食道を通して胃に送ります。しかし、これらが誤って気管(空気の通り道)に入ってしまうことがあります。これを「誤嚥(ごえん)」と呼びます。
気管は肺につながっているため、異物が入ると非常に危険です。「むせる」という行為は、この誤嚥した異物を気管から排出しようとする体の重要な防御反応です。
誤嚥を防ぐ「嚥下(えんげ)反射」
食べ物や飲み物を飲み込む動作を「嚥下(えんげ)」と言います。飲み込む瞬間、喉の奥にある「喉頭蓋(こうとうがい)」というフタが素早く気管の入り口を塞ぎ、食べ物が食道へ正しく流れるよう誘導します。
この一連の複雑な動きは「嚥下反射」と呼ばれ、無意識のうちに行われています。この反射がスムーズに働かないと、タイミングがずれ、誤嚥が起こりやすくなります。
むせと咳の防御反応
気管の粘膜は非常に敏感です。もし食べ物のかけらや水分が気管に入ると、体はこれを「異物」と感知し、即座に排除しようとします。その結果、激しい「むせ」や「咳」が起こります。
これは、異物が肺の奥深くに入るのを防ぎ、肺炎などを予防するための大切な体の仕組みです。
咳が止まらないのは、異物が完全に排出されるまで、あるいは気管の刺激が収まるまで防御反応が続いている状態と言えます。
加齢による嚥下機能の低下
年齢を重ねると、全身の筋肉が衰えるのと同様に、飲み込みに関わる喉の筋力や感覚も低下します。嚥下反射のタイミングが遅れたり、喉頭蓋がうまく閉じなくなったりすることが増えます。
このことにより、若い頃は何ともなかった水分や小さな食べ物でもむせやすくなります。これは加齢に伴う自然な変化の一つですが、頻度が高い場合は注意が必要です。
むせて咳が止まらなくなる主な原因
食べ方や飲み方の問題
病気ではなく、日常の習慣がむせを引き起こしている場合もあります。特に「ながら食い」や「早食い」は危険です。
テレビを見ながら、スマートフォンを操作しながらの食事は、飲み込むことへの意識が散漫になり、嚥下反射のタイミングがずれやすくなります。
また、よく噛まずに急いで飲み込むと、大きな塊が喉を通過するため、誤嚥のリスクが高まります。
むせやすい食べ方・飲み方
| 行動 | 理由 | 対策 |
|---|---|---|
| 早食い・かきこむ | よく噛まずに飲み込むため | 一口の量を減らし、30回程度噛む |
| ながら食い | 嚥下への意識が低下する | 食事に集中する |
| 水分で流し込む | 固形物と液体が同時に喉を通過するため | 食べ物を飲み込んでから水分をとる |
加齢に伴う筋力の衰え
前述の通り、加齢は嚥下機能低下の大きな要因です。舌や喉、首周りの筋力が低下すると、食べ物を食道へ送り込む力が弱まります。また、唾液の分泌量が減ることも関係します。
唾液は食べ物をまとめて飲み込みやすくする役割がありますが、これが減ると、口の中が乾燥し、食べ物がバラバラになって気管に入りやすくなります。
ストレスや疲労による影響
嚥下運動は、自律神経によってもコントロールされています。強いストレスや慢性的な疲労があると、自律神経のバランスが乱れ、嚥下反射がうまく働かなくなることがあります。
「喉がつかえる感じがする」「飲み込みにくい」といった症状が現れ、結果としてむせやすくなることもあります。
特定の病気による症状
むせて咳が止まらない状態が続く場合、背景に何らかの病気が隠れている可能性を考えなくてはなりません。
呼吸器系の病気、消化器系の病気、あるいは脳神経系の病気などが、嚥下機能に影響を与えていることがあります。
単なる「むせやすい体質」と自己判断せず、症状が続く場合は専門医に相談することが重要です。
むせと咳が続く時に考えられる病気(呼吸器系)
咳喘息(せきぜんそく)
咳喘息は、一般的な喘息のような「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難はなく、乾いた咳だけが長く続く病気です。
気道が過敏になっており、冷たい空気、タバコの煙、会話、ストレスなど、わずかな刺激でも咳の発作が起こります。
この気道の過敏性が、むせた時の刺激を増幅させ、咳が止まらなくなる一因となることがあります。
気管支喘息
気管支喘息も咳喘息と同様に気道が過敏な状態です。喘息患者が食事中や飲水時にむせると、その刺激が発作の引き金(トリガー)となり、激しい咳や喘鳴、呼吸困難を引き起こすことがあります。
特に、冷たい飲み物や酸味の強い食べ物が刺激になりやすいと言われています。
誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)
誤嚥性肺炎は、食べ物や飲み物、あるいは唾液が細菌と共に気管に入り、肺で炎症を起こす病気です。高齢者や寝たきりの方に多く見られます。
嚥下機能が低下していると、夜間に唾液が気管に流れ込む「不顕性誤嚥(ふけんせいごえん)」が起こりやすくなります。むせや咳が続くほか、発熱や痰の増加、元気がないといった症状が現れます。
誤嚥性肺炎の主な症状
| 症状 | 特徴 |
|---|---|
| 咳・痰 | 食事中や食後に悪化することがある。痰の色が濃くなることも。 |
| 発熱 | 原因不明の熱が続くことがある。高齢者では熱が出にくい場合もある。 |
| 全身倦怠感 | なんとなく元気がない、食欲がない、ぼーっとする。 |
COPD(慢性閉塞性肺疾患)
COPDは、主に長期間の喫煙によって肺に炎症が起き、呼吸機能が低下する病気です。日常的に咳や痰、息切れがあります。
COPDの患者は、もともと気道が狭くなっているため、わずかな誤嚥でも強い咳き込みにつながりやすい傾向があります。
また、咳をする体力自体も低下しているため、一度むせるとなかなか回復できないことがあります。
むせと咳が続く時に考えられる病気(消化器・耳鼻咽喉科系)
逆流性食道炎(GERD)
逆流性食道炎は、胃酸を含む胃の内容物が食道に逆流する病気です。
主な症状は胸焼けや「呑酸(どんさん)」(酸っぱいものがこみ上げる感じ)ですが、逆流した胃酸が喉や気管を刺激することで、慢性的な咳やむせを引き起こすことがあります。
特に夜間や早朝、横になっている時に咳が出やすいのが特徴です。
逆流性食道炎と咳の関係
| 逆流による刺激 | 起こる症状 |
|---|---|
| 胃酸が食道を刺激 | 咳反射が誘発される(食道気管支反射) |
| 胃酸が喉(咽喉頭)まで逆流 | 喉の炎症や声帯の浮腫が起こり、咳やむせ、声がれが出る |
| 胃酸が気管に直接入る | 誤嚥と同じ状態になり、激しい咳き込みが起こる |
咽喉頭(いんこうとう)アレルギー
花粉やハウスダストなどのアレルゲンが喉(咽頭や喉頭)の粘膜に付着し、アレルギー反応を起こす病気です。
「喉のイガイガ感」「かゆみ」「異物感」などが生じ、これが刺激となって咳やむせが出ることがあります。鼻水が喉に落ちる「後鼻漏(こうびろう)」も、咳やむせの原因となります。
嚥下障害
病気そのものというより、「飲み込む機能」自体が障害されている状態を指します。加齢による筋力低下のほか、脳梗塞やパーキンソン病などの脳神経疾患、あるいは喉の手術後などが原因となります。
食べ物が飲み込みにくい、時間がかかる、むせる、咳き込むといった症状が顕著に現れます。
嚥下障害のサイン
| タイミング | 主なサイン |
|---|---|
| 食事前 | よだれが多い、食べ物を認識しにくい |
| 食事中 | むせる、咳き込む、飲み込むのに時間がかかる |
| 食事後 | 声がガラガラになる(湿性嗄声)、口の中に食べ物が残る |
食道アカラシア
食道の運動機能に障害が起こり、食べた物が胃にスムーズに送られなくなる病気です。食道の下部(胃とのつなぎ目)がうまく開かず、食べ物が食道に溜まってしまいます。
これにより、胸のつかえ感や逆流、そして誤嚥による咳が引き起こされます。比較的まれな病気ですが、嚥下障害の原因の一つです。
危険な「むせ」と咳のサインとは
咳が2週間以上続く
風邪による咳は通常1〜2週間程度で改善します。しかし、むせを伴う咳が2週間以上、特に3週間を超えて続く場合は、単なる風邪や一時的なむせとは考えにくいです。
咳喘息、逆流性食道炎、あるいは他の慢性的な呼吸器疾患の可能性を疑い、一度医療機関を受診することが必要です。
発熱や胸の痛みを伴う
むせや咳に加えて、発熱、胸の痛み、呼吸困難、色のついた痰が出る場合は、肺炎(特に誤嚥性肺炎)や気管支炎など、肺で重い炎症が起きている可能性があります。
これらの症状は、体が深刻な感染症と戦っているサインです。特に高齢者の場合は、症状がはっきりしないこともあるため、注意深く観察し、早急に受診してください。
受診を急ぐべき症状
| 症状 | 疑われる状態 | 対応 |
|---|---|---|
| 38度以上の発熱 | 肺炎、重い気管支炎 | 早急に内科・呼吸器内科を受診 |
| 胸の痛み・呼吸困難 | 肺炎、喘息発作、心疾患など | 早急に受診(救急も考慮) |
| 血痰(痰に血が混じる) | 肺結核、肺がん、気管支拡張症など | 速やかに呼吸器内科を受診 |
体重が減少してきた
むせるのが怖くて食事が十分に摂れなくなり、体重が減少することがあります。これは栄養不足のサインであり、体力や免疫力の低下につながります。
また、COPD、肺がん、食道がんなどの病気が背景にある場合も体重減少が見られます。「食事が摂れない」「意図せず痩せてきた」という場合は、必ず医師に相談してください。
声のかすれ(嗄声)が治らない
むせや咳と共に、声のかすれ(嗄声)が続く場合、喉(声帯)に異常がある可能性が考えられます。
逆流性食道炎による胃酸の刺激で声帯が炎症を起こしている(逆流性喉頭炎)ことや、咳のしすぎで声帯ポリープができていること、あるいは喉頭がんや肺がんが反回神経(声帯を動かす神経)に影響している可能性も否定できません。
むせて咳が止まらない時は何科を受診すべきか
まずは呼吸器内科への相談を推奨
「むせて咳が止まらない」という症状の背景には、気管支喘息、咳喘息、COPD、誤嚥性肺炎など、呼吸器系の病気が隠れている可能性が多くあります。
特に咳が長く続く場合、呼吸器の専門家である呼吸器内科で精密検査を受けることが、正確な診断への近道です。
当院のような呼吸器内科クリニックでは、咳の原因を特定するための詳細な問診や検査(レントゲン、呼吸機能検査など)を行います。
症状に応じた診療科の選び方
咳以外の症状にも注目することで、受診すべき診療科の目安が立てやすくなります。ただし、複数の原因が関わっていることも多いため、自己判断は禁物です。
症状別の受診目安
| 主な症状 | 推奨される診療科 | 考えられる主な病気 |
|---|---|---|
| 咳が長く続く、息苦しさ | 呼吸器内科 | 咳喘息、気管支喘息、COPD |
| 発熱、色のついた痰 | 呼吸器内科・内科 | 肺炎、誤嚥性肺炎 |
| 胸焼け、酸っぱい感じ | 消化器内科・内科 | 逆流性食道炎 |
| 喉の違和感、鼻水 | 耳鼻咽喉科 | 咽喉頭アレルギー、後鼻漏 |
耳鼻咽喉科や消化器内科が適しているケース
むせや咳の原因が、明らかに喉や鼻にあると感じる場合(喉のイガイガ、鼻水が喉に落ちる感じが強いなど)は、耳鼻咽喉科の受診が適しています。
ファイバースコープで喉の状態を直接確認できます。また、胸焼けや胃酸の逆流感が強い場合は、消化器内科で胃カメラなどの検査を受けることが原因特定につながります。
複数の診療科での連携治療
例えば、呼吸器内科で喘息と診断されても、同時に逆流性食道炎を合併していると、喘息の治療だけでは咳が治まらないことがあります。
この場合は、呼吸器内科と消化器内科が連携して治療を進める必要があります。
まずは窓口となるかかりつけ医や、最も強く出ている症状の専門科を受診し、必要に応じて他の診療科を紹介してもらうのが良いでしょう。
日常生活でできる「むせ」と咳の予防・対策
食事の工夫と正しい姿勢
むせを防ぐためには、日々の食事が非常に重要です。まず、食事中は背筋を伸ばし、少し前傾姿勢(お辞儀をするような角度)を意識します。
顎を軽く引くことで、気管の入り口が狭まり、食べ物が食道へ流れやすくなります。また、食べ物や飲み物の形態を工夫することも有効です。
食事の際の注意点
| 工夫の種類 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 食べ物の形態 | パサパサするもの(パン、芋類)は水分で湿らせる。 |
| 飲み物 | 水やお茶はむせやすい。とろみ剤を使って飲み込みやすくする。 |
| 食べ方 | 一口の量を少なくし、よく噛んでから飲み込む。 |
口腔ケアの重要性
口の中が不潔だと、細菌が増殖します。その状態で誤嚥すると、細菌が唾液と共に肺に入り、誤嚥性肺炎のリスクが格段に高まります。
食後や就寝前の歯磨きやうがいを徹底し、口の中を清潔に保つことが、肺炎予防の基本です。入れ歯を使用している方は、入れ歯の清掃も忘れずに行いましょう。
口腔ケアのポイント
- 食後の歯磨き
- 舌の清掃(舌苔の除去)
- うがい(ブクブクうがい・ガラガラうがい)
- 定期的な歯科受診
嚥下体操と喉のトレーニング
飲み込みに関わる筋肉も、トレーニングで鍛えることができます。
食事の前に「嚥下体操」を取り入れると、喉の筋肉がほぐれ、唾液の分泌も促されるため、むせの予防に効果的です。
簡単な嚥下体操
| 体操の種類 | 方法 |
|---|---|
| 深呼吸 | 鼻から息を吸い、口からゆっくり吐き出す。 |
| 首の運動 | ゆっくりと首を左右に回したり、前後に倒したりする。 |
| パタカラ体操 | 「パ」「タ」「カ」「ラ」と一音ずつはっきり発声する。 |
禁煙と生活習慣の見直し
喫煙は、気道の粘膜を傷つけ、咳や痰の原因となるだけでなく、喉の感覚を鈍らせて嚥下反射を弱める可能性も指摘されています。むせや咳が気になる方は、禁煙が第一です。
また、過度な飲酒は筋肉を弛緩させ、逆流性食道炎を悪化させるため、控えることが賢明です。十分な睡眠と適度な運動を心がけ、体全体の調子を整えることも大切です。
よくある質問
- Qむせた後、咳だけが長く続くのはなぜですか?
- A
むせた時の刺激で、気管や気管支が一時的に過敏になっているためと考えられます。
特に、もともと咳喘息や気管支喘息の素因がある方の場合、むせが発作の引き金となり、気道の炎症が続いて咳だけが残ることがあります。
また、逆流性食道炎がある場合も、胃酸の刺激で喉が荒れているため、咳が長引きやすくなります。2週間以上続く場合はご相談ください。
- Q子供がよくむせて咳き込むのですが、大丈夫でしょうか?
- A
お子様、特に乳幼児は、まだ嚥下機能が発達途中のため、大人に比べてむせやすい傾向があります。
食べ物や飲み物の形態が年齢に合っているか、食事の環境(集中できるか、姿勢はどうか)を見直してみてください。
ただし、特定の食べ物(ピーナッツなど)で必ずむせる、咳き込みが激しい、顔色が悪くなる、体重が増えないなどの場合は、食物アレルギー、喘息、あるいは生まれつきの喉や食道の形態異常なども考えられるため、小児科や耳鼻咽喉科で相談することをお勧めします。
- Qストレスでむせやすくなることはありますか?
- A
はい、あります。
嚥下運動は自律神経によって調整されているため、強いストレスや緊張、不安を感じると、喉の筋肉が異常に緊張したり、唾液の分泌が減ったりして、飲み込みのタイミングがずれやすくなります。
これを「咽喉頭異常感症」や「ヒステリー球」と呼ぶこともあります。
検査で異常が見つからないのに症状が続く場合は、ストレスケアやリラックスできる環境を整えることも治療の一環となります。
- Q薬を飲むとむせることが多いのですが、どうすればよいですか?
- A
薬(特に錠剤やカプセル)が喉にひっかかり、むせてしまう方は少なくありません。いくつかの対処法があります。
まず、薬を飲む前に水や白湯で口を潤しておくことが大切です。上を向いて飲むと気管が開きやすくなるため、少し顎を引いて飲み込むように意識してください。
それでも難しい場合は、服薬用のゼリーを使用すると、薬がまとまって飲み込みやすくなります。
薬の種類によっては、砕いたりカプセルを開けたりしてはいけないものもあるため、飲み方を変更する場合は、必ず医師や薬剤師にご相談ください。