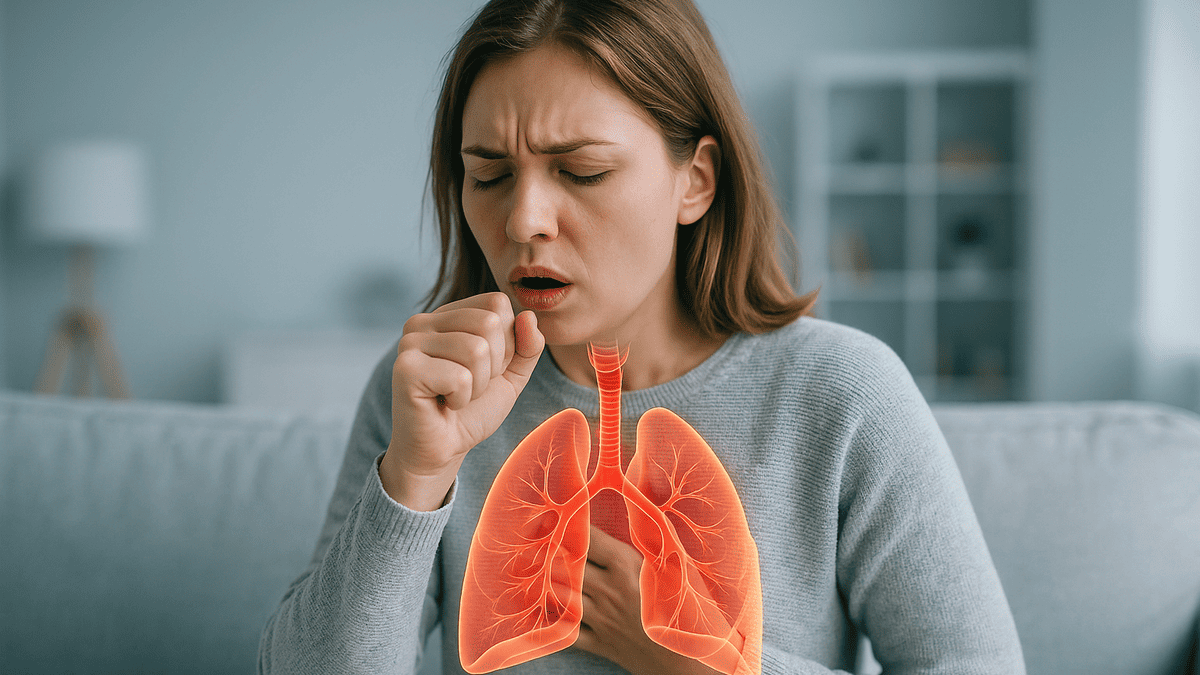風邪をひいた後、咳だけがいつまでも治らない、一度良くなったと思ったらまた咳や痰がひどくなる。そんな経験はありませんか。
多くの場合は自然に治る「急性気管支炎」ですが、症状が長引いたり何度も繰り返したりする背景には、単なる風邪ではない原因が隠れている可能性があります。
放置すると気管支の炎症が慢性化し、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。
この記事では気管支炎が治らない、繰り返す主な原因を詳しく解説し、症状を悪化させないための正しい治療法と、今日から実践できる生活習慣のポイントを呼吸器内科の視点から分かりやすく紹介します。
そもそも気管支炎とは 急性・慢性の違い
気管支炎とは、のど(咽頭)と肺を結ぶ空気の通り道である「気管支」に炎症が起きる病気です。
この気管支炎は症状が続く期間によって大きく「急性」と「慢性」に分けられ、それぞれ原因や対処法が異なります。
急性気管支炎の原因と症状
急性気管支炎のほとんどは、風邪やインフルエンザなどのウイルス感染が原因で発症します。ウイルスによって気管支の粘膜が傷つき、そこに炎症が起こります。
主な症状は、しつこい咳や痰、発熱、倦怠感などです。通常は1~3週間程度で症状は改善します。
慢性気管支炎の定義と主な原因
咳や痰が1年のうちに3ヶ月以上、それが2年以上連続して続く場合、「慢性気管支炎」と定義されます。
最大の原因は長期間の喫煙です。タバコの煙などの有害物質を吸い込み続けることで、気管支に常に炎症が起きている状態になります。
進行すると気道が狭くなり、呼吸が苦しくなる慢性閉塞性肺疾患(COPD)に至ることもあります。
急性気管支炎と慢性気管支炎の比較
| 項目 | 急性気管支炎 | 慢性気管支炎 |
|---|---|---|
| 主な原因 | ウイルス感染 | 長期の喫煙、大気汚染など |
| 症状の期間 | 数週間以内 | 2年以上続く |
| 主な症状 | 咳、痰、発熱、倦怠感 | 持続的な咳と痰、息切れ |
なぜ気管支炎が治らない・長引くのか
通常なら数週間で治まるはずの急性気管支炎が、なかなか治らない。その背景には、いくつかの要因が考えられます。ご自身の生活習慣や環境を振り返ってみましょう。
不十分な初期治療と自己判断
「ただの風邪だから」と自己判断して安静にせず、無理をしたり市販薬だけで済ませたりすると、炎症が十分に治まりきらないことがあります。
特に気管支の粘膜が受けたダメージが回復する前に活動を再開すると、症状がぶり返しやすくなります。
喫煙や受動喫煙による気道への刺激
喫煙は気管支炎を長引かせる最大の原因です。タバコの煙は気管支の粘膜を直接刺激し、炎症を悪化させます。また、粘液を排出する線毛の働きを弱めるため、痰が切れにくくなって咳が長引きます。
これは、ご自身が吸う場合だけでなく、周囲の人の煙を吸う「受動喫煙」でも同様です。
気管支炎を長引かせる要因
| 分類 | 具体的な要因 |
|---|---|
| 行動 | 無理をする、睡眠不足、喫煙 |
| 環境 | 空気の乾燥、ホコリや汚染物質 |
| 身体の状態 | 免疫力の低下、アレルギー体質 |
免疫力の低下
ストレスや疲労、栄養不足などによって体の免疫力が低下していると、ウイルスや細菌に対する抵抗力が弱まり、炎症が治りにくくなります。
気管支炎が治りきらないまま、新たな感染症にかかってしまうこともあります。
気管支炎を繰り返す背景にある他の病気
年に何度も気管支炎にかかるという方は気管支炎そのものではなく、背景に別の病気が隠れている可能性を考える必要があります。
特に、咳や痰が長引く場合は注意が必要です。
咳喘息や気管支喘息
特定の季節や時間帯(夜間~早朝)に咳がひどくなる、冷たい空気や会話で咳き込むといった症状がある場合、咳喘息や気管支喘息の可能性があります。
これらは気道にアレルギー性の炎症が起きている状態で、適切な治療を行わないと咳を繰り返します。
副鼻腔気管支症候群
鼻づまりや色のついた鼻水が続く「副鼻腔炎(蓄膿症)」を合併している場合、鼻水がのどに落ちる「後鼻漏(こうびろう)」によって気管支の炎症が誘発され、気管支炎を繰り返すことがあります。
これを副鼻腔気管支症候群と呼びます。
繰り返す気管支炎で考えられる病気
| 病名 | 主な特徴 |
|---|---|
| 咳喘息・気管支喘息 | 特定の状況で悪化する長引く咳、喘鳴(ゼーゼー) |
| 副鼻腔気管支症候群 | 色のついた鼻水や痰、後鼻漏を伴う |
| 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 主に喫煙者にみられ、体を動かした時の息切れが特徴 |
その他の呼吸器疾患
まれではありますが、百日咳やマイコプラズマなどの非定型的な細菌感染症、あるいは肺がんや結核などが、治りにくい咳の原因となっていることもあります。
自己判断はせずに、専門医による鑑別が重要です。
呼吸器内科で行う検査と治療法
長引く、あるいは繰り返す気管支炎の原因を正確に突き止めるため、呼吸器内科では詳しい検査を行います。
診断に基づき、症状を和らげるだけでなく、根本的な原因に対する治療を進めます。
正確な診断のための検査
問診で症状を詳しく伺った後、以下のような検査を組み合わせて診断します。
呼吸器内科での主な検査
| 検査名 | 目的 |
|---|---|
| 胸部X線(レントゲン) | 肺炎や肺がん、結核など他の病気がないかを確認する |
| 呼吸機能検査 | 気道が狭くなっていないか(喘息やCOPDの可能性)を調べる |
| 喀痰検査・血液検査 | 炎症の原因となっている細菌やアレルギーの有無を調べる |
症状を和らげる薬物療法
原因や症状に応じて、様々な薬を使い分けます。例えば、痰が絡む咳には痰を出しやすくする「去痰薬」を、気道が狭くなっている喘息などには気道を広げる「気管支拡張薬」を使用します。
細菌感染が疑われる場合には「抗菌薬(抗生物質)」を処方することもあります。
原因に合わせた専門的な治療
喘息が原因であれば、炎症を抑える「吸入ステロイド薬」が治療の中心となります。
また、ネブライザーという機器を使って薬剤を霧状にして吸入する治療は、薬剤を直接気管支に届けることができるため高い効果が期待できます。
気管支炎の主な治療薬
| 薬剤の種類 | 主な働き |
|---|---|
| 去痰薬 | 痰の粘り気を下げ、排出しやすくする |
| 気管支拡張薬 | 狭くなった気管支を広げ、呼吸を楽にする |
| 吸入ステロイド薬 | 気道のアレルギー性炎症を根本から抑える |
気管支炎を悪化させないための生活習慣
薬物治療と並行して、日々の生活習慣を見直すことが気管支炎の回復を早め、再発を防ぐ上で非常に重要です。気管支をいたわる生活を心がけましょう。
十分な休養と睡眠
体の回復には、何よりもまず休養が必要です。特に急性期は無理をせず、体を休ませることを最優先してください。十分な睡眠は免疫力を高めるためにも大切です。
適切な加湿とこまめな換気
空気が乾燥していると気管支の粘膜が傷つきやすくなり、咳を誘発します。加湿器などを使って室内の湿度を50~60%に保つようにしましょう。
また、定期的に窓を開けて換気し、室内の空気を清潔に保つことも重要です。
水分補給と栄養バランスの取れた食事
水分を十分に摂ることは痰を柔らかくし、排出しやすくするのに役立ちます。
また、粘膜の健康を保つビタミンAや、免疫力をサポートするビタミンCなどを多く含む、バランスの取れた食事を心がけましょう。
気管支の健康をサポートする栄養素
| 栄養素 | 多く含む食品の例 |
|---|---|
| ビタミンA | 緑黄色野菜(人参、かぼちゃ)、レバー |
| ビタミンC | 果物(柑橘類)、野菜(ピーマン、ブロッコリー) |
| タンパク質 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
禁煙の徹底
喫煙習慣がある場合、気管支炎を根本的に治すためには禁煙が必要です。
ご自身の意志だけでは難しい場合、禁煙外来などで専門家のサポートを受けることも有効な手段です。
気管支炎に関するよくある質問
最後に、気管支炎について患者様からよくいただく質問とその回答をまとめました。
- Q市販の咳止めを飲んでも大丈夫ですか?
- A
咳は異物を体外に排出しようとする重要な防御反応です。
自己判断で強力な咳止め薬を使用すると、かえって痰が気管支に溜まり、症状を悪化させる可能性があります。特に痰が絡む咳の場合は注意が必要です。
薬を使用する際は薬剤師に相談するか、医療機関を受診してください。
咳の種類と薬の選び方の注意点
咳の種類 薬選びのポイント 乾いた咳(コンコン) 咳中枢に働く鎮咳薬が使われることがある 湿った咳(ゴホゴホ) 痰を出しやすくする去痰薬が中心。鎮咳薬は慎重に。
- Q気管支炎は他の人にうつりますか?
- A
ウイルス感染による急性気管支炎は、その原因となっているウイルスが咳やくしゃみによって他の人にうつる可能性があります。
一方、喫煙が原因の慢性気管支炎や、アレルギーが関与する喘息などは感染症ではないため、人にうつることはありません。
- Q子供の気管支炎で特に注意すべき点は何ですか?
- A
お子さんは大人に比べて気道が細く、少しの炎症でも呼吸が苦しくなりやすい特徴があります。以下のサインが見られる場合は早めに小児科を受診しましょう。
- 咳で眠れない、嘔吐してしまう
- 呼吸時に肩が上下したり、小鼻がヒクヒクしたりする
- 顔色が悪く、ぐったりしている
- 水分が摂れない
以上
参考にした論文
ISHIFUJI, Tomoko, et al. Recurrent pneumonia among Japanese adults: disease burden and risk factors. BMC Pulmonary Medicine, 2017, 17.1: 12.
ITO, Kiyoaki, et al. Risk factors for long‐term persistence of serum hepatitis B surface antigen following acute hepatitis B virus infection in Japanese adults. Hepatology, 2014, 59.1: 89-97.
NAKAMURA, Yoichi, et al. Japanese guidelines for adult asthma 2020. Allergology International, 2020, 69.4: 519-548.
SUZUKI, Takeo, et al. Clinical characteristics, treatment patterns, disease burden, and persistence/adherence in patients with asthma initiating inhaled triple therapy: real-world evidence from Japan. Current Medical Research and Opinion, 2020, 36.6: 1049-1057.
WATASE, Mayuko, et al. Cough and sputum in long COVID are associated with severe acute COVID-19: a Japanese cohort study. Respiratory Research, 2023, 24.1: 283.
KADOWAKI, Toru, et al. An analysis of etiology, causal pathogens, imaging patterns, and treatment of Japanese patients with bronchiectasis. Respiratory investigation, 2015, 53.1: 37-44.
KURAI, Daisuke, et al. Virus-induced exacerbations in asthma and COPD. Frontiers in microbiology, 2013, 4: 293.
NAKAMURA, Kozue, et al. Cigarette smoking and the adult onset of bronchial asthma in Japanese men and women. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 2009, 102.4: 288-293.
IZUMIKAWA, Koichi, et al. Clinical features, risk factors and treatment of fulminant Mycoplasma pneumoniae pneumonia: a review of the Japanese literature. Journal of Infection and Chemotherapy, 2014, 20.3: 181-185.
IGARI, Hidetoshi, et al. Epidemiology and treatment outcome of pneumonia: Analysis based on Japan national database. Journal of Infection and Chemotherapy, 2020, 26.1: 58-62.
SUGIURA, Saiko, et al. Prevalence and risk factors of MRI abnormality which was suspected as sinusitis in Japanese middle‐aged and elderly community dwellers. BioMed Research International, 2018, 2018.1: 4096845.