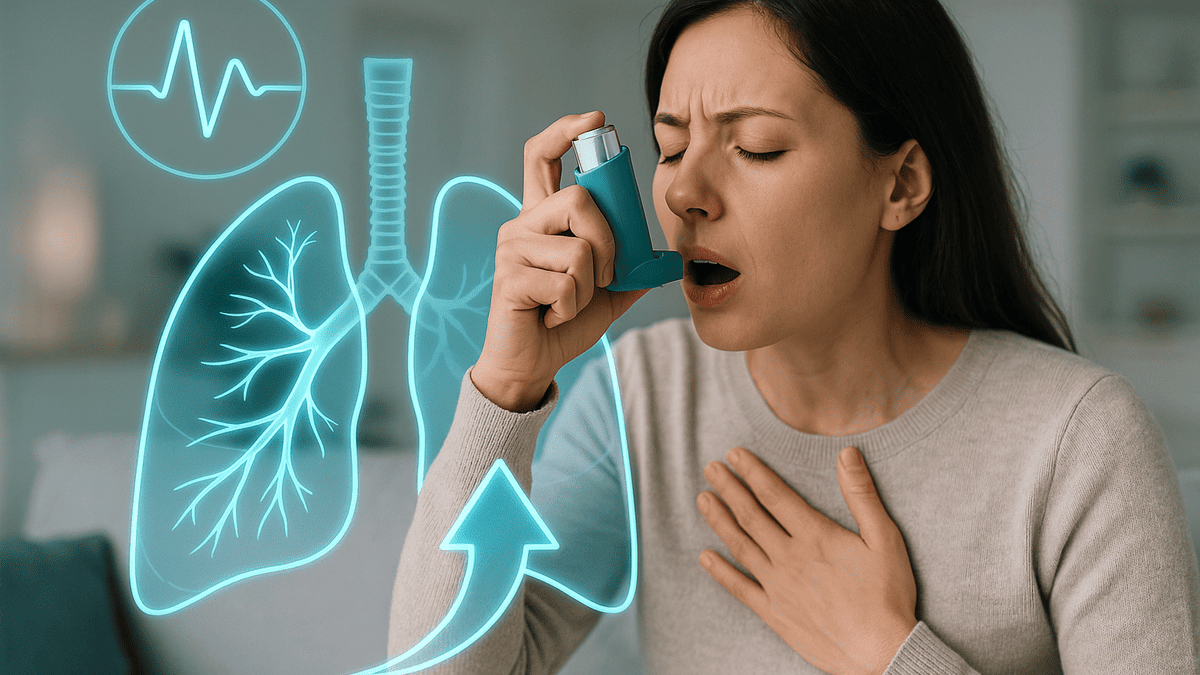気管支喘息は、咳や息苦しい発作を繰り返す慢性の病気です。適切な治療を行わずにいると日常生活に大きな支障をきたすだけでなく、命に関わる重篤な発作につながることもあります。
現在の喘息治療は単に発作を抑えるだけでなく、気道の炎症をコントロールして発作そのものを起こさせない「長期管理」が基本です。
この記事では喘息の根本原因である気道の炎症から、ご自身の状態を知るための重症度の考え方、そして重症度に応じた具体的な治療法まで専門医が分かりやすく解説します。
気管支喘息とは?気道の慢性的な炎症が原因
気管支喘息は空気の通り道である「気道」に、慢性的な炎症が起きている状態です。
症状がない時でも気道の内部では炎症がくすぶり続けており、この炎症のために気道が非常に敏感になっています。
喘息の基本的な病態
喘息患者様の気道は健康な人に比べて粘膜がむくんでおり、常に軽い炎症が続いています。このため、わずかな刺激にも過剰に反応してしまい、気道が急激に狭くなる「発作」を起こします。
炎症が長引くと気道の壁が厚く硬くなってしまう「リモデリング」という状態に進み、呼吸機能が元に戻りにくくなることもあるため、早期からの適切な治療が重要です。
主な症状(咳、喘鳴、呼吸困難)
喘息の症状は気道が狭くなることによって起こります。代表的な症状にはしつこい咳、息をする時に「ゼーゼー、ヒューヒュー」と音がする喘鳴(ぜんめい)、そして息苦しさ(呼吸困難)があります。
これらの症状は夜間から早朝にかけて現れやすいという特徴があります。
気管支喘息の代表的な症状
| 症状 | 特徴 |
|---|---|
| 咳 | 特に夜間や早朝に出やすい。会話や運動で誘発されることも。 |
| 喘鳴 | 息を吐く時に聞こえやすい「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音。 |
| 呼吸困難 | 息が苦しい、胸が締め付けられるような感覚。発作時には横になれないことも。 |
発作が起こるきっかけ
気道が過敏になっているため、様々な刺激が発作の引き金(アレルゲンや誘因)となります。
人によってきっかけは異なりますが、代表的なものを知っておき、できるだけ避けることが発作予防につながります。
- ダニ、ハウスダスト、カビ、ペットの毛
- 風邪などのウイルス感染
- タバコの煙(受動喫煙を含む)
- 気候の変化(寒暖差、台風など)
- 過労やストレス
喘息治療の2つの柱 長期管理と発作治療
現在の喘息治療は症状がある時だけ薬を使う対症療法ではなく、「長期管理薬」で普段から気道の炎症を抑え、発作を予防することが中心です。
これに加えて、万が一起こってしまった発作を速やかに鎮める「発作治療薬」を使い分けます。
長期管理薬(コントローラー)の役割
長期管理薬は喘息の根本原因である気道の炎症を抑えるための薬です。毎日規則正しく使用することで気道の過敏性を改善し、発作が起こりにくい状態を維持します。
症状がないからといって自己判断でやめてしまうと炎症が再燃して発作が起きやすくなるため、継続的な使用が大切です。
発作治療薬(リリーバー)の役割
発作治療薬は発作によって狭くなった気道を速やかに広げ、息苦しさを和らげるための薬です。即効性があるため「頓服薬」として使います。
ただし、この薬は気道の炎症を抑える作用はないため、頻繁に使用する状態は喘息のコントロールが不十分であるサインです。
発作治療薬の使用回数が増えてきたら、主治医に相談が必要です。
長期管理薬と発作治療薬の主な違い
| 種類 | 主な薬剤 | 役割 |
|---|---|---|
| 長期管理薬(コントローラー) | 吸入ステロイド薬など | 気道の炎症を抑え、発作を予防する(毎日使用) |
| 発作治療薬(リリーバー) | 短時間作用性β2刺激薬など | 発作時に気管支を広げ、症状を和らげる(発作時のみ) |
治療目標は「発作ゼロ」の状態
喘息治療の最終的な目標は喘息がない人と変わらない日常生活を送れることです。具体的には日中や夜間の症状がなく、発作治療薬を使う必要もなく、運動を含めた活動が制限されない状態を目指します。
この「コントロール良好」な状態を維持することが、将来の呼吸機能の低下を防ぐことにもつながります。
喘息の重症度を正しく評価する
適切な治療法を選択するためには、まず現在の喘息の状態、つまり「重症度」を正しく評価することが重要です。
重症度は、治療を開始する前と治療中の状態によって評価の仕方が異なります。
治療前の重症度分類
まだ本格的な治療を始めていない段階では、過去1ヶ月程度の症状の頻度や強さ、そして呼吸機能検査(スパイロメトリー)の結果などを基に、重症度を判断します。この分類によって、最初にどのレベルの治療から始めるかを決定します。
治療開始前の重症度分類の目安
| 重症度 | 症状の頻度(目安) |
|---|---|
| 軽症間欠型 | 週1回未満、夜間症状は月2回未満 |
| 軽症持続型 | 週1回以上だが、毎日ではない |
| 中等症持続型 | 毎日症状がある |
| 重症持続型 | 連日、日常生活が制限される症状がある |
症状と呼吸機能による判断基準
重症度の判断には問診による症状の確認が最も重要です。
「週に何回咳が出ますか」「夜中に息苦しくて目が覚めますか」「発作止めの薬を何回使いましたか」といった質問から、喘息のコントロール状態を評価します。
これに加えて、呼吸機能検査で気道の狭さの客観的な指標(1秒量など)を測定し、総合的に判断します。
治療ステップによる現在の重症度の評価
すでに治療を受けている場合は、「良好なコントロールを維持するために、どのくらいの強さの治療が必要か」という観点から重症度を評価します。
治療は強さに応じて「治療ステップ」が1から4まで設定されており、例えばステップ3の治療でコントロールが良好であれば「中等症」、ステップ4の治療でも症状が残るなら「重症」と判断します。
【重症度別】気管支喘息の基本的な治療法
喘息治療は現在の重症度に応じて段階的に行います。治療の基本となるのは、気道の炎症を抑える「吸入ステロイド薬」です。
症状や重症度に合わせて、他の薬剤を組み合わせる「ステップワイズ・アプローチ」がとられます。
軽症(治療ステップ1)の治療
症状の頻度が少ない軽症の喘息(軽症間欠型)では以前は発作時のみの治療も選択肢でした。
しかし現在は炎症を抑える観点から、症状がある時だけ吸入ステロイド薬と気管支拡張薬の配合剤を吸入する方法が推奨されています。
中等症(治療ステップ2-3)の治療
症状が比較的頻繁に起こる段階では、低用量〜中用量の吸入ステロイド薬を毎日定期的に使用することが基本となります。
これだけでコントロールが不十分な場合は長時間作用性β2刺激薬(LABA)やロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)などを追加します。
多くの場合、吸入ステロイド薬とLABAが一緒になった配合剤を使用します。
治療ステップに応じた薬剤の追加(基本例)
| 治療ステップ | 基本的な治療内容 |
|---|---|
| ステップ2 | 低用量吸入ステロイド薬(ICS) |
| ステップ3 | 低~中用量ICS + 長時間作用性β2刺激薬(LABA)など |
| ステップ4 | 中~高用量ICS + LABA + その他の長期管理薬 |
重症(治療ステップ4)の治療
高用量の吸入ステロイド薬と複数の長期管理薬を組み合わせてもコントロールが難しい重症喘息では、長時間作用性抗コリン薬(LAMA)の追加や、後述する生物学的製剤の使用を検討します。
専門的な医療機関での管理が必要になることが多いです。
喘息治療で使われる主な薬剤
喘息治療薬には様々な種類がありますが、中心となるのは吸入薬です。気道に直接薬剤を届けることで少ない量で高い効果を発揮し、全身への副作用を抑えることができます。
吸入ステロイド薬(ICS)
気道の炎症を抑える最も強力で基本的な薬です。毎日継続して使用することで発作を予防します。効果が現れるまでに数週間かかることもあります。
使用後は声がれや口内カンジダを防ぐために、必ずうがいをする必要があります。
長時間作用性β2刺激薬(LABA)
気管支を広げる作用が長時間(約12時間)持続する薬です。単独で用いることはなく、必ず吸入ステロイド薬と併用します。
吸入ステロイド薬だけではコントロールが不十分な場合に追加し、多くは配合剤として使用します。
主な吸入薬のデバイスの種類
| デバイス | 特徴 |
|---|---|
| pMDI(加圧式定量噴霧吸入器) | ガスで薬剤を噴霧するスプレータイプ。噴霧と吸入の同調が必要。 |
| DPI(ドライパウダー吸入器) | 粉末状の薬剤を自分の力で吸い込むタイプ。様々な形状がある。 |
| SMI(ソフトミスト吸入器) | ゆっくりと噴霧される霧状の薬剤を吸い込むタイプ。 |
ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)
アレルギー反応に関わる物質「ロイコトリエン」の働きを抑える飲み薬です。気道の炎症を抑え、気管支が収縮するのを防ぎます。
特に鼻のアレルギー(アレルギー性鼻炎)を合併している場合に効果が期待できます。
生物学的製剤
従来の治療ではコントロールが難しい、特定のタイプの重症喘息に対して使用する注射薬です。喘息の炎症に関わる特定の物質(サイトカインなど)の働きをピンポイントで抑えます。
どの製剤が適しているかは、血液検査などで炎症のタイプを調べて判断します。
自己管理(セルフマネジメント)の重要性
喘息治療を成功させるには、医師の治療と並行して患者様自身が自分の状態を把握し、管理していく「自己管理」が非常に重要です。
ピークフローメーターの活用
ピークフローメーターは、自宅で簡便に呼吸機能(息を思い切り吐き出す速さ)を測定できる器具です。
毎日同じ時間帯に測定して記録することで、自覚症状が現れる前の気道の状態変化を客観的に捉えることができます。
発作の予兆を早期に察知し、対応するのに役立ちます。
ピークフロー値によるゾーン管理
| ゾーン | ピークフロー値(自己最良値に対する割合) | 状態 |
|---|---|---|
| グリーンゾーン | 80%以上 | コントロール良好 |
| イエローゾーン | 60~80%未満 | 注意が必要(治療強化を検討) |
| レッドゾーン | 60%未満 | 危険な状態(発作治療、速やかな受診) |
喘息日記をつける
日々の症状、発作治療薬の使用回数、ピークフロー値などを記録する「喘息日記」は、自分の喘息の状態を把握し、医師に正確に伝えるための重要なツールです。
どのような時に症状が悪化するのかを把握するのにも役立ちます。
- その日の症状(咳、喘鳴、息苦しさ)の有無
- ピークフロー値
- 発作治療薬の使用回数
- 発作のきっかけになったと思われること
アレルゲンの回避と環境整備
ダニやハウスダストがアレルゲンとなっている場合は、こまめな掃除や寝具の管理が重要です。空気清浄機の使用や、ペットを飼っている場合は寝室を分けるなどの工夫も発作予防につながります。
自分のアレルゲンを知り、それを生活環境からできるだけ遠ざける努力が必要です。
喘息治療に関するよくある質問
ここでは、喘息の治療に関して患者様からよくいただく質問についてお答えします。
- Q薬はいつまで続ける必要がありますか?
- A
気管支喘息は気道の慢性的な炎症が本態の病気です。症状がなくなった後も気道の炎症は残っていることが多いため、自己判断で薬をやめると再発する可能性が高いです。
医師が気道の状態を評価しながら、薬の量を少しずつ減らしていくことはありますが、長期的な管理が必要な病気だと理解することが大切です。
- Q吸入薬の使い方が難しいのですが
- A
吸入薬は正しく使えて初めて十分な効果を発揮します。もし使い方に不安がある場合は、遠慮なく医師や薬剤師に相談してください。
薬局や病院では吸入指導用の器具を使って、実際に吸い方を確認しながら丁寧に説明します。動画などで使い方を解説している製薬会社のウェブサイトも参考になります。
- Q風邪をひくと喘息が悪化しますか?
- A
はい、風邪などのウイルス感染は喘息の増悪(悪化)の最も多い原因です。ウイルスによって気道の炎症が悪化し、発作が起きやすくなります。
普段から手洗いやうがいを励行し、感染予防に努めることが重要です。また、インフルエンザワクチンは毎年接種することが推奨されます。
以上
参考にした論文
NAKAMURA, Yoichi, et al. Japanese guidelines for adult asthma 2020. Allergology International, 2020, 69.4: 519-548.
ARAKAWA, Hirokazu, et al. Japanese guidelines for childhood asthma 2020. Allergology International, 2020, 69.3: 314-330.
NISHIMUTA, Toshiyuki, et al. Japanese guideline for childhood asthma. Allergology International, 2011, 60.2: 147-169.
ADACHI, Mitsuru, et al. Asthma control and quality of life in a real-life setting: a cross-sectional study of adult asthma patients in Japan (ACQUIRE-2). Journal of Asthma, 2019, 56.9: 1016-1025.
INOUE, Hiromasa, et al. Prevalence and characteristics of asthma–COPD overlap syndrome identified by a stepwise approach. International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 2017, 1803-1810.
OHTA, Ken, et al. Japanese guideline for adult asthma. Allergology international, 2011, 60.2: 115-145.
NIIMI, Akio, et al. Executive summary: Japanese guidelines for adult asthma (JGL) 2021. Allergology International, 2023, 72.2: 207-226.
MAKINO, S., et al. Survey of recognition and utilization of guidelines for the diagnosis and management of bronchial asthma in Japan. Allergy, 2000, 55.2: 135-140.
HAMASAKI, Yuhei, et al. Japanese guideline for childhood asthma 2014. Allergology International, 2014, 63.3: 335-356.
MASAKI, Katsunori, et al. Characteristics of severe asthma with fungal sensitization. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 2017, 119.3: 253-257.
SUZUKI, Takeo, et al. Clinical characteristics, treatment patterns, disease burden, and persistence/adherence in patients with asthma initiating inhaled triple therapy: real-world evidence from Japan. Current Medical Research and Opinion, 2020, 36.6: 1049-1057.