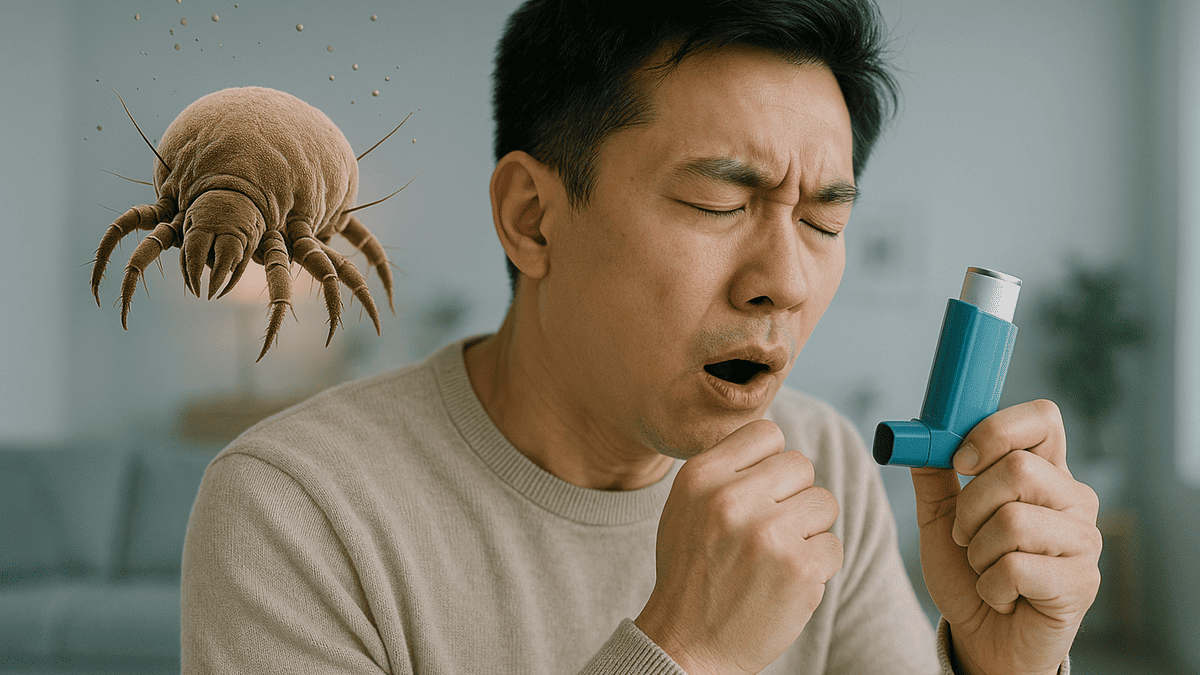特定の季節や場所で咳が止まらなくなる、ホコリっぽい部屋に入ると息が苦しくなる。そんな経験はありませんか。
その症状、もしかしたら「アレルギー性喘息」かもしれません。アレルギー性喘息は特定のアレルギー原因物質(アレルゲン)によって気道に炎症が起き、咳や息苦しさなどの発作を繰り返す病気です。
この記事ではアレルギー性喘息の基本的な知識から特徴的な症状、主な原因、そして呼吸器内科で行われる専門的な治療法まで分かりやすく解説します。
ご自身の症状を正しく理解し、適切な対策を講じるためにお役立てください。
アレルギー性喘息とは何か
喘息にはいくつかのタイプがありますが、日本の成人喘息患者さんの約6割を占めるといわれるのが「アレルギー性喘息」です。
アトピー型喘息とも呼ばれ、アレルギー反応が深く関わっています。
喘息とアレルギーの深い関係
アレルギー性喘息は私たちの体を守る免疫システムが、本来は無害であるはずの物質(アレルゲン)に対して過剰に反応してしまうことで発症します。
アレルゲンが体内に侵入するとIgE抗体という特殊なたんぱく質が作られ、このIgE抗体が気道の細胞と結びつくことで炎症を引き起こす化学物質が放出されます。
この反応が気道を狭くし、咳や喘鳴といった喘息症状を誘発するのです。
非アレルギー性喘息との違い
喘息の中にはアレルギーが関与しない「非アレルギー性喘息」もあります。こちらはウイルス感染やタバコの煙、ストレス、薬剤などが引き金となって発症します。
アレルギー性喘息が小児期や若年層に多いのに対し、非アレルギー性喘息は中高年以降に発症することが多い傾向にあります。
アレルギー性喘息と非アレルギー性喘息の比較
| 項目 | アレルギー性喘息 | 非アレルギー性喘息 |
|---|---|---|
| 主な発症原因 | アレルゲン(ダニ、花粉など) | ウイルス感染、薬剤、ストレスなど |
| 好発年齢 | 小児期、若年層 | 中高年以降 |
| 合併症 | アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎 | 副鼻腔炎などを合併することがある |
気道の慢性的な炎症が根本原因
アレルギー性喘息の根本には気道の「慢性的な炎症」があります。症状がない時でも気道の内側ではアレルギーによる炎症がくすぶり続けています。
このため、気道が非常に敏感な状態になっており、わずかな刺激でも容易に発作が起きてしまうのです。
治療の目標は、この慢性的な炎症をコントロールすることにあります。
アレルギー性喘息の特徴的な症状
アレルギー性喘息の症状は発作的に現れることが特徴です。症状の現れ方には個人差がありますが、代表的なものを紹介します。
繰り返す咳と痰
しつこい咳は喘息の最も一般的な症状の一つです。特に夜間から明け方にかけて悪化することが多く、一度出始めると止まらなくなることもあります。
気道の炎症によって分泌物が増えるため、粘り気のある痰が絡むこともあります。
喘鳴(ぜんめい)と息苦しさ
喘鳴は息を吐くときに「ゼーゼー」「ヒューヒュー」と音がする状態です。これは炎症によって気道が狭くなり、空気が通りにくくなるために生じます。
喘鳴と共に胸が締め付けられるような圧迫感や、呼吸が苦しいといった症状が現れます。これらが典型的な喘息発作です。
喘息発作の主なサイン
| 症状 | 特徴 |
|---|---|
| 喘鳴 | 呼吸時にゼーゼー、ヒューヒューという音がする |
| 咳 | 発作的に激しく咳き込む、夜間に悪化する |
| 呼吸困難 | 息が吐き出せない、息苦しい、胸が苦しい |
夜間や早朝に悪化する傾向
喘息の症状は1日の中でも変動します。自律神経の働きやホルモンの影響で、気道は夜間から早朝にかけて最も狭くなりやすい状態になります。
そのため、就寝中や起床時に咳や発作で目が覚めることは、喘息がうまくコントロールできていない重要なサインです。
鼻炎や結膜炎の合併
アレルギー性喘息の患者さんはアレルギー性鼻炎(くしゃみ、鼻水、鼻づまり)やアレルギー性結膜炎(目のかゆみ、充血)を合併していることが非常に多いです。
これらのアレルギー疾患は、「ワンエアウェイ・ワンディジーズ」という考え方でつながっており、鼻と気管支を同時に治療することが重要になります。
主な原因となるアレルゲン
アレルギー性喘息を引き起こすアレルゲンは身の回りの様々な場所に潜んでいます。原因を特定し、対策を講じることが症状の改善につながります。
室内のアレルゲン(ハウスダスト・ダニ)
日本で最も多いアレルゲンは、ダニの死骸やフンを含むハウスダストです。
これらは非常に小さく軽いため空気中に舞いやすく、吸い込みやすいという特徴があります。特に布団やカーペット、布製のソファなどに多く潜んでいます。
屋外のアレルゲン(花粉)
スギやヒノキ、ブタクサ、イネ科植物などの花粉もアレルギー性喘息の主要な原因です。
花粉症の症状と共に咳や喘息発作が悪化する場合は、花粉がアレルゲンである可能性が高いです。
主な吸入性アレルゲンとその対策
| アレルゲン | 主な発生源 | 対策のポイント |
|---|---|---|
| ダニ | 寝具、カーペット、ソファ | こまめな掃除、洗濯、防ダニ製品の活用 |
| 花粉 | スギ、ヒノキ、ブタクサなど | 飛散時期のマスク着用、帰宅時の除去 |
| ペット | 犬や猫の毛、フケ、唾液 | こまめなシャンプー、寝室に入れない |
ペットの毛やフケ
犬や猫、ハムスターなどのペットの毛やフケ、唾液、尿などもアレルゲンとなり得ます。
ペットを飼い始めてから咳が出るようになった場合は、ペットアレルギーを疑う必要があります。
カビ(真菌)
浴室やキッチン、エアコンの内部など、湿気が多くジメジメした場所にはカビが発生しやすくなります。
カビの胞子を吸い込むことでアレルギー反応が引き起こされ、夏場に症状が悪化する「夏型過敏性肺炎」の原因になることもあります。
アレルギー性喘息の悪化要因
アレルゲン以外にも喘息の症状を悪化させる様々な要因が存在します。これらを避けることも、安定した状態を保つためには重要です。
タバコの煙(受動喫煙を含む)
タバコの煙は気道にとって非常に強い刺激物です。
喫煙者本人だけでなく、家族など周りの人が吸うタバコの煙(受動喫煙)を吸い込むことでも気道の炎症が悪化し、発作の引き金となります。
ウイルス感染症(風邪など)
風邪やインフルエンザなどのウイルスに感染すると気道の粘膜が傷つき、炎症がひどくなります。このことにより喘息の症状が急激に悪化し、強い発作につながることがあります。
日頃からの感染予防対策が大切です。
気温の変化や気圧の変動
急に冷たい空気を吸い込んだり、季節の変わり目や台風の接近などで気温や気圧が大きく変動したりすると、気道が刺激されて発作が起きやすくなります。
マスクの着用などで、急激な温度変化から気道を保護する工夫が有効です。
- タバコの煙
- ウイルス感染
- 天候の変化
- 過労やストレス
ストレスや過労
精神的なストレスや身体的な疲労は自律神経のバランスを乱し、免疫機能を低下させます。その結果、気道が過敏になり、喘息の症状が悪化することがあります。
十分な休息と睡眠をとり、リラックスできる時間を持つことが重要です。
呼吸器内科で行う診断と検査
アレルギー性喘息の診断は症状の詳しい聞き取りと、いくつかの客観的な検査を組み合わせて行います。
詳細な問診と聴診
どのような症状がいつから、どんな時に起こるのかを詳しくお伺いします。
アレルギー性鼻炎やアトピー性皮膚炎の有無、家族のアレルギー歴なども診断の重要な手がかりになります。
聴診器で胸の音を聞き、喘鳴の有無を確認します。
アレルゲンを特定する血液検査
血液検査(特異的IgE抗体検査)によって、どのアレルゲンに対してアレルギー反応を持っているかを調べることができます。
原因アレルゲンを特定することで、具体的な対策を立てることが可能になります。
喘息診断のための主要な検査
| 検査名 | 何がわかるか |
|---|---|
| 呼吸機能検査 | 気道がどのくらい狭くなっているか |
| 呼気NO検査 | アレルギーによる気道の炎症の程度 |
| 血液検査 | 原因となっているアレルゲンの種類 |
呼吸機能検査(スパイロメトリー)
息を最大限吸い込み、勢いよく吐き出すことで肺活量や息の通りやすさ(気道の狭さ)を評価する検査です。
喘息の診断だけでなく、治療効果の判定にも用います。
呼気NO(一酸化窒素)検査
吐いた息の中に含まれる一酸化窒素(NO)の濃度を測定する検査です。アレルギーによる気道の炎症が強いと、NOの濃度が高くなります。
この検査は喘息の診断や、治療薬が適切かどうかの判断に非常に役立ちます。
アレルギー性喘息の治療法
アレルギー性喘息の治療目標は気道の炎症を抑えて発作を予防し、健康な人と変わらない日常生活を送れるようにすることです。
治療の二本柱 長期管理と発作治療
喘息治療は2種類の薬を使い分けるのが基本です。一つは症状がない時も毎日使用して発作を予防する「長期管理薬(コントローラー)」。
もう一つは、発作が起きてしまった時に症状を速やかに和らげるための「発作治療薬(レリーバー)」です。
長期管理薬(吸入ステロイド薬など)
治療の中心となるのが、気道の炎症を根本から抑える吸入ステロイド薬です。毎日規則正しく使用することで気道の過敏性を改善し、発作の起こりにくい状態を維持します。
その他、気管支を広げる効果が長く続く長時間作用性β2刺激薬などを配合した吸入薬も広く使われます。
治療薬の役割分担
| 種類 | 役割 | 主な薬剤 |
|---|---|---|
| 長期管理薬 | 発作の予防(毎日使用) | 吸入ステロイド薬 |
| 発作治療薬 | 発作時の症状緩和(頓用) | 短時間作用性β2刺激薬 |
発作治療薬(短時間作用性気管支拡張薬)
発作が起きて苦しくなった時に、一時的に気管支を素早く広げて呼吸を楽にする薬です。
あくまで緊急避難的な薬であり、これを頻繁に使う状態は喘息のコントロールが不良であるサインです。長期管理薬による治療を見直す必要があります。
アレルゲン免疫療法という選択肢
アレルギーの原因物質(アレルゲン)を少量から体に投与し、徐々に慣らしていくことで、アレルギー反応自体を弱める治療法です。
根本的な体質改善が期待でき、ダニやスギ花粉が原因のアレルギー性喘息に対して保険適用があります。
日常生活でできる対策とセルフケア
薬物治療と合わせて、日々のセルフケアを実践することが症状の安定につながります。
アレルゲンの除去と回避
原因となるアレルゲンを身の回りからできるだけ減らすことが最も基本的な対策です。
特に、一日の多くの時間を過ごす寝室の環境整備は重要です。
アレルゲン除去のための掃除のポイント
| 場所 | ポイント |
|---|---|
| 寝具 | 週に1回以上、シーツなどを洗濯または掃除機をかける |
| 床 | 掃除機はゆっくりかけ、拭き掃除も併用する |
| 室内全体 | 定期的な換気、空気清浄機の活用 |
正しい吸入薬の使用方法
吸入薬は正しく使えて初めて効果を発揮します。薬が確実に気管支まで届くよう、医師や薬剤師から指導された方法をきちんと守ることが大切です。
うまく吸入できない場合は、遠慮なく相談してください。
喘息日記(ピークフロー測定)の活用
ピークフローメーターという簡単な器具を使って、息を思い切り吐き出した時の速さ(ピークフロー値)を毎日記録することで、自分の気道の状態を客観的に把握できます。
症状が出ていなくても数値が低下していれば、発作が近づいているサインかもしれません。
体調の変化と共に記録する喘息日記は自己管理と治療方針の決定に役立ちます。
よくある質問
最後に、アレルギー性喘息に関して患者さんからよくいただく質問にお答えします。
- Qアレルギー性喘息は大人になってからでも発症しますか?
- A
はい、発症します。
小児期に発症することが多いですが、就職や結婚、引っ越しなどの生活環境の変化をきっかけに、成人してから初めて発症する方も少なくありません。
これまでアレルギーとは無縁だった方でも、長引く咳などの症状があれば注意が必要です。
- Q治ることはありますか?
- A
残念ながら、現在の医療ではアレルギー性喘息を完全に「完治」させることは難しいのが現状です。
しかし、適切な治療によって気道の炎症をコントロールし、症状が全くない「寛解」という状態を維持することは十分に可能です。
治療の目標は、喘息がない人と変わらない生活を送ることです。
- Q運動はしても良いですか?
- A
適切にコントロールされていれば、運動を制限する必要は全くありません。むしろ、体力向上や心肺機能の維持のために推奨されます。
ただし、運動が発作の引き金になる「運動誘発喘息」の場合は、運動前に発作予防の薬を使うなどの対策が必要です。運動の種類や強度について主治医とよく相談しましょう。
- Q妊娠・出産への影響はありますか?
- A
喘息のコントロールが良好であれば、妊娠・出産への影響はほとんどありません。むしろ、自己判断で治療薬をやめてしまう方が母子共に危険な状態になるリスクを高めます。
妊娠中も安全に使える薬はたくさんありますので、妊娠を希望する場合や妊娠がわかった場合は必ず主治医に相談してください。
以上
参考にした論文
KOMAI, Masato, et al. Role of Th2 responses in the development of allergen‐induced airway remodelling in a murine model of allergic asthma. British journal of pharmacology, 2003, 138.5: 912-920.
SAKAI, Hiroyasu, et al. Mechanisms underlying the pathogenesis of hyper-contractility of bronchial smooth muscle in allergic asthma. Journal of Smooth Muscle Research, 2017, 53: 37-47.
MIYASAKA, Tomomitsu, et al. The interplay between neuroendocrine activity and psychological stress-induced exacerbation of allergic asthma. Allergology International, 2018, 67.1: 32-42.
NAKAGOME, Kazuyuki; NAGATA, Makoto. Role of allergen immunotherapy in asthma treatment and asthma development. Allergies, 2020, 1.1: 33-45.
HIROSE, Koichi, et al. Allergic airway inflammation: key players beyond the Th2 cell pathway. Immunological reviews, 2017, 278.1: 145-161.
SHIBAMORI, Masafumi, et al. Intranasal mite allergen induces allergic asthma-like responses in NC/Nga mice. Life sciences, 2006, 78.9: 987-994.
IIJIMA, Koji, et al. IL-33 and thymic stromal lymphopoietin mediate immune pathology in response to chronic airborne allergen exposure. The Journal of Immunology, 2014, 193.4: 1549-1559.
YAMAMOTO, Hiroshi, et al. Adrenomedullin insufficiency increases allergen-induced airway hyperresponsiveness in mice. Journal of Applied Physiology, 2007, 102.6: 2361-2368.
TATEISHI, Kinji, et al. Comparison between allergen-induced and exercise-induced asthma with respect to the late asthmatic response, airway responsiveness, and Creola bodies in sputum. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 1996, 77.3: 229-237.
OHTA, Ken, et al. Antibody therapy for the management of severe asthma with eosinophilic inflammation. International Immunology, 2017, 29.7: 337-343.