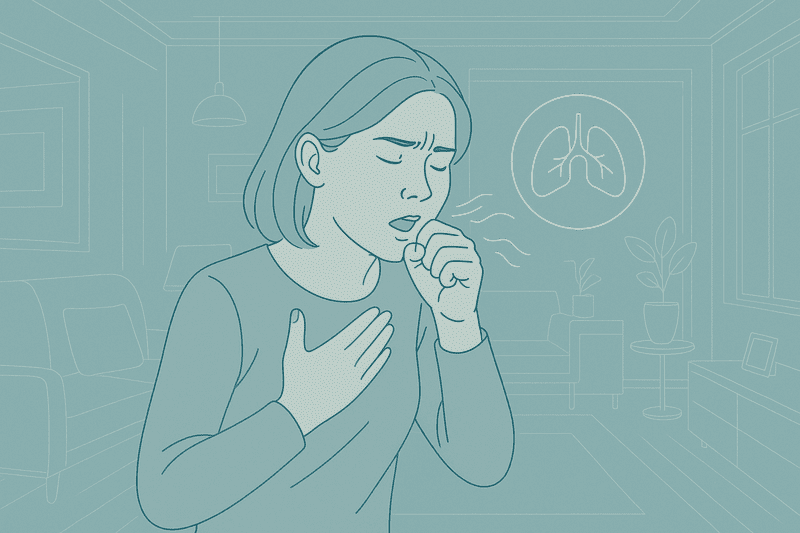大になってから「ゼロゼロ」「ゼーゼー」といった、痰が絡むような息苦しい咳が続くことはありませんか。風邪が長引いているだけだと思っていても、実は気管支喘息(ぜんそく)のサインかもしれません。
大人の喘息は、子どもの頃に経験がなくても発症することがあります。特に夜間や早朝に症状が悪化しやすいのが特徴です。
この記事では、大人の「ゼロゼロする咳」の原因、それがなぜ喘息と関連するのか、そして呼吸器内科で行う適切な検査や治療法について詳しく解説します。
咳に悩む大人は、ぜひ参考にしてください。
大人の「ゼロゼロする咳」とはどのような症状か
「ゼロゼロ」「ゼーゼー」鳴る音の正体
咳をした時や息を吐いた時に聞こえる「ゼロゼロ」や「ゼーゼー」という音は、医学的には「喘鳴(ぜんめい)」と呼ばれます。
これは、喉や気管支といった空気の通り道(気道)が何らかの原因で狭くなり、そこを空気が無理やり通過する際に生じる異常な呼吸音です。
健康な状態では、呼吸の音は静かですが、気道が狭くなると笛を吹くように音が発生します。このゼロゼロした咳は、気道に炎症や痰の蓄積があることを示唆する重要なサインです。
咳以外の主な随伴症状
ゼロゼロする咳が出る時、多くの場合、咳以外の症状も伴います。最も一般的なのは「息苦しさ」です。気道が狭くなっているため、十分な空気を吸い込んだり吐き出したりすることが難しくなります。
また、胸が締め付けられるような「胸部圧迫感」を感じることもあります。これらの症状は、気管支喘息の典型的な兆候であり、日常生活に支障をきたす原因となります。
ゼロゼロする咳に伴いやすい症状
| 症状 | 特徴 | 考えられる状態 |
|---|---|---|
| 息苦しさ(呼吸困難) | 特に息を吐く時が苦しい | 気道が狭くなっている |
| 胸の圧迫感 | 胸が締め付けられる感じ | 気管支の筋肉が緊張している |
| 痰(たん) | 粘り気が強く、切れにくい | 気道の炎症による分泌物 |
症状が出やすい時間帯や状況
ゼロゼロした咳や喘鳴は、一日中同じように続くとは限りません。特定の時間帯や状況で悪化しやすい傾向があります。
特に、夜間から早朝にかけては、気道が最も敏感になりやすく、症状が強まることが多いです。また、以下のような状況も症状を引き起こすきっかけとなります。
- 運動や階段の上り下りをした時
- タバコの煙や強い匂いを吸い込んだ時
- 季節の変わり目や、急に冷たい空気を吸った時
- 風邪をひいた時
なぜ大人の咳がゼロゼロ鳴るのか
気道(空気の通り道)の炎症
大人の咳がゼロゼロ鳴る根本的な原因は、気道の「慢性的な炎症」にあります。気管支喘息の場合、アレルギー反応やその他の刺激によって、気道の粘膜が常に腫れた状態になります。
この炎症が続くと、気道は非常に敏感になり、わずかな刺激にも過剰に反応してしまいます。炎症が起きている場所では、血液の成分が集まり、粘膜がむくみ、空気の通り道が物理的に狭くなります。
気道が狭くなる仕組み
気道の炎症に加えて、気道の周りを取り巻く「平滑筋(へいかつきん)」という筋肉が収縮することも、気道を狭くする大きな要因です。
敏感になった気道が刺激を受けると、この平滑筋がけいれんするように強く縮まります。この収縮により、空気の通り道はさらに狭くなり、ゼロゼロ、ゼーゼーという喘鳴や息苦しさを引き起こします。
発作時には、この筋肉の収縮を和らげる治療が必要です。
痰(たん)の増加と排出困難
炎症が起きている気道では、粘液(痰)の分泌が過剰になります。これは、気道が刺激物や異物を外に出そうとする防御反応の一つです。
しかし、喘息患者の痰は粘り気が非常に強く、健康な時のように簡単には排出できません。この粘り気のある痰が気道に溜まると、空気の通り道をさらに塞いでしまいます。
ゼロゼロする咳は、この痰を何とか外に出そうとして起こる反応でもありますが、痰が多すぎてうまく排出できない状態を示しています。
ゼロゼロする咳を引き起こす代表的な病気
気管支喘息(ぜんそく)
大人のゼロゼロする咳の原因として最も代表的なのが「気管支喘息」です。これは、気道が慢性的な炎症を起こし、様々な刺激に対して過敏に反応する状態を指します。
アレルゲン(ダニ、ハウスダスト、ペットなど)や、ウイルス感染、気候の変化、ストレスなどが引き金となり、気道が狭くなる発作を繰り返します。
夜間や早朝に症状が出やすいのが典型的な特徴です。大人の場合、子どもの頃に喘息がなくても、大人になってから初めて発症(成人発症喘息)することも珍しくありません。
気管支喘息の主な特徴
| 症状 | 発症のきっかけ | 検査所見 |
|---|---|---|
| 喘鳴(ゼロゼロ、ゼーゼー) | アレルゲン、風邪、運動 | 呼吸機能検査で気道が狭い |
| 息苦しさ、咳 | 夜間・早朝、寒暖差 | 呼気NO検査で炎症の数値が高い |
| 粘り気のある痰 | ストレス、過労 | 聴診で気道の狭窄音を確認 |
咳喘息(せきぜんそく)との違い
「咳喘息」も、咳が長引く原因の一つです。気管支喘息と同じように気道の炎症が根底にありますが、大きな違いは「喘鳴(ゼロゼロ、ゼーゼー)」や「息苦しさ」がほとんどなく、乾いた咳だけが長期間続く点です。
咳喘息は、気管支喘息の前段階とも考えられており、治療せずに放置すると、約3割が典型的な気管支喘息に移行すると言われています。ゼロゼロした咳がないからといって安心はできません。
気管支喘息と咳喘息の比較
| 項目 | 気管支喘息 | 咳喘息 |
|---|---|---|
| 主な症状 | 咳、喘鳴、息苦しさ | 咳のみ(乾いた咳が中心) |
| 喘鳴(ゼロゼロ) | あり | なし |
| 呼吸機能検査 | 異常が出やすい | 正常なことが多い |
COPD(慢性閉塞性肺疾患)
COPD(慢性閉塞性肺疾患)も、咳や痰、息切れを引き起こす病気です。主な原因は長期間の喫煙であり、「肺気腫」や「慢性気管支炎」と呼ばれる状態を含みます。
喘息と同様に気道が狭くなりますが、COPDの場合は炎症が肺の奥深く(肺胞)にまで及び、肺の組織が壊れてしまうことが特徴です。進行すると、常に息切れを感じるようになります。
ゼロゼロした咳が出るという点で喘息と似ていますが、主な原因や進行の仕方が異なります。
その他の呼吸器感染症(気管支炎など)
風邪やインフルエンザなどのウイルス感染、あるいは細菌感染によって引き起こされる「急性気管支炎」でも、気道に炎症が起こり、ゼロゼロした咳や痰が出ることがあります。
多くの場合、感染症が治まれば症状も改善しますが、炎症が長引くこともあります。また、百日咳など特定の感染症では、激しい咳が数ヶ月続くこともあり、喘息との見極めが重要です。
気管支喘息が大人になってから発症する要因
アレルギー素因(アトピー型)
大人の喘息のうち、半数以上はアレルギーが関与する「アトピー型」と考えられています。
子どもの喘息ほどではありませんが、大人でもダニ、ハウスダスト、ペットのフケ、カビ、花粉といった特定のアレルゲン(アレルギーの原因物質)に反応して発症することがあります。
これらのアレルゲンを吸い込むことで気道にアレルギー性の炎症が起こり、喘息症状を引き起こします。
- ハウスダスト、ダニの死骸やフン
- 犬や猫などのペットのフケ、毛
- ゴキブリなどの昆虫
- アスペルギルスなどのカビ
アレルギー以外の要因(非アトピー型)
一方、特定のアレルゲンがはっきりしない「非アトピー型」の喘息も大人には多く見られます。このタイプは、アレルギー以外の様々な要因が複雑に関与して発症します。
大人の喘息の主な誘因
| 分類 | 具体例 | 対策の方向性 |
|---|---|---|
| 感染症 | 風邪、インフルエンザ | 感染予防(手洗い、うがい) |
| 環境刺激 | タバコの煙(受動喫煙含む) | 禁煙、分煙の徹底 |
| 薬剤 | 解熱鎮痛薬(アスピリンなど) | 医師への申告 |
悪化させやすい生活習慣
喘息の発症や悪化には、日常生活の習慣も深く関わっています。最も大きな危険因子は「喫煙」です。タバコの煙は気道の炎症を直接悪化させ、治療薬(特に吸入ステロイド薬)の効果を著しく低下させます。
受動喫煙も同様に有害です。また、「過労」や「精神的ストレス」も、自律神経や免疫のバランスを乱し、喘息を悪化させる要因となります。不規則な生活や睡眠不足も避けるべきです。
ゼロゼロする咳を感じた時の受診の目安
すぐに病院へ行くべき症状
ゼロゼロする咳が出ていても、通常の生活が送れる場合が多いですが、中には緊急の対応が必要な「喘息の重積発作」の場合があります。
気道が極端に狭くなり、命に関わる危険性もあるため、以下の症状が見られる場合は、夜間や休日であっても直ちに救急外来を受診するか、救急車を呼ぶことを検討してください。
緊急受診が必要なサイン
| サイン | 状態 | 対処法 |
|---|---|---|
| 会話が途切れ途切れになる | 呼吸が苦しくて話せない | 救急要請を検討 |
| 横になれず座っていないと苦しい | (起坐呼吸) | 楽な姿勢で待機 |
| 唇や爪が青白い(チアノーゼ) | 酸素が不足している | 直ちに救急要請 |
呼吸器内科を受診するタイミング
上記のような激しい発作でなくても、ゼロゼロした咳が続く場合は呼吸器内科の受診が必要です。特に「市販の風邪薬や咳止めを飲んでも、咳が2週間以上続く」場合は、単なる風邪ではない可能性が高いです。
また、「特定の状況(夜間、運動後、季節の変わり目など)で決まって咳や息苦しさが出る」場合も、喘息を疑うサインです。
早期に診断を受け、適切な治療を開始することが、症状の悪化や気道の慢性的なダメージを防ぐために重要です。
受診時に医師に伝えると良い情報
正確な診断のために、医師に症状を詳しく伝えることが大切です。記憶があいまいな場合は、事前にメモを準備しておくとスムーズです。特に以下の情報は診断の手がかりとなります。
- いつから症状が始まったか
- どんな時に症状が出やすいか(時間帯、状況)
- ゼロゼロ、ゼーゼーという音がするか
- 息苦しさを伴うか
- アレルギー(花粉症、アトピーなど)の有無
- 喫煙歴
呼吸器内科で行う検査と診断
問診と聴診の重要性
診断の第一歩は、詳しい「問診」です。医師が、前述のような症状の経緯や生活環境、アレルギー歴などを丁寧に聞き取ります。
この問診が、喘息かどうか、あるいは他の病気の可能性を探る上で最も重要な情報源となります。続いて「聴診」を行います。聴診器を胸や背中に当て、呼吸音を確認します。
気道が狭くなっていると、特徴的な「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という喘鳴(ぜんめい)が聞こえることがあります。
症状が出ていない時には異常がなくても、深く息を吐き出してもらうことで喘鳴が確認できる場合もあります。
呼吸機能検査(スパイロメトリー)
気道がどの程度狭くなっているかを客観的に調べる検査が「呼吸機能検査(スパイロメトリー)」です。機械に向かって、できるだけ大きく息を吸い込み、その後、勢いよく最後まで息を吐き出します。
この検査により、肺活量や、息を勢いよく吐き出す量(1秒量)を測定します。喘息患者では、気道が狭いために1秒量が低下することが多いです。
また、気管支拡張薬を吸入した後に再度検査を行い、1秒量が改善すれば、喘息の可能性がより高くなります。
呼吸機能検査でわかること
| 指標 | 意味 | 喘息での傾向 |
|---|---|---|
| %肺活量 (%VC) | 肺の大きさ(吸える空気の量) | 正常なことが多い |
| 1秒率 (FEV1%) | 吸った空気を最初の1秒間で何%吐き出せるか | 低下する(気道が狭い) |
呼気NO(一酸化窒素)検査
近年、喘息の診断や治療効果の判定に広く用いられているのが「呼気NO(一酸化窒素)検査」です。喘息によって気道にアレルギー性の炎症が起きると、気道内で一酸化窒素(NO)が多く産生されます。
この検査では、マウスピースをくわえて一定の強さで息を吐き出し、吐いた息(呼気)に含まれるNOの濃度を測定します。数値が高いほど、気道の炎症が強いことを示します。
この検査は患者の負担が少なく、簡便に気道の炎症状態を評価できます。
胸部X線(レントゲン)検査
胸部X線(レントゲン)検査は、喘息そのものを直接診断するための検査ではありません。
主な目的は、ゼロゼロする咳や息苦しさを引き起こす他の病気(肺炎、肺結核、肺がん、心不全など)がないかを確認することです。
喘息の場合、レントゲン写真では異常が見られないことがほとんどですが、重症の感染症などを見逃さないために重要な検査です。
喘息と診断された場合の主な治療法
治療の基本的な考え方(発作予防と発作時治療)
気管支喘息の治療は、「発作を予防するための治療」と「発作が起きた時の治療」の2本柱で進めます。最も重要なのは、発作を予防する治療です。
これは、症状がない時でも毎日継続して行う治療で、「長期管理(コントローラー)」と呼ばれます。この治療により、気道の慢性的な炎症を抑え、発作が起きにくい状態を維持します。
一方、発作が起きてしまった時に、狭くなった気道を速やかに広げて症状を和らげるのが「発作治療(リリーバー)」です。
吸入ステロイド薬(長期管理薬)
長期管理の中心となる薬剤が「吸入ステロイド薬」です。ステロイドと聞くと副作用を心配する人もいますが、吸入薬はごく微量を直接気道に届けるため、飲み薬のような全身性の副作用はほとんどありません。
この薬には、喘息の根本原因である気道の「炎症」を強力に抑える作用があります。
ゼロゼロする咳や発作がなくなったと感じても、炎症自体は続いているため、自己判断で中断せず、毎日継続して使用することが非常に大切です。
主な長期管理薬(コントローラー)の種類
| 薬剤の種類 | 主な役割 | 使用方法 |
|---|---|---|
| 吸入ステロイド薬 (ICS) | 気道の炎症を抑える | 毎日、定期的に使用 |
| 長時間作用性β2刺激薬 (LABA) | 気道を長時間広げる | ICSとの配合剤が多い |
| ロイコトリエン受容体拮抗薬 (LTRA) | アレルギー反応を抑える(内服薬) | ICSに追加して使用 |
気管支拡張薬(発作治療薬)
発作治療薬(リリーバー)には、「短時間作用性β2刺激薬(SABA)」という即効性のある気管支拡張薬を用います。これは、発作によって急激に収縮した気道の筋肉を速やかに緩め、気道を広げて呼吸を楽にする薬です。
あくまで一時的に症状を抑えるための薬であり、気道の炎症を治す効果はありません。この薬の使用回数が多いということは、気道の炎症がコントロールできていないサインです。
リリーバーの使用が週に何度も必要な場合は、長期管理薬の見直しが必要なため、すぐに主治医に相談してください。
発作治療薬(リリーバー)の使い方
| いつ使うか | 期待する効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 発作時(苦しい時) | 数分で気道が広がり楽になる | 炎症を治す薬ではない |
| 運動前(予防) | 運動誘発喘息を防ぐ | 日常的な使用は避ける |
日常生活での自己管理(アレルゲン対策)
薬物治療と並行して、喘息の引き金となる要因を日常生活から取り除く自己管理も重要です。アトピー型の喘息であれば、アレルゲン(ダニ、ハウスダスト、ペットなど)の除去が効果的です。
こまめな掃除や寝具の管理(シーツの洗濯、布団乾燥機など)を心がけてください。
また、禁煙(受動喫煙の回避)は必須です。風邪やインフルエンザは喘息発作の大きな引き金になるため、手洗いやうがい、ワクチン接種などの感染予防も大切にします。
ゼロゼロする咳に関するよくある質問
咳止め薬を飲んでも良いか
ゼロゼロする咳が喘息によるものである場合、市販の咳止め薬(鎮咳薬)は逆効果になることがあります。喘息の咳は、気道に溜まった粘り気のある痰を排出しようとする体の反応でもあります。
咳止め薬で無理に咳を抑え込むと、痰が気道に詰まり、かえって息苦しさが悪化する危険性があります。
ゼロゼロした咳や喘鳴がある時は、咳止め薬に頼らず、気道を広げたり炎症を抑えたりする喘息の治療を優先するべきです。まずは呼吸器内科でご相談ください。
喘息は完治するのか
子どもの喘息は、成長とともに症状が出なくなる(寛解)ことも多いですが、大人の喘息(特に成人発症喘息)は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病と同様に、慢性的な病気として長く付き合っていく必要があります。
現在の医療では、喘息の体質そのものを完全になくす「完治」は難しいとされています。
しかし、吸入ステロイド薬などの長期管理薬を適切に継続することで、気道の炎症をコントロールし、健康な人と変わらない日常生活を送る「症状のコントロール(寛解)」は十分に可能です。
治療にかかる費用はどれくらいか
喘息治療は長期にわたることが多いため、費用も気になるところです。費用は、行う検査(呼吸機能検査、呼気NO検査など)や、処方される薬の種類・量によって変動します。
定期的な通院(月1回程度)と長期管理薬(吸入ステロイド薬など)の処方で、健康保険3割負担の場合、月々数千円程度が目安となることが多いです。
重症度や使用する薬剤(生物学的製剤など)によっては、さらに費用が必要となる場合もあります。
運動はしても良いか
喘息だからといって運動を諦める必要はありません。むしろ、適切にコントロールされていれば、適度な運動は体力や心肺機能の維持・向上に役立ちます。
ただし、運動によって発作が誘発される「運動誘発喘息」の場合は注意が必要です。運動前に主治医から処方された気管支拡張薬を予防的に吸入するなどの対策があります。
どのような運動が適しているか、どのような点に注意すべきか、主治医とよく相談することが大切です。