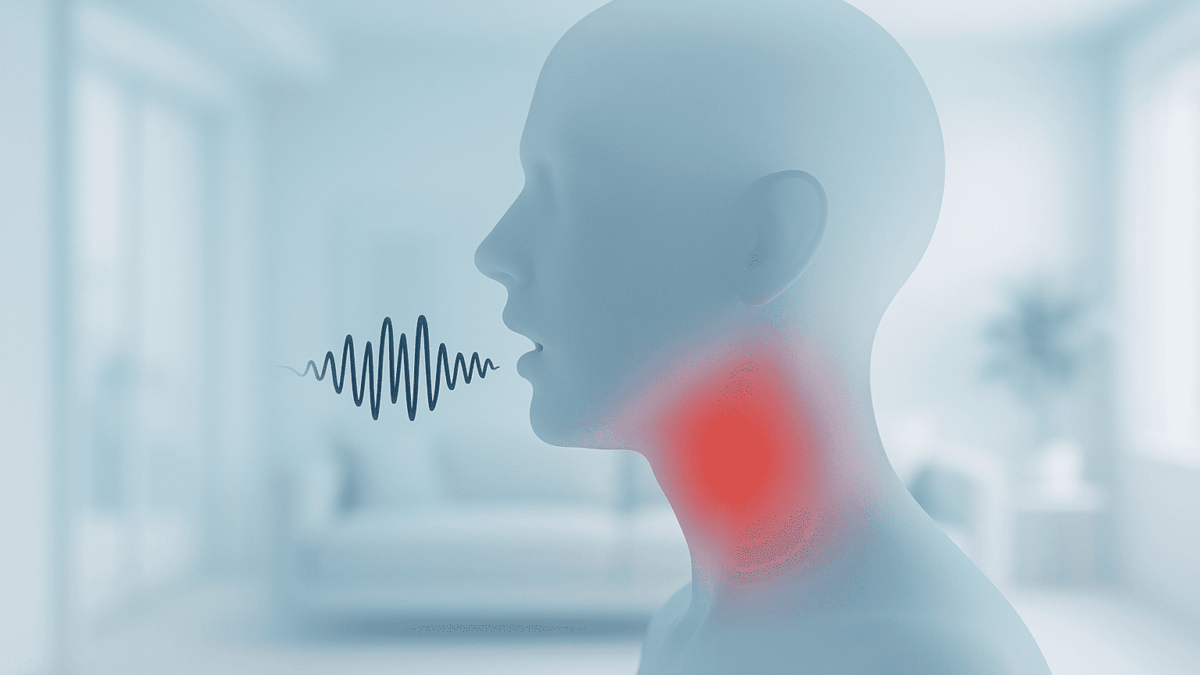「最近、声がかすれる」「声が低くなった気がする」「話しているとガラガラする音が混じる」といった声の変化は、多くの方が一度は経験するかもしれません。
一時的なものであれば心配いりませんが、症状が長引いたり、他の不調を伴ったりする場合は、何らかの病気が隠れている可能性も考えられます。
この記事では、のどのかすれ(嗄声:させい)やガラガラ声の原因、ご自身でできる対処法、そして医療機関を受診する目安や検査・治療について、詳しく解説します。
のどのかすれ(嗄声)とは何か
のどのかすれは、医学的には「嗄声(させい)」と呼ばれます。声の質が普段と異なり、かすれたり、ガラガラしたり、弱々しくなったりする状態全般を指します。
声は私たちのコミュニケーションにおいて非常に重要な役割を担っているため、声質の変化は日常生活や社会生活に影響を及ぼすことがあります。
声が作られる仕組み
私たちが声を出すためには、肺からの呼気が声帯を振動させ、その振動音が喉や口、鼻腔(咽頭・口腔・鼻腔)で共鳴し、唇や舌の動きによって言葉として形作られるという一連の働きが必要です。
声帯は、喉頭(のどぼとけの奥)にある左右一対のひだ状の組織で、発声時には閉じて振動し、呼吸時には開いています。この声帯の振動がスムーズに行われなくなると、声がかすれる原因となります。
声帯の構造と役割
| 構成要素 | 主な役割 | 特徴 |
|---|---|---|
| 声帯粘膜 | 振動して音源を作る | 非常に柔らかく、潤滑な粘液で覆われている |
| 声帯筋(甲状披裂筋) | 声帯の緊張や厚みを調節 | 声の高さや強さをコントロールする |
| 披裂軟骨 | 声帯の開閉を司る | 発声時と呼吸時で声帯の位置を調節する |
のどのかすれの主な症状
のどのかすれといっても、その現れ方は様々です。以下のような症状が代表的です。
- 声がガラガラする、雑音が混じる
- 声がかすれて聞き取りにくい
- 高い声が出しにくい、または低い声しか出ない
- 声が弱々しく、すぐに途切れてしまう
- 話しているとすぐに疲れる、のどに痛みを感じる
これらの症状は、単独で現れることもあれば、複数同時に現れることもあります。また、症状の程度も、軽いものから日常生活に支障をきたす重いものまで幅広いです。
声質の変化に気づいたら
声質の変化は、身体からのサインである可能性があります。特に、誘因がはっきりしないかすれや、徐々に悪化するかすれ、2週間以上続くような場合は注意が必要です。
風邪をひいた後など、一時的な声のかすれはよくありますが、長引く場合は自己判断せずに、原因を特定することが大切です。
声の変化に加えて、飲み込みにくさや息苦しさ、首のしこりなどの症状がある場合は、早めに医療機関を受診することを検討しましょう。
のどのかすれを引き起こす主な原因
のどのかすれは、様々な原因によって引き起こされます。原因を特定することが、適切な対処や治療への第一歩となります。
声の使いすぎや炎症によるもの
最も一般的な原因の一つが、声の使いすぎやのどの炎症です。これらは声帯に直接的な負担をかけ、正常な振動を妨げます。
急性声帯炎
風邪やインフルエンザなどのウイルス感染、あるいは細菌感染によって声帯に急性の炎症が起こる状態です。声帯が赤く腫れ上がり、うまく振動できなくなるため、声がかすれます。
通常、原因となる感染症の治癒とともに声も回復しますが、炎症が強い場合や無理に声を出し続けると、症状が長引くことがあります。
声帯ポリープ・声帯結節
声帯ポリープは、声の使いすぎや急激な発声(怒鳴る、咳き込むなど)によって声帯粘膜の血管が破れ、内出血が吸収されずにポリープ(こぶ)状になったものです。
片側の声帯にできることが多く、声がかすれたり、ガラガラしたりします。一方、声帯結節は、声帯への慢性的な機械的刺激によって、両側の声帯の同じ場所にペンだこのような硬い隆起ができるものです。
教師や歌手など、声を日常的に酷使する職業の方に見られやすく、「教師結節」とも呼ばれます。声がかすれるほか、高い声が出しにくくなることがあります。
ポリープ様声帯
声帯全体がぶよぶよと水っぽく腫れる状態で、主に喫煙が原因と考えられています。特に長期間の喫煙習慣がある中年以降の女性に多く見られます。
声が低くなり、ガラガラとした特徴的な声(ダミ声)になります。呼吸がしにくくなることもあります。
喉頭アレルギー
特定のアレルゲン(花粉、ハウスダストなど)を吸い込むことで、喉頭にアレルギー反応が起こり、声帯が腫れて声がかすれることがあります。咳やのどのイガイガ感を伴うこともあります。
加齢によるもの
年齢を重ねるとともに、身体の他の部分と同様に、声帯にも変化が現れます。これが声のかすれの原因となることがあります。
声帯萎縮
加齢により声帯の筋肉(声帯筋)が痩せたり、声帯粘膜の潤いが失われたりすることで、声帯がうまく閉じなくなり、隙間ができてしまいます。
これにより、息漏れのようなかすれた声(気息性嗄声)になったり、声が弱々しくなったり、長く話し続けるのが困難になったりします。声の老化は「老人の声」として知られ、多くの方が経験する可能性があります。
声帯萎縮で見られる声の変化
| 変化の種類 | 具体的な症状 | 影響 |
|---|---|---|
| 声の高さ | 男性は高くなる傾向、女性は低くなる傾向 | 声の印象が変わることがある |
| 声の強さ | 弱々しくなる、声量が低下する | 聞き返されることが増える |
| 声の質 | かすれる、ふるえる、息が漏れる | 明瞭さが失われる |
神経の麻痺によるもの
声帯を動かす神経(反回神経)が何らかの原因で麻痺すると、声帯が正常に開閉できなくなり、声がかすれます。
反回神経麻痺
反回神経は、脳から出て首を通り、胸部まで下降してから再び喉頭へ戻るという長い経路をたどるため、様々な部位の病気の影響を受けやすい神経です。
甲状腺がん、食道がん、肺がんなどの頸部や胸部の腫瘍、大動脈瘤、手術(甲状腺手術、食道手術、肺手術、頸椎手術など)による損傷、ウイルス感染などが原因で麻痺が起こることがあります。
片側の声帯が麻痺すると、声門が完全に閉じなくなるため、息漏れを伴うかすれた声になり、誤嚥(食べ物や飲み物が気管に入ること)しやすくなることもあります。
腫瘍によるもの
喉頭やその周辺にできる腫瘍も、声のかすれの重要な原因です。早期発見が重要となるケースもあります。
喉頭がんなどの悪性腫瘍
喉頭がんは、声帯やその周辺に発生するがんで、初期症状として声のかすれが現れることが多いです。特に喫煙や過度の飲酒との関連が深いとされています。
進行すると、のどの痛み、血痰、呼吸困難、嚥下困難などの症状が現れます。2週間以上続く原因不明の声のかすれがある場合は、喉頭がんの可能性も考慮して検査を受けることが大切です。
良性腫瘍
声帯にできる良性の腫瘍としては、乳頭腫や線維腫、血管腫などがあります。これらが声帯の振動を妨げることで、声がかすれます。
乳頭腫はヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因で、再発しやすい特徴があります。
その他の原因
上記以外にも、様々な要因がのどのかすれに関与することがあります。
逆流性食道炎
胃酸が食道に逆流し、さらに喉頭まで達すると、声帯や喉頭粘膜に炎症を引き起こし(喉頭咽頭酸逆流症:LPRD)、声がかすれたり、咳が出たり、のどの違和感が生じたりします。
胸やけなどの典型的な逆流性食道炎の症状がない場合でも、声のかすれが主症状となることがあります。
薬剤の副作用
一部の吸入ステロイド薬は、副作用として声がかすれることがあります。喘息治療などで使用している場合は、医師や薬剤師に相談してみましょう。
また、抗ヒスタミン薬や利尿薬など、のどの乾燥を引き起こす可能性のある薬剤も、間接的に声のかすれに影響することがあります。
喫煙
喫煙は、声帯に慢性的な炎症や乾燥を引き起こし、ポリープ様声帯や喉頭がんのリスクを高めるなど、声にとって多くの悪影響をもたらします。
タバコの煙に含まれる有害物質が声帯粘膜を刺激し、正常な機能を損ないます。
精神的ストレス
強い精神的ストレスや心理的な問題が原因で、声が出にくくなったり、かすれたりすることがあります(心因性発声障害)。喉頭自体には器質的な異常が見られないことが多いです。
こんな症状は要注意 早めに医療機関へ
のどのかすれはありふれた症状ですが、中には注意が必要なケースもあります。以下のような場合は、自己判断せずに耳鼻咽喉科などの医療機関を受診しましょう。
かすれが2週間以上続く場合
風邪などによる一時的な声のかすれは、通常1~2週間程度で改善します。
しかし、原因がはっきりしない声のかすれが2週間以上続く場合は、声帯ポリープや声帯結節、あるいは喉頭がんなどの病気が隠れている可能性も考えられます。
特に、喫煙歴のある方や50歳以上の方は注意が必要です。
呼吸困難や嚥下困難を伴う場合
声のかすれに加えて、息苦しさ(呼吸困難)や、食べ物や飲み物が飲み込みにくい(嚥下困難)、むせやすいといった症状がある場合は、喉頭やその周辺に大きな病変がある可能性があります。
例えば、進行した喉頭がんや両側の反回神経麻痺などでは、気道が狭窄したり、嚥下機能が低下したりすることがあります。
これらの症状は緊急を要する場合もあるため、速やかに医療機関を受診してください。
声以外の症状がある場合
声のかすれ以外に、以下のような症状が見られる場合も、詳しい検査が必要です。
- 首のしこりや腫れ
- 血痰(痰に血が混じる)
- 持続するのどの痛み
- 原因不明の体重減少
- 耳の痛み(放散痛)
これらの症状は、喉頭がんなどの悪性腫瘍を示唆するサインであることがあります。
注意すべき随伴症状
| 症状 | 考えられる主な原因・状態 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 呼吸困難 | 喉頭の腫脹、腫瘍による気道狭窄、両側反回神経麻痺 | 緊急性が高い場合あり、速やかに受診 |
| 嚥下困難・誤嚥 | 喉頭の腫瘍、反回神経麻痺、脳血管障害 | 誤嚥性肺炎のリスクあり、早期に受診 |
| 血痰 | 喉頭がん、肺がん、気管支拡張症など | 悪性腫瘍の可能性も考慮し、受診 |
医療機関で行われる検査
医療機関では、のどのかすれの原因を特定するために、いくつかの検査を行います。診断に基づいて適切な治療方針を決定します。
問診と喉頭の観察
まず、症状がいつから始まったか、どのような声の変化があるか、声を使う頻度、喫煙歴、既往歴、服用中の薬などについて詳しく問診します。
その後、医師が口を開けて舌を引っ張り、喉頭鏡という小さな鏡や圧舌子(舌を押さえる器具)を使って、喉頭の状態を視診します。これにより、声帯の動きや粘膜の状態をある程度把握できます。
喉頭内視鏡検査(ファイバースコープ)
より詳しく声帯や喉頭の状態を観察するために行われるのが、喉頭内視鏡検査です。鼻から細いファイバースコープ(カメラ付きの管)を挿入し、喉頭を直接観察します。
検査中の痛みは少なく、声帯の細かな動きや色調、小さな病変まで確認できます。発声時の声帯の振動を観察するために、ストロボスコピーという特殊な光源を用いることもあります。
この検査は、のどのかすれの診断において非常に重要です。
喉頭内視鏡検査でわかること
- 声帯の形、色、動き
- ポリープ、結節、腫瘍の有無や大きさ、性状
- 炎症の程度
- 声帯麻痺の有無
画像検査(CT、MRIなど)
喉頭内視鏡検査で腫瘍が疑われた場合や、反回神経麻痺の原因を調べる必要がある場合などには、頸部から胸部にかけてのCT検査やMRI検査などの画像検査を行います。
これらの検査により、腫瘍の広がりや深さ、リンパ節への転移の有無、神経麻痺の原因となる病変(例:肺がん、大動脈瘤)などを評価します。
主な画像検査とその目的
| 検査名 | 主な目的 | 特徴 |
|---|---|---|
| CT検査 | 腫瘍の広がり、骨への浸潤、リンパ節転移の評価 | 短時間で広範囲を撮影可能、X線を使用 |
| MRI検査 | 腫瘍の性状診断、軟部組織の描出に優れる | 放射線被曝なし、時間がかかることがある |
| 超音波検査(エコー) | 頸部リンパ節の評価、甲状腺の病変の確認 | 簡便に行える、被曝なし |
その他の検査
必要に応じて、以下のような検査も行われます。
- 病理組織検査(生検): 喉頭内視鏡検査などで悪性腫瘍が疑われる病変が見つかった場合、その一部を採取して顕微鏡で詳しく調べる検査です。がんの確定診断に必要です。
- 血液検査: 炎症の程度を調べたり、全身状態を把握したりするために行います。
- 音声機能検査: 声の高さ、強さ、発声持続時間などを測定し、客観的に音声機能を評価します。
のどのかすれの治療法
のどのかすれの治療は、原因や症状の程度によって異なります。原因疾患の治療が基本となりますが、声の衛生指導や音声治療、手術などが行われます。
保存的治療
手術を必要としない治療法で、多くの場合、まず保存的治療から開始します。
声の安静と生活指導
声帯炎や声帯ポリープ、声帯結節の初期などでは、声の安静が最も重要です。できるだけ声を出さないようにする(沈黙療法)、あるいは小さな声で話すように心がけます。
また、大声や長時間の会話を避け、筆談などを活用することも有効です。生活指導としては、禁煙、十分な水分摂取、室内の加湿、刺激物の摂取を控えることなどが挙げられます。
薬物療法
原因や症状に応じて薬物療法を行います。
薬物療法の例
| 薬剤の種類 | 主な目的・効果 | 対象となる主な状態 |
|---|---|---|
| 消炎鎮痛薬 | 声帯の炎症や痛みを抑える | 急性声帯炎、喉頭炎 |
| 抗菌薬(抗生物質) | 細菌感染を治療する | 細菌性声帯炎 |
| ステロイド薬 | 強い炎症を抑える | 重度の声帯炎、声帯浮腫(医師の判断で短期的に使用) |
| 去痰薬・粘液溶解薬 | 痰の切れを良くする、声帯粘膜の潤滑を助ける | 痰が絡む場合 |
| 胃酸分泌抑制薬 | 胃酸の逆流を抑える | 逆流性食道炎、喉頭咽頭酸逆流症 |
吸入療法
炎症を抑える薬液や声帯の潤いを保つための薬液を、ネブライザーという器具を使って霧状にし、直接喉頭に吸入する治療法です。
声帯に直接薬剤を届けることができるため、効果的に炎症を鎮めたり、粘膜を保護したりします。
音声治療(リハビリテーション)
声帯結節や声帯萎縮、一部の声帯麻痺などに対して、言語聴覚士などの専門家による音声治療が行われることがあります。
これは、正しい発声方法を習得し、声帯への負担を軽減したり、残存する機能を最大限に活用したりするためのリハビリテーションです。
腹式呼吸の練習、声帯のストレッチ、共鳴腔の適切な使い方などを学びます。根気強く続けることで、声質の改善が期待できます。
手術的治療
保存的治療で改善が見られない場合や、腫瘍が原因である場合などには、手術的治療が検討されます。
喉頭微細手術(ラリンゴマイクロサージェリー)
全身麻酔下で、顕微鏡を使って喉頭を拡大視しながら、声帯ポリープ、声帯結節、初期の喉頭がんなどの病変を切除する手術です。
非常に精密な操作が求められるため、専門的な技術が必要です。術後は、声帯の安静期間が必要となります。
喉頭枠組み手術
声帯麻痺や声帯萎縮によって声門閉鎖不全(声帯がうまく閉じない状態)がある場合に、声の改善を目的として行われる手術です。
局所麻酔下で行われることが多く、甲状軟骨(のどぼとけを形成する軟骨)の一部を切開したり、シリコンなどの人工物を挿入したりして、麻痺した声帯の位置を調整し、声門の隙間を狭めます。
代表的なものに甲状軟骨形成術Ⅰ型があります。
その他の手術
進行した喉頭がんに対しては、喉頭部分切除術や喉頭全摘術などのより大きな手術が必要になることがあります。
喉頭全摘術を受けると、声を失うため、食道発声や電気喉頭(人工喉頭)などの代用音声の習得が必要になります。
手術治療の選択肢
| 手術法 | 主な対象疾患 | 目的 |
|---|---|---|
| 喉頭微細手術 | 声帯ポリープ、声帯結節、早期喉頭がん、声帯嚢胞など | 病変の切除、声質の改善 |
| 甲状軟骨形成術Ⅰ型 | 片側反回神経麻痺、声帯萎縮 | 声門閉鎖不全の改善、声質の改善 |
| 喉頭全摘術 | 進行喉頭がん | がんの根治 |
日常生活でできるセルフケアと予防法
のどのかすれを予防したり、症状を悪化させないためには、日常生活での心がけが重要です。声帯に優しい生活習慣を送りましょう。
声の正しい使い方を意識する
無理な発声は声帯に大きな負担をかけます。以下の点に注意しましょう。
- 大声や奇声を出さない
- 長時間話し続けない(適度に休憩を挟む)
- 早口で話さない
- 咳払いをしすぎない(のどがイガイガする時は水を飲むなど工夫する)
- 電話で話すときは、受話器を口に近づけすぎず、自然な声量で話す
特に、騒がしい場所で話す際は、無意識に声が大きくなりがちなので注意が必要です。また、歌う前には十分なウォーミングアップを行い、無理のない音域で歌うようにしましょう。
のどの保湿と加湿
声帯は乾燥に弱いため、適度な潤いを保つことが大切です。
のどの潤いを保つ工夫
| 方法 | 具体的なポイント | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| こまめな水分補給 | 水や白湯などを少量ずつ頻繁に飲む | 声帯粘膜の乾燥を防ぐ |
| 室内の加湿 | 加湿器を使用する(湿度50~60%が目安)、濡れタオルを干す | 空気の乾燥を防ぎ、のどへの負担を軽減 |
| マスクの着用 | 特に乾燥した場所や人混みで | 呼気に含まれる水分でのどを保湿、感染予防 |
うがいも、のどの清潔を保ち、乾燥を防ぐのに役立ちますが、刺激の強いうがい薬の使いすぎはかえって粘膜を傷めることがあるので注意しましょう。
バランスの取れた食事と十分な睡眠
全身の健康状態は、のどの状態にも影響します。栄養バランスの取れた食事を心がけ、免疫力を高めましょう。特に、ビタミンA、C、Eなどは粘膜の健康維持に役立つとされています。
また、十分な睡眠は、身体の疲労回復だけでなく、声帯の修復にも重要です。不規則な生活や睡眠不足は避けましょう。
禁煙と節酒
喫煙は声帯にとって百害あって一利なしです。タバコの煙は声帯を直接刺激し、炎症や乾燥を引き起こすだけでなく、ポリープ様声帯や喉頭がんの最大のリスク因子です。
禁煙は、声の健康を守るために最も効果的な方法の一つです。アルコールも、過度な摂取はのどの粘膜を刺激し、脱水を引き起こす可能性があります。飲酒は適量を心がけましょう。
特に、アルコール度数の高いお酒をストレートで飲むのは避けた方が賢明です。
のどのかすれに関するよくある質問
- Qのどのかすれは自然に治りますか?
- A
原因によります。風邪などの一時的な炎症によるものであれば、安静にしていれば数日から1週間程度で自然に治ることが多いです。
しかし、声の使いすぎによるポリープや結節、加齢による声帯萎縮、神経麻痺、腫瘍などが原因の場合は、自然治癒が難しかったり、悪化したりすることもあります。
2週間以上かすれが続く場合は、医療機関を受診することをお勧めします。
- Q声変わりとの違いは何ですか?
- A
声変わりは、主に思春期の男性に起こる生理的な声の変化です。第二次性徴に伴い、喉頭が急速に成長し、声帯が長くなることで声が低くなります。
この過程で一時的に声が不安定になったり、かすれたりすることがありますが、通常は自然に落ち着きます。一方、成人後の明らかな原因のない声のかすれは、何らかの病的な状態を示唆することがあります。
特に、声変わりとは異なる声質の変化(ガラガラ声、弱々しい声など)や、他の症状を伴う場合は注意が必要です。
- Q歌いすぎでのどがかすれた場合、どうすれば良いですか?
- A
まずは声の安静が第一です。無理に声を出そうとせず、できるだけ話すのを控えましょう。のどを潤すためにこまめに水分を摂り、部屋の加湿も心がけてください。
のど飴をなめるのも良いですが、メントール系の刺激が強いものは避け、保湿効果のあるものを選びましょう。
数日安静にしても改善しない場合や、痛みが強い場合は、声帯炎や声帯ポリープなどができている可能性もあるため、耳鼻咽喉科を受診しましょう。
- Qどのような食べ物や飲み物がのどに良いですか?
- A
特定の食品が劇的にのどを良くするというよりは、バランスの取れた食事が基本です。その上で、のどの粘膜を潤し、刺激の少ないものが良いでしょう。
のどに優しいとされる飲食物の例
種類 具体例 ポイント 飲み物 水、白湯、麦茶、ハーブティー(カモミールなど) 常温または温かいもの。カフェインの多いものは利尿作用で脱水を招くことも。 食べ物 スープ、おかゆ、豆腐、うどん、果物(梨、りんごなど) 柔らかく、消化が良いもの。粘膜保護に役立つビタミンA、Cを含むもの。 避けた方が良いもの 香辛料の多いもの、熱すぎる・冷たすぎるもの、炭酸飲料、アルコール のどへの刺激が強いものは控える。 大根やはちみつ、生姜などがのどに良いと言われることもありますが、これらはあくまで補助的なものと考え、頼りすぎないようにしましょう。はちみつは1歳未満の乳児には与えないでください。
- Qマスクはのどのかすれに効果がありますか?
- A
はい、効果が期待できます。マスクを着用することで、自分の呼気に含まれる湿気でのどの粘膜が潤い、乾燥を防ぐことができます。
また、冷たい空気や乾燥した空気、ホコリやアレルゲンなどを直接吸い込むのを防ぐ効果もあります。
さらに、風邪などの感染症予防にもつながり、結果としてのどのかすれを防ぐことにも役立ちます。
- Q長引くのどのかすれは、がんの可能性もありますか?
- A
はい、その可能性も否定できません。特に、2週間以上続く原因不明の声のかすれは、喉頭がんの初期症状であることがあります。
喫煙歴のある方、50歳以上の方、飲酒量の多い方はリスクが高まります。声のかすれ以外に、のどの痛み、血痰、首のしこり、呼吸困難、嚥下困難などの症状がある場合は、特に注意が必要です。
心配な場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診し、専門医の診察を受けることが重要です。
以上