在宅酸素療法(HOT)を受けている方にとって携帯用酸素ボンベは外出を支える大切な機器です。
外出時に適切な携帯用の酸素ボンベを選び、うまく活用すれば、日常生活の行動範囲を広げてQOL(生活の質)の向上を目指せます。
本記事では携帯用酸素ボンベの基礎から選ぶポイント、安全対策まで幅広く解説し、通院や旅行などを快適に行うためのヒントを紹介します。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。
携帯用酸素ボンベとHOTの基本
外出を考慮した酸素ボンベを携帯する場合、HOTの特徴や携帯用酸素ボンベの役割を把握しておくことが重要です。
ここではそもそも在宅酸素療法とは何か、携帯用酸素ボンベとはどのようなものかを見ながら、その意義を解説します。
HOTとは?
在宅酸素療法(Home Oxygen Therapy, HOT)は、自宅で酸素吸入を行いながら生活する治療法です。
慢性呼吸不全や慢性閉塞性肺疾患(COPD)、間質性肺炎などの病気を抱える方に対して処方されることが多いです。
HOTは低酸素血症を改善し、息切れの軽減や倦怠感の改善、運動耐容能の向上など症状緩和に有効です。
さらに酸素不足から臓器を保護しQOLや生存期間の延長効果も実証されています。
携帯用酸素ボンベとは何か
自宅では酸素濃縮器などを使って酸素を吸入していても外出時には別の携帯できる酸素供給源が必要です。
携帯用の酸素ボンベはコンパクトで持ち運びやすいように設計された酸素供給機器です。酸素ボンベを携帯することで通院、買い物、散歩などの日常行動をより自由に行えるようになります。
選び方の重要性
携帯用の酸素ボンベは種類や容量、重量などがさまざまです。
使う機会や外出時間に応じて選ぶ機器を間違えると使い勝手が悪く外出を諦めてしまう場面が増えたり、必要な酸素量を満たせなかったりする恐れがあります。
適切に選ぶことは外出の継続性や安全性にも深く関係します。
外出時のメリット
携帯用酸素ボンベを利用すると外出先で酸素不足による息切れや倦怠感のリスクが軽減され、安心して行動できます。
外出が増えると気分転換や身体機能の維持にもつながります。
日々の行動範囲を広げることで社会参加の機会も得やすくなり、心身の健康を総合的にサポートします。
携帯用酸素ボンベを導入する利点
- 外出中の呼吸困難を和らげる
- 通院や買い物などの日常活動を継続しやすい
- 社会参加や旅行などのレジャーにも挑戦しやすい
- 精神面のストレス軽減に役立つ
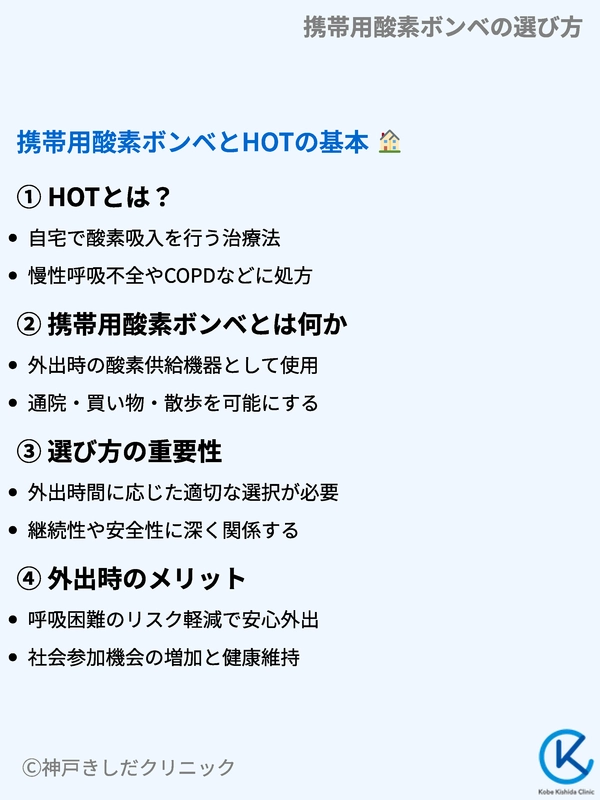
携帯用酸素ボンベの種類
携帯用酸素ボンベには大きく分けて高圧ガス式と液体酸素式、またはポータブル酸素濃縮器のような機器があります。
ここではそれぞれの仕組みと特徴を整理し、外出時に使いやすい機器の選択肢を確認しましょう。
高圧ガス式
一般的に知られている酸素ボンベです。頑丈な金属製ボンベ内部に高圧で酸素を詰め込んでおり、流量が一定なら安定した酸素供給を期待できます。
小型の高圧ガス式のボンベを携帯するケースも多く、再充填の際には専門業者や医療機関でガスを詰め直します。
- 長所:酸素の純度が高く構造が比較的シンプル
- 短所:ボンベが重くなりがちで長時間の外出には負担を感じる場合がある
液体酸素式
酸素を液体の状態でボンベに充填しておき、気化させることで酸素を供給します。
ガス式よりも多くの酸素を貯蔵しやすい点が特徴で、ボンベを小型化しやすい利点があります。
液体酸素式は同重量でより多くの酸素を携行でき、長時間外出には有利です。
ただし日本では住宅事情などから利用者はHOT患者全体の約1%と少なく、必要時のみ検討される方式です。
導入には据置きタンクの設置や取扱い訓練が必要である点に注意してください。
- 長所:同じ重量でも多くの酸素量を確保しやすい
- 短所:低温状態で保管するため、取り扱いに注意が必要
酸素濃縮器(ポータブル酸素濃縮器)
自力で空気中から酸素を取り込み、濃縮して供給する小型の装置です。ボンベ交換を不要にできるのが大きな利点ですが、電源を確保できる環境で使う必要があります。
近年は小型軽量化が進んでおり、バッテリー駆動モデルも出ています。酸素ボンベを携帯する代わりに、電源供給源を確保すれば連続使用が可能です。
- 長所:酸素を継ぎ足す手間がいらない
- 短所:バッテリー駆動時間や騒音などに配慮が必要
用途に合わせた選択ポイント
それぞれの形式にメリットとデメリットがあります。医療機関で指示された酸素流量や自身の体力、行動範囲などに応じて選ぶことが大切です。
旅行好きな方は長時間使いやすい液体酸素式やバッテリー式の酸素濃縮器を検討するとよいでしょう。
近距離の外出中心なら高圧ガス式のボンベを携帯しておけば安心です。
携帯用酸素ボンベの種類比較
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 高圧ガス式 | 高圧ガスを金属ボンベに充填 | 酸素純度が高く、安定供給が期待できる | ボンベが重くなりがち |
| 液体酸素式 | 液体酸素を気化して使用 | 同じ重量でも多くの酸素を持ち運び可能 | 温度管理が必要 |
| ポータブル酸素濃縮器 | 空気から酸素を分離・濃縮して供給 | ボンベ交換が不要で連続的に使用しやすい | バッテリー駆動時間の管理要 |
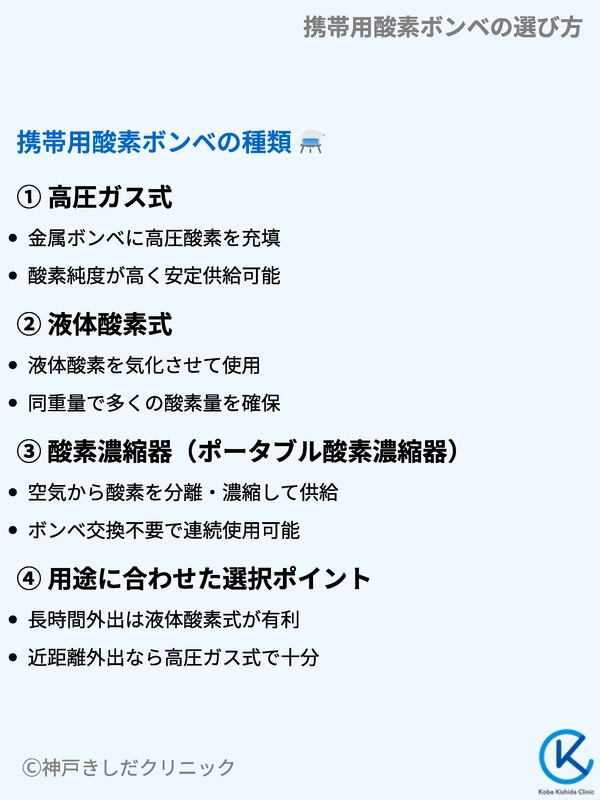
流量と必要酸素量の目安
携帯用酸素ボンベを利用するときには医師から指示された酸素流量を確実に満たす必要があります。
流量や酸素量を理解しておかないと外出時に酸素が足りなくなったり、逆に過剰な設備を用意して持ち運びが困難になったりするリスクがあります。
流量とは
酸素療法では1分間に必要な酸素の量を「流量(L/min)」という単位で示します。
例えば「2 L/min」の指示がある場合、1分間に2リットルの酸素を吸入する必要があります。
流量が高いほどボンベの消費が早く、ボンベが空になるまでの時間も短くなります。
酸素濃度とHOT治療
HOTを行う上では体内の酸素飽和度(SpO2)を一定以上に保つことが大切です。必要な酸素濃度を保つために医師からの指示どおりの流量を守りましょう。
流量を自己判断で増減すると体内の酸素過不足を招く危険性があります。
吸入時間とボンベ容量
携帯用酸素ボンベの容量はボンベサイズによって異なります。例えば「2 L/min」で使用した場合、容量「400 L」のボンベは約200分(3時間20分)利用できます。
ただし呼吸のパターンや酸素の使い方によって多少の誤差があるため、余裕を持った計画が必要です。
ボンベ容量と使用時間の目安
| ボンベ容量 (L) | 流量 2 L/min 時の使用目安 | 流量3 L/min 時の使用目安 | 流量4 L/min 時の使用目安 |
|---|---|---|---|
| 300 | 約150分(2時間30分) | 約100分(1時間40分) | 約75分(1時間15分) |
| 400 | 約200分(3時間20分) | 約133分(2時間13分) | 約100分(1時間40分) |
| 500 | 約250分(4時間10分) | 約166分(2時間46分) | 約125分(2時間5分) |
担当医との相談
日常的に必要な流量や使用時間は個人差があります。医師や担当スタッフと相談しながら自身に合ったボンベ容量や使用方法を確立してください。
特に長時間の外出や旅行など予定がある時には事前に使用量のシミュレーションをすると安心です。
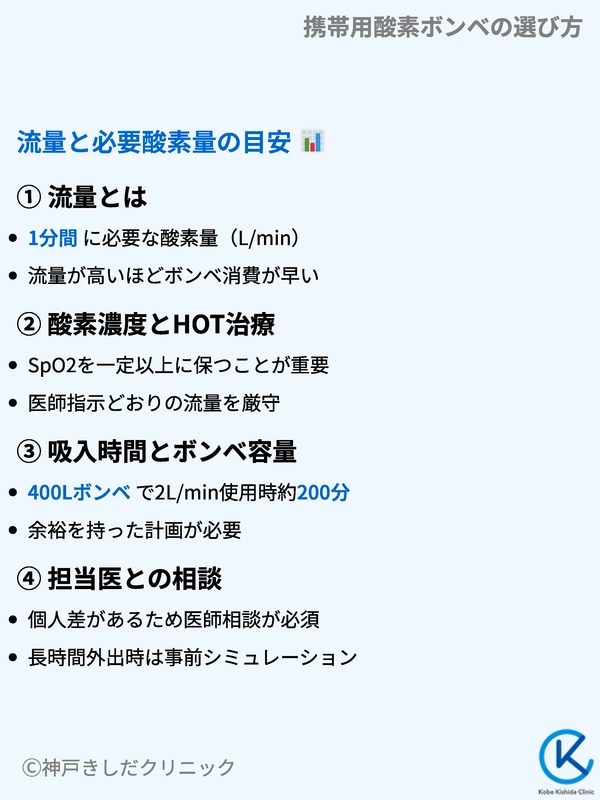
携帯用酸素ボンベ選びのポイント
携帯用の酸素ボンベを選ぶときには重量やサイズだけでなく、酸素供給方式やメンテナンスのしやすさ、価格など多岐にわたる項目を考慮します。
ここでは具体的に見ていきましょう。
重量とサイズ
外出で持ち歩く以上、重量やサイズは大きな負担につながります。可能な範囲で軽量かつ小型のものを選びたいですが、あまりに小さすぎると酸素量を確保できない恐れがあります。
自分がどの程度の重量を持って移動できるかを試したうえで、必要な容量とのバランスを取りながら検討してください。
酸素供給方式
- 定流量式:常に一定の酸素を出す方式。シンプルだがボンベの消費量が多い
- パルス式:吸気を感知して酸素を出す方式。効率的に酸素を使うためボンベの持ちが良い
パルス式は酸素を無駄なく使えるため、ボンベの交換頻度を減らしやすいです。
パルス(呼吸同調)式調節器を使うと酸素消費を2~3倍節約できる一方、呼吸が浅い患者ではセンサーが作動しないことがあります。
パルス式使用時に低酸素化する例も報告されているため、まずは主治医や呼吸療法士の助言を得ることをおすすめします。
メンテナンス性
携帯用酸素ボンベや酸素濃縮器は定期的な点検やクリーニングが必要です。
高圧ガス式の場合はボンベ交換が必要となり、交換体制もチェックが欠かせません。液体酸素式なら装置の定期点検、酸素濃縮器ならフィルター清掃やバッテリー管理が必要です。
これらの手間を踏まえて継続しやすい機器を選ぶと長く快適に使えます。
価格と保険制度
在宅酸素療法の費用には健康保険が適用される部分と自己負担になる部分があります。
在宅酸素療法に必要な機器レンタルや酸素補充費用は、公的医療保険が適用されます。
患者負担は1割負担で月約7,680円、3割負担で月約23,040円が目安です。高額療養費制度により一定額以上の自己負担は軽減されます。
一方、保険適用外となる付属品(カートやカバー等)や電気代は自己負担です。
保険内でどの形式のボンベや機器が適用されるのか事前に確認しておくことが大切です。
保険適用や費用
| 項目 | 内容 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 健康保険の適用範囲 | 在宅酸素療法に必要な機器や装置の一部 | どこまでカバーされるかを事前確認 |
| 自己負担部分 | 保険給付対象外の周辺機器・消耗品など | 交換ボンベ・アクセサリー類の費用を把握 |
| 公的補助(高額療養費制度など) | 医療費の上限設定や減額 | 所得による上限額の違いを調べておく |
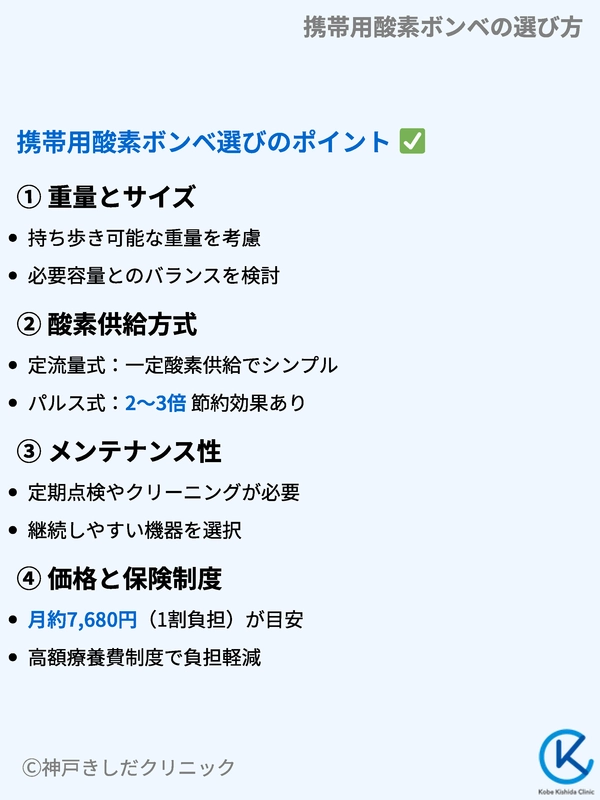
外出時に便利な付属品
携帯用酸素ボンベそのもの以外にも外出時の負担を減らし、快適に過ごすために役立つ付属品があります。
必要に応じて活用すると、移動しやすさや安全性が向上します。
交換用酸素ボンベ
長時間外出する時には予備の酸素ボンベがあると安心です。ボンベが空になる前に交換することで酸素切れを防げます。
交換用ボンベを何本持ち歩くかは体力や移動距離、予定時間に応じて調整してください。
カートやキャリーケース
ボンベを手持ちするのが難しい方は専用のカートやキャリーケースを使うと移動が楽になります。肩掛けタイプ、背負うタイプなど種類が豊富にそろっています。
取っ手の長さや車輪の滑らかさに着目しながら、自分の移動スタイルに合うものを選ぶと良いです。
携帯用酸素ボンベ運搬補助用具
| 用具名 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| カート型キャリー | 車輪付きで手元で引ける | 移動中の負担が少ない | 地形によっては段差がつらい場合も |
| ショルダーバッグ | 肩掛けや斜め掛けで運ぶ | 両手が自由になり使いやすい | 肩や背中への負担がかかりやすい |
| リュック型キャリー | 背負えるタイプ | 長距離移動や階段で便利 | 背中の負荷を考慮する必要がある |
携帯用バッテリー
ポータブル酸素濃縮器を使用する場合、バッテリーを複数用意しておくと安心です。
出先で充電できない状況が想定されるなら予備バッテリーを持参し、想定使用時間の1.5~2倍程度の容量を確保するとゆとりが生まれます。
酸素ボンベカバーの活用
酸素ボンベカバーはボンベ本体を保護し、衝撃や汚れから守る役割があります。
保温効果があるタイプや、周囲の視線からボンベを隠すためのデザイン性に優れたカバーも販売されています。自分の好みや用途に合わせて選んでみてください。
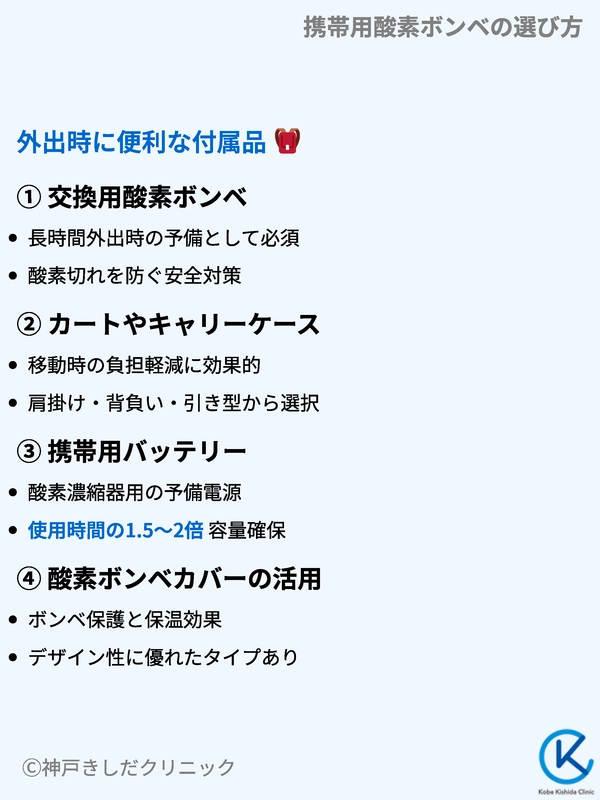
携帯用酸素ボンベの安全対策と注意点
携帯用の酸素ボンベは取り扱いを誤ると事故やトラブルが起こる可能性があります。特に火気や高温環境などには十分気をつける必要があります。
ここでは代表的な注意点を整理します。
火気の注意
酸素は燃焼を助長する性質があるため、ボンベを扱うときは喫煙や火の取り扱いに気をつけてください。
ボンベから一定の距離を保ち、火や高温のものを近づけないよう意識しましょう。
高温多湿の環境
酸素ボンベは40℃を超える場所に置かないことが安全基準です。
真夏の閉ざした車内など50℃近くになる環境で放置すると爆発的ガス放出の危険があります。
多湿環境での露滴は機器腐食の原因となるため、水濡れ時は速やかに拭き取りましょう。
「高温多湿を避け涼しい場所で保管」が鉄則です。
車内に長時間置きっぱなしにしないなど場所の管理を工夫してください。
安全管理に役立つリスト
- 暑い時期は車内に放置せず日陰や涼しい場所を選ぶ
- 雨や水濡れに注意し適切に水分を拭き取る
- 破損や変形の兆候があれば早めに医療機関や業者に相談する
破損や転倒への対策
携帯用酸素ボンベは衝撃に弱い部分があるため落下やぶつけるなどの転倒事故に注意しましょう。
外出先で置く際は安定した場所に置き、ボンベのキャップやカバーを正しく装着してください。
非常時の対応
万が一トラブルや異常を感じたら、まずは主治医や医療スタッフに連絡を取りましょう。
夜間や休日でも対応できる医療体制を事前に調べておくと安心です。
緊急時に備えて予備のボンベやバッテリーを常に用意しておくことも大切です。
安全対策と点検項目
| チェック項目 | 具体的な確認内容 | 推奨頻度 |
|---|---|---|
| ボンベや機器の外観 | へこみ、傷、変形、キャップのゆるみなど | 使用前・使用後毎回 |
| 吸入経路や接続チューブの確認 | ねじれや外れ、破れなどがないか | 使用前・使用後毎回 |
| 流量計の設定 | 指示どおりの流量になっているか | 使用前 |
| バッテリー(酸素濃縮器) | 充電量や劣化の有無 | 週1回程度以上 |
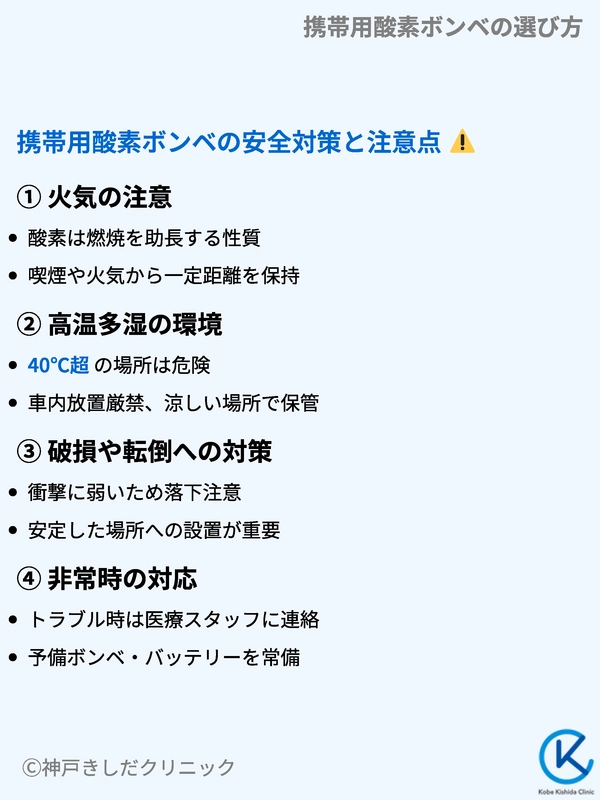
旅行や長時間外出時のコツ
外出が日常の近距離移動だけでなく、長時間におよぶ場合や旅行を考える場合には、さらに入念な準備が重要です。
あらかじめポイントを押さえておくと、不測の事態を避けやすくなります。
事前準備と医療機関への相談
旅行や遠出の予定が決まったら、まず主治医に相談してください。目的地の気候や標高、移動手段などを伝えれば、必要な流量やボンベ本数の目安を一緒に考えられます。
保険適用の範囲や、現地でのボンベ調達の可否も確認しておくと安心です。
交通手段ごとのポイント
- 飛行機:航空機利用時は搭乗2週間前までに航空会社へ医師の診断書や同意書を提出し、酸素使用の許可を得る必要があります。航空会社により、機内で使える酸素供給機材(自社提供酸素または特定の携帯濃縮器)に制限があるため、必ず事前確認してください。
- 電車:駅構内での移動や階段の有無を考慮してカートやキャリーを選ぶ
- 車:真夏の車内放置を避けて直射日光が当たらないよう管理
ホテル選びと滞在先での注意
宿泊先ではバッテリー充電や酸素ボンベ置き場を確保できるかを確認してください。酸素濃縮器を使うならコンセント位置や電圧の問題がないかも重要です。
海外旅行の場合は電圧変換アダプターが必要になることもあります。
緊急時の連絡先
旅先で体調不良になったときに備えて緊急連絡先を用意しておきましょう。
日本国内なら24時間対応の医療窓口や、かかりつけ医の連絡先をメモしておくと安心です。
海外では日本語が通じる医療機関を事前に調べ、保険会社の緊急連絡先もあわせて確認しておくとより安全です。
旅行準備のポイント
| 項目 | 内容 | 事前チェック |
|---|---|---|
| 航空会社への連絡 | 酸素ボンベや濃縮器の持ち込み許可や書類 | 搭乗日の2~3週間前には確認 |
| ホテルの設備 | コンセントの数、車いす対応客室など | 予約時に問い合わせ |
| 現地での医療体制 | 近隣病院、緊急連絡先 | ホームページや問い合わせ |
| 予備酸素ボンベの準備 | 移動時間+αを考慮した本数 | 移動日の前に手配 |
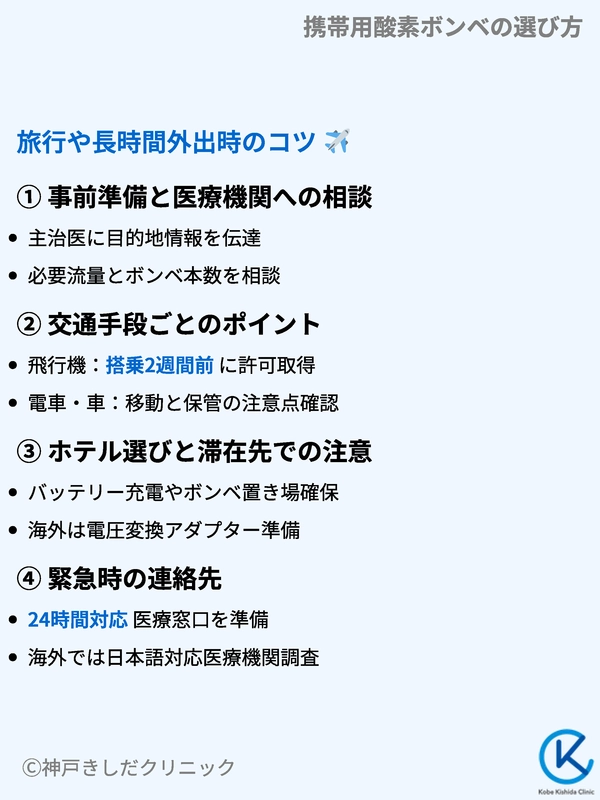
生活の質を向上させるための工夫
携帯用酸素ボンベの準備だけでなく、日常生活のさまざまな面を見直すことで呼吸機能や体力の維持にもつなげられます。
ここでは、より前向きな生活を送るためのヒントを紹介します。
運動やリハビリテーション
呼吸器疾患を抱えている方でも自分に合った範囲で運動やリハビリを行うと筋力や持久力が改善しやすくなります。
医師やリハビリスタッフと相談しながら、ウォーキングや軽い体操を取り入れてみましょう。
携帯用の酸素ボンベを用意すれば外での運動も挑戦しやすくなります。
日常活動の見直し
家事や買い物などの日常活動を計画的にこなし、体力をうまく温存する工夫も重要です。
動作に無理が生じると呼吸が乱れやすいので、休憩や作業スケジュールを細かく組み立てると負担が減らせます。
日常活動を調整するコツ
- 予定を詰め込みすぎず、余裕を持ったスケジュールを作る
- 長時間立ち仕事が続く場合、適宜座って休む
- 重い物はこまめに分けて運ぶ
- 配食サービスやオンライン通販を活用して買い物を最小限にする
食生活の調整
呼吸がしやすい身体を維持するには栄養バランスのとれた食事が大切です。
過度な塩分や糖分を控え、タンパク質やビタミン、ミネラルをバランスよく摂るよう心がけてください。
むやみに食事制限すると体力低下につながるので、専門家の助言を受けながら計画的に実践しましょう。
医療スタッフとの連携
HOT導入患者は必ず月1回以上の受診が必要で、状態に合わせて酸素流量や治療内容の見直しを行います。
症状の変化は都度主治医に報告し、必要なら処方修正してもらいましょう。
また24時間対応の訪問看護や酸素業者支援を活用し、緊急時にすぐ相談できる体制を整えておくと安心です。
HOTの治療方針や日常生活での注意点は、定期的に医療スタッフに相談しながらアップデートしていくのがおすすめです。
ちょっとした体調変化でも主治医に伝えることで、必要に応じて酸素流量や薬の調整を行えます。
さらに、看護師や呼吸療法士から具体的なアドバイスを得ると安心して生活できるでしょう。
医療スタッフとの連携事項
| スタッフ種別 | 主な役割 | 具体的な相談内容 |
|---|---|---|
| 主治医 | 治療方針の決定、薬剤処方など | 酸素流量や薬の調整、症状悪化時の対応 |
| 看護師・呼吸療法士 | 日常管理のサポート、器具の取り扱い指導 | ボンベ使用のタイミング、メンテナンス方法 |
以上
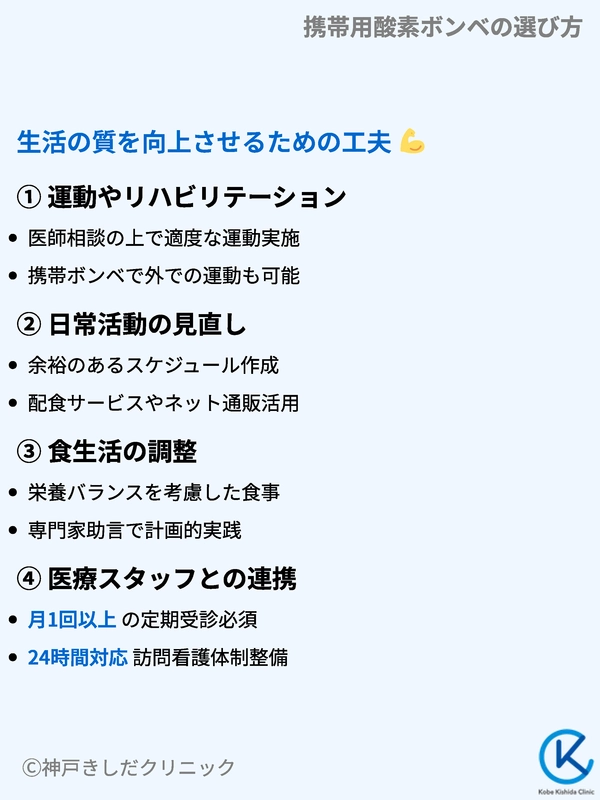
参考にした論文
KOZUI, K. I. D. A. Home Oxygen Therapy in Japan: Clinical application and considerations for practical implementation. JMAJ Research and Reviews, 2011, 54.2: 99-104.
BURIOKA, Naoto, et al. Health-related quality of life in patients on home oxygen therapy with telemonitoring. Yonago acta medica, 2020, 63.2: 132-134.
JACOBS, Susan S., et al. Home oxygen therapy for adults with chronic lung disease. An official American Thoracic Society clinical practice guideline. American journal of respiratory and critical care medicine, 2020, 202.10: e121-e141.
KOGA, Tomohiro, et al. The diagnostic utility of anti-melanoma differentiation-associated gene 5 antibody testing for predicting the prognosis of Japanese patients with DM. Rheumatology, 2012, 51.7: 1278-1284.
FUJINO, Takahisa, et al. Novel SARS-CoV-2 variant in travelers from Brazil to Japan. Emerging infectious diseases, 2021, 27.4: 1243.
LIN, Ching-Chi. Comparison between nocturnal nasal positive pressure ventilation combined with oxygen therapy and oxygen monotherapy in patients with severe COPD. American journal of respiratory and critical care medicine, 1996, 154.2: 353-358.
JCS JOINT WORKING GROUP, et al. Guidelines for the Diagnosis, Treatment and Prevention of Pulmonary Thromboembolism and Deep Vein Thrombosis (JCS 2009)–Digest Version–. Circulation Journal, 2011, 75.5: 1258-1281.
FAARC, Robert M. Kacmarek PhD RRT. Delivery systems for long-term oxygen therapy. Respiratory care, 2000, 45.1: 85.
BANDO, M., et al. Elevated plasma brain natriuretic peptide levels in chronic respiratory failure with cor pulmonale. Respiratory medicine, 1999, 93.7: 507-514.
KATO, Masahiko, et al. Obstructive sleep apnea and cardiovascular disease. Circulation journal, 2009, 73.8: 1363-1370.



