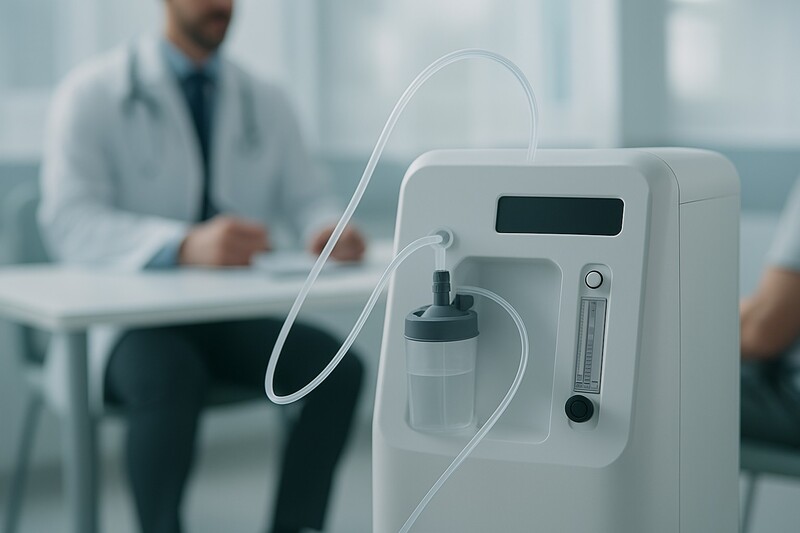在宅酸素療法は慢性の呼吸器疾患などで長期的に酸素供給が必要な方にとって外来や施設での治療だけでは支えきれない部分をサポートする治療方法です。
医師の診断から導入に至るまでには患者さんそれぞれの病状や生活環境を踏まえながら必要性を判断する手順が存在します。
この記事では在宅酸素療法の適応範囲やHOT(在宅酸素療法)を導入する基準、導入後の生活上の注意点、機器の種類などを詳しく解説し、より多くの方に在宅酸素療法を理解していただくことを目的としています。
在宅酸素療法とは何か
ここでは在宅酸素療法の基本的な概要についてどのような疾患に対して有用なのか、またどのような形で生活の一部となっていくのかをお伝えします。
呼吸が苦しくなる原因は多岐にわたり、慢性閉塞性肺疾患(COPD)や間質性肺炎、気管支喘息などが代表的です。
これらの病気によって血液中の酸素が十分に行き渡らなくなる場合に、家庭で酸素を吸入できるようにするのが在宅酸素療法です。
在宅酸素療法導入の背景
慢性的な呼吸不全があると、酸素を取り込む力が低下しやすくなります。外来通院や入院で酸素吸入をするだけでは十分な酸素量を維持できない場合もあります。
そこで医師が「日常的に酸素補給を要する」と判断した際に在宅酸素療法を検討します。
外部から酸素を供給することで血中酸素濃度を適切に保ち、症状の悪化を予防することが狙いです。
通院や入院との違い
在宅酸素療法は主に自宅で酸素を吸入しながら生活します。医療機関への長期入院を避け、できるだけ日常生活を継続しやすくする利点があります。
外来受診の頻度も患者さんによって異なりますが、在宅での酸素補給によって活動範囲を大きく制限しなくて済むようになる点が重要です。
治療とQOLの両立
慢性呼吸不全の患者さんには自宅での療養が長期化する傾向があります。自宅に酸素供給の機器を設置することで、治療と生活の両立がしやすくなります。
家族や介護者の協力のもと、医師の指示を受けつつ適切な酸素量を管理することが在宅酸素療法の特長です。
呼吸リハビリテーションとの関連
慢性呼吸不全の方は呼吸リハビリテーションを並行して行うことが多いです。
酸素吸入下で軽めの運動療法を行い、呼吸筋の負担を軽減しながら体を動かす習慣をつくることで、ADL(日常生活動作)の向上を目指せる場合があります。
在宅酸素療法に用いられる代表的な機器と機能
| 種類 | 機能・特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 酸素濃縮器 | 室内の空気から酸素を濃縮して供給する装置 | 電源があれば連続的に酸素供給可能 | 電気代がかかる |
| 液体酸素装置 | 液体酸素をタンクに貯めて使用 | 携帯用タンクに詰め替えが可能 | タンク管理に手間がかかる |
| 酸素ボンベ | 高圧ガスボンベ内に酸素を圧縮 | 電源不要で使用が簡単 | ボンベの交換が必要 |
| 携帯型酸素濃縮器 | 持ち運びできるコンパクトな酸素濃縮装置 | 外出先でも酸素吸入がしやすい | バッテリーの管理が必要 |
上記は代表的な機器の例です。医師や医療スタッフと相談しながら、日常生活に合わせて機器を選ぶことが大切です。
在宅酸素療法の適応範囲と診断までの流れ
在宅酸素療法の適応は多岐にわたり、医師は患者さんそれぞれの酸素飽和度や血液ガス分析を参考にしながら必要性を判断します。
ここではどのような基準で診断が下され、在宅酸素療法につながっていくかを解説します。
呼吸不全の評価基準
医師はパルスオキシメーターや血液ガス分析の結果をもとにして呼吸不全の重症度を評価します。特に酸素分圧(PaO2)や二酸化炭素分圧(PaCO2)などの数値が重要です。
慢性呼吸不全の場合、安静時の血液ガス分析結果を慎重にチェックし、長期的な酸素投与が必要かどうかを検討します。
代表的な疾患例
呼吸器の病気を中心に在宅酸素療法の適応が考えられます。代表的な疾患は以下の通りです。
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 間質性肺炎
- 進行期の気管支喘息
- 拘束性肺疾患(肺線維症など)
- 重症の心不全に伴う低酸素血症
これらの疾患に該当する場合、医師が血液検査や画像検査、呼吸機能検査を経て在宅酸素療法の必要性を検討します。
診断から治療方針決定までの流れ
医師が初診などで患者さんの呼吸状態を確認し、以下のような手順で治療方針を決めることが多いです。
- 症状の聞き取りと過去の治療歴の確認
- 血液ガス分析・呼吸機能検査などの検査実施
- 他の治療法(薬物療法・リハビリなど)の効果も含めた総合的な評価
- 在宅酸素療法の導入が適当かどうかの判断
- 患者さんや家族への説明と同意の取得
このような形で医師が判断し、患者さん自身にも納得していただいたうえでHOT導入へと進んでいきます。
呼吸状態の判定目安
| 指標 | 重症度の目安 | コメント |
|---|---|---|
| PaO2(動脈血酸素分圧) | 60Torr以下で慢性呼吸不全の可能性が高い | 安静時測定が大切 |
| PaCO2(動脈血二酸化炭素分圧) | 45Torr以上で呼吸不全傾向が見られる | 呼吸不全のタイプ分類に活用 |
| SpO2(経皮的酸素飽和度) | 90%未満で低酸素血症が疑われる | 容易に測定できるが正確性には限界がある |
患者さんの症状や検査結果を総合的に判断し、在宅酸素療法の適応かどうかを見極めます。
HOT導入の基準と判断のポイント
医師がHOTを導入するかどうかを判断する際のポイントには呼吸状態の客観的評価に加え、患者さんの生活背景や本人の希望も含まれます。
ここでは具体的なHOT導入の基準と導入を決めるときの重要な視点を紹介します。
HOTの適応を左右する要素
HOT導入を決めるとき、以下の要素が重要となります。
- 安静時の血液ガス分析でPaO2が55Torr以下(または60Torr付近で合併症あり)
- 心不全や肺高血圧症などの合併症の有無
- 既存の治療(吸入薬、リハビリなど)で改善が見られない場合
- 症状が進行しており、在宅での酸素補給が必要な場合
医師は上記のようなデータや病歴をもとに、患者さんと話し合いを進めます。
在宅酸素療法の適応と患者さんの生活環境
身体的な状態が在宅酸素療法に当てはまっても、実際に生活を維持していくうえでどのような課題があるかを考える必要があります。
例えば自宅で機器を設置可能か、階段の上り下りが多い住宅かどうか、家族や介護者のサポート状況など多面的に考慮します。
HOT導入のための医療保険上の条件
在宅酸素療法は医療保険の適用があり、一定の基準を満たすと保険診療で治療を受けられます。
具体的には、慢性呼吸不全で安静時PaO2が55Torr以下など、学会が定めている条件を満たす必要があります。
医師は患者さんの検査結果を踏まえ、保険適用の可否を確認します。
導入を決めるときの流れ
医師は血液ガスデータや画像診断を総合的に見て、患者さんの今後の生活環境も考慮しながらHOT導入の基準を満たすかどうかを判断します。
その際、患者さんにも導入後の生活を具体的にイメージしてもらい、自宅での過ごし方や外出の仕方などについて説明を行います。
HOT導入基準の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| PaO2の数値 | 安静時55Torr以下(または60Torr付近で合併症あり) |
| 合併症の有無 | 心不全・肺高血圧症・睡眠時無呼吸症候群など |
| 既存治療による改善度 | 薬物療法やリハビリで十分な効果が得られない |
| 生活環境・サポート体制 | 機器設置の可否、家族の協力、在宅ケアサービス |
| 患者さん本人の意向 | 日常生活への取り込み意欲や理解 |
医師は上記のような基準を総合的に評価し、在宅酸素療法に踏み切ります。
HOT導入を検討する上での注意点
HOT導入が決まった後、いざ生活に組み込むとなるといくつかの注意点があります。酸素供給機器を設置し、外出する際の携帯用酸素についてもよく理解する必要があります。
ここではHOT導入を検討する際に把握しておきたいポイントを取り上げます。
日常生活の変化
在宅酸素療法を始めると、どのように生活スタイルが変化するのか気にされる方が多いです。
例えば以下の場面で注意が必要です。
- 入浴時の酸素吸入
- 就寝時の酸素配管
- 台所など火気を使用する場所での酸素濃縮器の取り扱い
- 携帯用酸素ボンベの持ち運び
日常的に酸素チューブを身につけることに慣れるまで最初は戸惑う場合があります。
しかし医師や看護師から適切な指導を受けることで徐々に負担を減らせることが多いです。
在宅酸素療法で日々気をつけたいこと
- 酸素濃縮器やボンベを火気の近くに置かない
- 酸素チューブの引っかかりに注意して室内を整頓する
- 結露や湿度に配慮して機器を適切に管理する
- 電源コードの配線を安全に確保する
衛生面と機器管理
酸素チューブなどの器具は定期的に清潔に保つ必要があります。
鼻用カニューレやマスクなどを清掃せずに使い続けると、感染症や肌トラブルを起こすことがあります。医療機関から提供される使用方法マニュアルや看護師の指導を守り、管理を徹底しましょう。
安全性と火気の取り扱い
在宅酸素療法で使う機器は高濃度の酸素を扱うため火気に気をつけなければなりません。特にガスコンロやストーブなどの火元から距離を保ち、喫煙は絶対に避ける必要があります。
家族や同居の方にも十分注意を促し、安全対策を確実に行うことが大切です。
外出時の工夫
在宅酸素療法を導入している方でも医師が許可すれば外出や旅行が可能になる場合があります。
携帯用酸素ボンベや携帯型酸素濃縮器を活用することで、ある程度の活動範囲を確保できます。
ただし、移動距離や外出時間などをあらかじめ医師と相談しておくことが望ましいです。
外出時に携行する酸素機器比較
| 機器種別 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 携帯用酸素ボンベ | 電源不要で短時間の利用が可能 | 長時間の連続使用には向かない |
| 携帯型酸素濃縮器 | バッテリー式で一定時間使用可 | 重量やバッテリー寿命に注意が必要 |
外出の範囲や目的に合わせて機器を選び、充電やボンベの残量管理をしっかり行うよう心がけましょう。
在宅酸素療法に使用する機器の種類と特徴
HOT導入が決まると、次は実際にどのような機器を使用するかを検討します。
機器の選択は患者さんの病状や生活スタイル、住宅事情など多角的に考える必要があります。
酸素濃縮器の仕組みと利点
酸素濃縮器は周囲の空気から酸素だけを取り出して供給する装置です。主に電源を使用し、連続して酸素を作り出せるため安定した酸素吸入が行えます。
長期的に使用する場合、ボンベ交換の手間がかからない点が支持されています。ただし電源を要するため、停電時の対策を検討することが必要です。
液体酸素装置の特徴
液体酸素装置はタンクに液体酸素を貯蔵しておき、必要に応じて気化させながら酸素を吸入します。
携帯用タンクに注ぎ足すことができるため、ボンベよりも軽量かつ外出時の酸素確保が容易になるメリットがあります。
ただし、液体酸素タンクを安定して保管できるスペースや定期的に補充を受ける体制が求められます。
酸素ボンベを利用する場合
酸素ボンベは高圧で酸素が詰められており、電源を必要としません。
比較的簡単な構造で利用しやすい反面、ボンベが空になれば交換が必要です。ボンベの残量を常に意識して管理し、複数本を用意しておくなどの対策が必要になります。
携帯型酸素濃縮器の登場
近年では自宅内だけでなく外出先でも酸素吸入を行う方のために携帯型酸素濃縮器が活用されます。
バッテリーが内蔵されているため、持ち運びが可能です。移動が多い方やアクティブに外出したい方にとって、取り入れやすい選択肢といえます。
在宅酸素療法における機器選択リスト
- 酸素濃縮器:長時間の連続使用に適する
- 液体酸素装置:携帯タンクへの補充が可能
- 酸素ボンベ:電源不要だが交換頻度に留意
- 携帯型酸素濃縮器:外出や旅行に便利
機器選択と導入後のフォローアップ
機器を選んだら、それで終わりというわけではありません。安定した呼吸状態を保つためには導入後のフォローアップが非常に重要です。
ここでは機器選択の流れと導入後の定期受診やメンテナンスについて解説します。
患者さんの生活スタイルを考慮した機器選択
医師や臨床工学技士、看護師などがチームを組み、患者さんの生活習慣や住宅環境、家族構成などを踏まえて最適な機器を提案します。
例えば一人暮らしの方であれば、定期的に訪問サポートを受けやすいシステムかどうかも考慮します。
外出の頻度が高い方には携帯型の機器を主体に検討するなど患者さんがなるべく自立した生活を送れるように調整します。
導入直後の指導と説明
機器導入直後は患者さんに対して酸素吸入の方法や流量調整の仕方、火気や衛生面の注意点などを具体的に説明します。取扱説明書だけでなく、看護師や業者による実地指導が伴うことが多いです。
患者さんやご家族も最初は戸惑うことがあるため、わからないことはその都度確認することが大切です。
HOT導入時の導入・説明プラン例
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 導入前 | 検査結果の説明、機器選択の話し合い、保険適用の確認 |
| 導入当日 | 機器の設置、流量設定方法の説明、火気の注意点、酸素チューブの装着法 |
| 導入後1週間程度 | 電話相談や訪問看護による状態確認、必要に応じて流量調整 |
| 導入後1か月程度 | 医療機関での定期受診、機器トラブルの確認、QOLの評価 |
定期受診と在宅支援
在宅酸素療法を導入した後は定期的に外来受診を行い血液ガス分析やSpO2測定によって治療効果をチェックします。
同時に生活上の不便や機器の不具合がないかを確認し、必要に応じて医師が流量や薬物療法を見直します。
地域の訪問看護師や訪問診療医などと連携し、適切なサポートを続ける体制を整えます。
生活面でのフォローアップ
患者さんの体調や生活リズムに応じて訪問看護や訪問リハビリ、デイケアなどが利用できます。
在宅酸素療法で酸素を補給しながらでも社会活動や趣味を続ける方は少なくありません。
必要に応じて自治体の支援サービスや介護保険制度と連携し、サポートを受けながら生活の質を維持していくことが望まれます。
在宅酸素療法と生活の質
HOTを導入しても患者さんの生活が大きく制限されるわけではありません。むしろ十分な酸素供給によって活動量が増えたり体力が向上したりする可能性があります。
ここでは在宅酸素療法と生活の質の関係について解説します。
酸素療法が体にもたらす効果
慢性的な低酸素状態が改善すると全身の臓器への酸素供給が良くなり、疲労感や倦怠感が軽減しやすくなります。
肺だけでなく、心臓や脳への負担を緩和できることで日常生活動作がスムーズになる場合があります。結果として活動量が増え、筋力の維持につながるケースもあります。
呼吸リハビリとの併用
前述した呼吸リハビリテーションと併用することで、さらに効果を高められることが多いです。酸素を吸入しながら体を動かすことで、呼吸苦を感じにくくなり、トレーニングの継続が容易になります。医師や理学療法士と連携し、無理のない範囲で徐々に運動量を増やすことが大切です。
外出や社会参加
酸素ボンベや携帯型酸素濃縮器を利用すれば、通院だけでなく買い物や趣味の外出など幅広い活動ができるようになります。酸素療法を始めたからといって外出をあきらめる必要はありません。
適度に身体を動かし、気分転換をはかることが健康の維持に役立ちます。
在宅酸素療法によるQOL向上例
| 変化する側面 | 具体的な改善例 |
|---|---|
| 身体的な負担の軽減 | 疲労感の軽減、呼吸苦の軽減 |
| 精神的な安定 | 不安感や抑うつ傾向の緩和 |
| 活動量の増加 | 家事や趣味、外出の機会が増える |
| 社会的なつながり再構築 | 友人や家族との交流、地域活動への参加がしやすい |
在宅酸素療法は適切に活用すれば、生活の質を向上させる有力な選択肢になり得ます。
当院での在宅酸素療法の取り組みと受診の流れ
最後に、当院での在宅酸素療法に対する取り組みと、受診から導入に至るまでの大まかな流れをご紹介します。
患者さんが安心して治療を受けられるよう、多職種連携や情報共有を行っています。
受診から診断までの流れ
当院では初診時に呼吸器症状の有無や既往歴を丁寧に確認し、必要な検査をスピーディに実施します。
検査結果をもとに診断を行い、在宅酸素療法の適応があるかどうかを判断します。
導入の可能性がある方に対しては、保険適用の説明も含めてわかりやすくお伝えします。
HOT導入に向けたサポート体制
呼吸器内科医を中心に、臨床工学技士や看護師、ソーシャルワーカーが連携しながら患者さんをサポートします。
自宅での機器設置に不安がある場合は業者や訪問看護師と連絡を取り合い、スムーズに導入できるよう調整します。
患者さんの生活環境を把握し、必要ならケアマネジャーとも連携し、介護保険制度の活用も検討します。
定期的なモニタリング
在宅酸素療法を導入した後は適切な酸素濃度が保たれているかどうか定期的に確認します。外来受診時に血液ガス分析や呼吸機能検査を行い、必要に応じて流量の再調整を行います。
機器トラブルが疑われる場合は早めに相談し、不具合を解消します。
患者さんとの情報共有
当院では外来受診のタイミングで日常生活の様子や困りごとを詳しく伺います。医師や看護師だけでなく、臨床工学技士や業者も相談に応じます。
患者さんとのやり取りを重ね、よりよいHOT導入の維持を目指しています。
当院のHOT導入支援体制
| 担当スタッフ | 主な役割 |
|---|---|
| 呼吸器内科医 | 診断、治療方針の決定、処方、保険適用手続き |
| 臨床工学技士 | 機器選定、操作説明、定期点検 |
| 看護師 | 日常生活の指導、創傷ケア、定期的な状態確認 |
| ソーシャルワーカー | 保険制度や介護保険利用の調整、在宅サービスとの連携 |
| 訪問看護師 | 自宅での状態確認、機器の確認、衛生管理 |
| 酸素供給業者 | 機器の設置・点検、トラブル時のサポート |
各職種の連携で患者さんの負担を軽減しながら在宅酸素療法を継続できるよう工夫を凝らしています。
以上
HOT(在宅酸素療法)を知ろう
参考にした論文
KIDA, Kozui, et al. Long-term oxygen therapy in Japan: history, present status, and current problems. Advances in Respiratory Medicine, 2013, 81.5: 468-478.
RINGBAEK, Thomas Joergen. Home oxygen therapy in COPD patients. Danish medical bulletin, 2006, 53.3: 310-325.
SATAKE, Hiroyuki, et al. Effect of Respiratory Therapy on the Prognosis of Chronic Heart Failure Patients Complicated With Sleep-Disordered Breathing–A Pilot Efficacy Trial–. Circulation Journal, 2015, 80.1: 130-138.
MIYASAKA, Katsuyuki, et al. Tribute to Dr. Takuo Aoyagi, inventor of pulse oximetry. Journal of anesthesia, 2021, 35: 671-709.
OHUCHI, Hideo, et al. JCS 2022 guideline on management and re-interventional therapy in patients with congenital heart disease long-term after initial repair. Circulation Journal, 2022, 86.10: 1591-1690.
KACMAREK, Robert M.; STOLLER, James K.; HEUER, Al. Egan’s fundamentals of respiratory Care-E-book. Elsevier Health Sciences, 2016.
NAKANISHI, Hidehiko, et al. Persistent pulmonary hypertension of the newborn in extremely preterm infants: a Japanese cohort study. Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition, 2018, 103.6: F554-F561.
KREUTER, Michael, et al. Palliative care in interstitial lung disease: living well. The lancet respiratory medicine, 2017, 5.12: 968-980.
PIERSON, David J. Clinical practice guidelines for chronic obstructive pulmonary disease: a review and comparison of current resources. Respiratory care, 2006, 51.3: 277-288.