高齢のご家族が肺炎と診断され、「酸素吸入が必要です」と説明されると、多くの方が不安に感じるでしょう。
肺炎は高齢者にとって重症化しやすい病気であり、体内の酸素濃度が低下することが少なくありません。
この記事ではなぜ高齢者の肺炎で酸素吸入が必要になるのか、正常な酸素濃度はどのくらいなのか、そしてどのような場合に在宅酸素療法(HOT)へ移行するのか、その基準や注意点を分かりやすく解説します。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。
なぜ高齢者は肺炎で酸素不足に陥りやすいのか
高齢になると若い頃に比べて肺炎にかかりやすく、また重症化しやすい傾向があります。その背景には加齢に伴う身体の変化や他の病気の影響が関係しています。
加齢による呼吸機能の低下
年齢を重ねると肺の弾力性が失われたり、呼吸に関わる筋肉が衰えたりして肺活量が減少します。また、咳をして痰を体外に排出する力も弱まります。
これらの呼吸機能の低下により、ウイルスや細菌が肺に入り込んだ際に効率よく酸素を取り込み、二酸化炭素を排出することが難しくなります。
加齢に伴う呼吸器の変化
| 変化する部分 | 具体的な変化の内容 | 影響 |
|---|---|---|
| 肺組織 | 弾力性の低下、肺胞の減少 | ガス交換の効率が低下する |
| 呼吸筋 | 筋力の低下 | 深く呼吸したり、強く咳をしたりできない |
| 胸郭 | 可動域の減少 | 肺が十分に膨らみにくくなる |
誤嚥(ごえん)性肺炎のリスク
高齢者では食べ物や唾液が誤って気管に入ってしまう「誤嚥」が起こりやすくなります。これは飲み込む力(嚥下機能)や咳で異物を排出する反射機能が低下するために起こります。
誤嚥によって細菌が唾液などと一緒に肺へ流れ込むと誤嚥性肺炎を発症します。このタイプの肺炎は繰り返しやすいという特徴があります。
肺炎が引き起こす肺の炎症
肺炎になると肺の中で細菌やウイルスが増殖し、炎症が起こります。炎症が起きた肺胞(酸素と二酸化炭素の交換を行う小さな袋)には体液や膿が溜まります。
この状態では肺が正常に機能できなくなり、血液中に十分な酸素を取り込めない「低酸素血症」という状態に陥ります。
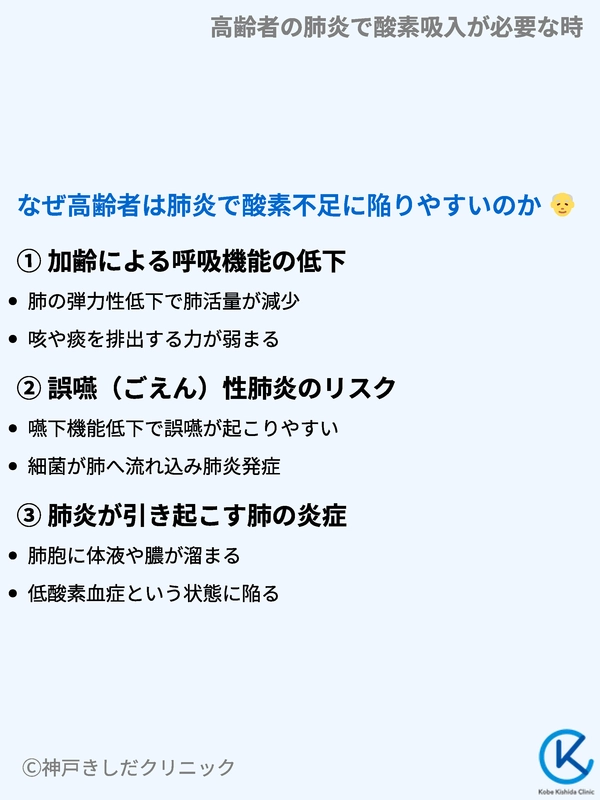
高齢者の正常な酸素飽和度(SpO2)と目標値
肺炎の治療ではパルスオキシメーターという機器で「酸素飽和度(SpO2)」を測定し、体内の酸素状態を把握します。この数値は治療方針を決める上で重要な指標となります。
酸素飽和度(SpO2)とは何か
酸素飽和度(SpO2)とは、血液中のヘモグロビンのうち、何パーセントが酸素と結合しているかを示した数値です。
指先に光を当てることで簡単に測定でき、全身にどれだけ酸素が供給されているかの目安になります。
健康な高齢者の正常値の目安
一般的に健康な人のSpO2の正常値は96%以上とされています。高齢者の場合、慢性的な呼吸器疾患がない限り、この値が基準となります。
ただし個人差もあるため、普段の数値を把握しておくことも大切です。
酸素飽和度(SpO2)の一般的な目安
| SpO2の値 | 身体の状態 | 考えられる対応 |
|---|---|---|
| 96%以上 | 正常 | 特に問題なし |
| 91~95% | 軽度の低下(準正常) | 安静を保ち、経過観察 |
| 90%以下 | 呼吸不全 | 酸素吸入などの治療が必要 |
肺炎治療における酸素飽和度の目標
肺炎入院患者では、安全域にSpO2を維持することが目標です。
多くの急性期患者では94~98%、高二酸化炭素血症リスクがある場合は88~92%程度を目安に酸素投与量が調整されます。
このように、患者さんの元々の呼吸機能や心臓の状態などを考慮して個別に目標値を設定します。
必ずしも100%を目指すわけではなく、安全な範囲で酸素濃度を維持することが重要です。
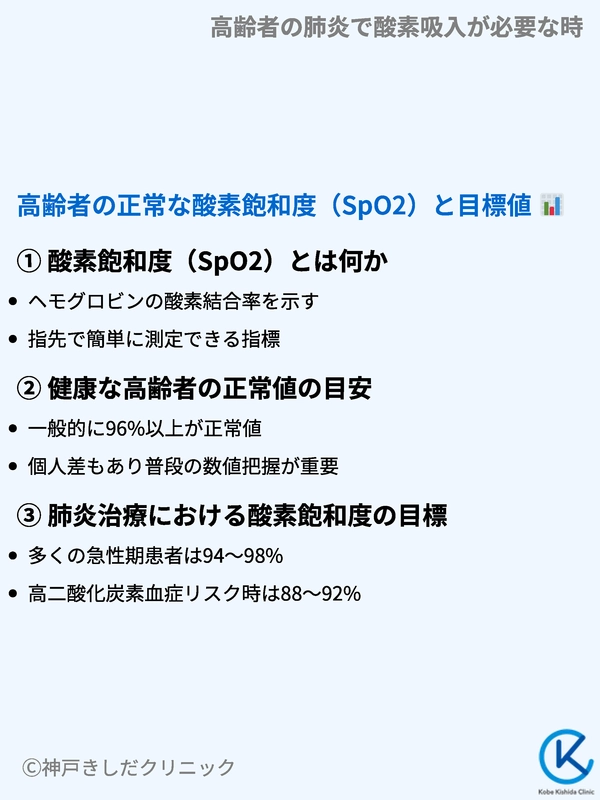
肺炎治療における酸素吸入の役割
SpO2が低下した場合、酸素吸入を開始します。酸素吸入は肺炎でダメージを受けた肺の働きを助け、身体を守るために欠かせない治療です。
低酸素血症の改善と臓器の保護
酸素吸入の最も重要な目的は低酸素血症を改善することです。体内の酸素不足が続くと、心臓や脳、腎臓といった重要な臓器に大きな負担がかかり、機能不全に陥る危険があります。
高濃度の酸素を供給することで血中の酸素濃度を保ち、これらの臓器を保護します。
呼吸困難感の緩和
酸素が不足すると身体はそれを補おうとして呼吸が速く、浅くなります。この状態は患者さんにとって非常に苦しいものです。
酸素を吸入すると呼吸が楽になり、息苦しさ(呼吸困難感)が和らぎます。このことにより体力の消耗を防ぎ、治療に専念しやすくなります。
酸素マスクと鼻カニューラの違い
酸素吸入には主に鼻カニューラと酸素マスクという2種類の器具を使います。どちらを使用するかは患者さんの状態や必要な酸素の量によって医師が判断します。
- 鼻カニューラ:鼻の穴にチューブを挿入するタイプ。会話や食事がしやすい。
- 酸素マスク:鼻と口を覆うタイプ。より高濃度の酸素を安定して供給できる。
酸素投与器具の選択
| 器具の種類 | 特徴 | 適した状態 |
|---|---|---|
| 鼻カニューラ | 装着の負担が少ない。食事や会話が可能。 | 比較的軽度の低酸素血症の場合 |
| 酸素マスク | 高濃度の酸素を安定供給できる。 | 中等度以上の低酸素血症の場合 |
| リザーバー付きマスク | さらに高濃度の酸素を供給できる。 | 重度の低酸素血症の場合 |
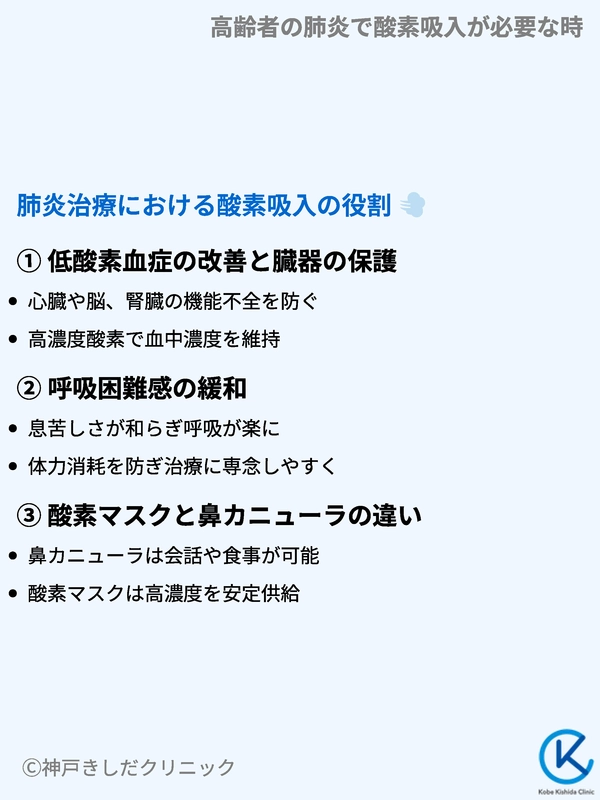
酸素吸入が必要になる具体的な基準
どのような状態になったら酸素吸入が始まるのでしょうか。判断はいくつかの客観的な指標に基づいて行います。
血中酸素飽和度(SpO2)による判断
最も重要な基準は血中酸素飽和度(SpO2)です。一般的に安静にしている状態でSpO2が90%を下回る場合、酸素吸入の適応となります。
これは身体が深刻な酸素不足の状態にあることを示しています。
呼吸の状態(呼吸回数や努力呼吸)
SpO2の数値だけでなく、呼吸の状態も重要な判断材料です。
呼吸回数が異常に多い(1分間に25回以上など)、肩で息をする(努力呼吸)、鼻翼をひくひくさせる(鼻翼呼吸)といったサインは身体が必死に酸素を取り込もうとしている証拠であり、酸素吸入を検討するきっかけになります。
意識状態の変化
酸素不足は脳の機能にも影響を与えます。
ぼんやりしている、呼びかけへの反応が鈍い、興奮して落ち着きがないなど、意識状態に変化が見られる場合も重度の低酸素血症が疑われ、速やかな酸素投与が必要です。
酸素吸入開始を判断するサイン
| 指標 | 具体的な基準・サイン | 意味すること |
|---|---|---|
| 酸素飽和度 | SpO2が90%以下 | 明らかな低酸素血症 |
| 呼吸状態 | 呼吸回数の増加、努力呼吸 | 身体が酸素を欲している状態 |
| 意識レベル | 傾眠、混乱、興奮 | 脳への酸素供給が不足している可能性 |
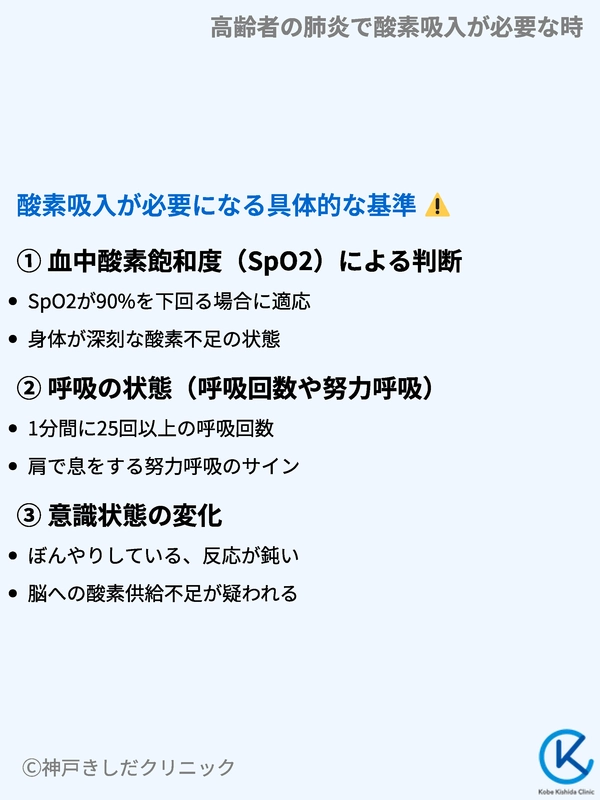
入院治療から在宅酸素療法(HOT)への移行
肺炎の急性期の治療が終わり、病状が安定しても肺の機能が完全には回復せず、酸素吸入が必要な状態が続くことがあります。
その場合、退院後もご自宅で酸素療法を続ける「在宅酸素療法(HOT)」へ移行します。
なぜ在宅酸素療法が必要になるのか
肺炎によって肺に受けたダメージが大きい場合や、元々COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの呼吸器疾患がある場合、退院後も慢性的な酸素不足の状態が続くことがあります。
在宅酸素療法はこのような方が息切れをせずに安定した日常生活を送り、社会復帰を目指すために行います。
在宅酸素療法へ移行する基準
在宅酸素療法への移行は定められた基準に基づいて慎重に判断します。
基本的には安静時の動脈血酸素分圧(PaO2)が60mmHg以下、または安静時のSpO2が90%以下といった状態が続く場合に適応となります。
在宅酸素療法(HOT)の主な導入基準
| 測定項目 | 基準値 | 補足 |
|---|---|---|
| 動脈血酸素分圧 (PaO2) | 55mmHg以下 | 重度の低酸素血症がある場合 |
| 動脈血酸素分圧 (PaO2) | 60mmHg以下 | 睡眠時や運動時に著しい低酸素血症がある場合 |
| 酸素飽和度 (SpO2) | 90%以下 | PaO2が60mmHg以下に相当する目安 |
退院に向けた準備と指導
在宅酸素療法への移行が決まると、入院中に患者さんとご家族を対象に機器の操作方法や日常生活での注意点について指導を行います。
安心して在宅療養を開始できるよう、医療スタッフがサポートします。
- 酸素濃縮器などの機器の取り扱い
- 火気の管理と安全対策
- 緊急時の連絡方法の確認
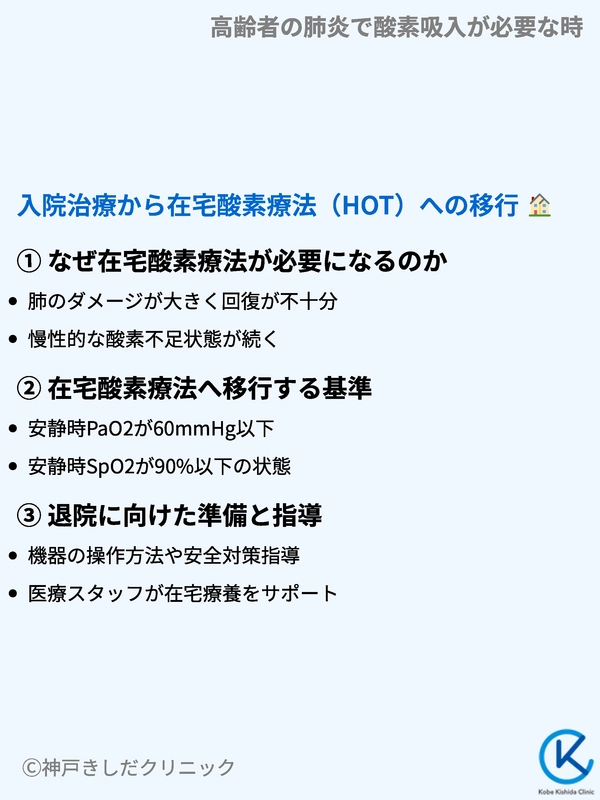
よくある質問(FAQ)
最後に高齢者の肺炎と酸素吸入に関してよくある質問にお答えします。
- Q肺炎が治れば酸素吸入は不要になりますか?
- A
肺炎自体が治癒すれば酸素吸入が必要なくなるケースも多くあります。
しかし肺炎をきっかけに呼吸機能の低下が顕著になり、慢性的な酸素不足が残ってしまうことも少なくありません。その場合は継続して在宅酸素療法が必要になります。
最終的な判断は退院前の検査結果などを見て主治医が行います。
- Q酸素マスクを着けていると話しにくいのですが。
- A
酸素マスクは口と鼻を覆うため、確かに会話や食事がしにくいという不便さがあります。
状態が安定し、必要な酸素量が少なくなれば鼻にチューブを入れる鼻カニューラに変更できる場合があります。変更が可能かどうかは主治医や看護師にご相談ください。
- Q家族として気をつけることは何ですか?
- A
ご家族のサポートは非常に重要です。特に患者さんの呼吸状態(息が苦しそうでないか)や酸素飽和度の変化に気を配ることが大切です。
また、在宅酸素療法に移行した場合は火気の管理を徹底し、機器の周りに燃えやすいものを置かないよう協力してください。
- Q夜だけ酸素濃度が下がるのはなぜですか?
- A
睡眠中は呼吸をコントロールする中枢の働きが低下するため、誰でも呼吸が浅くなりがちです。
呼吸機能が低下している高齢者ではこの影響がより顕著に現れ、睡眠中に酸素濃度が低下することがあります。
このため日中は酸素が不要でも、夜間のみ酸素吸入が必要になるケースがあります。
以上
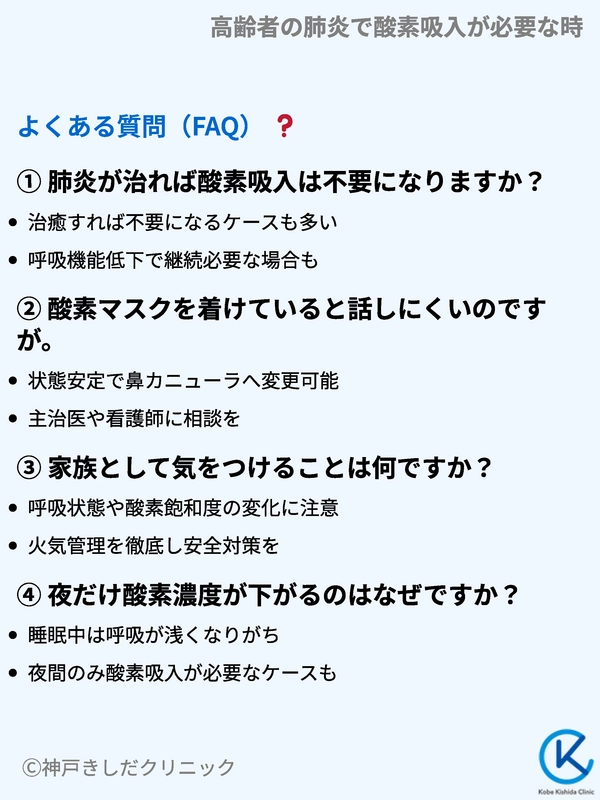
参考にした論文
YATERA, Kazuhiro; YAMASAKI, Kei. Management of the Diagnosis and Treatment of Pneumonia in an Aging Society. Internal Medicine, 2025, 64.4: 503-517.
MORIMOTO, Konosuke, et al. The burden and etiology of community-onset pneumonia in the aging Japanese population: a multicenter prospective study. PLoS One, 2015, 10.3: e0122247.
MIYASHITA, Naoyuki; MATSUSHIMA, Toshiharu; OKA, Mikio. The JRS guidelines for the management of community-acquired pneumonia in adults: an update and new recommendations. Internal Medicine, 2006, 45.7: 419-428.
YOSHIMATSU, Yuki, et al. “Diagnose, Treat, and SUPPORT”. Clinical competencies in the management of older adults with aspiration pneumonia: a scoping review. European Geriatric Medicine, 2024, 15.1: 57-66.
KOMIYA, Kosaku; YAMATANI, Izumi; KADOTA, Jun-ichi. Treatment strategy for older patients with pneumonia independent of the risk of drug resistance in the world’s top country for longevity. Respiratory Investigation, 2024, 62.4: 710-716.
SEKI, Masafumi, et al. Revision of the severity rating and classification of hospital‐acquired pneumonia in the Japanese Respiratory Society guidelines. Respirology, 2008, 13.6: 880-885.
SHINKAI, Masaharu, et al. Efficacy and safety of favipiravir in moderate COVID-19 pneumonia patients without oxygen therapy: a randomized, phase III clinical trial. Infectious diseases and therapy, 2021, 10.4: 2489-2509.
IGARI, Hidetoshi, et al. Epidemiology and treatment outcome of pneumonia: Analysis based on Japan national database. Journal of Infection and Chemotherapy, 2020, 26.1: 58-62.
KIDA, Kozui, et al. Long-term oxygen therapy in Japan: history, present status, and current problems. Advances in Respiratory Medicine, 2013, 81.5: 468-478.
KODAMA, Tatsuya, et al. Prediction of an increase in oxygen requirement of SARS-CoV-2 pneumonia using three different scoring systems. Journal of Infection and Chemotherapy, 2021, 27.2: 336-341.



