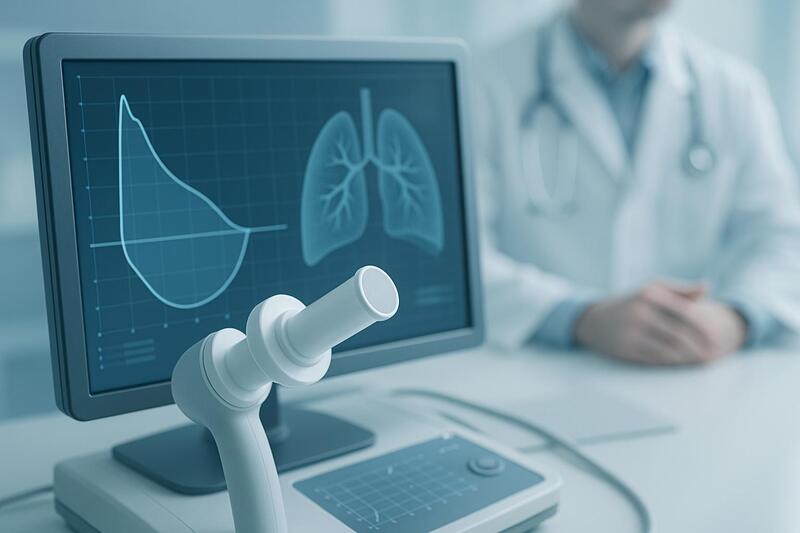呼吸の状態を調べる呼吸機能検査は喘息などの呼吸器疾患を早期に発見し、適切な対応につなげるうえで重要です。
息苦しさの原因がはっきりしない場合や咳が長引く場合にも有効な情報を提供し、治療方針を定める目安になります。
呼吸機能検査を正しく理解すると検査へ臨む際の心配が軽減され、病状の変化を客観的に知るきっかけにもなります。
この記事では呼吸機能検査の種類や目的、喘息診断の要点を詳しく紹介します。クリニックを受診しようか迷っている方や今後呼吸器内科で検査を検討している方にも役立つ情報をまとめています。
呼吸機能検査とは何か
呼吸機能検査は肺がどれだけ空気を取り込んだり吐き出したりできるかを評価するために行う一連の評価方法です。検査内容を把握すると肺の働きをより正確に理解できます。
喘息などの慢性呼吸器疾患の疑いがある場合だけでなく、症状が軽微でも繰り返す咳や息苦しさがあるときに検討することが多いです。
ここでは呼吸機能検査の概要を解説します。
呼吸機能検査の特徴
- 肺活量や換気能力を数値で確認できる
- 喘息などの病気の有無を客観的に判断しやすい
- 診断だけでなく治療効果の評価にも役立つ
これらの検査で肺や気道の状態を数値化すると適切な治療方針を検討しやすくなります。また、症状の原因を絞り込むうえでも重要です。
呼吸機能検査における主な評価指標
| 指標 | 内容 |
|---|---|
| 予測肺活量 | 年齢・身長・性別から導き出す理想的な肺活量 |
| 実測肺活量 | 実際に測定した肺活量 |
| 1秒量(FEV1) | 1秒間に吐き出せる最大の空気量 |
| 1秒率(FEV1%) | 1秒量を努力肺活量で割った値で、気道閉塞の度合いを把握しやすい |
| ピークフロー(PEF) | 勢いよく吐き出すときの最大呼気流量 |
呼吸機能検査が注目される背景
呼吸機能の異常は気づかないまま進行することがあります。特に日常生活での疲れやすさや軽い咳などは、単なる風邪や体力の問題とみなして放置しがちです。
しかし呼吸機能の低下がゆるやかに進むと、いつの間にか階段の昇り降りや軽い運動でも息切れを感じるようになります。
呼吸機能検査が注目されるのはこうした隠れた問題を早期に発見するきっかけになるからです。
さらに呼吸機能がどの程度低下しているかを数値化できれば診察室での説明や治療計画にも明確な根拠を持たせやすくなります。
主観的な訴えだけでなく、数値による裏付けを得ることが、より具体的な治療方針につながります。
呼気量と呼吸の深さを測る意味
呼吸は体内の酸素と二酸化炭素を交換するうえで重要です。吸い込む量と吐き出す量のバランスが崩れると全身の代謝や体力に影響を及ぼす可能性があります。
呼気量が十分であれば痰や不要なガスを効率よく排出できるため、気道の炎症も起こりにくくなります。
一方、息を深く吸うことが難しい状態が続くと肺の伸縮が妨げられ、慢性的な呼吸器トラブルを引き起こしやすいです。
呼吸機能検査はこれらの要素を数値化し、深呼吸の容量や素早く息を吐き出せるかどうかといった点を客観的に評価します。
この結果をもとに単なる体力不足なのか、それとも喘息などの異常が潜んでいるのかを区別しやすくなります。
病態の早期発見と生活改善
検査結果を活用すると初期段階で症状をとらえて必要な治療を始められます。例えば軽度の呼吸機能低下であれば、薬物療法とあわせて生活習慣を見直すだけで改善を期待できることがあります。
運動不足や肥満が影響しているケースもあるため、日常の過ごし方を変えるだけでも呼吸が楽になる可能性があります。
また、呼吸機能が正常であっても、検査によって自分の肺活量や呼気の勢いを知ることで日々の健康管理に役立てる方もいます。
定期的に検査を受けると数値の推移を見比べて呼吸器の衰えや肺の変化を捉えやすくなり、症状がなくても早い段階から対策に取り組むことができます。
喘息と呼吸機能検査の重要性
喘息は気道の炎症と過敏性が特徴の慢性疾患で、適切に管理しないと発作を繰り返し、生活の質を大きく損なう恐れがあります。
呼吸機能検査は気道がどの程度狭まっているかを把握するうえで重要な手段です。
息切れや咳だけでは他の呼吸器疾患と区別しにくい場合もあります。喘息を正確に見極めるために、呼吸機能検査で得られるデータは大切です。
ここからは喘息と呼吸機能検査の関係をみていきましょう。
喘息を疑うポイント
- 夜間や早朝に咳が出やすい
- 運動後に息苦しさや呼気がしづらくなる
- 季節の変わり目に喘鳴を感じる
これらの症状を一時的なものと考える方も多いですが、実際には気道に慢性的な炎症が起きている可能性があります。
呼吸機能のデータを客観的に確認することで喘息なのか別の原因があるのかを絞り込みやすくなります。
喘息と呼吸機能検査の関連指標
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 気道過敏性 | 刺激に対して気道が狭くなりやすい度合い |
| 可逆性の評価 | 気管支拡張薬投与後にFEV1などの数値がどの程度変化するか |
| ピークフロー変動 | 日々のピークフロー値の変動幅が大きいほど、気道の不安定性が高い可能性 |
| 呼気中一酸化窒素 | 気道炎症の指標となるが、継続的な測定が必要な場合もある |
喘息発作のリスク評価
喘息発作は急激に気道が狭くなって呼吸困難を引き起こす状態です。呼吸機能検査で1秒率やピークフロー値を確認すると気道の閉塞具合を具体的な数字で把握できます。
数値が低いほど発作のリスクが高まる可能性があるので、医師は早めの治療を提案しやすくなります。
また、発作を起こしやすい時期や条件を見つけるために自己測定器を使って日々のピークフローを記録する方法もあります。
この情報をもとに気温の変化やアレルゲンの存在など、発作を誘発しやすい要因への対策を取りやすくなります。
治療の効果判定
吸入ステロイドや気管支拡張薬を使用した際、呼吸機能がどの程度改善するかをチェックすると治療の方向性を判断しやすくなります。
治療開始前と比較して1秒量(FEV1)が明らかに増加すれば、処方薬が十分に機能していると考えられます。
逆に改善が乏しい場合は薬の種類や使用方法の変更、別の検査を検討するといった選択肢に進みます。
自覚症状だけでは捉えにくい細かな変化も数値化することで把握が容易になる点が呼吸機能検査の大きなメリットです。
患者さん自身も検査結果の推移を見ることで治療意欲が高まる傾向があります。
早期診断と生活指導
喘息は慢性的な疾患であり、治療とともに生活改善が大切です。呼吸機能検査の結果によっては発作を起こしやすい状況や活動レベルが明確になるため、適度な運動と休息のバランスを考えやすくなります。
さらに、喫煙や受動喫煙が気道に与える影響を数値で説明できるため、禁煙に踏み切るきっかけにする人も多いです。
早期診断と継続的な治療計画のもとで重症化を防ぎながら仕事や学校生活を続けやすくなります。
基本的な呼吸機能検査の種類と目的
呼吸機能検査には実施の方法や測定する指標によってさまざまな種類があります。それぞれが異なる角度から肺の状態を捉え、総合的な評価につなげます。
ここでは代表的な検査について説明します。
検査の実施で得られる主なメリット
- 肺の総合的な状態を多角的に評価できる
- 病態に応じた治療方針を選択しやすくなる
- 経時的な変化を捉えやすくなる
これらのメリットを活かすには検査前に禁煙や十分な休息を心がけるなど、検査精度を高める準備も大切です。
複数の検査を組み合わせると肺の働きをより正確に把握しやすくなります。
主な呼吸機能検査と目的
| 検査名 | 目的 |
|---|---|
| スパイロメトリー | 肺活量や1秒量など、基本的な呼吸指標を測定する |
| ピークフロー | 日々の最大呼気流量を記録し、変動をチェックする |
| 肺拡散能力検査 | 酸素と二酸化炭素の交換能力を把握し、肺胞の状態を見る |
| ガス分析 | 血中の酸素・二酸化炭素濃度を測定し、呼吸不全の程度を検討する |
スパイロメトリーとは
スパイロメトリーは呼吸機能検査の中でも代表的な方法で肺活量や1秒量(FEV1)などを計測します。息を最大限に吸い込んで一気に吐き出す操作を行い、そのときの空気の流れを機械がグラフ化します。
得られた曲線から肺の容量や気道の状態を把握でき、特に気管支の狭窄を示す疾患を疑うときに有用です。
しっかりと息を吐き切る必要があるため、検査を行う側と受ける側が息を合わせることがポイントになります。
結果は年齢や性別、身長などと比較して評価し、予想値との差が大きい場合には詳細な原因を探る流れになります。
ピークフロー測定の活用法
ピークフロー値は勢いよく息を吐き出したときの最大流量を示します。
家庭でも専用の簡易測定器を用いて計測しやすく、日々の変動を記録することで喘息などの症状コントロールに役立てられます。
たとえば朝と夜にピークフローを測り、その数値をグラフ化すると気道が不安定になりやすい時間帯が見えてきます。
こうしたデータは医師との診察時にも重要な情報源となり、発作予防や薬の調節を適切に行うために活用できます。
また、運動や気候の変化などピークフロー値に影響を与える要因を探ることで、自己管理の精度を高めることが可能です。
肺拡散能力検査とガス分析
スパイロメトリーやピークフローだけではわかりにくい疾患を疑うとき、肺拡散能力検査や血液ガス分析を行います。
肺拡散能力検査は一酸化炭素などのガスを吸い込み、どれだけ効率よく血中に取り込まれるかを調べる方法です。
肺胞と血液の間でガス交換が十分に行われていないと、息切れや疲労感を感じやすくなる可能性があります。血液ガス分析では血液中の酸素分圧や二酸化炭素分圧を測り、呼吸不全の有無や程度を数値化します。
これらの検査結果をもとに、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など他の疾患との鑑別を進めるケースもあります。
追加で行う呼吸機能検査
基本的な呼吸機能検査だけでは把握しきれない場合、追加の検査を組み合わせてより詳しく分析します。
ここでは、より詳しい機能評価や特殊な条件下での検査について解説します。
追加検査を検討する背景
- 基本検査で異常がみられたが原因が特定しにくい
- 治療を行っても症状改善が乏しい
- 運動や睡眠時など、特定の条件下で症状が顕著になる
こうしたケースでは専門的な装置を使った検査や長期間の観察が有用です。
より詳細なデータを収集することで最終的な診断や治療計画の正確性を高められます。
追加の呼吸機能検査
| 検査名 | 目的 |
|---|---|
| フル肺活量測定 | 静的肺気量分画を測定し、拘束性障害か閉塞性障害かを区別しやすくする |
| 体プレスモグラフィー | 胸腔内圧を測定し、気道抵抗や残気量をより正確に評価する |
| 運動負荷試験 | 運動中の呼吸機能変化を計測し、運動誘発性の症状を確認する |
| 睡眠時ポリソムノグラフィ | 睡眠時無呼吸症候群や夜間の呼吸状態を総合的に調べる |
体プレスモグラフィーの役割
体プレスモグラフィーは密閉されたボックス内で呼吸を行い、胸腔内圧の変化を利用して肺内の残気量や気道抵抗を算出する方法です。
スパイロメトリーだけでは正確に計測しにくいパラメータを得ることができます。特に気道がどれほど抵抗を受けているかを知る際に役立ち、喘息やCOPDなど閉塞性疾患の重症度を判断する一助となります。
検査では被験者がボックスに入り、通常の呼吸や深呼吸を繰り返すため、やや窮屈に感じる方もいるかもしれませんが、短時間で終了します。
得られた数値は細やかな治療方針の設定に反映されることが多いです。
運動負荷試験でわかること
運動負荷試験は実際に運動を行ったときの呼吸機能の変化を観察するために行われます。トレッドミルや自転車エルゴメーターを使用しながら心拍数や呼吸パターン、酸素摂取量などを測定します。
安静時には問題がない場合でも、運動すると息苦しさが出現するケースがあります。
この検査で運動誘発性喘息や心肺機能の限界点を明らかにすると、運動量の調整や発作予防の方法をより的確に選択しやすくなります。
特にスポーツ選手やアクティブに生活を送りたい方にとって、自分の呼吸能力を知ることは大切です。
睡眠時ポリソムノグラフィと呼吸
夜間のいびきや呼吸停止が見られる場合、睡眠時ポリソムノグラフィが行われることがあります。
この検査は脳波、心拍、呼吸の動きなどを一晩かけて総合的に記録します。睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合や夜間の喘息悪化の有無を確認したい場合に有用です。
実際に就寝している環境に近い状態で検査を行い、酸素飽和度の変化や呼吸停止の長さなどを数値化します。
結果を踏まえて、寝具の改善や口腔内装置、持続陽圧呼吸法(CPAP)などの対策を検討すると、日中の眠気や慢性的な疲労の緩和に役立ちます。
呼吸機能検査が示唆する結果の読み解き方
検査を受けても結果の数値やグラフをどのように解釈すればいいのか戸惑う方は少なくありません。
ここでは代表的な指標の読み方と、注意すべきポイントを解説します。
結果を把握するときの主な着目点
- 予測値と実測値の差
- 1秒率の低下や変動幅
- 気道抵抗や残気量の数値
これらの指標が意味する内容を知っておくと医師の説明を理解しやすくなり、治療や生活指導にも前向きに取り組みやすくなります。
主要な指標と読み解きの例
| 指標 | 低下している場合の考えられる要因 | 上昇している場合の考えられる要因 |
|---|---|---|
| FEV1(1秒量) | 気道狭窄や閉塞性疾患 | 気管支拡張薬が良好に効いている可能性 |
| FEV1% (1秒率) | 閉塞性障害(喘息、COPDなど) | 拘束性障害の可能性(肺活量自体が低下) |
| TLC (総肺気量) | 肺線維症などによる拘束性障害 | 閉塞性疾患で肺に空気が溜まりやすい |
| DLco (肺拡散能力) | 肺胞の損傷や間質性肺炎 | 偽高値の場合は測定誤差を疑う |
数値の変動と日常生活
呼吸機能検査の数値は一定ではなく、体調や季節、ストレスなどによって変動することがあります。例えば風邪をひいた直後やアレルギー反応が強い時期には、一時的に値が下がるケースがあります。
一方、適度な運動を継続して肺活量を増やしたり、禁煙によって気道の状態が改善したりすると数値が上向く例もあります。重要なのは単発の数値よりも経時的な変化の傾向です。
過去のデータと比較して急激な変動がある場合は何らかの原因が隠れている可能性があり、早めに医療機関へ相談することが望ましいです。
検査結果からわかる疾患の方向性
検査結果を見れば、ある程度疾患の可能性を推測できます。閉塞性の異常が大きい場合は、喘息やCOPDが疑われます。拘束性の異常が目立つときは、間質性肺炎や胸郭の異常などを考慮します。ただし、あくまでも可能性の域を出ないため、最終的な診断には症状や画像所見など総合的な判断が必要になります。呼吸機能検査が示すデータを他の検査結果や問診内容と組み合わせることで、より正確な病態を把握できます。
医師への質問ポイント
結果の数値だけを聞いてもピンとこない場合は医師に以下のような質問をすると具体的なイメージがつかみやすいです。
数値の異常がどれくらいのレベルなのか、その原因と考えられる疾患は何か、今後どんな治療や検査を視野に入れればいいのかなどを尋ねると理解を深めやすいです。
医師との情報共有を密に行うことで不安を軽減しながら効果的な治療を続けられます。
検査結果を踏まえた喘息の治療と管理
喘息の治療では発作を抑えることと気道の炎症を長期的にコントロールすることが中心になります。
ここでは呼吸機能検査の結果をどのように治療に反映していくかをご紹介します。
治療計画に含まれる要素
- 吸入ステロイドや長時間作用性β2刺激薬などの薬物療法
- アレルゲン回避や室内環境の改善
- 運動療法や呼吸リハビリテーション
計画を立てる際には検査結果とともに患者の生活背景や希望も考慮します。
治療効果を検証するために、定期的な検査が推奨されるケースも多いです。
喘息治療と検査結果との関係
| 治療アプローチ | 検査結果が示す主な判断材料 |
|---|---|
| 薬物療法 (吸入ステロイド, β2刺激薬など) | FEV1の改善度合いやピークフローの変動幅 |
| 環境整備 (アレルゲン除去) | 発作の頻度やピークフローの日内変動 |
| 運動療法・呼吸リハビリテーション | 肺活量や呼吸時の酸素飽和度 |
| 定期受診・検査 | 治療の継続的効果と症状の再評価 |
薬物療法の調整
呼吸機能検査でFEV1が大きく改善した場合は現在の吸入ステロイドや気管支拡張薬が十分な効果を発揮していると考えられます。
ただし、症状が落ち着いているからといって自己判断で薬の使用量を減らすと気道炎症が再び悪化するリスクがあります。
逆に数値があまり変わらない場合は薬の種類や投与方法を変える、または追加の検査を行って治療の方針を再検討するなどが選択肢に挙げられます。
医師と相談しながら呼吸機能の数値を参考により良い治療バランスを探すことが大切です。
環境整備と日常ケア
埃や花粉、ペットの毛などのアレルゲンにより気道が刺激されると呼吸機能が低下しやすくなります。定期的な掃除や換気、寝具のこまめな洗濯など生活環境を整えることで発作を予防できます。
検査結果に変動がある場合は季節性のアレルゲン対策が十分にできていない可能性が考えられるため、対策の見直しを行うとよいでしょう。
また、外出時にはマスクの着用や花粉シーズンの行動計画に気を配ると不要な刺激を減らせます。
長期的なフォローアップ
喘息は良くなったり悪くなったりを繰り返すことが多い慢性疾患です。そのため、治療効果の確認と症状の変化を早期に捉えるために定期的なフォローアップが重要です。
半年や1年ごとなど医師の指示に従い検査を受ける習慣を続けると、自覚症状と数値のギャップを発見しやすくなります。
もし悪化の兆候がある場合は早めに医師と相談し、治療計画の修正や薬の調整を検討していくことが効果的です。
生活の中で意識する呼吸状態のセルフチェック
呼吸機能検査は医療機関で行いますが、日常の中にも自分の呼吸状態を振り返る方法がいくつかあります。
ここでは簡単に取り組めるセルフチェックのヒントをまとめます。
日常でのセルフチェックの利点
- 体調変化に早めに気づきやすい
- 医療機関に行くタイミングを計りやすい
- アクティブな対策につながりやすい
こうしたセルフチェックを続けると自分自身の呼吸の特徴を把握しやすくなり、異常を早めに見つけるのに役立ちます。
セルフチェック項目と対策例
| チェック項目 | 内容 | 対策例 |
|---|---|---|
| 日中の疲労感 | 軽い運動でも息切れを感じるか | 運動量の調整や医師の受診 |
| 咳の頻度 | 朝晩など特定の時間帯に咳が続くか | アレルゲン対策や吸入薬の検討 |
| 寝起きの息苦しさ | 夜間に呼吸が乱れていないか | 枕や寝具の見直し、専門検査の検討 |
| ピークフロー値の変動 | 家庭でのピークフロー測定器を用いて日々の数値を記録する | 発作が起こりやすいタイミングの把握 |
呼吸を意識したリラックス法
呼吸が浅くなると酸素を十分に取り込めず疲れやすくなります。
腹式呼吸や4カウント呼吸などゆったりとしたリズムで息を吸って吐く方法を実践すると、気持ちが落ち着きやすくなります。
特に睡眠前のリラックスとして取り入れると夜間の呼吸状態が整い、睡眠の質向上を期待できることがあります。身体のこわばりを感じたときに意識的に取り組むのも良い方法です。
適度な運動習慣
ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は肺活量と呼吸筋力の向上に役立ちます。
ただし、過度な運動は逆効果になる可能性があるため、医師と相談しながら無理のない範囲で始めると安全です。運動前後にピークフローを計測すると、自分の運動負荷が適切かどうかを数値で確認できます。
定期的な運動により基礎体力を上げると、日常生活での息切れの頻度が減るケースもあります。
禁煙や受動喫煙の回避
喫煙は気道に大きな負担をかけ、呼吸機能を低下させる要因になります。受動喫煙も同様に有害で、特に喘息を持つ方は発作の引き金になるリスクが高いです。
自力で禁煙が難しい場合は医師の指導や禁煙外来を活用すると成功率が高まります。受動喫煙を避けるために、飲食店や公共の場での環境にも気をつけましょう。
長期的に見ると、これだけでも呼吸機能が明らかに改善する例があります。
呼吸機能検査に対する不安を減らすために
初めて呼吸機能検査を受けるときは検査内容や結果に対して不安を感じる方が多いです。
ここでは検査をスムーズに受けるためのポイントと心構えについて解説します。
不安を和らげる行動
- 検査の手順を事前に調べてイメージをつかむ
- 極端な空腹や過度な満腹を避ける
- リラックスできる服装を選ぶ
検査で力を入れて呼吸を行う場面があるため、きつめの服装だと息苦しさを感じる恐れがあります。
検査前に軽いストレッチをするなど、体をほぐしておくことも有効です。
検査当日に注意したいポイント
| ポイント | 理由 |
|---|---|
| カフェインの摂取を控える | カフェインが気管支や心拍に影響し、結果にブレが出る可能性 |
| タバコを吸わない | 喫煙直後は気道が刺激を受け、呼吸測定が正確になりにくい |
| 落ち着ける音楽などでリラックス | 不安や緊張が強いと、検査時に十分な呼吸が行いにくい |
医療スタッフとの情報共有
検査前に持病や薬の使用状況、普段の症状を医療スタッフに伝えると、より正確な検査データを得やすくなります。
呼吸機能検査では思い切り息を吐く場面が多いため、めまいや咳き込みが心配なときは事前に相談しておくと安心です。
医療スタッフは安全で正確な検査が行えるようにサポートし、必要があれば検査方法の工夫も行います。
継続的な検査で変化を捉える
呼吸機能検査は一度受けて終わりではなく、症状の変化や治療の進行に応じて複数回受ける場合があります。
特に喘息や慢性閉塞性肺疾患などの症状管理を行う際は経過観察のために定期的な検査が大切です。自分の数値がどのように推移しているかを理解すると、治療へのモチベーションを保ちやすくなります。
もし検査の結果に不安があれば遠慮せずに医師やスタッフに質問し、疑問を解消しておくことが大切です。
心のケアとサポート
呼吸器症状は慢性的なストレスの原因になることも多く、精神的な負担が積み重なると病状の改善を妨げる可能性があります。
家族や友人に相談するだけでなく、必要に応じてカウンセリングや患者会の情報を取り入れてみるとよいでしょう。
前向きな気持ちで検査や治療に取り組むためにも、精神面のサポートは大切です。
以上
参考にした論文
MAEDA, Takuya, et al. Respiratory Function is Associated with Cognitive Function Change in Japanese Community-Dwelling Older People: A 1-Year, Longitudinal, Observational Study. Aging Med Healthc, 2024, 15.3: 129-136.
STANOJEVIC, Sanja, et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. European Respiratory Journal, 2022, 60.1.
TACHIBANA, Yuka, et al. Relationship between respiratory function assessed by spirometry and mild cognitive impairment among community‐dwelling older adults. Geriatrics & Gerontology International, 2024, 24.10: 1001-1007.
MAKI, Naoki, et al. The effect of respiratory rehabilitation for the frail elderly: a pilot study. Journal of general and family medicine, 2016, 17.4: 289-298.
KAMATA, Hirofumi, et al. Pulmonary function and chest CT abnormalities 3 months after discharge from COVID-19, 2020–2021: A nation-wide multicenter prospective cohort study from the Japanese respiratory society. Respiratory Investigation, 2024, 62.4: 572-579.
TANAKA, Hiroshi; FUJII, Masaru; KITADA, Junya. Further examination of COPD using spirometry, respiratory function test, and impulse oscillometry. Nihon rinsho. Japanese Journal of Clinical Medicine, 2011, 69.10: 1786-1791.
ANKE, VAN EEKELEN. Respirology has been adopted as the preferred English journal of the Japanese Respiratory Society. 2023.
SUGIYAMA, Y., et al. An autopsy case of diffuse panbronchiolitis accompanying rheumatoid arthritis. Respiratory medicine, 1996, 90.3: 175-177.
STANOJEVIC, Sanja, et al. ERS/ATS technical standard on interpretive strategies for routine lung function tests. European Respiratory Journal, 2022, 60.1.
RAGHU, Ganesh, et al. An official ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline: treatment of idiopathic pulmonary fibrosis. An update of the 2011 clinical practice guideline. American journal of respiratory and critical care medicine, 2015, 192.2: e3-e19.