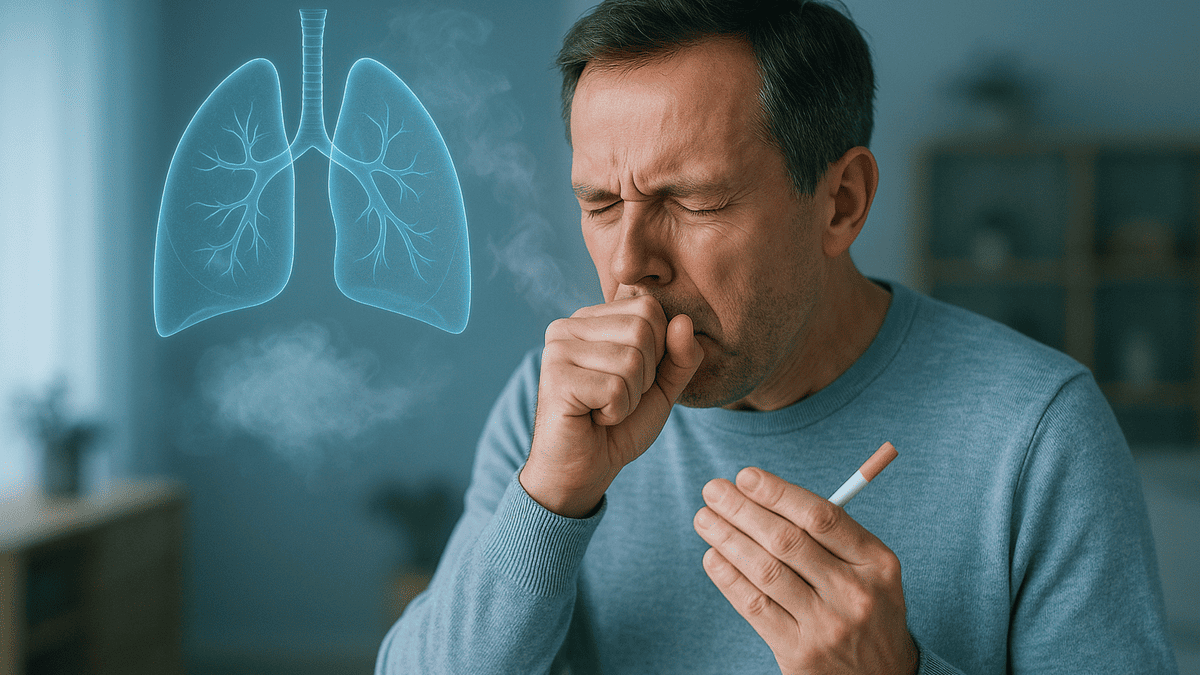「長年、咳や痰が続いている」「冬になると特に咳がひどくなる」といった症状を年齢や体質のせいだと諦めていませんか。
その症状、もしかしたら「慢性気管支炎」かもしれません。慢性気管支炎は主に長年の喫煙習慣によって気管支に炎症が続く病気です。
この記事では慢性気管支炎の症状や原因、急性気管支炎との違い、そして禁煙を中心とした治療法について呼吸器内科の専門医が詳しく解説します。
慢性気管支炎とは?急性との根本的な違い
「気管支炎」には急性と慢性の2種類があります。両者は名前が似ていますが、原因も経過も全く異なる病気です。
「2年以上、年に3ヶ月以上」続く咳と痰
慢性気管支炎は、その定義が明確に決まっています。「1年のうち3ヶ月以上、痰を伴う咳が続き、それが2年以上連続してみられる状態」を指します。
一時的な症状ではなく、長期間にわたって気管支の炎症が続いているのが特徴です。
急性気管支炎との原因と経過の違い
急性気管支炎は主にウイルス感染が原因で起こり、数週間で治癒する一過性の病気です。
一方、慢性気管支炎は長期間にわたる喫煙などの刺激によって気管支が傷つき、炎症が慢性化した状態です。原因を取り除かない限り、自然に治ることはありません。
急性気管支炎と慢性気管支炎の比較
| 項目 | 急性気管支炎 | 慢性気管支炎 |
|---|---|---|
| 主な原因 | ウイルス・細菌感染 | 長期間の喫煙など |
| 期間 | 一過性(数週間以内) | 慢性的(2年以上) |
| 主な症状 | 咳、痰、発熱 | 咳、痰(特に冬場に悪化) |
慢性気管支炎はCOPDの一種
慢性気管支炎は現在では「慢性閉塞性肺疾患(COPD)」という、より大きな病気の概念に含まれるものとして理解されています。
COPDはタバコ煙などを主とする有害物質を長期間吸入することで生じる肺の病気で、慢性気管支炎と肺の組織が破壊される「肺気腫」の2つの病態が混在しています。
なぜ発症するのか?最大の原因は「タバコ」
慢性気管支炎を引き起こす原因は複数ありますが、その中でも圧倒的に多いのが長年の喫煙習慣です。
タバコの煙が気管支を傷つける仕組み
タバコの煙にはニコチンやタールをはじめとする数多くの有害物質が含まれています。これらの有害物質を吸い込むと気管支の粘膜が常に刺激にさらされます。
この刺激により、気管支の粘膜に炎症が起き、痰を分泌する細胞が過剰に働いて、粘液(痰)の分泌量が増加します。これが慢性的な咳と痰の原因となります。
タバコの煙に含まれる主な有害物質
| 有害物質 | 体への影響 |
|---|---|
| ニコチン | 強い依存性を持ち、血管を収縮させる |
| タール | 発がん性物質を多く含み、肺を黒くする |
| 一酸化炭素 | 血液の酸素運搬能力を低下させ、息切れの原因になる |
長年の喫煙習慣がもたらすリスク
喫煙年数や1日の喫煙本数が多ければ多いほど発症のリスクは高まります。
長年にわたって気管支が有害物質にさらされ続けることで気管支の防御機能が破壊され、炎症が慢性化してしまうのです。
喫煙者における慢性気管支炎の発症率は非喫煙者に比べて著しく高いことがわかっています。
受動喫煙や大気汚染の影響
ご自身がタバコを吸わなくても家族や職場の人が吸うタバコの煙(受動喫煙)を長期間吸い続けることでも発症のリスクは高まります。
また、粉塵や化学物質などを扱う職業に従事している方や、PM2.5などの大気汚染に長期間さらされることも原因の一つとなり得ます。
慢性気管支炎の主な症状
慢性気管支炎の症状は、ゆっくりと進行するのが特徴です。初期症状を見逃さず、早めに対処することが重要です。
しつこく続く咳と痰(たん)
最も代表的な症状は、長引く咳と痰です。特に朝起きた時に、一日のうちに溜まった痰を排出しようとして、激しく咳き込むことが多くなります。
痰は粘り気があり、白色や黄色を帯びていることが一般的です。冬場に風邪をひくと、症状が悪化しやすい傾向があります。
進行すると現れる労作時息切れ
病気が進行し、COPDの病態が進むと体を動かした時に息切れ(労作時息切れ)を感じるようになります。
初めは階段や坂道を上る時に感じる程度ですが、悪化すると平地を歩くだけでも息が苦しくなり、日常生活に大きな支障をきたすようになります。
症状の進行段階
| 段階 | 主な症状 |
|---|---|
| 初期 | 咳、痰(特に冬場や朝) |
| 中期 | 階段などで息切れを感じる |
| 重症期 | 平地歩行や着替えなどでも息切れする |
感染を繰り返す「かぜをひきやすい」状態
慢性的な炎症によって気管支の防御機能が低下しているため、ウイルスや細菌に感染しやすくなります。このため「年に何回も風邪をひく」「一度ひくと治りにくい」といった状態になります。
感染をきっかけに症状が急激に悪化する「急性増悪」を繰り返すことも特徴です。
喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒュー)を伴うことも
気管支の炎症が強く、空気の通り道が狭くなると、息をする時に「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音(喘鳴)が聞こえることがあります。
これは気管支喘息の症状と似ていますが、慢性気管支炎の場合は持続的であることが多いです。
診断のために行われる検査
慢性気管支炎やCOPDの診断は、症状の問診といくつかの客観的な検査を組み合わせて行います。
問診と聴診による症状の確認
診断の第一歩は症状の詳しい聞き取りです。咳や痰の状態、息切れの程度、そして最も重要な喫煙歴について詳しく確認します。
聴診器で胸の音を聞き、異常な呼吸音がないかをチェックします。
呼吸機能検査(スパイロメトリー)
COPDの診断に必須の検査です。スパイロメーターという機械を使って思い切り息を吸ってから、できるだけ強く速く息を吐き出します。
このとき最初の1秒間で吐き出せる空気の量(1秒量)と、肺活量全体に対する1秒量の割合(1秒率)を測定します。
この1秒率が70%未満の場合、気道が狭くなっていると判断してCOPDと診断します。
呼吸機能検査の主な指標
| 指標 | 意味 | COPD診断基準 |
|---|---|---|
| 努力性肺活量(FVC) | 思い切り息を吐き出した時の空気の総量 | – |
| 1秒量(FEV1) | 最初の1秒間で吐き出せる空気の量 | 重症度の判定に用いる |
| 1秒率(FEV1/FVC) | 肺活量に対する1秒量の割合 | 70%未満 |
胸部X線(レントゲン)検査の役割
肺がんや肺炎、心不全など咳や息切れの原因となる他の病気がないかを確認するために行います。
また、COPDが進行して肺気腫の所見(肺の過膨張など)が見られることもあります。
必要に応じて行う追加検査(CT検査など)
X線検査だけではわからない肺の詳細な状態を調べるために胸部CT検査を行うことがあります。肺気腫の広がりや程度をより正確に評価することができます。
また、血液中の酸素濃度を測定する検査(パルスオキシメトリーや動脈血ガス分析)も行います。
慢性気管支炎の治療法
慢性気管支炎(COPD)の治療の目的は症状を和らげ、病気の進行を抑制し、生活の質を維持することです。
一度壊れた肺の組織は元には戻らないため、早期からの治療が重要です。
治療の第一歩は「禁煙」
最も重要で、かつ最も効果的な治療は「禁煙」です。
禁煙することで気道への刺激がなくなり、炎症の進行を食い止め、呼吸機能の低下するスピードを緩やかにすることができます。
自力での禁煙が難しい場合は禁煙外来で専門家のサポートを受けながら、禁煙補助薬などを用いて治療を進めることができます。
薬物療法(気管支拡張薬・去痰薬)
薬物療法の中心となるのは狭くなった気管支を広げる「気管支拡張薬」の吸入です。長時間作用性の吸入薬を定期的に使用することで息切れを和らげ、楽に動けるようになります。
また、痰の切れを良くする「去痰薬」を併用することもあります。
主な治療薬
- 長時間作用性抗コリン薬(LAMA)
- 長時間作用性β2刺激薬(LABA)
- 去痰薬
呼吸リハビリテーションの重要性
薬物療法と並行して、呼吸リハビリテーションを行うことも非常に大切です。息切れを恐れて動かないでいると、ますます筋力が低下し、さらに息切れが悪化するという悪循環に陥ります。
呼吸法や運動療法を通して楽な呼吸の仕方を学び、体力を維持・向上させます。
急性増悪(症状の急な悪化)時の対応
風邪などをきっかけに咳や痰、息切れが急激に悪化することがあります。これを「急性増悪」と呼びます。
痰の色が濃くなったり、量が増えたり、息苦しさが強まったりした場合は早めに医療機関を受診し、抗菌薬やステロイド薬による治療を受ける必要があります。
日常生活で気をつけるべきこと
治療効果を高め、快適な生活を送るためには日頃の自己管理が重要になります。
感染症の予防(ワクチン接種・手洗い)
インフルエンザや肺炎は急性増悪の大きな原因となります。インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンを定期的に接種することが強く推奨されます。
また、日頃からの手洗いやうがい、人混みを避けるなどの感染対策も大切です。
栄養バランスの取れた食事と水分補給
痩せすぎは呼吸筋の低下につながり、肥満は呼吸の負担を増大させます。バランスの取れた食事を心がけ、適切な体重を維持しましょう。
また、十分な水分補給は痰を柔らかくし、排出しやすくする助けになります。
適度な運動の継続
息苦しいからといって動かないでいると体力はどんどん低下してしまいます。
無理のない範囲でウォーキングなどの軽い運動を毎日続けることが、体力維持や息切れの改善につながります。呼吸リハビリテーションの指導のもと、安全な運動計画を立てましょう。
日常生活での自己管理のポイント
| 項目 | 具体的な行動 |
|---|---|
| 感染予防 | ワクチン接種、手洗い、うがい |
| 食事管理 | バランスの良い食事、十分な水分摂取 |
| 運動療法 | 無理のない範囲でのウォーキングなど |
よくある質問(Q&A)
最後に、慢性気管支炎について患者さんからよくいただく質問にお答えします。
- Q禁煙すれば治りますか?
- A
残念ながら一度破壊されてしまった肺の組織(肺気腫)や、慢性化した気管支の炎症が完全に元通りになることはありません。
しかし、禁煙は病気の進行を食い止めるための最も重要なステップです。
禁煙することで呼吸機能が低下する速度を非喫煙者と同じレベルまで緩やかにすることができます。
- Q治療にはどのくらいの期間がかかりますか?
- A
慢性気管支炎(COPD)は高血圧や糖尿病と同じように、生涯にわたって付き合っていく慢性疾患です。したがって治療も長期にわたって継続する必要があります。
自己判断で治療を中断せず、定期的に通院して医師とともに症状をコントロールしていくことが大切です。
- Q周りの人にうつりますか?
- A
慢性気管支炎そのものは感染症ではないため、周りの人にうつることはありません。
ただし慢性気管支炎の患者さんは免疫力が低下しているため、風邪などの感染症にかかりやすく、そのウイルスや細菌を周りの人にうつしてしまう可能性はあります。
- Q息苦しさが改善しない場合はどうすればよいですか?
- A
薬物療法や呼吸リハビリテーションを行っても息苦しさが強い場合は在宅酸素療法(HOT)の導入を検討することがあります。
これは自宅に設置した機械で高濃度の酸素を作り出し、鼻につけたチューブから吸入する治療法です。
体の酸素不足を補い、息切れを和らげ、生活の質を向上させることができます。
以上
参考にした論文
KATO, Akane; HANAOKA, Masayuki. Pathogenesis of COPD (persistence of airway inflammation): why does airway inflammation persist after cessation of smoking?. In: Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systemic Inflammatory Disease. Singapore: Springer Singapore, 2016. p. 57-72.
NOGUCHI, Shingo, et al. Association of cigarette smoking with increased use of heated tobacco products in middle-aged and older adults with self-reported chronic obstructive pulmonary disease, asthma, and asthma-COPD overlap in Japan, 2022: the JASTIS study. BMC Pulmonary Medicine, 2023, 23.1: 365.
SASAKI, Hidetada, et al. Effects of air pollution and smoking on chronic obstructive pulmonary disease and bronchial asthma. The Tohoku Journal of Experimental Medicine, 1998, 186.3: 151-167.
HIKICHI, Mari, et al. Pathogenesis of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) induced by cigarette smoke. Journal of thoracic disease, 2019, 11.Suppl 17: S2129.
ICHINOSE, Masakazu, et al. Japanese guidelines for adult asthma 2017. Allergology International, 2017, 66.2: 163-189.
SHIBATA, Yoko, et al. Management goals and stable phase management of patients with chronic obstructive pulmonary disease in the Japanese respiratory society guideline for the management of chronic obstructive pulmonary disease 2022. Respiratory Investigation, 2023, 61.6: 773-780.
HIZAWA, Nobuyuki. LAMA/LABA vs ICS/LABA in the treatment of COPD in Japan based on the disease phenotypes. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 2015, 1093-1102.
AOKI, Masakazu. Epidemiology of chronic airways diseases in Japan. Chest, 1989, 96.3: 343S-349S.
NAKAMURA, Yoichi, et al. Japanese guidelines for adult asthma 2020. Allergology International, 2020, 69.4: 519-548.
MUKAE, Hiroshi, et al. The Japanese respiratory society guidelines for the management of cough and sputum (digest edition). Respiratory Investigation, 2021, 59.3: 270-290.