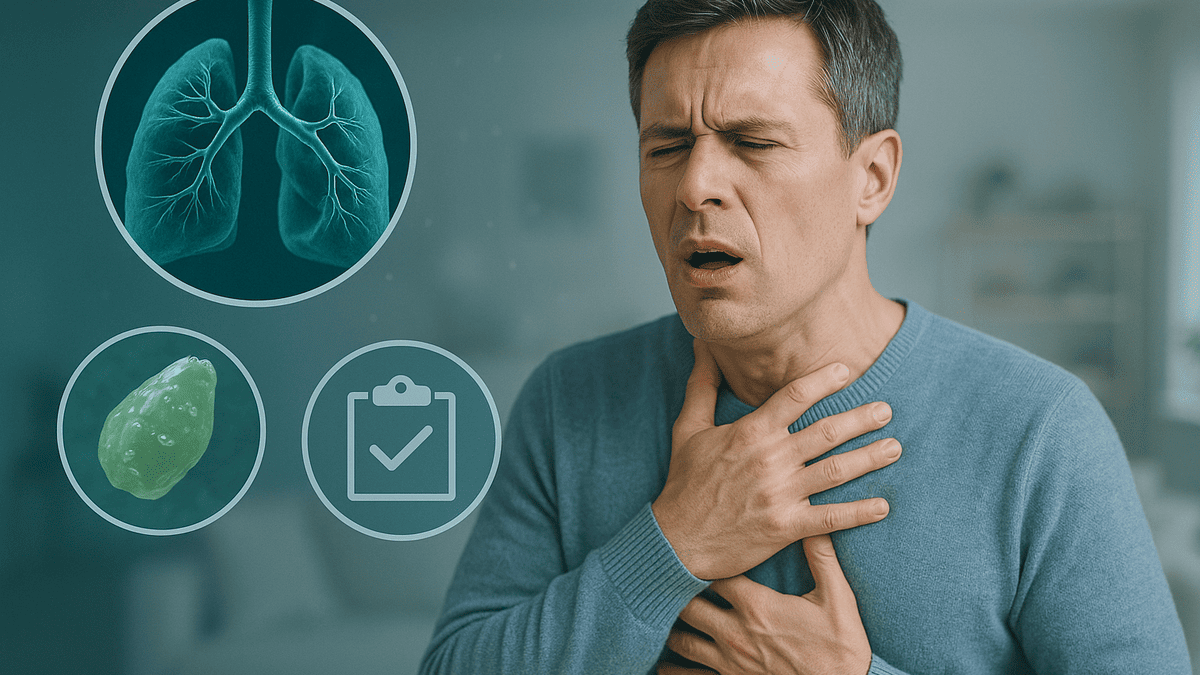「咳が長引くだけでなく、なんとなく息苦しい」「痰がからんでスッキリしない」そんな症状に悩んでいませんか。
アレルギー性気管支炎は咳だけでなく息苦しさや痰といった多彩な症状を伴うことがあります。
この記事ではアレルギー性気管支炎の具体的な症状、特に咳・痰・息苦しさの特徴を詳しく解説します。
ご自身の症状を客観的に見つめ直すためのセルフチェックリストも用意しました。つらい症状の原因を知り、適切な対処法を見つける一助としてください。
アレルギー性気管支炎の症状 なぜ息苦しくなるのか
アレルギー性気管支炎はアレルゲンによって気管支に炎症が起きる病気です。この「炎症」が、咳だけでなく、息苦しさという感覚にもつながっています。
気管支の炎症が引き起こす症状
アレルゲンを吸い込むと気管支の粘膜がアレルギー反応によって腫れ、敏感になります。この気道の粘膜の腫れが空気の通り道をわずかに狭くさせることがあります。
この状態が胸の圧迫感や「息が吸いにくい」といった息苦しさの感覚として現れるのです。
咳と痰が息苦しさを助長する
炎症によって気管支から過剰に分泌物(痰)が作られると、それが気道に絡みつき、さらに空気の流れを妨げます。また、激しい咳が続くと呼吸に使う筋肉が疲労し、体力を消耗します。
これらの要因が複合的に絡み合うことで、息苦しさの感覚が強まることがあります。
喘息(ぜんそく)の息苦しさとの違い
気管支喘息では気管支の筋肉が収縮することで気道が急激に狭くなり、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴を伴うはっきりとした呼吸困難発作が起こります。
一方、アレルギー性気管支炎の息苦しさはそこまで激しいものではなく、「なんとなく息苦しい」「胸が重い」といった、より軽度で持続的な感覚であることが多いのが特徴です。
ただし、症状の感じ方には個人差があります。
アレルギー性気管支炎と喘息の息苦しさの比較
| 項目 | アレルギー性気管支炎 | 気管支喘息(発作時) |
|---|---|---|
| 感覚 | 持続的な息苦しさ、胸の圧迫感 | 急激で発作的な呼吸困難 |
| 喘鳴(ゼーゼー音) | 通常はない | 伴うことが多い |
| 重症度 | 軽度~中等度 | 中等度~重度 |
咳の症状を詳しく見る
アレルギー性気管支炎の最も中心的な症状は「咳」です。その出方や特徴には診断の手がかりとなるいくつかのポイントがあります。
痰の絡まない乾いた咳(乾性咳嗽)
多くの場合、「コンコン」「コホコホ」といった痰の絡まない乾いた咳が特徴です。一度出始めると立て続けに出ることがあります。
風邪の後の咳と似ていますが、熱などの他の症状がなく、咳だけが数週間以上にわたって続く場合にこの病気を疑います。
特定の状況で悪化する咳
アレルギー性気管支炎の咳はアレルゲンとの接触や特定の状況で悪化しやすい傾向があります。
ご自身の咳がいつ、どんな時に出やすいかを観察することが原因を探る上で非常に重要です。このパターンを把握することが診断への近道となります。
咳が悪化しやすい状況の例
- 夜間、床に就いてから、または早朝
- 掃除中や、古い本を整理している時
- エアコンをつけた時
- 特定の季節(花粉シーズンなど)
喉のイガイガ感や違和感
咳だけでなく、喉の奥がイガイガしたり、むずがゆい感じがしたりすることもあります。
これはアレルギー反応によって喉の粘膜も刺激されているサインです。常に喉に何かが張り付いているような不快感を訴える方もいます。
咳の出方と疑われる原因
| 咳が悪化する状況 | 考えられる主な原因アレルゲン |
|---|---|
| 就寝時、起床時 | ダニ、ハウスダスト |
| 春や秋など特定の季節 | スギ、ヒノキ、ブタクサなどの花粉 |
| エアコン使用時、湿気の多い場所 | カビ |
痰(たん)の症状を詳しく見る
咳とともに痰が絡むこともあります。痰の状態は気管支の炎症の程度を知るためのバロメーターになります。
透明でサラサラした痰
アレルギー性気管支炎でみられる痰はウイルスや細菌感染によるものではないため、基本的には無色透明で比較的サラサラしていることが多いです。
量はそれほど多くないことが一般的です。
粘り気のある痰が絡むことも
炎症が長引くと痰の粘り気が増してくることがあります。
この粘り気のある痰が気道にへばりつくと、それを排出しようとしてさらに咳が出やすくなるという悪循環に陥ることがあります。喉に絡んでなかなか切れない不快感を伴います。
痰の色に注意が必要なケース
もし痰が黄色や緑色をしていたり、血液が混じったりする場合はアレルギー性気管支炎だけでなく、細菌感染や他の呼吸器の病気が合併している可能性があります。
このような色のついた痰が続く場合は速やかに医療機関を受診する必要があります。
痰の性状から考えられること
| 痰の性状 | 主な原因 | 考えられる状態 |
|---|---|---|
| 無色透明、漿液性 | アレルギー反応 | アレルギー性気管支炎、アレルギー性鼻炎 |
| 黄色・緑色、膿性 | 細菌感染 | 急性気管支炎、肺炎、副鼻腔炎の合併 |
| 血液が混じる(血痰) | 気道粘膜の損傷、その他 | 肺がんや結核など重篤な病気の可能性も |
【セルフチェック】あなたのアレルギー性気管支炎リスクは?
ご自身の症状がアレルギー性気管支炎にあてはまるか、簡単なチェックリストで確認してみましょう。多くあてはまるほどアレルギーが関与している可能性が高まります。
症状に関するチェックリスト
まずは現在の症状について振り返ってみましょう。以下の項目にいくつあてはまるか数えてみてください。
症状編セルフチェック
| チェック項目 | はい / いいえ |
|---|---|
| 熱はないのに咳だけが3週間以上続いている | |
| 咳とともに軽い息苦しさや胸の違和感がある | |
| 夜間や早朝に特に咳が出やすい | |
| 喉がイガイガ、ムズムズすることがよくある | |
| 市販の風邪薬や咳止めがあまり効かない |
生活習慣・体質に関するチェックリスト
次に、ご自身の体質や生活環境について確認します。アレルギーとの関連性を探る手がかりになります。
体質・環境編セルフチェック
| チェック項目 | はい / いいえ |
|---|---|
| 家族にアレルギー体質の人(喘息、アトピーなど)がいる | |
| 自分自身、花粉症やアレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎がある | |
| 掃除をすると咳や鼻水が出やすい | |
| 特定の季節になると咳が悪化する | |
| ペット(犬、猫など)を室内で飼っている |
チェック結果の考え方
これらの項目に複数あてはまる場合、あなたの長引く咳や息苦しさはアレルギー性気管支炎である可能性が考えられます。
ただしこれはあくまで簡易的なチェックであり、自己判断は禁物です。正確な診断のためには呼吸器内科専門医の診察を受けることが重要です。
アレルギー性鼻炎との深い関係
アレルギー性気管支炎の患者さんはアレルギー性鼻炎を合併していることが非常に多く、両者は密接に関連しています。
鼻と気管支はつながっている
鼻から気管支、肺までは、一本の空気の通り道(気道)でつながっています。そのため鼻にアレルギー性の炎症が起これば、気管支にも炎症が波及しやすくなります。
この考え方を「One airway, one disease」と呼びます。
後鼻漏(こうびろう)が咳を誘発する
アレルギー性鼻炎があると鼻水が作られ続けます。この鼻水が喉の奥に垂れ落ちる現象を「後鼻漏」といいます。
この後鼻漏が気管を刺激し、咳の原因となることがあります。特に仰向けに寝ると後鼻漏が起こりやすいため、夜間の咳の一因となります。
鼻の治療が咳の改善につながる
このため、アレルギー性気管支炎の治療では咳に対するアプローチだけでなく、鼻の症状をコントロールすることも非常に大切です。
鼻炎の治療をしっかり行うことで結果的に咳や痰、息苦しさが改善するケースは少なくありません。
呼吸器内科では鼻の状態も考慮に入れながら総合的に治療計画を立てます。
症状があるときに気をつけるべきこと
咳や息苦しさといった症状があるときは気道をさらに刺激するような行動を避け、体をいたわることが大切です。
刺激の強い環境を避ける
タバコの煙(受動喫煙を含む)やホコリっぽい場所、排気ガスが多い場所は症状を悪化させる大きな要因です。また、強い香水や芳香剤、殺虫剤なども刺激になることがあります。
症状が強い時期は、こうした環境に身を置かないように工夫しましょう。
急激な温度変化に注意する
寒い屋外から暖房の効いた室内へ入った時など急激な温度差は気道を刺激し、咳を誘発します。
外出時はマスクを着用する、マフラーなどで首元を冷やさないようにするなど、温度変化を和らげる工夫が有効です。
飲酒や香辛料の多い食事
アルコールを摂取すると体内の血管が拡張し、気道の粘膜の腫れや炎症を助長することがあります。
また、唐辛子などの香辛料を多く使った刺激の強い食事もむせる原因となり、咳を誘発しやすいため、控えるのが賢明です。
症状悪化を避けるためのポイント
| 避けるべきこと | 具体的な例 |
|---|---|
| 環境からの刺激 | タバコの煙、ホコリ、排気ガス、強い香り |
| 物理的な刺激 | 急激な温度差、冷たく乾燥した空気 |
| 食事による刺激 | アルコール、香辛料の多い食事 |
息苦しさを感じたら、いつ病院へ行くべきか
咳や息苦しさが続く場合、どのタイミングで医療機関を受診すればよいか迷うかもしれません。受診の目安と、診察で伝えるべきポイントを解説します。
2〜3週間以上症状が続く場合
咳や痰、息苦しさといった症状が2〜3週間以上続く場合は単なる風邪のなごりとは考えにくいため、一度呼吸器内科を受診することをお勧めします。
特に市販薬を試しても改善しない場合は専門的な診断が必要です。
日常生活に支障が出始めたら
「咳で夜眠れない」「息苦しくて会話や通勤が辛い」など、症状によって日常生活に支障が出ている場合は、我慢せずに早めに受診しましょう。
適切な治療を受けることで生活の質(QOL)を大きく改善できる可能性があります。
医師に伝えるべき症状のポイント
診察の際には、ご自身の症状をできるだけ具体的に伝えることが正確な診断につながります。
以下の内容をメモなどにまとめておくとスムーズに伝えられます。
診察時に伝えることリスト
- いつから症状が始まったか
- どんな症状があるか(咳、痰、息苦しさの程度)
- どんな時に症状が悪化するか(時間帯、場所、状況)
- アレルギー歴や家族歴
- 現在服用中の薬
アレルギー性気管支炎に関するよくある質問(Q&A)
最後に、アレルギー性気管支炎の症状について患者さんからよくいただく質問にお答えします。
- Q息苦しいのですが、心臓の病気の可能性はありますか?
- A
息苦しさは心臓の病気(心不全など)でも起こりうる症状です。
ただし、心臓が原因の場合は体を動かした時(労作時)に息切れが強くなったり、足のむくみを伴ったりすることが多いです。
アレルギー性気管支炎が疑われる場合でも他の病気の可能性を否定するために、問診や診察で総合的に判断します。心配な場合は遠慮なく医師にご相談ください。
- Qストレスで咳や息苦しさが出ることはありますか?
- A
はい、あります。
ストレスや疲労は自律神経のバランスを乱し、気道を過敏にさせることが知られています。
このため、精神的なストレスが引き金となって咳や息苦しさの症状が悪化することは十分に考えられます。
心身ともにリラックスできる時間を持つことも症状のコントロールには大切です。
- Q検査ではどんなことをしますか?痛い検査はありますか?
- A
アレルギー性気管支炎の診断で行う検査は、胸部X線(レントゲン)撮影や血液検査、呼吸機能検査などが中心です。
血液検査では採血を行いますが、それ以外に強い痛みを伴う検査は通常ありません。
呼吸機能検査は技師の掛け声に合わせて息を吸ったり吐いたりする検査で、患者さんの協力が重要になります。
- Q子供でもアレルギー性気管支炎になりますか?
- A
はい、お子さんでも発症します。
小児の場合は診断がより難しいことがありますが、長引く咳の原因として常に念頭に置くべき病気の一つです。
アトピー性皮膚炎や食物アレルギーなど、他のアレルギー疾患を持っているお子さんに多く見られる傾向があります。
お子さんの咳が長引く場合は、まずかかりつけの小理科医に相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらうのがよいでしょう。
以上
参考にした論文
YASUO, Masanori, et al. Self-assessment of allergic rhinitis and asthma (SACRA) questionnaire-based allergic rhinitis treatment improves asthma control in asthmatic patients with allergic rhinitis. Internal Medicine, 2017, 56.1: 31-39.
GALLUCCI, Marcella, et al. Use of symptoms scores, spirometry, and other pulmonary function testing for asthma monitoring. Frontiers in pediatrics, 2019, 7: 54.
MOTEGI, Takashi, et al. A comparison of three multidimensional indices of COPD severity as predictors of future exacerbations. International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 2013, 259-271.
TAKEMURA, Masaya, et al. Co-existence and seasonal variation in rhinitis and asthma symptoms in patients with asthma. Respiratory investigation, 2016, 54.5: 320-326.
NATIONAL ASTHMA EDUCATION, et al. Expert panel report 2: guidelines for the diagnosis and management of asthma. Diane Publishing, 1998.
SUZUKI, Tomoko, et al. Efficacy of fluticasone propionate compared with beclomethasone dipropionate in bronchial asthma: improvement in compliance and symptoms by fluticasone. In: Allergy & Asthma Proceedings. 2003.
WILSON, Sandra R., et al. Asthma outcomes: quality of life. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2012, 129.3: S88-S123.
RHEE, Hyekyun; BELYEA, Michael; MAMMEN, Jennifer. Visual analogue scale (VAS) as a monitoring tool for daily changes in asthma symptoms in adolescents: a prospective study. Allergy, Asthma & Clinical Immunology, 2017, 13: 1-8.
HOMMA, Tetsuya, et al. Beneficial effect of early intervention with garenoxacin for bacterial infection-induced acute exacerbation of bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease. International archives of allergy and immunology, 2019, 178.4: 355-362.
NAKAJIMA, Takeo; NAGANO, Tatsuya; NISHIMURA, Yoshihiro. Retrospective study of the effects of post-nasal drip symptoms on cough duration. in vivo, 2021, 35.3: 1799-1803.