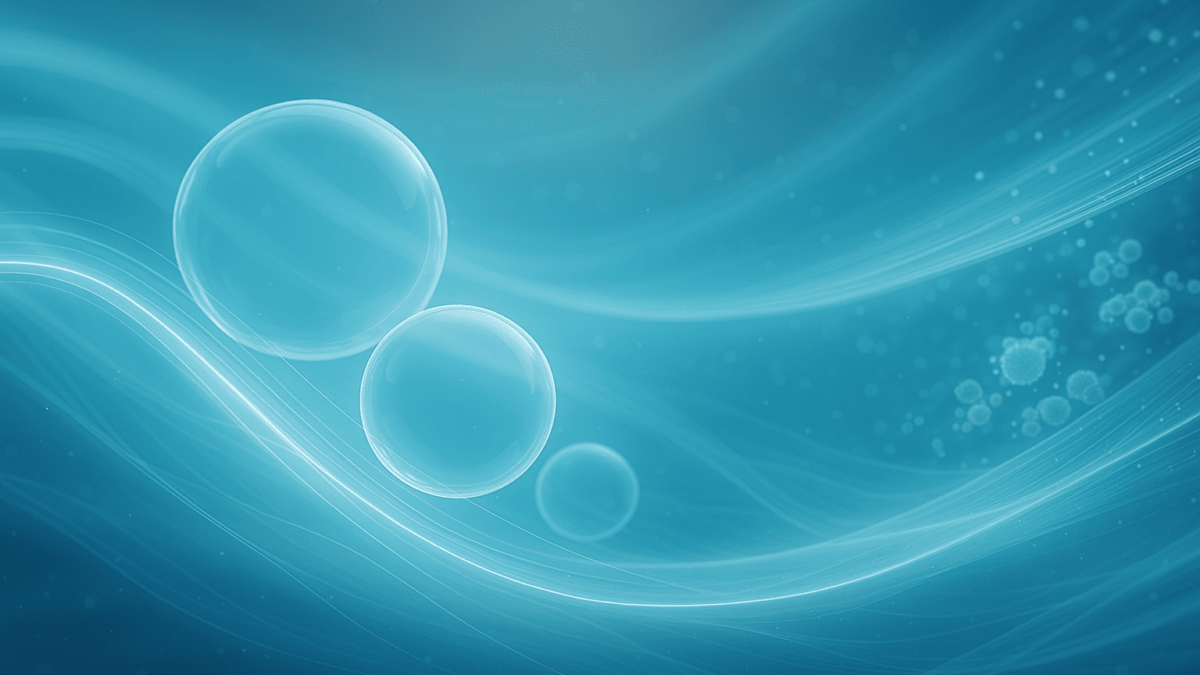日常生活のなかで、自分の便の状態を細かく意識する方は多くありません。しかし、便は食生活や腸内環境を反映し、身体のさまざまな変化を示す手がかりになります。
血液検査や画像検査だけではわかりにくい消化管や腸内細菌などのトラブルを把握するには、便を詳しく調べる糞便検査が大きな助けになります。
消化器系の症状が気になって医療機関を受診すべきかどうか悩んでいる方は、糞便検査の方法や種類、そして結果の見方を理解しておくと安心です。
そこで糞便検査の基礎知識から具体的な検査の種類まで、詳しくまとめました。
糞便検査とは何か
便の状態を調べる行為は、身体の中で起こるさまざまな問題を早期に見つけるうえで重要です。この節では、糞便検査の概略や目的などを整理します。
糞便検査の概要
糞便検査は、便を採取し、その中に含まれる血液・脂肪・細菌・炎症性物質などを評価します。医師や検査技師は、肉眼的な観察だけでなく、化学的・微生物学的・免疫学的な手法を組み合わせて詳しく調べます。
たとえば肉眼的な観察では、便の色や形状を見ます。化学的な分析によって便潜血や脂肪量を調べ、微生物学的な分析によって細菌や寄生虫卵の有無をチェックします。
これら複数の視点から便を総合的に評価することで、消化器に潜む疾患の可能性や腸内環境の乱れを把握するきっかけになります。
以下の一覧は、糞便検査全般で確認する主なポイントの例です。
| 主な検査項目 | 概要 |
|---|---|
| 視覚的特徴 | 色、形状、硬さなどの目視評価 |
| 化学的検査 | 便潜血・pH・脂肪分解の程度などの分析 |
| 微生物学的検査 | 細菌培養、寄生虫卵の検出など |
| 免疫学的検査 | 抗原・抗体の検出、カルプロテクチン測定など |
糞便検査が大切な理由
便は身体の消化過程を映す鏡といえます。消化管や肝臓、膵臓、腸内細菌叢の異常は、便に変化をもたらします。
血液検査や尿検査では見つけにくい腸内の問題を早期に見つけるには、定期的に便を調べることが有効です。
とくに腹痛や便秘、下痢、便に血が混じるなど気になる症状がある方は、こうした検査によって腸の状態や潜在的な疾患を把握できる可能性があります。
糞便検査が求められる主なケース
医師は主に以下のような状況で、糞便検査を実施することがあります。
- 血便や黒色便など便に異常が見られるとき
- 慢性的な下痢や便秘に悩まされているとき
- 腹痛や体重減少などが長期間続くとき
- 腸炎や潰瘍性大腸炎、クローン病などが疑われるとき
これらの症状を放置すると、重大な病気の発見が遅れてしまうこともあります。そのため「ちょっとおかしい」と感じた段階で医療機関へ相談し、必要に応じて糞便検査を受けることが重要です。
糞便検査の大まかな流れ
糞便検査では、医療機関から採便容器や必要書類を受け取り、あらかじめ自宅で便を採取するパターンが多いです。採取したらすみやかに提出し、検査機関で分析を行います。
検査結果は医師の解釈と合わせて、短期間で説明されることが一般的です。ただし検査項目によっては培養などに時間を要する場合もあります。
一連の流れをもう少し詳しくまとめると、次のとおりです。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 検査の説明 | 医師やスタッフから必要な検査項目について説明を受ける |
| 採便容器の受取 | 採取専用の容器、スプーン、手袋などを手渡される |
| 自宅での採便 | 指示された方法で便を容器に採取し、所定の量を入れる |
| 提出・保存 | 速やかに医療機関に持参するか、必要があれば低温保存などを行う |
| 分析 | 検査機関が便を分析し、医師が結果を判断する |
採便時には、異物が混入しないように気をつけながら正しい方法で行うことが大切です。
糞便検査の主な種類
糞便検査と一口にいっても、検査項目は多岐にわたります。ここでは代表的な種類を5つ取り上げ、それぞれどのような目的で実施されるかを解説します。
便潜血
消化管内で出血がある場合、わずかな血液でも便に混じります。便潜血検査は、その少量の血液を免疫学的手法などで調べる方法です。
大腸がんや潰瘍性大腸炎などでは出血が起こりやすいため、早期発見につながることがあります。医師は便潜血の陽性反応が見られたとき、大腸内視鏡検査などさらに詳しい検査を検討することが多いです。
下の一覧に、便潜血検査の特徴を簡潔に示します。
| 項目 | 特徴 |
|---|---|
| 検査方法 | 免疫学的手法(ヒトヘモグロビンを特異的に捉える) |
| 主な対象疾患 | 大腸がん、潰瘍性大腸炎、ポリープなど |
| 出血量の目安 | ごく微量でも検出できる |
| 結果が陽性となった場合 | 内視鏡検査での精密検査を考慮する |
便潜血が陽性でも、必ず重篤な病気があるわけではありません。痔など比較的軽度の原因の場合もあります。とはいえ、消化管の状態をより正確に知るためには追加の精密検査が必要です。
便中脂肪
便中脂肪検査は、便の中の脂肪分を定量または定性で測定し、消化や吸収の状態を把握する方法です。脂肪の吸収は主に小腸で行いますが、膵臓の消化酵素や胆汁酸の働きにも依存しています。
膵臓の疾患や胆道系のトラブル、あるいは小腸の吸収不良などがあると、便に未消化の脂肪が増えます。この検査によって原因を推測しやすくなり、さらに詳細な検査につながる可能性があります。
便中細菌培養
食事や生活環境を通じて、私たちの腸内には多種多様な細菌が棲みついています。この細菌バランスが崩れると、感染症や下痢、腹痛などの症状が引き起こされることがあります。
便中細菌培養は、便を培地に播いて細菌の種類や量を確認する方法です。特に病原菌と疑われる細菌がいるかどうかや、薬剤耐性などを調べる場合に役立ちます。
| 検査目的 | 対象となる主な細菌 |
|---|---|
| 腸炎の原因検索 | サルモネラ属菌、赤痢菌、腸炎ビブリオなど |
| 日和見感染リスクの判定 | 免疫力低下時に悪さをする常在菌や耐性菌の有無 |
| 腸内環境の評価 | ビフィズス菌、乳酸菌など善玉菌の減少や悪玉菌の増加 |
腸炎の症状が出ているとき、医師はこの検査を行い、細菌による感染かどうかを確認します。陽性となった場合は、原因菌の特徴に合った治療薬を検討する流れにつながります。
寄生虫卵検査
国内ではあまり多く見られませんが、海外旅行や特定の水・食物を摂取した経験がある方においては、寄生虫の感染がゼロとは言い切れません。
寄生虫卵検査では、便を顕微鏡で観察し、回虫や鉤虫、原虫などの卵や虫体を探します。感染が確認されると、その寄生虫に応じた駆虫薬の使用を考慮します。
以下のような要素をチェックしながら、寄生虫の有無を判断します。
| チェック項目 | 具体例 |
|---|---|
| 肉眼的観察 | 便の表面に虫体が見えるか |
| 顕微鏡下観察 | 便を薄く広げ、卵やシスト(嚢子)を確認する |
| 追加染色法 | 特殊染色で微小な寄生虫や原虫を検出する |
腹痛や下痢が長引く場合、渡航歴や食事歴など生活背景を踏まえて、寄生虫が原因になっているかどうかを疑う必要があるため、この検査が行われることがあります。
便中カルプロテクチン
カルプロテクチンとは、白血球由来のタンパク質の一種で、腸管に炎症が生じると便中に増加しやすい性質があります。
潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患、あるいは感染性腸炎でも上昇しやすいため、便中カルプロテクチン検査は腸管の炎症度を客観的に評価する指標として役立ちます。
血液検査だけでは腸内の炎症を正確に把握しづらい場合にも、補助的な意味合いで医師が選択するケースがあります。
検査前の準備と採便方法
糞便検査を正確に行うには、検査前の準備や採便時の注意点が大切です。食事制限が必要な検査もあれば、常用薬を調整する場面があるなど、検査項目によって差があります。
この章では、主な注意点や具体的な採便方法を説明します。
食事に関する留意点
便潜血検査のように、特定の検査では採便前数日間の食事に気をつけるよう指示される場合があります。
赤身の肉や鉄分を多く含むサプリメントを多量に摂取すると、化学的な反応で便潜血検査に影響が出ることがあるためです。
ただし免疫学的便潜血検査の場合は、かつて主流だった化学的便潜血検査ほど厳しい食事制限を課すことは少なくなっています。
いずれにしても医師からの説明をよく聞き、指示された範囲で無理のない調整を行うことが大切です。
採便のタイミング
便を採取するタイミングは、検査目的や検査項目によって異なる場合があります。医師やスタッフは具体的な回数や期間を案内するので、その指示に従うことが望ましいです。
たとえば便潜血検査では、別の日に採取した2回分の便が必要となる場合があります。
腸内細菌培養を行うときは、抗生物質を服用していない状態が求められることもあるため、服薬歴などを事前に確認しておくほうが安全です。
下の一覧に、採便のタイミング例を挙げます。
- 便潜血検査:指示された期間内に2回採便するよう案内を受けることが多い
- 便中細菌培養:抗生物質の服用が終了してから数日後に採取するよう案内されるケースがある
- 便中カルプロテクチン:腸の炎症状態を反映するため、症状が強い時期を狙って採便する場合もある
採取容器の扱いと保存方法
採便容器には、通常スプーンのような道具が付属します。便に直接触れることを避けたい場合は、使い捨て手袋やラップを活用するのも方法のひとつです。
便を容器に入れるときは、多すぎず少なすぎず、検査機関や医師の指示する量に合わせる必要があります。
また、細菌培養や寄生虫卵検査などでは、採取後の便を温度管理したまま持参するといった要件があることもあります。
以下は採便容器の取り扱い例です。
| 工夫点 | 具体的な例 |
|---|---|
| 手指の衛生 | 採便前後にはしっかり石けんで手を洗う |
| 異物混入の防止 | ラップをトイレの便座に敷いて便を受け止めるなどして便器の水が混ざらないようにする |
| 採取後の保管温度 | 便中細菌培養や寄生虫卵検査の場合、常温保管か低温保管かの指定を守る |
| 容器のラベル管理 | 複数の検査を行う場合は、混乱しないように名前と日時をしっかり記入する |
受診前の段階で自宅で採便を行い、すぐに提出できない場合は、冷蔵庫などの涼しい場所に保管するよう求められることがあります。
ただし、検査によって保存方法が異なるため、スタッフの案内をよく確認することが重要です。
注意点とトラブル対策
自宅での採便は慣れない作業でもあり、予想外のトラブルを感じる方もいます。例えば、便が思うように採れなかったり、採便容器に入れすぎてうまく閉じられなかったりといったことが起こります。
医療機関から事前に配布された説明資料や口頭指導を参考にしながら落ち着いて作業することがポイントです。万が一不明点があれば、再度問い合わせるなどして、安全かつ正確な手順を守りましょう。
検査結果の見方とその後の対応
糞便検査の結果は、医師が最終的に判断し、ほかの検査結果と合わせて総合的に解釈します。そのため、数値だけを見て自己判断するのは危険です。
この章では、一般的な結果の捉え方や次のステップについて整理します。
陰性と陽性、正常値と参考値
便潜血検査や寄生虫卵検査などは、陰性・陽性といった形で示されることが多いです。一方で便中脂肪やカルプロテクチンなどは、測定値が基準の範囲内かどうかを確認します。
基準値は施設や測定方法によってばらつきがありますが、医師がそれを踏まえて解釈します。
結果が基準から外れているからといって、すぐに重大な病気を疑う必要はありませんが、症状やそのほかの検査結果と併せて精密検査が必要になるケースもあります。
以下に、糞便検査の結果例を示します。
| 検査名 | 結果表示の例 | 一般的な判断 |
|---|---|---|
| 便潜血検査 | 陰性 or 陽性 | 陽性の場合、大腸内視鏡検査を追加で行う可能性あり |
| 便中脂肪 | 数値(%, g/day) | 高値の場合、膵や胆道、小腸などの異常を疑う |
| 便中細菌培養 | 菌種名, 菌数の多寡 | 病原菌が多い場合は感染症の治療や制菌剤の選択を検討 |
| 寄生虫卵検査 | 陰性 or 寄生虫卵確認 | 寄生虫卵があれば、種類に応じて駆虫薬や生活指導を検討 |
| 便中カルプロテクチン | 数値(μg/gなど) | 炎症性腸疾患が疑われる場合、内視鏡検査で粘膜状態を調べる |
次のステップとして考えられる検査
糞便検査の結果が疑わしい時や、腸の状態をより詳しく調べたい時には、大腸内視鏡検査や腹部CT、血液検査などを組み合わせることがあります。
たとえば便潜血検査で陽性となり、かつ腹部症状がある場合、医師は大腸内視鏡検査を提案することが多いです。
また便中カルプロテクチンが高めで、炎症性腸疾患が疑われるケースでは、内視鏡で実際に腸の粘膜を観察し、組織を採取する可能性があります。
必要に応じた医療機関の受診
糞便検査の結果から、消化器疾患や腸内細菌バランスの崩れなどが判明すると、診療科の選択も考えねばなりません。消化器内科でさらに精密検査を行い、適切な治療に進むことが大切です。
たとえば感染症が確認された場合、抗菌薬や整腸薬の処方が必要ですし、炎症性腸疾患が疑われれば専門の治療方針を検討します。
もし不安が続くようであれば、早めにお近くの医療機関に相談するのが望ましいです。
再検査が求められる場合
便潜血検査で一時的に陽性が出たものの、その後に何も異常が見つからないことや、便中細菌培養で要疑義の結果が得られたケースでは、再検査を実施することがあります。
特に採便方法や保存状態が適切でなかった可能性がある場合、正確な結果を得るために再度の提出を求められることもあります。その際は、採便手順や保管方法などを再確認して正しく行うよう意識してください。
糞便検査からわかる主な疾患と留意点
糞便検査の結果が一定の範囲を外れると、さまざまな消化器系の疾患を示唆します。体質や生活習慣によっても影響は異なるため、結果の解釈には総合的な視点が欠かせません。
ここでは主に異常値から疑われることの多い疾患例を取り上げます。
炎症性腸疾患(IBD)
潰瘍性大腸炎やクローン病などのIBDは、便潜血検査や便中カルプロテクチンで異常が出ることがしばしばあります。これらの病気は腸内に慢性的な炎症を生じさせ、下痢や腹痛、血便などが続きやすいです。
糞便検査だけで診断を確定するのは難しいですが、炎症の程度を把握する目安として役立ちます。
以下の一覧は、IBDの特徴的な症状や合併症です。
- 腹痛や下痢が長期にわたって続く
- 血便や粘液便が見られる
- 発熱や倦怠感など全身症状が起こる
- 関節炎や皮膚症状といった腸以外の合併症が生じることもある
大腸ポリープ・大腸がん
便潜血検査で陽性となり、内視鏡検査を行った結果として大腸ポリープや大腸がんが見つかるケースがあります。
大腸ポリープは良性の場合でも、放置するとがん化するリスクがあるため、必要に応じて切除を検討することが一般的です。
大腸がんに関しては早期発見が治療成績を左右しやすいため、便潜血検査の受診や定期的な健診が重要とされています。
吸収不良症候群
小腸や膵臓、胆道に問題があって必要な栄養素を吸収できない状態を、吸収不良症候群と呼びます。便中脂肪量が増加するステアトリア(脂肪便)が代表的なサインです。
たとえば慢性膵炎による酵素不足や、胆汁酸の分泌障害などさまざまな原因が考えられます。
この場合、脂溶性ビタミンの欠乏など栄養面での影響も無視できないので、医師は血液検査や画像検査などを追加して詳しく探る必要があります。
| 主な原因 | 具体例 |
|---|---|
| 膵臓の消化酵素不足 | 慢性膵炎や膵がんなどによって酵素分泌が減少する |
| 胆汁酸の分泌・流出障害 | 胆石症や胆汁うっ滞によって脂質の乳化が十分に行えない |
| 小腸粘膜の機能障害 | セリアック病やクローン病などで絨毛が傷つく |
| 細菌の過剰繁殖 | 小腸内細菌異常増殖症(SIBO)などで吸収が阻害される |
感染症
サルモネラ属菌や腸炎ビブリオなど食中毒を引き起こす病原菌が便中細菌培養で発見されると、急性の腸炎が疑われます。この場合は嘔吐や発熱、激しい下痢が一緒に起こるケースが多く見られます。
適切な抗菌薬や対症療法によって症状を抑え、脱水などの二次的な問題を防ぐことが求められます。
また海外旅行後に寄生虫卵検査で陽性になった際には、原因となる寄生虫に合わせた駆虫薬や栄養管理が必要になることがあります。
消化器以外の病気との関係
糞便検査の異常は、消化器系以外の全身性疾患を示唆する場合もあります。慢性疾患によって栄養障害が生じ、便に特徴的なパターンが表れることもあるため、総合的な医療機関での評価が有用です。
医師の判断により内科や外科、専門外来などと連携しながら対処していくと安心です。
よくある質問
糞便検査に関しては、事前の準備や検査の手順などで疑問を抱える方が多いです。ここでは質問とそれに対する回答をまとめます。
- Q糞便検査は痛みや不快感がありますか?
- A
基本的に採便は自宅で行い、肛門にカメラなどを挿入するわけではないので、痛みはありません。ただ慣れない手順に戸惑うことはあるかもしれませんが、説明書どおりに行えば安全です。
- Q結果が出るまでどれくらい時間がかかりますか?
- A
便潜血や便中カルプロテクチンなど、迅速に結果を出せる項目は数日から1週間ほどかかるのが一般的です。
便中細菌培養や寄生虫卵検査は培養や顕微鏡検査に時間を要するため、もう少し日数がかかることがあります。
- Q検査に麻酔や鎮静は必要ですか?
- A
糞便検査そのものは、麻酔や鎮静を使用しません。肛門から直接検体を採取するような場面(直腸診など)でも、通常は軽い潤滑剤を塗布するだけなので、麻酔の必要がほとんどありません。
- Q保険は適用されますか?
- A
便潜血検査を含めた多くの糞便検査は、医師の判断で行う場合、健康保険の対象となります。
ただし検査目的が自由診療にあたるときは適用外になることがあるため、費用面を知りたい場合は医療機関へ事前に相談してください。
- Qどのくらいの頻度で検査を行うべきでしょうか?
- A
症状や既往歴、年齢などにより変わります。定期健診や生活習慣病健診の一環として年に1回程度行う場合もあります。
特定の症状がある場合や消化器疾患の既往がある場合は、医師の指示を優先し、適切な間隔で検査を受けると安心です。
以上