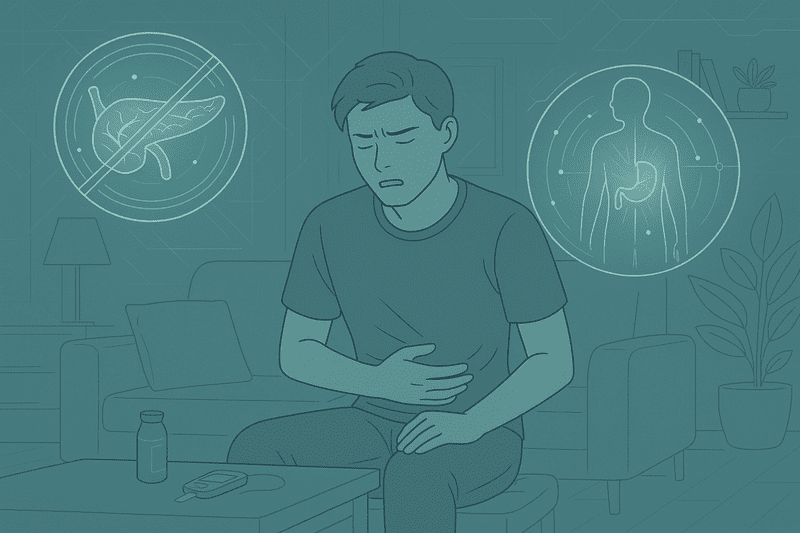「インスリンが出ない」または「インスリンが出ないとどうなるのか」と不安に感じていませんか?
インスリンは、私たちの体がエネルギーを正常に利用するために必要不可欠なホルモンです。
もしインスリンが出ない、あるいはその働きが著しく低下すると、血糖値が異常に高くなるだけでなく、体はエネルギー源を求めて脂肪を分解し始めます。
その結果、血液が酸性に傾く「糖尿病ケトアシドーシス」という、命に関わる危険な状態を引き起こすことがあります。
この記事では、インスリンの役割から、インスリンが出ない状態がもたらす影響、特に危険な糖尿病ケトアシドーシスの症状や原因について詳しく解説します。
インスリンとは?体内でどのような役割を果たしているのか
インスリンは、膵臓の「ランゲルハンス島」という組織にあるβ細胞から分泌されるホルモンの一種です。
食事によって血糖値(血液中のブドウ糖濃度)が上昇すると、それを感知してインスリンが分泌されます。インスリンは、私たちの体にとって非常に重要な役割を担っています。
血糖値を下げる唯一のホルモン
私たちの体内には血糖値を上げるホルモン(グルカゴン、アドレナリン、コルチゾールなど)は複数存在しますが、血糖値を下げる方向に作用するホルモンはインスリンだけです。
食事をすると、食べ物に含まれる炭水化物が消化・吸収されてブドウ糖となり、血液中に入って血糖値が上がります。
インスリンはこのブドウ糖を体の細胞が利用できるように手助けし、結果として血糖値を適切な範囲内に保ちます。
血液中のブドウ糖をエネルギー源として細胞に取り込む
インスリンの最も重要な働きのひとつが、血液中のブドウ糖を筋肉や脂肪、肝臓などの細胞に取り込ませることです。インスリンは、細胞の表面にある「インスリン受容体」に鍵と鍵穴のように結合します。
すると、細胞はブドウ糖を取り込むための「扉(糖輸送担体)」を開き、ブドウ糖を細胞内に引き入れます。細胞に取り込まれたブドウ糖は、私たちが活動するためのエネルギー源として利用されます。
インスリンが出ないと、この「扉」がうまく開かなくなり、ブドウ糖が細胞に入れず血液中に溢れてしまいます。
インスリンの主な役割のまとめ
| 役割 | 具体的な働き | 影響 |
|---|---|---|
| 血糖値の調節 | 血液中のブドウ糖を細胞に取り込ませる | 血糖値を適切な範囲に下げる |
| エネルギー供給 | ブドウ糖をエネルギー源として利用させる | 体の細胞が活動エネルギーを得る |
| 貯蔵 | 余ったブドウ糖を肝臓や筋肉でグリコーゲンとして蓄える | エネルギーを貯蓄する |
肝臓での糖新生や脂肪の分解を抑制する
インスリンは、エネルギーの「利用」と「貯蔵」を促進するだけでなく、「放出」を抑制する働きも持っています。
具体的には、肝臓でアミノ酸などから新たにブドウ糖が作られる「糖新生」という働きや、蓄えられた脂肪が分解されてエネルギー源として放出されるのを抑えます。
インスリンが正常に働いていると、体はまず血液中のブドウ糖を優先的に使い、不必要な糖新生や脂肪分解が起こらないように調節されます。
しかし、インスリンが出ないと、この抑制が効かなくなり、体は「エネルギーが足りない」と勘違いしてしまいます。
インスリンが出ないとはどういう状態?
「インスリンが出ない」という状態には、いくつかの異なる背景があります。
インスリンの分泌が全くなくなってしまう場合から、分泌量が減る場合、あるいは分泌はされていてもその効果が十分に発揮されない場合まで様々です。
インスリン分泌が絶対的に不足する(主に1型糖尿病)
これは、インスリンを分泌する膵臓のβ細胞そのものが、何らかの原因(多くは自己免疫)によって破壊されてしまう状態です。
β細胞が壊れると、インスリンを物理的に作れなくなるため、インスリンの分泌量が極端に減少するか、全く出なくなってしまいます。
これが「インスリン依存状態」であり、1型糖尿病の典型的な病態です。この場合、体外からインスリンを補給する治療(インスリン注射)が生命維持に必要です。
インスリンの効きが悪くなる(インスリン抵抗性)
これは、インスリン自体は分泌されているものの、その作用する先の細胞(筋肉や肝臓など)がインスリンに対して鈍感になり、うまく反応できなくなっている状態です。
「インスリン抵抗性」と呼ばれます。体は血糖値を下げようと、膵臓が頑張って通常より多くのインスリンを分泌しようとします(高インスリン血症)。
肥満や運動不足、ストレスなどが主な原因と考えられており、2型糖尿病の初期によく見られます。この段階では「インスリンが出ない」わけではありませんが、インスリンの働きが悪い状態です。
インスリン不足の主なタイプ
| タイプ | インスリン分泌 | 主な原因 | 関連する糖尿病の型 |
|---|---|---|---|
| 絶対的不足 | 極端に少ない、または全く出ない | 膵臓β細胞の破壊(自己免疫など) | 主に1型糖尿病 |
| 相対的不足 | 需要に対して不足(分泌遅延・低下) | 膵臓β細胞の疲弊 | 主に2型糖尿病 |
| インスリン抵抗性 | 分泌されている(むしろ過剰なことも) | 肥満、運動不足、遺伝的要因 | 主に2型糖尿病 |
インスリン分泌が相対的に不足する(主に2型糖尿病)
インスリン抵抗性が続くと、膵臓はインスリンを多く分泌しようと働き続けます。しかし、その状態が長く続くと膵臓のβ細胞が疲弊してしまい、次第に十分な量のインスリンを分泌できなくなってきます。
また、食後の血糖値上昇に対してインスリンが素早く分泌される「初期分泌」が遅れることもあります。
このように、インスリン抵抗性によって必要なインスリン量が増えているのに対し、実際の分泌量が追いつかなくなった状態を「相対的不足」と呼びます。
これは進行した2型糖尿病で見られる状態です。
インスリンが出ないとどうなる?体に起こる深刻な変化
インスリンが絶対的に、あるいは相対的に不足すると、体はエネルギー源であるブドウ糖を正常に利用できなくなります。その結果、体に様々な深刻な変化が起こります。
「インスリンが出ないとどうなるのか」、その具体的な影響を見ていきましょう。
血糖値が異常に高くなる(高血糖)
インスリンが出ない、または効かないと、血液中のブドウ糖は細胞の中に入ることができません。
さらに、肝臓での糖新生やグリコーゲンの分解が抑制されなくなるため、肝臓からも血液中にブドウ糖が放出され続けます。
食事から摂取したブドウ糖と、肝臓で作られたブドウ糖の両方が血液中に溢れかえり、血糖値は異常な高値(例:300mg/dL以上、時には1000mg/dLを超えることも)を示します。
これが「高血糖」状態です。
高血糖で起こる主な症状
| 症状 | 原因 |
|---|---|
| 口渇・多飲 | 高血糖による脱水。体は水分を欲します。 |
| 多尿・頻尿 | 血糖値が一定以上(約160〜180mg/dL)になると尿中に糖が漏れ出し、その際に水分も一緒に排出されます。 |
| 体重減少 | ブドウ糖をエネルギーとして利用できず、代わりに筋肉や脂肪が分解されるためです。 |
| 全身倦怠感 | 細胞がエネルギー不足に陥るためです。 |
細胞がエネルギー不足に陥る
血液中にはブドウ糖が溢れているにもかかわらず、インスリンがないために細胞はそのブドウ糖を取り込むことができません。
体全体が「飢餓状態」に陥っているのと同じです。特に、エネルギーを多く消費する筋肉細胞や脳細胞が正常に機能しにくくなります。これが、高血糖の際に強い倦怠感や疲労感を感じる大きな理由です。
脂肪の分解が亢進しケトン体が増加する
ブドウ糖を利用できない体は、代わりのエネルギー源を確保しようとします。
インスリンには脂肪の分解を抑制する働きがありましたが、インスリンが出ないとこの抑制が解除され、体内の脂肪組織が急速に分解され始めます。
分解された脂肪(遊離脂肪酸)は肝臓に運ばれ、そこで「ケトン体」という物質に作り替えられます。
ケトン体は、ブドウ糖が使えない時のための代替エネルギー(特に脳にとって重要)ですが、インスリンが極度に不足した状態では、このケトン体が過剰に作られすぎてしまいます。
危険な合併症「糖尿病ケトアシドーシス(DKA)」とは
インスリンが極度に出ない状態が続くと、高血糖と高ケトン体血症が同時に進行し、「糖尿病ケトアシドーシス(DKA)」という非常に危険な状態に陥ります。
これは糖尿病の急性合併症の一つであり、緊急の治療が必要です。
糖尿病ケトアシドーシスの概要
糖尿病ケトアシドーシスは、インスリンの著しい不足によって引き起こされます。
ブドウ糖が利用できず、代わりに脂肪が急速に分解された結果、血液中にケトン体(アセトン、アセト酢酸、β-ヒドロキシ酪酸)が蓄積します。
ケトン体は酸性の物質であるため、血液中に増えすぎると血液全体が酸性に傾いてしまいます。この状態を「アシドーシス」と呼びます。
高血糖による脱水と、アシドーシスが組み合わさった深刻な状態が、糖尿病ケトアシドーシスです。
命に関わる緊急性の高い状態
糖尿病ケトアシドーシスは、治療が遅れれば命を落とす可能性のある緊急事態です。
高血糖による極度の脱水は、血液の循環を悪化させ、腎臓の機能を低下させます。また、アシドーシスが進行すると、体内の様々な酵素や臓器が正常に働かなくなり、呼吸困難や意識障害を引き起こします。
発見が遅れると、昏睡状態に陥ることも少なくありません。
糖尿病ケトアシドーシスの危険なサイン
| 分類 | 危険なサイン | 概要 |
|---|---|---|
| 高血糖 | 極度の口渇、多飲、多尿 | 体内の水分が大量に失われ、脱水が進行します。 |
| アシドーシス | 吐き気、嘔吐、腹痛 | 消化器症状が強く出ることがあります。 |
| アシドーシス | 深く大きな呼吸(クスマウル大呼吸) | 体をアルカリ性に戻そうと、酸性の原因物質(二酸化炭素)を必死に排出しようとする呼吸です。 |
| アシドーシス | 呼気のアセトン臭(果物様、甘酸っぱい匂い) | ケトン体の一種であるアセトンが呼気中に排出されるためです。 |
| 重症化 | 意識障害、傾眠、昏睡 | 脳機能が著しく低下しているサインです。 |
1型糖尿病患者に特に多いが2型糖尿病でも起こり得る
糖尿病ケトアシドーシスは、インスリンが絶対的に不足しやすい1型糖尿病の患者さんが発症するケースが最も多いです。
1型糖尿病の診断時に初めてケトアシドーシスで発見されることもありますし、インスリン注射を自己判断で中断してしまった場合などにも起こります。
しかし、2型糖尿病の患者さんでも発症することがあります。
特に、感染症や他の病気(シックデイ)にかかった時や、手術、強いストレスがかかった時、あるいは「清涼飲料水ケトーシス(ペットボトル症候群)」と呼ばれる状態では、インスリンの必要量が急激に増大し、相対的なインスリン不足が深刻化してケトアシドーシスを引き起こすことがあります。
糖尿病ケトアシドーシスの主な症状
糖尿病ケトアシドーシスは、その進行度によって様々な症状が現れます。初期症状を見逃さず、重症化する前に対処することが非常に重要です。
インスリンが出ないとどうなるか、その具体的な症状のサインを知っておきましょう。
初期症状(喉の渇き、多飲、多尿、倦怠感)
初期の段階では、著しい高血糖による症状が中心となります。血糖値が上がることで喉が異常に渇き、大量の水分を欲するようになります(多飲)。それに伴い、尿の量や回数が非常に増えます(多尿)。
また、細胞がエネルギー不足に陥っているため、体全体が重く、強いだるさ(倦怠感)を感じます。
この段階では、単なる夏バテや疲れと勘違いしてしまうこともありますが、糖尿病の既往がある方や、急激な体重減少がある場合は特に注意が必要です。
糖尿病ケトアシドーシスの症状の進行
| 進行度 | 主な症状 |
|---|---|
| 初期 | 極度の口渇、多飲、多尿、全身倦怠感、体重減少 |
| 中等症 | 吐き気、嘔吐、腹痛、食欲不振 |
| 重症 | 深く大きな呼吸(クスマウル大呼吸)、呼気のアセトン臭、意識障害、昏睡 |
進行した場合の症状(吐き気、嘔吐、腹痛)
病状が進行し、ケトン体が増加してアシドーシスが始まると、消化器系に症状が現れ始めます。強い吐き気や、何度も嘔吐を繰り返すことがあります。
また、原因不明の腹痛(時には激痛)を伴うこともあり、虫垂炎などの他の消化器疾患と間違われることさえあります。
水分や食事を全くとれなくなり、脱水と栄養失調がさらに悪化するという悪循環に陥ります。
重症化した場合(呼吸困難、意識障害、昏睡)
アシドーシスがさらに重症化すると、体は血液の酸性を何とか中和しようと必死になります。その結果、「クスマウル大呼吸」と呼ばれる、深くて大きな、荒い呼吸が見られるようになります。
これは、酸性の原因となる二酸化炭素を肺からできるだけ多く排出しようとする体の防御反応です。
この段階になると、意識が朦朧としたり(傾眠)、呼びかけに反応しなくなったり(意識障害)、最終的には昏睡状態に陥り、命の危険が差し迫ります。
特徴的な呼気(アセトン臭・果物のような甘酸っぱい匂い)
糖尿病ケトアシドーシスに特徴的な所見として、呼気からアセトン(ケトン体の一種)の匂いがすることがあります。
これは「アセトン臭」と呼ばれ、よく「果物が腐ったような匂い」「甘酸っぱい匂い」「マニキュアの除光液のような匂い」と表現されます。
もし、高血糖の症状とともに、本人や周囲の人がこのような匂いに気づいた場合は、ケトアシドーシスを強く疑う必要があります。
ケトアシドーシスを疑う症状
- 普段と比べて極端に喉が渇く
- 吐き気や嘔吐が続く
- お腹が痛い
- 呼吸が荒く、甘酸っぱい匂いがする
- 意識がぼんやりする
糖尿病ケトアシドーシスの原因
糖尿病ケトアシドーシスは、インスリンの作用が極度に不足することで引き起こされます。
その引き金となる原因は様々ですが、インスリン治療中の方にとっても、そうでない方にとっても知っておくべき重要な要因があります。
インスリン注射の中断や不足
1型糖尿病の患者さんや、インスリン治療中の2型糖尿病の患者さんにとって、これが最も重大な原因です。
インスリン注射は生命維持に必要です。「食事がとれないから」あるいは「自己判断で」インスリン注射を中断してしまうと、体内のインスリンが急速に枯渇し、数時間から数日でケトアシドーシスを発症する可能性があります。
また、インスリンポンプのトラブル(チューブの閉塞や外れ)や、インスリン製剤の劣化(高温での放置など)によって、適切にインスリンが投与されていない場合も同様のリスクがあります。
感染症や他の病気(シックデイ)
糖尿病の患者さんが、風邪、インフルエンザ、肺炎、尿路感染症などの感染症にかかったり、他の病気を併発したり(胃腸炎、心筋梗塞、脳卒中など)、発熱したりした場合を「シックデイ(病気の日)」と呼びます。
このようなシックデイでは、体は病気と闘うために血糖値を上げるホルモン(ストレスホルモン)を多く分泌します。その結果、インスリンの必要量が普段よりも大幅に増加します。
普段通りのインスリン量では足りなくなり、インスリン不足に陥ってケトアシドーシスを引き起こすことがあります。
シックデイの主な例
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 感染症 | 風邪、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、尿路感染症、膀胱炎 |
| 消化器系 | 胃腸炎(嘔吐、下痢)、胆嚢炎、膵炎 |
| その他 | 高熱、心筋梗塞、脳卒中、強い歯痛 |
過度なストレスや外傷、手術
感染症と同様に、強い精神的ストレス、大きな怪我(外傷)、あるいは手術なども、体にとっては大きな負担(ストレス)となります。
これらのストレスは、血糖値を上げるホルモンの分泌を促し、インスリンの必要量を増加させます。その結果、相対的なインスリン不足が生じ、ケトアシドーシスの引き金となることがあります。
ケトアシドーシスを誘発する可能性のある薬剤
| 薬剤の種類 | 主な作用 | 注意点 |
|---|---|---|
| ステロイド薬 | 炎症を抑えるが、血糖値を上げる作用がある | 高用量の使用時にインスリン需要が増大します。 |
| SGLT2阻害薬 | 尿中に糖を排泄させる糖尿病治療薬 | 血糖値が高くなくてもケトアシドーシス(正常血糖ケトアシドーシス)を起こすことが報告されています。 |
糖分の過剰摂取や清涼飲料水の多飲(ペットボトル症候群)
これは特に、糖尿病と診断されていない若い人や、2型糖尿病の軽症例でも起こりうる原因として注意が必要です。
喉の渇きに任せて、糖分を多く含む清涼飲料水やスポーツドリンク、ジュースなどを大量に飲み続けると(1日に数リットルなど)、血糖値が急激かつ著しく上昇します。
膵臓のインスリン分泌能力がその急激な糖負荷に追いつかなくなり、インスリンが相対的に枯渇し、ケトアシドーシスを発症することがあります。
これは「清涼飲料水ケトーシス」または「ペットボトル症候群」と呼ばれています。
糖尿病ケトアシドーシスが疑われる場合の対処法
糖尿病ケトアシドーシスは、放置すれば命に関わる緊急事態です。インスリンが出ないとどうなるか、その最悪の事態がケトアシドーシスです。
もし、ご自身やご家族に前述のような症状(強い喉の渇き、吐き気、嘔吐、腹痛、意識が朦朧とするなど)が見られた場合、迅速な対応が必要です。
すぐに医療機関を受診する
糖尿病ケトアシドーシスが疑われる症状があれば、様子を見ることは非常に危険です。直ちに医療機関(かかりつけの糖尿病内科、または救急外来)に連絡し、受診してください。
受診の際は、「糖尿病があること(またはその疑いがあること)」「いつからどのような症状があるか」「インスリン治療中かどうか」「食事がとれているか」などを具体的に伝えてください。
救急受診の目安
- 吐き気や嘔吐が止まらない
- 水分を全く受け付けない
- 意識がはっきりしない、呼びかけへの反応が鈍い
- 呼吸が荒く、苦しそう
- 血糖値が300mg/dL以上で、尿ケトン体陽性が続く
自己判断でインスリンを調整しない
インスリン治療中の方がシックデイなどで高血糖になった場合、インスリンの増量が必要なケースが多いですが、その調整は非常に専門的な判断を要します。
特に、ケトアシドーシスが疑われるような状態では、自己判断での調整は危険を伴います。インスリン注射を自己判断で中断するのは絶対に避けてください。
まずはかかりつけ医に連絡し、指示を仰ぐことが最も安全です。
意識障害がある場合は救急車を要請する
もし、呼びかけに応えない、意識が朦朧としている、けいれんを起こしているなどの重篤な状態が見られる場合は、ためらわずにすぐに119番通報し、救急車を要請してください。
電話口で「糖尿病で意識がおかしい(または、意識がない)」こと、「糖尿病ケトアシドーシスの可能性がある」ことを明確に伝えてください。
よくある質問
- Qインスリンが出ているか自分で確認する方法はありますか?
- A
インスリンがどの程度出ているかを正確に知るには、医療機関での血液検査(空腹時のインスリン値やCペプチド値、糖負荷試験など)が必要です。
自分で「インスリンが出ない」状態を直接確認することは困難です。
ただし、血糖値が異常に高い(例えば食後でもないのに250mg/dLを超えるなど)状態が続く場合は、インスリンが不足しているか、効きが悪くなっている可能性が非常に高いと考えられます。
- Q糖尿病ケトアシドーシスは予防できますか?
- A
はい、適切な自己管理によって予防は可能です。1型糖尿病やインスリン治療中の方は、医師の指示通りにインスリン注射を継続することが最も重要です。
また、シックデイ(病気の日)の対応方法(インスリン量の調整や水分補給、どのような場合に受診するか)をあらかじめ主治医と確認しておくことが大切です。
2型糖尿病の方や糖尿病予備群の方は、清涼飲料水の多飲を避け、バランスの取れた食事と運動を心がけ、良好な血糖コントロールを維持することが予防につながります。
- Q1型糖尿病と診断されたらインスリン注射は一生必要ですか?
- A
1型糖尿病は、膵臓のβ細胞が破壊され、インスリンを自分で作り出す能力が失われてしまう病気です。現在の医療では、失われたβ細胞の機能を完全に取り戻す治療法は確立されていません。
そのため、体外からインスリンを補うインスリン治療が生きていくために継続して必要となります。
インスリン治療は、不足しているホルモンを補うためのものであり、血糖値をコントロールし、ケトアシドーシスのような危険な状態を防ぎ、健康な生活を送るために不可欠な治療です。
- Qインスリンが出ないと必ず糖尿病ケトアシドーシスになりますか?
- A
インスリンの分泌が「全く出ない」状態(1型糖尿病など)を放置すれば、高確率で糖尿病ケトアシドーシスを発症します。
一方、2型糖尿病のように「出ているが効きが悪い(インスリン抵抗性)」あるいは「分泌量が減っている(相対的不足)」状態では、すぐにケトアシドーシスになるわけではありません。
多くの場合、まずは高血糖による合併症(神経障害、網膜症、腎症など)がゆっくりと進行します。
ただし、前述したように、感染症やストレス、清涼飲料水の多飲などが引き金となり、2型糖尿病でもケトアシドーシスを発症することがありますので、注意が必要です。