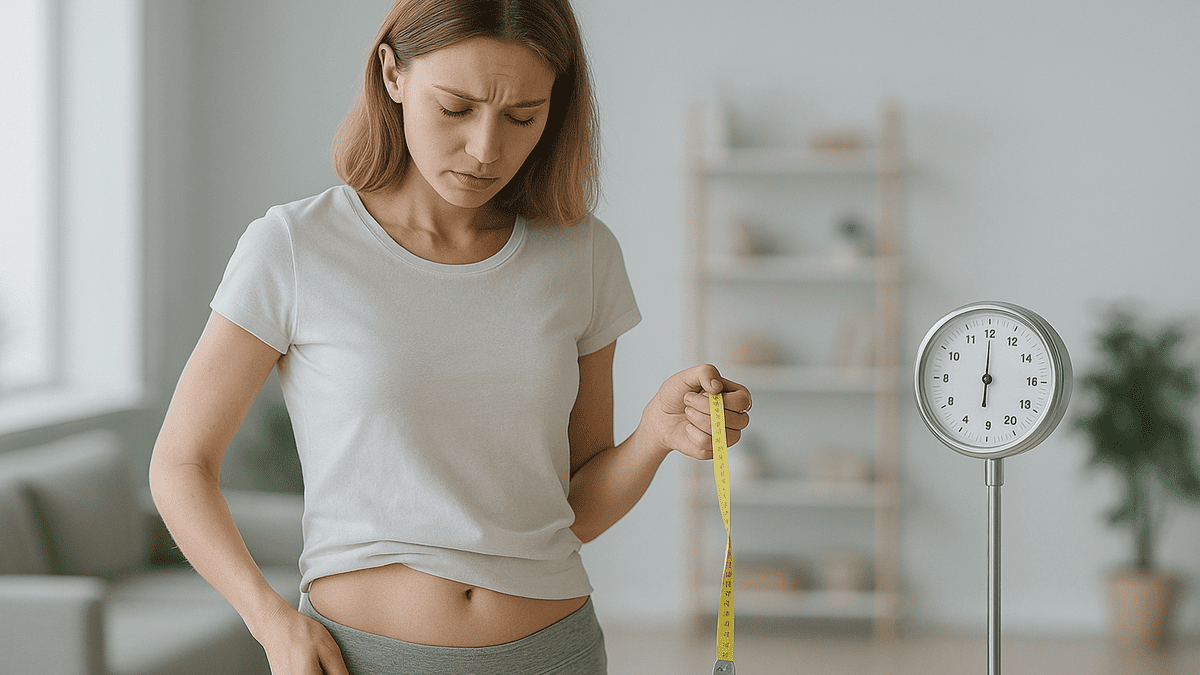「1型糖尿病と診断される前に急に体重が減った」「治療を始めたら体重が増えてきて不安」といった経験はありませんか。
1型糖尿病では、病気そのものの影響や治療によって体重が大きく変動することがあります。
この記事では1型糖尿病で体重が減少する根本的な理由から治療開始後の体重変化、そして健康的な体重を維持するための栄養管理と食事のポイントについて詳しく解説します。
正しい知識を身につけ、ご自身の体と向き合い、前向きな治療を続けるための一助としてください。
1型糖尿病で体重が減少する主な理由
診断前に急激な体重減少を経験する方は少なくありません。これはインスリンが極度に不足することで、体がエネルギーを正常に利用できなくなるために起こります。
インスリン不足によるエネルギー利用の障害
インスリンの最も重要な働きのひとつは血液中のブドウ糖を細胞に取り込み、エネルギーとして利用できるようにすることです。
1型糖尿病ではこのインスリンが分泌されなくなるため、食事から摂取した糖をエネルギーに変えることができません。細胞がエネルギー不足の飢餓状態に陥ります。
インスリンの働きと不足時の影響
| 項目 | インスリンが正常に働く場合 | インスリンが不足した場合 |
|---|---|---|
| ブドウ糖の行方 | 細胞に取り込まれ、エネルギーになる | 細胞に入れず、血液中に溢れる(高血糖) |
| 体のエネルギー源 | 主にブドウ糖を利用する | ブドウ糖が使えず、代替エネルギーを探す |
| 体重への影響 | 摂取した栄養がエネルギーとして使われ、維持される | 栄養が使えず、体重が減少する |
糖の尿中排泄(尿糖)
細胞が利用できなかったブドウ糖は血液中に溜まり、高血糖状態となります。
血糖値が一定のレベル(通常160~180mg/dL)を超えると、腎臓から尿の中へ糖が漏れ出てきます。これが「尿糖」です。
本来エネルギーになるはずだった糖が水分と一緒に体外へ排出されてしまうため、カロリーが失われ体重減少の一因となります。
筋肉や脂肪の分解
体はエネルギー源であるブドウ糖を使えないため、代わりのエネルギー源として体に蓄えられている脂肪や筋肉のたんぱく質を分解し始めます。
この体の組織の分解が急激な体重減少の直接的な原因となります。特に筋肉量が減ると基礎代謝も低下し、体力の低下にもつながります。
「痩せ」が示す危険なサイン
1型糖尿病による体重減少は、単に「痩せる」というだけでなく、体が危険な状態にあることを示すサインです。
特に注意が必要なのが「糖尿病ケトアシドーシス(DKA)」です。
糖尿病ケトアシドーシス(DKA)のリスク
脂肪が急激に分解されると、「ケトン体」という酸性の物質が血液中に増えます。このケトン体が過剰に蓄積し、血液が酸性に傾いた状態が糖尿病ケトアシドーシスです。
意識障害や昏睡に至ることもある、命に関わる危険な状態です。
DKAの主な症状
| 症状の分類 | 具体的なサイン |
|---|---|
| 初期症状 | 極度の口渇、多飲、多尿、体重減少 |
| 進行時の症状 | 強い倦怠感、吐き気、嘔吐、腹痛 |
| 危険なサイン | 深く大きい呼吸(クスマウル呼吸)、息が果物のような甘酸っぱい匂いがする |
栄養失調と体力低下
エネルギーが利用できず、筋肉が分解される状態が続くと、体は栄養失調に陥ります。
このことにより、日常生活を送る上での体力が著しく低下し、疲れやすさやだるさを常に感じるようになります。
感染症への抵抗力低下
高血糖状態は白血球の働きを弱め、体の免疫機能を低下させます。また、栄養状態の悪化も抵抗力を下げる要因です。
これらの影響により、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなったり、治りにくくなったりします。
インスリン治療開始後の体重変化
インスリン治療を開始すると、多くの場合、減少した体重が元に戻り始めます。これは治療が順調に進んでいる証拠ですが、一方で体重の増えすぎを心配する声も聞かれます。
なぜ体重が増加に転じることがあるのか
インスリン補充が始まると、これまで利用できなかったブドウ糖が再び細胞のエネルギー源として使えるようになります。また、尿糖として失われていたカロリーも体内に留まるようになります。
さらに、筋肉や脂肪の分解が止まり、体が正常な状態に戻ろうとするため、体重が増加に転じます。
体重増加は「回復の証」
治療開始後の体重増加は体が飢餓状態から脱し、健康を取り戻している過程で起こる自然な現象です。
特に診断前に減少した分の体重が戻るのは、体が正常な水分バランスと栄養状態を回復している証拠と捉えることが大切です。
治療前後の体の変化
| 項目 | 治療前(インスリン不足時) | 治療後(インスリン補充時) |
|---|---|---|
| エネルギー利用 | 糖が利用できず、脂肪・筋肉を分解 | 糖が正常に利用され、分解が停止 |
| 尿糖 | 尿中に糖が排泄され、カロリーが失われる | 尿糖が消失し、カロリーが保持される |
| 体の状態 | 脱水・栄養失調状態 | 正常な水分・栄養状態へ回復 |
過度な体重増加を防ぐ考え方
回復期を過ぎても体重が増え続ける場合は、食事内容やインスリン量が過剰になっている可能性があります。
しかし、体重を気にするあまり自己判断でインスリンを減らすのは非常に危険です。適切な食事管理と運動を通じて健康的な体重維持を目指します。
- 食事内容の見直し(カロリー過多になっていないか)
- インスリン量の再評価(医師との相談)
- 身体活動量の向上
健康的な体重を維持する栄養管理
適切な体重を維持するためにはインスリン療法と合わせた栄養管理が重要です。食事から摂る栄養素が体の構成要素となり、活動の源となります。
カーボカウントの重要性
1型糖尿病の食事管理の基本は、カーボカウントです。食事に含まれる炭水化物量を把握し、それに見合ったインスリン量を投与することで食後の血糖値を安定させます。
このバランスが取れると過剰なインスリン投与による低血糖や、それを補うための過食を防ぎ、体重管理がしやすくなります。
バランスの取れた食事の基本
炭水化物だけでなく、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂取することが、健康な体作りには必要です。
特に筋肉の材料となるたんぱく質は、意識して十分に摂ることが大切です。
栄養バランスを整える食事の構成
| 食事の要素 | 役割 | 主な食品 |
|---|---|---|
| 主食 | 主なエネルギー源(炭水化物) | ごはん、パン、麺類 |
| 主菜 | 筋肉や血液の材料(たんぱく質) | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 副菜 | 体の調子を整える(ビタミン・ミネラル) | 野菜、きのこ、海藻 |
適切なカロリー摂取量の設定
一日に必要なエネルギー量は年齢、性別、身体活動量によって異なります。
医師や管理栄養士と相談し、ご自身の目標体重や活動量に見合ったカロリー摂取量を知ることが体重管理の第一歩です。
食事療法の具体的なポイント
日々の食事で少し工夫するだけで栄養バランスは大きく改善します。ここでは、すぐに実践できる具体的なポイントを紹介します。
主食・主菜・副菜を揃える
毎回の食事でごはんなどの「主食」、肉や魚などの「主菜」、野菜中心の「副菜」を揃えることを意識しましょう。この形を基本にすると自然と栄養バランスが整いやすくなります。
丼ものや麺類などの単品料理を食べる際も、野菜やたんぱく質をプラスする工夫が有効です。
たんぱく質を十分に摂取する
筋肉量を維持し、基礎代謝を保つために、たんぱく質は毎食欠かさず摂りましょう。肉、魚、卵、大豆製品などを偏りなく取り入れるのが理想です。
特に痩せすぎが気になる方は意識してたんぱく質を増やすことが体重回復につながります。
たんぱく質を多く含む食品の例
| 食品カテゴリ | 具体例 | ポイント |
|---|---|---|
| 肉類 | 鶏むね肉、ささみ、赤身肉 | 脂肪の少ない部位を選ぶ |
| 魚介類 | 青魚(サバ、アジ)、白身魚、エビ | 良質な脂質も摂取できる |
| 卵・大豆製品 | 卵、豆腐、納豆、牛乳 | 手軽に取り入れやすい |
間食(補食)の選び方とタイミング
食事と食事の間が長く空く場合や低血糖の予防、体重増加を目指す場合には、間食(補食)が有効です。ヨーグルトや牛乳、おにぎり、ナッツなど栄養価の高いものを選びましょう。
空腹を感じた時にだらだらと食べるのではなく、時間を決めて計画的に摂ることが大切です。
運動療法との連携
食事療法と運動療法を組み合わせることで、より効果的な体重管理が可能になります。運動は血糖コントロールを改善し、筋力を維持する上でも重要です。
体重管理における運動の役割
運動は消費カロリーを増やすだけでなく、インスリンの効果を高める(インスリン感受性を改善する)働きがあります。
このため、少ないインスリンで血糖をコントロールできるようになり、体重管理に繋がりやすくなります。また、心肺機能を高め、気分をリフレッシュさせる効果もあります。
低血糖に注意した運動の進め方
運動中は血糖値が下がりやすいため、低血糖対策が重要です。
運動前には必ず血糖値を測定し、必要であれば補食を摂ります。運動中もブドウ糖などを携帯し、いつでも補食できるように準備しておきましょう。
筋力トレーニングのすすめ
ウォーキングなどの有酸素運動に加えて、筋力トレーニングを取り入れることをお勧めします。筋肉量が増えると基礎代謝が上がり、エネルギーを消費しやすい体になります。
このことは、痩せすぎの改善と過度な体重増加の予防の両方に役立ちます。
運動の種類と主な目的
| 運動の種類 | 主な目的・効果 | 注意点 |
|---|---|---|
| 有酸素運動 | 脂肪燃焼、心肺機能向上 | 比較的長く続けられる強度で行う |
| 筋力トレーニング | 筋肉量増加、基礎代謝アップ | 正しいフォームで行い、無理をしない |
Q&A
最後に、1型糖尿病の体重管理に関してよくある質問にお答えします。
- Q痩せすぎが心配です。どうすれば体重を増やせますか?
- A
まずは、インスリン投与量が適切か、食事からのエネルギー摂取量が十分かを確認することが基本です。
その上で食事の回数を増やしたり、たんぱく質や良質な脂質を含む間食を取り入れたりする方法があります。例えばナッツやチーズ、アボカドなどを食事に加えるのも良いでしょう。
自己判断で進めず、必ず医師や管理栄養士に相談してください。
- Qインスリンを自己判断で減らして体重を調整しても良いですか?
- A
絶対にやめてください。
体重を気にしてインスリンを意図的に減らす行為は「インスリン・オミッション」と呼ばれ、深刻な高血糖や糖尿病ケトアシドーシスを引き起こす大変危険な行為です。
体重のことで悩みがある場合は正直に医療スタッフに打ち明け、安全な方法を一緒に考えましょう。
- Q成長期の子供の体重管理で気をつけることは何ですか?
- A
成長期の子供にとって体重や身長が順調に増えることは非常に重要です。体重増加を恐れて食事を制限することは、健全な発育を妨げる可能性があります。
必要なエネルギーや栄養素をしっかり摂取し、成長曲線に沿って発育しているかを確認しながら、食べる量に見合ったインスリン調整を行うことが基本方針となります。
- Q筋肉をつけたいのですがプロテインを飲んでも良いですか?
- A
適切な食事でたんぱく質が不足している場合には、補助的にプロテインを利用することも選択肢の一つです。
ただし、製品によっては糖質が多く含まれているものもあるため、栄養成分表示をよく確認する必要があります。
また、腎臓に負担がかかる可能性もあるため、使用する前には必ず主治医に相談することが大切です。
まずは食事からたんぱく質を摂ることを基本としましょう。
以上
参考にした論文
SASAKI, Akira, et al. Metabolic surgery in treatment of obese Japanese patients with type 2 diabetes: a joint consensus statement from the Japanese Society for Treatment of Obesity, the Japan Diabetes Society, and the Japan Society for the Study of Obesity. Diabetology international, 2022, 13.1: 1-30.
ARAKI, Eiichi, et al. Japanese clinical practice guideline for diabetes 2019. Diabetology international, 2020, 11.3: 165-223.
HANAMURA, Isaki, et al. Clinical Evaluation of Body Composition, Diet, and Physical Activity in Type 1 Diabetes: A Controlled Cross-Sectional Study. Diabetology, 2025, 6.4: 29.
HANEDA, Masakazu, et al. Japanese clinical practice guideline for diabetes 2016. Diabetology international, 2018, 9.1: 1-45.
NEVILLE, Susan E., et al. Diabetes in Japan: a review of disease burden and approaches to treatment. Diabetes/metabolism research and reviews, 2009, 25.8: 705-716.
TAMURA, Yoshiaki, et al. Nutrition management in older adults with diabetes: a review on the importance of shifting prevention strategies from metabolic syndrome to frailty. Nutrients, 2020, 12.11: 3367.
FRANZ, Marion J., et al. The evidence for medical nutrition therapy for type 1 and type 2 diabetes in adults. Journal of the American Dietetic Association, 2010, 110.12: 1852-1889.
EHRMANN, Dominic, et al. Risk factors and prevention strategies for diabetic ketoacidosis in people with established type 1 diabetes. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2020, 8.5: 436-446.
KAUFMAN, Francine R. (ed.). Medical management of type 1 diabetes. American Diabetes Association, 2012.
KAWAMORI, Ryuzo, et al. Voglibose for prevention of type 2 diabetes mellitus: a randomised, double-blind trial in Japanese individuals with impaired glucose tolerance. The lancet, 2009, 373.9675: 1607-1614.