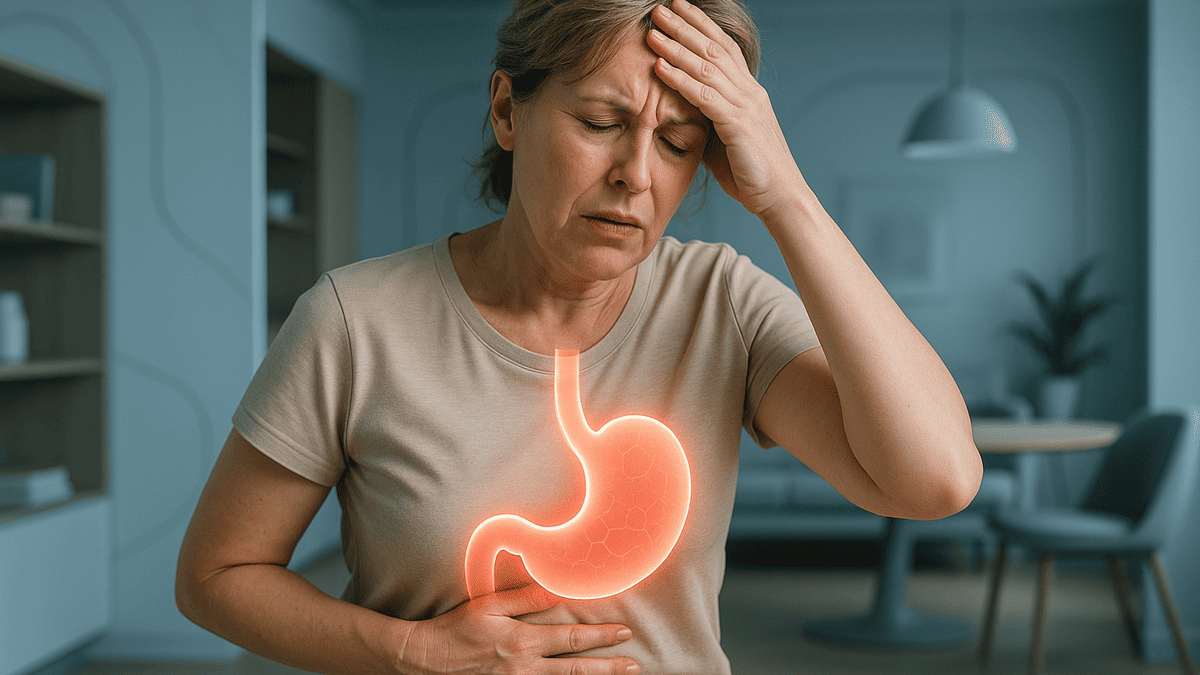SGLT2阻害薬は血糖値を下げる効果が期待できる糖尿病治療薬の一つです。この薬は尿中に糖を排出させることで血糖値を改善しますが、その影響でケトアシドーシスという重篤な副作用を引き起こす可能性があります。
ケトアシドーシスは血液が酸性に傾き、吐き気や腹痛、ひどい場合には意識障害に至る危険な状態です。
この記事ではSGLT2阻害薬を服用している方やそのご家族に向けて、ケトアシドーシスの初期症状や危険因子、そして日常生活で実践できる予防法について分かりやすく解説します。
正しい知識を身につけ、安全な治療を続けるための参考にしてください。
SGLT2阻害薬とは?糖尿病治療における役割
SGLT2阻害薬は比較的新しいタイプの糖尿病治療薬です。血糖コントロールを目的として多くの患者さんに使用されています。
ここでは、この薬の基本的な働きや治療で選ばれる理由について解説します。
SGLT2阻害薬の基本的な働き
SGLT2阻害薬は腎臓の尿細管という場所で糖の再吸収を担う「SGLT2」というたんぱく質の働きを妨げます。通常、腎臓でろ過された血液中の糖は、尿細管で再吸収されて体内に戻ります。
この薬はその再吸収を抑え、余分な糖を尿と一緒に体外へ排出させることで血糖値を低下させます。
インスリンの分泌に直接作用しないため、単独使用では低血糖のリスクが低いという特徴も持ちます。
なぜSGLT2阻害薬が選ばれるのか
この薬が治療の選択肢となる理由は血糖降下作用だけではありません。体重減少効果や血圧低下作用も報告されており、心臓や腎臓を保護する効果も期待されています。
これらの複数の利点から、特に肥満を伴う2型糖尿病患者様や、心血管疾患のリスクが高い患者様に対して積極的に使用を検討します。
主なSGLT2阻害薬の種類
日本国内では複数のSGLT2阻害薬が承認され、使用されています。それぞれに特徴があり、患者様の状態に合わせて医師が適切な薬を選択します。
国内で処方される主なSGLT2阻害薬
| 一般名 | 主な商品名 | 特徴 |
|---|---|---|
| イプラグリフロジン | スーグラ | 国内で最初に登場したSGLT2阻害薬の一つ |
| ダパグリフロジン | フォシーガ | 心不全や慢性腎臓病の治療にも用いられる |
| エンパグリフロジン | ジャディアンス | 心血管イベントのリスクを低下させるデータがある |
| カナグリフロジン | カナグル | 腎臓保護効果に関するデータがある |
副作用「ケトアシドーシス」の危険性
SGLT2阻害薬は多くの利点を持つ一方で、注意すべき副作用の一つに「ケトアシドーシス」があります。これは迅速な対応が必要な危険な状態です。
どのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。
ケトアシドーシスとは何か
ケトアシドーシスは、体内で「ケトン体」という酸性の物質が異常に増え、血液が酸性に傾いてしまう状態(アシドーシス)を指します。
体はエネルギー源として主に糖を利用しますが、糖がうまく利用できない状況になると、代わりに脂肪を分解してエネルギーを作り出します。この時にケトン体が産生されます。
ケトン体が増えすぎると体内のバランスが崩れ、様々な臓器に悪影響を及ぼすのです。
なぜSGLT2阻害薬でケトアシドーシスが起こるのか
SGLT2阻害薬は尿中に糖を排出するため、体内の糖が不足していると体が錯覚することがあります。その結果エネルギー不足を補おうとして脂肪の分解が進み、ケトン体の産生が過剰になるのです。
また、この薬の作用によりインスリンの分泌が低下しがちになることも、ケトン体の産生を促進する一因と考えられています。
血糖値が正常でも起こる「正常血糖ケトアシドーシス」
通常の糖尿病ケトアシドーシスは著しい高血糖(250mg/dL以上)を伴うことがほとんどです。
しかしSGLT2阻害薬を服用している場合、血糖値がそれほど高くない、あるいは正常範囲内であってもケトアシドーシスを発症することがあります。これを「正常血糖ケトアシドーシス」と呼びます。
血糖値だけで安心せず、吐き気や倦怠感などの症状に注意することが極めて重要です。
ケトアシドーシスの主な原因
| カテゴリ | 具体的な原因 | 体への影響 |
|---|---|---|
| 糖の利用低下 | インスリン作用の極端な不足 | 細胞がブドウ糖を取り込めなくなる |
| 代替エネルギー産生 | 脂肪の分解亢進 | エネルギー源としてケトン体が過剰に作られる |
| SGLT2阻害薬の影響 | 尿中への糖排泄促進 | 体が糖不足と認識し、脂肪分解をさらに進める |
注意すべきケトアシドーシスの初期症状
ケトアシドーシスは早期発見と早期対応が大切です。SGLT2阻害薬を服用している方は、これから挙げる初期症状を見逃さないようにしましょう。
少しでもおかしいと感じたら、自己判断せずに対応することが求められます。
体が発する危険信号を見逃さない
初期症状は風邪や胃腸炎の症状と似ていることがあるため、見過ごされやすい傾向があります。
しかし、これらは体が発している重要な危険信号です。特に複数の症状が同時に現れた場合は、ケトアシドーシスの可能性を疑う必要があります。
ケトアシドーシスの初期症状チェック
| 症状の種類 | 具体的な症状 | 注意点 |
|---|---|---|
| 消化器症状 | 吐き気、嘔吐、腹痛、食欲不振 | 胃腸炎と間違いやすいが、最も頻度の高い症状 |
| 全身症状 | 強い喉の渇き、多尿、体重減少、全身の倦怠感 | 脱水やエネルギー不足を示唆するサイン |
| 神経症状 | 頭痛、意識がもうろうとする、意識レベルの低下 | 症状が進行している可能性があり、緊急性が高い |
吐き気や腹痛などの消化器症状
ケトアシドーシスの初期症状として最も多く見られるのが、吐き気や嘔吐、腹痛です。
「食べ過ぎたかな」「胃の調子が悪いのかな」と感じるかもしれませんが、SGLT2阻害薬を服用中の場合は安易に考えず、他の症状がないか注意深く観察してください。
食事が摂れないほどの強い症状がある場合は特に注意が必要です。
倦怠感や意識障害などの全身症状
体が酸性に傾くと、全身に強い倦怠感(だるさ)が現れます。普段とは違う、起き上がれないほどの強いだるさを感じたら注意信号です。
症状が進行すると意識がぼんやりしたり、呼びかけへの反応が鈍くなったりすることがあります。
家族など周りの方が「様子がおかしい」と感じた場合は、すぐに医療機関へ連絡してください。
呼気の甘酸っぱい匂い(ケトン臭)
ケトン体の一種であるアセトンは、甘酸っぱい果物が腐ったような特徴的な匂いがします。
血液中のケトン体が増えると、このアセトンが呼気や尿に混じって排出されるため、自分や周りの人が息の匂いの変化に気づくことがあります。
これはケトアシドーシスの特徴的なサインの一つです。
ケトアシドーシスを誘発する危険因子
SGLT2阻害薬を服用しているだけですぐにケトアシドーシスになるわけではありません。特定の状況や行動が、そのリスクを高める引き金(誘因)となります。
どのようなことが危険因子になるのかを知り、日常生活で避けるよう心掛けましょう。
過度な糖質制限(ケトジェニックダイエットなど)
食事からの糖質摂取が極端に少ないと体はエネルギー源を脂肪に頼らざるを得なくなり、ケトン体の産生が亢進します。
SGLT2阻害薬を服用中に自己判断で厳しい糖質制限やケトジェニックダイエットを行うことは、ケトアシドーシスのリスクを著しく高めるため、絶対に避けてください。
食事療法は必ず医師や管理栄養士の指導のもとで行いましょう。
- 炭水化物の極端な制限
- 長期間の絶食や欠食
- 不適切なダイエット
ケトアシドーシスの危険を高める因子
| 危険因子 | 具体的な状況 | なぜリスクが高まるか |
|---|---|---|
| シックデイ | 発熱、下痢、嘔吐、食欲不振など | 脱水や食事不足によりケトン体が増えやすい |
| 脱水 | 水分摂取不足、多量の発汗 | 血液が濃縮され、アシドーシスが進行しやすくなる |
| 過度のアルコール摂取 | 多量の飲酒 | 脱水を助長し、肝臓での糖新生を抑制する |
脱水状態やシックデイ(体調不良の日)
発熱、下痢、嘔吐などで食事ができず、水分も十分に摂れない状態を「シックデイ」と呼びます。
このような体調不良時は脱水になりやすく、体はストレス状態に陥ります。このストレスがケトン体の産生を促すホルモンの分泌を刺激します。
SGLT2阻害薬の利尿作用も相まって、ケトアシドーシスのリスクが非常に高まるため、シックデイの対応(シックデイルール)を知っておくことが重要です。
手術前後や過度のアルコール摂取
大きな手術や麻酔は体に大きなストレスを与え、ケトン体を増やすホルモンを分泌させます。そのため、手術前にはSGLT2阻害薬を一時的に中止(休薬)することが一般的です。
また、多量のアルコール摂取も危険です。アルコールは利尿作用があり脱水を助長するうえ、肝臓での糖の産生を妨げます。
これらの複合的な要因により、ケトアシドーシスの引き金となる可能性があります。
SGLT2阻害薬服用中のケトアシドーシス予防法
ケトアシドーシスは危険な状態ですが、日常生活での注意点を守ることで予防が可能です。
ここでは、安全に治療を続けるために心掛けてほしいポイントを具体的に解説します。
適度な糖質摂取の重要性
SGLT2阻害薬を服用しているからといって、糖質を完全に避ける必要はありません。むしろ、極端な糖質制限はケトアシドーシスのリスクを高めます。
主治医や管理栄養士と相談の上、自分にとって適正な量の糖質(炭水化物)を毎日の食事でしっかり摂ることが予防の基本です。
こまめな水分補給を心掛ける
SGLT2阻害薬には利尿作用があるため、普段から意識して水分を摂ることが大切です。特に夏場や運動時など汗を多くかく場面では、通常よりも多めの水分補給を心掛けてください。
脱水はケトアシドーシスの大きな誘因です。喉が渇く前に、こまめに飲む習慣をつけましょう。
- のどが渇く前に飲む
- 1日に1.5L~2Lを目安に
- 水やお茶など糖分のない飲み物で
予防のための生活習慣
| 項目 | 具体的な行動 | 目的 |
|---|---|---|
| 食事 | 極端な糖質制限を避け、バランス良く食べる | ケトン体の過剰な産生を防ぐ |
| 水分 | 意識してこまめに水分を摂取する | 脱水を防ぎ、体内のバランスを保つ |
| 体調管理 | シックデイルールを理解し、体調不良時に備える | 体調不良時のリスクを最小限に抑える |
シックデイルールの徹底
シックデイ(発熱、下痢、嘔吐、食欲不振など体調が悪い日)には、特別な対応が必要です。食事が摂れない場合はSGLT2阻害薬を自己判断で休薬することも考えられます。
どのような状態になったら薬を休み、いつ医療機関に連絡すべきか、あらかじめ主治医と具体的な対応(シックデイルール)を確認しておくことが、あなた自身の安全を守ります。
定期的な医師への相談
治療薬や食事、生活習慣について少しでも疑問や不安があれば、遠慮なく主治医に相談してください。定期的な診察は体の状態を確認し、副作用の兆候を早期に発見するためにも重要です。
自己判断で薬の量を調整したり、服用を中止したりすることは絶対にやめましょう。
もしも初期症状が現れたら?緊急時の対処法
予防を心掛けていても、ケトアシドーシスの初期症状が現れる可能性はゼロではありません。万が一の時に慌てず適切に行動できるように、緊急時の対処法を知っておきましょう。
自己判断で薬の服用を続けない
吐き気や腹痛、強い倦怠感などケトアシドーシスを疑う症状が現れた場合は、まずSGLT2阻害薬の服用を中止してください。
そして食事や水分が摂れる場合は、糖分を含むジュースやスポーツドリンクを少しずつ補給し、安静にしましょう。
ただし、これはあくまで応急処置であり、医療機関の受診に代わるものではありません。
速やかに医療機関を受診する
症状が軽いと感じても、ケトアシドーシスは急速に悪化することがあります。疑わしい症状があれば、様子を見ずにすぐに主治医に連絡するか、近隣の医療機関を受診してください。
夜間や休日の場合は救急外来の受診もためらわないでください。早期の対応が重症化を防ぐ鍵となります。
医師に伝えるべき情報
受診の際には医師に正確な情報を伝えることが迅速な診断と治療につながります。以下の情報を整理して伝えられるように準備しておくとスムーズです。
- 服用しているSGLT2阻害薬の名前
- いつから、どのような症状があるか
- 直近の食事内容や水分摂取の状況
- 体調不良(シックデイ)の有無
医療機関に伝えるべき情報リスト
| 分類 | 伝える内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 服用薬 | SGLT2阻害薬の商品名と用法用量 | お薬手帳を持参すると確実 |
| 症状 | 吐き気、腹痛、倦怠感など具体的な症状と発現時期 | 症状の強さや変化も伝える |
| 生活状況 | 食事や水分の摂取状況、飲酒の有無など | ケトアシドーシスの誘因を探る手がかりになる |
SGLT2阻害薬とケトン体の関係
ケトアシドーシスを理解する上で、ケトン体そのものについての知識も助けになります。ケトン体は必ずしも悪者ではなく、体の重要なエネルギー源でもあります。
SGLT2阻害薬がケトン体にどう影響するのかを見ていきましょう。
ケトン体とはエネルギー源の一つ
ケトン体はアセト酢酸、β-ヒドロキシ酪酸、アセトンの3つの物質の総称です。これらは体内のブドウ糖が不足した際に、肝臓で脂肪が分解されて作られるエネルギー源です。
特に脳は通常はブドウ糖しかエネルギーとして利用できませんが、飢餓状態など特殊な状況下ではケトン体もエネルギー源とすることができます。
SGLT2阻害薬がケトン体を増やす理由
SGLT2阻害薬は尿中に糖を強制的に排出させます。このことにより体は糖が不足していると判断し、代替エネルギーとして脂肪の分解を始めます。
その結果、肝臓でのケトン体産生が促進され、血中のケトン体濃度が上昇しやすくなります。この状態が行き過ぎると、ケトアシドーシスに至る危険性があるのです。
ケトン体の自己チェック方法
シックデイなどで体調が優れない時には自分でケトン体をチェックすることも可能です。薬局などで市販されている尿ケトン試験紙を使えば尿中のケトン体の有無を手軽に調べられます。
試験紙が陽性(色が変わる)になった場合はケトン体が増加しているサインです。すぐに主治医に連絡し、指示を仰ぎましょう。
ただし、これはあくまで目安であり、医師の診断に代わるものではありません。
ケトン体が増加しやすい状況
| 状況 | 体の状態 | ケトン体の動き |
|---|---|---|
| 長時間の絶食・飢餓 | エネルギー源のブドウ糖が枯渇 | 脂肪を分解しケトン体を産生 |
| 激しい運動 | 筋肉でのブドウ糖消費が増大 | エネルギー不足を補うため産生 |
| SGLT2阻害薬服用時 | 尿中への糖排泄により糖が不足 | 体が糖不足と認識し産生を促進 |
ケトアシドーシスに関するよくある質問
最後に、SGLT2阻害薬とケトアシドーシスに関して患者様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。治療への理解を深める一助としてください。
- QSGLT2阻害薬を飲んでいれば誰でもなりますか?
- A
いいえ、誰でもなるわけではありません。SGLT2阻害薬の副作用として報告されていますが、その頻度は高くありません。
しかし、前述したような危険因子(過度な糖質制限、脱水、シックデイなど)が重なると発症リスクは高まります。リスクを正しく理解し、予防策を講じることが重要です。
- Q症状がないか確認するために自分でケトン体を測るべきですか?
- A
日常的に毎日測定する必要はありません。しかし発熱や嘔吐、食欲不振といったシックデイの状態になった時には、尿ケトン試験紙でセルフチェックを行うことが有用です。
陽性反応が出た場合は体に異変が起きているサインと考え、速やかに医療機関に相談してください。
シックデイに備えて、試験紙を一つ手元に置いておくと安心です。
- Q他の糖尿病治療薬と一緒に使うとリスクは高まりますか?
- A
特にインスリン製剤を使用している方は注意が必要です。
インスリンの量が不足するとケトン体が産生されやすくなるため、SGLT2阻害薬との併用でケトアシドーシスのリスクが相対的に高まる可能性があります。
自己判断でインスリンの量を減らすことは絶対に避けてください。
他の薬との組み合わせについては、主治医が患者様一人ひとりの状態を考慮して判断しますので、処方された通りに正しく服用を続けてください。
以上
参考にした論文
TAKEMURA, Miho; IKEMURA, Kenji; OKUDA, Masahiro. Factors and preventive strategies for perioperative euglycemic diabetic ketoacidosis in patients with type 2 diabetes receiving sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors: a retrospective study. Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences, 2025, 11.1: 79.
ABIRU, Norio, et al. Overlapping risk factors for diabetic ketoacidosis in patients with type 1 diabetes on ipragliflozin: case analysis of spontaneous reports in Japan from a pharmacovigilance safety database. Expert Opinion on Drug Safety, 2023, 22.8: 697-706.
MENGHOUM, N.; ORIOT, P.; HERMANS, M. P. Clinical and biochemical characteristics and analysis of risk factors for euglycaemic diabetic ketoacidosis in type 2 diabetic individuals treated with SGLT2 inhibitors: a review of 72 cases over a 4.5-year period. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 2021, 15.6: 102275.
GOTO, Shunsaku, et al. Life-threatening complications related to delayed diagnosis of euglycemic diabetic ketoacidosis associated with sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors: a report of 2 cases. The American Journal of Case Reports, 2021, 22: e929773-1.
MIYAZAKI, Masamune, et al. Euglycemic ketoacidosis in a patient without diabetes taking sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors for heart failure. The American Journal of Case Reports, 2024, 25: e943945-1.
FRALICK, Michael, et al. Identifying risk factors for diabetic ketoacidosis associated with SGLT2 inhibitors: a nationwide cohort study in the USA. Journal of General Internal Medicine, 2021, 36.9: 2601-2607.
ZHAO, Qingnan, et al. The risk factors of diabetic ketosis and diabetic ketoacidosis among patients with type 2 diabetes mellitus treated with SGLT2 inhibitors: a retrospective study. Expert Opinion on Drug Safety, 2024, 23.1: 57-65.
SEKI, Hiroyuki, et al. Sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor-associated perioperative ketoacidosis: a systematic review of case reports. Journal of Anesthesia, 2023, 37.3: 465-473.
NORIHITO, Yoshida, et al. Sodium-Glucose Cotransporter 2 (SGLT2) Inhibitor-and Metformin-Associated Euglycemic Diabetic Ketoacidosis and Lactic Acidosis Leading to Refractory Acute Kidney Injury: Successful Management With Hemodialysis. Cureus, 2025, 17.3.
YOSHIDA, Yumiko, et al. Euglycemic Diabetic Ketoacidosis in a Patient with Type 2 Diabetes and Preserved Insulin Secretion on Empagliflozin. Internal Medicine, 2025, 4752-24.
KAWAHARA, Junko, et al. Life-threatening coronary vasospasm in patients with type 2 diabetes with SGLT2 inhibitor-induced euglycemic ketoacidosis: a report of two consecutive cases. Diabetology international, 2024, 15.1: 135-140.