糖尿病や血糖値が気になる方にとって食後1時間や2時間の血糖値は健康管理の重要な指標です。
食後1時間でどの程度の血糖値に落ち着いていればよいのか、あるいは食後2時間で血糖値がどのくらいまで上がるとリスクが高まるのかなど具体的な基準や管理のコツを知ることは大切です。
本記事では食後の血糖値に着目しながら糖尿病の予防やコントロールに役立つ実践方法を詳しく解説します。
生活習慣の見直しや食事・運動のコツ、定期的な測定と受診のポイントを押さえて健康な血糖値を維持するきっかけにしてください。
食後血糖値の測定が重要な理由
食後血糖値を安定させることは糖尿病の予防や進行を抑えるうえで大切です。
特に食後1時間から2時間にかけて血糖値が大きく変動するため、どのタイミングで測定すればよいかを理解しておくと効果的な血糖コントロールにつながります。
ここでは血糖値の基本的なメカニズムや測定を継続するメリットを解説します。
血糖値の基本メカニズム
血糖値は血液中のブドウ糖濃度を示す数値で、主に食事とインスリンの働きで上下します。
炭水化物を摂取すると消化・吸収を経てブドウ糖が血液中に取り込まれ、血糖値が上昇します。
その後、インスリンが分泌されることで細胞内にブドウ糖が取り込まれて血糖値が下がる仕組みです。
血糖値の主な影響要因
| 影響要因 | 内容 |
|---|---|
| 食事 | 摂取する糖質量や食物繊維、脂質、タンパク質のバランスによって血糖値の上がり方が異なる |
| インスリン | 膵臓で分泌されるホルモン。血糖値を下げる主な役割を担う |
| 生活習慣 | 運動不足や過度なストレス、喫煙などが血糖値に影響を与える |
食後に血糖値が上昇する仕組み
食後に血糖値が上がるのは自然な現象ですが、過剰な上昇が続くと血管や神経に負担がかかりやすくなります。
食事直後は胃腸で糖質が吸収され、血液中にブドウ糖が急激に供給されます。
通常は膵臓からインスリンが分泌されて細胞にブドウ糖を取り込み血糖値を下げますが、インスリンの分泌量が追いつかなかったり細胞がインスリンに反応しにくくなったりすると高血糖状態が長引きます。
血糖値測定を継続するメリット
定期的に血糖値を測ると、以下のメリットがあります。
血糖値測定で得られる主なメリット
- 自分の食事パターンと血糖値の関係を把握しやすくなる
- 早めの段階で食事や運動など生活習慣の見直しができる
- 血糖値の変動幅を知ることで低血糖や高血糖への対策を取りやすくなる
- 医療機関を受診するべきタイミングを判断しやすくなる
血糖値測定は自己管理を高めるだけでなく、医療機関での診察時に具体的なデータとして活用できます。
血糖値管理の初期目標
食後血糖値を適切に管理するための初期目標としては生活習慣の基本を整えつつ、食後1時間や2時間の値が適正範囲に近づくように意識することが大切です。
たとえば食後1時間で高くなりすぎないように食物繊維を増やす、食後2時間に200mg/dLを超えないような食べ方を工夫するなど具体的な方策を立てると行動に移しやすくなります。
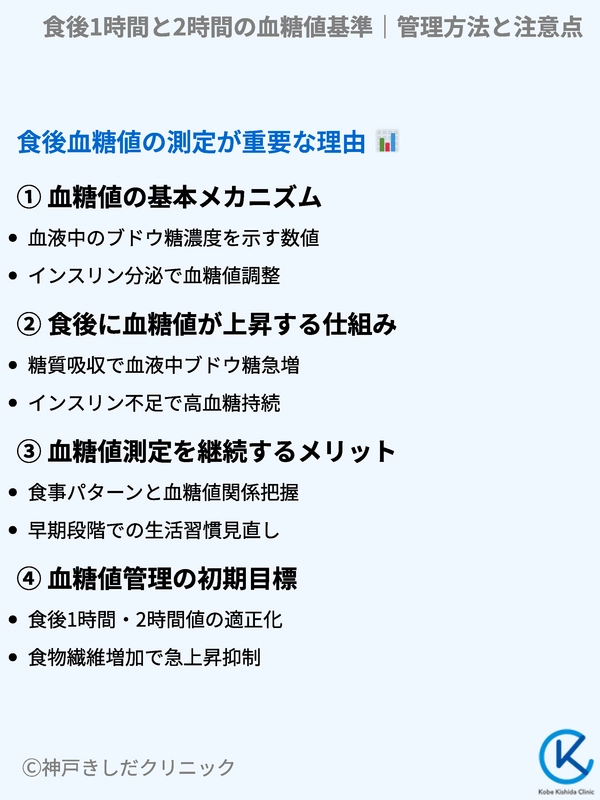
食後1時間と2時間の血糖値の一般的な基準
食後1時間での血糖値や食後2時間の数値は、糖尿病の有無や予備群かどうかを見極めるうえで重要な指標です。
食後2時間の値が200mg/dLを超えると要注意という話をよく聞きますが、その背景や基準について詳しく押さえましょう。
ここでは一般的な目安と血糖値を知ることの意義について解説します。
食後1時間の正常値と注意点
食後1時間は食事で摂取した糖質が血液中に流れ込むタイミングです。
健康な人の多くは血糖値が140mg/dL前後で推移するといわれますが、食後1時間の血糖値は個人差があります。
血糖値が急激に上がりすぎると血管に負担がかかり、インスリンの分泌量も増えます。
インスリンの出が不十分だと血糖値が高い状態が続くため、このタイミングで測定を行い、食後1時間血糖値の正常値に近い範囲を確認しておくと良いでしょう。
食後1時間に気をつけたいポイント
- 食事の質だけでなく食べる速度も影響する
- 食後の軽い運動やストレッチで血糖値が下がりやすくなる
- 血糖値が高くなりやすい食品を続けて摂取しない
食後2時間の目安と200mg/dLを超えるリスク
食後2時間は一般的に血糖値がピークから下がり始めるタイミングです。
食後2時間血糖値が200mg/dLを超える場合、糖尿病やその予備群の可能性があります。
健常者であっても一時的に血糖値が高めになることはありますが、慢性的に高い状態が続くかどうかが重要です。
血糖値と200mg/dL超えのリスク比較
| 血糖値範囲 (mg/dL) | 状態の目安 | 主なリスク・注意点 |
|---|---|---|
| ~140前後 | 比較的安定 | 通常の範囲だが、生活習慣次第で変動する |
| 141~199 | やや高め | 糖尿病予備群の可能性があり要注意 |
| 200以上 | 高血糖リスク大 | 糖尿病の疑いが強く、医療機関での検査を推奨 |
食後2時間で血糖値を測ることで長時間高血糖が続いていないかどうかを知る目安になります。
毎回200mg/dLを超えているようならば食事や運動、必要に応じて専門医の診察を受けるほうが良いでしょう。
血糖値を知ることで得られる気づき
血糖値を測定すると食生活や運動習慣の影響が数値として現れるため、自分の身体への理解が深まります。
たとえばある特定の食品を食べるときに血糖値が急上昇する、夕食後だけ極端に血糖値が高くなるなど個人差があるパターンを把握できます。
血糖値測定で改善しやすい項目
- 間食や甘い飲み物の回数
- 夕食時間と就寝時間の間隔
- 食物繊維の摂取量や食べる順番
自己測定・病院測定それぞれの利点
血糖値の測定方法には自己血糖測定(SMBG)と病院での定期検査があります。どちらも目的が異なるため、両方を活用することが重要です。
自己測定と病院測定の特徴比較
| 測定方法 | 特徴 | メリット |
|---|---|---|
| 自己血糖測定 | 自宅で簡易的に測定可能 | リアルタイムで数値を把握しやすい |
| 病院での測定 | 血液検査や専門医の診断を含む | 専門的な検査で総合的な状態を確認できる |
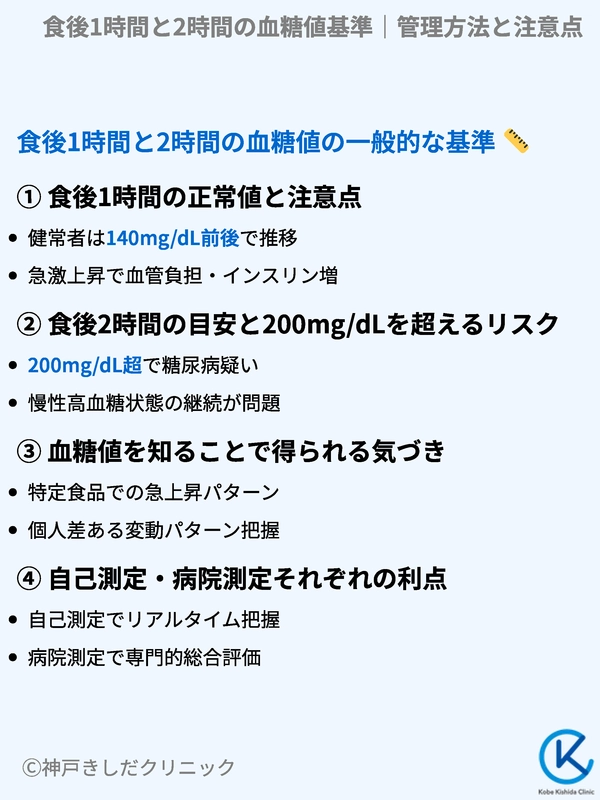
血糖値管理の実践方法
血糖値は食事や運動と密接に関わります。食後1時間、2時間の血糖値を良好に保つには適切な食事と適度な運動を日々の生活に取り入れることが必要です。
ここでは生活習慣全体を見直すうえで重要となるポイントを整理し、血糖管理の基本を紹介します。
食事療法の基本
食事療法というと難しく感じる方もいますが、まずはバランスを意識して糖質・タンパク質・脂質を適度に配分することから始めると取り組みやすくなります。
糖質の質や量だけでなく、ビタミンやミネラル、食物繊維も偏りなく摂ると血糖値が急上昇しにくくなります。
食事療法のポイント
- 主食・主菜・副菜をバランスよく配置
- 野菜や海藻、きのこ類を積極的に活用
- ゆっくりよく噛んで食べる
適度な運動の重要性
運動不足が続くと血糖値が高いままになりやすく、インスリンの働きも鈍くなりがちです。
ウォーキングやストレッチなど軽度の運動でも継続することで血糖値のコントロールに良い影響を与えます。
運動と血糖値の関係
| 運動内容 | 効果 | おすすめ頻度 |
|---|---|---|
| ウォーキング | インスリン感受性の向上、ストレス解消 | 週3~5回、1回30分程度 |
| 筋力トレーニング | 基礎代謝の向上、血糖値の安定 | 週2~3回、無理のない負荷で |
| ストレッチ | 血行促進、疲労回復 | 毎日少しずつ |
生活習慣全体を整えるコツ
血糖値を安定させるには食事と運動だけでなく睡眠やストレス管理も視野に入れることが大切です。
短い睡眠が続いたり過度なストレスがかかったりすると、ホルモンバランスが乱れて血糖値が上がりやすくなります。
生活習慣の見直しに役立つリスト
- 1日の就寝時間と起床時間を固定する
- スマホやパソコンの使用時間を調整し、寝る前はリラックスする時間を確保
- ストレッチや軽い体操で身体をほぐし、血行を促進する
血糖管理とストレスの関係
ストレスを受けると体内でストレスホルモンが分泌されます。このホルモンは血糖値を上げる作用を持ち、糖質代謝にも影響を及ぼします。
ストレス解消のために甘いものを過剰摂取すると、さらに血糖値が乱れやすくなるため注意が必要です。
適度な運動や趣味の時間を設けるなどしてストレスをこまめに発散すると血糖コントロールに良い影響を期待できます。
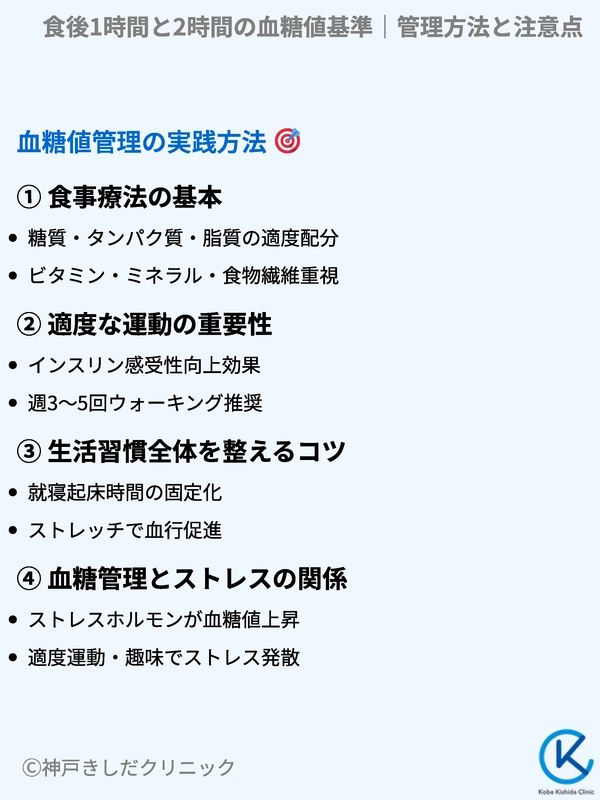
食後血糖値を安定させる食事のポイント
食後1時間、2時間の血糖値を安定させるには日常の食事内容を見直すことが効果的です。
食物繊維やGI値を意識すると、同じカロリーでも血糖値の上がり方が変わってきます。
ここでは具体的に押さえておきたい食事面の工夫を解説します。
食物繊維を意識する
食物繊維が多い食品を摂ると糖質の吸収速度がゆるやかになります。
野菜や海藻、きのこ類、全粒粉などを使ったメニューを取り入れると食後の血糖値の急上昇を抑えやすくなります。
特に食後1時間血糖値の正常値に近づけたい方は食物繊維を意識すると良いでしょう。
食物繊維を多く含む食品一覧
| 食品 | 食物繊維量(100gあたり) | 調理例 |
|---|---|---|
| ごぼう | 約5.7g | きんぴら、煮物 |
| アボカド | 約5.3g | サラダ、ディップ |
| ブロッコリー | 約4.4g | 茹でて副菜、生野菜サラダ |
GI値を参考にした食品選び
GI値(グリセミック・インデックス)は、食品が血糖値をどの程度上昇させるかを示す目安です。
GI値が高いほど血糖値を急激に上げやすく、低いほどゆるやかになります。
GI値の区分表
| GI値区分 | 例 |
|---|---|
| 高GI(70以上) | 白パン、白米、じゃがいもなど |
| 中GI(56~69) | 玄米、全粒粉パン、さつまいもなど |
| 低GI(55以下) | 大豆製品、きのこ、海藻類、野菜全般 |
高GI食品をすべて避けるのではなく、組み合わせや食べ方を工夫すると食後血糖値が安定しやすくなります。
糖質量を調整する具体例
糖質量の管理は糖尿病の食事療法でよく取り入れられます。
主食の量を少し減らす、野菜やタンパク質を先に食べるなどの工夫で食後2時間血糖値が200mg/dLを超えないよう抑制できます。
食事全体の糖質量調整例
| 食事内容 | 糖質量 | 主な調整ポイント |
|---|---|---|
| 朝食:ご飯120g、味噌汁、焼き魚、サラダ | 約40g | 野菜を増やし、白米を少なめに |
| 昼食:玄米100g、野菜たっぷりスープ、鶏むね肉ソテー | 約35g | 玄米でGI値を下げる |
| 夕食:ご飯80g、野菜炒め、豆腐、みそ汁 | 約30g | 主食を少なく、副菜を充実させる |
食事リズムで変わる血糖値
食事時間の間隔が空きすぎると次の食事で過剰に食べたり血糖値が急上昇しやすくなります。
3食を規則正しく摂ることが重要で、寝る直前の食事を避けると朝の血糖値にも良い影響があります。
食事リズムを整えるためのリスト
- 朝食を抜かずに摂る
- 昼食と夕食の間隔を空けすぎない
- 夜食や深夜の間食はできるだけ控える
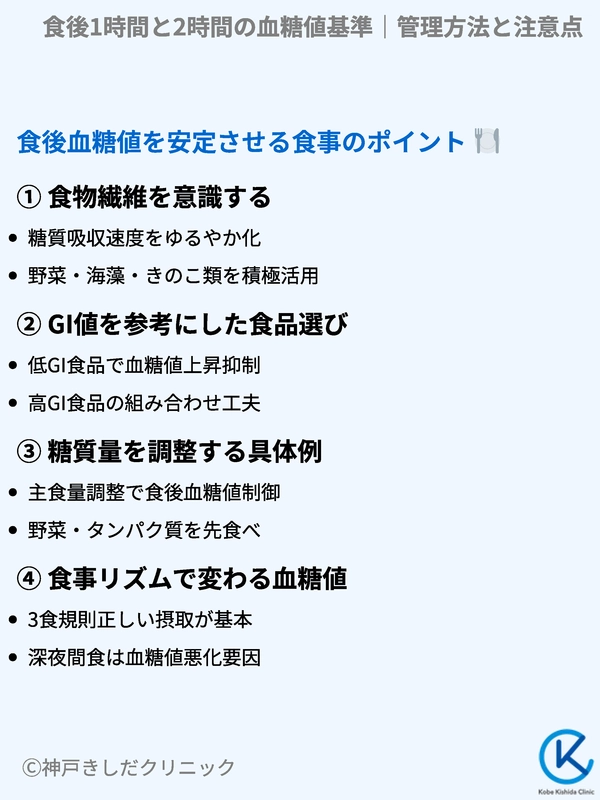
運動を取り入れて血糖値をコントロール
運動は血糖値を下げる助けになるだけでなく、インスリン感受性を高める役割も持ちます。無理のない範囲で継続することが大切です。
ここでは具体的な運動内容や日常生活への組み込み方を紹介します。
有酸素運動と筋力トレーニング
ウォーキングやスイミングといった有酸素運動は血液の循環を改善し血糖値を下げやすくする効果が期待できます。
また、筋力トレーニングは筋肉量を増やし、エネルギー代謝の向上につながります。
これらをバランスよく取り入れると効率的に血糖値をコントロールできます。
運動種類と期待できるメリット
| 運動種類 | メリット | 実施目安 |
|---|---|---|
| 有酸素運動 | 体脂肪燃焼、血行促進 | 1回20~30分、週3~5回 |
| 筋力トレーニング | 基礎代謝向上、筋肉維持 | 1回15~20分、週2~3回 |
| 柔軟運動 | 怪我予防、リラックス効果 | 毎日の習慣として数分程度 |
運動強度の選び方と注意点
運動強度が高すぎると続かずに疲労がたまってしまいます。
軽めのウォーキングから始めて、慣れてきたら少しずつ負荷を上げると無理なく継続できます。
ただし、持病がある場合は医師に相談のうえで始めると安心です。
日常生活に組み込む簡単な方法
運動のためのまとまった時間が取れなくても日常生活の中でこまめに身体を動かすだけでも効果があります。
取り入れやすい運動習慣
- エスカレーターではなく階段を使う
- 電車通勤の際に1駅分歩いてみる
- 家事や掃除を積極的に行う
- テレビを見ながら簡単な筋トレをする
運動時の低血糖対策
糖尿病治療を行っている方やインスリン注射を使用している方は、運動時に低血糖を起こしやすい場合があります。
事前に軽い炭水化物を補給したり、運動中に異変を感じたらすぐにブドウ糖や甘いジュースを摂取するなど適切な対応が必要です。
低血糖はめまいやふらつきなどの症状があるため自己判断で無理をせず早めに対応してください。
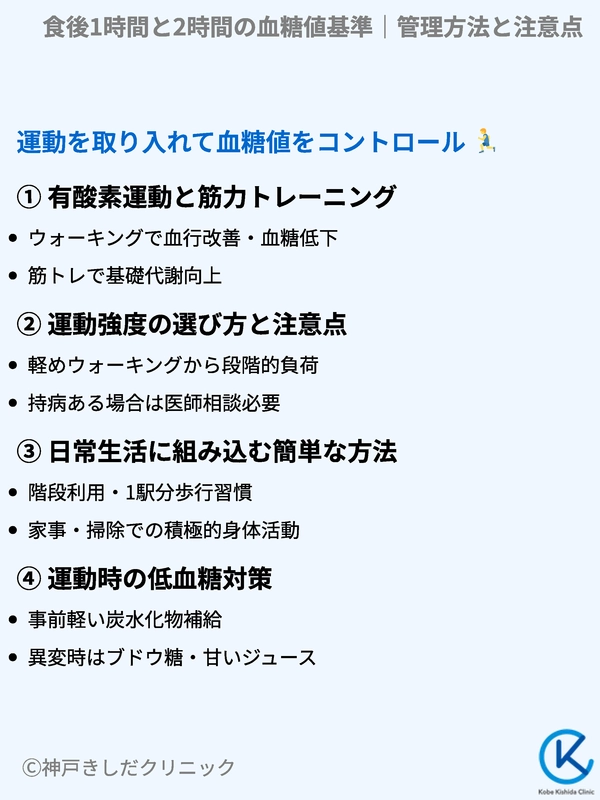
定期的な血糖値のモニタリングと受診のタイミング
血糖値は一時的に改善しても、食生活や運動不足が続くと再び悪化しやすい特徴があります。
そこで、定期的な自己モニタリングと医療機関での検査を組み合わせることが大切です。
ここでは測定のタイミングや検査数値の見方について解説します。
自己血糖測定でわかる変化
自己血糖測定は簡易的な血糖計を用いるため、日常生活のなかで数値を把握しやすいのがメリットです。
毎日同じタイミングで測定すると食後1時間や2時間の血糖値の変化がより明確になります。
自己血糖測定を継続するメリット
- 食事内容や運動量が血糖値に及ぼす影響を実感しやすい
- 血糖値の変動パターンを把握し、低血糖や高血糖への対策を立てやすい
- 医師との相談時に具体的な数値を共有しやすい
病院での検査が必要な理由
病院では血糖値だけでなく、HbA1c(ヘモグロビンA1c)など長期的な血糖管理状況を示す指標も測定します。
自己血糖測定だけでは把握しきれない部分を補い、総合的に健康状態を評価できる点が大きな特徴です。
特に食後2時間血糖値が200mg/dLを超える状況が続いたり、自覚症状がある場合は早めの受診を検討してください。
検査数値の見方を知る大切さ
病院で受け取る検査結果表には血糖値やHbA1cだけでなくさまざまな数値が並びます。
どこを見ればいいか戸惑う人も多いですが、主治医に相談しながら自分の数値の特徴を理解すると、生活習慣の改善ポイントがわかりやすくなります。
主な検査項目と意味
| 検査項目 | 内容 | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| 空腹時血糖 | 空腹時の血糖値 | 高値の場合は早期対策が重要 |
| 食後血糖値 | 食後1~2時間の血糖値 | 食事の内容や量、インスリン分泌能力を確認 |
| HbA1c | 過去1~2か月の平均血糖値 | 高値が続くほど合併症リスクが上がる |
受診のタイミングを逃さない工夫
症状がなくても定期的に血糖値をチェックし、異常を感じたら早めに医師の診察を受けることが大切です。
忙しさを理由に後回しにすると気づかないうちに糖尿病が進行してしまうリスクがあります。
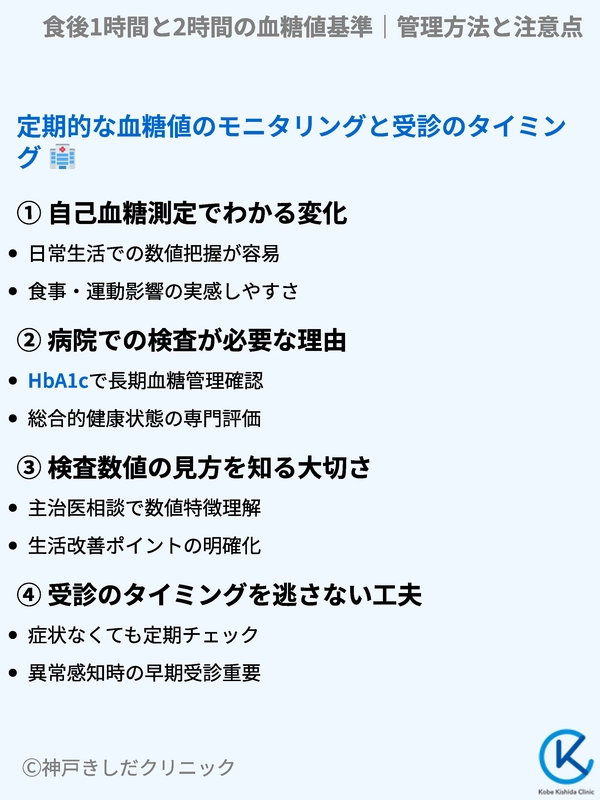
血糖値管理を継続するための心構え
血糖値を安定させるには一時的な対策だけでなく、長期的に取り組む継続力が必要です。
特に食後1時間や2時間の血糖値が高い方は生活習慣や食事内容をトータルで見直すことが求められます。
ここでは管理を続けるうえでの心構えやモチベーション維持のコツを紹介します。
目標値設定とモチベーション維持
漠然と「血糖値を下げたい」というだけでは途中で意欲が低下しやすくなります。
具体的な目標値を決める、あるいは「食後2時間血糖値が200mg/dLを超えないようにする」などのわかりやすい目安を持つとモチベーションを保ちやすくなります。
モチベーション向上につながる工夫
- 1か月後や3か月後に達成したい数値を決める
- 毎日の食事内容や運動量を手帳やアプリに記録する
- 小さな達成感を積み重ねて自己肯定感を高める
生活習慣の見直しポイント
食事や運動以外にも毎日の中で血糖値に影響を与える行動はいくつもあります。
たとえば睡眠不足が続くと血糖コントロールが乱れやすくなり、飲酒量の増加や喫煙習慣も血管に負担をかける原因です。
健康的な体を目指すには多角的に生活習慣を振り返る視点が重要です。
サポートを活用するメリット
自己流で頑張ろうとしても、途中で挫折したり問題を見落とすことがあります。
医師や管理栄養士、看護師などの専門家からサポートを受けると自分では気づかない課題を発見しやすくなり、より効率的な血糖コントロールを実現しやすくなります。
サポート体制の例
| サポート提供者 | サポート内容 |
|---|---|
| 医師 | 血液検査や薬物療法、具体的な生活指導 |
| 管理栄養士 | 食事指導、献立作成のアドバイス |
| 看護師 | 日常生活上の注意点や測定器具の使い方指導 |
小さな成功体験を積み重ねる
血糖値管理は長期戦です。一気に完璧を目指そうとすると、かえってストレスが増えて継続が難しくなります。
小さな目標をクリアして自己肯定感を持つことが長く続けるポイントです。
たとえば「1週間に3回ウォーキングする」「夕食のご飯の量をいつもより20g減らす」など、小さな成功を重ねていきましょう。
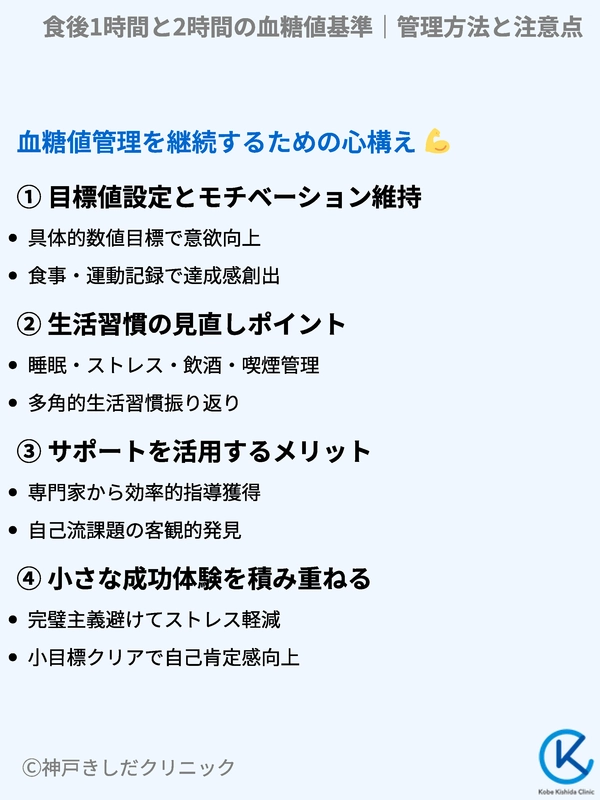
よくある質問
血糖値管理を始めると、食事や測定タイミングなど疑問点がいくつも出てくるものです。
ここではよく寄せられる質問を取り上げ、疑問を解消するためのヒントをまとめました。
食後に血糖値を測定する回数
食後1時間や2時間の測定を毎食行う必要はありません。
まずは1日1回、食後2時間の血糖値を測り、数値を記録すると生活習慣の影響を把握しやすくなります。
血糖値が不安定であれば医師と相談して測定回数を増やしてみるとよいでしょう。
血糖値と食後高血糖の関係
食後高血糖は食事後に血糖値が急激に上昇して高い状態が続くことをいいます。これが続くと血管へのダメージが蓄積し、合併症リスクが高まります。
食後1時間や2時間の血糖値を測ることで自分が食後高血糖を起こしやすいかどうかを確認できます。
食事のタイミングと血糖値
食事の回数や間隔は血糖コントロールに影響を与えます。
1日2食になってしまうと次の食事で大量に糖質を摂取しがちで血糖値が急上昇しやすくなります。
可能であれば3食をバランスよく摂り、間食を適度にコントロールすることがポイントです。
血糖値以外に注目すべき指標
血糖値以外にも、HbA1cが長期的な血糖管理を示す重要な指標になります。この数値が高い場合、平均して血糖値が高めに推移していることを意味します。
さらに、血圧や血中脂質、体重・腹囲などをあわせて確認し、総合的に健康を管理する意識を持つと安心です。
以上
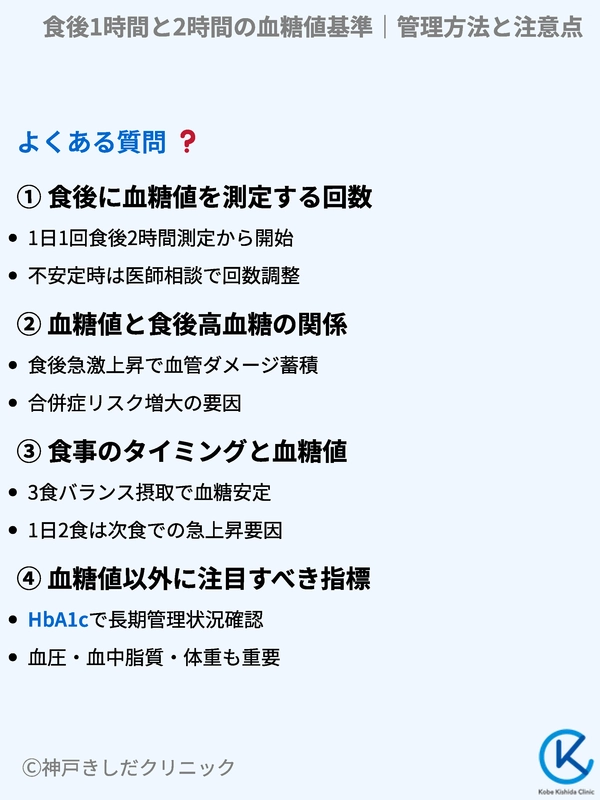
参考にした論文
MITSUISHI, Sumie, et al. Can fasting glucose levels or post-breakfast glucose fluctuations predict the occurrence of nocturnal asymptomatic hypoglycemia in type 1 diabetic patients receiving basal-bolus insulin therapy with long-acting insulin?. PLoS One, 2015, 10.12: e0144041.
MORI, Hiroko, et al. Glycemic Profiling in Patients with Drug-Naïve Type 2 Diabetes by Continuous Glucose Monitoring. Journal of UOEH, 2018, 40.4: 287-297.
KATAHIRA, Takehiro, et al. Postprandial plasma glucagon kinetics in type 2 diabetes mellitus: comparison of immunoassay and mass spectrometry. Journal of the Endocrine Society, 2019, 3.1: 42-51.
NAKANISHI, Shuhei; YONEDA, Masayasu; MAEDA, Shusaku. Impact of glucose excursion and mean glucose concentration in oral glucose-tolerance test on oxidative stress among Japanese Americans. Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy, 2013, 427-433.
TAKAHASHI, Hiroshi, et al. Prediction of nocturnal hypoglycemia unawareness by fasting glucose levels or post-breakfast glucose fluctuations in patients with type 1 diabetes receiving insulin degludec: a pilot study. Plos one, 2017, 12.7: e0177283.
SUZUKI, Kazunari, et al. The effects of postprandial glucose and insulin levels on postprandial endothelial function in subjects with normal glucose tolerance. Cardiovascular Diabetology, 2012, 11: 1-9.
YAMASA, Toshihiko, et al. Evaluation of glucose tolerance, post-prandial hyperglycemia and hyperinsulinemia influencing the incidence of coronary heart disease. Internal Medicine, 2007, 46.9: 543-546.
MIYAGI, Masahiko, et al. Urinary Myoinositol Index: A New and Better Marker for Postmeal Hyperglycemia. The Showa University Journal of Medical Sciences, 2012, 24.1: 33-41.
CERIELLO, Antonio, et al. Postprandial glucose regulation and diabetic complications. Archives of internal medicine, 2004, 164.19: 2090-2095.
LIND, Marcus, et al. The association between HbA1c, fasting glucose, 1-hour glucose and 2-hour glucose during an oral glucose tolerance test and cardiovascular disease in individuals with elevated risk for diabetes. PLoS One, 2014, 9.10: e109506.



