血糖値コントロールに取り組む糖尿病患者の中には食事回数を減らすことで体重管理や血糖値の上下を緩やかにしようとする方が少なくありません。
近年、夕食のみとする一日一食(OMAD)がダイエット法として話題になることがありますが、糖尿病治療の標準的手法ではありません。
一部の患者が自己判断で試みる場合もありますが、医学的には慎重な検討が必要な方法です。
食事回数やタイミングを変えるときは栄養バランスや生活リズム、体への負担などを多方面から考慮する必要があります。
ここでは一日一食のメリット・デメリットや、血糖値管理への影響などを詳しく見ていきます。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。
糖尿病と食事回数の基礎知識
糖尿病の治療では食事療法や運動療法、必要に応じた薬物療法などが大きな柱になります。
血糖値の急激な変動を防ぎ、安定したコントロールをめざすうえで食事回数の設定は大きな意味を持ちます。
糖尿病とはどのような病気か
糖尿病は血液中のブドウ糖濃度が慢性的に高くなる疾患です。インスリンの分泌量が低下する1型糖尿病とインスリンが十分に分泌されていても効果的に働きにくい2型糖尿病の2種類が代表的です。
特に2型糖尿病は生活習慣との関連が深く、食事や運動、ストレスなどが複雑に絡み合って血糖値の上昇につながります。
放置すると血管がダメージを受けて腎機能の低下や網膜症、神経障害などの合併症リスクが高まります。
食事回数と血糖値の関係
食事をとれば血糖値は上昇し、体はインスリンを分泌して血糖値を下げようとします。
食事回数が少ないと次の食事までの空腹時間が長くなり、空腹感が強い状態でまとめて糖質を摂取することにもなりかねません。
結果として食後の急激な血糖値上昇や、その後の血糖値乱高下につながる場合もあります。
反対に食事回数が多すぎると1回あたりの食事量が減っても、常に血糖値が上がりやすい状態になる可能性があります。食事回数と血糖値のバランスを考えることは重要です。
食事頻度を見直す意義
食事回数を適切に調整すると血糖値を必要以上に乱高下させにくい傾向があります。
一方で、糖尿病患者それぞれの体質や生活リズムは異なるため、一般的に1日3食が望ましい場合もあれば、状況によっては分割して1日4〜5食にすることもあります。
そこに一日一食のような極端に少ない回数の食事形態を組み合わせると、血糖値コントロールに影響を及ぼすだけでなく、他の栄養素不足やリバウンドなどの課題も考えられます。
食事回数が血糖値に与える影響
| 食事回数 | 主な特徴 | 血糖値コントロールへの影響 |
|---|---|---|
| 1日1食 | 空腹時間が長くなり、一度に摂る量が増える | 食後血糖値が急上昇しやすい、栄養バランスに注意 |
| 1日2食 | 朝食を抜くなどで時間を短縮 | 空腹時の強い飢餓感で次の食事量が増加しがち |
| 1日3食 | バランスが取りやすい | 一般的な方法で血糖値の安定をはかりやすい |
| 1日4食以上 | 小分けにして食べられる | 血糖値変動を抑えられるが、摂取カロリー過多に注意 |
食事回数の変更は血糖値の動きに直結するため、自身の生活リズムだけでなく医療者のアドバイスを受けながら慎重に検討することが大切です。
- 食事回数を増やせば血糖値の急激な上昇を緩和しやすい
- 食事回数を減らすと空腹時間が長くなりやすい
- 過度な制限による栄養不足の可能性もある
食事回数に関しては血糖値だけでなく、エネルギー量や栄養素のバランスを総合的に踏まえて調整することが望ましいです。
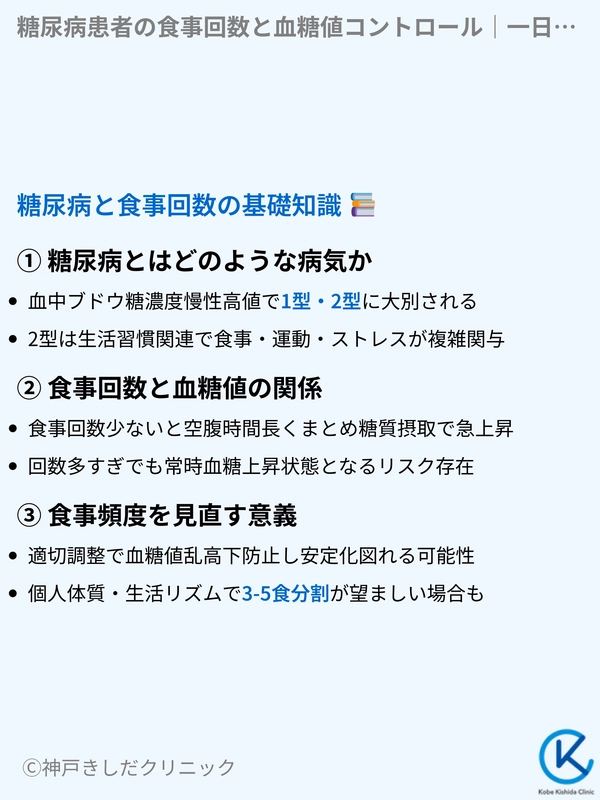
一日一食で夕食のみをとる方法の概要
一日一食の中でも夕食のみをとる方法は日中は何も食べず夜になってからまとめて食事をとるパターンです。
最近はダイエット目的でこの形態に関心を持つ方が増えており、糖尿病患者でも試したいと考えることがあります。
どのような狙いがあるのか
夕食のみとする目的は主に体重減少や摂取カロリーの制限です。
日中の摂取をゼロに近づけることで総摂取カロリーを抑え、体重を落とす狙いがあります。また、空腹時間が長いと内臓を休められるという考え方もみられます。
しかし糖尿病患者の場合は体重減少だけでなく、血糖値の安定や生活リズムへの影響を同時に考慮する必要があります。
そして、糖尿病患者にその医学的有用性が確認されているわけではありません。
- 一気に摂取カロリーを減らして体重コントロールを狙う
- 昼間に空腹を感じやすい
- 血糖値の乱高下に注意が必要
メリットとデメリット
メリットとしては食事の準備が1回で済むため食事管理がわかりやすいという声があります。食事の自由度がやや低くなり、結果的に摂取カロリーを抑えやすい面もあるでしょう。
一方で空腹時間が長いため、夕食時に過剰摂取になる可能性は高まります。
さらに、糖尿病患者にとって血糖値の急上昇と急下降は、動脈硬化の促進など合併症リスクを高める要因になり得ます。
一日一食のメリット・デメリット
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 食事管理 | 1回のため管理がわかりやすい | 夜に偏ることで不均衡になりやすい |
| 摂取カロリー | 総量を抑えやすい | 1回の食事量が増え、急激な血糖値上昇に注意 |
| 生活リズム | 仕事中は食事を気にしなくてよい | 昼間の空腹感が強くなり集中力に影響が出る場合も |
| 栄養バランス | 食材を限定しやすい場合がある | ビタミンやミネラルなどの不足が起こりやすい |
| 血糖値コントロール | 食後に分泌されるインスリンのピークは夕食時1回だけになる (メリットとまでは言い難い) | 血糖値の乱高下が大きくなる可能性がある |
見落としがちなリスク
「一日一食の夕食のみで糖尿病を管理しようとする方」もいますが、この方法を長期間続けるにはリスクがあります。
栄養不足だけでなく低血糖や高血糖のリスクが増大し、特に1型糖尿病などインスリン分泌が極端に不足する患者では糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)を招く可能性もあります。
さらに夕食を過度にとってしまうと胃腸に負担がかかり、睡眠にも影響を与えます。
こうした点を踏まえると、一日一食に踏み切る前に医師や管理栄養士と相談したほうがよいでしょう。
一日一食を検討する際に考慮したい項目
- 栄養素不足による体調不良の可能性
- 血糖値急上昇や急下降の危険性
- 日中の活動レベルとエネルギー需要
- 夜間の過剰摂取と睡眠の質低下
一日一食(夕食のみ)を実践するなら、主治医と相談の上で経過を慎重に観察し、定期的な検査を行いながら進める必要があります。
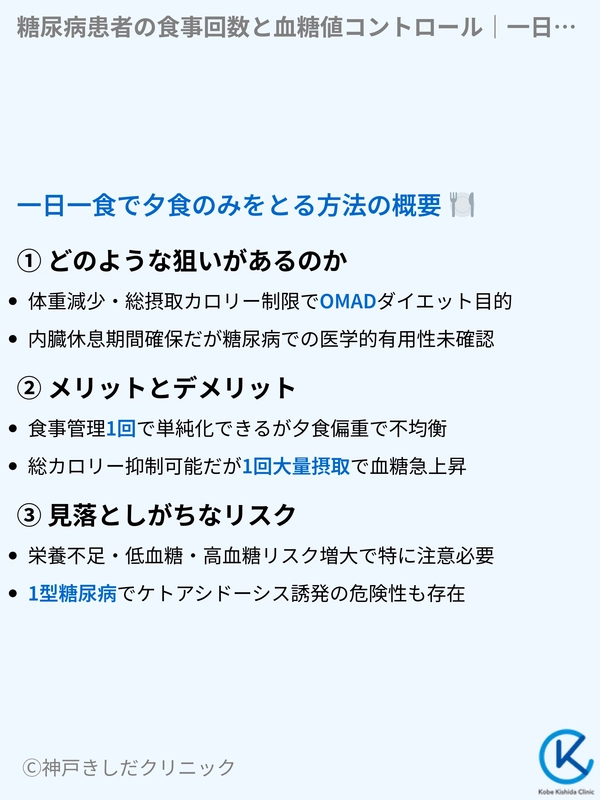
血糖値コントロールにおける注意点
糖尿病管理においては血糖値を常に安定させる工夫が必要です。
一日一食のように食事回数を極端に減らすと血糖値コントロールがかえって複雑になる可能性があります。
血糖値が上下するメカニズム
食事による血糖値の変動は糖質が吸収されて血液中のブドウ糖濃度が上昇し、それに応じてインスリンが分泌される一連の流れから生じます。
しかし、長時間空腹の状態が続くと体がエネルギー不足を補おうとして糖新生を活性化し、血糖値が思わぬタイミングで上昇することがあります。
また、食後にインスリンが過剰に分泌されると低血糖に陥ることもあるため、一日の血糖値の推移を予測するのは容易ではありません。
血糖値の変動イメージ
| 時間帯 | 状況 | 血糖値の変動 |
|---|---|---|
| 食後すぐ | ブドウ糖吸収開始 | 上昇傾向 |
| 食後2〜3時間 | インスリン作用ピーク | 一時的に安定または低下傾向 |
| 空腹時 | 血糖値低下 | 低血糖リスクまたは肝臓の糖放出で上昇 |
| 次の食事直前 | 再び空腹状態 | 血糖値はやや低いか、場合によって上昇 |
このように1日の中でも血糖値は常に変化し続けます。食事を1回しかとらない場合はその前後の血糖値の乱高下がより顕著になる恐れがあるのです。
食事療法との関連性
糖尿病の食事療法はカロリー制限や糖質制限などを組み合わせて、血糖値を緩やかに上下させる工夫を行います。
分割食やバランスのとれた食事が推奨されるのは身体への負荷が過度に偏らないようにするためです。
一日一食では糖質の摂取タイミングが1回に集中するため、血糖値を安定させたい食事療法の方針とは必ずしも合致しません。
そのため、一日一食を選ぶときは従来の食事療法とのギャップをどう埋めるかが大きな課題となります。
- 従来の食事療法は1日3食や4食に分けることが多い
- 緩やかな血糖値上昇をめざして糖質をコントロールする
- 一日一食では必要な栄養素・カロリーを一度にまとめて摂ることになるため、血糖値が急上昇しやすい
運動や薬物療法との併用
運動療法はインスリンの感受性を高め、血糖値を下げる効果が見込めます。
薬物療法では経口薬や注射薬(インスリンやGLP-1受容体作動薬など)を使い分けて血糖値を調整します。
一日一食の食事パターンでは運動をするタイミングによって低血糖を起こしやすくなる場合があるため注意が必要です。
また、薬物療法を受けている方は食事回数の変化と投薬量のバランスに大きなズレが生まれないよう、主治医と相談したうえで進めたほうがよいでしょう。
運動と薬物療法における注意点
- 運動前の血糖値を確認し、極端に低い場合は運動を中断する
- 運動直前に軽く炭水化物を補給する習慣がある場合は一日一食では食事がない時間帯の対応を検討する
- 薬物療法中の方は食事量やタイミングの変化が薬効に影響するため、変更時は医師に相談する
適度な運動は血糖値コントロールに役立ちますが、一日一食という食事回数の制限がある場合、低血糖や脱水症状などのリスクが高まる可能性があります。
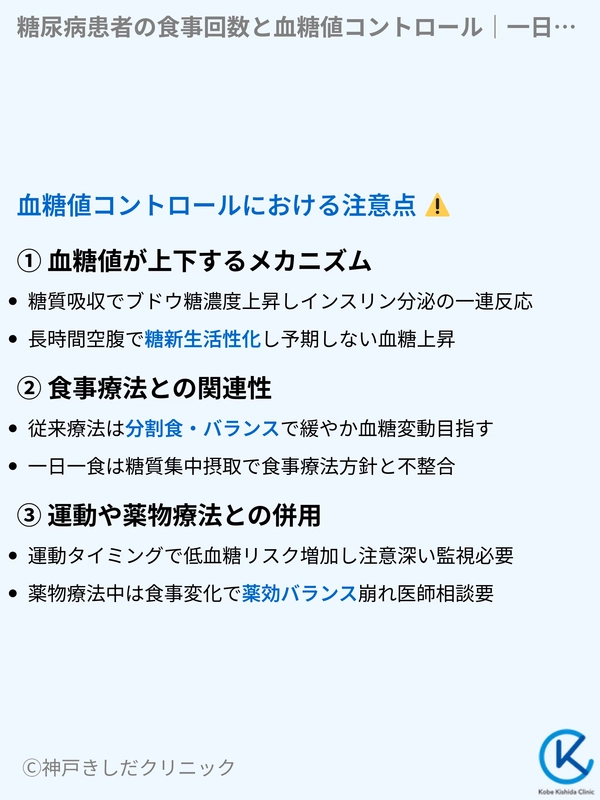
一日一食の夕食のみで糖尿病を考える際のポイント
糖尿病患者が「一日一食の夕食のみ」という食生活を実践する場合、以下の点に留意しておくことが重要です。
血糖値への影響
夕食1回にまとめて糖質を摂取すると食後高血糖になりやすく、インスリンの分泌量や作用とのバランスが崩れやすいです。
特に2型糖尿病の方はインスリン抵抗性が高い場合があるため、少量の糖質でも血糖値が急上昇するケースが考えられます。
また、空腹時間が長引くほど肝臓の糖放出などが生じ、血糖値が思わぬ形で変動する点にも気をつける必要があります。
糖尿病患者が一日一食を行うときの血糖値推移イメージ
| 時間帯 | 可能な状態 | 対応や注意点 |
|---|---|---|
| 朝〜夕方 | 長時間の空腹状態 | 低血糖症状や飢餓感、集中力低下に注意 |
| 夕食直後 | まとめて糖質を摂取するため血糖値急上昇 | 食物繊維やたんぱく質を一緒に摂る工夫が重要 |
| 夕食2〜3時間後 | インスリン作用ピークで血糖値が急降下の恐れ | 運動タイミングや薬剤調整の必要性がある |
| 深夜〜早朝 | 食事から時間が経過 | 追加の栄養補給がなく低血糖リスクが高まる |
筋肉量と基礎代謝
一日一食にすると必要なカロリーやたんぱく質が不足しやすく、筋肉量が減って基礎代謝が下がる可能性があります。
筋肉量が減少するとインスリンの感受性も下がりやすく、結果的に血糖値コントロールが難しくなる場合があります。
特に高齢の糖尿病患者は筋力低下が健康状態に直結するため、食事回数を減らすときはたんぱく質源やビタミン、ミネラルなどを確保する工夫が欠かせません。
- たんぱく質不足で筋肉量が低下しやすい
- 筋肉量が少ないとインスリン抵抗性が上昇する
- 運動と十分な栄養摂取を組み合わせることが重要
栄養バランスの確保
夕食のみで1日の必要栄養素をすべてカバーするのは難しく、糖尿病であればなおさらバランスに気を配る必要があります。
糖質、たんぱく質、脂質に加え、ビタミンやミネラル、食物繊維など多様な栄養素を過不足なく摂取するのは簡単ではありません。
もし一日一食に挑戦するなら栄養バランスを支える具体的な食材選びやサプリメントの活用なども検討した方が安全です。
一回の食事で取り入れたい栄養素
- たんぱく質(肉、魚、大豆製品、卵など)
- 脂質(良質な油脂、ナッツ、青魚など)
- 炭水化物(白米だけでなく全粒穀物や豆類も活用)
- ビタミン・ミネラル(野菜、果物、海藻類)
- 食物繊維(野菜、きのこ、海藻、豆類)
このようなバランスを夕食1回ですべて補うのは大変であるため、実践する場合は食材を厳選しながら工夫を凝らす必要があります。
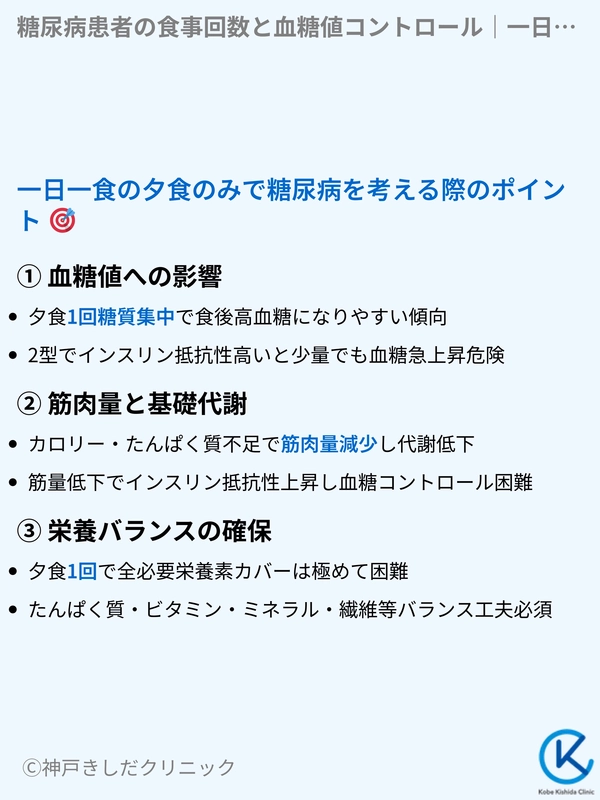
多食回数との比較
一日一食を検討する際には、あえて2食や3食と比べてどのような違いがあるのかを理解することが大切です。
それぞれの食事回数にはメリットと課題が存在します。
1日3食・1日2食との違い
一般的な1日3食の食事パターンは、朝・昼・夜でエネルギーと栄養を分散し、血糖値変動をやわらげやすい方法として知られています。
一方、1日2食の場合は朝食または夕食を抜くことが多く、抜いたタイミングに空腹が長くなり、まとめ食いのリスクが生じます。
一日一食では2食よりもさらに空腹時間が長く、飢餓状態に近づきやすいため血糖値の乱高下が大きくなる傾向があります。
食事回数による特徴
| 食事回数 | 特徴 | 血糖値への影響 |
|---|---|---|
| 1日3食 | バランスがとりやすく多くの人に受け入れやすい | 緩やかな血糖値変動をめざしやすい |
| 1日2食 | 朝食か昼食を抜くケースが多い | 空腹時間が長く、次の食事で過食の恐れ |
| 1日1食 | 空腹時間が最も長くなる | 食後血糖値の急上昇リスクが高まる |
血糖値への影響比較
1日3食を基本とし、血糖値を安定させるために糖質を分割して摂取するのが従来の考え方です。
これに対し一日一食は食事による血糖値上昇のタイミングを1回にまとめるため、一見するとインスリン負荷を減らせるように思われます。
しかし実際には1回の食事で大量に糖質やカロリーを摂取するため、血糖値急上昇が顕著になることが多いです。
また、空腹時間が長くなることで肝臓からの糖放出も活性化し、思わぬタイミングで血糖値が上昇するリスクがあります。
- 3食分散の方が血糖値の上昇をコントロールしやすい
- 一日一食は1回の負荷が大きく、変動幅が大きい傾向
- 空腹時間における体内の糖新生やホルモンバランスにも留意する必要がある
日常生活へのフィット感
糖尿病管理には無理のない生活習慣が欠かせません。
一日一食にすると夜まではまともに食事をせず、仕事や家事などを行う必要があるため、日常的に強い空腹と戦うことになります。また、低血糖のリスクも無視できません。
3食や2食の方が体内リズムを安定させ、日常生活との相性もとりやすいと感じる方が多いです。
単純に摂取カロリーを減らすだけでなく、持続的に実行しやすいかどうかを考慮することが大切です。
食事回数と生活習慣の関係を示すリスト
- 夜勤や不規則勤務の場合1日3食以外の分割が望ましいケースもある
- 学校やオフィスで昼食を摂る習慣があると一日一食は不便
- 家族がいる場合は共同生活の中で食事回数を極端に変えると負担になる
- 血糖値測定や薬のタイミングが複雑化する可能性がある
生活リズムとあまりにかけ離れた方法はストレスも大きく、長期的には体調管理を難しくします。
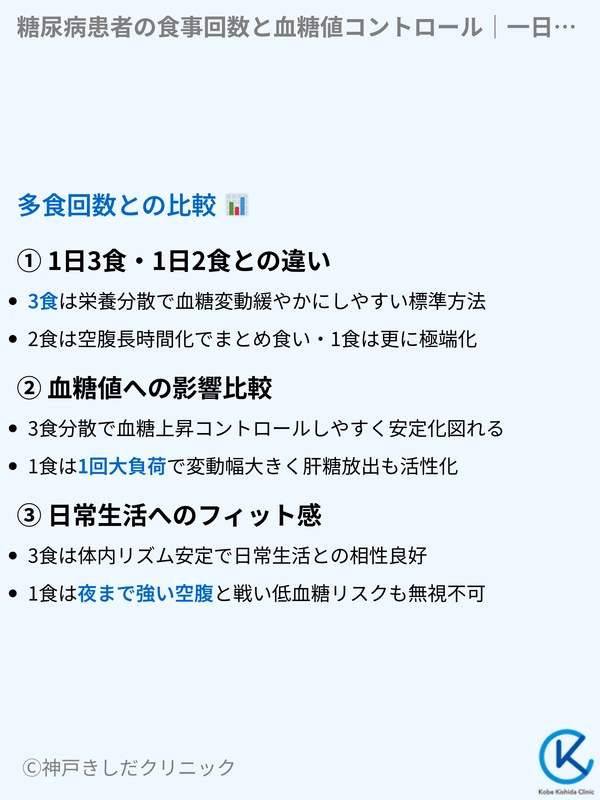
クリニック受診のすすめ
糖尿病をコントロールするには、自己判断だけでは限界があります。
一日一食など特殊な食事法に取り組む際は専門医や医療スタッフのサポートを受けることが重要です。
血糖値測定の重要性
糖尿病管理で大切なのは自己血糖測定や定期的なHbA1c(ヘモグロビンA1c)のチェックです。
一日一食を行う場合も空腹時血糖や食後血糖をこまめに測定して数値の推移を確認する必要があります。
血糖値が急上昇しているのに自覚症状が少ないケースもあるので、客観的なデータを把握する意義は大きいです。
血糖値測定のタイミングと注意点
| タイミング | 目的 | 注意点 |
|---|---|---|
| 空腹時(朝起床時) | 基礎的な血糖値レベルの確認 | 測定前の飲食に注意 |
| 食前 | 食事前の血糖値をチェック | 低血糖症状の有無も確認 |
| 食後2時間 | 食事による血糖値のピーク・持続時間の把握 | 忘れずにタイマーを設定 |
| 就寝前 | 夜間の血糖値変動リスクを予測 | 必要なら軽食摂取も検討 |
専門医との相談
一日一食のような食事パターンは体への負担や栄養不良を引き起こすリスクがあります。
特に糖尿病患者は血糖値が変化しやすいため、独断で始めると合併症を悪化させる可能性があります。
主治医や管理栄養士、糖尿病専門医への相談は個々の病状や生活背景に応じた助言をもらううえで有効です。具体的なアドバイスを受けながら進めることで安全性を高められます。
- 現在のHbA1cや血糖値の傾向を分析してもらう
- 食事回数を減らすメリット・デメリットを医師と共に検討
- 必要に応じてサプリメントや薬剤調整の指示を仰ぐ
個別性に応じた指導
糖尿病のコントロールには個人差が大きく、年齢や性別、合併症の有無、ライフスタイルなどさまざまな要因が関わります。一日一食が合う人もいれば、まったく合わない人もいます。
専門医の指導を受けることで栄養指導や生活習慣改善を自分に合ったかたちで組み立てやすくなります。
同じ「一日一食」でも毎回の食事内容やタイミング、摂取カロリー目安が異なる場合があります。
個別指導で着目される主なポイント
- 既存の病歴や合併症の状態
- 仕事や学業などの生活パターン
- 運動や睡眠時間、ストレスレベル
- 遺伝的素因や家族歴
こうした要素を総合的に判断してこそ適切な食事回数や食事内容が導き出せます。
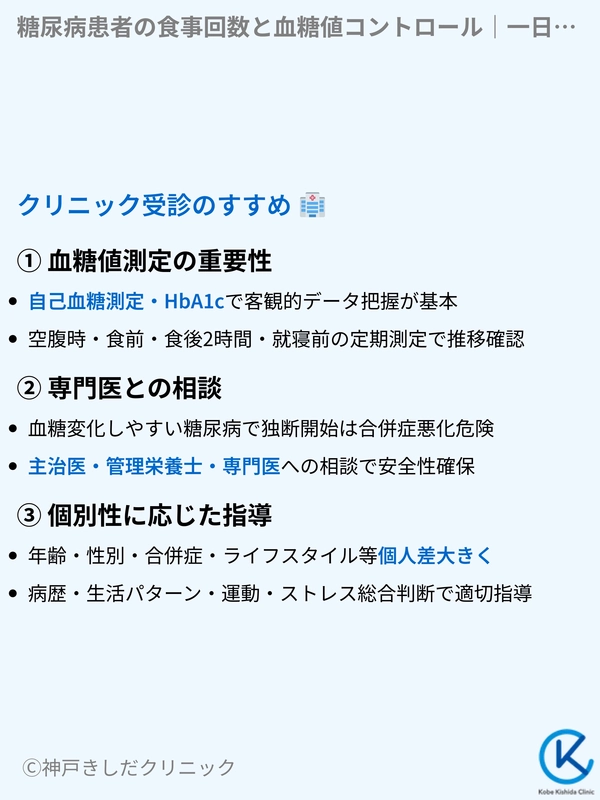
生活習慣全体を見直す必要性
糖尿病は血糖値だけでなく、心血管リスクや腎機能、精神的健康状態など多岐にわたる要素が絡みます。
一日一食など特定の食事法だけに注目しすぎると、運動不足や睡眠不足、ストレス過多など他の生活習慣の改善がおろそかになる恐れがあります。
食事療法『だけ』に頼らない考え方
もちろん食事管理は糖尿病治療の大きな柱ですが、運動や適切な睡眠、ストレスのコントロールも重視する必要があります。
食事回数を減らすだけで血糖値がコントロールできるわけではなく、身体活動量やホルモンバランス、生活リズム全般との調和が不可欠です。
食事療法に加えて取り入れたいこと
| 項目 | 具体例 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 運動療法 | ウォーキング、軽い筋トレ、スイミングなど | インスリン感受性の向上、体重管理 |
| 睡眠管理 | 毎日6〜8時間の十分な睡眠、規則正しい就寝時間 | ホルモンバランスの安定、疲労回復 |
| ストレス対策 | 趣味やリラクゼーション、カウンセリングなど | ストレスホルモンによる血糖上昇の抑制 |
| 定期検診 | 血液検査、合併症のスクリーニング | 早期発見と状態把握 |
ストレスケアの視点
ストレスが強いとコルチゾールなどのホルモンが増加し、血糖値が上昇しやすくなります。
一日一食のような厳しい食事制限は空腹時間が長く精神的負担が増す恐れがあります。加えて栄養不足になればイライラや集中力低下を招き、結果的にストレスが高まる悪循環が生じることもあります。
気分の浮き沈みが大きいと感じる方は無理な食事制限ではなく、まずはストレスコントロールから取り組むのもよいでしょう。
- ストレスが血糖値に直接影響することがある
- 空腹ストレスが大きすぎると精神面にも悪影響
- 趣味や運動を通じてリラックスできる時間を確保する
長期的な健康維持のために
糖尿病は一時的な血糖値の改善だけでなく、合併症を防ぎながら長く健康を保つことが重要です。
極端な食事制限を短期間で実行してもリバウンドや合併症リスクの上昇という別の問題が起こり得ます。
一日一食を検討している方も長期的視野で血糖値や体重、栄養バランスをコントロールするために、複数の要素を統合的に見直すことが望ましいです。
長期的な健康管理のための要点
- 生活リズムと食事パターンの調和を保つ
- 定期的な検診で血糖値や合併症リスクをチェック
- 運動・睡眠・ストレスケアを並行して行う
- 必要に応じて医師や専門家のアドバイスを受ける
極端な方法だけに頼るのではなく、自分の体がどのように変化しているかを定期的に観察し、必要に応じて軌道修正していく姿勢が重要です。
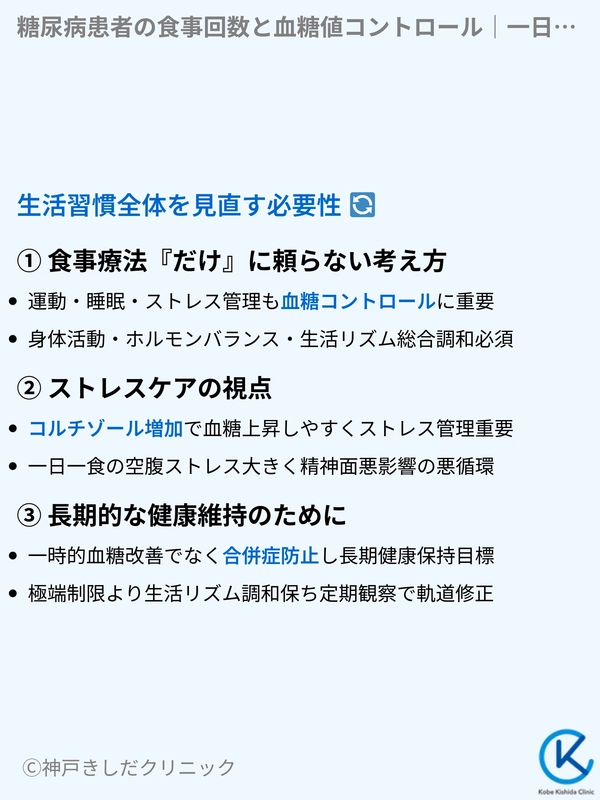
よくある質問
糖尿病患者が一日一食に挑戦する際には疑問や不安が尽きません。いくつか代表的な質問とその答えをまとめます。
一日一食は本当に痩せるのか
短期的には体重が減少する傾向があります。しかし、空腹時間が長い分、過食につながりやすい面もあります。さらに、筋肉量が減って基礎代謝が落ちる可能性があるため、必ずしも長期の減量効果が見込めるとは限りません。健康的な痩せ方をめざすなら、栄養バランスと運動を組み合わせるほうが血糖値の安定にもつながります。
運動はどのように組み合わせればいい?
空腹時に激しい運動を行うと低血糖のリスクが高まります。一日一食を選択した場合は、食事のあと2〜3時間ほど経ってから適度な運動を行うなど、血糖値の急降下を避ける工夫が必要です。運動内容や強度は、主治医と相談したうえで決めるのが安心です。
どうして血糖値が安定しないのか
糖尿病はインスリンの分泌量や感受性に問題があるため、一日の食事バランスが乱れたり、空腹時間が長くなったりすると血糖値の上下動が大きくなります。一日一食は特に食後血糖値の上昇が激しくなる可能性があるため、バランスのとれた栄養摂取と複数回に分割する食事パターンのほうが安定しやすい場合があります。
以上
参考にした論文
SAITO, Toshikazu, et al. Lifestyle modification and prevention of type 2 diabetes in overweight Japanese with impaired fasting glucose levels: a randomized controlled trial. Archives of internal medicine, 2011, 171.15: 1352-1360.
FUJII, Hiroki, et al. Impact of dietary fiber intake on glycemic control, cardiovascular risk factors and chronic kidney disease in Japanese patients with type 2 diabetes mellitus: the Fukuoka Diabetes Registry. Nutrition journal, 2013, 12: 1-8.
KAHLEOVA, Hana, et al. Eating two larger meals a day (breakfast and lunch) is more effective than six smaller meals in a reduced-energy regimen for patients with type 2 diabetes: a randomised crossover study. Diabetologia, 2014, 57: 1552-1560.
HORIKAWA, Chika, et al. Dietary sodium intake and incidence of diabetes complications in Japanese patients with type 2 diabetes: analysis of the Japan Diabetes Complications Study (JDCS). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2014, 99.10: 3635-3643.
MURAKAMI, Kentaro, et al. Dietary glycemic index and load in relation to metabolic risk factors in Japanese female farmers with traditional dietary habits2. The American journal of clinical nutrition, 2006, 83.5: 1161-1169.
ALKHULAIFI, Fatema; DARKOH, Charles. Meal timing, meal frequency and metabolic syndrome. Nutrients, 2022, 14.9: 1719.
SHIMIZU, Mika, et al. Cross‐sectional association of irregular dietary habits with glycemic control and body mass index among people with diabetes. Journal of Diabetes Investigation, 2025, 16.2: 285-291.
OKUDA, Masayuki; FUJIWARA, Aya; SASAKI, Satoshi. Adherence to the Japanese Food Guide: The association between three scoring systems and cardiometabolic risks in Japanese adolescents. Nutrients, 2021, 14.1: 43.
ST-ONGE, Marie-Pierre, et al. Meal timing and frequency: implications for cardiovascular disease prevention: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation, 2017, 135.9: e96-e121.
SAKURAI, Masaru, et al. Dietary glycemic index and risk of type 2 diabetes mellitus in middle-aged Japanese men. Metabolism, 2012, 61.1: 47-55.



