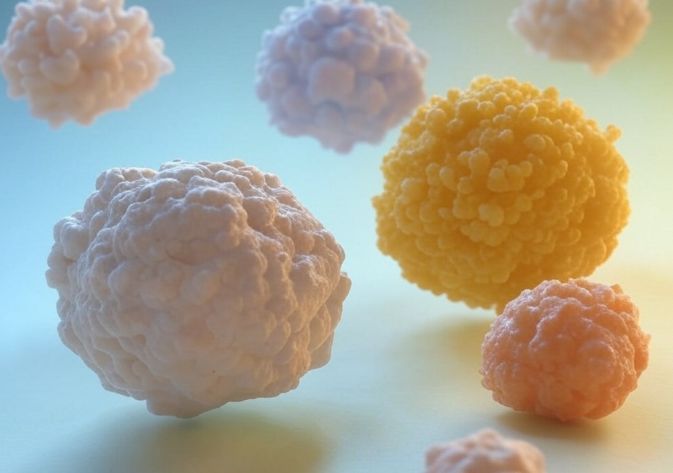脂質は毎日の食生活で欠かせない栄養素の1つであり、エネルギー源として重要です。
しかし脂質には多くの種類があり、その摂り方を誤ると体重管理だけでなく血糖値の乱れにもつながります。
ここでは
脂質の基礎知識
脂質は糖質やたんぱく質と並ぶエネルギー源であり、身体機能を維持するうえで大切です。
ここでは脂質を知るうえで押さえておきたいポイントを取り上げます。脂質に対する正しい理解を得ると、日々の食生活を見直すうえでも役立つでしょう。
脂質とは何か
脂質は炭素・水素・酸素などが結合した化合物の総称です。
主な役割はエネルギーを蓄えることや細胞膜を構成することなどで、体内のあらゆる組織に存在します。多くの食品に含まれ、特に植物油や動物性の食材には豊富に含まれています。
脂質は1gあたり9kcalのエネルギーをもたらすため適度な摂取は健康を支えますが、過剰な摂取は肥満や生活習慣病のリスク要因になりやすいです。
エネルギー源としての重要性
糖質が不足した際に脂質は身体を動かす貴重なエネルギー源になります。エネルギー源が糖質だけではなく脂質にも分散されることで、身体は安定した状態を保ちます。
また、食事から摂った脂質が身体に蓄積されることで飢餓状態や体調不良時のエネルギー補給に役立ちます。
一方で脂質を多量に摂りすぎるとエネルギー過多になり、肥満や血糖値上昇などに影響を与えることがあります。
細胞膜やホルモン合成にもかかわる
脂質は身体の細胞を取り巻く膜の材料にもなります。細胞膜を守ることで外部からの刺激を和らげたり、栄養分や老廃物のやり取りをコントロールしたりします。
また、ホルモン合成にもかかわるため、血圧や代謝、ストレス応答などの調整を担います。
脂質が不足すると細胞膜が弱くなるだけでなく、ホルモンバランスの乱れにより体調を崩すことも考えられます。
脂質過剰摂取のリスク
身体に必要な脂質ですが、過剰摂取すると体重増加や内臓脂肪蓄積の要因になりやすいです。
さらに脂質の種類によっては血中コレステロールの増加に影響を及ぼし、動脈硬化や心筋梗塞などのリスクを高めます。
とくに糖尿病に着目した場合、血糖値が不安定な状態で脂質を過剰に摂ると血管障害の進行を促進しやすくなります。
脂質全般を忌避する必要はありませんが、質と量をバランスよく管理することが大切です。
脂質に関する基礎的な表
| 項目 | 役割 | 過不足時の影響 |
|---|---|---|
| エネルギー源 | エネルギー貯蔵、糖質不足時の代用エネルギー | 過剰:肥満、生活習慣病のリスク増 不足:疲れやすい |
| 細胞膜の構成要素 | 細胞の外部刺激を和らげる、物質のやり取りを整える | 不足:細胞膜機能の低下 |
| ホルモン合成 | 代謝や血圧などの調節 | 不足:ホルモンバランスの乱れ |
主な脂質の種類
食生活においては脂質の種類を知ることが食事管理のカギになります。
ここでは代表的な脂質の種類を解説します。正しい知識を得ると自分の食生活にどんな油脂が多いかを振り返るきっかけになるでしょう。
飽和脂肪酸
飽和脂肪酸は動物性脂肪に多く含まれる脂質の種類です。肉の脂身やバター、ラードなどに豊富です。
常温で固体になりやすく、過剰に摂るとLDLコレステロール(一般的に“悪玉コレステロール”と呼ばれます)を増加させ、動脈硬化や心血管系の疾患リスクを高めます。
ただし、極端に避けると栄養バランスを崩す原因になるため、適度な摂取が望ましいです。
不飽和脂肪酸(オメガ3系・オメガ6系・オメガ9系)
不飽和脂肪酸にはオメガ3系、オメガ6系、オメガ9系があります。
オメガ3系は青魚やえごま油、アマニ油などに含まれ、血液をさらさらにする働きが知られています。
オメガ6系は大豆油やコーン油などに多く、身体の機能調整に関与しますが、摂りすぎると炎症が起きやすくなる可能性があります。
オメガ9系はオリーブオイルに豊富で、血中コレステロールをコントロールする働きが期待されています。
これらをバランスよく摂ると健康づくりに役立ちます。
トランス脂肪酸
トランス脂肪酸は植物油を加工する過程で生じることが多く、マーガリンやファットスプレッドなどに含まれます。
過剰に摂るとLDLコレステロールを増やし、HDLコレステロール(一般的に“善玉コレステロール”と呼ばれます)を減らすため動脈硬化や心血管疾患のリスクを高めます。
欧米ではトランス脂肪酸の摂取量が多く、健康に対する影響が懸念されてきましたが、日本国内でも加工食品をよく食べる方は注意が必要です。
コレステロール
コレステロールは卵黄やレバー、エビなどの動物性食品に多く含まれます。
細胞膜やホルモンの材料になり、身体にとって大切ですが、過剰に摂ると血中コレステロールが高くなりやすいです。
特に糖尿病の方は血管合併症のリスクがさらに高まるため、コレステロールを意識した食事管理が求められます。
食事からだけでなく身体の中で合成されることも考慮しながら総摂取量をコントロールすることが重要です。
主な脂質と特徴
| 脂質の種類 | 含有食品例 | 体への影響 |
|---|---|---|
| 飽和脂肪酸 | バター、肉の脂身、ラードなど | LDLコレステロールを高めやすい |
| 不飽和脂肪酸(オメガ3) | 青魚、えごま油、アマニ油 | 血液をさらさらにし、炎症抑制を助ける |
| 不飽和脂肪酸(オメガ6) | 大豆油、コーン油、ゴマ油 | 過剰摂取で炎症や生活習慣病のリスク増 |
| 不飽和脂肪酸(オメガ9) | オリーブオイル、アボカド | LDLコレステロールのコントロールを助ける |
| トランス脂肪酸 | マーガリン、ショートニング | LDLコレステロール上昇、HDLコレステロール低下 |
| コレステロール | 卵黄、レバー、エビ | 細胞膜やホルモン合成に重要だが過剰注意 |
脂質の働きと身体への影響
脂質はエネルギーを補給するだけでなく、身体のさまざまな機能を調整します。
ここでは脂質が身体に与える影響を深く見てみましょう。摂り過ぎによるリスクだけでなく、不足や質の偏りによるデメリットも理解することが大事です。
体内での脂質の役割
脂質はエネルギー源としての役割に加えて次のような働きがあります。
- 細胞膜を構成して物質のやり取りを管理する
- 脳など中枢神経系の保護膜を形成する
- ホルモンや胆汁酸をつくる材料になる
- 脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の吸収を助ける
脂質は身体のさまざまな場所で活躍し、健康を維持します。
しかし、量だけでなく種類のバランスを整えることがポイントになります。
過剰摂取による肥満や動脈硬化
脂質を多量に摂取すると高カロリーになりやすく肥満を招きます。肥満が進むと内臓脂肪が増えやすく、糖尿病や脂質異常症、高血圧など生活習慣病のリスクが上昇します。
また、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸、コレステロールを過剰に摂り続けると動脈硬化が進みやすくなります。
血管が硬くなると高血圧や心筋梗塞、脳卒中など深刻な病気につながる可能性があります。
不足や偏りによる身体への影響
脂質を極端に制限するとエネルギー不足や脂溶性ビタミンの吸収不良が生じます。
特に脂溶性ビタミンは骨の健康や抗酸化作用などに関与するため、これらが不足すると身体の機能が低下しがちです。
さらに、細胞膜やホルモンの材料が不十分になり、疲れやすさやホルモンバランスの乱れを招くことも考えられます。
食事全体のバランスが大切
脂質摂取を考えるうえでは糖質やたんぱく質など他の栄養素とのバランスも見逃せません。
炭水化物を減らすダイエットが話題になることがありますが、脂質を極端に増やすとコレステロールや飽和脂肪酸を多く摂りやすくなるため、慎重な管理が必要です。
総エネルギー量の何割を脂質から摂るか、自分の身体や生活習慣に合わせて考えてみましょう。
脂質摂取バランスの目安
| 栄養素 | エネルギー比率の目安(%) | 主な役割 |
|---|---|---|
| 脂質 | 20〜30 | エネルギー源、細胞膜構成、ホルモン合成 |
| たんぱく質 | 10〜20 | 筋肉や臓器の材料 |
| 炭水化物 | 50〜65 | エネルギー源(主に糖質) |
糖尿病との関係
糖尿病は血糖値のコントロールが困難になる病気です。ここでは脂質と糖尿病がどのように関わり合うのかを解説します。
脂質の過剰摂取や質の偏りが血糖コントロールにどのような影響を及ぼすかを知ると、糖尿病予防や合併症リスクの軽減に役立ちます。
脂質代謝とインスリン抵抗性
糖尿病ではインスリンの働き(または分泌量)が不足し、血糖値が上昇しやすい状態になります。
内臓脂肪が増えるとインスリン抵抗性が高まると考えられており、血中の余分な脂質がインスリンの効きを妨げる要因の1つとなります。
こうした状態が続くと高血糖が慢性化しやすくなり、合併症のリスクも高まります。
動脈硬化との関連
糖尿病になると高血糖によって血管が傷つきやすい状況になります。
そこに飽和脂肪酸やトランス脂肪酸が多い食生活が加わると、血中コレステロールが上昇し、血管内にプラークができて動脈硬化が進行しやすいです。
動脈硬化が悪化すると脳卒中や心筋梗塞など深刻な病気を引き起こす恐れがあります。
食事療法における脂質の制限
糖尿病の食事療法では糖質だけでなく脂質の摂り方も大切です。
飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の摂取を控えめにし、不飽和脂肪酸を増やすと血中脂質の状態が改善しやすいと考えられます。
ステロールの摂取量にも注意が必要で、動物性食品を過剰に摂らないように心がけるとよいでしょう。
血糖値管理のための注意点
糖尿病の方が脂質を管理する際は以下の点を意識すると血糖値コントロールに役立つ場合があります。
- 内臓脂肪を増やさないように総カロリー量を適切にする
- 飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を減らし、不飽和脂肪酸を意識する
- 食物繊維を多く含む野菜や海藻類を組み合わせる
- 間食をコントロールして血糖値の急上昇を避ける
糖尿病と脂質の関連に関する表
| 要素 | 影響 |
|---|---|
| インスリン抵抗性 | 内臓脂肪増加により高まる可能性 |
| 血中コレステロール | 飽和脂肪酸、トランス脂肪酸過多で上昇しやすい |
| 動脈硬化のリスク | 高血糖と高脂質の組み合わせで進行しやすい |
| 食事療法での脂質管理の重要性 | 血糖値と血中脂質を同時に調整するために必須 |
脂質を意識した食事のポイント
脂質の種類を知ったうえで、どのように食事に取り入れればよいか悩む方もいるでしょう。
ここでは日々の調理や食材選びに役立つポイントを紹介します。ちょっとした工夫が長期的な健康管理につながります。
食材選びのコツ
肉類を選ぶときは赤身や脂肪分の少ない部位を選ぶと飽和脂肪酸を抑えられます。鶏肉なら皮を取り除いた部位を使うとよいです。
また、魚は青魚に多く含まれるオメガ3系の脂肪酸を摂取できるので、週に数回は取り入れてみてください。
植物性食品をうまく組み合わせると不飽和脂肪酸が増え、コレステロール摂取量も抑えられます。
脂質を意識した食材のリスト
- 赤身の牛肉、皮なし鶏肉
- 青魚(サバ、イワシ、サンマなど)
- 大豆製品(豆腐、納豆、豆乳)
- オリーブオイル、えごま油、アマニ油
- アボカド、ナッツ類(アーモンド、くるみ)
調理法で変わる脂質摂取
同じ食材でも調理法によって脂質量が変わります。揚げ物やバター・ラードを使った炒め物は脂質が増える傾向があります。
一方、蒸す・煮る・茹でるなどの方法を選ぶと脂質の摂取を抑えられます。
サラダドレッシングもオイルベースよりヨーグルトベースなどを選ぶと脂質量を低減できます。
外食や中食で気をつけたい点
忙しい現代では外食や弁当、総菜を利用する機会が多くなりがちです。こうした食事は味付けが濃いものや揚げ物が多く、飽和脂肪酸やトランス脂肪酸を取り入れやすい傾向があります。
選ぶ際に以下のような工夫をするとよいでしょう。
- 野菜やサラダ、スープなどを組み合わせて過度な脂質を抑える
- 揚げ物ではなく、焼き物や刺身などに変える
- ドレッシングやソースは別添えにして使う量を調整する
- デザートや甘い飲み物は控える
食事記録で客観的に把握
自分がどのくらい脂質を摂取しているかを知るために食事記録をつけると客観的に把握しやすいです。
カロリーや栄養素をすべて数値化するのは大変かもしれませんが、食べた内容をざっくりメモするだけでも脂質の摂り過ぎに気づきやすくなります。
記録していると、どういった食材や調理法が多いかも見えてくるでしょう。
調理方法と脂質量の概略表
| 調理法 | 特徴 | 脂質摂取量 |
|---|---|---|
| 揚げる | 衣が油を吸収しやすい | 多くなりがち |
| 炒める | 油を使うが、揚げるよりは少なく抑えられる | 中程度 |
| 焼く | 余分な脂が落ちることもある | 中程度 |
| 煮る・蒸す | 調味料の選び方で脂質を抑えやすい | 少なめ |
| 茹でる | 油を使わずに調理できる | 少なめ |
脂質の種類の一覧と摂取目安
脂質にはいろいろな種類があり、それぞれの特徴を知ることが食事管理に役立ちます。
ここでは脂質の種類の一覧と一般的な摂取目安を解説します。自分の生活習慣や健康状態に合わせて調整すると、無理なく実践しやすくなります。
脂質の種類を整理する
前述のとおり、脂質の種類は大きく飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸(オメガ3、オメガ6、オメガ9)、トランス脂肪酸、コレステロールに分かれます。
飽和脂肪酸やトランス脂肪酸は過剰摂取を避け、不飽和脂肪酸を十分に摂ることが大切です。
コレステロールも必要量を超えないようにコントロールしてください。
一般的な摂取目安
1日に摂取する総エネルギー量のうち、脂質から得る割合は20〜30%程度が推奨とされることが多いです。
例えば1日2,000kcalを摂る人であれば脂質由来は400〜600kcal程度が望ましい計算になります。
飽和脂肪酸は全エネルギーのうち7%以下に抑えるようにすることがよく提案されます。
エネルギー割合と脂質の大まかな目安表
| 総エネルギー量(kcal/日) | 脂質摂取(20〜30%) (kcal) | 脂質量 (g)(1g=9kcal換算) |
|---|---|---|
| 1,600 | 320〜480 | 約36〜53 |
| 2,000 | 400〜600 | 約44〜67 |
| 2,400 | 480〜720 | 約53〜80 |
| 3,000 | 600〜900 | 約67〜100 |
コレステロール摂取の指標
コレステロールの摂取目安は1日200〜300mg以下とすることが多いですが、健康状態や個人差によって変わります。
卵1個には約200mgのコレステロールが含まれるため、毎食卵料理が続くと過剰になりやすいかもしれません。食品表示をチェックしながら、摂りすぎにならないように工夫してください。
バランスを整えるための工夫
脂質の種類の一覧を意識して、それぞれをバランスよく摂るためには以下のような工夫ができます。
- オメガ3系脂肪酸を意識して魚やえごま油、アマニ油を取り入れる
- オリーブオイルを使用してオメガ9系脂肪酸も活用する
- 飽和脂肪酸を取りすぎないように、肉よりも魚や大豆製品を選ぶことを心がける
- トランス脂肪酸を含む加工食品を控えめにする
脂質コントロールの重要性
脂質は身体にとって重要なエネルギー源ですが、過不足や偏りがあると健康リスクが高まります。
ここでは脂質コントロールの必要性についてさらに深く踏み込みます。生活習慣病の予防や改善に取り組みたい方はぜひ参考にしてみてください。
生活習慣病リスクとの関連
脂質を多く含む食品を好んで食べる人は総エネルギーの過剰摂取につながりやすい傾向があります。
肥満はもちろん、脂質異常症や高血圧などの生活習慣病のリスクを高めます。
また、糖尿病との関連も大きく、すでに糖尿病を持っている方は血中脂質のコントロールが合併症予防においてとても大切です。
生活習慣病と脂質との関連
| 疾患 | 脂質との関連 |
|---|---|
| 糖尿病 | 内臓脂肪増加によるインスリン抵抗性の上昇 |
| 脂質異常症 | LDLコレステロールや中性脂肪の増加 |
| 高血圧 | 血管壁の硬化、血液ドロドロ状態による血管抵抗上昇 |
| 動脈硬化 | LDLコレステロール過多や高血糖で進行 |
身体バランス維持に欠かせない要素
脂質は脂溶性ビタミンの吸収を助け、細胞やホルモンの材料として欠かせない栄養素です。
完全に脂質をカットするのではなく、必要な分を質の良い脂質から摂ることが身体バランスを保つカギになります。
無理な食事制限は体調不良やリバウンドを起こしやすいため注意しましょう。
運動習慣との併用
食事だけでなく、運動も脂質コントロールを助けます。運動によってエネルギー消費量が増えると、摂取した脂質を効率的に使えます。
ウォーキングや軽いランニング、水泳など有酸素運動を取り入れて、脂質代謝を活性化させることが大切です。
筋力トレーニングを組み合わせると基礎代謝の向上も期待できます。
定期的な検査での確認
血中脂質や血糖値、肝機能などを定期的に検査し、自分の健康状態を把握することが脂質コントロールの要になります。
数値に変化が見られたら食事内容や運動量を見直してみましょう。
医療機関に相談すると、より適切な指導を受けられます。
日常生活で気をつけたいポイント
ここでは具体的な生活習慣の中でどのように脂質を管理したらよいかについてまとめます。
何気ない日常の積み重ねが将来の健康状態に大きく影響します。適切な知識を身につけ、続けられる方法を見つけてみてください。
買い物時のラベルチェック
市販の加工食品を購入する際は栄養成分表示や原材料名を確認すると、自分がどのくらいの脂質を摂ろうとしているかをイメージしやすくなります。
特に「マーガリン」「ショートニング」などトランス脂肪酸を含みやすい原材料や、「動物性油脂」が多いことを示す表記があるものには気をつけましょう。
食事スケジュールを整える
夜遅い時間に大量の食事を摂ると脂質が蓄積しやすく、肥満や糖尿病リスクが高まります。
規則正しい時間に食事をとることで、血糖値や脂質のコントロールがしやすくなります。
また、食事の時間が不規則な場合は調整可能な範囲でできる限り同じような時間帯に食べる工夫をするとよいでしょう。
生活リズムを整えるためのリスト
- 朝食を抜かずに軽めでも食べる
- 昼は主菜・副菜をバランスよく組み合わせる
- 夜は寝る3時間前までに済ませる
- 間食や夜食の頻度を減らす
アルコールとの付き合い方
アルコールの過剰摂取はエネルギー過多になるだけでなく、脂質異常や肝機能への負担につながります。
ビールやカクテルなどは糖質も多いため、脂質だけでなく血糖コントロールにも影響を与えます。
飲酒量を見直し、適量を守って嗜むことが健康管理のポイントです。
ストレス管理も考慮
過度のストレスがかかると食生活が乱れたり、血糖値のコントロールが難しくなることがあります。
ストレス解消のために暴飲暴食をしてしまうと、脂質や糖質を過剰に摂取する原因になるかもしれません。
ウォーキングなど軽い運動や趣味の時間を設けて、ストレスをため込まないよう心がけてみましょう。
ストレス軽減につながる習慣
| 取り組み | 期待できる効果 |
|---|---|
| ウォーキング | 血行促進、リフレッシュ効果 |
| ヨガやストレッチ | リラックス効果、身体のこわばり緩和 |
| 趣味を見つける | 楽しみの確保で過度なストレスを避けやすくする |
| 規則正しい就寝・起床 | 自律神経を整え、暴食リスクを低減 |
以上
参考にした論文
SONE, Hirohito, et al. Comparison of various lipid variables as predictors of coronary heart disease in Japanese men and women with type 2 diabetes: subanalysis of the Japan Diabetes Complications Study. Diabetes care, 2012, 35.5: 1150-1157.
TANIGUCHI, Ataru, et al. Remnant-like particle cholesterol, triglycerides, and insulin resistance in nonobese Japanese type 2 diabetic patients. Diabetes care, 2000, 23.12: 1766-1769.
YATAGAI, Toshimitsu, et al. Hypoadiponectinemia is associated with visceral fat accumulation and insulin resistance in Japanese men with type 2 diabetes mellitus. Metabolism, 2003, 52.10: 1274-1278.
TAMURA, Yoshifumi, et al. Effects of diet and exercise on muscle and liver intracellular lipid contents and insulin sensitivity in type 2 diabetic patients. The journal of clinical endocrinology & metabolism, 2005, 90.6: 3191-3196.
HIRANO, Tsutomu. Pathophysiology of diabetic dyslipidemia. Journal of atherosclerosis and thrombosis, 2018, 25.9: 771-782.
OKADA-IWABU, Miki, et al. A small-molecule AdipoR agonist for type 2 diabetes and short life in obesity. Nature, 2013, 503.7477: 493-499.
SCHULZE, Matthias B., et al. Relationship between adiponectin and glycemic control, blood lipids, and inflammatory markers in men with type 2 diabetes. Diabetes care, 2004, 27.7: 1680-1687.
ELSHORBAGY, Amany, et al. Association of BMI, lipid-lowering medication, and age with prevalence of type 2 diabetes in adults with heterozygous familial hypercholesterolaemia: a worldwide cross-sectional study. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2024, 12.11: 811-823.
MINAMINO, Tohru, et al. A crucial role for adipose tissue p53 in the regulation of insulin resistance. Nature medicine, 2009, 15.9: 1082-1087.
KADOWAKI, Takashi, et al. Adiponectin and adiponectin receptors in insulin resistance, diabetes, and the metabolic syndrome. The Journal of clinical investigation, 2006, 116.7: 1784-1792.