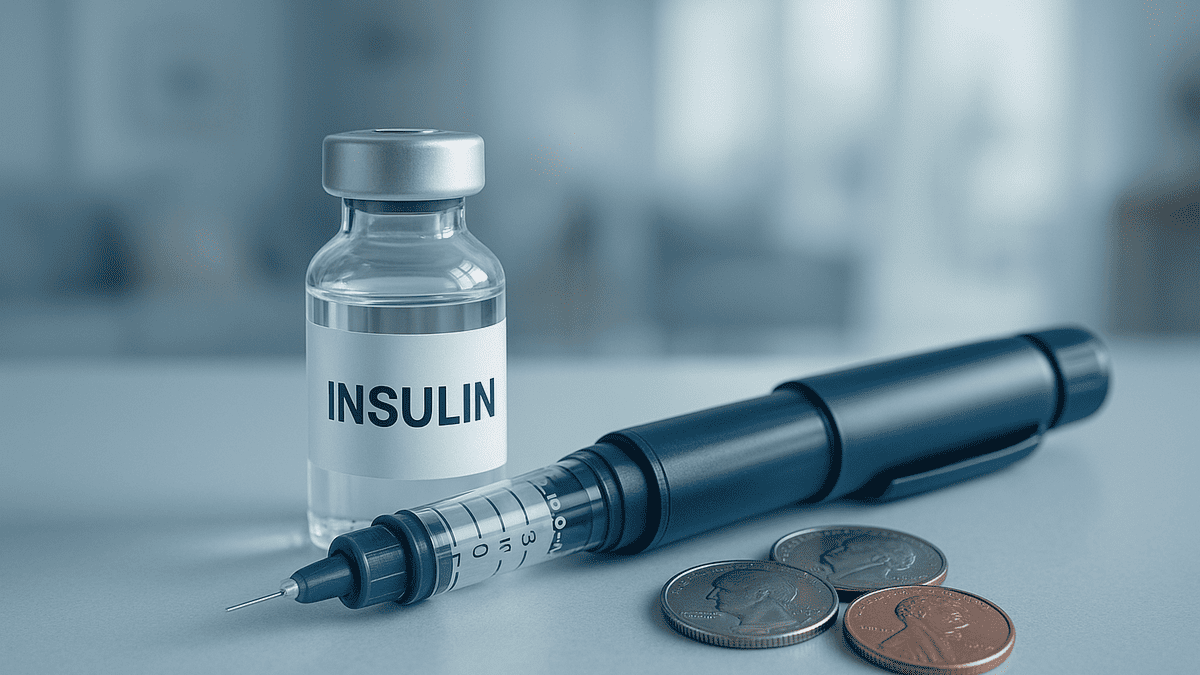インスリン治療を始めるにあたり、「治療に一体いくらかかるのだろう」「保険は使えるの?」といった費用の問題は多くの方が抱く大きな不安の一つです。
インスリンは生命を維持するために重要な薬ですが、継続的な治療となるため経済的な負担も気になるところです。
この記事ではインスリンの値段の決まり方から保険適用の仕組み、1ヶ月あたりの自己負担額の目安、そして負担を軽減するための公的制度まで、お金に関する情報を詳しく解説します。
正しい知識を得て、安心して治療に臨みましょう。
インスリン治療にかかる費用の内訳
インスリン治療の費用は、インスリン製剤そのものの値段だけではありません。主に「薬剤費」「医療機器費」「診察・検査費」の3つで構成されます。
薬剤費(インスリン製剤)
治療の中心となるインスリン製剤の費用です。インスリンの種類(超速効型、持効型など)や、使用する量によって費用は変動します。この薬剤費が、月々の費用の大部分を占めることになります。
医療機器費(注射針・血糖測定器など)
インスリンを注射するための注射針や、日々の血糖値を測定するための血糖自己測定(SMBG)器、センサー、穿刺針なども費用に含まれます。これらは消耗品のため、毎月一定の費用がかかります。
診察・検査費
定期的に医療機関を受診する際の診察料や、血糖コントロールの状態を確認するための血液検査(HbA1cなど)の費用です。
また、治療を開始する際には在宅での自己注射を管理・指導するための「在宅自己注射指導管理料」が算定されます。
インスリン治療費の主な構成要素
| 費用の種類 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 薬剤費 | インスリン製剤の費用 | 使用量や種類で変動 |
| 医療機器費 | 注射針、血糖測定関連の費用 | 消耗品として毎月発生 |
| 診察・検査費 | 診察料、血液検査、指導管理料 | 通院ごとに発生 |
インスリンの値段はどう決まるか
インスリン製剤の値段は製薬会社が自由に決めているわけではありません。国が定めた公定価格である「薬価」に基づいて決まっています。
国が定める「薬価」
日本国内で使われる医療用の医薬品は、すべて国によって価格(薬価)が定められています。この薬価は、2年に一度見直されます。
そのため、同じインスリン製剤でも時期によって価格が変動することがあります。
インスリンの種類と薬価の違い
インスリンには作用が現れる時間や持続時間によって様々な種類があります。
一般的に新しい技術を用いて開発されたインスリン製剤ほど薬価は高くなる傾向にあります。
インスリン製剤の薬価(一例)
| インスリンの種類 | 特徴 | 薬価の傾向 |
|---|---|---|
| 超速効型 | 効果が速く、食事に合わせて使用 | 比較的新しいものが多く、様々 |
| 持効型溶解 | 効果が長く続き、1日の基礎を補う | 新しい製剤は高めの傾向 |
| 混合型 | 超速効型と中間型などを混合 | 製品により異なる |
※上記はあくまで一般的な傾向です。実際の薬価は製品ごとに異なります。
ペン型注射器の種類による費用の差
インスリン製剤には本体を繰り返し使う「カートリッジ式」と、本体ごと使い切る「プレフィルド(使い捨て)型」があります。
一般的に、カートリッジ式の方が1本あたりの薬剤費は安価ですが、別途注入器本体の費用がかかる場合があります。
一方、使い捨て型は手軽ですが、1本あたりの費用はやや高めになる傾向があります。
インスリン治療と医療保険の仕組み
インスリン治療は公的医療保険の適用対象です。これにより、患者さんの自己負担は大幅に軽減されます。
健康保険の適用範囲
医師が糖尿病治療に必要と判断したインスリン製剤や関連する医療機器、診察・検査は、すべて健康保険の適用となります。
処方箋を持って調剤薬局で薬を受け取る際に保険証を提示することで、自己負担割合に応じた支払いで済みます。
自己負担割合(1割~3割)
医療費の自己負担割合は、年齢や所得によって異なります。ご自身の負担割合が何割かを確認しておきましょう。
年齢・所得に応じた自己負担割合
| 対象者 | 負担割合 |
|---|---|
| 75歳以上(一定所得以上を除く) | 1割 |
| 70歳~74歳(一定所得以上を除く) | 2割 |
| 70歳未満 | 3割 |
※70歳以上でも、現役世代並みの所得がある場合は3割負担となります。
在宅自己注射指導管理料とは
医師の指導のもと、患者さんが自宅でインスリン自己注射を行う場合に算定される費用です。
これには定期的な指導や管理、そして注射針や血糖測定チップなどの消耗品費用の一部が含まれています。この管理料も保険適用の対象です。
【シミュレーション】1ヶ月の自己負担額の目安
では、実際に1ヶ月あたりどのくらいの費用がかかるのでしょうか。インスリンの使用量や種類によって大きく異なりますが、一般的なモデルケースで見てみましょう。
3割負担の場合のモデルケース
ここでは、1日に超速効型インスリンを3回、持効型インスリンを1回注射し、血糖測定を1日3回行うケースを想定します。
1ヶ月の自己負担額の目安(3割負担)
| 費用の内訳 | 金額(目安) |
|---|---|
| 薬剤費(インスリン4本) | 約6,000円~12,000円 |
| 在宅自己注射指導管理料など | 約4,000円~6,000円 |
| 合計(月額) | 約10,000円~18,000円 |
1割負担の場合のモデルケース
同じケースで、自己負担が1割の場合の費用です。
1ヶ月の自己負担額の目安(1割負担)
| 費用の内訳 | 金額(目安) |
|---|---|
| 薬剤費(インスリン4本) | 約2,000円~4,000円 |
| 在宅自己注射指導管理料など | 約1,500円~2,000円 |
| 合計(月額) | 約3,500円~6,000円 |
※これらはあくまで一例です。インスリンポンプを使用する場合や、他の糖尿病薬を併用する場合は費用が異なります。
自己負担を軽減する公的医療制度
医療費の負担が重いと感じる場合、利用できる公的な助成制度があります。ご自身が対象となるか確認してみましょう。
高額療養費制度の活用
1ヶ月の医療費の自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた分が後から払い戻される制度です。上限額は年齢や所得によって定められています。
入院や手術などで医療費が高額になった際に大きな助けとなります。
小児慢性特定疾病医療費助成制度
18歳未満(条件により20歳未満まで)の1型糖尿病のお子さんが対象となる制度です。
この制度を利用すると医療費の自己負担額に上限が設けられ、負担が大幅に軽減されます。申請には医師の診断書などが必要です。
自治体独自の医療費助成
お住まいの市区町村によっては独自の医療費助成制度(例:ひとり親家庭等医療費助成、心身障害者医療費助成など)を設けている場合があります。
対象となる条件や助成内容は自治体によって異なるため、役所の担当窓口で確認してみましょう。
確定申告と医療費控除
1年間に支払った医療費の合計が一定額を超える場合、確定申告を行うことで「医療費控除」が受けられ、所得税や住民税が還付・軽減される可能性があります。
本人だけでなく、生計を共にする家族の医療費も合算できます。薬局のレシートや交通費の領収書は大切に保管しておきましょう。
インスリンの購入方法と処方の流れ
インスリンは安全な治療のために厳しく管理された医薬品です。正しい手順で購入する必要があります。
医療機関での診察と処方箋
インスリン治療を始めるには、まず医師の診察が必要です。医師が患者さんの状態を診断し、適切なインスリンの種類と量を決定し、処方箋を発行します。
インスリンは医師の処方箋がなければ購入できません。
調剤薬局での受け取り
発行された処方箋を調剤薬局に持って行くと、薬剤師が処方内容を確認し、インスリン製剤を渡してくれます。
この際、薬剤師から薬の取り扱いや保管方法について説明を受けます。
通販や個人輸入はできない理由
インスリンは医師の管理下で使う必要のある処方箋医薬品であり、インターネット通販などで購入することは法律で認められていません。
また、海外からの個人輸入も品質や安全性が保証されておらず、深刻な健康被害につながる恐れがあるため、絶対に行わないでください。
インスリン入手までの流れ
| 場所 | 行うこと | 受け取るもの |
|---|---|---|
| 糖尿病内科クリニック | 医師の診察を受ける | 処方箋 |
| 調剤薬局 | 処方箋を提出する | インスリン製剤・医療機器 |
よくある質問(Q&A)
最後に、インスリンの値段や購入に関してよくある質問にお答えします。
- Qインスリンにジェネリック医薬品はありますか?
- A
インスリンのようなバイオテクノロジーを用いて作られる医薬品の後続品は、「バイオシミラー(バイオ後続品)」と呼ばれます。
日本でもいくつかのインスリン製剤でバイオシミラーが承認されており、先行品よりも薬価が安く設定されています。
治療の選択肢の一つとなり得ますので、関心がある場合は主治医にご相談ください。
- Q薬局によって値段は変わりますか?
- A
インスリン製剤自体の値段(薬価)は全国一律で同じです。
しかし、薬局で支払う総額には薬剤師の技術料である「調剤料」や、薬局の体制に対する加算などが含まれるため、薬局によって数百円程度の差が出ることがあります。
- Q治療費についてどこに相談すれば良いですか?
- A
まずはかかりつけの医療機関の相談窓口や、ソーシャルワーカーに相談するのが第一歩です。高額療養費制度や各種助成制度について詳しく教えてくれます。
また、お住まいの市区町村の役所の担当課や、加入している健康保険組合に問い合わせることも有効です。
以上
参考にした論文
IWASAKI, K., et al. PDB8 Changes in Cost of ORAL Antidiabetic Drugs By Introduction of Formularies in JAPAN: A Simulation Using Health Insurance Claims Database. Value in Health, 2021, 24: S78-S79.
ISHIMURA, Atsushi; SHIMIZU, Yutaka; YABUKI, Naohiro. Relationship between Treatment Satisfaction and the Burden Associated with Payment of Outpatient Medical Expenses in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. The Journal of Community Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2023, 15.1: 36-41.
SAKODA, Sayaka; TAMURA, Masaoki; WAKUTSU, Naohiko. What discourages adults’ use of insulin-infusion pumps in Japan, habit or financial aid?. International Journal of Economic Policy Studies, 2023, 17.1: 331-345.
KATADA, A.; ASCHER-SVANUM, H. Review of the usual treatment of adults with type 2 diabetes in Japan. Value in Health, 2014, 17.3: A262.
FUNAKOSHI, Mitsuhiko, et al. Diabetes control in public assistance recipients and free/low-cost medical care program beneficiaries in Japan: a retrospective cross-sectional study. BMJ Public Health, 2024, 2.1.
INOUE, Kosuke, et al. Association between industry payments and prescriptions of long-acting insulin: an observational study with propensity score matching. PLoS Medicine, 2021, 18.6: e1003645.
TODA, Mitsutoshi, et al. Preferences for Injectable Lipid-Lowering Therapies in Japanese Patients with Atherosclerotic Cardiovascular Disease: Findings from a Japanese Cross-sectional Study. Advances in Therapy, 2025, 1-17.
YANG, Chen-Yi, et al. Cost-effectiveness of GLP-1 receptor agonists versus insulin for the treatment of type 2 diabetes: a real-world study and systematic review. Cardiovascular Diabetology, 2021, 20.1: 21.
YANG, Chao, et al. Comparing the economic burden of type 2 diabetes mellitus patients with and without medical insurance: a cross-sectional study in China. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 2018, 24: 3098.