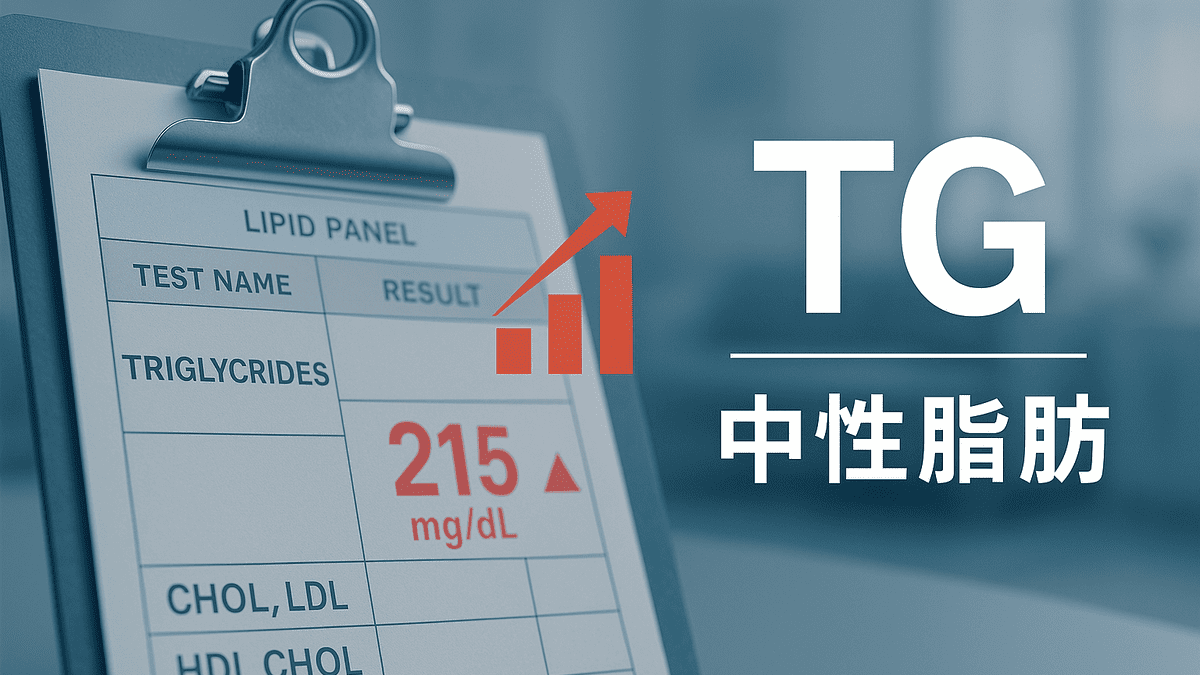健康診断の結果を見て「TG(中性脂肪)」の数値が高く、不安に感じていませんか。「特に自覚症状はないけれど、このまま放置しても大丈夫だろうか」と心配になる方も多いでしょう。
中性脂肪は体にとって必要なエネルギー源ですが、増えすぎると動脈硬化を進め、様々な生活習慣病のリスクを高める危険なサインとなります。
この記事ではTG(中性脂肪)の基準値や数値が高い場合のリスク、そして日常生活で実践できる効果的な下げ方について、専門医が詳しく解説します。
TG(中性脂肪)とは?体にとっての役割
中性脂肪は、しばしば「悪者」として扱われがちですが、本来は私たちの体が活動するために重要な役割を担っています。
体を動かすエネルギー源
中性脂肪の最も大きな役割は体を動かすためのエネルギー源となることです。
食事から摂取した脂質や使い切れなかった糖質・タンパク質などが体内で中性脂肪に変換されます。そして活動に必要なエネルギーとして使われます。
余ったエネルギーの貯蔵庫
活動で消費されずに余ったエネルギーは中性脂肪として皮下脂肪や内臓脂肪に蓄えられます。これは食事を摂れない時や飢餓状態に備えるための体の大切な仕組みです。
しかし、現代の食生活ではエネルギーを過剰に摂取しやすく、この貯蔵庫が溢れがちになることが問題となります。
コレステロールとの違い
中性脂肪とコレステロールはどちらも血液中の脂質ですが、その役割は異なります。
中性脂肪が主にエネルギー源として使われるのに対し、コレステロールは細胞膜やホルモン、胆汁酸の材料となるなど、体の構成成分としての役割が中心です。
両者は役割が違いますが、どちらも増えすぎると動脈硬化の原因となります。
中性脂肪とコレステロールの主な違い
| 項目 | 中性脂肪(トリグリセリド) | コレステロール |
|---|---|---|
| 主な役割 | エネルギー源として貯蔵・利用 | 細胞膜やホルモンなどの材料 |
| 主な原因 | カロリー過多、アルコール、糖質 | 脂質の多い食事、遺伝的要因 |
健康診断におけるTGの基準値
健康診断で示されるTGの数値が、どのような状態を意味するのかを正しく理解しましょう。
TGの正常値・要注意・異常値
日本動脈硬化学会が定める診断基準では、空腹時の採血で測定したTG値によって、正常、境界域、異常(高トリグリセリド血症)に分類されます。
中性脂肪(TG)の診断基準(空腹時)
| 判定 | TG値(mg/dL) |
|---|---|
| 正常 | 149以下 |
| 境界域高値 | 150~499 |
| 高値 | 500以上 |
TG値が150mg/dL以上の場合、「脂質異常症」の一つである「高トリグリセリド血症」と診断され、生活習慣の改善や治療の検討が必要になります。
基準値から外れるとどうなるか
TG値が高い状態が続くと血液がドロドロになり、血管の内壁に脂質が蓄積しやすくなります。
このことにより動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる病気のリスクが高まります。自覚症状がないからといって、決して軽視してはいけません。
検査前に注意すべきこと
中性脂肪の値は直前の食事の影響を非常に受けやすいという特徴があります。検査前日の夜から当日の朝にかけて、食事やアルコールの摂取を控える(通常は10時間以上の絶食)のが一般的です。
正確な数値を把握するためにも、健康診断前の指示を必ず守るようにしましょう。
TGが高い状態が示す危険性
高い中性脂肪値は様々な病気の引き金となります。具体的にどのような危険性があるのかを見ていきましょう。
動脈硬化の進行と心血管疾患
TG値が高いと血液中に超悪玉コレステロールとも呼ばれる「小型LDLコレステロール」が増加します。この小型LDLコレステロールは血管の壁に入り込みやすく、動脈硬化を強力に促進します。
その結果、心臓の血管が詰まる心筋梗梗塞や、脳の血管が詰まる脳梗塞のリスクが著しく上昇します。
急性膵炎のリスク
中性脂肪が極端に高い値(特に500mg/dL以上)になると、急性膵炎を発症するリスクが高まります。
急性膵炎はみぞおちに激しい痛みが走り、重症化すると命に関わることもある危険な病気です。TG値が非常に高い場合は速やかな治療が必要です。
脂肪肝と肝機能障害
使い切れなかった中性脂肪は肝臓にも蓄積します。この状態が「脂肪肝」です。
脂肪肝を放置すると、肝臓に炎症が起きて「非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)」に進行し、さらには肝硬変や肝がんへと至る可能性があります。
お酒を飲まない人でも起こるため注意が必要です。
高いTG値がもたらす主な健康リスク
| リスク | 概要 |
|---|---|
| 動脈硬化 | 血管が硬く、もろくなり、心筋梗塞や脳梗塞の原因となる |
| 急性膵炎 | 腹部に激痛が走り、重症化すると命の危険がある |
| 脂肪肝 | 肝臓に脂肪が蓄積し、肝硬変や肝がんへ進行する可能性 |
中性脂肪が高くなる主な原因
TG値が高くなる背景には日々の生活習慣が大きく関わっています。ご自身の生活を振り返ってみましょう。
過食とカロリーオーバー
消費するエネルギーよりも摂取するエネルギー(カロリー)が多い状態が続くと、余ったエネルギーが中性脂肪として体に蓄えられます。
特に脂質の多い食事は高カロリーになりやすく、中性脂肪を増やす直接的な原因となります。
アルコールの過剰摂取
アルコールは肝臓での中性脂肪の合成を促進する働きがあります。また、アルコール自体もカロリーが高く、一緒につまみを食べることでさらにカロリーオーバーになりがちです。
お酒の飲み過ぎは中性脂肪を増やす大きな原因の一つです。
糖質の多い食生活
ご飯やパン、麺類などの主食、甘いお菓子やジュースなどに含まれる糖質も、摂りすぎると体内で中性脂肪に変換されます。
特に果物に含まれる「果糖」や、清涼飲料水に多い「ブドウ糖果糖液糖」は、中性脂肪に変わりやすい性質を持つため注意が必要です。
運動不足による消費エネルギーの低下
日常的に体を動かす習慣がないと摂取したエネルギーを消費しきれず、中性脂肪として蓄積しやすくなります。
デスクワーク中心の生活や車での移動が多い方は意識的に運動を取り入れることが重要です。
中性脂肪を増やす主な原因
- 食べ過ぎ(特に脂っこいもの)
- お酒の飲み過ぎ
- 糖質の摂り過ぎ(甘いもの、主食の重ね食べ)
- 運動不足
中性脂肪を効果的に下げる食事のポイント
高い中性脂肪値を改善するためには食事の見直しが最も重要です。今日から実践できるポイントを紹介します。
まずは摂取カロリーの見直しから
ご自身の年齢や性別、活動量に見合った適切なエネルギー摂取量を把握し、食べ過ぎを防ぐことが基本です。
腹八分目を心掛け、間食や夜食を控えるだけでも、摂取カロリーは大きく変わります。
アルコールを控える・休肝日を設ける
アルコールが原因で中性脂肪が高い場合は禁酒が最も効果的です。
すぐに禁酒するのが難しい場合でも、飲む量を減らしたり、週に2日以上の休肝日を設けたりすることから始めましょう。
この対策で肝臓を休ませ、中性脂肪の合成を抑えることができます。
青魚に含まれるEPA・DHAを積極的に
サバ、イワシ、サンマなどの青魚に多く含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)という不飽和脂肪酸には、肝臓での中性脂肪の合成を抑え、血液中の中性脂肪を減らす働きがあります。
積極的に食事に取り入れましょう。
EPA・DHAを多く含む魚
| 魚の種類 | 特徴 |
|---|---|
| サバ、イワシ、サンマ | 特に含有量が多い。缶詰でも手軽に摂取できる。 |
| ブリ、アジ | 日常的に食卓にのせやすい。 |
糖質の質と量を考える
糖質を完全に抜く必要はありませんが、質と量を意識することが大切です。
白米を玄米や雑穀米に変える、食物繊維の多い野菜から先に食べる(ベジファースト)などの工夫で血糖値の急上昇を抑え、中性脂肪の合成を抑制できます。
甘いジュースや菓子類はできるだけ控えるようにしましょう。
食事と組み合わせたい運動習慣
食事改善と運動を組み合わせることで中性脂肪はより効果的に下がります。
おすすめは有酸素運動
中性脂肪をエネルギーとして効率よく燃焼させるためには、ウォーキング、ジョギング、水泳、サイクリングなどの有酸素運動が効果的です。
少し息が弾むくらいの強度で1回30分以上、週に3日以上行うことを目標にしましょう。
運動を続けるためのコツ
「運動」と意気込むと長続きしにくいものです。まずは日常生活の中で体を動かす機会を増やすことから始めましょう。
エレベーターを階段に変える、一駅手前で降りて歩くなど小さな工夫の積み重ねが大きな効果を生みます。
運動療法の注意点
心臓や膝などに持病がある方は運動を始める前に必ず医師に相談してください。
無理な運動はかえって体を痛める原因になります。ご自身の体力に合った安全で継続可能な運動を見つけることが大切です。
薬物治療が必要になる場合
生活習慣の改善を続けても中性脂肪値が十分に下がらない場合や、数値が極端に高い場合には薬物治療を検討します。
生活習慣の改善でも数値が下がらない時
数か月にわたって食事療法や運動療法に取り組んでもTG値が目標まで下がらない場合、特に心筋梗塞などのリスクが高いと考えられる患者さんには薬物治療を開始します。
遺伝的な要因が関わっていることもあります。
主に使用される治療薬
中性脂肪を下げる薬として主に使用されるのは「フィブラート系薬剤」や「EPA製剤」です。
フィブラート系薬剤は肝臓での中性脂肪の産生を抑え、分解を促進します。EPA製剤は青魚の成分であるEPAを高純度にしたもので、同様に中性脂肪の産生を抑制します。
薬物治療と生活習慣改善の併用
薬を飲み始めたからといって生活習慣の改善をやめて良いわけではありません。薬物治療は、あくまで食事療法と運動療法を補助するものです。
この3つを車の両輪のように並行して続けることが中性脂肪をコントロールし、将来の健康を守る上で重要です。
よくある質問
中性脂肪について、患者さんからよくいただくご質問にお答えします。
- Q中性脂肪はどのくらいで下がりますか?
- A
生活習慣の改善、特に食事とアルコールの見直しによる効果は比較的早く現れます。真剣に取り組めば、1~2か月で数値の改善が見られることも少なくありません。
大切なのは改善した数値を維持するために健康的な生活を継続することです。
- Qお菓子や果物はやめるべきですか?
- A
完全にやめる必要はありませんが、量と頻度を減らすことが重要です。
お菓子に含まれる砂糖や、果物に含まれる果糖は中性脂肪に変わりやすいため、摂りすぎは禁物です。食べるなら食後のデザートとして少量にするなどの工夫をしましょう。
- Q痩せているのに中性脂肪が高いのはなぜですか?
- A
痩せている方でもアルコールの摂取量が多かったり、甘いものをよく食べたりする食生活を送っていると中性脂肪は高くなります。また、遺伝的な体質が関係している場合もあります。
体型に関わらず、数値が高い場合は生活習慣を見直すことが大切です。
- Qサプリメントは効果がありますか?
- A
EPAやDHAを含むサプリメントなど中性脂肪対策を謳う製品は多くあります。補助的に利用することは考えられますが、その効果は医薬品とは異なります。
サプリメントに頼る前に、まずは食事や運動といった生活習慣の基本を見直すことが先決です。
使用したい場合は事前に医師や薬剤師に相談することをお勧めします。
以上
参考にした論文
YAMASHITA, Shizuya, et al. Managing hypertriglyceridemia for cardiovascular disease prevention: Lessons from the PROMINENT trial. European Journal of Clinical Investigation, 2024, 54.9: e14227.
MURASE, Toshio, et al. Severe hypertriglyceridemia in Japan: differences in causes and therapeutic responses. Journal of Clinical Lipidology, 2017, 11.6: 1383-1392.
SHOJI, Tetsuo, et al. Impaired metabolism of high density lipoprotein in uremic patients. Kidney international, 1992, 41.6: 1653-1661.
TERAMOTO, Tamio, et al. Executive summary of the Japan Atherosclerosis Society (JAS) guidelines for the diagnosis and prevention of atherosclerotic cardiovascular diseases in Japan—2012 version. Journal of atherosclerosis and thrombosis, 2013, 20.6: 517-523.
ISO, Hiroyasu, et al. Serum triglycerides and risk of coronary heart disease among Japanese men and women. American journal of epidemiology, 2001, 153.5: 490-499.
NAKAMURA, Haruo, et al. Primary prevention of cardiovascular disease with pravastatin in Japan (MEGA Study): a prospective randomised controlled trial. The Lancet, 2006, 368.9542: 1155-1163.
SEKIMOTO, Miho, et al. JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis: epidemiology, etiology, natural history, and outcome predictors in acute pancreatitis. Journal of hepato-biliary-pancreatic surgery, 2006, 13: 10-24.
OKAMOTO, Kohji, et al. Tokyo Guidelines 2018: flowchart for the management of acute cholecystitis. Journal of Hepato‐biliary‐pancreatic Sciences, 2018, 25.1: 55-72.
LAUFS, Ulrich, et al. Clinical review on triglycerides. European heart journal, 2020, 41.1: 99-109c.
TADA, Hayato, et al. Clinical characteristics of Japanese patients with severe hypertriglyceridemia. Journal of Clinical Lipidology, 2015, 9.4: 519-524.