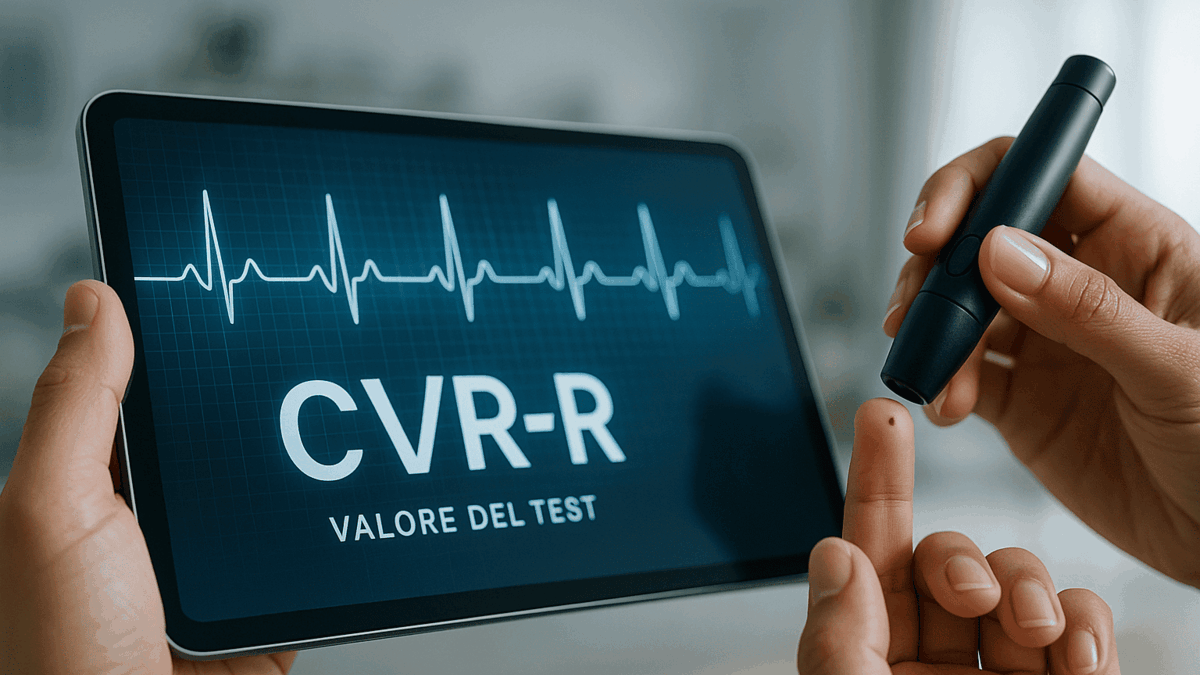糖尿病の合併症と聞くと、手足のしびれ(末梢神経障害)や目の病気(網膜症)、腎臓の病気(腎症)を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、これらと同じくらい重要で、かつ自覚症状が出にくいのが「自律神経障害」です。
この記事では心電図検査でわかる「CVR-R」という指標に焦点を当て、糖尿病性自律神経障害を早期に発見することの重要性や、検査の内容、そして日常生活でできる対策について専門医の視点から詳しく解説します。
糖尿病性自律神経障害とは何か
糖尿病性自律神経障害は高血糖によって全身の機能を調整する自律神経がダメージを受ける病気です。
三大合併症の一つでありながら、初期には症状が出にくいため見過ごされがちです。
糖尿病の三大合併症の一つ
糖尿病の合併症は主に高血糖によって細い血管が傷つけられることで起こります。特に代表的なのが「網膜症」「腎症」「神経障害」で、これらを三大合併症と呼びます。
神経障害はさらに、手足の感覚に関わる「感覚・運動神経」の障害と、内臓や血管の働きを調整する「自律神経」の障害に分けられます。
糖尿病の三大合併症
| 合併症 | 主な障害部位 | 代表的な症状 |
|---|---|---|
| 網膜症 | 目の網膜 | 視力低下、失明 |
| 腎症 | 腎臓 | むくみ、腎不全(透析) |
| 神経障害 | 末梢神経、自律神経 | 手足のしびれ、立ちくらみ |
自律神経の役割と障害の影響
自律神経は私たちの意思とは関係なく、心臓の動き、血圧、消化、体温などを24時間体制でコントロールしている生命維持に重要な神経です。
この自律神経が障害されると体の様々な調節機能がうまく働かなくなり、立ちくらみや胃もたれ、便秘、排尿障害など多岐にわたる不調が現れます。
なぜ自覚症状が出にくいのか
自律神経障害の症状はゆっくりと進行し、また「なんとなく調子が悪い」といった曖昧なものが多いため、年齢のせいや疲れのせいだと自己判断してしまいがちです。
手足のしびれのようなはっきりとした症状に比べて気づきにくく、検査で初めて異常を指摘されるケースも少なくありません。
CVR-Rとは?心拍の「ゆらぎ」を見る検査
CVR-Rは自律神経の中でも特に心臓をコントロールする機能が正常に働いているかを調べるための、簡便で有用な指標です。
心電図検査でわかること
心電図検査は心臓が動く時に発生する微弱な電気信号を記録するものです。
不整脈や狭心症、心筋梗塞など心臓自体の病気を見つけるのが主な目的ですが、心拍のリズムを詳しく解析することで自律神経の状態を評価することもできます。
CVR-R(R-R間隔変動係数)の基本
CVR-Rは心電図の波形の中の「R波」と呼ばれる特定の波の間隔(R-R間隔)が、どれくらい「ゆらいでいるか」を数値化したものです。
健康な人の心臓は常に一定のリズムで動いているわけではなく、呼吸などに合わせて拍動の間隔が微妙に変動しています。
この自然な「ゆらぎ」が、自律神経が正常に機能している証拠です。
CVR-Rが示すもの
| CVR-Rの値 | 心拍のゆらぎ | 自律神経の状態 |
|---|---|---|
| 高い | 大きい | 正常に機能している |
| 低い | 小さい(単調) | 機能が低下している疑い |
なぜ心拍の「ゆらぎ」が重要なのか
心拍のゆらぎは主に副交感神経(体をリラックスさせる神経)の働きによって生み出されます。
糖尿病によって自律神経障害が始まると、まずこの副交感神経の機能から低下していくことが多いため、心拍のゆらぎが小さくなります。
このため、CVR-Rの低下は自律神経障害の非常に早い段階のサインを捉えることができるのです。
CVR-R検査の具体的な内容
CVR-Rの検査は通常の心電図検査とほとんど同じで、患者さんの負担が少ないのが特徴です。
検査の流れと所要時間
ベッドに仰向けに寝て、胸や手足に電極を装着します。検査自体は数分で終了します。
検査では通常の心電図記録に加えて、安静にした状態と深く呼吸をした時の心拍の変動を記録します。
安静時と深呼吸時の測定
まず、リラックスした状態で安静時の心拍を記録します。その後、合図に合わせてゆっくりと深い呼吸を繰り返していただき、その間の心拍の変動を記録します。
深呼吸をすると健康な人では心拍のゆらぎがより大きくなるため、この反応を見ることで、より正確に自律神経の機能を評価できます。
痛みや負担はほとんどない
心電図検査は体の表面に電極を貼り付けるだけで、痛みや放射線被ばくの心配は全くありません。
リラックスして検査を受けることが正確な結果を得るために大切です。
CVR-Rの基準値と結果の解釈
検査結果は年齢などを考慮して評価します。数値が低い場合は自律神経障害の可能性を考え、さらなる評価や対策が必要になります。
CVR-Rの正常値と異常値
CVR-Rの正常値は一般的に2.0%以上とされています。ただしこれはあくまで目安であり、年齢によって基準は異なります。
2.0%を下回る場合は「異常」、2.0~2.5%程度は「境界域」として注意深い経過観察が必要です。
CVR-Rの判定目安
| 判定 | CVR-Rの値(目安) |
|---|---|
| 正常 | 2.5%以上 |
| 境界域 | 2.0~2.4% |
| 異常 | 1.9%以下 |
年齢による基準値の変化
加齢とともに自律神経の機能は自然と低下するため、CVR-Rの値も年齢が上がるにつれて低くなる傾向があります。
そのため検査結果を評価する際には、ご自身の年齢における基準値と比較することが重要です。
検査結果が低い場合に考えられること
CVR-Rの値が低い場合、最も考えられるのは糖尿病による自律神経障害の始まりです。
しかし、糖尿病以外にも加齢、過度の疲労やストレス、特定の薬剤の影響などで数値が低くなることもあります。
総合的に判断し、原因に応じた対策を考えます。
自律神経障害が進行した場合のリスク
初期には症状がなくても、自律神経障害が進行すると生活の質を大きく損なう様々な症状が現れ、時には命に関わる事態も引き起こします。
立ちくらみや無自覚性低血糖
血圧の調節機能が障害されると急に立ち上がった時に血圧が下がり、めまいや立ちくらみ(起立性低血圧)を起こしやすくなります。
また、血糖値が下がった時の警告サイン(動悸、冷や汗など)を感じにくくなる「無自覚性低血糖」は、意識障害や事故につながる非常に危険な状態です。
胃腸の不調
胃の動きが悪くなると少量の食事でも胃がもたれたり、吐き気を感じたりします(胃不全麻痺)。
また、腸の動きが乱れることで頑固な便秘や、逆に激しい下痢を繰り返すこともあります。
自律神経障害による胃腸症状
- 胃もたれ、早期満腹感
- 吐き気、嘔吐
- 頑固な便秘
- コントロール不能な下痢
排尿障害やED(勃起不全)
膀胱に尿が溜まっても尿意を感じにくくなったり、尿の勢いが弱くなったりする排尿障害が起こります。
残尿が増えると尿路感染症の原因にもなります。
また、男性ではED(勃起不全)も自律神経障害の早期から見られる症状の一つです。
心筋梗塞や突然死のリスク
最も深刻なのは心臓に関わる合併症です。
自律神経障害が進行すると痛みを感じる神経も鈍くなるため、心筋梗塞を起こしても典型的な胸の痛みを感じない「無痛性心筋梗塞」を発症することがあります。
発見が遅れ、命に関わるリスクが高まります。また、重篤な不整脈による突然死のリスクも上昇することが知られています。
CVR-Rの低下を防ぎ、改善を目指すために
一度障害された神経を完全に元に戻すのは難しいですが、進行を食い止め、症状を和らげるためにできることはたくさんあります。
血糖コントロールの徹底
自律神経障害の予防と進行抑制の基本は良好な血糖コントロールを維持することです。
HbA1cの目標値を医師と相談し、日々の血糖値の変動をできるだけ小さくすることが、神経へのダメージを最小限に抑えます。
血糖コントロールの目標(個別設定が原則)
| 指標 | 目標値 |
|---|---|
| HbA1c | 7.0%未満 |
| 食前血糖値 | 80~130mg/dL |
| 食後2時間血糖値 | 180mg/dL未満 |
血圧や脂質の管理
高血圧や脂質異常症は高血糖と同様に血管や神経にダメージを与え、自律神経障害を悪化させます。
食事療法や運動療法、必要であれば薬物治療によって、血圧やコレステロール値もしっかりと管理することが重要です。
生活習慣の見直し
禁煙は必須です。喫煙は血流を悪化させ、神経障害を進行させる大きな要因です。
また、過度なアルコール摂取も神経に悪影響を及ぼすため、節酒を心掛けましょう。
バランスの取れた食事とウォーキングなどの適度な運動を習慣にすることも、全身の健康維持につながります。
糖尿病内科での定期的な検査の重要性
自覚症状のない段階から合併症のリスクを評価し、早期に対策を始めるために、定期的な検査は欠かせません。
なぜ早期発見が重要なのか
CVR-Rの低下は自律神経障害の非常に初期のサインです。
この段階で異常を発見し、血糖コントロールの強化や生活習慣の改善に取り組むことで、その後の重篤な合併症への進行を食い止められる可能性が高まります。
症状が出てからでは治療が難しくなることが少なくありません。
CVR-R以外の神経障害検査
クリニックではCVR-Rの他にも様々な角度から神経障害の有無や程度を評価します。
感覚神経を調べるアキレス腱反射や振動覚検査、血圧の変動を見るシェロングテストなどを組み合わせて、総合的に診断します。
症状に対する治療
立ちくらみや胃腸の不調、排尿障害など、すでに出てしまっている症状に対しては、それらを和らげるための対症療法も行います。
生活指導や症状に応じた薬物治療によって、生活の質を維持することを目指します。
よくある質問
CVR-Rや自律神経障害について、患者さんからよくいただく質問にお答えします。
- QCVR-Rの検査はどのくらいの頻度で受ければ良いですか?
- A
糖尿病と診断されたら、合併症の初期評価として一度は受けることをお勧めします。
検査結果が正常であっても、血糖コントロールの状態などに応じて、1年に1回など定期的に検査を行い、経時的な変化を見ていくことが重要です。
- QCVR-Rが低くても症状がなければ大丈夫ですか?
- A
症状がないからといって安心はできません。
CVR-Rの低下は自覚症状よりも先に現れる「危険信号」です。このサインを見逃さず、将来の深刻な合併症を予防するための対策を始める絶好の機会と捉えることが大切です。
- Q一度下がったCVR-Rの値は元に戻りますか?
- A
残念ながら、一度障害された神経機能を完全に元に戻すのは困難です。
しかし徹底した血糖コントロールや生活習慣の改善によって、さらなる低下を防いだり、わずかに改善したりする可能性はあります。
最も重要な目標は現状を維持し、進行させないことです。
- Q検査当日に食事や薬の制限はありますか?
- A
通常、食事の制限はありません。
ただし服用している薬によっては自律神経機能に影響を与えるものもありますので、いつも飲んでいる薬については事前に医師やスタッフにお知らせください。
検査前の喫煙やカフェイン摂取は結果に影響する可能性があるため、控えるのが望ましいです。
以上
参考にした論文
NAGAYOSHI, Yasuhiro, et al. Coefficient of R‐R interval variations under deep breathing load in patients with wild‐type transthyretin amyloid cardiomyopathy: A case‐control study. Health Science Reports, 2023, 6.1: e938.
SAITO, Takatoshi, et al. Coefficient of variation of R–R intervals in electrocardiogram is a sensitive marker of anemia induced by autonomic neuropathy in type 1 diabetes. Diabetes research and clinical practice, 2007, 78.1: 60-64.
ISHIKAWA, Yoshiaki Morishita, et al. Hideki Kamiya1*, Yuka Shibata1, 2, Tatsuhito Himeno1, Hiroya Tani3, Takayuki Nakayama3, Kenta Murotani4, Nobuhiro Hirai1, Miyuka Kawai1, Yuriko Asada-Yamada1, Emi Asano-Hayami1, Hiromi Nakai-Shimoda1, Yuichiro Yamada1, Takahiro. 2020.
ANDO, Akihiko, et al. Small fibre neuropathy is associated with impaired vascular endothelial function in patients with type 2 diabetes. Frontiers in Endocrinology, 2021, 12: 653277.
KIMURA, Moritsugu, et al. Detection of autonomic nervous system abnormalities in diabetic patients by 24-hour ambulatory blood pressure monitoring. Tokai J Exp Clin Med, 2018, 43.3: 97-102.
KAGEYAMA, SHIGERU, et al. A critical level of diabetic autonomic neuropathy. The Tohoku Journal of Experimental Medicine, 1983, 141.Suppl: 479-483.
HAYASHI, Yusuke, et al. Simplified electrophysiological approach combining a point‐of‐care nerve conduction device and an electrocardiogram produces an accurate diagnosis of diabetic polyneuropathy. Journal of Diabetes Investigation, 2024, 15.6: 736-742.
ASO, Yoshimasa, et al. High serum levels of CCL11/Eotaxin-1 are associated with diabetic sensorimotor polyneuropathy and peripheral nerve function but not with cardiac autonomic neuropathy in people with type 2 diabetes. Postgraduate Medicine, 2024, 136.3: 318-324.
ARIMURA, Aiko, et al. Intraepidermal nerve fiber density and nerve conduction study parameters correlate with clinical staging of diabetic polyneuropathy. Diabetes research and clinical practice, 2013, 99.1: 24-29.
KOBORI, Mariko, et al. Four‐year sequential nerve conduction changes since first visit in Japanese patients with early type 2 diabetes. Journal of Diabetes Investigation, 2017, 8.3: 369-376.