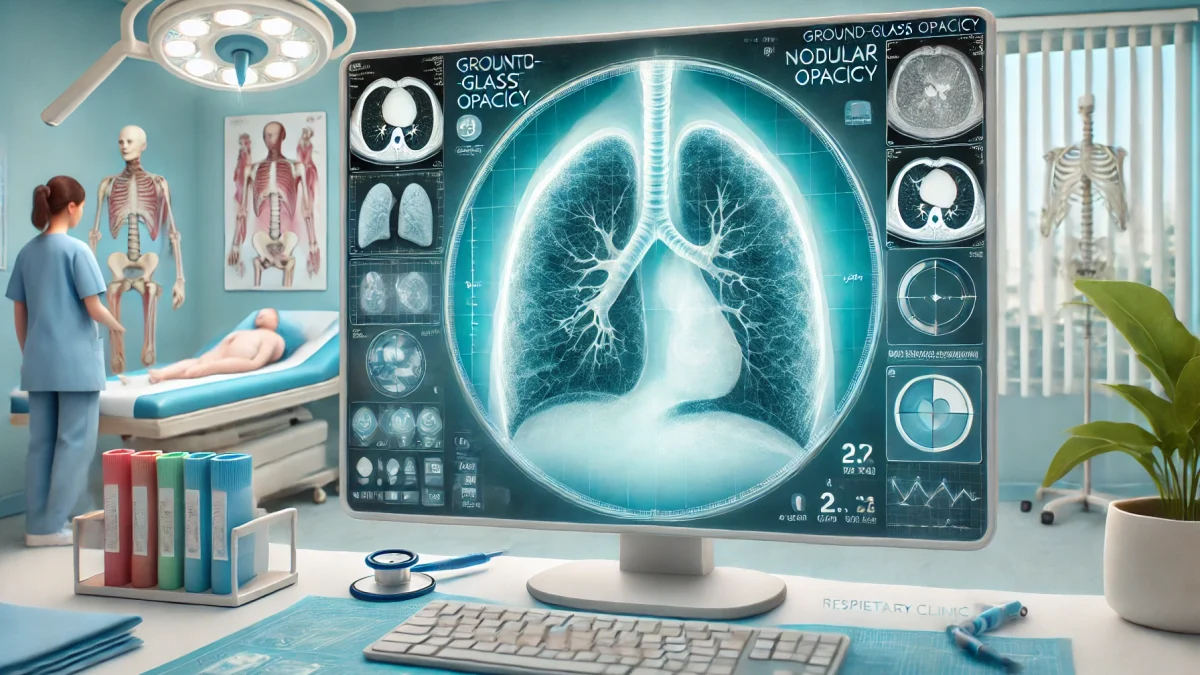健康診断で「肺にびまん性陰影(浸潤影・すりガラス影・粒状影・斑状影)がある」と指摘された方は、原因がわからないうえに、日常生活をどう変えればいいのか不安になられているのではないでしょうか。
びまん性陰影にはさまざまな種類と原因があり、経過観察で済む場合と、治療が必要となる疾患が潜んでいる場合があります。
ここでは、浸潤影、すりガラス影、粒状影、斑状影などの陰影がどのような仕組みで生じ、どんな可能性が考えられるかを解説します。
COPD(慢性閉塞性肺疾患)に関わるリスクや受診の目安も合わせて紹介しますので、検診後の肺異常についてご不安な方はぜひ参考にしてみてください。
健康診断で肺のびまん性陰影(浸潤影・すりガラス影・粒状影・斑状影)を指摘されるなど、胸部レントゲン異常で再検査や精密検査をご希望の方は、神戸きしだクリニックの呼吸器内科で対応させていただきます。詳しくはこちら
この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長
医学博士
日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医
日本核医学会認定 核医学専門医
【略歴】
神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)
健康診断で「浸潤影・粒状影・斑状影(肺のびまん性陰影)」を指摘されたら
肺のびまん性陰影とは、胸部X線写真やCT検査で肺全体に広がって見える陰影を指す言葉です。放置していいものか、それとも専門医を受診したほうがいいのかと迷ってしまう方が多いです。
肺のびまん性陰影とは何か
びまん性陰影は、「肺に広範囲な変化が見られる状態」を意味します。細かい粒のような影や、薄いすりガラス状の影など、複数のパターンがあります。
単純に肺の内部が白く濁っているように見える影ではなく、病変の広がり方や形状によって推測できる疾患も変わります。
異常陰影の種類と特徴
肺のびまん性陰影には、下記のような種類(名称・呼ばれ方)があります。
- 浸潤影
- すりガラス影
- 粒状影
- 斑状影
影の種類と発生状況によって考えられる疾患が変わります。すりガラス影の場合は間質性肺炎の可能性を考えたり、粒状影であればサルコイドーシスなどを念頭に置いたりします。
放置していいケースと早急な受診が必要なケース
経過観察だけで十分な場合もありますが、早い時期に呼吸器内科を受診した方が安心なケースもあります。
例えば過去の健康診断データや喫煙歴、呼吸困難感の有無などを総合的に判断して、受診の緊急度を考えるとよいです。気になる症状があれば早めに専門医へ相談しましょう。
少しでも心配があるなら専門医に相談する
とくに肺の疾患は自覚症状が乏しいまま進行することが多く、健康診断の結果だけでは判断が難しい場合もあります。早めの段階で専門家の意見を聞くことで、その後の方針がはっきりします。
| 疑問 | 対応の例 |
|---|---|
| すぐに病院へ行ったほうがいい? | 喫煙歴がある、呼吸苦や咳が続く場合は早めに受診を考える |
| 放置してもよいケースはある? | 無症状で、以前の検査でも変化がない場合は経過観察 |
| 受診するならどの科に行くべき? | 呼吸器内科や専門外来 |
| 検査はどの程度時間がかかる? | CT、血液検査、肺機能検査などで半日から1日ほど |
| 費用はどれくらい? | 保険適用の検査が多いが、内容によって数千円~1万円程度 |
肺のびまん性陰影が出る主な原因
びまん性陰影は炎症性疾患から腫瘍性疾患まで多岐にわたり、原因により対処法も変わります。大まかにどのような疾患が考えられるか見ていきましょう。
感染症による影
細菌やウイルス、真菌などの感染症が原因でびまん性陰影を生じることがあります。肺炎や結核、ニューモシスチス肺炎などが代表的です。
特に新たに高熱や痰の色の変化、だるさが出ている場合は、感染症を疑う必要があります。
- 発熱と痰が出る肺炎の疑い
- しつこい咳で結核を疑うケース
- 免疫力低下時に疑うニューモシスチス肺炎
炎症性疾患(間質性肺炎など)
間質性肺炎や膠原病など、肺の組織に慢性的な炎症が起こる病気があります。
初期は軽い息切れや少しのだるさしか感じない方もいますが、進行すると呼吸困難などに繋がります。すりガラス影が特徴として出ることも多いです。
腫瘍性疾患
がんが原因でびまん性陰影が広がるケースもあります。肺がんの一部や転移性腫瘍が肺全体に影響している可能性も否定できません。
喫煙歴が長い方、持続する咳や血痰などがある場合は慎重なチェックが必要です。
その他(アレルギーや粉塵、環境要因)
アレルギー性の肺炎(過敏性肺炎など)や粉塵による肺疾患(じん肺など)が原因となることもあります。
職業上、粉塵を吸い込みやすい環境にいる方や動物性のアレルゲンに触れる機会が多い方は、その可能性を考慮する必要があります。
肺のびまん性陰影を引き起こす代表的な疾患
| 疾患名 | 主な特徴 | 主な影の種類 |
|---|---|---|
| 肺炎 | 発熱・痰などの症状 | 浸潤影 |
| 結核 | 長引く咳、体重減少 | 斑状影、粒状影 |
| 間質性肺炎 | 息切れ、すりガラス様陰影 | すりガラス影 |
| 肺がん(一部) | 血痰、喫煙歴 | 斑状影、浸潤影 |
| サルコイドーシス | 無症状やリンパ節腫脹 | 粒状影 |
| 過敏性肺炎 | アレルゲンへの暴露 | すりガラス影、粒状影 |
| じん肺 | 粉塵暴露が長期間続く | 粒状影 |
COPDとのかかわり
びまん性陰影と直接的に「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」が結びつくことは少なく見えますが、喫煙歴などのリスク因子が重なっているとCOPDを併発するケースも考えられます。
COPDは慢性的な咳や痰、息切れを特徴とする病気です。
COPDのメカニズムと進行
COPDは気管支や肺胞が慢性的にダメージを受けて、呼吸機能が低下していく病気です。特にたばこの煙や有害物質の吸入が原因となりやすく、時間をかけてゆっくりと進行することが多いです。
初期は咳や痰の量が少し増える程度ですが、次第に息苦しさや運動時の呼吸困難が目立つようになります。
びまん性陰影とCOPDリスク
COPDを持っている方、または軽度のCOPD予備軍の方に別の疾患が重なると、胸部画像上でびまん性陰影が指摘されるケースもあります。
喫煙歴が長く、一度でもCOPDと診断されたことがある方は、肺の陰影を見落とさずに受診するとよいでしょう。
自覚症状が乏しい初期症状
COPDの初期ははっきりした症状がない場合が多いです。朝の咳や軽い痰、ちょっとした運動で息切れを感じる程度でも、実はCOPDの入り口に立っている可能性があります。
健康診断で肺の陰影を指摘されたのを機に、呼吸器の専門医に相談すると、早期発見と対策につながります。
クリニックでできる検査とCOPD評価
COPDかどうかを判定するために、専門医はスパイロメトリー(肺機能検査)を行い、1秒量(FEV1)などを調べます。
検査の結果でCOPDか否か、あるいはどの程度進行しているかを把握できます。さらに胸部CTで肺の陰影や気管支の変化を総合的に診断します。
COPDのリスク要因
- 長期間の喫煙
- 有害物質の慢性的な吸入(職場環境など)
- 大気汚染が深刻な地域での長期生活
- 肺機能の低下を放置
- 風邪や肺炎などを繰り返し、慢性化させる
クリニック受診の流れ
健康診断で肺のびまん性陰影を指摘されたときは、呼吸器内科を受診する流れが一般的です。どのような検査を受けるのか、どのくらい時間や費用がかかるのか、あらかじめ把握しておくとスムーズです。
問診・肺機能検査
まずは問診にて、過去の健康診断結果や喫煙歴、生活習慣などを詳しく確認します。その後、呼吸機能を調べるスパイロメトリー検査などを実施し、肺活量や空気の流れ方を評価します。
画像検査(胸部X線・CT)
すでに健康診断で胸部X線写真を撮影している場合は、その結果をもとにさらに詳細なCT検査をすることが多いです。
CTはより詳細な肺の構造を映し出し、浸潤影やすりガラス影、粒状影、斑状影などの性質を見極める材料になります。
血液検査・アレルギー検査
炎症や感染症、アレルギーの可能性を調べる目的で、血液検査やアレルギー検査を行うことがあります。これにより、炎症反応の程度や特定の病原体の存在、アレルギー反応の有無などを確認します。
結果説明・今後の方針決定
検査結果を総合的に判断し、考えられる原因や必要な治療、経過観察の期間を提案します。疑わしい所見がある場合には、追加の検査を行うこともあります。
特に喫煙歴がある方の場合、COPDの可能性や併発症についても説明させていただくことが多いです。
受診時の一般的な検査内容
| 検査名 | 内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 問診 | 過去の病歴、喫煙歴、症状のヒアリング | 約10~15分 |
| 肺機能検査 | スパイロメトリーによる呼吸機能チェック | 約15~20分 |
| 胸部X線・CT | 肺の詳細画像を撮影し、陰影の状態を確認 | 約30分(CT含む) |
| 血液検査 | 炎症反応や感染症、アレルギーなどを確認 | 採血後の待ち時間含め約30分 |
| 専門医からの説明 | 総合的な診断、今後の治療方針の相談 | 約15~20分 |
日常生活で気をつけること
肺のびまん性陰影が見つかったからといって、必ず重大な疾患があるわけではありません。
しかし、呼吸器の健康を保つために日ごろから意識して行えることがあります。生活習慣の改善は、疾患の予防だけでなく、進行を遅らせる役割も期待できます。
喫煙習慣の見直し
呼吸器の健康を守るうえで、たばこを吸っている方は禁煙を検討するとよいでしょう。喫煙は肺に直接影響を与え、COPDをはじめ、さまざまな肺疾患のリスクを高めます。
運動習慣の取り入れ方
適度な運動は肺機能を維持するうえで大切です。ウォーキングや軽いジョギング、エアロビクスなどの有酸素運動を無理のない範囲で継続することが望ましいです。
苦しくなるほど激しい運動は避けつつ、呼吸を意識しながら体を動かしましょう。
- ウォーキング(1日30分を目標に)
- 軽いジョギング(週2~3回)
- 呼吸法を意識したストレッチ
- 自宅でできる体操やヨガ
食事と体重管理
過度な肥満は肺に負担をかけ、呼吸困難を悪化させる要因にもなりやすいです。逆にやせすぎも体力や免疫力の低下を招きます。
バランスの良い食事を心がけ、適正体重を維持することが重要です。タンパク質やビタミン、ミネラルを含む食品をバランスよく取り入れましょう。
定期的な検診と予防接種
健康診断で指摘を受けた後も、定期的な健診を続けることが大切です。
また、肺炎球菌ワクチンやインフルエンザワクチンなどの予防接種を受けることで、肺炎やインフルエンザが重症化するリスクを減らせます。特に高齢者や持病を持つ方は優先的に検討しましょう。
肺の健康を維持するためのポイント
| 取り組み | 具体的な例 | 期待できる効果 |
|---|---|---|
| 禁煙 | 禁煙外来の利用、禁煙補助薬の活用 | 肺機能低下の抑制、COPD予防 |
| 有酸素運動 | ウォーキング、軽いジョギング、ヨガ | 肺活量維持、血行促進 |
| バランスの良い食事 | 野菜・果物・タンパク質をバランスよく摂取 | 免疫力向上、体重管理 |
| 定期的な健診・受診 | 年1~2回の健康診断、肺機能検査 | 早期発見・早期対処 |
| 予防接種の検討 | 肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン | 重症化リスクの低減 |
喫煙との関係
喫煙は肺の大きなリスク要因であり、肺がんやCOPDだけでなく、間質性肺炎などの病気の悪化要因にもなります。
- 肺がんリスクの増大
- COPDの進行リスクが高まる
- 他の肺疾患悪化の可能性
- 周囲への受動喫煙被害
健康診断でびまん性陰影を指摘された場合、まず喫煙歴の有無を医師に詳しく伝えましょう。喫煙期間や本数も問診で確認されることが多いです。
なぜ喫煙は肺に悪いのか
タバコの煙には多くの有害物質が含まれていて、気道や肺胞にダメージを与えます。炎症が慢性化するとCOPDにつながり、遺伝子レベルの損傷が進めば肺がんのリスクも高まります。
禁煙による改善効果
禁煙を続けると、肺機能が徐々に回復する可能性があります。咳や痰の量が減るだけでなく、将来的なリスク低減にもつながります。
ただし、すでにびまん性陰影を伴う疾患がある場合は、禁煙だけで完治するわけではありません。医師との相談を通じて治療方針を決める必要があります。
他人への影響(受動喫煙)
受動喫煙でも肺疾患のリスクが高まります。家族や同僚など周囲の健康にも影響を与えるため、できるだけ屋内禁煙を徹底したり、喫煙スペースを活用したりするなどの配慮が求められます。
喫煙と肺機能の関係
| 喫煙状態 | 肺機能への影響 | 疾患リスク |
|---|---|---|
| 非喫煙者 | 比較的安定している | 肺がん・COPDリスクは低め |
| 軽度喫煙 | 軽度な炎症・肺機能低下 | COPD・肺がんのリスクは多少上昇 |
| 重度喫煙 | 顕著な炎症・肺機能低下 | COPD・肺がんリスク大幅に上昇 |
| 禁煙開始後 | 時間とともに回復傾向 | リスクは徐々に低下 |
治療や経過観察の選択肢
肺のびまん性陰影の原因となっている病気によって、治療方針や経過観察の回数は異なります。医師と相談しながら、自分の状態に合った選択肢を見つけることが大切です。
内服薬や吸入薬
間質性肺炎やCOPDなどでは、ステロイド薬や免疫抑制剤、吸入薬を使うケースがあります。炎症を抑えたり気道を広げたりすることで症状を和らげ、進行を遅らせることを目指します。
自己判断で薬をやめると症状が悪化する恐れがあるため、指示に従って服用を続けましょう。
リハビリテーション
呼吸機能が低下している場合、呼吸リハビリテーションの導入を検討します。
専門の理学療法士や作業療法士と相談しながら、呼吸筋のトレーニングや有酸素運動を組み合わせたプログラムを実施することで、生活の質を維持します。
外科的治療が必要な場合
腫瘍性疾患が原因でびまん性陰影が出ている場合、外科的治療が選択肢に入ることがあります。
手術の適応可否は病気の進行度や患者さんの全身状態によります。医師が画像検査や病理検査の結果を総合的に検討し、方針を決めます。
経過観察のポイント
原因によっては、すぐに治療を始めるよりも経過観察を行うほうが望ましいケースもあります。
特に無症状で、陰影の変化が長期間認められない場合などは、定期的な画像検査で変化をチェックします。
症状の有無や画像上の変化がポイントとなるため、医師から提示されたスケジュールに従って受診を続けましょう。
まとめ
健康診断の結果で「肺のびまん性陰影」を指摘されると不安になるかもしれません。
しかし、陰影の種類や広がり方は個々人によって異なり、必ずしも重篤な病気が潜んでいるわけではありません。まずは適切な検査を受け、原因を突き止めることが大切です。
とくに喫煙歴やCOPDのリスクがある方は早めの受診を心がけると、将来的な合併症や進行を防ぐうえで役立ちます。
呼吸器内科では、画像診断や肺機能検査を総合的に評価し、必要な場合には治療を提案します。日常生活の改善や禁煙、定期的な検査など、予防と早期発見によって肺の健康を守ることができます。
一人で判断が難しい場合は、遠慮せず医療機関に相談しましょう。
- 胸部画像で異常陰影を指摘されたら専門医を受診
- 喫煙歴や症状を医師に詳しく伝える
- 生活習慣の見直しで肺の負担を減らす
- 定期的な検査を継続し、変化を早期に見つける
肺の健康を保つために大切なポイントまとめ
| 項目 | 重要ポイント |
|---|---|
| 受診タイミング | 異常陰影を指摘されたら早めに呼吸器内科で検査 |
| 禁煙の徹底 | 肺へのダメージを軽減 |
| 運動習慣 | ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動で肺活量を維持 |
| 食生活 | バランスの良い栄養摂取で免疫力を保つ |
| 定期検診・再検査 | 変化の有無を確認し、早期に対応 |
自分の肺の状態を正しく知っておくことで、今後の生活習慣や受診のタイミングを決めやすくなります。原因が複雑な場合もありますが、専門家と連携しながら一つひとつ対処していきましょう。
当院(神戸きしだクリニック)への受診について
胸部レントゲン異常で精密検査をご希望の方は、当院の呼吸器内科で対応させていただきます。経験豊富な専門医による丁寧な診察と、充実した検査機器による精密検査を提供しています。
呼吸器内科の診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 – 12:00 | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ 隔週 | 休 |
| 13:30 – 16:30 | – | ○ | ○ | ○ | – | 休 | 休 |
検査体制
- 呼吸機能検査
- 胸部レントゲン検査
- 喀痰検査
- 血液検査
など、必要に応じた検査を実施いたします。高度な画像検査(CT・MRIなど)が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院(当院の道路向かい)と連携し、スムーズな検査実施が可能です。
受診時の持ち物
- 健康診断の結果(胸部レントゲン写真・結果報告書)
- 健康保険証
- お薬手帳(服用中のお薬がある方)
予約・受診方法
当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約
お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。
▽ クリック ▽