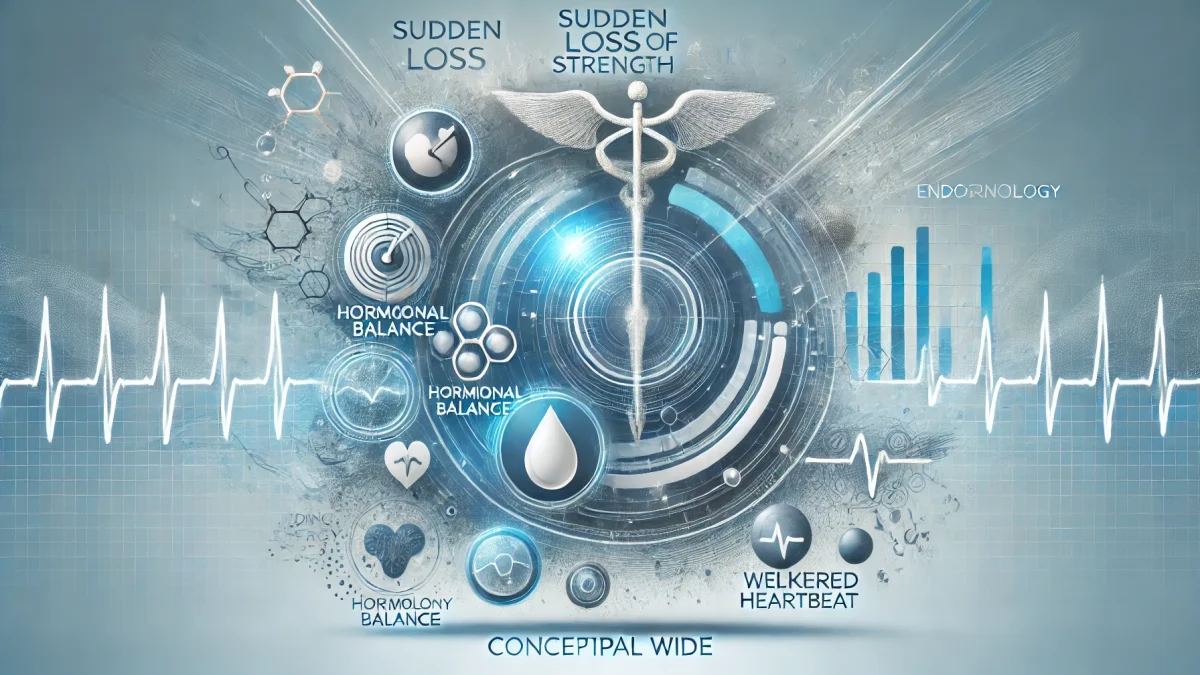ふとしたときに「最近、体力が急に落ちたような気がする…」と感じる瞬間がある方は、加齢のせいだと片付けてしまうと、見過ごしてしまう要因が潜んでいる可能性があります。
食事や睡眠などの日常生活の乱れから、内分泌系が関係する病気まで、思いも寄らない形で体力低下が進んでいるかもしれません。体力が落ちたと実感するときは、まず原因を整理してみましょう。
この記事では体力の急激な低下に焦点を当て、考えられる原因や内分泌の影響、受診の目安について解説します。
「最近、体力が急に落ちた」と感じていませんか?これは単なる疲れや加齢ではなく、内分泌系の乱れによるホルモンバランスの変化や甲状腺機能の低下など、身体からのSOSサインかもしれません。
神戸きしだクリニックの内分泌内科では、詳細な検査を通じて体力低下の根本原因を特定し、お一人おひとりのライフスタイルに合わせた効果的な治療プランをご提案します。健やかで活力ある毎日を取り戻すための第一歩として、ぜひ一度ご相談ください。詳しくはこちら
この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長
医学博士
日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医
日本核医学会認定 核医学専門医
【略歴】
神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)
体力が急に落ちたと感じるときに気づくポイント
体力の急激な低下は、日常の何気ないところにサインとして表れることがあります。気になる初期症状や生活上での変化を確認することで、原因の絞り込みにつながります。
ここでは、体力が落ちたと感じたときに注目したいポイントを整理します。
自覚症状のサイン
体力低下を最初に感じやすいのは、個人の自覚症状です。急に疲れやすくなったり、動くたびに息切れするようになったりすると、不安につながります。
こうした変化は意外と長期的に続くものではなく、ふとしたときに「なんだかおかしい」と気づく場合が多いです。毎日の生活で意識してみると、サインを早めに把握できます。
周囲との比較
以前は同じ距離を歩いても平気だったのに、最近は友人や家族と一緒に出かけると疲れを感じる回数が増えたと感じることも、体力低下の兆候です。
周囲の人々と同じ行動をとったとき、自分だけが著しく疲れやすいようなら、身体面の見直しが必要です。
日常動作の変化
洗濯物を運ぶ、階段を上る、買い物袋を持つなど、日常的な動作がつらくなった場合は要注意です。ここで日常動作の変化をまとめた一覧を示します。
日常動作における負担の例
| 動作の種類 | 以前の状況 | 現在の状況 |
|---|---|---|
| 階段の上り下り | 息切れが少なく、休憩せず登れた | 数段登るだけで呼吸が乱れ、休憩したくなる |
| 重い荷物の持ち運び | 軽いストレッチ感覚で運べた | 腰や肩に痛みが出て途中で下ろしたくなる |
| 掃除や片付け | 30分以上動き続けても問題なかった | 10分ほどで疲労感を感じて一旦座りたくなる |
| 買い物での歩行 | 複数の店を回っても疲れにくかった | 1店舗巡るだけで足が重いと感じる |
このように日常動作のちょっとした変化に気づいた段階で、できるだけ早く対策したいところです。
睡眠や食欲の乱れ
体力低下が進むと、睡眠時間をしっかり確保しても疲れが抜けないように感じる場合があります。
また、食欲が低下すると必要な栄養を十分に摂取できず、さらに体力が落ちる悪循環に陥ることもあるので注意が必要です。
- 朝起きても疲れが取れていない
- 夜中に何度も目が覚めてしまう
- 食事をしていても量が減る、味が薄く感じる
こうした兆候を放置せず、日々の体調変化を意識してください。
体力低下の主な原因
体力が急に落ちたとき、原因を一気に特定するのは難しいかもしれません。まずは複数の可能性を広く捉え、自分の生活習慣や健康状態を客観的に見直すことが重要です。
ここでは、体力低下によく挙げられる原因を取り上げます。
加齢や運動不足
年齢を重ねると筋力や骨密度の低下が進みやすくなりますが、それだけでなくライフスタイルの変化も体力を左右します。
運動不足が続くと筋肉量が減り、基礎体力が落ちる原因になります。
加齢と運動習慣に関するデータ
| 年齢帯 | 推奨される運動量 | 運動不足の影響 |
|---|---|---|
| 20代~30代 | 週2~3回の有酸素運動 | 基礎体力維持がしやすい |
| 40代~50代 | 週2回以上の筋トレ+有酸素運動 | 筋力低下を食い止めるうえで大切 |
| 60代以上 | 軽めの有酸素運動+ストレッチ | 日常動作の負担を軽減して生活の質を保ちやすい |
適度な運動習慣を身につけると、年齢による体力の低下をある程度食い止めやすくなります。
不規則な生活リズム
睡眠時間が不規則、食事の時間帯がバラバラ、仕事や勉強のスケジュールが超過しているなど、生活リズムの乱れは体力低下を招きます。
特に夜間の睡眠不足は自律神経のバランスを崩しやすく、疲労回復を妨げます。
- 夜更かしや早朝の過度な残業が多い
- 食事時間が日によって大きく異なる
- 休日と平日の睡眠時間に極端な差がある
こうした点を見直すだけでも、体力の変化が顕著に表れることがあります。
ストレスやメンタル面の影響
職場や家庭でのストレスが蓄積すると、自律神経やホルモン分泌の乱れを引き起こし、結果的に体力低下につながることがあります。
心身は相互に影響を及ぼすので、メンタルが不安定になると体力も落ちやすくなります。
ストレスと体力低下の関連例
| ストレス要因 | 身体的影響 | 心理的影響 |
|---|---|---|
| 過重労働・長時間労働 | 免疫力の低下、睡眠不足 | 疲労感による意欲の減退 |
| 家庭内問題(介護など) | 食欲不振、腰痛や肩こり | 不安感、落ち込み |
| 対人関係トラブル | 頭痛、胃痛 | 気分の波、集中力の低下 |
| 経済的な不安 | 慢性的な身体のこわばり | 常に考え事をして眠れない |
ストレスケアをするだけでも、体調が改善するケースは珍しくありません。
潜在的な病気の可能性
体力低下には、思わぬ病気が隠れていることがあります。
貧血や甲状腺機能異常、心臓や肺などの疾患は、体に負担をかけて疲れやすくする原因になり得ます。検査で血液やホルモン値を調べた上で、必要に応じて専門医へ相談してください。
体力低下と内分泌異常
内分泌系が乱れると、ホルモンの調節機能に不具合が生じやすく、体力や気力の低下につながることがあります。
内分泌系とは何か、そして具体的にどのような病気が体力低下につながるかを見ていきましょう。
内分泌とは
内分泌は、体内のさまざまな器官から分泌されるホルモンを通じて、身体機能を調節する仕組みです。
ホルモンは血流に乗って全身に運ばれ、代謝や成長、ストレス反応などを調整します。
- 代謝を活発化させるホルモン
- 体温調節や水分バランスに関わるホルモン
- 性ホルモンやストレスに関連するホルモン
どれか1つの分泌が乱れるだけで、全身の機能バランスが崩れる可能性があります。
ホルモンバランスの崩れ
ホルモンバランスが崩れると、体力低下のほかにも様々な症状が現れます。例えば甲状腺ホルモンが少ないと、新陳代謝が落ちて疲れやすく、むくみや寒がりなどが生じやすくなります。
逆にホルモンが過剰な場合は、心拍数や血圧が上がりやすくなるなどの影響があります。
代表的なホルモンの働きと影響
| ホルモン名 | 働き | バランスが崩れた場合の症状 |
|---|---|---|
| 甲状腺ホルモン | エネルギー消費や代謝を促進 | 疲労感、体重増加、冷え、動悸など |
| コルチゾール | ストレス応答、代謝調整 | 倦怠感、免疫力低下、血糖値異常 |
| インスリン | 血糖値を下げる | 血糖値の乱高下、疲れやすさ、倦怠感 |
| 性ホルモン | 生殖機能や骨の維持に関与 | 更年期症状、骨密度低下、疲労感 |
こうしたホルモンの乱れを総合的に評価するのが、内分泌内科の領域です。
代表的な内分泌疾患
甲状腺機能低下症や副腎不全など、代表的な内分泌疾患は体力低下やだるさ、意欲低下を引き起こします。
特に甲状腺機能低下症は比較的多い疾患で、女性に多く見られます。症状が似ていても、病気の種類や治療法は異なるため、専門的な検査が重要です。
受診を検討したい症状
内分泌系の病気を疑う症状として、以下のような兆候があります。
- 原因不明の体重増加・減少
- 朝起きるのがつらく、何をしても疲労感が抜けにくい
- 皮膚の乾燥やむくみ、便秘
- 動悸や息切れ
これらが続く場合、専門医に相談すると原因を特定しやすくなります。
自分でできる体力低下へのアプローチ
体力が落ちたと感じたとき、すぐに大きなトレーニングを始めたり、極端な食事制限をしたりする必要はありません。
まずは生活習慣を適度に見直し、体と心の両面からサポートすることが大切です。
ライフスタイルの見直し
日々の生活スタイルが疲れやすさに直接関わってくるため、定期的に見直してみると改善のヒントが見つかることがあります。
- 就寝・起床時間の固定化
- スマートフォンやPCなどのデジタル機器との付き合い方
- 軽めのストレッチやマッサージの習慣化
小さな変化でも積み重なると大きな違いになります。
生活スタイル改善の段階的ステップ
| ステップ | 実施内容 | メリット |
|---|---|---|
| Step1 | 就寝前1時間は画面を見ない | 睡眠の質向上、入眠のしやすさ |
| Step2 | 毎朝同じ時間に起きる | 体内時計の調整、集中力の安定 |
| Step3 | 軽い散歩やストレッチを日課に | 血行促進、ストレス解消、体力維持 |
| Step4 | 食事のバランスを再確認 | 栄養バランスの改善、疲労回復速度向上 |
食習慣の調整
高カロリー・高脂質の食事が多いと、内臓への負担が増して体力を消耗しやすくなります。
また、タンパク質やビタミン、ミネラルなどが不足すると筋力や免疫力の低下につながります。
- 野菜を多めに取り入れる
- タンパク質を意識したメニュー構成(肉、魚、大豆製品など)
- 発酵食品や水溶性食物繊維の積極的な摂取
食習慣の変化は短期間で成果を感じにくいですが、継続すると体力面でプラスに働きます。
適度な運動メニュー
急に激しい運動をすると、体への負担が大きく逆効果になることもあります。適度な負荷で、継続しやすい運動メニューを考えるのがコツです。
ウォーキングや軽い筋トレなど、ライフスタイルに合わせたものが良いでしょう。
運動メニュー例
| 運動名 | 運動強度 | 時間(目安) | メリット |
|---|---|---|---|
| ウォーキング | 低~中 | 30分前後 | 心肺機能の向上、リフレッシュ |
| スクワット | 中 | 10回×3セット | 下半身の筋力強化、代謝向上 |
| 軽めのヨガ | 低 | 15~20分 | 体の柔軟性向上、リラックス効果 |
| ラジオ体操 | 低~中 | 5分程度 | 全身をまんべんなく動かせる |
自分が楽しく続けられるメニューを選ぶことが、モチベーションを保つためのポイントです。
ストレスマネジメント
ストレスは体力や気力の消耗につながりやすく、放置すると免疫力の低下や内分泌バランスの崩れを招きやすいです。
こまめにストレス解消の時間を取ることも忘れずに行いましょう。
- 深呼吸や瞑想
- 趣味の時間の確保
- 友人や家族とのコミュニケーション
小さなストレス発散を積み重ねると、体力面にもポジティブな影響があります。
内分泌内科を受診すべきタイミング
体力低下に対して生活改善を試しても良くならない、あるいは異常なほど疲れやすいと感じる場合、内分泌内科など専門科の受診を考える必要があります。
何を目安に受診を検討すれば良いのか、ここで確認してみましょう。
単なる疲れや老化との見極め
体力が落ちたという感覚だけでは、加齢や単なる疲労なのか、内分泌異常なのか判別が難しいです。
以下のような傾向がある場合は、単なる疲れや加齢だけでは説明できない可能性があります。
- 生活リズムの改善を行っても症状が変わらない
- 体重や食欲など体組成・摂取量に異常がある
- 普段と同じ活動でも極端に疲れる
少しでも心当たりがあるなら、早めの受診が負担軽減につながります。
血液検査やホルモン検査
内分泌内科では、血液検査によってホルモン値を調べるのが基本です。
甲状腺機能や副腎皮質ホルモン、性ホルモンなどをチェックして、異常がないかを確認します。
内分泌内科で測定する主な項目
| 検査名 | 主なチェック項目 | 意味合い |
|---|---|---|
| 甲状腺機能検査 | TSH、FT3、FT4 | 甲状腺ホルモンの過不足 |
| 副腎機能検査 | コルチゾール、ACTH | 副腎疲労やクッシング症候群など |
| 血糖値・HbA1c | 血糖値と過去約2か月間の平均血糖 | インスリンの働きや糖代謝 |
| 性ホルモン関連検査 | エストロゲン、テストステロン、LH、FSHなど | 更年期障害や生殖機能の状態把握 |
こうした検査を行うことで、ただの疲労ではなくホルモン異常が原因なのかを確認できます。
クリニックでの診察の流れ
内分泌内科クリニックでは、まず問診で生活習慣や症状の経緯、既往歴などを詳しく聞き取ります。その後、必要に応じて血液検査や超音波検査などを行い、検査結果を踏まえて治療方針を決定します。
時間がかかる場合もありますが、原因を特定するうえで大切なプロセスです。
内分泌専門医の役割
内分泌専門医は、ホルモンに関する知識と経験をもとに診断を行います。
一般内科では原因を特定しづらい場合も、専門の検査や視点で状態をチェックすることで、適切な治療を導きやすくなります。
体力低下が気になる方へのセルフモニタリング
体力が落ちたと感じる方は、日々の体調や生活習慣を記録し、変化を把握する習慣をつけると原因を発見しやすくなります。ここではセルフモニタリングのポイントを挙げます。
日々の健康チェック項目
- 朝起きたときの疲労感の度合い
- 1日の運動や活動量
- 食事の内容と量、水分摂取量
- 夜の就寝時間と睡眠時間
毎日でなくても、週に数回記録しておくだけでも傾向をつかみやすくなります。
健康チェック項目を可視化した例
| チェック項目 | 日付 | 評価・内容 |
|---|---|---|
| 起床時の疲労感 | 4/1 | やや疲れが残る |
| 食事バランス | 4/1 | 朝食抜き、昼夜で炭水化物多め |
| 運動・歩数 | 4/1 | 散歩15分、歩数5,000歩 |
| 睡眠時間 | 4/1 | 23:30就寝~6:30起床(7時間) |
チェックリストの作り方
体力の急激な落ち込みを感じる人は、上記の項目をもとに自分なりのチェックリストを作成すると便利です。
紙の手帳やスマートフォンのメモ機能など、扱いやすいツールを選びましょう。
データ化と継続のコツ
データ化する際には、数値やキーワードを簡潔にまとめると後から振り返りやすくなります。
継続が難しいと感じるなら、1~2個の項目から始めて、習慣になったら少しずつ増やしていくと負担が少なくなります。
- まずは「起床時間」「就寝時間」「疲労感」の3項目だけを記録
- 続ける自信がついたら食事や運動も追加
無理のない範囲で習慣づけるのが長続きのコツです。
家族や周囲との情報共有
自分一人で管理するよりも、家族や友人と情報を共有すると客観的なアドバイスを得やすくなります。周囲にサポートしてもらうことで、生活習慣の改善もスムーズに進むことが多いです。
体力低下を補うために考慮したいサポート
体力が落ちたときは、日常のちょっとした工夫だけでなく、場合によっては外部のサポートも利用するのが大切です。
ここでは、サプリメントや生活環境、リハビリなどの視点からサポート方法を紹介します。
栄養サプリメントや食材
食事だけでは十分な栄養が取り切れないと感じたときは、サプリメントや特定の食材を活用するのも1つの方法です。
ビタミンや鉄分、カルシウムなど、不足しやすい栄養素を補うと体力の回復に役立つことがあります。
体力面をサポートする栄養素の例
| 栄養素 | 期待できる主な働き | 含まれる食材 |
|---|---|---|
| タンパク質 | 筋肉量維持、疲労回復 | 肉、魚、卵、大豆製品 |
| 鉄分 | 酸素運搬、貧血予防 | レバー、ほうれん草、ひじき |
| ビタミンB群 | エネルギー代謝サポート | 豚肉、豆類、玄米など |
| ビタミンC | 免疫力サポート、コラーゲン生成 | 柑橘類、パプリカ、いちご |
こうした栄養素を補うだけでも、日々の疲労感が和らぐケースがあります。
運動指導やリハビリの利用
専門家のアドバイスを受けて運動メニューを組み立てると、自分に合った無理のないトレーニングを実行しやすくなります。
特に高齢の方や病気を抱えている方は、リハビリを通じて安全に筋力や持久力を高めるのが有効です。
- パーソナルトレーニング
- フィットネスクラブやヨガ教室
- 介護施設や病院でのリハビリプログラム
運動の種類や負荷のかけ方を専門家と相談すると、ケガのリスクも抑えられます。
生活環境の整備
生活環境が快適だと、疲れの蓄積を予防できます。
部屋の温度や湿度管理、寝具の見直し、家のバリアフリー化など、体力面への配慮があるだけで負担が変わってきます。
生活環境の整備ポイント
- エアコンや加湿器で適度な温湿度を保つ
- 腰や首に負担をかけにくいマットレスの選択
- 段差の少ないレイアウトにして転倒リスクを減らす
- 掃除や片付けがしやすい部屋づくり
このように環境を整えると、日常生活を快適に送れる時間が増え、体力温存にもつながります。
医療機関との連携
自宅でできる工夫と合わせて、定期的にかかりつけ医や内分泌内科に相談するのも心強い方法です。
症状の経過を共有しながら治療方針を決めると、病気の早期発見や予防につなげやすくなります。
まとめ:早めの気づきと対策が大切
体力の急激な低下は、生活習慣だけでなく内分泌異常など複数の要因が絡んでいる可能性があります。早めの気づきとアクションが、その後の生活の質を左右します。
最後に、チェックしておきたい要点を振り返りましょう。
体力低下を放置するリスク
体力低下をそのままにすると、慢性的な疲労感や生活意欲の低下へとつながりやすくなります。
活動量が減ると筋力がさらに落ち、悪循環が起こることもあります。
受診を検討する目安
- 原因がわからない疲れやだるさが長く続いている
- 体重増減やホルモンバランスが疑われる症状がある
- 日常動作に支障が出るレベルで息切れする
こうした状況に当てはまるなら、一度内分泌内科などの専門家へ相談するのが安心です。
生活改善とのバランス
体力低下の原因が生活習慣にある場合、食事や運動、睡眠などの見直しによって劇的に改善するケースもあります。
一方で、内分泌異常など専門的な診察や治療が必要なこともあるので、バランスを取りながら進めてください。
生活改善と専門医受診を両立するためのヒント
| 対策 | 主な目的 | ポイント |
|---|---|---|
| 運動・食事療法 | 生活習慣の改善 | 続けやすいメニューを取り入れる |
| 定期的な検査 | 病気の早期発見 | 血液検査やホルモン検査を活用 |
| 情報共有 | 正しい知識のアップデート | 医師や家族との連携で客観視 |
安心して暮らすために
体力が落ちて日常生活がしんどいと感じるときは、一度しっかり原因を調べることが重要です。
内分泌の問題や他の疾患が隠れているケースもあるので、「ただの疲れ」と決めつける前に、専門医への受診を検討すると安心につながります。
早期に手を打つことで、これからの生活をより快適に過ごしやすくなるでしょう。
当院(神戸きしだクリニック)への受診について
神戸きしだクリニックの内分泌内科では、体力低下の原因となるホルモンバランスの乱れに関する専門的な診察を行っております。
急な体力低下や慢性的な疲労感は、甲状腺機能低下症やその他の内分泌系疾患が隠れている可能性があります。
活力ある日常生活を取り戻すため、原因不明の体力低下や全身倦怠感にお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。
内分泌内科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |
| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |
| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |
| 月 | – | 〇 |
| 火 | 〇 | 〇 |
| 水 | – | 〇 |
| 木 | 〇 | – |
| 金 | – | 〇 |
| 土 | 〇 隔週 | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |
検査体制
- 甲状腺機能検査(TSH・FT3・FT4)
- 副腎皮質ホルモン検査(コルチゾールなど)
- 下垂体ホルモン検査
- 血液検査(貧血・炎症反応・電解質バランスなど)
- 自己抗体検査(バセドウ病・橋本病など)
など、症状に応じた適切な検査を実施いたします。専門的な精査や詳細検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など高度医療機関と連携して対応いたします。
予約・受診方法
当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約
お電話での予約も受け付けております。健康診断の再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。
▽ クリック ▽