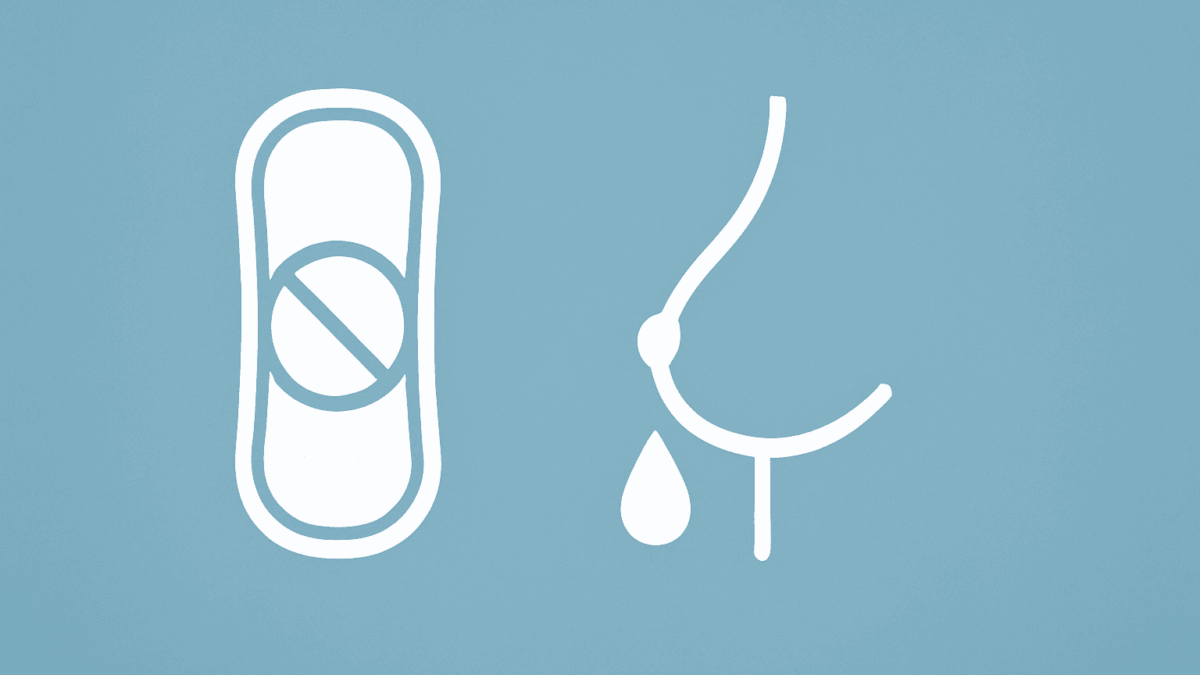「最近、月経が来ない」「妊娠・授乳中ではないのに母乳のようなものが出る」といった症状でお悩みではありませんか?
これらの症状は、ホルモンバランスの乱れ、特に「プロラクチン」というホルモンが高くなる「高プロラクチン血症」が原因かもしれません。
この記事では、高プロラクチン血症の原因、検査、治療法について、内分泌内科の視点から分かりやすく解説します。
ご自身の症状と照らし合わせながら、適切な対処法を知るための一助となれば幸いです。
「月経が不規則になった」「授乳していないのに乳汁が出る」こんな症状は高プロラクチン血症と呼ばれる内分泌異常の可能性があります。
下垂体腺腫(プロラクチノーマ)や薬剤の副作用、あるいは甲状腺機能低下症などが原因となることがあり、放置すると骨密度低下や不妊など、将来的な健康リスクにつながる可能性があります。これらの症状でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。詳しくはこちら
この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長
医学博士
日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医
日本核医学会認定 核医学専門医
【略歴】
神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)
月経が止まる・母乳が出る… もしかして高プロラクチン血症?
月経不順や無月経、乳汁分泌(母乳が出ること)は、女性にとって心配な症状です。
これらの背景には、脳の下垂体から分泌される「プロラクチン」というホルモンの過剰分泌が隠れていることがあります。
プロラクチンとは?
プロラクチンは、脳の下垂体前葉という場所から分泌されるホルモンの一種です。主な働きは、出産後の女性において乳腺の発達を促し、母乳の産生・分泌を維持することです。
妊娠中や授乳中には、プロラクチンの分泌量が増加するのが正常な状態です。
高プロラクチン血症とは?
高プロラクチン血症とは、妊娠・授乳期以外にもかかわらず、血液中のプロラクチン濃度が異常に高くなる状態を指します。
プロラクチン値が高くなると、体の様々な機能に影響が出ることがあります。
プロラクチン値の目安
| 状態 | 一般的なプロラクチン基準値 (ng/mL) | 備考 |
|---|---|---|
| 非妊娠・非授乳期の女性 | 約 5~25 未満 | 検査機関により基準値は異なる場合があります |
| 妊娠後期 | 高値 (~200程度) | 生理的な増加です |
| 授乳期 | 高値 | 授乳刺激により変動します |
なぜ月経が止まったり母乳が出たりするの?
プロラクチンは、卵巣での女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)の分泌を抑制する働きがあります。
そのため、プロラクチン値が高くなると、排卵が抑制されたり、月経周期が乱れたりして、月経不順や無月経(月経が止まる)を引き起こします。
また、プロラクチン本来の作用である乳汁分泌が、妊娠・授乳中でなくても起こることがあります(乳汁漏出)。
他にどんな症状がある?
高プロラクチン血症では、月経異常や乳汁分泌以外にも、以下のような症状が現れることがあります。ただし、症状の現れ方には個人差があります。
高プロラクチン血症で見られる可能性のある症状
| 分類 | 主な症状 |
|---|---|
| 女性特有 | 月経不順、無月経、不妊、性欲低下、乳汁漏出 |
| 男性特有 | 性欲低下、勃起不全(ED)、不妊、女性化乳房 |
| 男女共通 | 頭痛、視野障害(下垂体腫瘍が大きい場合) |
高プロラクチン血症の主な原因
高プロラクチン血症を引き起こす原因は様々です。原因を特定することが、適切な治療方針を決める上で重要になります。
薬剤性(お薬の影響)
特定の薬剤の副作用として、プロラクチン値が上昇することがあります。
特に、精神科や消化器科で処方される薬の一部には、プロラクチンの分泌を促す作用を持つものがあります。
薬の服用を開始してから症状が現れた場合は、薬剤性の可能性を考えます。
プロラクチン値を上昇させる可能性のある薬剤の例
| 薬剤の種類 | 主な用途 |
|---|---|
| 抗精神病薬 | 統合失調症など |
| 抗うつ薬(一部) | うつ病など |
| 消化管機能改善薬(一部) | 吐き気、胃腸症状など |
| 降圧薬(一部) | 高血圧 |
※上記は一例です。服用中の薬がある場合は、医師に必ず伝えましょう。自己判断で薬を中断しないでください。
下垂体腫瘍(プロラクチノーマなど)
脳の下垂体に腫瘍ができることで、プロラクチンが過剰に産生される場合があります。
プロラクチンを産生する下垂体腫瘍を「プロラクチノーマ」と呼び、高プロラクチン血症の最も重要な原因の一つです。
腫瘍が大きくなると、周囲の視神経を圧迫して視野障害(特に両耳側が見えにくい)や頭痛を引き起こすこともあります。
甲状腺機能低下症
甲状腺ホルモンの分泌が低下する甲状腺機能低下症も、プロラクチン値を上昇させる原因となることがあります。
甲状腺ホルモンを分泌させるよう指令を出すホルモン(TRH)が、プロラクチンの分泌も刺激するためと考えられています。
その他の原因(ストレス、多嚢胞性卵巣症候群など)
強い精神的・身体的ストレス、激しい運動、睡眠不足なども一時的にプロラクチン値を上昇させることがあります。
また、排卵障害を伴う多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)や、腎不全、肝硬変などの全身性疾患が原因となることもあります。
その他の原因となりうるもの
- 身体的・精神的ストレス
- 睡眠不足
- 胸部の手術や帯状疱疹などの刺激
- 多嚢胞性卵巣症候群 (PCOS)
- 腎不全、肝硬変
どんな検査をするの? 検査の流れ
高プロラクチン血症が疑われる場合、原因を特定するためにいくつかの検査を行います。
問診と診察
まず、症状(月経の状態、乳汁分泌の有無、その他の自覚症状など)について詳しく伺います。現在服用中の薬、既往歴、妊娠・出産の経験なども重要な情報です。
診察では、乳汁分泌の確認や、下垂体腫瘍に伴う視野障害がないかなどを調べます。
血液検査(プロラクチン値、ホルモン検査)
血液検査でプロラクチン値を測定します。これが高プロラクチン血症の診断の基本です。
同時に、他の下垂体ホルモン(成長ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、副腎皮質刺激ホルモン、性腺刺激ホルモンなど)や、甲状腺ホルモン、性ホルモンなども測定し、原因を探る手がかりにします。
血液検査で調べる主な項目
| ホルモン名 | 主な目的 |
|---|---|
| プロラクチン (PRL) | 高プロラクチン血症の診断 |
| 甲状腺ホルモン (TSH, FT4, FT3) | 甲状腺機能低下症の有無を確認 |
| 性ホルモン (LH, FSH, E2) | 卵巣機能や排卵の状態を確認 |
| その他の下垂体ホルモン | 下垂体全体の機能を確認 |
画像検査(頭部MRIなど)
プロラクチン値が著しく高い場合や、下垂体腫瘍が疑われる場合には、頭部のMRI検査を行います。MRI検査により、下垂体腫瘍の有無、大きさ、位置などを詳細に確認できます。
特にプロラクチノーマの診断には重要な検査です。
その他の検査
必要に応じて、視野検査(下垂体腫瘍による圧迫がないか確認)、薬剤負荷試験(プロラクチンの分泌反応を見る)などを行うこともあります。
高プロラクチン血症の治療法
高プロラクチン血症の治療は、原因や症状の程度、妊娠希望の有無などによって異なります。
原因に応じた治療の選択
治療の基本は、原因を取り除くことです。
薬剤性が原因であれば、可能であれば原因薬剤の中止や変更を検討します。甲状腺機能低下症が原因であれば、甲状腺ホルモン補充療法を行います。
薬物療法(ドーパミン作動薬)
プロラクチノーマなどの下垂体腫瘍が原因の場合や、原因不明(特発性)の高プロラクチン血症に対しては、薬物療法が第一選択となります。
主に「ドーパミン作動薬」という種類の薬を使用します。この薬は、プロラクチンの分泌を抑制し、多くの場合、腫瘍を縮小させる効果も期待できます。
主なドーパミン作動薬
| 薬剤名(一般名) | 特徴 | 主な副作用 |
|---|---|---|
| カベルゴリン | 週1~2回の服用で効果が持続 | 吐き気、めまい、便秘など |
| ブロモクリプチン | 1日1~2回の服用 | 吐き気、嘔吐、起立性低血圧など |
| テルグリド | 1日1回の服用 | 吐き気、眠気など |
※副作用の出方には個人差があります。医師の指示に従って服用してください。
手術療法(下垂体腫瘍の場合)
薬物療法で効果が不十分な場合や、薬の副作用が強い場合、腫瘍が大きく視神経への圧迫症状が強い場合などには、手術(経蝶形骨洞手術など)を検討することがあります。
手術は、脳神経外科医と連携して行います。
経過観察
プロラクチン値の上昇が軽度で、症状もほとんどなく、妊娠希望もない場合などは、特に治療を行わず定期的に経過観察することもあります。
治療中の注意点と生活上のアドバイス
高プロラクチン血症の治療を続ける上で、いくつか注意点があります。日常生活での工夫も、症状の改善や再発防止につながることがあります。
薬の副作用について
ドーパミン作動薬は、吐き気、めまい、便秘、眠気などの副作用が出ることがあります。多くは服用開始初期に見られますが、徐々に慣れてくることが多いです。
副作用が続く場合や、気になる症状がある場合は、自己判断で薬を止めずに必ず医師に相談してください。服用量を調整したり、他の薬に変更したりすることで対処できる場合があります。
定期的な通院と検査の重要性
治療効果を確認し、副作用をチェックするために、定期的な通院と血液検査(プロラクチン値など)が必要です。
薬物療法を行っている場合は、薬の量を調整するために欠かせません。下垂体腫瘍がある場合は、定期的なMRI検査で腫瘍の大きさの変化を確認することも重要です。
定期検査の目的
| 検査項目 | 主な目的 |
|---|---|
| 血液検査 (プロラクチン値など) | 治療効果の判定、薬の量調整 |
| 問診・診察 | 症状の変化、副作用の確認 |
| MRI検査 (必要な場合) | 下垂体腫瘍の大きさの変化を確認 |
食事や運動に関する注意
特定の食事が高プロラクチン血症を直接改善するという証拠はありませんが、バランスの取れた食事を心がけることは体全体の健康維持に役立ちます。
過度な運動はプロラクチン値を上昇させる可能性があるので、適度な運動を心がけましょう。
ストレス管理
ストレスはプロラクチン値を上昇させる要因の一つです。日常生活でストレスを溜め込まないように、自分なりのリラックス法を見つけることが大切です。
十分な睡眠をとることも、ホルモンバランスを整える上で役立ちます。
ストレス軽減のヒント
- 十分な睡眠
- 軽い運動(ウォーキングなど)
- 趣味の時間
- リラックスできる時間(入浴、音楽鑑賞など)
いつ、何科を受診すればいい?
月経が止まったり、母乳が出たりする症状に気づいたら、どのタイミングで、どの診療科を受診すればよいのでしょうか。
受診の目安となる症状
以下のような症状が続く場合は、医療機関への受診を検討しましょう。
- 3ヶ月以上月経が来ない(無月経)
- 月経周期が著しく不規則になった
- 妊娠・授乳中ではないのに、乳首から分泌物(特に白色や透明)が出る
- 不妊で悩んでいる
- 原因不明の頭痛や視野の異常がある
まずは婦人科? それとも内分泌内科?
月経不順や無月経、乳汁分泌といった症状は、婦人科系の疾患が原因である可能性もあります。そのため、まずは婦人科を受診することも選択肢の一つです。
婦人科での診察や検査の結果、ホルモン異常、特に高プロラクチン血症や下垂体の問題が疑われる場合には、内分泌内科への受診を勧められることがあります。
最初からホルモンの病気を疑う場合や、以前に高プロラクチン血症や下垂体の病気を指摘されたことがある場合は、直接、内分泌内科を受診することも可能です。
診療科選択の考え方
| 主な症状・状況 | 最初に検討する診療科 | 次に検討する診療科 |
|---|---|---|
| 月経不順、無月経、不正出血 | 婦人科 | 内分泌内科(ホルモン異常が疑われる場合) |
| 乳汁分泌 | 婦人科 または 内分泌内科 | ー |
| 頭痛、視野障害を伴う場合 | 内分泌内科 または 脳神経外科 | 婦人科(ホルモン検査のため) |
| 不妊 | 婦人科(不妊治療専門) | 内分泌内科(ホルモン異常が原因の場合) |
当クリニック(内分泌内科)での対応
当クリニックでは、高プロラクチン血症を含む下垂体疾患やその他のホルモン異常の診断・治療を行っております。
問診、血液検査、必要に応じた画像検査(連携医療機関にて)などを通じて原因を特定し、患者さん一人ひとりに合わせた治療方針を提案します。
婦人科や脳神経外科との連携も密に行っていますので、安心してご相談ください。
紹介状は必要?
他の医療機関で検査や治療を受けている場合は、これまでの経緯や検査結果がわかる紹介状(診療情報提供書)があるとスムーズな診療につながります。しかし、紹介状がなくても受診は可能です。
初めて受診される方や、どの科にかかればよいか分からないという方も、まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問 (FAQ)
- Q妊娠を希望していますが、治療は可能ですか?
- A
はい、可能です。高プロラクチン血症は不妊の原因となることがありますが、薬物療法などでプロラクチン値を正常化させることで、排卵が回復し妊娠が可能になるケースが多くあります。
妊娠希望がある場合は、治療開始前に必ず医師にお伝えください。妊娠に適した薬剤の選択や、妊娠後の治療方針について相談します。
プロラクチノーマがある場合でも、多くは薬物療法を行いながら妊娠・出産が可能です。
- Q薬はずっと飲み続ける必要がありますか?
- A
原因や病状によって異なります。薬剤性が原因であれば、原因薬剤の中止・変更で改善すれば、治療薬は不要になることが多いです。
プロラクチノーマなどの下垂体腫瘍が原因の場合、長期間の服用が必要になることもありますが、腫瘍が縮小・消失したり、プロラクチン値が安定したりすれば、医師の判断で減量や休薬を試みることもあります。
自己判断での中断は再発のリスクがあるため、必ず医師と相談しながら進めましょう。
- Q男性でも高プロラクチン血症になりますか?
- A
はい、男性でも高プロラクチン血症になることがあります。男性の場合、症状としては性欲低下、勃起不全(ED)、不妊、まれに女性化乳房(胸が膨らむ)などが現れます。
原因は女性と同様に、薬剤性や下垂体腫瘍(プロラクチノーマ)などがあります。気になる症状がある場合は、泌尿器科または内分泌内科にご相談ください。
- Q治療費はどのくらいかかりますか?
- A
治療費は、行う検査(血液検査、MRIなど)や処方される薬剤の種類、量、治療期間によって異なります。高プロラクチン血症の治療は、基本的に健康保険が適用されます。
診察料、検査料、薬剤料などがかかりますが、高額療養費制度の対象となる場合もあります。詳細については、診察時に医師またはスタッフにお尋ねください。
当院(神戸きしだクリニック)への受診について
神戸きしだクリニックの内分泌内科では、高プロラクチン血症に関連するホルモンバランスの異常について専門的な診察を行っております。
月経不順や無月経、乳汁分泌、性欲低下などの症状は、下垂体から分泌されるプロラクチンというホルモンの過剰分泌が原因となっていることがあります。
適切な診断と治療でホルモンバランスを整え、月経機能を回復するため、これらの症状にお悩みの方は、どうぞお気軽に当院までご相談ください。
内分泌内科
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |
| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |
| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |
| 月 | – | 〇 |
| 火 | 〇 | 〇 |
| 水 | – | 〇 |
| 木 | 〇 | – |
| 金 | – | 〇 |
| 土 | 〇 隔週 | - |
| 日 | - | - |
| 祝 | - | - |
検査体制
- プロラクチン測定
- 下垂体ホルモン検査
- 甲状腺機能検査
- 性ホルモン検査(エストロゲン・プロゲステロンなど)
- 下垂体MRI検査
- 経時的プロラクチン測定
など、症状に応じた適切な検査を実施いたします。専門的な精査や詳細検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など高度医療機関と連携して対応いたします。
予約・受診方法
当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約
お電話での予約も受け付けております。健康診断の再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。
▽ クリック ▽