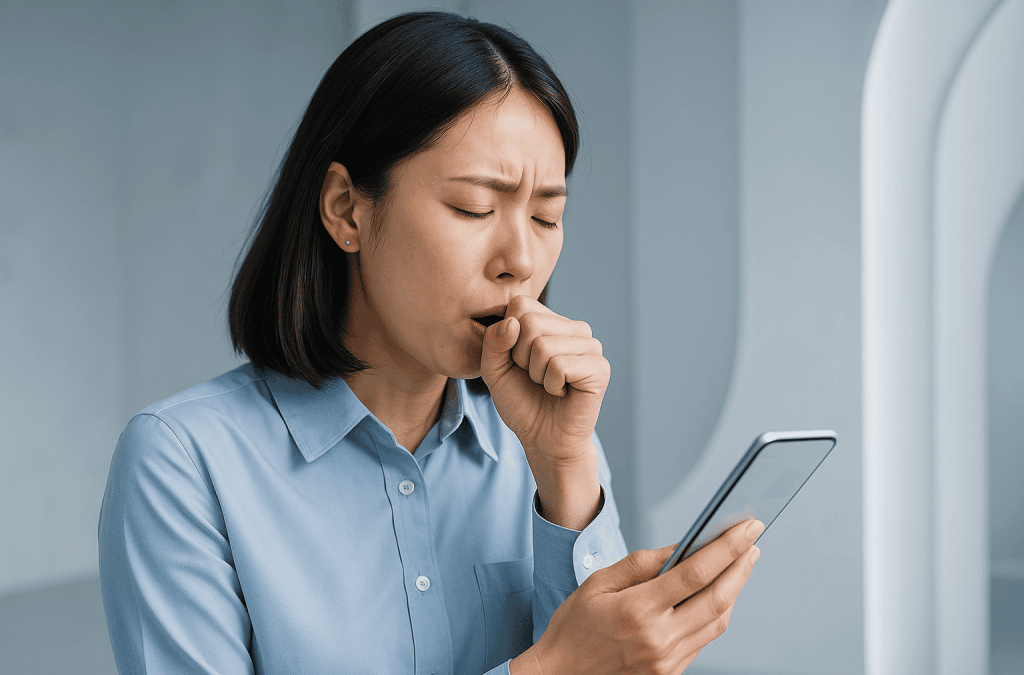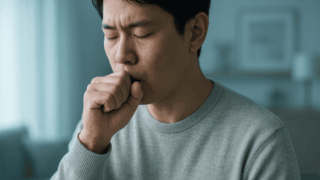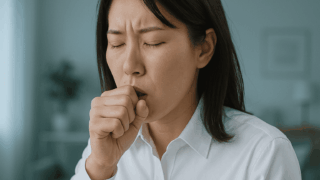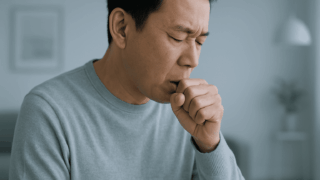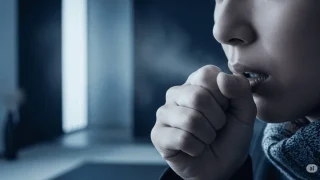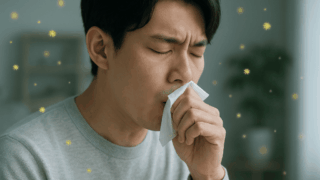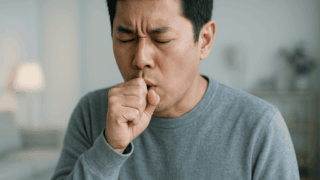「コンコン」「ゴホゴホ」と続く咳は、誰にとってもつらい症状です。単なる風邪だと思っていても、なかなか治らなかったり、特定の状況でひどくなったりすると不安になるものです。
咳は体の重要な防御反応ですが、その裏には様々な原因が隠れている可能性があります。
この記事では、咳の症状を正しく理解し、ご自身の状態を把握するための一助として、咳の種類や原因、考えられる病気について詳しく解説します。
ご自身の咳と向き合い、適切な対処法を見つけるための参考にしてください。
咳のセルフチェックで確認すべきこと
咳が続くとき、まずはご自身の症状を客観的に把握することが大切です。医療機関を受診する際にも、正確な情報を医師に伝えることで、スムーズな診断につながります。
以下のポイントを意識して、ご自身の咳を観察してみましょう。
いつから咳が出ていますか?
咳が始まった時期と、現在まで続いている期間は、原因を考える上で非常に重要な情報です。
3週間未満であれば「急性」、3週間から8週間であれば「亜急性」、8週間以上続く場合は「慢性」と、期間によって原因となる病気がある程度絞られます。
いつから始まったか、おおよその時期を思い出してみましょう。
どんな種類の咳ですか?
痰が絡む「ゴホゴホ」という湿った咳(湿性咳嗽)か、痰の絡まない「コンコン」という乾いた咳(乾性咳嗽)かによって、考えられる原因は異なります。
また、犬が吠えるような特徴的な咳や、息が苦しくなるような発作的な咳など、咳の音や出方にも注意を払いましょう。
咳の種類の確認ポイント
| 確認項目 | チェックポイントA | チェックポイントB |
|---|---|---|
| 痰の有無 | 痰が絡む、湿った感じ | 痰は出ない、乾いた感じ |
| 咳の音 | ゴロゴロ、ゼロゼロ | コンコン、ケンケン |
| 咳の出方 | 一度出ると止まらない | 単発で出る |
咳以外の症状はありますか?
咳だけでなく、他にどのような症状があるかも重要な手がかりです。発熱、鼻水、のどの痛み、息苦しさ、胸の痛み、声がれ、体重減少など、咳と同時に現れている症状がないか確認しましょう。
これらの随伴症状は、原因疾患を特定する上で有力な情報となります。
どんな時に咳が出やすいですか?
特定の時間帯や状況で咳が悪化する場合、その状況が原因に関連している可能性があります。
例えば、朝方に多いのか、夜寝るときにひどくなるのか、食事の後や運動中に出やすいのかなど、ご自身の生活パターンと咳が出るタイミングを関連付けてみましょう。
持続期間による分類
咳は、症状が続く期間によって大きく3つに分類します。この分類は、原因を推定するための第一歩として非常に重要です。
急性咳嗽
急性咳嗽は、咳が出始めてから3週間未満の状態を指します。最も一般的なタイプであり、その多くはウイルスや細菌による感染症が原因です。
いわゆる「風邪(感冒)」やインフルエンザ、急性気管支炎などがこれにあたります。通常、原因となる感染症が治るとともに、咳も自然に軽快していくことが多いです。
亜急性咳嗽
咳が3週間以上経っても治まらず、8週間未満まで続く状態を亜急性咳嗽と呼びます。風邪などの感染症の後に、気道の過敏性が高まって咳だけが長引く「感染後咳嗽」が主な原因として挙げられます。
その他、咳喘息やアトピー咳嗽、副鼻腔気管支症候群の初期症状である可能性も考えます。
慢性咳嗽
8週間以上にわたって咳が続く場合、慢性咳嗽と診断します。単なる風邪の後遺症とは考えにくく、背景に何らかの特定の病気が隠れている可能性が高まります。
咳喘息、アトピー咳嗽、胃食道逆流症(GERD)、副鼻腔気管支症候群などが主な原因です。まれに肺がんや結核、間質性肺炎などの重篤な病気が原因であることもあるため、注意が必要です。
持続期間による分類と主な原因
| 分類 | 期間 | 主な原因 |
|---|---|---|
| 急性咳嗽 | 3週間未満 | 感冒、インフルエンザ、急性気管支炎 |
| 亜急性咳嗽 | 3~8週間 | 感染後咳嗽、咳喘息、副鼻腔炎 |
| 慢性咳嗽 | 8週間以上 | 咳喘息、アトピー咳嗽、胃食道逆流症 |
咳の性質による分類
咳は痰を伴うかどうかで「乾性咳嗽」と「湿性咳嗽」に分けられます。この性質の違いも、原因を探る上で大切な手がかりです。
乾性咳嗽(からせき)
乾性咳嗽は、痰を伴わない乾いた咳で、「コンコン」「コホコホ」といった音が特徴です。気道に炎症があったり、過敏になっていたりする場合に起こりやすいです。
咳喘息やアトピー咳嗽、胃食道逆流症、一部の薬剤の副作用(ACE阻害薬など)、間質性肺炎の初期などで見られます。刺激性のガスを吸い込んだり、精神的な要因で起こったりすることもあります。
湿性咳嗽(痰を伴う咳)
湿性咳嗽は、気道から分泌された痰を体の外に出すための咳で、「ゴホゴホ」「ゼロゼロ」といった湿った音がします。
気道にウイルスや細菌が感染して炎症が起こり、粘液の分泌が増えることが主な原因です。感冒、気管支炎、肺炎、副鼻腔気管支症候群、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などで見られます。
痰の色や粘り気も、原因を推測する上で参考になります。
乾性咳嗽と湿性咳嗽の主な特徴
| 項目 | 乾性咳嗽(からせき) | 湿性咳嗽(痰を伴う咳) |
|---|---|---|
| 音 | コンコン、コホコホ | ゴホゴホ、ゼロゼロ |
| 痰 | ほとんど出ない、または少量 | 絡んでおり、しばしば排出される |
| 主な原因 | 咳喘息、アトピー咳嗽、胃食道逆流症 | 感染症、COPD、副鼻腔気管支症候群 |
痰の色や性状から考えられること
湿性咳嗽の場合、痰の状態を観察することも大切です。ただし、色だけで病気を断定することはできませんので、あくまで目安として参考にしてください。
| 痰の色・性状 | 考えられる状態 | 主な関連疾患 |
|---|---|---|
| 透明・白色 | 気道の分泌物が多い状態 | 感冒の初期、気管支喘息、COPD |
| 黄色・緑色 | 細菌感染の可能性 | 気管支炎、肺炎、副鼻腔炎 |
| 錆色・赤褐色 | 古い血液が混じっている可能性 | 肺炎球菌性肺炎など |
時間帯や状況による分類
咳が特定の時間帯や状況で出やすくなる場合、その背景にある原因を推測するヒントになります。
朝の咳(起床時咳嗽)
朝、目が覚めたときに咳き込む場合は、いくつかの原因が考えられます。
睡眠中に鼻水がのどに流れる「後鼻漏(こうびろう)」が刺激になっている場合(副鼻腔炎など)や、睡眠中に溜まった痰を排出しようとする場合(慢性気管支炎、COPDなど)があります。
また、室内の空気が乾燥していたり、アレルゲン(ハウスダストなど)が多かったりすることも一因です。
夜間咳嗽
夜、特に就寝時や夜中に咳が悪化するのは、咳喘息や気管支喘息の典型的な症状の一つです。横になることで気道が狭くなりやすくなることや、自律神経の働きなどが関係しています。
また、胃食道逆流症でも、就寝中に胃酸が食道やのどに逆流し、咳を引き起こすことがあります。心不全の場合も、横になると心臓への負担が増え、肺に水が溜まりやすくなるため咳が出ることがあります。
食後咳嗽
食事中や食後に咳が出やすくなる場合、胃食道逆流症(GERD)が強く疑われます。胃酸や食べたものが食道に逆流し、その刺激が咳反射を引き起こします。
特に、油っこい食事や食べ過ぎ、食後すぐに横になる習慣がある人は注意が必要です。
また、高齢者の場合、飲み込む機能(嚥下機能)が低下し、食べ物や唾液が誤って気管に入る「誤嚥(ごえん)」によって咳が誘発されることもあります。
運動誘発性咳嗽
運動中や運動直後に咳が出る場合は、「運動誘発性気管支攣縮」の可能性があります。
これは気管支喘息の一種で、運動によって気道が冷やされたり乾燥したりすることが引き金となり、気管支が収縮して咳や息切れが起こります。
特に、冷たく乾燥した空気の中で行う冬のスポーツなどで起こりやすいです。
時間帯・状況別の咳と関連疾患
| 咳の出るタイミング | 主な原因 | 考えられる病気 |
|---|---|---|
| 朝方・起床時 | 後鼻漏、溜まった痰の排出 | 副鼻腔炎、COPD、慢性気管支炎 |
| 夜間・就寝時 | 気道の過敏性、胃酸の逆流 | 咳喘息、気管支喘息、胃食道逆流症 |
| 食事中・食後 | 胃酸の逆流、誤嚥 | 胃食道逆流症、嚥下機能障害 |
| 運動中・運動後 | 気道の乾燥・冷却による収縮 | 運動誘発性喘息 |
特殊なタイプの咳
咳の中には、音や出方に特徴があり、特定の病気を示唆するものがあります。ここではいくつかの特殊な咳について解説します。
発作性咳嗽
一度咳が出始めると、立て続けに激しく咳き込み、なかなか止まらなくなる状態を発作性咳嗽といいます。顔が赤くなったり、息苦しさを感じたりすることもあります。
百日咳やマイコプラズマ肺炎などの特定の感染症や、咳喘息、気管支喘息などで見られる特徴的な症状です。
犬吠様咳嗽(けんばいようがいそう)
「ケン、ケン」という、犬が吠えるような甲高い音の乾いた咳を犬吠様咳嗽といいます。これは、のどの奥(喉頭)周辺が腫れて空気の通り道が狭くなることで生じます。
主に乳幼児に多いクループ症候群(急性喉頭炎)で典型的に見られる症状です。
心因性咳嗽
体の病気が原因ではなく、精神的なストレスや心理的な要因によって引き起こされる咳です。日中の活動中には出るものの、何かに集中しているときや睡眠中には出なくなるのが特徴です。
他の病気の可能性をすべて除外した上で診断します。チック症の一種として現れることもあります。
季節性咳嗽
特定の季節になると決まって咳が出る場合、アレルギーが関係している可能性があります。
春や秋など、花粉が飛散する時期に悪化する場合は花粉症(アレルギー性鼻炎・結膜炎)に伴う咳が考えられます。
後鼻漏や、のどのイガイガ感が咳を引き起こします。
刺激性咳嗽
タバコの煙、冷たい空気、香水、ホコリ、排気ガスといった特定の刺激物を吸い込んだときに誘発される咳です。
気道が過敏になっている状態(咳喘息、COPDなど)で起こりやすく、刺激物が気道の咳受容体を直接刺激することで生じます。
特殊な咳の特徴と注意点
| 咳のタイプ | 特徴 | 主な関連疾患・状態 |
|---|---|---|
| 発作性咳嗽 | 激しい咳が連続して起こる | 百日咳、マイコプラズマ、咳喘息 |
| 犬吠様咳嗽 | 犬が吠えるような甲高い咳 | クループ症候群(小児) |
| 心因性咳嗽 | 睡眠中は消失し、日中に出る | 精神的ストレス |
医療機関を受診する目安
ほとんどの咳は自然に治まりますが、中には注意が必要なものや、専門的な治療を要するものもあります。どのような場合に医療機関を受診すべきか、その目安を知っておくことが大切です。
すぐに受診すべき咳のサイン
以下のような症状が咳と同時に見られる場合は、重篤な病気が隠れている可能性があるため、早めに医療機関を受診することを推奨します。
特に呼吸困難や血痰が見られる場合は、速やかな対応が必要です。
- 呼吸が苦しい、息切れがする
- 唇や顔色が悪くなる(チアノーゼ)
- 血の混じった痰(血痰)が出る
- 高熱が続く
- 胸に強い痛みを感じる
- 急激な体重減少がある
どの診療科を受診すればよいか
咳の症状でどの診療科にかかればよいか迷うことも多いでしょう。まずはかかりつけの内科や、呼吸器内科を受診するのが一般的です。
鼻水やのどの痛みが強い場合は耳鼻咽喉科、お子さんの場合は小児科が適しています。
受診する診療科の目安
| 主な症状 | 推奨される診療科 | 補足 |
|---|---|---|
| 長引く咳、息切れ | 呼吸器内科、内科 | 咳の原因を専門的に調べます。 |
| 咳、鼻水、のどの痛み | 耳鼻咽喉科、内科 | 鼻やのどが原因の咳を考えます。 |
| 子供の咳 | 小児科 | 子供特有の病気を考慮します。 |
医師に伝えるべき情報
診察を受ける際には、事前に情報を整理しておくと、診断がスムーズに進みます。以下の点をメモなどにまとめておくと良いでしょう。
- いつから咳が始まったか
- どのような咳か(乾性、湿性、発作性など)
- 痰の有無、色、量
- 咳以外の症状(発熱、鼻水、息苦しさ、胸痛など)
- 咳が出やすい時間帯や状況
- 現在治療中の病気や、服用中の薬
- 喫煙歴、アレルギーの有無
よくある質問
咳に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
- Q咳止めを飲んでも大丈夫ですか?
- A
咳は体を守るための防御反応でもあるため、一概に止めれば良いというものではありません。
特に、痰を伴う湿性咳嗽の場合、無理に咳を止めると気道に痰が溜まり、かえって症状を悪化させる可能性があります。
市販の咳止め薬を使用する際は、薬剤師に相談し、ご自身の咳のタイプ(乾性か湿性か)に合ったものを選ぶことが重要です。
症状が長引く場合は、自己判断で薬を続けるのではなく、医療機関を受診してください。
- Q子供の咳で注意すべき点は何ですか?
- A
子供は大人に比べて気道が狭く、咳が重症化しやすい傾向があります。特に乳幼児の場合、自分の症状をうまく言葉で伝えられません。保護者の方が注意深く様子を観察することが大切です。
子供の咳で特に注意したいサイン
観察ポイント 危険なサイン 考えられること 呼吸の様子 肩で息をしている、呼吸が速い、小鼻がヒクヒクする 呼吸困難 咳の音 犬が吠えるような咳、ヒューヒュー・ゼーゼーという音 クループ、喘息、気管支炎 全身状態 顔色が悪い、ぐったりしている、水分がとれない 重症化の兆候 上記のようなサインが見られた場合は、夜間や休日であっても速やかに医療機関を受診してください。
- Q咳は他の人にうつりますか?
- A
咳そのものがうつるわけではありませんが、咳の原因となっている病原体(ウイルスや細菌)が、咳のしぶき(飛沫)によって他の人に感染することはあります。
インフルエンザ、感冒、百日咳、結核などは感染力があります。
感染症が原因の咳が出ている間は、マスクを着用する(咳エチケット)、人混みを避けるなどの配慮が必要です。
- Q喫煙と咳の関係について教えてください。
- A
喫煙は咳の最も大きな原因の一つです。タバコの煙に含まれる有害物質が気道を常に刺激し、炎症を引き起こすため、慢性的な咳や痰の原因となります。
これは「喫煙者咳嗽」とも呼ばれます。また、喫煙は慢性閉塞性肺疾患(COPD)や肺がんの最大のリスク因子です。
長期間喫煙している方で、咳や息切れが続く場合は、呼吸器内科での詳しい検査を推奨します。禁煙は、これらの病気の予防と症状改善のために最も重要なことです。
以上